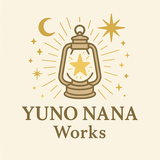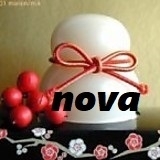リアル・ペイン 心の旅のレビュー・感想・評価
全168件中、1~20件目を表示
今観るに値する、ジェシー・アイゼンバーグの才能溢れる秀逸ロードムービー
ベンジー役を務めた俳優のジェシー・アイゼンバーグが監督・脚本・製作をも務めた第97回アカデミー賞で脚本賞と助演男優賞にノミネートされた注目のロードムービーです。
真田広之さんはじめ、賀来賢人さんなど、近年日本の俳優さんの中にも、出演側だけでなく製作にも積極的に参加し結果を残している俳優さんが増えたように思います。
主観的な目と客観的な目の両方を持ち合わせ、常に俯瞰して作品を眺めながら、同時に感情を込めて役を演じるというのは、想像するにどんなに難しいことだろうと思われます。投打で活躍する二刀流の大谷翔平さんのように、俳優界の二刀流である彼らは、大変器用で才能にあふれているといえます。
ストーリーは、ユダヤ人で人好きのするデヴィッド(キーラン・カルキン)と、彼と兄弟のように育った少し人見知りな従兄弟のベンジーの物語。一見正反対な性格のように見える彼らは、ともに感受性が高く繊細である点において共通しているともいえる。終始取り立てて大きな事件が起きるわけでもなく、物語は家族のルーツの地を巡る旅を通して、そこに参加する人たちとの交流や心の動きを静かに丁寧に描いています。
観終わって感じるのは、
「絶妙なココロの居心地の悪さ」とでもいいましょうか…🧐
やっぱり現実ってそんなに簡単ではないよねって思い知らされるのだ。
全ては、少し意地悪なエンディングによるものでしょう。奔放で人たらしでどこか危ういデヴィッドを好演したキーラン・カルキン、彼が最後に空港でほんの少しでもニコリと笑ってくれたのなら後味はもう少し軽やかになっていたことでしょう。そこを安直にそうしなかったところが、ジェシー・アイゼンバーグの絶妙なバランス感覚だと思います。
他人の痛みのホントのところは
その人にしかわからない
分かりたいけど分からない
簡単じゃない
リアルペイン
それも含めて、痛い
それでも誰かと少しでも分かり合いたいという気持ちを諦めたくないし
諦めちゃいけない。
そんな風に優しく耳元で諭されたような気がしましたよ🙄
とても美しく
余韻のある映画でした。
みんな痛みを抱えて生きていく
ニューヨークに住むユダヤ人のデヴィッドと、兄弟のように育った従兄弟ベンジー。亡くなった最愛の祖母の遺言によって、自分たちのルーツを知るポーランドのツアー旅行に参加する。
その過程でそれぞれの痛み、人生を見つめ合い、時にはぶつかり、時には涙し、ハグし合う。
明るく陽気でマイペースなコミュ力オバケのベンジーを演じたキーラン・カルキンが素晴らしかった。底抜けの明るさで人の懐にスッと入って魅力するのに、ふとした瞬間どこか寂しそうで、脆そう。このベンジーのキャラクターがストーリーの肝と言っても過言ではないから、それを見事に演じていたキーラン・カルキンに拍手を送りたい。
そしてその対極にいるデヴィッドは、真面目で大人数もハメを外すのも苦手。私はデヴィッドの気持ちがすごくわかる。というかデヴィッドみたいな人の方が大半だろうから、ベンジーを羨ましくも憎たらしくも思う気持ちがすごくわかると思う。
ホロコーストからの生き残りの祖母を持つふたりは、ユダヤ人の歴史の痛みを知ることで、自身の痛みや生き方を振り返る。
こんな地獄を生き抜いて生まれた自分たちは、ちゃんと真っ当に大切に生きないとと思う。でもそれは日本人だって同じだ。
けれど思うのだ。確かに過去の歴史と比べると今の方が幸せで、当時の人たちからしたら今の時代のそれぞれが抱えている痛みなんて痛みに思われないかもしれない。
「昔はなーもっと大変だったんだぞ」その一言で何も言えなくなってしまい、痛みが膿んで治らなくなる人だっているのだ。
自分の抱える痛みは自分にしかわからないし、人の数だけ痛みの種類がある。
でも理解ができない痛みを抱える人に寄り添って、大好きだよと抱きしめることで、理解は出来なくても、その人の痛みを和らげることは出来るんだと信じたい。
歴史と今の痛みを描きながら、ユダヤ人の歴史も学べる素敵なロードムービーだった。
人生はままならないけれど
ジェシー・アイゼンバーグが優秀な監督であることを証明した。彼自身による脚本・監督で、小品の豊かなドラマが生まれた。アメリカで生まれ育ったユダヤ人移民の3世の青年二人は、ポーランドから逃れてアメリカにやってきた祖母が亡くなったことで、二人でそのルーツをめぐる旅行に出かける。
キーラン・カルキン演じるベンジーは鬱で薬の大量服薬をしたばかり、普段は明るい奴だが、心に何かを苦しみを抱えている。そんな彼は、ユーモアセンスもありコミュニケーション能力に長けているような、空気が読めないような、複雑な男だ。幼いころは彼と兄弟同然に育ったデヴィッドは、彼が辛い時に力になれなかったことを悔いている。同時に、いつも人に愛されるベンジーが気に入らない、でも、本当はデヴィッドはそんなベンジーみたいになりたかった。愛憎が入り混じる複雑な関係性をさらりとユーモアも交えて描いて見せるジェシー・アイゼンバーグの芝居を引き出す力が素晴らしい。
自分の人生も見つめなおしてみたくなる。
家族の歴史を辿る旅は今の自分とこれからの自分を考える旅
ジェシー・アイゼンバーグが自らのルーツであるユダヤ系ファミリーの歴史を辿る旅を、疎遠だった従兄弟とのロードムービーとして描いている。アイゼンバーグはホロコーストを生き延びたポーランド人の祖先を持つ。従って本作は、自伝的要素が多く含まれたアイゼンバーグによるファミリー・ヒストリーと言ってもいいだろう。
実際に、映画はワルシャワにあるゲットーの英雄記念碑やクリジボウスキ広場、ルブリンの旧ユダヤ人墓地、最後はナチスの強制収容所のガス室へと舞台を転換させていく。それは、我々もホロコーストツアーが体験できる時間でもある。こんな機会は貴重だと思う。
過去に目を向けることは今を、そして、これからを見つめること。主演と監督を兼任するアイゼンバーグの脚本は、彼が演じる主人公のデヴィッドと、この役で本年度の演技賞を総取りしそうなキアラン・カルキン扮する従兄弟のベンジーが、互いの不信感を不器用に乗り越えていく過程に重きを置いている。それは誰もが思い当たることだから、人種や舞台を超えて心に刺さるのだ。
ショパン曲のBGMの煩さは敢えての狙いか
映画に登場する早口で饒舌で神経質なユダヤ系アメリカ人男性、と聞けば大勢がウディ・アレン監督・主演の諸作を思い浮かべるだろう。ジェシー・アイゼンバーグは、アレン監督の「カフェ・ソサエティ」で主演し、もともと親和性が高かったのか影響を受けたのかは定かでないが、アイゼンバーグ監督第2作でそうしたキャラクターである主人公デヴィッドを自ら演じるということは、性的虐待で映画界を追放されて不在となったアレンの“立ち位置”を受け継ぐ意志の表れだろうか。
デヴィッドと従兄弟のベンジー(演じたキーラン・カルキンがアカデミー賞助演男優賞ノミネート)は正反対な性格と説明されているが、どちらも神経症気味で生きづらさを感じているという共通点がある。そんな2人のロードムービーなので、理屈っぽい長台詞、奇声、突飛な行動などが、観る人によってはイライラさせられる要素になるかも。
2人は亡き祖母がナチスドイツに迫害されるまで暮らしていたポーランドを訪れ、第二次大戦の史跡ツアーに参加する。ガイドのジェイムズ(「エマニュエル」でも重要な役を演じたウィル・シャープ)が史跡の説明をしているあいだ、ポーランドを代表する作曲家ショパンのピアノ曲がBGMで鳴りまくっていて、これが台詞に重なって相当うるさいのだが、その後の展開を考えると、あのうるささもジェイムズの内なるいらだちを観客に体感させる演出の狙いなのかもしれない。精神的にしんどい映画ではあるが、本編1時間半という短さに救われる。
純文学に浸る様なロードムービー
こんな奴とは友だちになりたくない
本当の痛みは誰も分からない
自分にも同い年の従兄弟がいるので、
割と感情移入しながら観れた。
はっきり言って赤の他人より気まずい旅になる。
しかもベンジーには思い過去もあって、
鬱病で気分屋で自分のペースに巻き込む性格でもある。
やれやれって感じだけど、
ベンジーには自分にはない魅力があって、
近くの人はしんどいけど、ツアー客くらいなら
好かれてしまって、ベンジーの嫌なところは
自分が憧れてしまってるところでもある。
とてもよく分かる関係性で見てる分には楽しい。
ただなんとなく暗い気持ちが常にあるのは、
ベンジーの本心が分からない所にある。
本当の痛みが結局旅を通しても分からないところが
とてもしんどい。
なので、エンディング後の結末も
暗いものしか想像出来ない事が本当に辛い。
痛すぎるぞ!!本当の痛みは終わらない〜
イタイやつ
予告を見た時、
ベンジー(キーラン・カルキン)は
なんて身勝手なやつだろう、と思った。
身勝手な人間からは、なるべく遠ざかっていたい。
だからこの映画は、観たくないと思ってた。
それから、痛いのも苦手(身も心も)。
だから真っ正面から「ペイン」なんて掲げてるこの映画は、
観たくないと思ってた。
でも、観てしまったw
冒頭から
デヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ――ちなみに監督・脚本もこの方)が
兄弟のように育った従兄弟のベンジーに
振り回されて可哀想。
笑えるんだけど、苦笑い。
2人は、
ユダヤ人の心の痛みを感じるための
ポーランド・ツアーに参加。
ツアー客は2人を入れて6人。ガイドが1人。
ベンジーは、皆とひととおり悶着を起こしていって。
デヴィッドは気が気じゃないんだけれど、思いは複雑。
というのも、結局皆だいたいは、
自分とは違って突拍子もないベンジーを好きになる
っていうわけで。
たしかにベンジーは、
いつどこで何を言い出すか
わかったもんじゃない。
(このあたり、脚本が上手い)
要するに、
荒立てないだけがコミュニケーションじゃない
ってことかな。それには同意。
それと同時にデヴィッドは、
ベンジーの心の状態が心配でもあって。
最終的にワタクシもまた、
すっかりデヴィッドと同じ心持ちになって、
少なくともベンジーを嫌いじゃなくなったし、
2人とも元気でやってくれ
と願ったのでありました。
うん、観てよかった。
* * *
ちなみに real pain には
「苦痛の種」「不愉快な奴」「うんざり」
(イタイやつ?)という意味があるらしい。
ここではおそらく
「リアルな(心の)痛み」と掛けてるんだろう。
ホロコースト系ロードムービー
複雑なニュアンスで、戦争の傷を辿る旅。
ショパンのピアノ曲に彩られた40男のルーツを辿る旅。
ポーランドにルーツを持つ2人のユダヤ人。
従兄弟同士のデヴィッドとベンジーは、ホロコーストの生き残りの祖母を
半年前に亡くした。
落ち込むベンジーを伴って祖母のポーランドの家を訪ねるために、
ポーランドのツアーに申し込む。
それは当然、アウシュビッツへ向かう旅でもあった。
ツアーはガイドを入れて7人の少人数。
60代のマダムが「ダーティ・ダンシング」のジェニファー・グレイ、
だった。
素敵に歳を重ねていて懐かしかった。
心配症のデヴィッドと気儘で天然のベンジー。
ユダヤ人の苦しみや痛みは想像もつかないけれど、
ポーランドは美しい。
ショパンが「革命のエチュード」を作曲したとき、
ワルシャワはロシアからの独立を目指した反乱に失敗したのだ。
それが1830年のこと。
なんとポーランド人はナチスに300万人殺されたそうだ。
なんと言うルーツ‼️
ベンジーが素敵な列車でパニックを起こすシーン。
アウシュビッツへ送られる過去の同胞たちが、
自分のことのように思えたのだ。
彼の繊細で壊れそうな心の“痛み“
ポーランドの英雄碑でお茶目なシェーみたいなポーズで記念撮影。
ツアーのみんなも真似して記念撮影。
ベンジーは周りを巻き込んでみんな彼が好きになる。
真面目なデヴィッドは、通り一遍の知り合いにしかなれないのに、
ベンジーは盛大なハグで、みんなと別れを惜しまれる。
なのに、なのに、
デヴィッドは可愛い息子と妻のいる家庭に戻り、
ペベンジーは「一番落ち着く」と言う空港で人混みを眺めて
いつまでも佇んでいる。
彼は進めない。
歴史に取り残され、生産的な生き方ができずにいる。
それはユダヤ人だからだけではじゃないだろう。
人は痛みを克服することは出来ない。
折り合いをつけるだけ。
ベンジーは折り合いをつけられるのだろうか?
「ソーシャル・ネットワーク」や「グランド・イリュージョン」の主演を...
痛みのツアー
「行く事は叶わないが見る事は出来る」
いいやつなんだろうけど
沁みるストーリー、キーラン・カルキンの演技は圧巻
幾重もの奇跡の果てに
疎遠になっていた従兄弟同士が、亡き祖母の遺言で参加したポーランドのツアーにてあれやこれや騒ぎを起こすが…といった物語。
性格は真反対。元気で破天荒に見えるベンジーも抱える闇があるらしく時に情緒が…。そんな彼を冷静に抑え込むデイブも彼もまた…。
そんな状況の中、ユダヤに縁のある個性的な人々と一緒に、祖母とも関係のあるホロコーストの歴史に触れていくが…。
いやぁ〜何というか、大変おこがましいですがデイブとワタクシって色々似てるな(イケメン顔以外)と思い、深く感情移入しちゃいました。
常識ハズレで空気も読まずにその時々の気持ちをヅケヅケと言い放っては皆を困惑させるベンジー。そんな彼の奇行を皆に謝る、神経質ながら常識人のデイブ。
…しかし何故でしょう。蓋を開けてみれば皆に心を開かれているのは…。
彼のことが大好きで大嫌い。
そんな彼になりたい。
…う〜ん、この複雑な気持ちよ!!
真面目にやるのが馬鹿馬鹿しく思えてしまう…。
特にジェームズとの別れ…気を遣いっぱなしだったデイブの方が遥かに淡白だったことが印象的だった。
…とはいえ本筋は勿論そこではないですね。
誰にも表面上には見えない心の闇を抱えて生きているわけだし。ここからの物語はどうなるのか。
そして石の置く場所よ…
リアルペイン…それは1人になった寂しさか、或いは闘魂注入のことか、はたまたこれからの不安か…。
あとは序盤のヨーグルト捨てるのは、ゾンビランド1.2の酒ポイッを思い出してちょっと笑っちゃった(笑)
終始聞かれる美しいピアノの旋律とともに、解決などではなく、抱えて生きていくしかない、最後の希望とも不安ともとれなくない眼差しに、そんなことを思わされた作品だった。
ロードムービー
亡くなった祖母のルーツを旅する 親戚同士の男二人のロードムービー。...
全168件中、1~20件目を表示