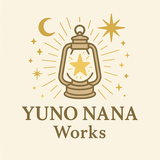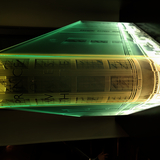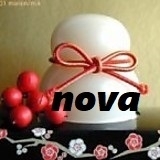リアル・ペイン 心の旅のレビュー・感想・評価
全218件中、1~20件目を表示
今観るに値する、ジェシー・アイゼンバーグの才能溢れる秀逸ロードムービー
ベンジー役を務めた俳優のジェシー・アイゼンバーグが監督・脚本・製作をも務めた第97回アカデミー賞で脚本賞と助演男優賞にノミネートされた注目のロードムービーです。
真田広之さんはじめ、賀来賢人さんなど、近年日本の俳優さんの中にも、出演側だけでなく製作にも積極的に参加し結果を残している俳優さんが増えたように思います。
主観的な目と客観的な目の両方を持ち合わせ、常に俯瞰して作品を眺めながら、同時に感情を込めて役を演じるというのは、想像するにどんなに難しいことだろうと思われます。投打で活躍する二刀流の大谷翔平さんのように、俳優界の二刀流である彼らは、大変器用で才能にあふれているといえます。
ストーリーは、ユダヤ人で人好きのするデヴィッド(キーラン・カルキン)と、彼と兄弟のように育った少し人見知りな従兄弟のベンジーの物語。一見正反対な性格のように見える彼らは、ともに感受性が高く繊細である点において共通しているともいえる。終始取り立てて大きな事件が起きるわけでもなく、物語は家族のルーツの地を巡る旅を通して、そこに参加する人たちとの交流や心の動きを静かに丁寧に描いています。
観終わって感じるのは、
「絶妙なココロの居心地の悪さ」とでもいいましょうか…🧐
やっぱり現実ってそんなに簡単ではないよねって思い知らされるのだ。
全ては、少し意地悪なエンディングによるものでしょう。奔放で人たらしでどこか危ういデヴィッドを好演したキーラン・カルキン、彼が最後に空港でほんの少しでもニコリと笑ってくれたのなら後味はもう少し軽やかになっていたことでしょう。そこを安直にそうしなかったところが、ジェシー・アイゼンバーグの絶妙なバランス感覚だと思います。
他人の痛みのホントのところは
その人にしかわからない
分かりたいけど分からない
簡単じゃない
リアルペイン
それも含めて、痛い
それでも誰かと少しでも分かり合いたいという気持ちを諦めたくないし
諦めちゃいけない。
そんな風に優しく耳元で諭されたような気がしましたよ🙄
とても美しく
余韻のある映画でした。
みんな痛みを抱えて生きていく
ニューヨークに住むユダヤ人のデヴィッドと、兄弟のように育った従兄弟ベンジー。亡くなった最愛の祖母の遺言によって、自分たちのルーツを知るポーランドのツアー旅行に参加する。
その過程でそれぞれの痛み、人生を見つめ合い、時にはぶつかり、時には涙し、ハグし合う。
明るく陽気でマイペースなコミュ力オバケのベンジーを演じたキーラン・カルキンが素晴らしかった。底抜けの明るさで人の懐にスッと入って魅力するのに、ふとした瞬間どこか寂しそうで、脆そう。このベンジーのキャラクターがストーリーの肝と言っても過言ではないから、それを見事に演じていたキーラン・カルキンに拍手を送りたい。
そしてその対極にいるデヴィッドは、真面目で大人数もハメを外すのも苦手。私はデヴィッドの気持ちがすごくわかる。というかデヴィッドみたいな人の方が大半だろうから、ベンジーを羨ましくも憎たらしくも思う気持ちがすごくわかると思う。
ホロコーストからの生き残りの祖母を持つふたりは、ユダヤ人の歴史の痛みを知ることで、自身の痛みや生き方を振り返る。
こんな地獄を生き抜いて生まれた自分たちは、ちゃんと真っ当に大切に生きないとと思う。でもそれは日本人だって同じだ。
けれど思うのだ。確かに過去の歴史と比べると今の方が幸せで、当時の人たちからしたら今の時代のそれぞれが抱えている痛みなんて痛みに思われないかもしれない。
「昔はなーもっと大変だったんだぞ」その一言で何も言えなくなってしまい、痛みが膿んで治らなくなる人だっているのだ。
自分の抱える痛みは自分にしかわからないし、人の数だけ痛みの種類がある。
でも理解ができない痛みを抱える人に寄り添って、大好きだよと抱きしめることで、理解は出来なくても、その人の痛みを和らげることは出来るんだと信じたい。
歴史と今の痛みを描きながら、ユダヤ人の歴史も学べる素敵なロードムービーだった。
痛みは天秤にかけられない
原題「A Real Pain」は、「面倒なやつ、困ったやつ」といった意味だ。
オープニングで空港のベンチに座るベンジーの横にこのタイトルが浮かぶ場面は、彼がその面倒なやつであることを示唆しているようでもあり、実際ツアーの序盤ではその通りの印象を受ける。
それがラストシーンで再び彼の面差しと共にこのタイトルを見る時には、直訳の「本当の痛み」の方の意味合いが色濃く浮かぶ。最初のタイトルコールと対になった演出が効いている。
多分多数派だと思うが、私もまたデヴィッド寄りの人間なので、彼がベンジーの奔放さに困惑する気持ちは手に取るように分かった。
ワルシャワ蜂起記念碑の前で、おどけた写真を撮るベンジーを不謹慎に思って小声で注意したら、意外と他のツアーメンバーもベンジーのノリに付き合いだすのを見て気後れするところなんかはすっかりデヴィッド目線になり、疎外感に胸の奥がヒリヒリした。
ルワンダ虐殺サバイバーのエロージュやガイドのジェームズとの間には気を揉むようなやり取りがあったのに、最終的にベンジーは好かれてしまう。一見不躾なのに、その裏にある率直さという美徳がちゃんと伝わるのは羨ましい個性だ。
自由なベンジーの横にいると余計に自分の不器用さが際立って惨めな気分になる。一方で、彼がほんの数ヶ月前にオーバードーズ(OD)で生死の境を彷徨ったことも知っている。そんなデヴィッドは、好意や羨望に憎しみまでも入り混じった複雑な感情をベンジーに抱く。
だが、ベンジーの目にはデヴィッドの生き方の方が自分の人生よりよほど眩しかったのではないだろうか。行きの飛行機でデヴィッドの仕事をからかった時や、彼の家族の話を聞いている時、ベンジーはどこか寂しげだった。
対人関係は不器用であっても、デヴィッドには定職があり、家に帰れば愛しい妻とかわいい我が子がいる。
自分の家に会いに来るよう請うベンジーに、デヴィッドはベンジーの方がニューヨークに来ればいいのにと返す。でも多分、デヴィッドの幸せな家庭を見ることはベンジーにとって辛いことなのだ。
ラストシーンを見る頃、私はいつの間にかベンジーの目線になっていた。
こうした2人の男性それぞれの生きづらさが、ホロコースト史跡ツアーの道程と共に描かれる。
ツアーメンバーとの夕食の席で、デヴィッドはベンジーについて「祖母がホロコーストを生き延びた結果奇跡的に僕たちは生まれたのに、あんなこと(OD)をしていいのか」といった主旨のことを言った。確かにホロコーストは近代で他に類を見ないほどの圧倒的な「痛み」だ。その痛みを前にすれば現代人のパーソナルな苦悩は、一見ちっぽけなもののようでもある。
デヴィッドの言葉は、祖母のルーツを尊重する思いから出たものだろう。だが一方でこれは苦悩を抱える本人にとってはあまり役立たない論理だ。むしろ、ホロコーストの苦難に時間の隔たりを超えて全霊で感情移入する敏感さを持つからこそ、ベンジーは生きづらさに苦しんでいる。
「本当の痛み」は主観的なものであり、別の悲劇と比べたからといって卑小になったり偽物になるわけではない。
この物語がありがちな結末を迎えるとしたら、別れ際の2人の明るい表情で終わることだろう。だが実際は、あたたかい家庭に帰るデヴィッドと、そのまま空港に残るベンジーが対照的に描かれた。
旅の始まりでは待ち合わせ時間の何時間も前から空港に来ていて、旅の最後の別れ際にはしばらく空港に残ると言ったベンジー。元の日常で彼を待っている孤独との再会をしばし先送りにしているような、憂いを含んだ眼差しに胸が締め付けられる。
旅の経験は確かにこれからのベンジーにとって支えになるだろう。でも、彼の苦悩が即座に消えるわけではない。結局は旅の後の日常で、ひとりで地道に折り合いをつけてゆかなければならない。Real Painとはそういうものだ。
そんなことを思わせる、まさに現実的なラストシーンだった。
重いテーマの作品だが、全編を彩るショパンを聴きながらデヴィッドたちが訪れる史跡を順番に見ているうちに、ツアーに同行してポーランドを巡っているような気持ちになる。また、基本的にデヴィッドとベンジーのやり取りは軽やかで時にユーモアがあり、物語に親しみを感じさせてくれる。
人の心の痛みというものについてやわらかに問いかけ、安直ではないラストでその問いを問いのまま観客の心に残す。繊細で率直な誰かとしばらく過ごした後のような、不思議な余韻の残る映画だった。
人生はままならないけれど
ジェシー・アイゼンバーグが優秀な監督であることを証明した。彼自身による脚本・監督で、小品の豊かなドラマが生まれた。アメリカで生まれ育ったユダヤ人移民の3世の青年二人は、ポーランドから逃れてアメリカにやってきた祖母が亡くなったことで、二人でそのルーツをめぐる旅行に出かける。
キーラン・カルキン演じるベンジーは鬱で薬の大量服薬をしたばかり、普段は明るい奴だが、心に何かを苦しみを抱えている。そんな彼は、ユーモアセンスもありコミュニケーション能力に長けているような、空気が読めないような、複雑な男だ。幼いころは彼と兄弟同然に育ったデヴィッドは、彼が辛い時に力になれなかったことを悔いている。同時に、いつも人に愛されるベンジーが気に入らない、でも、本当はデヴィッドはそんなベンジーみたいになりたかった。愛憎が入り混じる複雑な関係性をさらりとユーモアも交えて描いて見せるジェシー・アイゼンバーグの芝居を引き出す力が素晴らしい。
自分の人生も見つめなおしてみたくなる。
めんどくさい若者も見守れる大人たち(旅の間限定で)
よくも悪くも、いや、いいも悪いもないのだけれど、自分の視点がデヴィッドでもベンジーでもなく、ツアーに参加しているほかの大人たちに近づいていた。ベンジーの混乱もデヴィッドの葛藤もわかるが、ほかの大人たち(ベンジーを嫌うおじさんを除く)は基本的に、彼らが悩みを突き詰めたところでわかりやすい答えが出ることなどないとわかったうえで、ベンジーがとっちらかってジッタバッタしているけれど本質的には善良な人間であることを感じて好意的に受け止めているし、ツアーの間くらいなら見守っていようという気持ちを持っている。もはや同じ土俵にいない大人たちと、大人の年齢なのに土俵から折りられないデヴィッドとベンジーという対比が印象に残る。そして短い旅の道連れという後腐れのない関係だからこそ、彼らは目立つベンジーと交流し、デヴィッドのことはあまり頓着しない。そりゃそうだよな、デヴィッドに旅の道連れとして面白みがないことは本人も自覚しているだろうし、自分が見向きもされないという自虐はあの環境では自業自得でもあり、そういう小さな残酷さがチクチクと効いてくる。しかしベンジーはあの後どうしたのか、で、見る人の人生観が問われる作品でもある。自分はどうしても、ベンジーには悲観的な未来しか想像できないのだけれど。
家族の歴史を辿る旅は今の自分とこれからの自分を考える旅
ジェシー・アイゼンバーグが自らのルーツであるユダヤ系ファミリーの歴史を辿る旅を、疎遠だった従兄弟とのロードムービーとして描いている。アイゼンバーグはホロコーストを生き延びたポーランド人の祖先を持つ。従って本作は、自伝的要素が多く含まれたアイゼンバーグによるファミリー・ヒストリーと言ってもいいだろう。
実際に、映画はワルシャワにあるゲットーの英雄記念碑やクリジボウスキ広場、ルブリンの旧ユダヤ人墓地、最後はナチスの強制収容所のガス室へと舞台を転換させていく。それは、我々もホロコーストツアーが体験できる時間でもある。こんな機会は貴重だと思う。
過去に目を向けることは今を、そして、これからを見つめること。主演と監督を兼任するアイゼンバーグの脚本は、彼が演じる主人公のデヴィッドと、この役で本年度の演技賞を総取りしそうなキアラン・カルキン扮する従兄弟のベンジーが、互いの不信感を不器用に乗り越えていく過程に重きを置いている。それは誰もが思い当たることだから、人種や舞台を超えて心に刺さるのだ。
ショパン曲のBGMの煩さは敢えての狙いか
映画に登場する早口で饒舌で神経質なユダヤ系アメリカ人男性、と聞けば大勢がウディ・アレン監督・主演の諸作を思い浮かべるだろう。ジェシー・アイゼンバーグは、アレン監督の「カフェ・ソサエティ」で主演し、もともと親和性が高かったのか影響を受けたのかは定かでないが、アイゼンバーグ監督第2作でそうしたキャラクターである主人公デヴィッドを自ら演じるということは、性的虐待で映画界を追放されて不在となったアレンの“立ち位置”を受け継ぐ意志の表れだろうか。
デヴィッドと従兄弟のベンジー(演じたキーラン・カルキンがアカデミー賞助演男優賞ノミネート)は正反対な性格と説明されているが、どちらも神経症気味で生きづらさを感じているという共通点がある。そんな2人のロードムービーなので、理屈っぽい長台詞、奇声、突飛な行動などが、観る人によってはイライラさせられる要素になるかも。
2人は亡き祖母がナチスドイツに迫害されるまで暮らしていたポーランドを訪れ、第二次大戦の史跡ツアーに参加する。ガイドのジェイムズ(「エマニュエル」でも重要な役を演じたウィル・シャープ)が史跡の説明をしているあいだ、ポーランドを代表する作曲家ショパンのピアノ曲がBGMで鳴りまくっていて、これが台詞に重なって相当うるさいのだが、その後の展開を考えると、あのうるささもジェイムズの内なるいらだちを観客に体感させる演出の狙いなのかもしれない。精神的にしんどい映画ではあるが、本編1時間半という短さに救われる。
こんな従兄弟がいたら楽し…よ、40代?!
凸凹な従兄弟2人のロードムービー。ホロコーストから現代までのユダヤ系の人々の歴史を後景としつつ、2人の間やその周囲の人々の(温かな)関わりを描いています
固く真面目に生きているデヴィッドとヒッピー的に生きているベンジーというのは、米国のユダヤ系青年のあるある典型例なんですかね?そこら辺のリアリティを含めた背景知識があると、もっと深く楽しめるのだろうと思います。
率直故にちょっと厄介だけど人に好かれていてでも危ういベンジーの造形は、確かにこういう人いるなあと思わされました。対照的な従兄弟2人の憎愛ありキャッキャしたじゃれ合いありの絆は憧れま…
…って、え?この人たち40代なの!?
日本語の紹介文では40代を迎えた生きづらさが云々と書かれているけど、そうした年齢設定が本当にあるのかは検索してもハッキリしない…本編を見ているときは、20代後半〜30代半ばくらいかなと思っていたのですが。
デヴィッドはともかくベンジーが40代でのあのキャラだとしたら、結構話が違ってくる気が…と言うことで、考察(?)次第でまた別の見方ができる映画でした。
純文学に浸る様なロードムービー
こんな奴とは友だちになりたくない
本当の痛みは誰も分からない
自分にも同い年の従兄弟がいるので、
割と感情移入しながら観れた。
はっきり言って赤の他人より気まずい旅になる。
しかもベンジーには思い過去もあって、
鬱病で気分屋で自分のペースに巻き込む性格でもある。
やれやれって感じだけど、
ベンジーには自分にはない魅力があって、
近くの人はしんどいけど、ツアー客くらいなら
好かれてしまって、ベンジーの嫌なところは
自分が憧れてしまってるところでもある。
とてもよく分かる関係性で見てる分には楽しい。
ただなんとなく暗い気持ちが常にあるのは、
ベンジーの本心が分からない所にある。
本当の痛みが結局旅を通しても分からないところが
とてもしんどい。
なので、エンディング後の結末も
暗いものしか想像出来ない事が本当に辛い。
痛すぎるぞ!!本当の痛みは終わらない〜
文化的な面で理解しきれなかった
国内線の機内で見ました。作中でも飛行機を含めた旅行記、ロードムービーなのでなんとなくシンパシーを感じながら見るにはちょうどよかったですね。
それくらいたまたまの鑑賞なので本当に簡素なあらすじでしか事前情報は無いです。
二人の若者が旅の中で自分と向き合い、グループと親睦を深めていく。
そんなくらいの認識で見はじめました。
主人公二人のキャラクターはオープニングからわかりやすく、マイペースで空気を読まずずけずけ行くタイプのベンジー、気配り屋で心配性のデビッド。どっちものキャラクターも誇張されつつも、誰しも現実の交友関係の中で思い当たる友人を当てはめながら見られるような造詣。
会話のやり取りもあからさまに今イラっとしてるんだろうな(笑)とか、嫌々だった割りに結果楽しそうだなとか、見ててすんなり感じ取れる上手なテンポでした。
性格の違う二人がお互いを思い合いながらもそれぞれの生活、歳とともに距離が開いてしまっている感じもなんだか現実的で思うところがありました。
最終的にはほんの一部かもしれないけど、二人の胸の内を吐露しあって、お互いの絆を再確認して幕を閉じる。
この後二人がどうなっていくのかはわかりませんが、なんとなく昔仲良かったけど疎遠になってしまった古い友人にまた会いたいななんて気持ちがじんわり湧く良い映画でした。
ただ、もう少しツアーグループの他メンバ達にも光を当てるのかと思ったら特にそんな深掘りも無く、なんだからあっさりと解散してしまいました。おばあちゃんちの写真は送ったのかな。たぶんベンジーのキャラだとそんな社交辞令すっかり忘れて送ってないだろうな(笑)
ベンジーの人を振り回しつつも魅了するキャラクターを際立たせるための舞台装置だった感が否めなかったですね。
二人の共通の祖母のルーツに深く関わるホロコーストの記憶を巡る旅。この辺も日本人の感覚からかなり遠くてイメージが全然つかなかったです。歴史的に痛ましい事実であることをは知識として知っててもあそこまで感傷的なツアーを巡るのってなんだかリフレッシュを目的とする旅行の目的に相反するような…自身の祖父母の第二次大戦の痛ましい記憶(があったとして)を追体験するツアーに参加したいか?って考えるとちょっと想像が付かないですね…この辺は現代日本人の平和ボケ感覚なのかもしれない。
二人が心情を吐露するためには心を揺さぶる旅である必要があったのかもしれないけど、なんだか歴史の傷を描きたいのか現代に生きる人々の傷を描きたいのか、特にガス室あたりとかはもう題材が重すぎてどっちにどう感情を抱けばいいのかよくわからなくなりました。
欧米(作中でもそうですが巻き込まれた移民の方々もいるのであえて米も含みます)の人達には共感できるくらいには鮮明な記憶として刻まれてるのかなぁなんてちょっと作品に入りこめなかった部分もあり☆3とさせていただきました。というかあらすじにコメディって書いてあったけどコメディ要素少なすぎません?と今更思いました。
イタイやつ
予告を見た時、
ベンジー(キーラン・カルキン)は
なんて身勝手なやつだろう、と思った。
身勝手な人間からは、なるべく遠ざかっていたい。
だからこの映画は、観たくないと思ってた。
それから、痛いのも苦手(身も心も)。
だから真っ正面から「ペイン」なんて掲げてるこの映画は、
観たくないと思ってた。
でも、観てしまったw
冒頭から
デヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ――ちなみに監督・脚本もこの方)が
兄弟のように育った従兄弟のベンジーに
振り回されて可哀想。
笑えるんだけど、苦笑い。
2人は、
ユダヤ人の心の痛みを感じるための
ポーランド・ツアーに参加。
ツアー客は2人を入れて6人。ガイドが1人。
ベンジーは、皆とひととおり悶着を起こしていって。
デヴィッドは気が気じゃないんだけれど、思いは複雑。
というのも、結局皆だいたいは、
自分とは違って突拍子もないベンジーを好きになる
っていうわけで。
たしかにベンジーは、
いつどこで何を言い出すか
わかったもんじゃない。
(このあたり、脚本が上手い)
要するに、
荒立てないだけがコミュニケーションじゃない
ってことかな。それには同意。
それと同時にデヴィッドは、
ベンジーの心の状態が心配でもあって。
最終的にワタクシもまた、
すっかりデヴィッドと同じ心持ちになって、
少なくともベンジーを嫌いじゃなくなったし、
2人とも元気でやってくれ
と願ったのでありました。
うん、観てよかった。
* * *
ちなみに real pain には
「苦痛の種」「不愉快な奴」「うんざり」
(イタイやつ?)という意味があるらしい。
ここではおそらく
「リアルな(心の)痛み」と掛けてるんだろう。
ホロコースト系ロードムービー
複雑なニュアンスで、戦争の傷を辿る旅。
ショパンのピアノ曲に彩られた40男のルーツを辿る旅。
ポーランドにルーツを持つ2人のユダヤ人。
従兄弟同士のデヴィッドとベンジーは、ホロコーストの生き残りの祖母を
半年前に亡くした。
落ち込むベンジーを伴って祖母のポーランドの家を訪ねるために、
ポーランドのツアーに申し込む。
それは当然、アウシュビッツへ向かう旅でもあった。
ツアーはガイドを入れて7人の少人数。
60代のマダムが「ダーティ・ダンシング」のジェニファー・グレイ、
だった。
素敵に歳を重ねていて懐かしかった。
心配症のデヴィッドと気儘で天然のベンジー。
ユダヤ人の苦しみや痛みは想像もつかないけれど、
ポーランドは美しい。
ショパンが「革命のエチュード」を作曲したとき、
ワルシャワはロシアからの独立を目指した反乱に失敗したのだ。
それが1830年のこと。
なんとポーランド人はナチスに300万人殺されたそうだ。
なんと言うルーツ‼️
ベンジーが素敵な列車でパニックを起こすシーン。
アウシュビッツへ送られる過去の同胞たちが、
自分のことのように思えたのだ。
彼の繊細で壊れそうな心の“痛み“
ポーランドの英雄碑でお茶目なシェーみたいなポーズで記念撮影。
ツアーのみんなも真似して記念撮影。
ベンジーは周りを巻き込んでみんな彼が好きになる。
真面目なデヴィッドは、通り一遍の知り合いにしかなれないのに、
ベンジーは盛大なハグで、みんなと別れを惜しまれる。
なのに、なのに、
デヴィッドは可愛い息子と妻のいる家庭に戻り、
ペベンジーは「一番落ち着く」と言う空港で人混みを眺めて
いつまでも佇んでいる。
彼は進めない。
歴史に取り残され、生産的な生き方ができずにいる。
それはユダヤ人だからだけではじゃないだろう。
人は痛みを克服することは出来ない。
折り合いをつけるだけ。
ベンジーは折り合いをつけられるのだろうか?
それぞれの痛みと生きていく
人に嫉妬する痛み。
押し寄せる感情をうまくコントロールできない痛み。
愛する人を亡くした痛み。
ホロコーストによる歴史的な痛み。
大小様々な痛みとどう向き合うかが淡々と、かつコミカルに描かれる。
本当の痛みと向き合うってどういうこと?
お墓に石を置くことで痛みと向き合ったと言えるか?
より辛い経験をした人がいるのに自分の苦しみは正当化できるのか?
痛みと向き合うことで何かが変わるのか?
そんな問いを投げかけられてる気がした。
最後ベンジーは空港に残るが、彼の中で痛みとの向き合い方にはっきりとした答えが見つけられていない。
自分たちのルーツや自身の心の痛みと向き合いながらも、旅は道連れ世は情け
『ソーシャル・ネットワーク』では実在の天才、『バットマンvsスーパーマン』では悪の天才。
卓越した演技力で天才を演じてきたジェシー・アイゼンバーグだが、彼自身も天才であった。
注目を集めた監督デビュー作に続く監督2作目。その天才ぶりを確かなものに。
ユダヤ人のデヴィッドと従兄弟のベンジー。実の兄弟のように育ってきたが、ここ暫く疎遠。
大好きだった祖母が亡くなり、追悼と遺言で、自分たちや祖母、ユダヤ人のルーツを辿るポーランド・ツアーに参加する事に。
その旅の中で…
勿論ハートフルやユーモア、二人の掛け合いもあるが、思ってたより淡々と静かな印象。特別何か起こるロードムービーってほどでもない。
だけど、しみじみ心に染み入る。
気分や雰囲気は観光。ポーランドの美しい風景や歴史に触れる。
劇中彩るは、ポーランド出身のショパンの曲の数々。これが絶品。
ああ、良かった、楽しかった…だけで終わらない。
ちょっぴりのほろ苦さ、抱える悲しみ、痛み…。
ジェシー・アイゼンバーグの才(監督・脚本・製作・主演)に感嘆。
自分たちのルーツや自分自身。共に40男二人の心の旅路。
片や真面目で心配症。片やマイペースでトラブルメーカー。片や家族持ちで、片や独り身。何もかも正反対。
デヴィッド×ベンジーの掛け合いがメイン所で、ジェシー・アイゼンバーグ×キーラン・カルキンの素晴らしきケミストリー。
どちらがどちらなんて愚問。天才役多いが、ネガティブ人間も十八番。アイゼンバーグのハマり役。
何もかも正反対なのに、呼応するようなキーランの存在感。
言うまでもなく、あの名子役の弟。長らく兄の陰に埋もれていたが、数年ほど前からTVシリーズなどで実力が評価。
そんな絶好時に、本作。かなりの図々しく図太い性格で面倒臭い面も。が、ただの困ったちゃんでなく、不思議な魅力や人間味がある。所謂嫌いになれないタイプ。
劇中でも笑わせ、何かしでかすかもしれないと目を離せず、背景にそうとは見えない悲しみを滲ませ、しんみりさせる感動に大きく貢献。彼の全てが本作のハイライトだ。
本作の名演とこれまでの地道な努力がオスカー助演男優賞という形になったのも納得。
にしてもベンジーの良くも悪くも周囲を巻き込む破天荒な言動と、振り回されるデヴィッド。
ツアーの面々に迷惑がられたり、好かれたりのベンジー。
記念碑銅像の前でポージング写真。デヴィッドは断るが、ツアーの面々は参加。ベンジーの人を惹き付ける才…?
列車を乗り過ごしてしまった。戻りの列車に無賃し、車掌をやり過ごしながら、降りる方法教えま…いえいえ、こういう事しちゃダメ! 反面教師的に教えてくれます…多分。
ツアーの面々。ツアーガイドのイギリス人男性、ユダヤ人老夫婦、ユダヤ人女性、ルワンダ虐殺を経験しユダヤ教徒になったルワンダ人…。主演二人の土壇場の中で各々個性を見せ、彼らとの交流も見所の一つ。
美しい風景とクラシック名曲でポーランド観光に浸れるが、本作はユダヤ人の悲劇と歴史を知る教養の旅でもある。
ツアー参加者はただの遊び気分じゃない。自身のルーツや己を見つめ直す。
ポーランドという国やユダヤ人について詳しく知らない日本人の私が知った風に語るべきではないだろう。
ツアーガイドが説明してくれるし、その場その場が物語る。
ただ迫害されただけじゃなく、勇敢に闘った秘話。
強制収容所。壁に染み付いた青いシミ。ゾッとした…。
今も国のあちこちに残っている。風化されない為に。
日本人にポーランドやユダヤ人の歴史と言われてもピンと来ないかもしれない。
ならば、こう思えばいい。
広島/長崎を訪れ、戦争の傷痕に思いを馳せる。
戦争を遠い昔と思うなら、大震災。阪神淡路や東日本、昨今だと能登。未だ残る傷痕。
今年は終戦80年だが、戦争は風化されつつある。大震災も関心薄れつつある。
風化させてはならない。忘れてはならない。
その悲劇・歴史・傷痕に激しく動揺したのは神経質なデヴィッドではなく、ベンジーの方であった。
列車移動する自分たちに違和感。あの時代、ユダヤ人が列車で移動させられると言ったら…。
墓巡り。知識をひけらかせてただ解説するのは違う。
今を生きる我々は犠牲になった同胞を歴史の1ページとしか見ておらず、傲慢や敬意に欠けている。もっと謙虚に彼らに寄り添うべきだ。
彼の発案で石を置く気持ちの証が素敵だ。
言いたい事、分かる気がする。
実は誰よりも人の心の痛みが分かるベンジー。
何故なら、本人がそうだから。
半年ほど前、自殺未遂を起こしたベンジー。
理由は語られない。特定の理由にしなかった事で、何かを抱える現代人皆に通じる。
それもあり、疎遠となったデヴィッド。
心配していた。
助けや支えになってあげられなかった。
それを吐露するシーン。
ああいう奴でも根は繊細なんだ。
陰ながら心配し思いやる優しさにジ~ン…。
40男二人が面と向かって傷を癒し合うのはちと小っ恥ずかしい。
凸凹言い合いしながらも、こうやって会って、旅して、他愛ない話をするだけでも。
どれほど力になれるか。支えになるか。嬉しい事か。
自分たちのルーツや自分自身。旅の中で痛みを知って、向き合って。
大きく人生や価値観が変わったとは言わない。
何も変わらないし、何か少なからず得たかもしれない。
しかしきっと、これからの旅路のより良い活力になった。
キーラン・カルキン❗️
言いたい事をズバズバ言って、空気も読めなくて、自分勝手で何にも気にしなそうなんだけど、どこか影があって悲しみや問題を抱えているベンジー。
そのベンジーを演じたキーラン・カルキンが素晴らしい❗️
ベンジーとデヴィットが従兄弟という距離感も良かった。
痛み=生
人間の生き方について深く問いを投げかける映画はたくさんあるが、今作は生を「痛み」という視点で見ていく。
ビンタされた時のような身体的な痛みから、家族の死と向き合う時のような精神的な痛みなど、誰もがそれなりの痛みを抱えて生きている中、登場人物一人一人の痛みも描かれていく。
ホロコーストという人類史上最大の痛みの一つを取り上げているにもかかわらず、それでも映画は驚くほどさっぱりした仕上がりで、淡々と情景が流れていく。
今作の好きなポイントは、結局痛みと共に生きていくしかないという点をあっさりと見せていること。強制収容所が残酷にも人々の生活のすぐそばにあるというのもショックだが、痛みと共に淡々と進んでいく人生の旅を表している。しかし、それは絶望的でなく、無気力にも感じさせない。
個人的に好きなシーンは、亡くなったおばあちゃんの家の玄関に弔意を表し石を置いたベンジーとデイビットに隣人さんが「危ないからやめとけ」とばさっと言い放つシーン。思わず吹き出してしまった笑
全218件中、1~20件目を表示