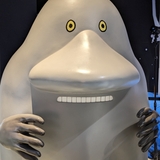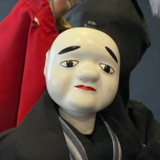海の沈黙のレビュー・感想・評価
全202件中、41~60件目を表示
ポエム的あるいは演歌的
先生のお嬢さんを巡る三角関係。ずる賢く立ち回り、社会的な成功を手に入れる男。画壇から放逐され、放浪しながら贋作と刺青で生計をたてる孤高の天才画家。どうも今の時代の感じがしない。大正とか昭和前期とか…。
女の肌と刺青。北の港町。父を飲み込んだ海とそれを照らす炎。真作を超える贋作。30年ぶりの再会。などなど、情念、情感を掻き立てる要素は満載なんだけど、ストーリーというよりは演歌の歌詞みたいな感じ。
これに浸ろう!と思ってみる人にはいいだろうけど…。
石坂浩二と本木雅弘がほぼ同じ年頃というのは、いささか無理がある。ライバルを蹴落とすのにどんな悪辣な手を使ったかは知らないが、そもそも、お嬢さんの背中に観自在菩薩を彫ろうという点で、陰謀とかなくても放逐されていたのでは…。
ここの海の表現はお前より上、とか言われても、僕なら、で、それが?という感じしかしない…。
天才の謎
倉本聰の新作に食指。
一般に巨匠と呼ばれる画家の高齢期の作品には、匠気も緻密さも消え去り、高揚感のみを叩きつけるような迫力を感じますが、さて倉本作品は。
監督はあくまで進行役という感じなので、脚本の完成度の高さは感じるのですが。
宮崎駿みたくもっとハチャメチャにやっちゃって良かったと思いますね。
冷静沈着な概括が倉本作品の若さであり、脚本家の宿命なのでしょうが。
晩年の画家の激情に対する憧憬の思いを感じました。
モックンはため息が出るほど美しいのですが、この役には少し早かったかな。
キョンキョンは実にいい顔をしていた。
キョンキョンのシーンだけを集めて観ていたいくらい。
コメントを寄せた著名人の中に津山に匹敵する天才アーティストがおりまして、天才は天才を知ると言うことで、彼女のコメントの中に作品の謎を紐解くヒントがあるとは思うのですが…
情けない事に私には彼女の言葉のいとが理解出来ないのでありました。
中々理解が難しい作品でした~
古いねぇ
金田一(石坂浩二)さん、小池(中井貴一)さん、事件です、贋作です。
モックンの演技、特にラスト近くの気迫の演技が、印象的。キョンキョンも熟女になってきて、歳相応の演技が良かった。だか、配役の設定が??だと思う。石坂浩二の実年齢83歳。モックン58歳、仲村トオル59歳。同期という設定は無理があるでしょう。下手したら、モックンは、石坂浩二の息子役でもOKだと思う。石坂浩二には申し訳ないが、せめてモックンたちと歳の近い阿部寛とか、椎名桔平に演じて欲しかった。中井貴一は、相変わらず上手だが、「嘘八百」の古物商の小池さんのイメージがあるので、贋作云々という映画での出演はどうかな…(←もっと何年か後だったら良いかも)
あと、清水美砂の自死の理由と刺青に拘る理由が理解できなかった。😩
清水美沙の尻
なんだろう、とにかくストーリーが面白くないて退屈きわまりない。
中井貴一や小泉今日子の良さもあんまり出てなかったな。
仲村トオルもあんな端役で使うとかもったいない。
清水美沙の尻は良かった。
美の価値は
美の価値は誰かの評価によって決まるのではない。美そのものに価値があるのである。
絵画を題材にした美を追求する映画である。
生い立ちの不幸から美術の世界にのめり込み、不穏な出来事を経てやがて贋作制作に携わる竜次。
竜次の学生時代の恋人で、今は竜次のライバルだった田村の妻となっている杏奈。
数十年ぶりの再会。手が触れた一瞬に時を遡る。
けして幸福とは言えないここまでの2人の人生。お互いの人生について知る由もない。
ただ再会の場に喜びの笑顔はなかった。
死の床で聞いたかつての恋人からのありがとう。竜次は床を抜け出し絶筆となる絵を完成させる。
それは海で遭難した両親をなんとか救いたい竜次の血の色をした真っ赤な心の炎だ。
ここからは私の連想したこと。
厄介事のほんどは人間関係の厄介さ。
それまでのその人の人生など知ることもなく、ただ今のその人だけを見て、勝手に良い人そうでない人などと判断しがち。来し方など想像もせずに、人間関係が悪いなどと一方的な愚痴を言いがち。想像力と冷静な判断力、気をつけたい。
濃厚かつ重厚な邦画
さすが倉本聰、至極の物語
謎のご婦人キョンキョンは綺麗だが
一枚の絵、それのみの美の是非をあなたにも問う映画
「著名画家」というブランド有無で世間の絵の評価判断が左右するのは事実であり、この映画が伝えたい「一枚の絵、それのみの美の是非」にまったくの同感でありますが、一方で「倉本 聰」の脚本(ブランド)でこの映画を観に行ったのも事実であります(笑)。
映画に出てくる絵画は、パッと出も含めて総じて素晴らしく、この物語にふさわしいものばかり。スクリーン映写を通しての絵であるものの、何度も心動かされます。実際は誰が描いたのかCopilotで調べたのですが、「それは興味深い話ですね」と、訳わからない回答がきたのでわかりません。(パンフレットには書かれているのでしょうね)音楽や映像も美しく、それらを背景に田村安奈(小泉今日子)と津山竜次(本木雅弘)の人生晩年を迎えた役同士の再会シーンは、時の流れや変化により変わるもの、変わらない事を静かに感じさせてくれました。好演です。一方で津山と田村修三(石坂浩二)が学生時代の同期という設定は、本木さんが老けメイクしても年齢差は埋められず、観る側を混乱させるミスキャストと言えます。これを良しとしてまかり通ってしまうことがまた、「巨匠ブランド」の負の部分と言えるでしょう。
この物語のポイントとなる田村の描いた絵に描き加え、より良くしたという行為ですが、画力が制作者以下であっても、本人と違った視点が加わることによってブラッシュアップされることがあります。なので、終盤まで津山が天才的な画力を持つことを示すオリジナルの絵が一度も出てこなかったために、ラストシーンの一枚に期待したのですが、死線を乗り越え、熱く描き続けるシーンを見せつけられた上で出来上がった津山の絵は、果たして田村の絵を越えたのか。
「映画のラストを飾る絵だから」といった前置き無しに、ただ一枚の絵を見た時にあなたはどう感じるか。この物語の最後、観る側にもこの物語のテーマを突きつけてきた気がします。
話は普通、役者の演技美
倉本聰 89歳
巨匠
とは相性が良くない。
彼のドラマにハマった事はない。
だから、集大成とは言われてもそれほど興味はなかった。
だが、時間的に他の選択肢がなく、消去法ですらなく観賞。
そんな後ろ向きな姿勢だから、初めから懐疑的。
だが、入りは意外に良かった。
予告編でわかっていたことではあったが、
贋作の経緯には興味を惹かれた。
残念ながらその後はどんどんトーンダウン、
特に目を見張るような展開はなく芸術のありようのような話に。
不滅の恋とやらも個人的には全く響かず、
経緯の説明不足で不可解さだけがどんどん募った。
刺青を取り上げていることにも嫌悪感が残った。
そして、最後の高尚なナレーション。
巨匠はこれを主張したかったのかʅ(◞‿◟)ʃ
それとも、もしかして自分も有望な若手を潰してきたという懺悔?
後者なら⭐︎2つ増やすけどw
元木はじめ俳優陣は大熱演。
個人的にはそれが大仰で舞台のように見えた。
また、石坂浩二は年齢的に違和感ありすぎじゃ?
巨匠の御希望?
全202件中、41~60件目を表示