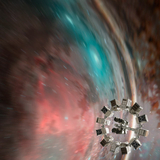本心のレビュー・感想・評価
全151件中、41~60件目を表示
次々枝分かれし空中分解
テーマと俳優はいいが…
親子愛という原点から次々枝分かれしていき空中分解していく様をみました。
感動すべきシーンはクライマックスも含めことごとく感情移入できず。
核たる部分を120分かけて丁寧に掘り下げ描写されていたら…。
あくびがでてしまいました。
今後もSF邦画の発展をいのります。
もっと冗談ぽく言ってよ
保証しますよ、本物以上のお母さまをつくります。
一年近く眠り続けた人間が、髪型も、爪も、髭も、そのままなのか?って時点で物語を受け入れるには抵抗があったが、それはさておき。
『本心』と言うより、副題の『The real you』のほうがより内面の葛藤が伝わってくる気がする。『PLAN75』のように、自分で死を選ぶ制度ができる近未来。母が自由死を決めた理由を知りたかっただけなのに、知らなかった、知りたくもない事実や感情を目の当たりにする戸惑い。わが身が石川朔也と同じ立場になり得た時、そして同じような事実を知った時、同じように戸惑い、後悔する気がする。でも人は、見たくもないのに見られる状況(例えば覗きやストーカーや盗撮もその延長だろう)にあると欲求に勝てない。うまい匙加減で、こっちの心理を揺さぶって来るなあと思った。
だけど、どこかムズムズしていた。これは"あっち側の人間"が描く、"こっち側の人間"の話。あっち側=富める者と、こっち側=貧しき者。なんでだろう、何か高みから眺められている不快感かある。不快感の向く先は、役者ではなく、原作者に対してなんだが。それを"こっち側の人間"の僻みととらえても仕方がないかもしれないけど。
リアルアバター、ウーバー進化版の代行サービス、近い将来こういうもんが出てきたら、人はどれだけ心がすさんでいくのだろう。最後に添えられた手は、そんな壊れていこうとする未来への”希望”なのだろうか。
全体のストーリーは面白いんだけど。
死んだ人間のアバターをつくって会話するってのはもう始まっているけど、かなり気持ち悪いよね、ってぼんやりした感情を映画化してくれたのはチャレンジングだし評価したいんだけど。
映画全体に細かいノイズがあって、いまいちその世界に入り込めなかった。
ロボットが溶接している隣で溶接している人間が「そのうち俺たちはいらなくなちゃうよ」なんて会話するんだけど、いつの時代の話?80年代?90年代?_って思ったら2025年ということらしい。
そんなことあんたが生まれる前から言われてたことだよ、岸谷君。って心で突っ込みをいれたらなんか止まらなくなっちゃって。
病室の窓からの景色が、真っ赤な紅葉→雪景色→満開の桜と変化することで1年たちました!ってことを表現するんだけど、桜は紅葉しませんけどって思ってしまう。
ここ数年は、横浜流星と池松壮亮を交互に見てるんじゃないかって言う感じなので、この人は仮面ライダーじゃないし、野良の殺し屋でもないって言い聞かせながら見てるのに、三好彩花の役を三吉彩花が演じてるから、プチ混乱してしまう。
これから死ぬって人が最後に挨拶するのがリアルアバターってことはないんじゃないの?プラン75の倍賞さんの状態ならわかるけど、家族に囲まれてるのにバイトに向かって『ありがとう』っていう人生の最後はどうなのよ?
全体としては面白い話なんで、もうちょっとノッて観たかったという感じがするな。
もったいなかった。
A271 汗臭い!?言われたらショックやで
2024年公開
池松壮亮イライラする~!
でもそれだけ役に入り込んでいるわけで素晴らしいです。
オカンの本心なんか聞きたいか?
ウチのオカンも結構今までの人生にて愚痴聞くけど
まあその時によってよう変わりますわ。
人間なんかそんなもん。
¥3百万もよう出せんわ。
宣伝は妻夫木が怪しげでしたが
それよりもリアルアバターが怖い。
今のウーバー配達員の仕組みを見ていると納得感高い。
使う奴はどう考えてもまともとは思えず
いずれ闇バイト風に利用されるかな。
実際そういう描写もあるが。
まあこいつらアカウント停止は間違いないけど。
三吉彩花ってこんなに良かったっけ?
ちょっと背が高すぎるけど。(関係ないか)
70点
鑑賞 2024年11月18日 ムービックス京都
配給 ハピネット
自分の本心も気づいていない時があるのに
原作は未読。
リアル・アバターという職業ができていたり、仮想空間に作られたバーチャル・フィギュアなるものが実現できていたり、自由死という制度ができていたりと思ったよりも近未来の話だった。リアル・アバターはウーバーの配達待ちをしている人たちを思わせるし、たしかに悪ふざけをするやつらも出てきそうだし、それによって低評価にさせられる人たちも生まれそうではある。近未来感の加減はなかなかうまい。
話の方は、亡くなった母が自分に話そうとしていた「大切な話」を知るために、母のバーチャル・フィギュアを契約するというもの。同居することになった母の友人・ミヨシアヤカとともに探るうちに2人の距離も近くなっていく。自由死という制度に対して、ぼんやりとした説明しかなかったし、バーチャル・フィギュアにしても説明不足な印象は拭えない。たぶん原作ではそれなりに説明がされているのだろうと想像する。その説明不足なところが原因だろうか、一応感動の結末のはずだが、今ひとつ伝わってこなかった。
結末まで観て思うのは、自分の本心もちゃんと気づけていないときがあるのに、他人の本心なんて理解できるわけがないということ。でも、わかり合おうとする必要があるし、例え幻想であってもわかり合えたと思える瞬間は貴重なんだろう。それがテーマなのかは定かではないけど。
それにしても、ミヨシアヤカという女性の役を三吉彩花が演じていることに戸惑ってしまった。これは原作者が彼女をイメージして役名を決めたのか?映画化するときには原作者の意向でキャスティングが決まってたり、シャワーのシーンなんかもちゃんと撮ってほしい旨伝えられたりしたのだろうか。なんて妄想をしてみた。もちろんそんなことはないはず。
現代版"たった1年の浦島太郎"
原作は未読、予告編の不思議さに魅せられて、鑑賞しました。
予告編から、謎解きサスペンス映画を想像しましたが、ただの近未来映画でした。
未来あるあるのハリボテ的な多々問題を、紹介だけして、何も解決できないならば、
せめてひとつのテーマに絞って、掘り下げた方が良い作品に仕上がったと思う。
浦島太郎現象は、1年後ではなく、せめて5年以上後位にした方が、作品としての説得感があったと思う。
それでも、近未来ギアはすべて、チープでダサかった。
ウーバーイーツ的な活動と。友人の存在全てが、作品を惑わすだけで
本来 語らなければいけない 事から、かけ離れているだけで、不要だった。<糞脚本賞>
すなわち、映画の中で、"言いたい事・表現したい事"が、支離滅裂で、作品の筋が通っていなかった。
主人公の最初の ぶっきらぼうなせりふが。。。下手なのが 映画の冒頭で気になって、映画に集中できませんでした。
得るものも、考えさせることもない
この映画を観たら、家に帰って「浦島太郎の絵本」をもう1度読破した方が、楽しいかもしれない。
SFからもはや現実に落とし込まれたAI、仮想空間の設定が秀逸
予告編を観て、ゾッとするような怖さを感じた。演技派の池松壮亮、田中裕子というキャスティングにも惹かれて観賞。
【物語】
朔也(池松壮亮)は母(田中裕子)と2人暮らし。工場で働き、裕福では無いが平穏に暮らしていたが、最近母の様子が少しおかしいことが気に掛っていた。ある日工場にいるときに「今晩大事な話がある」という電話を受け取る。約束が有り、すぐに帰ることは出来なかったが、嫌な予感がして家路を急ぐ朔也は、豪雨で今にも氾濫しそうな川べりに立つ母を目にし、駆け寄ろうとするが次に見たときには母の姿は無かった。咄嗟に川に飛び込んだ朔也は、命は助かったものの昏睡状態に陥り、目覚めたのは1年後だった。
母は生前に「自由死」を選択していたことから自殺と断定されたと警察に聞かされる。 眠っていた1年の間に工場は機械化により朔也の仕事は消失していた。 幼馴染みに紹介された新たな仕事を通じて、仮想空間上に任意の人間を作るVF(バーチャルフィギュア)という技術を知った朔也は、ほぼ全財産を注ぎ込んで母のVF制作を依頼する。目的は母が”自由死”を選んだ理由を知ることだった。VFのINPUTデータとして母の生前の情報を集める中で、母には若い友人(三吉彩花)がおり、彼女は朔也の人生に大きな影響を与えた昔の同級生にそっくりであることを初めて知る。
【感想】
設定がタイムリーであり、秀逸。
昨今CHAT-GPTなどの出現によってAIが急激に身近になった。使ったことのある人は皆、「もうここまで来たんだ」と思ったのではないか。
俺もPCからある質問を投げたときの回答があまりに理路整然としていたことに驚きを隠せなかった。 映画の世界ではだいぶ前からAIによって人が支配されるSFが描かれていたが、それがいよいよ現実になりつつあると実感する。 そうなると、便利さを越えて誰しも恐怖を感じるようになる。
SFではそれが戦争・殺人などに繋がって行くが、既に商品化されているバーチャル空間用ゴーグルを使ったバーチャルフィギュアという、ずっと身近な形を設定し、SFとは言えないより身近さを演出している。架空の人物を作り出すという部分は、少なくとも庶民が手に入れられる価格でまだあそこまで制作することは出来ないと思うが、3~5年後はあそこまで行くかも知れないと思わせるリアリティー。 実際手に入れたら朔也同様、嬉しい現実である一方怖くなるだろう。
この設定の巧みさに加えて、予告編からは母と息子の関係に焦点を当てたドラマを想像したが、もっと様々な人間関係や過去と現在が絡んで見応えのあるドラマになっていた。
人間それぞれの裏に隠された真実、本心を覗き見る、ホラーと言うと言い過ぎかも知れないが、怖いもの見たさをくすぐる作品。
バーチャルと生身の人間との乖離を埋めるはずの想像力の欠如
バーチャルの始まりは、アルタミラ洞窟の壁画にまで遡るという話を聞いて、とても納得したことがある。言語や文字もある意味バーチャルだが、電信や電話、はたまた、ラジオやテレビ、PCやVR、本作のようなAIを活用したVF(バーチャルフィギュア)と、現代に近づくに連れて加速度的に進化を遂げて来たバーチャル化に対して、生身の人間の進化の速度はそれほど速くはないと思う。体格は少しよくなったし、寿命も延びた。でも、中身は案外1000年や2000年前と違わないんじゃないだろうか。
それ故に、急速に乖離するバーチャルと生身の人間、そしてその乖離は、いつしか、バーチャル空間を通してやり取りする、生身の人間同士の関係にも当てはまるようになってしまった。
映画で描かれているように、資本を持つ者にとって、朔也たちは人格を持った人間ではなく、リアルなアバター。あくまでもアバターなのだから、クライアント側は何の良心の呵責もなく雑に扱える。
また、アバターを雇うゆとりがないコインランドリーの客のような者も、相手の弱みを見つけると、暴言や暴力でマウントを取ってストレス解消を図ろうとする。自分とは直接関係しない人間だから。
どうしてそうなるのか。というより、なぜそういうことができるようになってしまうのか。
理由のひとつは、圧倒的に増加していく情報量の中で、それを人より素早く処理して優位性を保つことには経済的な意味があるが、他者とのコミュニケーションは、いわゆるコスパの面では優先度は低くなっていることにあると思う。そして、その先に起きているのが、映画が描く「自由死」が制度化された世界の姿ではないだろうか。
象徴的な所で言うと、妻夫木演じる野崎の娘。生まれつきの環境のおかげで、デジタルには詳しいが、決定的に道徳が欠如している。本来、人との関わりの中で育まれるはずの想像力がないのだ。こんな悪魔のような人間がうじゃうじゃと湧いて、これからのイニシアチブをとっていく世界は、残念ながら明るい展望を持つことができない。
大賀演じるイフィーも「交通事故にあった俺だから、“そちら側”の気持ちが想像できる」とか言って二分している時点で、間違えている。不遇な環境に置かれたものを、本人の努力不足や自己責任と無自覚に断じていることに気づいていないのだから。
逆の意味では、過去のトラウマから、人とふれ合うことが出来なくなってしまった三好の存在がリアルに迫ってくる。そして、他者とのコミュニケーションで大切だったのは、実は「体温や触覚」だったのではないかとまで思わされた。(朔也と三好2人の場面では、鍋の暖かさ、シャワーの冷たさなど、温度がさりげなく強調されているし…)
それにしても、「本心」ってなんだろう。
「真実はいつもひとつ!」なんて、単純なものじゃないよなぁと思う。
こちらが、原作の平野啓一郎イコール「分人主義」と思って観ているせいもあるけれど、その人との関係を離れた「本心」なんて、単なるフィクションに過ぎないし、陰謀論のように、ない物をあるはずと思って探し続けるのはナンセンスだよというのが答えかも…。
ラストシーンの解釈について、いろんな人と語りあいたい映画。
石井裕也監督の作品、自分は結構好きなんだなぁということを改めて思った。
役者たちはみんな素晴らしいが、特に三吉彩花の光り方にやられた。
テクノロジーで補えないもの
すぐそこに来る未来のような、もう始まっているような世界。ただ、あらためて感じたのは、技術が進歩しようが、AIが日常を運営しようとも、人の心に関する事は人にしか理解出来ない、また人が関わり続けなければならないことだという事。使う側使われる側、のような格差も描かれていて胸が痛む。
原作を読んで自ら映画化を望んだという池松壮亮の本人であるかのような演技、他全てのキャストが自然で、説得力のようなものを感じ入ってしまった。どんなに自動化やらAi運用やらが進んでも、人の心が大切であることは変わらないと実感出来る作品。
本心とは何か?を問いかける良作
近々あり得る話しだが、大事な話しって・・?
最後のシーンで全て救われた
さようなら、母さん
2024年映画館鑑賞108作品目
11月17日(日)イオンシネマ石巻
通常価格1800円−dポイント300円
原作未読
原作は『マチネの終わりに』『ある男』の平野啓一郎
監督と脚本は『川の底からこんにちは』『ハラがコレなんで』『ぼくたちの家族』『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』『町田くんの世界』
『生きちゃった』『茜色に焼かれる』『アジアの天使』『月』『愛にイナズマ』の石井裕也
粗筋
母秋子が息子朔也の目の前で雨のため激流の川に身を投げ自殺した
救おうと川に飛び込んだ朔也は重傷を負い一年近く意識不明で入院していた
母は政府が新たに導入した自由死という制度を利用し自殺したのだった
勤めていた工場は完全機械化され知らない間に無職になっていた
一年後リアルアバターという一種の代行業に転職していた朔也は幼馴染岸谷の紹介でVF(バーチャルフィギュア)の開発者野崎と出会い亡くなった母をVFによって蘇らせることを依頼した
さらなるバージョンアップをするために野崎の勧めで母の友人の彩花と会うことに
朔也が知らない母の事実が明るみになっていく
三吉彩花の役名が三好彩花
なぜこんな紛らわしいことをするのか
いろいろと事情があるのだろう
石井裕也監督のことだから深い意図があるんだろう
ネットで検索すれば容易にわかることだが今はやらない
シャワーを浴びるシーンで嘘みたいなボインを披露
峰不二子を彷彿させる漫画みたいなオッパイ
彼女には大変失礼だがあれが1番嘘っぽい
死にかけの田中泯の芝居が良い
朔也を通じてイフィーに告られる彩花の表情の移り変わりが良い
彼女はわりとうまい
なぜかつてあんなマイナーなアイドルグループに所属していたのか事務所の売り出し方が疑問
普通にまずはファッションモデルとして売り出せば良いのに
とはいってもさくら学院からBABYMETALが誕生しているからな
あといわき市出身の松井愛莉もそれなりによくやっている
近未来を感じさせるのは前半の方で後半はちょっと「うーん」
最後の方はなんとなくモヤっとした
思ったより田中裕子の出番が多くない
母と息子のやりとりが中心の作品かと思いきやそうではない
朔也と彩花は同居はするが男と女の関係にはならない
恋人ではなく同居人だ
彩花は朔也に好意があるようだ
結局ラストがよくわからない
観る側に委ねたか
亡くなった母との再会といえば風間杜夫主演『異人たちとの夏』を思い出す
あちらは幽霊でこっちはVF
科学が発展するとあの世の世界はどんどん風化していくのだろうか
そういえば『エコエコアザラク』というホラー漫画で母を亡くした男が手術で体の一部に母の顔を作り一人二役をする話があった記憶がある
まあだいぶ昔の話で当時は小学生だったはずだからあてにはならないが
あと『激烈バカ』で息子に対してじゃなくて夫に残した最期の言葉が「ヘタクソ!」ってのも笑えたなあ
あれが1番の本心だろうけど最後の最後で命を振り絞って鬼のような顔して言い放ちすぐ息を引き取る中年女性を今でも痛烈に覚えている
配役
亡くなった母をVFで再現した一人息子で一年間意識不明で入院し退院後リアルアバターに転職した汗っかきの石川朔也に池松壮亮
自由死を選んだ朔也の母で同性愛者の石川秋子に田中裕子
秋子の親友だが年齢は朔也にだいぶ近い元SEXワーカーの三好彩花に三吉彩花
朔也の幼馴染で2人で中国に移り住みたい岸谷に水上恒司
朔也に惚れ込み彩花に惚れた著名なアバターデザイナーだが交通事故の影響で残り一生車椅子生活を続けなければいけないイフィーに仲野太賀
朔也のリアルアバターのクライアントで病院で薬物による自由死を選んだ若松に田中泯
VFの開発者の野崎将人に妻夫木聡
野崎の娘で生意気なあずさに太田凛音
野崎のお手伝いをするVFで元になった人物はすでに病死している中尾に綾野剛
朔也の高校時代に片思いしていたクラスメイトで売春がバレて退学する村田由紀に宮下咲
村田由紀に対する侮辱的発言で朔也に首を絞められる高校時代の担任に結城貴史
朔也に写真で遺体の確認と母明子は捜査の結果「自殺」と伝えるベテラン刑事に二階堂智
ベテラン刑事に同行した若い刑事に笠原秀幸
コインランドリーの清掃員に中村中
コインランドリーで清掃員にキレまくる利用客に大津尋葵
レストランの支配人に佐藤貢三
レストランのウェイターに福田航也
レストランのピアニストに後藤亜蘭
ふざけたクライアントの指示で朔也がメロンを買おうとした高級果物店の店員に坂ノ上茜
リアルアバターの先輩に前田勝
リアルアバターの先輩に佐野弘樹
リアルアバターのAIアシスタントの声に窪田正孝
人間の本心はAIのデータには到底入らない。
今まさになりつつあるバーチャル世界とそれを操るAIをもてはやす社会を危ぶむ識者のどちらが人間にとって善なのか。
愛する人の死後、残された者は故人がどう考え、何を思っていたのか、とても気になるが知るすべは無い。それはAIを駆使してアバターとして蘇ったつもりになっても故人の思考は蘇られない。当たり前だけれど。
だから生きてる今をもっと大切に、周りの人と関わり合うことの大切さを知らせてくれる映画。
親孝行したい時には親は無しとは良く言ったものです。こんな昔から言い古された格言、これこそ人間として生まれて来た者の永遠のテーマなのではなかろうか。それは戦前、戦中、戦後、現代、未来、どんなに技術が進み今現在では想像もつかない物が出来、事になっても変わらないのだろう。
だからこそ人と関わり合うことの大切さ、人への思いやり、優しさが大事なんだろう。
愛しい人が故人になる前にしておかないと、いなくなってから後悔することのないように。
でも中々出来ないんだよね。
作品の中身はと言うと今すぐに起こりそうなAIに人間が評価され、AIに人間が指示されて動くようになる仕事は嫌な世界だなと危惧します。そういったことへの警鐘の意味も原作にはあるのかも。
三吉彩花さん、表情だけの演技すごかった!
<まずは、他の人が書かなさそうな事から>
三吉彩花という役名で出てくる女優は、三吉彩花だよね。役名が女優名を使っているのはなんでかな。ただ、三吉彩花さんは単なる「美形のモデルあがりの女優」かと想像していたら、なんのなんの!すばらしい演技でした。特に、セリフなしで表情だけでの演技。顔は口ほどにものを言うといいますが、表情だけで、みるみる心の変化が起きているあの演技力は、すごい評価されそう。
あと気になったのが、「竹内力」という名前が、エグゼクティブプロデューサーとして、エンドロールでクレジットされていたのですが、竹内力って、あの竹内力か?
そして、田中裕子のクレジットは、一人だけロールではなくフェードインで表示されて、ここでも貫禄?を見せていた。 エンドロールもいろいろな情報が入ってておもしろい。
<さて、やっと映画の感想>
時々思う事ですが、映画の予告が、必ずしも映画の本質をちゃんと予告していない事がある。
最近では、シビルウォーがそれ。 この映画「本心」も、予告だけを見れば、近未来のAI に翻弄される人間を描く事が、ストーリーの中心かと思っていたが、あくまで一つの舞台設定に過ぎない。
亡くなったお母さんの「本心」を知りたいと思って、VFを提供する会社の門を叩き、そこから知らなかった様々な側面が出てくる、という部分には予告編との違いはない。しかし、この映画が本当に描きたかった「本心」の姿は、、、、 ぜひ映画を見てください。 暗い話ではなく、最後はハッピーエンドな雰囲気で締め括る、ほんのり暖かな良質な映画でした。
詰んだ人生の起死回生が「中国に行こうぜ」の連呼とは?
予告で観た、田中裕子さんが何気なく戯けながら踊る仕草と、流れる楽曲が印象的だったので、鑑賞した次第。
多分に原作を読まない限り、映画だけでは本質は掴めないと判断。原作者が書いた分人主義の流れを汲んでいるのかしら? とは思っていたのですが、そのような印象かな。
全般的に、脚本に散りばめられた「各人には秘められた分人が存在する」的な要素が大仰すぎてノイズに感じられて、素直に鑑賞しづらかった。とはいえ、目を引く要素にもなっているんで楽しめる部分でもありました。
しかしなんだろう、このテクノロジーを不穏なモノ、異質なモノとして捉える演出は、いつまでも変わらないもんですねー。
ところでなぜそこまで中国に行きたいんだろう? 本作の世界観設計で唯一わからなかったわ。まー「アメリカ行こうぜ」も今更感は出るだろうけどさー。
全151件中、41~60件目を表示