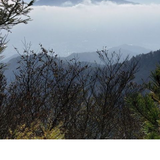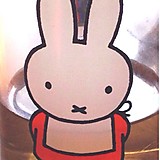宝島のレビュー・感想・評価
全142件中、1~20件目を表示
『国宝』と『宝島』の深層構造 カタルシスと反カタルシス(『宝島』バージョン)
李相日監督『国宝』は、ヤクザの子・喜久雄と、歌舞伎役者の子・俊介のふたりで演じる「二人藤娘」「二人道成寺」が目を引くが、なにゆえ二人演目なのか。
物語中、喜久雄と俊介が歌舞伎舞台から上方を見て、「あそこから何やらずっと見てるな」と頷き合うシーンがある。
文化人類学者の山口昌男は、渡辺保『女形の運命』を参照し、こう書いている。
「歌舞伎の舞台においては、二人の役者が舞台のほぼ中央の一点との関係において作る三角形があり、この三角形の頂点は、舞台の空間あるいは観客の視線の力学上の中心点である。そしてこの『中心』には深層に通じる意味が匿されている。この『中心』の意味は、歌舞伎の最も『神話的な部分である』『三番叟』を見るとよくわかる。『三番叟』で翁になった一座の統率者(座頭)は、この『中心』である舞台正面へ来て平伏する。この礼は、観客は自分達に向けられたものであると誤解するが、実は、観客席の屋根の上にある櫓に対して行われたものである。櫓はいうまでもなく神降臨の場であり、この礼はいわば降臨する神への礼である」(「天皇制の象徴的空間」、『天皇制の文化人類学』所収)。
ふたりを見守っていたのは「神的な何か」であろうが、「天皇制の象徴的宇宙を形成するモデルは演劇の構造の中に再現される」(同書)。とすると、それは天皇制の中心にいる「天皇」にほかならない。
こう言ってよければ、喜久雄はヤクザ=周縁の出身だ。「賤(しず)の者」である。高貴な出身の者が、何らかの事情で身をやつして漂流し、しかし本来の身分が知れて復辟する「貴種流離譚」という物語類型があるが、喜久雄の場合、この逆である。だが、天皇制は、対立する極性を包括する構造を持っている。賤の者を貴い者へと転生させる。
喜久雄は、ある景色をずっと探していた。「鷺娘」の終幕で、光に包まれる喜久雄=花井東一郎は、「天皇」の威光の中で、その景色を見たかのようだ。だから「国宝」になれる。
日本のZ世代が、皇族を単なるタックスイーターだとしか思っていないのであれば、こうした「天皇ロマン主義」は雲散霧消し、天皇制は消滅するのかもしれない。だが、空白になった「統合の象徴」に、何がやって来るのか。
大友啓史監督『宝島』は、米軍統治下の沖縄で、米軍の物資を奪って民衆に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる者たちを描く。
宜野湾市の売春街「真栄原新町」の誕生と消滅を追ったルポルタージュ『沖縄アンダーグラウンド』で、藤井誠二は沖縄ヤクザのルーツをこう語っている。
「沖縄ヤクザのルーツの一つは、戦後の米国統治下で『戦果アギヤー』と呼ばれた、衣類や薬品などの米軍物資を基地から盗み出し、沖縄や台湾や近隣アジア一帯に売りさばいていたアウトロー集団である。『戦果アギヤー』が扱う盗品は、拳銃や火薬など戦争で使用する武器弾薬類も含まれていた。
米軍の取り締まりが厳しくなると、彼らは特飲街の米兵相手のバーからみかじめ料を取ったり、酒場を経営したりしてシノギを得るようになる。彼らは不良米兵対策の用心棒としても重宝されていた。(中略)一九六〇年代に入ると県内各地でアウトローたちが新たに頭角をあらわすようになり、それがグループ化して愚連隊になっていく。那覇市を拠点とした『那覇派』と、コザ市(現沖縄市)を拠点とした『コザ派』が生まれ、縄張りなどをめぐって血みどろの抗争を繰り返すようになった。
コザ派は主に戦果アギヤーをルーツとし、那覇派は空手道場の使い手たちが用心棒稼業をはじめたことが母体となっている」。
戦果アギヤーのカリスマ的リーダー、オンの弟・レイは地元のヤクザになり、行方不明になったオンの情報を収集している。親友のグスクも警官になり、オンの行方を追う。オンの恋人・ヤマコも、彼を思い続けている。だが、オンは失踪後、亡くなっていた。沖縄の女性が米兵との間に身籠った子どもを養育していた時に、だ。その「アメラジアン」の子・ウタも死亡する。
『ウンタマギルー』で知られる高嶺剛監督の『パラダイスビュー』で、沖縄語(ウチナーグチ)の「ヌチ(命)」と「マブイ(魂)」について話すシーンがあるのだが、ヌチは動詞的に使用されることがあり、その意味は「殺す」であるという。してみると、「命どぅ宝(命こそ宝)」は、別の意味を帯びてくる。
『国宝』には、天皇ロマン主義的カタルシスがある。マージナル(周縁的)な存在が、「歌舞伎さえ上手うなれば、あとは何にもいりません」と悪魔と契約し、どん底から這い上がって芸道のてっぺんに上りつめる。そこに天皇制の機能を感じとることができる。
対して、『宝島』にカミはいない。カタルシスも生じない。重い問いを投げかけられるのみだ。前者は「ハレ」の映画、後者は「ケ」の映画。どちらも豊かな作品ではあるが、豊かさの質がちがう。
『宝島』は、沖縄の戦後史を「蹂躙の歴史」として見せる。それが現在に続く、ヤマトとオキナワ、島国の日常だ。
(参考文献)
藤井誠二『沖縄アンダーグラウンド 売春街を生きた者たち』講談社、2018年。
山口昌男『天皇制の文化人類学』岩波現代文庫、2000年。
本土とは全く違う「戦後」の風景に脚光を当てる
沖縄の歴史を知るという視点、映画としての娯楽性という視点、個人的にはそれぞれの尺度での評価にギャップが生じた作品だった。
1972年以前の、アメリカの施政下にあった頃の沖縄の姿をここまでクローズアップした作品には多分初めて触れた。本土復帰という出来事を知識として知ってはいても、何故沖縄の人々がそれを求め、どのようにしてそこに至ったのかをここまで踏み込んで想像したことはなかったと、本作を観た後振り返って思う。
今年を戦後80年とマスコミは呼ぶが、沖縄にとっての戦後は1972年5月15日以降、しかもそれ以降もアメリカ軍は駐留したままだから手放しで喜べない戦後なのかもしれない。
本作ではいくつかの史実(厳密にはそれを元にしたエピソード)が描写される。宮森小学校米軍機墜落事故、糸満轢殺事件、毒ガス漏洩事件。沖縄の人々の怒りの発露とも言えるコザ暴動に至るまで、どんな理不尽が積み上がってきたかがよくわかる。
一方、沖縄の人々の生活の経済面は軍人軍属相手の商売に支えられており、問題の根の深さや解決の難しさを思わせる。
少し調べればそういった出来事や当時の社会構造は知識としては知ることができるが、本当に理解する必要があるのはその時そこにいた人々、直接影響を受けた人々の感情だ。物語はそこに思いを馳せる手助けをしてくれる。そういう意味で有意義な作品だと思う。
それだけに、エンターテインメント性という観点で見ると若干空回り感というか、もやっとしたものが残る感じなのが惜しかった。
要所要所ではいいと思える部分もあった。まず、主要キャストの演技は素晴らしかった。個人的には窪田正孝の危なっかしさ、奥野瑛太の振り切った今際の際、チラ見せなのに存在感あるピエール瀧が特によかった。コザ暴動の映像には迫力があった。
原作の主要キャラにまつわるエピソードや登場人物が結構削られていたが、それは原作付き映画の宿命のようなものだし、悪いことばかりだとも思わない。特に今回の原作小説は、語り部(ユンター)の口述という体裁を取っているせいかもしれないが、話が右往左往して一直線に進まないので、映画の枠に合うよう削ることで話の筋を追いやすくなった気もする。
ただ細部については、説明が足りないのではと思う場面がぽつぽつとあった。原作の情報からいくつか補足する。
グスクが洞窟(ガマ)に入った時錯乱したのは自身が集団自決の生き残りなのでそのトラウマが蘇ったからだということ、よって彼は天涯孤独であるからカリスマのオンちゃんに絆を見出していたということも重要な要素のような気がするが、映画の描写で果たして伝わるのだろうか。
また、グスクがヤマコを諦めたのは、原作ではヤマコがレイに無理矢理犯されたショックで引きこもりグスクを遠ざけたからなのだがここも削られて、グスクとヤマコの関係が軽く感じられた。(家に侵入したレイとヤマコの緊張感に溢れたやり取りはとてもよかったのだが)
終盤、住民たちに「戦果」を配ったのはレイの仕業なのだが、その説明は映画ではなかった気がする(私が見落としたかな? ガスマスクで推測できることではあるが)。
ウタに関するエピソードをごっそり削った煽りで、ラストのオンちゃんの遺骨に辿り着くくだりが少々不自然になってしまった(吐血はしたけど、生きてるなら念のため病院に連れて行ってほしいとつい思った)。
また、この物語においてオンちゃんの行方というのは作品に娯楽性をもたらすミステリ要素にもなり得たと思うのだが、この謎の解明に至る道筋が断片的で中途半端な印象だった。そもそも原作自体にもその傾向があったが、映画化で色々削ったことで余計にそうなった気がする。
そんなわけで、おろそかにできない題材と頭で理解してはいても、エンタメ面での引力不足、人間ドラマの掘り下げ不足を感じた。
とはいえ、この時代の沖縄にスポットライトを当てたことの意義は大きい。私自身、そういえばあまり知らないなあと思って、ついネットでググったり新書を買ったりした。
「戦後」という言葉から浮かぶ風景が本土の人間と沖縄の人々とでは全く違うということ、かの時代を生きた沖縄の人々の感情を、本作から生々しく感じた。その違いを踏まえると、現在の沖縄の抱える問題の見え方もまた変わってくるのではないだろうか。
消えぬ熱を感じさせて
どう生きるか?
戦後の沖縄、その激動の時代を生きる若者たち。
そんな理不尽な状況の中でも、義勇として突き進もうとする男。そんなリーダーの男が姿を消す。
誰もが慕った彼を探そうとする模索する中、時間だけが流れる。そうした時間により溜まる人々の心のマグマが目の前の理不尽な状況と重なり決壊する心の叫びが、その時代の中を生き抜く者たちの情熱と行動が観てるものの心に問い掛ける。
この歯痒さと虚しさが共存する中で島民たちの思いを乗せた熱を感じさせてくれた。
共感できず おもしろくない
一生懸命作ったことはわかるんだけど、感動できなくておもしろくない。
登場人物の関係性が掴みにくく、誰が兄で彼氏なのか画面上で判別できなかったり、感情のつながりが伝わってこなくて、共感できなかった。
そのためか人々が何故オンチャンに惹かれ続けるのか、行動の根拠が分からないまま、ゴージャスなシーンに無駄に予算が使われたんだなぁと思ってしまった。
扱っているテーマが良くても、エンタメとして刺さる部分がなければ説明的なだけでつまらない。これならドキュメンタリーを見た方がいい。
編集後に皆の意見を取り入れて改善するような会議ができなかったのだろうか?
爆死もやむなし
テンポが悪すぎて3時間が長く感じた。特に後半は冗長なシーンが多く、国宝とは対照的。原作は紛れもない傑作だが、変なストーリー変更ばかりでその良さを半分も活かせていない。刑事が米軍基地で大暴れしてお咎めなしとか、ハリウッドの娯楽大作なら許せるが一応戦後の沖縄を描いた社会派作品(ですよね?)としては興醒め。まあ、大友が監督となった時点でこの大失敗は約束されていたということか。
沖縄の歴史
骨太な内容で面白かった。
沖縄の歴史を忘れてはいけないと思う。
ウタが撃たれて、浜に行くと、そこにオンの遺体があるのは急展開すぎると思った。それと亡くなってから大分経つのに、あそこに置いといて残るか?
この作品に限らないが、芸能人の歯が白すぎるのが気になる。歯を汚しているシーンもあるが、そうしてない時の落差がすごい。
エンドロールの始まりで、監督の名前がドーンと出たのは、少し冷めた。
今日が最終日だった
やっぱり見た方がいいと思い見に行きました
沖縄言葉対応字幕付きだったので何言ってるのかちゃんとわかった。
コザの襲撃事件すごかった
声を挙げないと何も動かない
声を挙げてもどうにもならない
と沖縄の戦後の苦しみを感じる事が出来た
3時間弱あったが緩む事なく最後まで見れた
今こんな時だからこそ見れて良かったなと
戦争は反対
最終日に見にいけてよかった
沖縄の近代リアル映画
映画レビューの賛否両論が目立つ様になってから観ました。結論から言うと沖縄の人じゃないと方言だったり、当時の心境など分からないので批判的なレビューも出てくるよな〜とも思いました。
私には凄く良かった、感動した映画でした、191分があっという間にでした、原作通りの熱量をよくあれだけの時間に入れ込んだな〜との印象を受けました。役者の演技も素晴らしかったです!最後がハッピーエンドでなかったのも現在の沖縄に通じる深い表現ですね。ただ原作を考えるとドラマの方が尺的な問題も解決できもっと良かったかもしれません、それは否定しません。
批判的なレビューも多いですが、関係者の皆様その様なもんは気にしないで下さい。この映画を理解するには近代沖縄の知識が必要不可欠です、当事者の心境を真剣に考えたこともないのに天安門事件の映画をエンタメ的な角度のみで簡単に批判する様なもんですからね、批判ほど簡単な事は無いです。(そういう方ほどものを作った事は無いのでしょう)
とにかく凄い熱量の素晴らしい映画である事は間違いありません。
忘れ物をとりに
監督の大友さんはNHKの朝ドラ『ちゅらさん』を撮られた方らしい。『ちゅらさん』は人気になり沖縄ブームが訪れ、ビギンの曲が流行ったり、劇中のマスコット『ゴーヤマン』が売れたりした。ところが沖縄の明るく楽しい面しか描いてないのではとの批判もあり、大阪に住む沖縄出身者の人にもエイサーやら沖縄民謡に親しんでもらうのは嬉しいが戦争の事や基地の事も同時に学んでほしいと言われた。
この映画ではのっけからセンカアギャーという米軍基地に忍びこんで盗んだ物資を配ったり安くで売ったりする若者が描かれる。米軍相手にいろいろな接待をする女の人や暴行事件やら基地反対闘争やら軍用機の事故、暴動に至るまで沖縄の裏現代史がこれでもかと語られている。一面的な見方のようにも思えるがそれに類する事故、事件が起こっていることを思えば全くの作り事ではない。昨今、外国人政策をどうするべきかという議論がわき起こっているが話題になっている外国人に在日米軍は含まれないのだろう。在日米軍を前にはしゃいで見せる女性総理を沖縄の人はどう見ているのだろうか?少なくとも女性総理はこの映画を見ていないだろうし、見ていたとしたら、屈託のないはしゃぎぶりをされることはなかっただろうなと感じた。
見て楽しい映画ではないがいろいろ考えさせられる映画であり、沖縄を知るうえで見ておくべき映画だと思った。
レビューのなかで沖縄方言が分からないというのがあったが自分としては主演の妻夫木さんの方言のアクセントが変で気になりました。育ちが日本本土で最近沖縄に来て頑張って方言しゃべってますという感じがしました。
何故か感動出来なかった
東映の大作が大コケと聞いて昔、東映で仕事をした身として打ち切られる前にと見に行った。
冒頭から嘘みたいな逃亡劇を見せられ、米軍や基地、警察や諜報部門のザルの様な大甘の描かれ方を見るに付け感動どころか退屈至極、広瀬すずさんにも違和感。妻夫木さんに罪は無い。
ただ二人とも酷い目にあいながら顔がキレイ過ぎる。VXガスを盗み基地内で使用しようとしたのになんのお咎めも無く無罪放免とは。
全てが絵空事に見えた。
最後、確かにこれはコケても仕方がないなと納得した。
戦後の沖縄の痛みと誇り
傑作。これは本当に映画なのか。戦後の沖縄に没入し、心が震えた。ウチナンチュの血に今も流れる魂の記憶。妻夫木聡も瑛太も広瀬すずもみんなウチナンチュの魂を宿していた。沖縄は子宝の島。子宝島。今を生きるウチナンチュの母として我が子を守り、愛し、大切に育てていきたい。この映画がたくさんの人に届きますように。
熱量は感じて受け取りました。
昨日TOHO渋谷で鑑賞しました。
ここからネタバレします。
1年前に原作は諸事情にて流し読みラストが⁉️
でした。
確かにスクリーンから熱量はしっかりと感じて受け取りました。
テーマは沖縄県のアメリカ軍の基地問題だと思います。
それと絡まるアメリカ軍の嘉手納基地から物資を奪う沖縄の地元の組織のリーダーオンが消息たち、仲間グスク、ヤマコ、レイ達がそれぞれ追跡するストーリーです。
ラストが中々難しいかと思いました?
(*^▽^*)🤔😅🥹😃
今回はなんと言ってもラスト嘉手納基地?
でグスクとレイの迫真の演技とセリフが良かったです。👍
この映画の関係者様お疲れ様です。
ありがとございました。
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
観てると胸が締め付けられる
「武器持たなきゃだーれも話聞いてくれん!」「これが平和?平和な時なんて一秒も無かった!」など胸に刺さる台詞多数。レイの荒唐無稽な野望?の告白も、そんな未来を口にしなきゃやってらんねえよという想いの現れなのかと思うととても辛いシーン。沖縄を首都にするというのは捨て石にされた故郷への悲しみと首都にすれば捨て石にしたりしないだろという考えと解釈してこれまた辛くなった。
ただ冒頭は沖縄弁が上手く聞き取れず雰囲気で観ていた。またおんちゃんが生きているというミスリードと自分の読解力の無さ故、最後のレイをずっとおんちゃんと勘違いしながら観ていた……。
「英雄のいない時代は不幸だが、英雄を必要とする時代はもっと不幸である。」 英雄が消えた島
本レビューは原作のレビューも兼ねてますので原作のネタバレを含みます。
戦後の米軍統治下で苦しい生活を強いられていた沖縄の人々にとって米軍施設から医薬品や食料、はては学校建設に使える資材までを奪い取り人々に分け与えた義賊集団「戦果アギャー」のリーダー格オンは間違いなく人々が待ち望んだ英雄だった。
先の大戦で唯一の地上戦を経験し、県民の四人に一人が犠牲になった沖縄。沖縄県民に遺族でない者は存在しないとまで言われた。生き延びたすべての沖縄県民がその家族を失った。
そんな戦争の傷が癒えない中で米軍統治下においてもさらなる仕打ちを受け続けた沖縄の人々、そんな打ちひしがれた彼らが英雄を欲したのも致し方なかった。
オンは沖縄の人々が背負わされてきた重荷を帳消しにするほどのでっかい戦果を挙げてこそ真の英雄になれると言っていた。そんな彼が極東一の規模を誇る米軍基地を襲撃した嘉手納アギャーで行方知れずとなる。彼はそこで「予定にない戦果」を手に入れていた。彼が手にした思いがけない戦果とは。それこそ彼が言っていた「人々の重荷を帳消しにするでっかい戦果」だったのだろうか。
彼が手に入れた予定にない戦果、それは島の娘と米軍の将校クラスの人間との間に生まれた一人の赤ん坊だった。オンはこの赤ん坊の命と引き換えに密輸組織クブラのもとで強制労働を強いられる。英雄と呼ばれた男が命を賭して守り抜いた赤ん坊ウタは成長し、オンの仲間たちの前に忽然と姿を現す。
オンの仲間たち、グスクはガマでの集団自決のトラウマに苦しめられ、今もガマの亡霊の呪縛から逃れられない。それを振り払うかのように彼は走り続けた。彼の眼前には常に先に走るオンの背中があった。グスクはその背中を追い続けていた。
ヤマコは「鉄の暴風」と呼ばれた米軍の艦砲射撃の集中砲火の中で目の前で両親を失い茫然自失の状態の中、自分の手を握り締めて助けてくれたその手の感触を忘れていなかった。最後に嘉手納基地のフェンスの金網越しに握りしめた手の感触を彼女も追い続けた。
海で溺れかけた自分の命の恩人であり英雄と周りから称えられた兄の存在を追い続けた弟のレイも同じく。彼らは各々が心の中に住む英雄の姿を追い求め続けた。
しかしオンは一向に見つからない。すでにこの世にはいないのではないか、そんな諦念に包まれる中で三人は己の中に存在する英雄像を模索し始める。
ヤマコは米軍機墜落事故により目の前で自分の教え子を失ったことから本土復帰を目指してその活動に身を投じていく。
レイは刑務所の中で活動家たちに感化されて次第に過激化してゆく。かたや民主的な運動家になったヤマコ、かたやテロリストとなったレイ。二人はその手段は違えど共に真の沖縄の平和を目指した。そのはざまで揺れ動くグスク。彼もオンを探し出すためとはいえ刑事と米軍諜報部の手先という二足の草鞋を履き、オンを探しつつ米兵の犯罪捜査に明け暮れた。
そんな三人の前に現れたウタの存在。彼こそかつての英雄が命を賭して守り抜いた「戦果」だった。しかしオンが命を賭して守り抜いた基地の子は米軍基地で銃撃を受け命を落とす。基地で生まれた基地の子は基地によってその命を奪われてしまう。
かつての人々の希望を託された英雄と呼ばれた男が命を賭して守り抜いた命は無残にも奪われてしまうのだった。英雄と呼ばれた男の命がけの行動はすべて無駄だったのだろうか。
あまりにも理不尽なこの結末。それはまるで沖縄のたどってきた歴史を思わせた。幾度となく苦難を強いられては本土に訴えてきた沖縄の人々。
米軍統治下で米兵による犯罪被害を幾度となく受けて不満が爆発しコザ暴動にまで発展、本土復帰への運動も大きくなった。しかし本土に復帰しても基地負担は変わらずその後も米軍機墜落事故や米兵による犯罪被害はなくならなかった。
無残な事件が起きるたびに県民の人々は決起して声を上げてきた。しかしいくら声を上げようともその声は本土には響かない。
沖縄の思いはけしてかなえられないのだろうか、沖縄に真の平和は訪れないのだろうか。かつての英雄が命を賭して守り抜いたウタはその命を奪われた。
どんなに人々が必死になって声を上げても何も変わらないようにオンの命がけの行動もただの徒労に終わってしまったのだろうか。
しかしウタは常に三人のそばにいた。まるで三人を陰で支えるかのように。彼はオンの遺志を引き継いでいたのかもしれない。オンの代わりになって彼ら仲間を見守るようにと。
米軍機墜落事故で教師を続ける自信を亡くしたヤマコを立ち直らせたのはウタであった。言葉も話せなかった彼がヤマコの放課後の読み聞かせで話すことができるようになった。その姿を見たヤマコは再び教師としての自信を取り戻すのだった。
グスクが追う女給殺人事件の目撃者もウタであり、そのおかげでグスクは犯人にたどり着けた。レイにも何かとまとわりついたウタ。彼こそオンの代わりに三人を見守っていたのかもしれない。けしてオンが命を懸けた行為は無駄ではなかったのだろう。
人々が英雄を必要とする時代は不幸な時代である。何の不安もない平和な時代には英雄は必要ないだろう。そして人々が他者に英雄を望む社会もまた不幸である。英雄を他者に求めればそれは時として独裁を生む。誰もが時代の英雄を待ち望めばそこに独裁者が生まれる危険性が生じる。かつてのナポレオンしかり、ヒトラーしかり、そしてトランプしかりだ。
グスクたちはオンを探し求めながら、次第に自分たちの手でこの島の状況を打開しなければという考えになる。英雄を追い求めるのではなくて自分自身が英雄にならざるを得ないのだと覚悟する。そうしてヤマコは本土復帰運動に身を投じ、レイも同じくテロリストとして過激な行動に出た。
苦難の時代においては皆が英雄にならざるを得ない。英雄とは特別な存在ではなく自分たちの取り巻く環境を改善するために行動に移せる者をいうのだろう。今も沖縄の人々は声を上げ続けている。彼らは皆一人一人が英雄に違いない。
そして本土に生きる我々ももはや沖縄の犠牲のもとで暮らしていることにいい加減目を向けるべきなんだろう。
本作は原作者が相当の覚悟に臨んで執筆した沖縄の一大叙事詩であり、当時の沖縄の現状を事細かく描いていてとても読み応えのある作品だった。
そして今回の映画化だが、700ページに及ぶ長編だけに省略化は致し方ないとしても、沖縄のリアル英雄である瀬長亀次郎の登場シーンがすべてカットされたのが残念なのと、あとこれは改変というより改悪に近いのだが、グスクとアーヴィンの関係性である。原作ではアーヴィンは人格者でグスクと良好な関係を持ちながらもやはり二人の関係は利害関係の上に成り立つもので日米安保条約下での日米関係に類似している。彼らはけして利害なしの友達関係にはなれないのである。しかし映画では終盤アーヴィンがグスクから友達だとして説得されるシーンを入れている。これは現実の日米関係としても原作の意図としても受け入れられない改変ではないだろうか。このせいで作品全体が甘ったるくなった印象を否めない。原作ではアーヴィンこそウタを死なせた銃撃命令を下した人物なのだから。
あと本作は日本映画では大作の部類に入るらしいが、前半に関しては絵的にスケール感が感じられずこじんまりとした印象を受けた。後半になりコザ暴動のあたりからコザの街の全景が映し出される画角の広いカットがようやく目立つようになりスケール感が感じられて何とか盛り返した感じだった。正直前半まではこれは失敗作かなと思いながら鑑賞していた。
映画自体も三時間越えの大作だが、総じて原作の持つ熱量には及ばなかった。脚本が弱いのとやはり絵作りが弱かったのが残念。映画の賛否が分かれるのも致し方ないと感じた。
ただ映画「雪風」同様沖縄の歴史を知らない世代にはそれを知らしめたという点で意義のある作品だったと思う。
本作を鑑賞して物足りないと感じた方には原作を読まれることをお勧めしたい。役者陣に関しては原作のイメージ通りでとても良かった。
脚本の瑕疵と泣かせ下手な演出
原作未読なため、種々不可解な点がありモヤモヤしていたところ、原作から補足されているレビューを読んでいくぶん理解できた。けどそれって映画としてダメなんじゃないか。
ガスマスクが配られるくだりも、誰がなぜという疑問が回収されず放置だし、二重スパイ容疑で公安から拷問を受けたグスクがあっさり解放されたのは米軍の脅しだったのか?
最大の疑問点というか明らかに瑕疵と思われるのは、ウタが撃たれて瀕死なのに、なぜ病院に行かずあの海岸に行けたのか。ウタ以外の誰も知らない場所なのに。車内では急いで!と大騒ぎしていたのに。しかもそこで見出すのはオンの白骨化した亡骸、っていやいや。ガマの中ならまだしも、台風銀座の沖縄の海岸で無傷な全身骨格なんて。ここで全員涙に暮れるんだけど、いやいやウタをなんとかしたれよと思えて鼻白らむ。ウタはその後どうなったん?
どうもね。小学校に米軍機が墜落したシーンでヤマコが泣き叫ぶ。泣かせどころなんだが泣けない。何でかな。
沖縄の背負わされた苦難の歴史もとってつけたよう。3人の異なる生きざまも未消化で、3時間超の尺をもってしても食い足りないというのは、脚本と演出がダメなんだろう。
戦果アギヤー
戦後になっても平和を感じたことがない
インパクトもあり、ずっしりした言葉だ。
私が知らない1952~1972の沖縄を
知る事が出来た。
想像では分からない現実だったのだろう。
沈黙、国家の闇、犠牲
戦争に負けて他国に占領される
という嫌な事をストレートに描かれている。
日本の縮図。
兄を慕い想うレイ役の窪田正孝さん
の演技は狂気だが彼の気持ちや行動が
物語っている。怒り狂うはず。
何が怖いって世界でも変わらず
起きてる事。人間が一番おぞましい。
とても良いが、とてもモヤる……
あらすじが面白そうなので興味を持っていたものの、上映時間が3時間超えというのと低い評価を目にするのとで観ようか迷っていましたが、時間があったので観に行ったものです。
原作は未読です。
米軍統治下の沖縄の状況が描かれ、その理不尽さに対する怒りや悲しみの想いが強く伝わる作品でした。
俳優陣の演技も、妻夫木聡や窪田正孝の怒りを含んだやさぐれ感や、広瀬すずの怒りや悲しみを堪えている凛とした佇まいなど、素晴らしかったと思います。
墜落事件でのヤマコの慟哭や、悲しみを飲み込み強くあろうとする様子。
血まみれのレイとヤマコとの感情がぶつかり合う緊迫感あるやり取り。
暴動の混乱ぶりや、その中を行くグスク。
基地を襲撃するレイと止めようとするグスクとのやり取り。
演技の素晴らしさもあり、印象深い良い場面でした。
襲撃時のレイとグスクとのやり取りなどは、やや目頭が熱くなってしまいました。
理不尽な状況は続いている今現在に、その想いが叩きつけられているのだろうと。
……と、良いところもありましたが、モヤるところも結構ありました。
グスクの語りで状況説明がされるのは良かったですが、その心情説明はいらないだろと思う部分も。
回想シーンも、長いと感じる部分や、入れるタイミングがどうかと感じる部分もありました。
血まみれのレイがヤマコの元へ来た場面など、緊迫感が高まろうかというところで回想シーンになり一旦緊迫感がそがれてしまったような気がするので、別の構成の仕方が良かったのではと。
クライマックスも、レイとグスクとのやり取りまでは良かったのですが、急にヤマコやウタや諜報員が集結してゴタゴタしたご都合主義な展開という印象に。
諜報員とグスクにそれまでどれだけ信頼関係があったのかが分かりづらいので、トモダチという言葉だけで信頼関係があったとして見逃す流れは、うーん……と。
何より、少年ウタの扱いがモヤモヤしました。
思わせぶりな登場の仕方の割に、主要人物との交流度合いの描写があまりなく、ヤマコが気にかけているくらいしか。
襲撃の場面では、何でこの状況で父親のことを聞くのかとか、レイを身を挺して助けるとか、唐突な感じで。
もっとウタの父親に対する想いやレイとの交流の描写があれば良かったと思いますが。
最後も、撃たれたのに病院に連れて行かないのかというところがモヤモヤして、オンの回想シーンも全然入ってきませんでした。
吐血してもう助からないだろうから本人の希望を聞こう、ということだとしても、モヤモヤします。
3人がオンの死を知り衝撃を受け悲しみに暮れるのも分かりますが、その横でウタが死にそうになっているのをほったらかしているのはどうなのかと。
オンの葬式は厳かに行われたようですが、ウタは?、と。
個人的なイメージとしては、こういった社会的なテーマの話では、少年とか若者といったキャラクターはやはり次の世代、未来の象徴なので、死んでしまうのはどうなのかと。
大人が何とか守ろうとするべきだろうと。
死んでしまったとしても、それは大きな悲劇であるという認識が必要なのではと。
オンの死については重要で悲劇的な扱いで描かれましたが、ウタの死については特に描かれずオンの死にかき消されてしまったという印象です。
オンが守った命、未来を失ったというのが最も悲劇的だと思いますが、そこに触れなかったのはかなりモヤモヤしました。
あと、そこに触れなかったためか、オンの存在や予定外の戦果がマクガフィン的とも感じてしまいました。
戦後沖縄の理不尽が強く伝わるところなど、とても良かったと思います。
が、少年の扱いの雑さがとてもモヤりました。
この力作を世に送り出してくださったことに、心より感謝とエールを送りたい
9月最後の土曜日、映画『宝島』を観た。
全国で観客の入りが芳しくないことをとても残念に思い、レビューを書き残しておきたい。
この映画が私たちにもたらしたものは、ただのエンターテインメントではない。それは、戦後沖縄が抱え続けてきた「魂の傷」と「真実の重さ」を、容赦なく、そして克明に描き出した映像の力ではないだろうか。
妻とともに観に行ったが、「本当にあったことか知りたくなった」「暗くて暴力が怖い」という率直な感想は、まさに『宝島』が成功している証だと感じた。観客が、通常の映画に求める「救い」や「答え」が不在であることに戸惑い、閉塞感を覚えたという事実こそが、この作品の真髄ではないだろうか。
なぜなら、この映画は、観客が目を背けがちな、あるいは知っているつもりでいた「簡単には解決しない現実」を突きつける、セミドキュメンタリーとしての役割を十全に果たしているからだ。
終始、観客を引っ張った「おんちゃん」という存在の謎と悲劇、そして、その絶望性が「命」の象徴であるウタの消滅とともに明らかになる終幕は、安易な希望を提供することを拒否している。それは、制作陣が「ヤマトの同情だけの責任逃れ」を排し、沖縄の現実と正面から向き合った、勇気ある姿勢の表れではないかと強く感じた。
観客は、救いのない暗さにダブルパンチを食らいながらも、この映画が「正しく、偽りなく、詳しく沖縄の抱える問題を描いている良い映画」であることを認めざるを得ない。大友啓史監督が見せた、史実に忠実なドキュメンタリー性と、飽きさせない演出、そして暴力表現の必要性とコントロールの妙は、この重い題材を3時間という長尺で見事に描き切っている。
『宝島』は、現代の戦争や世界の抱える問題の焦点として、沖縄の問題を人類全体の問題として捉え直すきっかけを与えてくれたのではないだろうか。
安易な「答え」がなくても、観客の心に火を灯し、「そんなに簡単なことではないが、生き続けなければならない」という言葉とともに、「そろそろ本当に生きる時がきた」と問いかける力。
この映画は、多くの議論と葛藤を呼び起こしながら、沖縄の過去と現在を未来へ語り継ぐ、かけがえのない「宝」となっている。この力作を世に送り出してくださったことに、心より感謝とエールを送りたい。
大作なのに、、
この作品は見なくてはならない映画だと、期待していた。
3時間が長いとは感じなかった。
しかし、
自分が時代背景に詳しくないこと、沖縄訛り、回想と妄想が散りばめられ、
話の展開についていくのがやっとだった。
ストーリーを理解することに集中し、そこに生まれる感動とか、心の動きを感じるところまではいかなかった。
ウタはオンが助けた子供だったことが、特に驚くほどのこともなく、一体何だったのか?
もっと早くにヤマコやレイたちに伝える機会はあっただろうし、(ウタも父のことを知りたがっていたし)
アメリカが必死になって探していたのは、高官が子探しを命じていただけということなのか。
機密ではなく、親子愛?!
レイはあんなにも覚悟をもって、毒ガス作って嘉手納に突入したのに、仲間を捨てて、車で逃げるのか…
グスクたちに任せて、なぜ基地に戻りはしなかったのか…
そして、まだ生きているのに、病院じゃなくあの場所に行ったのか…
すべては、最後のストーリーを展開するためのご都合主義感があったのは残念。
そして、広瀬すず演じるヤマコが妻夫木聡演じるグスクをニイニイと呼ぶから、てっきり兄妹と思っていたので、後半のグスクの恋心にハテナとなったり、かと思えば別の人と結婚していたり、、
詳しく描く余力がないのであれば、
そのへん飛ばしても良かったのでは?と思った。
ただ、1人1人の役者は熱量があり、
エキストラの迫力は素晴らしかった。
オンちゃんをみんなが慕う意味は永山瑛太から滲み出ている感じはあったし、その弟のレイの苦悩を窪田正孝が見事に演じていて助演男優賞!
複雑な沖縄の時代背景にお金をかけ、きちんと描かれていて、素晴らしい映像の大作に仕上がっていただけに、感情移入できなかったことは残念。
もう少し、誰かの人物像にフォーカスしても良かったのかも。
役者も映像も題材もいいのに、
ラストに辿り着くまでは良かったのに、
米軍基地内に主要キャスト集合して、この伏線回収に、「え?なんで?」となった。
これが隠していたこと?探し求めたもの?
原作があるから仕方ないけど、この映画、ココに辿り着く必要があったのかな??こんな結末見せるなら、通過点のひとつで良かったのに。
衝撃と感動とはならず、
「たぎれ!」と心揺さぶられ損ねた感じとなった。
こんなにも大作なのに、あっという間に上映回数が減ってしまい、ラストがラストなだけにもう一回見たいともならなかった。
本来なら、何度か見て、理解して、心が動く作品なんだろうけど…もったいない。
酷評のようですが、映像としては素晴らしく、映画館で見て損はない!!
全142件中、1~20件目を表示