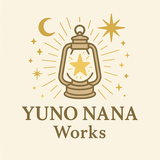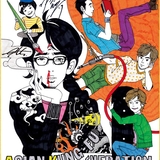宝島のレビュー・感想・評価
全625件中、1~20件目を表示
「ナンクルない」では終われない―突きつけられる沖縄の現実
映画「宝島」は、真藤順丈の小説『宝島』を原作としています。この小説は第160回直木賞を受賞しており、沖縄戦後の混沌とした時代を背景に、若者たちの成長と葛藤を描いています。
1952年、米軍統治下の沖縄。物資を奪って困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちがいました。グスク、ヤマコ、レイの幼なじみ3人は、英雄的存在のリーダー・オンと共に活動していましたが、ある夜の襲撃でオンが“予定外の戦果”を手に入れたまま消息を絶ちます。残された3人は、それぞれの道を歩みながら、オンの行方を追うことになります。
当初は沖縄本土復帰50周年の公開を目指していましたが、コロナ禍による二度の延期を経て、6年がかりでようやく完成しました。総制作費は25億円に膨れ上がったそうです。大友啓史監督ならではの映像美は見どころで、米軍統治下の沖縄の空気をリアルに感じることができます。
上映時間は191分。3時間を超えますが、不思議と冗長さはなく、むしろ物語を描き切るために必要な尺だと感じました。
今をときめく日本映画界の豪華キャストも圧巻です。窪田正孝さんの放つ狂気には目が離せません。ヒロインの広瀬すずさんは、正義感と澄んだ瞳で観客を惹き込み、息をのませます。主演の妻夫木聡さんは、クライマックスでの叫びや、緊迫感あふれるレイとのやりとりに胸を打たれます。そして永山瑛太さんの存在感も忘れてはいけません。誰もが熱演し、作品全体に重厚さを与えていました。
映画「宝島」で描かれているのは、遠い過去の話ではありません。ほんの半世紀前、この国のすぐ隣の小さな島で起きていた現実です。戦後、日本(本土)は東京オリンピック(1964年)や日本万国博覧会(1970年)など高度経済成長に沸きましたが、その陰で沖縄が辿った苦難の歴史をここまで詳しく描いた作品は、これまでになかったかもしれません。
「知らないことは罪深い」
映画を観終えたあと、そう感じる人は多いでしょう。
私もその一人です。知っているつもりで実は知らなかった大切な事実を突きつけられ、胸の奥がざわつきました。それは、語りたかったけれど語れなかった沖縄の人々の心の声を、少しだけ代弁しているように感じられます。熱く、鋭く、ときに優しく、ときに苦しく――その声は私たちの胸に突き刺さります。
そして、その苦悩は「現在」にもなお続いています。歴史の「声なき声」に耳を澄ませるよう、映画は静かに問いかけてくれます。
私たちが知る沖縄は、多くの場合「観光地としての沖縄」です。ソーキそばやゴーヤチャンプルといった食文化、年中温暖な気候、「ナンクルナイサ〜」と踊り明かす陽気な県民性。どこか気ままで陽気な人たちだと、勝手に思い込んでいました。
作中でもその陽気さは描かれています。戦禍の中でも踊りをやめない人々。独特の沖縄弁は、最初は耳に馴染みにくいですが、30分もすると自然と心地よく響きます。長尺だからこそ、この言葉のリズムや響きが当時の世界観を体現する大事な演出になっていました。
観終えて感じる県民性は、観る前より少し哀愁を帯びて映ります。
クライマックスでグスクが叫んだ言葉がすべてを物語っています。
「なんくるないで済むか!!」
「ナンクルならんぞーーー!」
怒りや葛藤を抱えながらも、それでも米国と共存し、生き抜くしかなかった当時の沖縄。そのやるせなさを、この「ナンクルナイサ(なんとかなるさ)」という言葉は含んでいるように思えました。
時は2025年、大阪万国博覧会。
日本は平和に見えますが、平和ボケしている暇はありません。米軍基地の割合は本土返還当時より増えており、日本や東南アジアの防衛のため、沖縄の米軍基地が抑止力として不可欠になっている現実からも目を背けてはいけません。沖縄だけを国際政治の犠牲者にしてはいけないと強く思います。
戦争を知らない若い世代にこそ、ぜひ観てほしい作品です。歴史を知るための重要な映画であり、未来に向けた沖縄からのメッセージでもあります。
自分の目で確かめてほしい作品
2度の延期を乗り越え、6年かけて作り上げた作品からは、何としてでもこの歴史を、メッセージを、現代の私たちに伝えたいという想いで溢れていて、何度も心が熱い想いでたぎった。
確かに3時間は長いと感じる人もいると思う。
歴史物は難しく、時代背景的にも重い内容だから腰が重い人もいると思う。
沖縄の方言がきつくてわかりづらいというレビューもわかる。
けれど、見ないで判断しないでほしい。
見て、知って、感じる想いは100人いれば100通りある。この作品は届けたい想いで溢れているから、それを自分の目と耳と心で受け取った上で判断してほしい。
私は本当に見て良かった。
同じ3時間作品の「国宝」「鬼滅」と比べたら、個人的には圧倒的に最後まで没入して見ることができた3時間11分だった。あっという間だった。
私はこれまでたくさんの戦争を題材にした作品を見てきたけれど、戦後のアメリカ統治下だった沖縄をここまで描いた作品は見たことがない。
だからこそ初めて知ることも多かった。
思えば沖縄は唯一日本で地上戦が行われ、4人に1人が亡くなるという悲劇に見舞われた土地だ。
それなのに、戦後も沖縄だけがこんなにも理不尽な悔しさに耐え続けていた。同じ日本なのに。
特に今回描かれた本土復帰前の沖縄は、ずっと怒りと悔しさとやり場のない思いで渦巻いている。
そんなぐつぐつと煮えたぎる思いが、クライマックスのコザ暴動で爆発する瞬間は圧巻だった。あのシーンは本当に自然と涙が出たし、その後の妻夫木くん演じるグスクと、窪田くん演じるレイの対話は、現代に生きる私たちへのメッセージに思えて胸に響いた。
綺麗事でもいい。私も信じたい。諦めたくない。
暴力に支配される生き物ではなく、トモダチを信じられる人間でいたいと思った。
今の私に何ができるのか。
このたぎる想いを未来に繋げていきたいと思った。
是非多くの方に映画館でこの作品のもつパワーを感じてほしい。
たぎれ、日本!!
沖縄の”感情”に触れる機会をもたらす人間ドラマの力作
戦後沖縄をこれほど一連の感情として見つめた経験はかつてなかった。その意味でこの物語は我々に191分の爆発的な感情体験をもたらしてくれる。私が何より唸ったのは、妻夫木演じる役柄を主役に据えているところ。人間的なスケールで言うと英雄オンちゃんに誰も敵わない。が、本作では彼の失踪によって梯子が外され、行き先や目標をなくした妻夫木はじめ3人こそが舵を握るのだ。実際のところ、戦後沖縄の右も左も分からない状況で悩み、生き抜き、世の中の底力となり得たのは彼らのような人たちだったのかも。傷だらけで葛藤しながらも希望だけは失わない。そんな彼らは、オン以上に共感すべき等身大の「思いをつなぐ」人たちだ。ハードボイルド的なディテクティヴストーリーの体を取りつつ、過去から未来へと貫く躍動と祈りすら感じさせる本作。実際の歴史写真に彩られたエンドクレジットに至るまで、歴史のダイナミズムと次世代への想いが詰まった力作だ。
堂々たる大作
堂々たる大作だった。コザ暴動に至るまでの、沖縄県民たちの怒りのフッテージが高まる必然性が克明に描かれていた。アメリカにも日本の本土にも苦しめられてきた沖縄の歴史、その中で翻弄された人々の生き様が色濃く刻印された作品だった。こういう骨太の社会をえぐるエンターテインメント作品が日本で出てきたことは素晴らしいことだと思う。
本土復帰前の沖縄を再現するためには、25億円かけるのは必然だっただろう。ここが安っぽかったり嘘くさかったりすると、本気度も伝わらないし、沖縄の人々の怒りも薄まってしまっただろうなと思う。
役者陣も本当にいい仕事をしたと思う。沖縄出身の俳優をもっと主要キャストに入れることはできなかったかとか、色々と思うところはあるのだけど、妻夫木聡をはじめ、出演した役者はみないい表情をしていた。特に個人的には窪田正孝の「野良犬」感がすごく良かった。危険な匂いをプンプンさせているんだけど、放ってはおけない感じ。
広瀬すずは、『遠い山なみの光』と本作で子どもを守れなかった小学生の教師の役を演じている。奇妙な接点を持った2作が9月に相次いで公開されているので、合わせて見るといいかも。
沖縄の、日本の未来のために観られるべき超重要作
長く待ち望んでいた、日本現代史における大事件を題材とする社会派の劇映画がようやく登場した。同ジャンルの製作は韓国がここ10年ほど活発で、本邦で公開されるたび「日本はずいぶん遅れをとってしまった」と嘆いていたが、この「宝島」が流れを変えてくれたらと願う。
第二次世界大戦で連合国側に敗戦した日本は1952年発効のサンフランシスコ平和条約で主権を取り戻すも、沖縄県だけは米国の統治下に置かれた。米軍基地から市街に繰り出す米兵らによる若い女性への殺人や暴行などが頻発し、軍用機が墜落事故を起こして大勢が犠牲になるなど理不尽な出来事から県民らの不満が爆発して、1970年のコザ暴動が起きた――という大まかな流れを知ってはいた。それでも、真藤順丈の直木賞受賞作を大友啓史監督が映画化した「宝島」を観ながら、自分が知ったつもりになっていたのはごくうわべだけで、沖縄であの時代を生きた人々の苦しみ、悲しみ、怒りといった感情の部分にまでは思いが至っていなかったことを痛感していた。
ストーリーは「戦果アギヤー」と呼ばれた若者たちを中心に進む。ある夜の襲撃でリーダー格のオン(永山瑛太)が失踪し、時を経てグスク(妻夫木聡)は刑事に、ヤマコ(広瀬すず)は教師に、レイ(窪田正孝)はヤクザになる。オンの不在を内に抱えつつ、60年代の沖縄の現実を生きる3人。だが、度重なる米兵らの犯罪行為に住民たちの怒りがついに爆発し、1970年12月20日未明に米兵と軍属車両を襲撃する暴動が起きる。
観客も主要登場人物らに没入し、占領下の沖縄での出来事を追体験することになる。それによって、うわべの知識にとどまっていた沖縄の人々について、より自分に近づけて感じることができる。個人の自由について、国が独立することについて、より深く考えるきっかけを得られる。「宝島」にみなぎる演者と作り手の熱量が観る者にも伝わるからこそ、それが可能になる。
レビューの冒頭で現代史をベースにした社会派劇映画のジャンルで日本は韓国に遅れていると書いたが、この手の邦画がまったく作られなかったわけではもちろんない。ただ、国家権力、政治家、官僚や大企業などに関わる事件や不祥事を真正面から取り上げ、批判すべきことはしっかり批判して描く作品は、邦画界では避けられがちだ。これは単に作り手側だけの問題ではなく、観客側にもこのタイプの作品を積極的に求めないというマイナス要因があるように思う。一方の韓国では、こうしたジャンルの映画が観客に支持され大ヒットし、それが次の製作を後押しする好循環が続いているようだ。
現代史の不都合な真実、暗い部分に光を当て、きちんと向き合うことは、明日を、未来をより良く変えることにつながる。優れた劇映画にはそれを促す力があると信じるし、「宝島」に続く力作が今後増えることを切に願う。
スタッフと役者の本気度を買う。
観た時から随分時間がたってしまった。
いまではもうすっかり上映館数が少なくなってしまった。
もっと盛り上げてあげたかった。
感想をうまく言語化できない気がして投稿が遅れてしまった。
以下は観た直後に書いたものに少し手を入れたもの。温めただけで大した変化はないが。
公開前より、業界につながりを持つ知人から「前評判がすこぶる良い」と聞き、満を持して鑑賞した。
私は沖縄びいきであり、その歴史についても関心がある。また、役者も良い意味でなじみがあり好きな人が多いので、
そういう意味では概ね想定通りの内容であり、想定通りの出来だった。
まず、全体として「沖縄の歴史」を描くことへの覚悟が感じられた。
できるだけ安っぽい演出を回避しようという意識も感じられた。
セットから音楽、隅々まで意気込みを感じられる作りだった。
役者も人ひとりが真摯に演じているのがわかった。
特筆したいのは以下3名。
妻夫木聡:さすが座長。安定感の上に熱のある目で感情移入させられる。
最近は安定しすぎて「こなし」そうになってしまわないかも危惧するのだが、
この映画に限らず、彼は決して「手を抜く」ことをしていないのがわかる。
もはや「泣き芸」ともいえる「泣き」の演技も健在だ。「感情が“漏れ”出る」のを表現するのがうまい。
広瀬すず:私はなんやかんやいって彼女に圧倒的ヒロイン性を感じるし、もはや本人もそこに覚悟を決めているようにすら感じる。
特にシリアスな演技はうまいと思うし、彼女の放つ生命エネルギーのようなものを感じつい魅せられてしまう。美人すぎるがゆえに演技力が過小評価されているように思っている。今回は同時期に同じく戦争をテーマとして「遠い山なみの光」にも出ているのでぜひそちらとの見比べをしたい。
永山瑛太:彼の演技力は言わずもがななのだが、今まで手一番彼を「かっこいい!」と思った。
なんだあのビジュは。ファッションもよいし長髪も普段は好きではないのだが今回は似合いすぎるほどであった。
あれじゃカリスマにもなるわ。背も高いし。
確かな制作陣と役者によって作られた本作は劇場で見るに大いに値する。
くしくも題名に「宝」がつくこともあり、大ヒットの「国宝」と公開前から比べられてしまっている当作品。
制作費・キャスティング等から「超大作」とういうふれこみなのに…という記事が多いようだが。
しかし、そもそも描きたいものが全く異なるため作品として比べるのは違うと感じる。
公開後の監督のせいでケチがついてしまったのが本当にもったいない。
ぜひ多くの人に見てもらいたい映画である。
なお、おなじコザ騒動を描いた作品で秀逸なものがある。
演劇だが「hana -1970、コザが燃えた日-」である。
これはアプローチは全く異なれど、沖縄の怒りが底のほうからじっくりと伝わってくる秀作である。
特に当時無名(っていうか今はどうしている??)で初舞台という上原千果さんが素晴らしかった。
演出が「舞台ならでは」のものがあるため、そのままの感動を得るのは難しいかもしれないが、
興味のある人は何らかの方法で見てもらえたらと思う。
最後に一つだけ、難点をいえば、
ラスト「ウタ」が「オン」の元へ行くシーン、あれはちょっと狙いすぎではあった。
そこまでにいたる事情も爪の甘さも感じた。そこだけファンタジーであった。原作がどうかはわからないが。
「戦争」に興味をもってもらうための、エンターテイメント性を持たせるためとはいえ、
そこももうちょっと頑張ってほしかった。
究極の空回り
沖縄に対する熱量だけはギリギリ伝わった。と言うより本作の制作意図や多くの思いを無駄にしてはいけない、とこちらが全力で歩み寄った気がする。3時間の長丁場もあるが、見終わった後は何とも言えない失望感で嫌な疲れ方だった。
なぜこんなにも空回ったのか。
結局のところ何を一番伝えたかったのかさっぱり分からない。ストーリーも話としては分かるが、さんざん風呂敷を広げておきながら全てがとっ散らかって全く回収できていないとしか思えなかった。登場した誰にも感情移入できず「なんでこうなるの?」ばかりだったが、それでも最後にきっと回収するのだろうと思っていたら、ちょっと理解しがたい着地。これならいっその事シンプルなドキュメンタリーで見せてくれた方が100倍マシだったというのが本音だ。
そして最も重要な場面であろう「コザ暴動」の迫力の無さ。暴動に発展するまでの点と点が線に繋がっていく描写が絶望的なほど雑で、「群衆の怒り」が全然伝わらず映画のクライマックスとしてまるで成立していないように感じた。暴動と言えば、かつて観たキャスリン・ビグロー監督の「デトロイト」という作品を思い出す。ここではデトロイト暴動が描かれており、黒人と警察の小競り合いから火種が徐々に広がっていき、やがて激しい対立に発展していくまでの様子を凄まじい緊張感と共に見せてくれる。あまりの迫力に言葉を失うほどで、ビグロー監督の手腕が冴えに冴えている。それと比べるのも何だが、「宝島」のコザ暴動の描写は何もかもチグハグで、申し訳ないが正直「見るに堪えない」ものだった。
沖縄の重い歴史の大切さを痛感するし、作品自体は熱を帯びている。役者もみな素晴らしい。なのに全体を通して観るとびっくりするほど響かない。一体どういう事なんだ!あんなに楽しみにしてたのに。期待値が高かったのも良くなかったかも知れないが、基本的に脚本や演出にかなり問題があったように個人的には思ってしまう。
期待からの落差があまりに大きすぎて、このままだと今年一番ガッカリした作品になりそうだ。
上映時間長かったが、それでも観てよかった。
熱量にやられて、初めてレビューを書きたくなった
原作既読。最初は★3.5ぐらいかなと思った。
主人公3人の演技はいい、3時間でも飽きない、暴動シーンは圧巻、でも…なんで役者が沖縄の人じゃないの?…方言分かりにくくない?…叫びすぎでは?…時間軸混乱してない?…結末これどうなの?…などと考えた。
でも、しばらくして気づいた。どうやら私はこの映画を素直に受け止められないみたい。
我慢して、我慢して、爆発!みたいなエネルギーがこの映画には溢れている。そして、その怒りや憤りの一部はヤマトゥに向けられている。それを正面から受け止めるのはシンドイから、ヒネた態度で流してしまっていた気がするのだ。
この映画が沖縄で人気なのは納得がいく。ウチナンチュはこの映画のもたらす高揚とカタルシスを、少なくともヤマトンチュよりは素直に味わえただろう。
でも、ヤマトンチュの端くれの私にはそうはいかなかった。映画のコピーは「たぎれ!」だったけど、むしろたぎられる側。おかげで熱量にやられて、ずっとモヤモヤ。そして見てから2週間以上たってから、ここに会員登録して、駄文を書き込んでいる。
そうさせるほどの余韻をもたらしたという意味で、この映画の力は強い。名作だ。
再上映
10月上旬で近くの映画館の上映終了し、近くで上映待ってた所、シネマロサでの上映。
上映期間はできる限り観たいと思います。以前は沖縄言葉の字幕ありませんでしたが今回観劇しまた新しい気持ちで観劇しました。
観るか観ないかは自由ですが、沖縄の人達の気持ちを理解し、基地の問題は、沖縄だけの問題ではなく日本の課題であり一緒に考えていかなければならないと考えさせられる映画です。
楽しいとか、映像が綺麗とかではなく、同じ日本でこれだけつらく大変な時期を乗り越えてきた沖縄の現実を知るのに良い映画だと思います。大きなスクリーンで観たほうが迫力があって最高です。また何度か観に行きます。
沖縄の人こそ観て欲しい『宝島 HEROE'S ISLAND』☆“沖縄ことば対応字幕付き上映”◎良かった
全編に沖縄の息づかい・エネルギーを感じる素晴らしい映画です。大友監督率いる制作陣と、最高の演技で魅せてくれた妻夫木さんはじめキャストの皆さんには、ありがとうと言いたいです。
戦後から復帰前までの米軍統治下にあった沖縄。アメリカーに理不尽な仕打ちを受けながらも、基地経済に頼らなければ生きていけないという現実…。そこで繰り広げられる若者の群像劇に惹き込まれ、濃厚な映画体験でした。(原作未読です)
ストーリーの主軸となるコザの英雄オンちゃんのオチが弱いとのコメントが散見されるのは何故だろう?オンちゃんのように迷わず利他的に行動出来る人が今居たらSNSで賞賛されるだろうが、なぜこの物語の中ではモノ足りないと言われるのかとても不思議。伏線は最初から随所に散りばめられているので、何度か観て楽しむのも良しです。最初観た時はラストの伏線回収に舌を巻きました。
5回観ましたがその都度発見があります。俳優の皆さんが役を生きていて感情移入から泣いてしまう時もあります。エキストラの皆さんの表情など観るのも楽しいです。セットや小道具も凝っています。珊瑚の島・沖縄の海を真上から走るように映す冒頭から嘉手納アギヤーのアクションシーンを経て、小舟がたたずむ凪の海にタイトルが浮かび上がってくるのとか最高じゃないですか。動と静、沖縄の海をよく捉えています。
本土の方が沖縄に想いを馳せとても熱意のこもった映画を、それも商業ベースに乗せなければならないメジャー枠で6年掛けて完成し悲願の全国公開に至ったのに、沖縄県民が観ないでどうする?
『宝島』は「興行収入見込めそうだし、その企画やってみようか」と軽々しく手を出せる原作で無いのは私でもわかる。そこに制作陣が果敢に挑んだのは何故か?本土の人間として沖縄を捨て石にした事への贖罪の気持ちからかもしれない。または世界で戦争がリアルタイムで起きている事への警笛かもしれない…それなら全国、いや全世界の人が観るべき映画だと思う。
「戦争で悲惨な目に合うのは、負けた国の女と子供だ。最前線で戦う俺たちじゃないんだ。だから絶対に勝たなければいけないんだ」
これは映画『木の上の軍隊』での山下少尉の言葉で、とても重くて悲しいセリフですが本作を観て思い出しました。
「宝島」は沖縄では公開時こそ大入りでしたが、今は空席も多いし上映回数も減ってきています。まだ観ていない県民は必ず映画館で観て欲しい。特に沖縄市民はあの圧巻のコザ暴動のシーンを見なければいけない、そして考えなければいけないと思う。コザ暴動は中の町バス停附近からゴヤ十字路、第二ゲート、現在の中央パークアベニュー、そしてコザ十字路にまで及んだのです。
日常的に見慣れた場所で1970年に自然発生的に起きたコザ暴動を、壮大に、生々しく映像化し、エンタメとして見事に昇華してくれました。自分自身もあのさなかに居合わせたような気になって、スクリーンで何度でも見たくなります。
方言(ウチナーグチ)は本島内でも市町村によって全く雰囲気が変わります。コザが舞台の本作では、ちゃんとコザの人の話し方・イントネーションに寄せていて、妻夫木さんは立派なコザのにぃにぃです!チバナ役の瀧内公美さんの間の取り方とか抑揚の付け方がその辺にいるオバサンそのものでびっくりしました。あと、語尾の「〜やさ」は実際に使います。
【沖縄ことば対応字幕付き上映】も最近始まったようなので、言葉をしっかり聞き取りたいという方はそちらも合わせてご覧下さい。私もまた観に行きます。
※追記※沖縄ことば対応字幕付き上映の感想
観てきたので書いておきます。
まず、全てのセリフに付かない、最小限の字幕が新鮮だった。それで良かったと思う。
10月にライカムで上映していた(たぶん2回だけ)“字幕付き”とは違うものだった。
今回の沖縄ことば字幕付き上映は、例えばヤッチー=兄ちゃん、たっぴらかすよー=叩くよー、というふうに置き換えられていた。
しかし前回のはヤッチー等の単語は訳さずそのままの表記で、全てのセリフに字幕が付いていたと思う。
その違いから、監督が方言(沖縄ことば)に拘って最後まで字幕を付けたくなかった気持ちがよく伝わってきた。
方言はウチナーンチュのアイデンティティだから。そのアイデンティティも奪われていたからだ。(劇中で教壇に立つヤマコの後ろ、黒板の隅にぶら下げられている方言札)
今回、ガマでグスクが頭をかかえて発狂したシーンで発見があった。集団自決のトラウマとは思っていたが、日本軍?のような声が字幕で現れ衝撃だった(怖くて書けない…いろんな意味で)。男性の声だけなので誰なのかはわからないが、私は聞き取れてなかった。※集団自決については考えるだけで具合が悪くなるが、きちんと調べ、学ばなければならない。
10月のライカムで見た字幕付きには、その声に字幕は付いていたかな?グスクのお母さんの字幕は覚えている。反対に今回の(沖縄ことば字幕付き)にはグスクのお母さんの声に字幕は無かった。
10月のライカム字幕付きの時に、持ち込みお菓子(グミかチョコ)の袋を開けて食べ始めた人がいて、カサカサ響く音が気になりその男性の字幕を見逃したかもしれない。
話がそれましたが、今回沖縄ことば字幕付き上映も観て良かったです。大友監督の並々ならぬ覚悟をさらに感じました。
最後に、映画「宝島」を観て熟考され作品を評価し、沖縄に気持ちを寄せている方が全国にも多くいらっしゃる事を映画.comのレビューで知り嬉しくなりました。ありがとうございます。
グスクが思っていたほど、あまり変わっていない
コザ暴動は、当時テレビニュースで見た記憶がありますが、まだ子どもだったので詳細はよく分からなかったですね。今回それを元にした再現を見ましたが、抑圧されていた人達が爆発する様子がよく分かりました。復帰後でも、基地は残っているし、性犯罪が起きたり、ヘリが墜落したり、戦争は起こっているし、この暴動のキッカケと変わらない状況が続いています。グスクが希望したような世界にはなっていないので、人間って進歩していませんね。
ちょっと編集方法によって、判りづらい感じになっているのが残念。何か起こったことを見せてから、「それは実は」という遡ったシーンを見せることがいくつかありましたが、あまり多用すると、見ている方は疲れてしまいますね。あともう少しストーリーを整理した方がいいと思います。
戦後の沖縄を考える上で、参考になる作品だと思います。
数多の犠牲を強いられている沖縄の現実
長尺であることが見ない理由になるなら、それはあまりにもったいない。
迫力のあるコザ騒動のシーンはもちろんだが、
あの広瀬すずが鉢巻を巻いてデモ行進し「アメリカ出て行け!」と叫ぶ。
そのシークエンスが衝撃的だ。
なぜなら、今を生きる私たちはあまりにも政治的言動に敏感で弱腰になっているから。
本土の平和のために常に犠牲を強いられてきた沖縄について少しでもその痛みを共有するということ。
本作の意義は大きい。
早々にYahoo記事などで興行を叩かれているのも、テーマが「沖縄」だからではないかと穿った見方をしてしまう。
どこからの横槍でも入っているのかと。
学校行事で映画鑑賞に行くなら「国宝」ではなく「宝島」でしょう。
配信で191分見られますか?無理でしょう。
映画館で見るしかない。
見てよかった
最後に明かされる真相以外は、見事な出来。
戦後の沖縄の現状と、そこに暮らす人々の我慢ならない怒りを伝えてくる、非常に力の入った大作。
重厚で見ごたえがある。
引き込まれるドラマで、クライマックスの暴動シーンまでが見せる。
ただそのあとの終盤で、序盤から物語全体を通してずっと引っ張り続けている謎、主人公たちの尊敬する兄貴分オン/永山瑛太が行方不明になったいきさつのすべてが、ついに明かされるクライマックス、そこが失望しかなかった。
入手しようとしていた銃器に代わる大きな戦果で、米軍がいまだに行方を追っているものとは何か?
感動する場面だとばかりに回想シーンで説明されるのだが、感動どころか驚きもなかった。
こんなことが真相だったのか?
これが知られると今でも米軍は困るのか?
拍子抜けだった。
それでも、この最後の真相以外は立派なものだったので、評価は高い。
あと、コザ派と那覇派という言葉が説明なしに出てくるが、それが住民全体を指すものなのか、ヤクザの派閥のことなのかが分からなかった。
それと、寝たきりの男がオンのことを語っているのに、ドクターストップがかかって主人公が全部を聞き終わる前に追い出されるシーンは、ご都合主義丸出しで大嫌いだ。
お話は……
第二次世界大戦の終戦直後から始まる。
県民の4人に1人が死ぬという大きすぎる被害を出した沖縄。
終戦後は駐留基地のアメリカ兵たちが特権階級扱いで、犯罪をおかして逮捕しても、МP=米軍憲兵が出てきて連れていき、無罪にされて警察はなにもできないという状況に、地元民の怒りが蓄積していく。
そんな沖縄のコザの町では、主人公の少年・妻夫木聡は、絶大な信頼を寄せる年長のオン/永山瑛太に付き従い、売りさばく物資を盗み出そうとグループで米軍基地に侵入し、発覚して大騒動の中を逃走するが、そのときからオンが行方不明になる。
時が経ち、主人公・妻夫木聡は刑事になっていたが、オンがどうなったのかがいまだに最大の関心事だった。
主人公刑事に、ひとりの米軍将校が接触してくる。
彼はオンが生きていて、何か大きな事件を計画しているのでそれを突き止めたいと言い、協力し合おうと持ち掛けてくる。
主人公刑事は、基地に侵入したあの夜、最後までオンと一緒にいた者が、病院で寝たきりになっているのを見つけ、話を聞くと、オンはあの夜の基地内で、実は銃器を手に入れようとしていて失敗したのだが、代わりに違う戦果を手に入れたと言う。
米軍は現在でもそれを探して、オンの行方を知りたがっているのだ。
それがなんなのか分からないうちに、犯罪をおかした米兵がまた無罪になったことに端を発してコザの町で騒動が起こり、米軍が鎮圧しようとしても治まらず、暴動に発展する……。
というのが主人公刑事の物語を簡単に書いたもの。
長いドラマなので、幼なじみの広瀬すずや窪田正孝らの物語には触れていない。
日本映画の底力を感じた!
今までレビューを書いたことありませんでしたが、『宝島』のことを知ってほしくて投稿しました。
とにかく大画面で見てほしい作品!!
この作品を劇場で見られて最高に良かったです。
すべての演者や作り手、作品を送り出す側が、当事者の方々に報いようと、恥じないようにと、考え抜いて全身全霊をかけて作り上げた。その誠意と熱意、映画人たちの魂に完全に心を奪われました。
当時の空気や音を感じながら物語に没入し、自分がその場に居合わせてるかのようにあらゆる感情を味わい、謎の真相にたどり着く。
そして最後の言葉で我に返り、あれはスクリーン越しに見ていた自分に投げかけられたものだと気付かされ愕然とする。
物語と現実が交差しながら、命と尊厳について必死に投げかけてる。俳優たちの魂を感じて目が離せない。こんな作品を日本でも作れるのだと衝撃です。
映画ファンとして、この国に生きる者として、この作品を世に出してくれた事に心から感謝しています。
観る前は巷の酷評を目にしてましたが、あれは劇中で表現されてるものをあえて無視して、世間の興味を削ぐためだったんじゃないかとさえ思えました。
観客動員数や興行収入を取り沙汰す記事も、不都合なものから目を背けるこの社会そのものを現してるようで空虚に感じます。
だれかに我慢させたまま蓋をし続けるような社会を、本当に私たちは子々孫々まで残すのか。戦後80年のいま、切実に私たちの心が問われていると思います。
目の前にあるのに手が届かない宝島
日本映画で久しぶりに観た社会派ドラマの大作で、3時間の上映時間もあっと言う間でした。映画は、嘉手納の米軍基地から掠奪を繰り返すグループが米軍に追われる緊迫したシーンから始まります。消息不明のリーダーの行方を追い続ける男女三人のドラマを縦軸に、52年の嘉手納基地襲撃から70年のコザ暴動までの激動する沖縄現代史を横軸にした、エンタメと社会派ドラマのバランスが見事な、実に見応えのある大作です。沖縄らしい美しい海や風景のシーンはほとんどなく、猥雑で埃っぽいギラギラした風俗街や貧しい下町や基地の鉄条網のフェンスなど殺伐とした風景ばかりです。また、沖縄の底知れぬ闇を感じさせるような夜のシーンも、マイケル・マンの『ヒート』のようで魅力的です。さらに役者の皆さんの沖縄弁の台詞回しや現地のエキストラのおかげでとてもリアルな作品世界に引き込まれます。もっと主役三人のドロっとした情念があってもいいような気がするけど、その分、積もりに積もった民衆の怒りが、クライマックスのコザ暴動で大爆発するカタルシスは最高です。役者では、妻夫木聡が大熱演で、優しくももの悲しい沖縄弁の台詞回しが最高です。広瀬すずは、『遠い山なみの光』に続いて見事な作品選びで、これだけ違う役柄を演じ切っているのに感心します。窪田正孝は、立ち姿からしてギラついた感じがよかったです。
感謝しかないです。
沖縄出身者です。宝島観ました。
中々触れられていなかった戦後アメリカ統治下だった沖縄の史実を映画化して頂き感謝でしかないです。監督や役者の熱意に本当に感動しました!
小学生のとき、今から40数年前にもなりますが、ゴヤのセンター通りは復帰前の名残りが今より残っていて、土曜日の夜に車で家族で通ると、米兵相手に飲み屋で働く女性たちが街を出歩くたくさんのアメリカ人の客引きをしていました。酒に酔って大声を出す軍人は怖かった記憶があります。米軍が犯罪を犯しても日米地位協定により、日本の法律で裁くのが難しいという沖縄の現状を当時父から聞いて、小学生ながらショックを受けました。戦後は日本全国が大変な状況はあったと思います。しかしながらアメリカ統治下に置かれてしまった沖縄の状況やウチナーンチュの声は一体、本土に届いているのだろうか?切ない気持ちにさせられる事がありました。この映画を通して、全国の人の沖縄を理解してくれているレビューを見て、こんな時代がきてくれたことに感謝とグスクのセリフ「10年後、20年後はもっと良くなっているはずやさ」が心に刺さります。ウチナーンチュ含め日本人が改めて平和を願う気もちにさせられる映画だと思います。
全625件中、1~20件目を表示