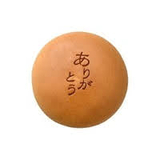宝島のレビュー・感想・評価
全766件中、421~440件目を表示
いまだからこそ観るべき映画
エンタメというより史実として観たので身震いするシーンが幾つもあった。
戦争に負け、焼け野原となった沖縄には、当時の写真やフイルムが米軍が撮ったものしか残っていないと言う。
なので、この映画が持つ意味、力は凄く強いと感じた。
やまこが先頭に立ち進む戦争反対のデモ行進。
そしてコザ暴動。
火の手が放たれる中をかちゃーしを踊る女。我慢も限界にきた群衆の中から聞こえ漏れるたっくるせーの声。
本当にこんな風だったんだなと胸が熱くなった。
後半に差しかかると原作とは違う内容に進んでいくこと気が付いた。
映画を観た後、この映画の為に新たに作られたこの部分が見る人によって感じ方が随分異なって、口コミにも書かれているのだと感じた。
オンとレイはやまこが同じにおいがすると言った表裏一体の兄弟。
レイは基地の中にVXガスを抱えて突入する。
沖縄を日本の首都にしろ。
やまこを総理大臣にしろと大きな戦果をまくし立てる。
一方、オンは女の叫ぶ声を聞き駆けつけると、身籠った女が赤子を産み息絶える。
そこは恐らく御嶽だと思われる場所。
嘉手納はセーダカ(霊力)が強いからね、何があっても不思議ではないよ。とどこかのシーンでオバァが呟いていた。
オンは赤子が泣かないと臍の尾を歯で噛み切り助ける。
この子こそが劇中何度も登場する謎の花売りの混血児ウタで、後半のカギとなって行く。
沖縄だった土地はアメリカに摂取され基地となり、沖縄でもアメリカでもない御嶽に産み落とされた、日本人でもアメリカ人でもない混血児ウタ。
勾玉を首から下げた英雄オンはやはり神の使いなのか。
拉致され離れ島までのシーンは相当割愛されているが、意識朦朧、この世とあの世の狭間にいる極限を感じさせる演出なのかもしれない。
映画の冒頭に戦果を上げ、村人に物資を分け与えるひーじゃー(樋水)のシーンが何回か登場する。
水を汲み、洗濯をし、皆が集まり笑い寛ぐ場面だ。
世界のあちこちで戦さがはじまり、分断が起きている。
戦果をあげろと、領土を奪え取り返せと
オンが最後に欲しがった戦果は、大きな戦果ではなく、ウタが笑って暮らせるひーじーゃでの幸福な日常なのだろう。
余韻が残る、考えさせられる映画でした。
怒りは伝わってくる
2025年劇場鑑賞257本目。
エンドロール後映像無し。
鑑賞後調べたら事件自体は結構史実通りなんですね。大きく分けて消えた英雄(米軍備蓄品泥棒)を追うサスペンスの要素と、戦後の沖縄県民の怒りについての二つを描いていました。消えたと言っても米軍基地でやらかして逃亡のシンガリを務めたら、他にも死んだ仲間がいるような状況で行方不明ってそれもう死んでんじゃね?と伊之助じゃなくても思うのですが、親友、弟、彼女がそれぞれ探しています。
後でこの一緒に親友が逃げる時に聞こえたものが伏線になっていたのはやられたと思いました。
上映時間に対して長いなとは頭は思わなかったのですが、膀胱はそうもいかず、1時間くらい経過でこりゃ最後までもたないな、と一番なんとかなりそうな場面で1回行きましたがそれでもエンドロールだいぶ手前で尿意の限界が来てエンドロール突入した瞬間トイレに行き、エンドロール終了には間に合ったという感じです。
今、来週の沈黙の艦隊の続編に備えてAmazonプライムのドラマを全話観たばかりなのですが、つくづくアメリカは傲慢だなぁと痛感しました。
全体的に面白くはあったのですが、突き抜ける部分となるとどこだろ、という感じでちょっと点は辛くなってしまいました。
広瀬すずよし
テーマは素晴らしいと思いますが……
アメリカ占領期の沖縄を民衆側から描いた作品であることは素晴らしいと思い、高い評価をつけたいところですが……
正直なところ、あまり響かなかった作品です。登場人物が多く、それぞれのエピソードを無理矢理詰め込んだ結果、内容が散らかって薄くなってしまったと感じます。
ラストの展開も、うーん……そう終わらせるのか……という感じ。
3時間超の長尺映画でありながら、民衆の怒りが、沖縄の怒りが、残念ながら薄っぺらく感じてしまいました。
窪田正孝さんの演技は『国宝』の横浜流星さんと並ぶのでは、というくらい素晴らしいと思いました。
前半、暴力場面だけが目立つ。後半になってやっと、、、
見応えありました。
誰か教えて下さい。
沖縄の苦悩がうまく描写された映画だった。
それだけでも見る価値はある。
ただ…ラストの謎解きが私には理解できず、モヤモヤが残ってしまったので、どなたか解説して下さい。
①オンちゃんが赤ん坊を抱き上げた後に、オンちゃんを取り囲んだ武装した日本人は何者?
②悪石島?の海岸でオンちゃん達は爆撃を受けるが、戦後なのに何故爆撃?
③結局、オンちゃんが米軍基地から持ち出した秘密って、米軍人が孕ませた赤ん坊のこと?そんなことで諜報部員が動いたり箝口令が敷かれたりしてたの?
よろしくお願いします。
誠実に作りたいという気持ちは伝わりました
巨匠大友啓史によるお金をかけた壮大な自己満映画
おんちゃんが沖縄の希望の象徴ならば物語の冒頭におんちゃんが何をやろうとして何が出来なかったのかを具体的に見せるべきだった。
コソ泥の様を描いてこれからは島の英雄になるって宣言しただけでは何がしたかったのか分からない。
だから主要キャスト3人がなぜおんちゃんにこだわって探し続けるのか、観客に全く伝わらない。
グスクの視点に立ってみると、刑事になったのはおんちゃんを探すため。ではなぜおんちゃんを探したいのか、根源的な動機が見えない。
例えばグスクは山子が好きだけど、山子はおんちゃんと付き合ってる。
そのおんちゃんが行方不明になって落ち込む山子。そんな山子を励ますためにグスクは必死でおんちゃんを探し続ける。
これならキャラクターの感情動作として分かりやすい。
でもこの映画ではそういう描き方をしていない。だからグスクの心理が分かりにくい。グスクだけでなく山子もレイも20年に渡っておんちゃんにこだわり続ける理由がよく分からない。
山子は3人の中で唯一おんちゃんと付き合ってたという強い動機付けを持ってるが、割とサクサク自分の人生を切り開いて行ってるのでおんちゃんがいなくても別に困らない。さっさと新しい出会い見つければいいのにぐらい思ってしまう。
主要キャスト3人の間に、戦後長い間踏みにじられてきた沖縄の人権を取り戻したいという強い気持ちがあるのは理解できる。
でもその事とおんちゃんを探す事とは直接関わりが無い。だからこの物語の主軸がどこにあるのか、一体何を描きたかったのか、3時間を通して何を伝えようとしていたのか、結局最後まではっきりしなかった。
リアリティ
「るろうに剣心」シリーズの大友啓史監督ということで、エンタメ系を想像していましたが、ちょっと違った作品でした。終戦後も米軍統治が続いた沖縄を舞台に、島民の苦悩や若者たちの葛藤がドラマチックに描かれているのですが、登場人物らの心模様やお互いの絆の演出が個人的にはわかりにくい印象でした(汗;)。大友氏がNHK時代に演出を手がけた大河ドラマ「龍馬伝」に少し重なりました。例えば、レイ(窪田正孝)の人物描写で、口元をナイフで裂くシーンやヤマコ(広瀬すず)に迫るシーンなど、徹底的にリアリティを追求した激しい描写でありながら、登場人物らに感情移入して強いカタルシスを感じるというより、目を背けたくなるような感覚でした。とても評判のよい大作ですが、個人的な好みとは合いませんでした(残念!)。
カタカナの「オキナワ」をもっと知ってほしい
クライマックスは、1970年に実際に起きたコザ暴動。
そこに至る沖縄の悲しい歴史を下地に、フィクションを絡めて熱く盛り上がるストーリー。
主役三人の演技の素晴らしさも相まって、何度も嗚咽をこらえて胸がつまった。
復帰前の沖縄住民には、憲法による人権の保障がなかった。このことが、米軍や米兵の横暴が野放しにされた遠因であるかも知れないと思う。
しかし、フィクションパートの組み立てはあまりうまくなかった。米軍が追っていた「秘密」の重要性について、観客は理解しにくかったのではないだろうか。また、レイがヤマ子の元を訪ねたとき、首飾りを受け取ったヤマ子はなぜすぐにレイの後を追わなかったのか。登場人物の行動に、ちょっと不可解な点が残る。
3時間に迫る長い映画だが、クライマックスまではそんなに長さを感じなかった。が、その後がものすごく説明的でいささか退屈だった。もう少しうまく整理することはできなかったのだろうか。観客がすべて理解するより、“察する”程度でもよかったような気がする。
でもまあこれで却って原作を読む楽しみが増えた。上述した点が原作ではどう表現されていたのかを知りたいと思ったのである。それに、脳内で登場人物を妻夫木聡や広瀬すずで想像しながら、感動的な台詞を追体験したい。
ふと、アメリカとウクライナを思い出しました。
戦後沖縄の歴史で知らなかった事も多く、もっと学びなおしたいと感じました。「予想外の◯◯」にドキドキしつつ、かつての沖縄の繁華街の雰囲気や暴動など丁寧さと臨場感に魅了されました。主人公の刑事が語った「アメリカのお陰で豊かになった、平和になったから、感謝しろ!?(怒 正確なセリフでないです)」を観たときは、米国とウクライナ会談での副大統領の迷言(?)を想起してしまいました。そして暴動で自動車がひっくり返るシーンでは、映画「ジョーカー」を思い出した次第です。これはもう、アメリカ自体について勉強したくなりました。3時間ですが飽きることのない知的興奮をありがとうございます。原作もぜひ味わいたいです。
暴力が
自分の祖父母、父母が育って来た時代のことだと思う。歴史的なエピソードは聞いたことはある。この映画は暴力と大きい音ばっかで苦しかった。怖いよ。
僕の祖父母はこんな怒ったり暴力ばっかの話はしなかった。小学校の先生でお花たくさん植えて、市場で買い物して重いもの沢山運んで子育てして、真面目に働いて子ども三人内地の大学へ行かせた。そして僕らが今いる。それこそ生き抜いたんだと思う。僕のばあちゃんは感情に流されずにしっかり真面目に生き抜いた。
この映画は大事な歴史的一面を切り取ったものだとは思うけど、ちょっと何に主軸を置きたかったのかストーリーの展開がわかりにくかった
追記 これを書いたら鑑賞者が減るのかなと思って書かなかったんだけど、誰かがはっきり書いてたので追記すると、僕も自己満足で何が言いたいのか全体が見えなくなってる映画だと思った。
やるせない気持ちだけが残った。
子供時代に沖縄返還されたけど当時は正直よく分からなかったな。何故沖縄が占領されっぱなしなのか、日本なのに日本じゃなかったのか、何で返還してくれたのかなどなど。まだ歴史とか習って無かったし戦争に負けたから沖縄が取られたって位の認識。
3時間映画ですがもっと削れる所あったんじゃ?もうちょい構成を変えればコンパクトになるんじゃ?って思わせられた。
確かにセットなどにお金が掛かっており演者も良い芝居をしていたし当時の沖縄の雰囲気も良く出ていたけど、どこか冗長に感じた。
ポイントは行方不明になったオンちゃんなんだろうな。物語全体としてはオンちゃんに関するミステリー的な探偵物っぽい所もある。
オンちゃんは何を見つけてやらかしたのか?
その間に占領下の沖縄の諸問題を散りばめた感じ。
終戦から本土復帰までの沖縄の様子を少し理解する事ができたのは良かったけどやるせない気持ちだけが残った。
物語は主人公のグスク視点で話が進む。
終戦後沖縄は米国の占領下にあり日本とは別の国扱いで沖縄に行くにはパスポート(沖縄から本土に行くにも)が必要だった時代の話。
若者のリーダー格のオンちゃんは兄貴風で面倒見も良くてリーダーシップもあり若者の憧れだった。
オンちゃんは若い男衆を引き連れて米軍基地の倉庫から缶詰などの食料品や家庭薬の様な医薬品を盗んで商売したり分け与えたりしていた。
ある日の襲撃はそれなりに大規模で普段は取らない銃器など武器もかっぱらった。しかし米軍もいつまでも取られっぱなしでいるはずもなく大規模な逆撃を受けて散り散りに逃げる事に。何人か死亡、何人か逮捕、何人か逃亡となったがオンちゃん1人だけ消息不明に。
一緒に襲撃したものの離れ離れになったオンちゃんを探すために情報収集には警察が1番と刑事になった親友のグスク。襲撃時に逮捕され刑務所行きになったオンちゃんの弟レイは出所後ヤクザの下っ端チンピラに。オンちゃんの恋人ヤマコは教師になった。それぞれ行方不明になったオンちゃんを探していたが一向に消息は分からず。
米兵の犯罪や沖縄のヤクザの抗争、本土復帰デモ、本土の経済関係者など色々な問題を抱えながら地道に解決していくグスクは敏腕刑事として活躍し米軍からも一目置かれる存在に。そして色々な情報からどうやら襲撃したあの日に米軍側に何かがあったらしい事、オンちゃんは色々あって別の島にいるらしい事、オンちゃんを探しているのは他にもいる事など断片的な情報。
果たしてオンちゃんはどこにいるのか?
米軍の知られると不味い事とは?
沖縄はどうなっていくのか?(ここは映画に無いけど)
演技はともかくもうちょっと年齢が経った風貌にして欲しかったな。青年時代から20年以上経っても見た目がそんなに変わらないと言うか加齢が少ないな。
日本の映画にありがち。もっとシワを増やすとか白髪を増やすとか着ているものを工夫するとか。
窪田正孝がめっちゃいい
原作は読んでません。なんとなく予告で気になったので見てみましたが正直ストーリー自体はあまりピンとこないと言うか面白いかと聞かれたらつまらなくはないがめっちゃ面白いわけでもないといった感想です。
他の方のレビューを見た感じ、おそらく原作を読んでこその面白さがある作品のようですね。
自分としてはなんといっても窪田正孝さんの演技力が凄まじかったと思います。
昨年の「クラウド」や今年春に公開された「悪い夏」などでもいわゆるアウトロー的な怖い人を完璧に演じており、昔はそんなイメージなかったのですが最近の彼はマジで凶暴な男をやらせたらすごいなと思います!
広瀬すずも良かったですね、彼女は今年初めに公開された「ゆきてかへらぬ」でも難しい役どころをやっていて、その時の役に通じるようなシーンもありました。
窪田正孝さんとのあのシーンが自分的にはめちゃくちゃ釘付けになりましたね。それほどあのシーンでの広瀬すずは気迫がすごかったです。
しかしこの作品気になったのはなぜにおっさんの俳優の中で広瀬すずがヒロインなのか?
瑛太の恋人が広瀬すずは見た目に無理がある。
どうみても年の離れた妹にしか見えなかった。
やはりどうしても広瀬すずは童顔なので安達祐実のようにだいぶ年がいってから色気が出てくるタイプなんじゃないかと思う。
3時間の長さはそれほど気にならなかったが
結構ダレると言うか回りくどいなと思うところもあった。
サブスク等に出たら改めて見て確認したいがあまり自分的にはピンとこない作品だった。
沖縄の歴史
「熱い」「暑い」「厚い」
アメリカ統治下の沖縄で、米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える若者たち。グスク(妻夫木聡)、ヤマコ(広瀬すず)、レイ(窪田正孝)の3人。そして、リーダーとしてみんなを引っ張っていたのが、一番年上のオン(永山瑛太)。いつか「でっかい戦果」を上げることを夢見るの3人。そして、最後に明かされる戦果…。こんなに素晴らしい人間がいるのかと言うくらい。
沖縄戦は知っていても戦後の沖縄の問題に関心を持ったことはなかった。その意味でも「熱い」「厚い」「暑い」作品だった。
戦後アメリカ統治の沖縄、日本へ返還される沖縄、その後の基地問題と多くの課題が未だに宙に浮いたままの状態だと感じざるを得ない。
広瀬すずは若い時から中年の役まで素晴らしい。
大作と名作と作品の長さ
沖縄の歴史について戦後の様々な葛藤や苦しみを
乗り越えて今があるのはよく伝わってきました。
とても丁寧に一場面一場面作られているのも良く解りました。創り手の重厚な熱意はすごいと思うし、それには
ただただ拍手です。ですが…ですが長い、とにかく長い。
果たして鑑賞する観客達の事は考えてくれていたのか?
照明の角度や演劇舞台の様な凝った演出、正直ちょっと
一方的な感じがしてしまいました。トイレで席を立つ人も
ちらほら。大作とは創り手が胸を張って言えるけど名作は
観客に評価されてはじめて名作だよなあとかそんな事を
考えてしまいました。見応えはありましたが、間延びをどうしても感じてしまいました。自分の集中力に持続力がないのかもしれませんが。
沖縄の辛い歴史を描く
セリフから米軍だけでなくヤマト(本土)への怒りが伝わってきた。沖縄の悲しみや悔しさを表現し、沖縄では大ヒットしていると聞くが平日昼の都内シアターではあまり入ってなかった。テーマ的に避けている人も居るかもしれない。妻夫木聡や広瀬すず、窪田正孝など俳優陣の演技は素晴らしくゴザ騒動などを再現した当時の沖縄も興味深い。長さに耐えられれば映画館での鑑賞オススメします。賛否両論あるが難しいテーマでこれだけのお金かけて映画を作ろうとしたチャレンジは評価したいし沖縄の辛い歴史が重すぎないタッチで描かれてる映画は貴重と思う。
原作は未読だが、なぜ皆がそこまでオンチャンに拘るのか前半で上手く表現できたら良かったと思う。そこが落ちてないために話にのめり込めず残念。いちおうミステリーですよね?
全766件中、421~440件目を表示