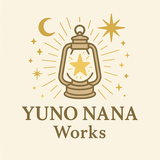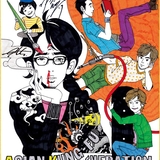宝島のレビュー・感想・評価
全771件中、1~20件目を表示
『国宝』と『宝島』の深層構造 カタルシスと反カタルシス(『宝島』バージョン)
李相日監督『国宝』は、ヤクザの子・喜久雄と、歌舞伎役者の子・俊介のふたりで演じる「二人藤娘」「二人道成寺」が目を引くが、なにゆえ二人演目なのか。
物語中、喜久雄と俊介が歌舞伎舞台から上方を見て、「あそこから何やらずっと見てるな」と頷き合うシーンがある。
文化人類学者の山口昌男は、渡辺保『女形の運命』を参照し、こう書いている。
「歌舞伎の舞台においては、二人の役者が舞台のほぼ中央の一点との関係において作る三角形があり、この三角形の頂点は、舞台の空間あるいは観客の視線の力学上の中心点である。そしてこの『中心』には深層に通じる意味が匿されている。この『中心』の意味は、歌舞伎の最も『神話的な部分である』『三番叟』を見るとよくわかる。『三番叟』で翁になった一座の統率者(座頭)は、この『中心』である舞台正面へ来て平伏する。この礼は、観客は自分達に向けられたものであると誤解するが、実は、観客席の屋根の上にある櫓に対して行われたものである。櫓はいうまでもなく神降臨の場であり、この礼はいわば降臨する神への礼である」(「天皇制の象徴的空間」、『天皇制の文化人類学』所収)。
ふたりを見守っていたのは「神的な何か」であろうが、「天皇制の象徴的宇宙を形成するモデルは演劇の構造の中に再現される」(同書)。とすると、それは天皇制の中心にいる「天皇」にほかならない。
こう言ってよければ、喜久雄はヤクザ=周縁の出身だ。「賤(しず)の者」である。高貴な出身の者が、何らかの事情で身をやつして漂流し、しかし本来の身分が知れて復辟する「貴種流離譚」という物語類型があるが、喜久雄の場合、この逆である。だが、天皇制は、対立する極性を包括する構造を持っている。賤の者を貴い者へと転生させる。
喜久雄は、ある景色をずっと探していた。「鷺娘」の終幕で、光に包まれる喜久雄=花井東一郎は、「天皇」の威光の中で、その景色を見たかのようだ。だから「国宝」になれる。
日本のZ世代が、皇族を単なるタックスイーターだとしか思っていないのであれば、こうした「天皇ロマン主義」は雲散霧消し、天皇制は消滅するのかもしれない。だが、空白になった「統合の象徴」に、何がやって来るのか。
大友啓史監督『宝島』は、米軍統治下の沖縄で、米軍の物資を奪って民衆に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる者たちを描く。
宜野湾市の売春街「真栄原新町」の誕生と消滅を追ったルポルタージュ『沖縄アンダーグラウンド』で、藤井誠二は沖縄ヤクザのルーツをこう語っている。
「沖縄ヤクザのルーツの一つは、戦後の米国統治下で『戦果アギヤー』と呼ばれた、衣類や薬品などの米軍物資を基地から盗み出し、沖縄や台湾や近隣アジア一帯に売りさばいていたアウトロー集団である。『戦果アギヤー』が扱う盗品は、拳銃や火薬など戦争で使用する武器弾薬類も含まれていた。
米軍の取り締まりが厳しくなると、彼らは特飲街の米兵相手のバーからみかじめ料を取ったり、酒場を経営したりしてシノギを得るようになる。彼らは不良米兵対策の用心棒としても重宝されていた。(中略)一九六〇年代に入ると県内各地でアウトローたちが新たに頭角をあらわすようになり、それがグループ化して愚連隊になっていく。那覇市を拠点とした『那覇派』と、コザ市(現沖縄市)を拠点とした『コザ派』が生まれ、縄張りなどをめぐって血みどろの抗争を繰り返すようになった。
コザ派は主に戦果アギヤーをルーツとし、那覇派は空手道場の使い手たちが用心棒稼業をはじめたことが母体となっている」。
戦果アギヤーのカリスマ的リーダー、オンの弟・レイは地元のヤクザになり、行方不明になったオンの情報を収集している。親友のグスクも警官になり、オンの行方を追う。オンの恋人・ヤマコも、彼を思い続けている。だが、オンは失踪後、亡くなっていた。沖縄の女性が米兵との間に身籠った子どもを養育していた時に、だ。その「アメラジアン」の子・ウタも死亡する。
『ウンタマギルー』で知られる高嶺剛監督の『パラダイスビュー』で、沖縄語(ウチナーグチ)の「ヌチ(命)」と「マブイ(魂)」について話すシーンがあるのだが、ヌチは動詞的に使用されることがあり、その意味は「殺す」であるという。してみると、「命どぅ宝(命こそ宝)」は、別の意味を帯びてくる。
『国宝』には、天皇ロマン主義的カタルシスがある。マージナル(周縁的)な存在が、「歌舞伎さえ上手うなれば、あとは何にもいりません」と悪魔と契約し、どん底から這い上がって芸道のてっぺんに上りつめる。そこに天皇制の機能を感じとることができる。
対して、『宝島』にカミはいない。カタルシスも生じない。重い問いを投げかけられるのみだ。前者は「ハレ」の映画、後者は「ケ」の映画。どちらも豊かな作品ではあるが、豊かさの質がちがう。
『宝島』は、沖縄の戦後史を「蹂躙の歴史」として見せる。それが現在に続く、ヤマトとオキナワ、島国の日常だ。
(参考文献)
藤井誠二『沖縄アンダーグラウンド 売春街を生きた者たち』講談社、2018年。
山口昌男『天皇制の文化人類学』岩波現代文庫、2000年。
「ナンクルない」では終われない―突きつけられる沖縄の現実
映画「宝島」は、真藤順丈の小説『宝島』を原作としています。この小説は第160回直木賞を受賞しており、沖縄戦後の混沌とした時代を背景に、若者たちの成長と葛藤を描いています。
1952年、米軍統治下の沖縄。物資を奪って困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちがいました。グスク、ヤマコ、レイの幼なじみ3人は、英雄的存在のリーダー・オンと共に活動していましたが、ある夜の襲撃でオンが“予定外の戦果”を手に入れたまま消息を絶ちます。残された3人は、それぞれの道を歩みながら、オンの行方を追うことになります。
当初は沖縄本土復帰50周年の公開を目指していましたが、コロナ禍による二度の延期を経て、6年がかりでようやく完成しました。総制作費は25億円に膨れ上がったそうです。大友啓史監督ならではの映像美は見どころで、米軍統治下の沖縄の空気をリアルに感じることができます。
上映時間は191分。3時間を超えますが、不思議と冗長さはなく、むしろ物語を描き切るために必要な尺だと感じました。
今をときめく日本映画界の豪華キャストも圧巻です。窪田正孝さんの放つ狂気には目が離せません。ヒロインの広瀬すずさんは、正義感と澄んだ瞳で観客を惹き込み、息をのませます。主演の妻夫木聡さんは、クライマックスでの叫びや、緊迫感あふれるレイとのやりとりに胸を打たれます。そして永山瑛太さんの存在感も忘れてはいけません。誰もが熱演し、作品全体に重厚さを与えていました。
映画「宝島」で描かれているのは、遠い過去の話ではありません。ほんの半世紀前、この国のすぐ隣の小さな島で起きていた現実です。戦後、日本(本土)は東京オリンピック(1964年)や日本万国博覧会(1970年)など高度経済成長に沸きましたが、その陰で沖縄が辿った苦難の歴史をここまで詳しく描いた作品は、これまでになかったかもしれません。
「知らないことは罪深い」
映画を観終えたあと、そう感じる人は多いでしょう。
私もその一人です。知っているつもりで実は知らなかった大切な事実を突きつけられ、胸の奥がざわつきました。それは、語りたかったけれど語れなかった沖縄の人々の心の声を、少しだけ代弁しているように感じられます。熱く、鋭く、ときに優しく、ときに苦しく――その声は私たちの胸に突き刺さります。
そして、その苦悩は「現在」にもなお続いています。歴史の「声なき声」に耳を澄ませるよう、映画は静かに問いかけてくれます。
私たちが知る沖縄は、多くの場合「観光地としての沖縄」です。ソーキそばやゴーヤチャンプルといった食文化、年中温暖な気候、「ナンクルナイサ〜」と踊り明かす陽気な県民性。どこか気ままで陽気な人たちだと、勝手に思い込んでいました。
作中でもその陽気さは描かれています。戦禍の中でも踊りをやめない人々。独特の沖縄弁は、最初は耳に馴染みにくいですが、30分もすると自然と心地よく響きます。長尺だからこそ、この言葉のリズムや響きが当時の世界観を体現する大事な演出になっていました。
観終えて感じる県民性は、観る前より少し哀愁を帯びて映ります。
クライマックスでグスクが叫んだ言葉がすべてを物語っています。
「なんくるないで済むか!!」
「ナンクルならんぞーーー!」
怒りや葛藤を抱えながらも、それでも米国と共存し、生き抜くしかなかった当時の沖縄。そのやるせなさを、この「ナンクルナイサ(なんとかなるさ)」という言葉は含んでいるように思えました。
時は2025年、大阪万国博覧会。
日本は平和に見えますが、平和ボケしている暇はありません。米軍基地の割合は本土返還当時より増えており、日本や東南アジアの防衛のため、沖縄の米軍基地が抑止力として不可欠になっている現実からも目を背けてはいけません。沖縄だけを国際政治の犠牲者にしてはいけないと強く思います。
戦争を知らない若い世代にこそ、ぜひ観てほしい作品です。歴史を知るための重要な映画であり、未来に向けた沖縄からのメッセージでもあります。
本土とは全く違う「戦後」の風景に脚光を当てる
沖縄の歴史を知るという視点、映画としての娯楽性という視点、個人的にはそれぞれの尺度での評価にギャップが生じた作品だった。
1972年以前の、アメリカの施政下にあった頃の沖縄の姿をここまでクローズアップした作品には多分初めて触れた。本土復帰という出来事を知識として知ってはいても、何故沖縄の人々がそれを求め、どのようにしてそこに至ったのかをここまで踏み込んで想像したことはなかったと、本作を観た後振り返って思う。
今年を戦後80年とマスコミは呼ぶが、沖縄にとっての戦後は1972年5月15日以降、しかもそれ以降もアメリカ軍は駐留したままだから手放しで喜べない戦後なのかもしれない。
本作ではいくつかの史実(厳密にはそれを元にしたエピソード)が描写される。宮森小学校米軍機墜落事故、糸満轢殺事件、毒ガス漏洩事件。沖縄の人々の怒りの発露とも言えるコザ暴動に至るまで、どんな理不尽が積み上がってきたかがよくわかる。
一方、沖縄の人々の生活の経済面は軍人軍属相手の商売に支えられており、問題の根の深さや解決の難しさを思わせる。
少し調べればそういった出来事や当時の社会構造は知識としては知ることができるが、本当に理解する必要があるのはその時そこにいた人々、直接影響を受けた人々の感情だ。物語はそこに思いを馳せる手助けをしてくれる。そういう意味で有意義な作品だと思う。
それだけに、エンターテインメント性という観点で見ると若干空回り感というか、もやっとしたものが残る感じなのが惜しかった。
要所要所ではいいと思える部分もあった。まず、主要キャストの演技は素晴らしかった。個人的には窪田正孝の危なっかしさ、奥野瑛太の振り切った今際の際、チラ見せなのに存在感あるピエール瀧が特によかった。コザ暴動の映像には迫力があった。
原作の主要キャラにまつわるエピソードや登場人物が結構削られていたが、それは原作付き映画の宿命のようなものだし、悪いことばかりだとも思わない。特に今回の原作小説は、語り部(ユンター)の口述という体裁を取っているせいかもしれないが、話が右往左往して一直線に進まないので、映画の枠に合うよう削ることで話の筋を追いやすくなった気もする。
ただ細部については、説明が足りないのではと思う場面がぽつぽつとあった。原作の情報からいくつか補足する。
グスクが洞窟(ガマ)に入った時錯乱したのは自身が集団自決の生き残りなのでそのトラウマが蘇ったからだということ、よって彼は天涯孤独であるからカリスマのオンちゃんに絆を見出していたということも重要な要素のような気がするが、映画の描写で果たして伝わるのだろうか。
また、グスクがヤマコを諦めたのは、原作ではヤマコがレイに無理矢理犯されたショックで引きこもりグスクを遠ざけたからなのだがここも削られて、グスクとヤマコの関係が軽く感じられた。(家に侵入したレイとヤマコの緊張感に溢れたやり取りはとてもよかったのだが)
終盤、住民たちに「戦果」を配ったのはレイの仕業なのだが、その説明は映画ではなかった気がする(私が見落としたかな? ガスマスクで推測できることではあるが)。
ウタに関するエピソードをごっそり削った煽りで、ラストのオンちゃんの遺骨に辿り着くくだりが少々不自然になってしまった(吐血はしたけど、生きてるなら念のため病院に連れて行ってほしいとつい思った)。
また、この物語においてオンちゃんの行方というのは作品に娯楽性をもたらすミステリ要素にもなり得たと思うのだが、この謎の解明に至る道筋が断片的で中途半端な印象だった。そもそも原作自体にもその傾向があったが、映画化で色々削ったことで余計にそうなった気がする。
そんなわけで、おろそかにできない題材と頭で理解してはいても、エンタメ面での引力不足、人間ドラマの掘り下げ不足を感じた。
とはいえ、この時代の沖縄にスポットライトを当てたことの意義は大きい。私自身、そういえばあまり知らないなあと思って、ついネットでググったり新書を買ったりした。
「戦後」という言葉から浮かぶ風景が本土の人間と沖縄の人々とでは全く違うということ、かの時代を生きた沖縄の人々の感情を、本作から生々しく感じた。その違いを踏まえると、現在の沖縄の抱える問題の見え方もまた変わってくるのではないだろうか。
自分の目で確かめてほしい作品
2度の延期を乗り越え、6年かけて作り上げた作品からは、何としてでもこの歴史を、メッセージを、現代の私たちに伝えたいという想いで溢れていて、何度も心が熱い想いでたぎった。
確かに3時間は長いと感じる人もいると思う。
歴史物は難しく、時代背景的にも重い内容だから腰が重い人もいると思う。
沖縄の方言がきつくてわかりづらいというレビューもわかる。
けれど、見ないで判断しないでほしい。
見て、知って、感じる想いは100人いれば100通りある。この作品は届けたい想いで溢れているから、それを自分の目と耳と心で受け取った上で判断してほしい。
私は本当に見て良かった。
同じ3時間作品の「国宝」「鬼滅」と比べたら、個人的には圧倒的に最後まで没入して見ることができた3時間11分だった。あっという間だった。
私はこれまでたくさんの戦争を題材にした作品を見てきたけれど、戦後のアメリカ統治下だった沖縄をここまで描いた作品は見たことがない。
だからこそ初めて知ることも多かった。
思えば沖縄は唯一日本で地上戦が行われ、4人に1人が亡くなるという悲劇に見舞われた土地だ。
それなのに、戦後も沖縄だけがこんなにも理不尽な悔しさに耐え続けていた。同じ日本なのに。
特に今回描かれた本土復帰前の沖縄は、ずっと怒りと悔しさとやり場のない思いで渦巻いている。
そんなぐつぐつと煮えたぎる思いが、クライマックスのコザ暴動で爆発する瞬間は圧巻だった。あのシーンは本当に自然と涙が出たし、その後の妻夫木くん演じるグスクと、窪田くん演じるレイの対話は、現代に生きる私たちへのメッセージに思えて胸に響いた。
綺麗事でもいい。私も信じたい。諦めたくない。
暴力に支配される生き物ではなく、トモダチを信じられる人間でいたいと思った。
今の私に何ができるのか。
このたぎる想いを未来に繋げていきたいと思った。
是非多くの方に映画館でこの作品のもつパワーを感じてほしい。
たぎれ、日本!!
沖縄の”感情”に触れる機会をもたらす人間ドラマの力作
戦後沖縄をこれほど一連の感情として見つめた経験はかつてなかった。その意味でこの物語は我々に191分の爆発的な感情体験をもたらしてくれる。私が何より唸ったのは、妻夫木演じる役柄を主役に据えているところ。人間的なスケールで言うと英雄オンちゃんに誰も敵わない。が、本作では彼の失踪によって梯子が外され、行き先や目標をなくした妻夫木はじめ3人こそが舵を握るのだ。実際のところ、戦後沖縄の右も左も分からない状況で悩み、生き抜き、世の中の底力となり得たのは彼らのような人たちだったのかも。傷だらけで葛藤しながらも希望だけは失わない。そんな彼らは、オン以上に共感すべき等身大の「思いをつなぐ」人たちだ。ハードボイルド的なディテクティヴストーリーの体を取りつつ、過去から未来へと貫く躍動と祈りすら感じさせる本作。実際の歴史写真に彩られたエンドクレジットに至るまで、歴史のダイナミズムと次世代への想いが詰まった力作だ。
堂々たる大作
堂々たる大作だった。コザ暴動に至るまでの、沖縄県民たちの怒りのフッテージが高まる必然性が克明に描かれていた。アメリカにも日本の本土にも苦しめられてきた沖縄の歴史、その中で翻弄された人々の生き様が色濃く刻印された作品だった。こういう骨太の社会をえぐるエンターテインメント作品が日本で出てきたことは素晴らしいことだと思う。
本土復帰前の沖縄を再現するためには、25億円かけるのは必然だっただろう。ここが安っぽかったり嘘くさかったりすると、本気度も伝わらないし、沖縄の人々の怒りも薄まってしまっただろうなと思う。
役者陣も本当にいい仕事をしたと思う。沖縄出身の俳優をもっと主要キャストに入れることはできなかったかとか、色々と思うところはあるのだけど、妻夫木聡をはじめ、出演した役者はみないい表情をしていた。特に個人的には窪田正孝の「野良犬」感がすごく良かった。危険な匂いをプンプンさせているんだけど、放ってはおけない感じ。
広瀬すずは、『遠い山なみの光』と本作で子どもを守れなかった小学生の教師の役を演じている。奇妙な接点を持った2作が9月に相次いで公開されているので、合わせて見るといいかも。
沖縄の、日本の未来のために観られるべき超重要作
長く待ち望んでいた、日本現代史における大事件を題材とする社会派の劇映画がようやく登場した。同ジャンルの製作は韓国がここ10年ほど活発で、本邦で公開されるたび「日本はずいぶん遅れをとってしまった」と嘆いていたが、この「宝島」が流れを変えてくれたらと願う。
第二次世界大戦で連合国側に敗戦した日本は1952年発効のサンフランシスコ平和条約で主権を取り戻すも、沖縄県だけは米国の統治下に置かれた。米軍基地から市街に繰り出す米兵らによる若い女性への殺人や暴行などが頻発し、軍用機が墜落事故を起こして大勢が犠牲になるなど理不尽な出来事から県民らの不満が爆発して、1970年のコザ暴動が起きた――という大まかな流れを知ってはいた。それでも、真藤順丈の直木賞受賞作を大友啓史監督が映画化した「宝島」を観ながら、自分が知ったつもりになっていたのはごくうわべだけで、沖縄であの時代を生きた人々の苦しみ、悲しみ、怒りといった感情の部分にまでは思いが至っていなかったことを痛感していた。
ストーリーは「戦果アギヤー」と呼ばれた若者たちを中心に進む。ある夜の襲撃でリーダー格のオン(永山瑛太)が失踪し、時を経てグスク(妻夫木聡)は刑事に、ヤマコ(広瀬すず)は教師に、レイ(窪田正孝)はヤクザになる。オンの不在を内に抱えつつ、60年代の沖縄の現実を生きる3人。だが、度重なる米兵らの犯罪行為に住民たちの怒りがついに爆発し、1970年12月20日未明に米兵と軍属車両を襲撃する暴動が起きる。
観客も主要登場人物らに没入し、占領下の沖縄での出来事を追体験することになる。それによって、うわべの知識にとどまっていた沖縄の人々について、より自分に近づけて感じることができる。個人の自由について、国が独立することについて、より深く考えるきっかけを得られる。「宝島」にみなぎる演者と作り手の熱量が観る者にも伝わるからこそ、それが可能になる。
レビューの冒頭で現代史をベースにした社会派劇映画のジャンルで日本は韓国に遅れていると書いたが、この手の邦画がまったく作られなかったわけではもちろんない。ただ、国家権力、政治家、官僚や大企業などに関わる事件や不祥事を真正面から取り上げ、批判すべきことはしっかり批判して描く作品は、邦画界では避けられがちだ。これは単に作り手側だけの問題ではなく、観客側にもこのタイプの作品を積極的に求めないというマイナス要因があるように思う。一方の韓国では、こうしたジャンルの映画が観客に支持され大ヒットし、それが次の製作を後押しする好循環が続いているようだ。
現代史の不都合な真実、暗い部分に光を当て、きちんと向き合うことは、明日を、未来をより良く変えることにつながる。優れた劇映画にはそれを促す力があると信じるし、「宝島」に続く力作が今後増えることを切に願う。
沖縄を伝えるということ
大友監督のティーチインがあるとのことで鑑賞。
興行的には大コケという話だったが、どんなものか興味はあった。ハゲタカやるろ剣、良かったしね。
結論から言うと響かなかった。
沖縄の苦闘の日々を描いているのだから、明るい話な訳がないのはまあその通りなのだが、緩急の緩が余りになさ過ぎじゃないか。ずっと重苦しい空気のままこの尺の長さで突っ走られると、ついていくのがしんどいなぁと感じた。
ティーチインの中で、画面の暗さは当時の沖縄を踏まえた意図的なものとのことだったが、それにしても暗すぎて、誰が誰だか分からない。
原作でも人間関係が複雑に絡み合っていて、把握するのに根気がいったのだが、登場人物が多く、故にそれぞれの人物のキャラ付けが薄いから、感情移入に至らず。
あとね、これもまた原作でも思ったことなんだけど、予定外の戦果ってのがやはり弱くない?
クライマックスも現実感が余りなく、うーん、という感。
それでもこの沖縄を描きたい、伝えたい、というパッションがあることだけはよく分かった。
消えぬ熱を感じさせて
どう生きるか?
戦後の沖縄、その激動の時代を生きる若者たち。
そんな理不尽な状況の中でも、義勇として突き進もうとする男。そんなリーダーの男が姿を消す。
誰もが慕った彼を探そうとする模索する中、時間だけが流れる。そうした時間により溜まる人々の心のマグマが目の前の理不尽な状況と重なり決壊する心の叫びが、その時代の中を生き抜く者たちの情熱と行動が観てるものの心に問い掛ける。
この歯痒さと虚しさが共存する中で島民たちの思いを乗せた熱を感じさせてくれた。
劇場で、たぎれ!
ただその地で生まれただけなのに
教科書には書かれていない、ただその地に生まれ生活してきたなんの落ち度も罪もない人々の葛藤と攻防が描かれており、今こそ観るべき映画だと強く思った。
余所ものにいいようにされかねない(されてきている)地域に住む自分にはとても響いた。
そして、戦争と沖縄返還が描かれるも、ストーリーはまた別のミステリーのようなベースに沿って進むため、御涙頂戴や教訓めいた重苦しさは無く、上映時間も全く長く感じないほど没入出来た。
沖縄のセンシティブな面しか見えてこない
戦後の米軍統治下の沖縄を描いた同名小説を原作とする作品。
戦後の混乱と本土復帰前の混沌とした状況を描いている。
宮森のジェット戦闘機墜落事故、コザ暴動と戦後沖縄のセンシティブな出来事を力を入れて表現している、のは良いのだけど「それだけ?」とも思ってしまう。
虐げられた沖縄は描かれているけど、それでも許容し生き抜く多くの庶民は描き切れていない気がする。
分かりやすく言うと、県外の人間が沖縄の暗部に衝撃を受けて県民や国民を煽っているようにしか見えない。
この映画を推す人の多くが煽られてるんだなぁと思ってしまう。
本土で生まれて、進学を機に沖縄に住み続けて30年以上たつが、「沖縄の伝え方」はすごく気にしてしまう。
そのほか、ストーリーの軸が複数あるので、結局作品として何を伝えたかったのか見てる側には今ひとつ伝わりにくい仕上がりになっているのも残念。
沖縄の辛い歴史
セリフから米軍だけでなくヤマト(本土)への怒りが伝わってきた。沖縄の悲しみや悔しさを表現し、沖縄では大ヒットしていると聞くが平日昼の都内シアターではあまり入ってなかった。テーマ的に避けている人も居るかもしれない。妻夫木聡や広瀬すず、窪田正孝など俳優陣の演技は素晴らしくゴザ騒動などを再現した当時の沖縄も興味深い。長さに耐えられれば映画館での鑑賞オススメします。賛否両論あるが難しいテーマでこれだけのお金かけて映画を作ろうとしたチャレンジは評価したいし沖縄の辛い歴史が重すぎないタッチで描かれてる映画は貴重と思う。
原作は未読だが、なぜ皆がそこまでオンチャンに拘るのか前半で上手く表現できたら良かったと思う。そこが落ちてないために話にのめり込めず残念。いちおうミステリーですよね
スタッフと役者の本気度を買う。
観た時から随分時間がたってしまった。
いまではもうすっかり上映館数が少なくなってしまった。
もっと盛り上げてあげたかった。
感想をうまく言語化できない気がして投稿が遅れてしまった。
以下は観た直後に書いたものに少し手を入れたもの。温めただけで大した変化はないが。
公開前より、業界につながりを持つ知人から「前評判がすこぶる良い」と聞き、満を持して鑑賞した。
私は沖縄びいきであり、その歴史についても関心がある。また、役者も良い意味でなじみがあり好きな人が多いので、
そういう意味では概ね想定通りの内容であり、想定通りの出来だった。
まず、全体として「沖縄の歴史」を描くことへの覚悟が感じられた。
できるだけ安っぽい演出を回避しようという意識も感じられた。
セットから音楽、隅々まで意気込みを感じられる作りだった。
役者も人ひとりが真摯に演じているのがわかった。
特筆したいのは以下3名。
妻夫木聡:さすが座長。安定感の上に熱のある目で感情移入させられる。
最近は安定しすぎて「こなし」そうになってしまわないかも危惧するのだが、
この映画に限らず、彼は決して「手を抜く」ことをしていないのがわかる。
もはや「泣き芸」ともいえる「泣き」の演技も健在だ。「感情が“漏れ”出る」のを表現するのがうまい。
広瀬すず:私はなんやかんやいって彼女に圧倒的ヒロイン性を感じるし、もはや本人もそこに覚悟を決めているようにすら感じる。
特にシリアスな演技はうまいと思うし、彼女の放つ生命エネルギーのようなものを感じつい魅せられてしまう。美人すぎるがゆえに演技力が過小評価されているように思っている。今回は同時期に同じく戦争をテーマとして「遠い山なみの光」にも出ているのでぜひそちらとの見比べをしたい。
永山瑛太:彼の演技力は言わずもがななのだが、今まで手一番彼を「かっこいい!」と思った。
なんだあのビジュは。ファッションもよいし長髪も普段は好きではないのだが今回は似合いすぎるほどであった。
あれじゃカリスマにもなるわ。背も高いし。
確かな制作陣と役者によって作られた本作は劇場で見るに大いに値する。
くしくも題名に「宝」がつくこともあり、大ヒットの「国宝」と公開前から比べられてしまっている当作品。
制作費・キャスティング等から「超大作」とういうふれこみなのに…という記事が多いようだが。
しかし、そもそも描きたいものが全く異なるため作品として比べるのは違うと感じる。
公開後の監督のせいでケチがついてしまったのが本当にもったいない。
ぜひ多くの人に見てもらいたい映画である。
なお、おなじコザ騒動を描いた作品で秀逸なものがある。
演劇だが「hana -1970、コザが燃えた日-」である。
これはアプローチは全く異なれど、沖縄の怒りが底のほうからじっくりと伝わってくる秀作である。
特に当時無名(っていうか今はどうしている??)で初舞台という上原千果さんが素晴らしかった。
演出が「舞台ならでは」のものがあるため、そのままの感動を得るのは難しいかもしれないが、
興味のある人は何らかの方法で見てもらえたらと思う。
最後に一つだけ、難点をいえば、
ラスト「ウタ」が「オン」の元へ行くシーン、あれはちょっと狙いすぎではあった。
そこまでにいたる事情も詰めの甘さも感じた。そこだけファンタジーであった。原作がどうかはわからないが。
「戦争」に興味をもってもらうための、エンターテイメント性を持たせるためとはいえ、
そこももうちょっと頑張ってほしかった。
共感できず おもしろくない
一生懸命作ったことはわかるんだけど、感動できなくておもしろくない。
登場人物の関係性が掴みにくく、誰が兄で彼氏なのか画面上で判別できなかったり、感情のつながりが伝わってこなくて、共感できなかった。
そのためか人々が何故オンチャンに惹かれ続けるのか、行動の根拠が分からないまま、ゴージャスなシーンに無駄に予算が使われたんだなぁと思ってしまった。
扱っているテーマが良くても、エンタメとして刺さる部分がなければ説明的なだけでつまらない。これならドキュメンタリーを見た方がいい。
編集後に皆の意見を取り入れて改善するような会議ができなかったのだろうか?
究極の空回り
沖縄に対する熱量だけはギリギリ伝わった。と言うより本作の制作意図や多くの思いを無駄にしてはいけない、とこちらが全力で歩み寄った気がする。3時間の長丁場もあるが、見終わった後は何とも言えない失望感で嫌な疲れ方だった。
なぜこんなにも空回ったのか。
結局のところ何を一番伝えたかったのかさっぱり分からない。ストーリーも話としては分かるが、さんざん風呂敷を広げておきながら全てがとっ散らかって全く回収できていないとしか思えなかった。登場した誰にも感情移入できず「なんでこうなるの?」ばかりだったが、それでも最後にきっと回収するのだろうと思っていたら、ちょっと理解しがたい着地。これならいっその事シンプルなドキュメンタリーで見せてくれた方が100倍マシだったというのが本音だ。
そして最も重要な場面であろう「コザ暴動」の迫力の無さ。暴動に発展するまでの点と点が線に繋がっていく描写が絶望的なほど雑で、「群衆の怒り」が全然伝わらず映画のクライマックスとしてまるで成立していないように感じた。暴動と言えば、かつて観たキャスリン・ビグロー監督の「デトロイト」という作品を思い出す。ここではデトロイト暴動が描かれており、黒人と警察の小競り合いから火種が徐々に広がっていき、やがて激しい対立に発展していくまでの様子を凄まじい緊張感と共に見せてくれる。あまりの迫力に言葉を失うほどで、ビグロー監督の手腕が冴えに冴えている。それと比べるのも何だが、「宝島」のコザ暴動の描写は何もかもチグハグで、申し訳ないが正直「見るに堪えない」ものだった。
沖縄の重い歴史の大切さを痛感するし、作品自体は熱を帯びている。役者もみな素晴らしい。なのに全体を通して観るとびっくりするほど響かない。一体どういう事なんだ!あんなに楽しみにしてたのに。期待値が高かったのも良くなかったかも知れないが、基本的に脚本や演出にかなり問題があったように個人的には思ってしまう。
期待からの落差があまりに大きすぎて、このままだと今年一番ガッカリした作品になりそうだ。
爆死もやむなし
テンポが悪すぎて3時間が長く感じた。特に後半は冗長なシーンが多く、国宝とは対照的。原作は紛れもない傑作だが、変なストーリー変更ばかりでその良さを半分も活かせていない。刑事が米軍基地で大暴れしてお咎めなしとか、ハリウッドの娯楽大作なら許せるが一応戦後の沖縄を描いた社会派作品(ですよね?)としては興醒め。まあ、大友が監督となった時点でこの大失敗は約束されていたということか。
沖縄の歴史
骨太な内容で面白かった。
沖縄の歴史を忘れてはいけないと思う。
ウタが撃たれて、浜に行くと、そこにオンの遺体があるのは急展開すぎると思った。それと亡くなってから大分経つのに、あそこに置いといて残るか?
この作品に限らないが、芸能人の歯が白すぎるのが気になる。歯を汚しているシーンもあるが、そうしてない時の落差がすごい。
エンドロールの始まりで、監督の名前がドーンと出たのは、少し冷めた。
全771件中、1~20件目を表示