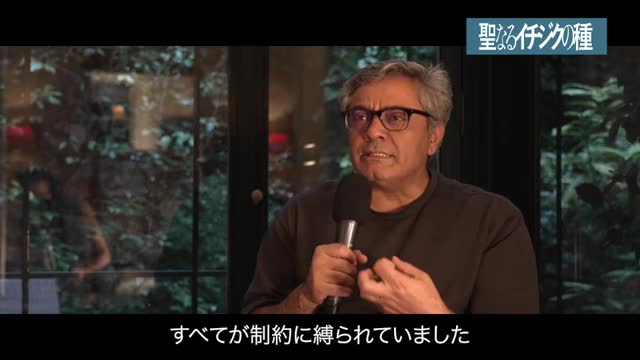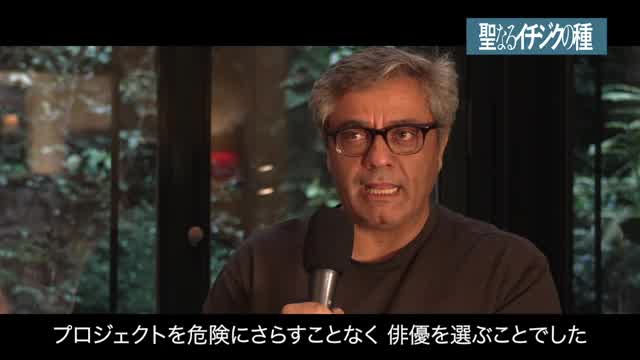聖なるイチジクの種のレビュー・感想・評価
全34件中、1~20件目を表示
男尊女卑
イラン映画を観ると毎回思うのは女性の人権の低さ。21世紀にもなりどうして女性は男性に意見すべきではないという考えが未だ根強いのか考えてしまう。
家族が一つの銃を巡ってお互い疑心暗鬼になっていくっていうのが簡単なあらすじやけど、銃が無くなるまでにも物語がある。イラン国内での暴動、親子の思想の違いによるギスギス…えらいお母さんがお父さんに気をつかうんやなと思ってたけど母の終盤の言葉に集約されている。「本性を見せたくなかった」という言葉に。イスラム教においての離婚は夫側からの申し出は比較的容易だが、妻側からは裁判所を通じてなど手続き自体がとても大変なのだという。このお母さん、内心は離婚したくてもできなかったんちゃうかなと思ってしまった。ただ、子どもの前で父を批判しないのは家庭の均衡を守る意味もあったんかなと。
ヒジャブの本来の意味って男性の視線から守るとかいう意味もあるらしいが、この国では女性が抑圧されている象徴としての意味で被っているのかなと思ってしまう。少なくとも世論は後者で認識している人が多いと思われる。ネットがある以上拡散は止められずこれは暴力ではなく正当な逮捕だと言い切るのは国際社会的にも難しいやろう。
国の問題も真正面から描きつつ、ある一家の崩壊の様子を映した本作。長い映画やけど引き込まれて長さを感じなかった。観終わった後日本で生きていることの幸福を痛感した。
監督が命を懸けたイチジクの種は聖(きよ)く育つか…?
ある出来事をきっかけに転がる負の連鎖は『別離』、歯車が狂っていく人間模様は『英雄の証明』を彷彿。サスペンスフルなヒューマンドラマ仕立てで、国の情勢も絡めて。160分超えながら、またまたイランから見応えたっぷりの衝撃作が世に問う。
でもなかなかにイラン国内の情勢は日本人には分かり難い。
本作にも大きく関与する事件をまず知っておかないといけない。
2022年、イラン国籍のクルド人女性マフサ・アミニさんが、イスラム教の女性が頭や身体を覆う布=ビジャブの着け方を理由に、イランの風紀を取り締まる道徳警察に逮捕。その直後、不審死を遂げた。
警察は急性の心臓発作などと公表したが、同じく拘束された女性によれば、警察からの暴行があったという…。
これに対し“女性・命・自由”のスローガンで、イラン各地で大規模な抗議デモに発展。
政府当局は武力でデモを弾圧…。
まるで半世紀前の韓国のような…。
ほんの3年前の事件で、世界各国にも抗議デモは拡がり、日本でもニュースで報じられたろうが、ほとんど知らない自分を恥じたい…。
国家公務員のイマンはデモ参加者に処分を下すのが仕事。
勤続20年の真面目な仕事ぶりが評価され、引っ越しも出来、年頃の娘2人にも各部屋を与えられる。そう喜びも束の間、実際の仕事の内容は不当なもので、心身共に疲れ果てていた。
妻ナジメは疲労困憊の夫を心配。娘たちにも父の負担にならぬよう、SNSなどに踊らされないよう言い付ける。
が、2人の娘レズワンとサナは、SNSを通じて今国で何が起きているのか目の当たりにする。さらには、デモに参加していた友人が怪我をし、逮捕され…。
そんな時、家の中から一丁の拳銃が消えた。それは仕事上、イマンが護身用に国から支給されたものだった…。
核開発やイスラエルとの軍事衝突で国際問題の表舞台。
その国の内部も。こんなにも厳しいのか…!
友人の怪我は痛々しい。本来なら病院に行かねばならないが、そうなるとデモに参加していた事が分かる。逮捕により人脈から父の立場も危うくなる。
一歩外に出ればすぐそこで、起きている事にショックを隠せない娘たち。それに父も、しかも体制側で関わっているという現実…。
苦しい立場と体制側の父、そんな父と真っ向から意見がぶつかる娘たち、板挟みの母。そこで消えた拳銃…。
無くした事を知られれば懲罰は勿論、信用すら失う。
当初は自分が無くしたと思うが…、次第に家族に疑惑の目を向ける…。
消えた拳銃の行方を、父・母・娘たちの視点から描く羅生門スタイルになるのかなと思いきや、まさかのキチ○イ展開に…!
イマンの疑心暗鬼は常軌を逸脱。深層心理に長ける同僚に家族を尋問させたり、家族旅行と偽って家族を砂漠の小屋に監禁し尋問。それでも口を割らない家族に遂に堪忍袋の緒が切れたイマンは、同僚から借りた拳銃を家族に向ける…。
『シャイニング』級のホラー。砂漠の迷路のような小路を追い掛け回すシーンは『シャイニング』を彷彿。
ちなみに拳銃は次女が隠し持っていた。母や自分たちに厳しい父を懲らしめたかった。
家族の為に保身を守ろうとした父の気持ちも分からんではないが、何故暴挙に至ってしまったのか…?
マフサ・アミニさんの事件を発端とした虐げられる女性、無いに等しい自由…。
男尊女卑に家父長制…。
イマンの暴挙は国家権力の具現…。
イランという国や個々を蝕む。
タイトルの由来になっている、イチジクが元木に纏わり付き、締め殺して育つ如く。
これまでの監督作でもイラン政府を批判したとして、厳しい処分を下されたモハマド・ラスロフ監督。
本作では禁固8年、鞭打ち、財産没収の実刑に…。
判決前に国外へ脱出。もう祖国へ帰れないかもしれない。
そんな覚悟で作ったであろう本作。母国を批判するだけの作品じゃない。
イランが変わる事を願ってーーー。
監督の思いと訴えに打ちひしがれる。
8分目までは秀逸
映画としての評価は、星5を付けたいけど、どうしても1つ減らしてしまう惜しい作品。前半から中盤に掛けての母と娘の気持ちの葛藤はあまりに素晴らしく、息をのんでしまう。特に娘の友達に対する母の気持ちの揺らぎは、非常に臨場感があり、イランで自分を殺して生きている女性の姿を生々しく伝えてくる。特に、娘の友達が大学の暴動に巻き込まれ、顔を負傷する場面の緊迫感は、観客の胸を締め付けてくる。
しかし、この物語の主題である「銃の喪失」の真相に迫る後半はなんだか微妙な展開に。父親も悩める存在として書き出されていた前半に対して、後半はただ理不尽な暴力を家族にふるう悪役に成り下がってしまう。なんだかんだで妻に悩みを告白し、妻もそれを受け入れるという夫婦のきずなが見られた前半とはかなり温度差が出てしまった。銃泥棒の犯人は末娘だったわけだが、その動機もいまいち共感できない。少なくとも前半では、妻が夫に理不尽に抑圧を受けていた様子は感じなかったので…。
陸の孤島のような隔絶された場所での、母娘VS父という構図は、『シャイニング』ばりのスリリングさはあり、エンタメとしてのよさは感じられたが、全体の整合性は外してしまったイメージだった。
とはいえ、日本ではほとんど見えないイランの一般家庭の息苦しさを、スリラーテイストにまとめ上げた類を見ない作品。監督も出演者も文字通り命を懸けた作品として、一見の価値あり。まさに作品完成の過程自体が、一種のスリラーなので、ぜひパンフレットを入手したり、作り手の気持ちに触れてほしい。
父の本性〜自由を抑圧するイラン国家そのものか?
衝撃作でした。
平和な国では絶対に描けない作品と表現。
監督も出演者もスタッフも命懸けの撮影だったとか。
監督は完成前に逮捕が迫り、走って国境を越えて国外脱出。
その後の撮影はズームで演出したそうです。
父親が見せる仕事での悩み・・・死刑執行に押印する苦悩・・・
そんなもの見せかけのポーズでしかなかった。
いえ、妻や娘に豊かな暮らしをさせるために、
魂を売って頑張ってきたのでしょう、20年も。
心は蝕まれています。
それにしても次女の用意周到と猫かぶりは母親譲り‼️
(いえ、イランで良い暮らしをするための女の方便や駆け引き)を
如実に表すものでした。
仮面夫婦という言葉がありますが、この家族は、
《仮面家族》だった。
スマホで世界の現実を寸時に知れるし、イラン国家の歪みも
若者は容易く知ることが出来る。
学生のデモが多発している現実。
【マフサ・アニミの死】への抗議運動に揺れる2022年を舞台にしている。
反ヒジャブ運動では大学生が500人も政府に殺されたと聞きます。
その時期を背景に、反政府運動が激化したので、父親は身を守るために
政府から護身用に拳銃を配られたのです。
エリート公務員一家が一丁の銃を巡って崩壊する様を描くサスペンス。
ヒジャブで髪を隠して大人しくしてろと言われる女たち。
抑圧されてるし、不自由だし、そんなことを守ってる社会は
馬鹿馬鹿しいし可笑しい。
ラストに使われる父親に追いかけられる母親と姉妹が逃げる回廊は
イランの遺跡なのだろうか?
とても効果的な映像を演出している。
ストシーンは、デモの様子をスマホで写して流しているが、
残された女3人の女たちのその後は?
フィクションだが、彼女たちはどうなる?
それを知りたい。
そして寄生木のイチジクが寄生して乗っ取ってしまう元の木は
はたして民主化勢力なのか?
弾圧国家なのか?
その答えは歴史が何年後かに示すのでしょうか?
イラン テヘラン 聴かせて 政治情勢
イランというのは不思議な国で、強権的な体制で国民を抑圧しているイメージが強いが、映画界に目を向けるとアッバス・キアロスタミやアスガー・ファルハディといった逸材を生んでいる。確かに彼ら以外は(本作の監督を含め)国外に流出している例も多いが。ファルハディなど必ずしも国家観に沿った作風とも言えないように思うけれど。
この映画はヒジャブ着用をめぐって拘束後死去した女性に端を発する反政府デモを背景に、ある家族にじわじわ迫りくる閉塞感を描いている。アスペクト比の異なる画面は実際の記録映像と覚しい。父親が裁判所の調査官という言わば為政者側に属しているのが、とりわけ状況を複雑にしている。八方ふさがりの家族を襲うジレンマに、見ている方もずっと胸が押しつぶされる思いだ。
ところが一転、テヘランから脱出した後はにわかにぐだぐだな展開となり、銃の顛末もあまりにも肩透かしで、廃墟の追っかけっこのくだりは取ってつけたような。これで終わられても、残された家族もただでは済まないだろうし、あとは地獄の日々が待っているだけのような気がする。
【”女性の命、人権を蔑ろにする国、男にイスラムの神の加護はない。”今作はイラン革命裁判所の審議官になった男が、護身用に渡された銃を紛失した事で窮地に立たされ、本性を現し報いを受ける寓話である。】
<Caution!内容に触れています。>
ー 今作は、2022年にイラン・テヘランでヒジャブ着用を義務付ける法律に違反したとして、警察に逮捕された女性アフサアミニさんの不審死により、テヘランで起きた”女性・命・自由”運動を背景に描かれている。
そして、今作製作により有罪を言い渡されたモハマド・ラスロフ監督はドイツに亡命したのである。
ご存じの通りイランは、映画大国であるがモハマド・ラスロフ監督やジャヒール・パナヒ監督は、反体制的な映画製作により、度々国家から厳しい処分を受けている。
だが、モハマド・ラスロフ監督は、そのような危険を承知でこの運動を弾圧する政府の役人の一家をドラマとして描いたのである。ー
■革命裁判所の審議官に20年掛けて昇進したイマン(ミシャク・ザラ)は彼を昇進させた上司から護身用の銃を渡される。
抗議デモ参加者に対する山の様な判決書に目を通すことなくサインする事を裁判官から求められる彼は日に日に疲れが溜まって行くが、銃の紛失を切っ掛けに、それまで彼を娘達レズワン、サナたちからの糾弾から彼を擁護して来た妻ナジメ(ソヘイラ・ゴレスターニ)にも当たるようになり、到頭彼女達を郊外の叔父の家に連れて行き、誰が銃を盗んだのかを尋問する愚かしい行為に走るのである。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・イマンが昇進した当初、妻ナジメはお祝いをするし、食洗器を買ってくれと頼むし、官舎に引っ越すので娘達に部屋を与えられると喜びを隠せない。
だが、夫が革命裁判所の審議官になった事で、家族には政府に対する忠誠がじわじわと求められるのである。
・レズワンの親友がデモに巻き込まれ、散弾銃を顔に受け血塗れになってイマン家に担ぎ込まれる辺りから、物語はきな臭くなる。血まみれの顔から散弾を取り出すナジメの表情と娘達の怯えた表情。
・イマンとナジメはそれでも、娘達に政府に対する忠誠を強制し、娘達は激しく反発するのである。そして、ある日イマンの銃が無くなるのである。
イマンは最初、自分のミスと思い部屋中を探し回るが、徐々に疑いはあろうことか、妻や娘に向けられて行くのである。
■今作では、スマホで撮影したと思われる実際のデモで、道路に血だらけで横たわる学生やニュースなどが映される。
正式なカメラでは当然、無理だったのであろうが、それが逆に臨場感を増している。
・イマンは上司から見つからないと懲役3年だと叱責され、代わりの銃を渡されるが、焦りを深めて行くのである。街中で隣に停まった車の若い女性が、ヒジャブを付けていない姿を見た時の彼の険しい顔。
・到頭、彼は妻と娘達を郊外の叔父の家に連れて行き、誰が銃を盗んだのかを尋問する愚かしい行為に走るのである。妻とレズワンを牢に閉じこめるが、銃を盗んでいたサナは脱出する。
サナは父に向けて且つて家族が仲が良かった頃に行ったピクニックの時の音声を流すのだが、イマンにはその想いが届かない。そして、サナは逆に父を閉じこめナジメとレズワンを開放するが父も脱出し、激しい追いかけ合いが始まり、イマンとサナは銃を向け合うのである。
そして・・。
<今作は、イラン革命裁判所の審議官になった男が、護身用に渡された銃を紛失した事で窮地に立たされ、愚かしき本性を現し報いを受ける”女性の命、人権を蔑ろにする国、男にイスラムの神の加護はない。”事を描いた恐ろしくも哀しき寓話なのである。>
<2025年4月20日 刈谷日劇にて鑑賞>
家族の関係とは何かが良く分かる映画
イランの見ごたえのある素晴らしい映画でした。国家を大事にするあまり、家族関係が壊れていく様を観ることは胸が締め付けられる思いでした。また、最後のシーンに行きつくまでに流れを変えることは出来なかったのか残念に思いました。
なお、上映終了後、次女が銃を持ち出した理由について考えていたのですが、私は妹はお父さん、そしてその後ろにいる社会体制を純粋に困らせたかったのではないかと思いました。お母さんにかばってもらい、その後、お姉さんにかばってもらったシーンで、何故、正直に「お父さん、私が持ち出した」という一言が言えなかったのか、いや言わなかったのか、不思議でした。みなさんはどう思われましたか?
庇護と支配、リスペクトと服従
イランにおける国家権力と女性との関係を、家長である父と、妻娘に投影して分かりやすく映画にした感じ。
男は、弱くて劣ったものである女性を庇護し、良い暮らしをさせるために、外部のあらゆる敵と戦う。その代償は女たちからのリスペクトと自分への服従。
その女性達が男と対等な者として自己主張し始めたら。
リスペクトと服従を拒否し始めたら。
一転して恐ろしさを見せつけて力で支配下に置こうとする
イマンの本性を知った妻と娘は抵抗し、結託して彼をあえて崩れそうな場所に誘い込んで落下させる。
「父」とともに葬られた銃は暴力の、指輪はイスラム教的家父長制の権威の、分かりやすいメタファーだろう。
かくあれかし、というラストのよう。
映画はここで終わるが、ストーリーは終わらないと思う。
強権をふるう父を葬ったは良いが、妻と娘たちはこの後どうするのだろう。
今まで当然のことと受け取っていた良い生活は、父がもたらしたものだ。
彼女たちはこの瞬間から自分で自分を守り、食わせていかなくてはならない、茨の道なき道に突入したのだ。
専業主婦と世間知らずの若い娘たちには想像もつかないような、とんでもない苦難の予感しかない。
体制の権威を葬るということは、そのおかげで受けてきた恩恵も当然に手放すことだが良いんですよね、という覚悟を女性たちに問うているようにも感じる。
イマンが良心を犠牲にしてただ家族のためにと苦悩しながら今の仕事にしがみついているのを娘たちは知らない。パパを汚いとか非道だとか罵るけれど、パパがそうやって稼いだお金で良い暮らしをして大学にも行っている自分に対しては何も思いが及ばない娘たちに違和感があったが、娘たちの世間知らず、思慮の浅さを際立たせるための演出だったのかもと思ってしまった。
ちょっとズルくないですか
前半が硬派な社会派ドラマ、後半はファミリーホラー
テンポが良いとは言えず、大分冗長な感じがしました。
見事なジャンルMix作品
予告では銃盗難に焦点が当たっていたので、ミステリー中心の作品だろうと
思っていたら、それだけじゃなくてジャンルMixのエンターテイメント作品となっていた。
約3時間が次のジャンルで約1時間ずつ。
・イランという国の窮屈な体制を描く社会派章
・銃紛失or盗難事件のミステリー章
・家族内サバイバルホラー章
イランの体制は本当に窮屈だ。
宗教が要因ではなく、権力者の宗教の解釈によるものだと思う。
国にまつわる仕事は監視されていたり(盗聴エピソード)、
女性のファッション(ヒジャブ🧕など)、体型が出ないように、髪色、ネイルなど
自由がきかなかったり、若い子はやはりスマホで世界の情報を得ていることから
もっと自由になりたいのは自明の理。そこが自由にできない窮屈さが強調されている。
銃紛失・盗難疑惑も家庭内で起きてしまうが、
それも父親の秘密主義(これは仕事上、仕方のないことだが)及び
父親の仕事へのアンチテーゼが生んだ事件だと思う。
しかし、家族を疑い尋問にかけていく流れは、やはりお国柄だと思うし、
どんどん家族が崩壊していくきっかけになっていて、誰の犯行かはわからなかった。
長女の友達が犯人かも!?とも思ったが、動機がないよなぁと思ったり。
ラスト1時間はまさかの父親による妻&娘二人の監禁、
そして妻・娘が逃亡してからのvs構図になり、サバイバルホラー化していく流れは
実にエンターテインしている。オチも読めない。
ただ、次女が銃を盗んだことがわかり、次女が巧みに父親を誘い出し、
母親・長女を救い出しつつ、みんなで逃げる&父親に追われる構図には目が離せず、
ラストのオチも予想外でめちゃめちゃ楽しめた。
あまりにも面白く、パンフレットも購入した。じっくり理解を深めていこうと思う。
完成度高い
現代社会の病理が上手く描かれている。
最初は題名が可愛いと思った。
冒頭で流れるイチジクの生態。
結局、イチジクって誰(何)なのか?
末娘って事ならかなり封建主義的な発想で父親がまさにその様な男性。
母親も母の鑑のような母性溢れる描き方をされている。
昔ながらの権威主義的な父親の方に肩入れしてしまうのは、自分の年齢のせいなのか、作品の作りなのか。
だって、隠蔽体質な権力は問題あるけど、YouTubeやSNSで発信される情報が全て真実と思い込むのも早計というか。
正しいからってそれが全て真っ直ぐ通る程世の中は簡単じゃないし。
結局、民衆は権力であれ、YouTube等の金権威主義的集団にであれ、誰かしらに搾取され続けて生きるしかないのではないかと思う次第で。
事前情報なしで観たので物語に意外性があって面白かった
2022年のイラン治安当局の役人の一家4人の生活と家族の崩壊を描く。
イランで起きた政府への抗議運動(と政府による弾圧や虐殺)を物語の背景にしており、映画では抗議運動と政府弾圧の実際の映像も織り交ぜている。
治安当局の役人の妻の視点を中心に物語は進む。
細かくは書かないが、物語の構造的には「シャイニング」のイランの政治的映画版と言ってもいいほどだと思います。
実質的な主役である妻を演じたソヘイラ・ゴレスターニがとても美しい。
事前情報なしで観たので、物語に意外性があって面白かった。
「聖なるイチジクの種」の意味は、映画の冒頭テロップから、各々が考えることだと思う。
監督のモハマド・ラスロフは、2024年に秘密裏にイランを出国している。そして、映画製作による国家安全保障に関わる罪で、欠席裁判により2024年5月に禁錮8年の実刑判決が出ているそうです。
撒いたものを刈り取る
治安維持のためにはある程度の市民の権利を制限することはやむを得ないと仕事に突き進む父親と、夫の本性を知りつつも良い暮らしと名声のためなんでも夫の側に着く母親。
そんな父を嫌いではないのだが友人の受けた不当な扱いやネット発の情報から、父のしていることや信条、父に盲従する母を受け入れられない娘たち。
思想信条や宗教は我が国とは異なっているが結構構図としては受け入れやすいものだったと思う。
では家族はどうすればよかったのかと問われると正直答えに窮する。
母に倣って父に盲従すれば裕福な暮らしを続けられたのだろうし、逆に父が信条に合わない仕事を拒めばクビになっただろうが家族の関係は改善したかもしれない。
ただどの選択肢も得るものと失うものがあるわけで難しい。
やはり父の撒いた種が実を結んだと言えるのだろう。
「関心領域」を思い出したけど…
期待し過ぎたせいか、3時間も使う必要あったかな…。実際のデモ映像は説得力ありました。けど家族に焦点を当てて宗教や政治の問題を描いたとしたら…あの次女があれ程行動する背景が描かれてなくて「あんたかい?!銃持ってんのは!」肩すかしでした。父親の仕事への葛藤や辛さは少しあったけど。母の「家族の為にも仕事が大切」的な感じが「関心領域」みたいで怖かった。宗教や政治の矛盾、女性の権利、社会は革命を起こそうとしてるけど【自分の生活は守りたい】。色んな事訴えたかったのかな、でも作品としては…何かが足りない。
現実と希望
国から有罪判決を下された監督が撮影した
ヒューマンサスペンス。
国の制度、立場、男性が優先で命より
大切なのか………。
家庭内に銃が持ち込まれて、庇護者の立場で
あるべきなのに女性達を抑圧していく。
それは家庭内だけでは無く、職場、学校、警察
あらゆる場所で。
宿主の木に枝を巻き付けて締め付ける。
そして元の木を殺してしまう。
痛烈なタイトルの影にある、絞め殺しの木。
独裁者が居続ける体制を信じ、その中で
生きてきた男性の末路。
好きな爪の色や髪も染めらない国。
混沌とした男性社会がうずめく。
聖なるイチジクの種は、どの世界でも
存在する。自由の為に。
イランの現実と希望を垣間観た。
展開の意外性に唖然、そして最後は納得。
すこぶる真面目な映画だった。
初めは、政治的意見や価値観の違いで家族が壊れていく話か、ないしはそれらを乗り越えてハッピーエンドに至るファミリードラマかと思って、それに何の疑問も持っていなかった。
マフサ・アミニさんの事件を発端に起きたイランの政情不安も、長女の親友の一件も、あくまで家族の問題や絆を描くためのバックグラウンド、エピソードとして設定されているのかと思った。
前半~中盤にかけての人物描写はしっかりしていて、特に母親の複雑な心情の見せ方にはとても好感が持てたし、しっかり感情移入できて、さあ、問題を抱えたこの家族が、どうなっていくんだろう。価値観の違いが家族を破壊するのか、それとも許しと共感の展開が待っているのか…。ドキドキ。
そんな感じで観進めていくと、起承転結の「結」に入るあたりから、なんだか予想と全く違う展開になっていく…。
アレ、アレ、何だこれ、といった混乱の中で一気にラストまで到達。
そこで初めて、「ああ、これは100%政治的メッセージが主眼の映画だったんだ。」と気が付いた(あくまで私の見方です)。
太古の昔から人間社会が本来的に抱える男性の優位性と、近代以降それを是とせずに様々な試行錯誤を繰り返して来た歴史、それでも未だ全く道半ばで、ジェンダーに関わらず自由な幸福追求が出来ているとはお世辞にも言えない現実、それらについて思考を迫り、問題解決を阻んでいるものは何かを、強く考えさせられる映画でした。
こんな声が聞こえてくるよう。
「男どもよ、胸に手を当ててよく考えてみろ。お前は大丈夫か?」
同じく年ごろの娘二人を持つ父親としては、中々身につまされた…。
タイトルなし(ネタバレ)
2022年9月以降のイラン。
巷では、道徳警察に拘束された後、不審死を遂げた22歳の女性マフサ・アミニの事実解明を巡って抗議活動が続けられていた。
彼女はヘジャブの着け方を理由に道徳警察に拘束されたのだ。
若い世代では厳格化するイスラム政治に対する不満が高まっていたのだ。
20年間の勤務態度が認められて予審判事に昇進したイマン(ミシャク・ザラ)のふたりの娘レズワン(マフサ・ロスタミ)、サナ(セターレ・マレキ)もそんな若い世代だった。
妻ナジメ(ソヘイラ・ゴレスターニ)は、ふたりの娘にいくらかの理解は示しているが、それでも厳格な夫イマンを裏切るようなことはしない。
しかしながら、予審判事に昇進したイマンの様子が次第に変わっていく。
以前は家庭的であったが、現在は道徳警察から提出される膨大な起訴状を処理するだけで疲弊し、起訴内容も吟味できないまま、道徳違反・神法に対する反逆の名目での若い者への死刑判決への押印も押さねばならない状況だからだ。
そんな中、レズワンの親友の女子大生が大学の抗議活動に巻き込まれて負傷してしまう。
親友は革新的な思想の持主なのだ。
レズワンとサナは、彼女を家に匿って手当をしたが、一段落ついたところで彼女は学生寮に戻り、その夜、道徳警察に拘束され、そのまま行方不明となってしまう・・・
といったところからはじまる映画で、このあたりまでで中盤。
ポスターなどで喧伝される「家庭内で消えた一丁の銃・・・」というサスペンス映画を期待したら、この中盤までの社会派部分がすこぶる面白い。
残り1時間ほどになって、イマンが護身用に当局から借り受けていた銃が家庭内で行方不明となってしまうわけだが、この段になってからはまるで別の映画のよう。
小規模のヒネったサスペンス映画風で、家庭内に国家の暗喩を凝縮する狙いは面白いが、いささか平凡。
というか、あまり面白くない。
というのも、あまりに性急な展開で、イマンが強権国家の代替になるあたり、うまく描かれているとは思えない。
ま、業務多忙で、国家の権力に毒されてしまったのかもしれないが。
そんなヒネった(描写的にはグダグダな)サスペンス映画から、エンディングでは再び社会派の顔をみせる。
この構成は悪くない。
タイトルの「聖なるイチジク」が暗示するところは、疑念・信念・神の念・新しい時代を願う念、といくつもに解釈可能ですね。
<以下、ネタバラシ>
おまけとして、銃紛失の顛末、実際はどうだったのか。
真相が明確に語られないので、次のとおり推理しました。
なお、妹が銃を所持していたのは映画で描かれている。
姉が銃の存在そのものを知らなかったのは、彼女のリアクションで当然という前提。
父親による尋問に対する告白、その後のリアクションから考えると
1 母親がベッドサイドの引き出しから盗んだ(告白どおり)
2 盗んだ銃は母親が冷凍庫の中に隠した(告白どおり)
3 妹が冷凍庫から偶然、発見して所持
4 母親は冷凍庫の銃が紛失していることから「運河に捨てた」と告白した
ということかしらん。
前半と後半では大差はあるが、通してみれば、評価はこのぐらいといったところでしょうか。
家庭内の緊迫感の描写が今一つに感じます
2022年9月ヒジャブを着けなかったとして若い女性が道徳警察に逮捕され死亡した事件を基にした映画です。その映像をドキュメンタリーとしてイランでの人権抑圧を描写しています。
一方、それだけでは芸術性が薄いので、革命裁判所で調査官として働く男性の家族の問題や対立とセットにして、作品化しています。
しかし、両者がうまくかみ合っているようには見えません。
取り調べを重視せず判事のさじ加減で有罪にする現状に悩みながらも、男性は生活のためと割り切って生きるようになります。
長女は友人が受けた暴力、そして警察に連行される事態に誠実に向き合います。
母親は反政府活動に関わらないように2人の娘に諭します。
そのような中、父親の護身用拳銃が家の中から消えてしまいます。残念ながらこの事件が問題の種であるにもかかわらず、唐突すぎて違和感を覚えます。
男は、自身の組織内の保身のため、家族内の犯人を捜すことに必死になります。
このあたりの描写が冗長に感じますし、男の凶暴さも不徹底で鬼気迫るというほどではありません。家父長制の強い社会では、父親の存在感や圧迫感はとても強いと思うのですが。(私の経験では)
権力機構の末端に属することの象徴としての拳銃所持と、それが失われた失態に対する怖れは理解できます。
しかし、父親の拳銃を隠し、父親を危険にさらす向こう見ずな思春期の末娘の心理が不十分に感じます。
最後に、家族に対する詰問・軟禁、そして末娘とのドタバタもなぜか緊張感がありません。
上映の約3時間が、やや間延びした印象を与えます。
イチジクの種を撒こう‼️
イチジクの種はワガママ、嘘、ジコチュー、独断、偏見といった鳥の糞に包まれて運ばれ、他の木にまとわりつくように大地に根を張る‼️判事に昇格した主人公は、報復の危険から身を守るための拳銃を支給される。ところがある日、その拳銃が消えてしまう。本人はもちろん妻、長女、次女を巻き込んでの疑惑合戦へ・・・‼️イランで行われる反政府デモを絡めて物語は進行‼️拳銃が見つからないとクビになり、懲役刑の恐れもあることから、主人公は苛立ち、ついには郷里への里帰りと見せかけ、妻、長女、次女を監禁し、自白させようとする‼️長女の友人がデモで負傷し、その友人に関わりたくない妻、友人を助けてくれない父や母に不満を募らせる長女、拳銃を探す過程で家族全員を疑わざるをえない主人公‼️中盤まではその心理戦みたいな描写が見事で、郷里での終盤では、自分たちを撮影しようとするカップルとカーチェイスしたり、キレた主人公が家族を追い回すホラー映画みたいになって、その緊迫したスリリングな演出はヒジョーに素晴らしいと思います‼️ただ、結局銃を盗んだのは次女で、主人公の家庭内における独裁者的な振る舞いに我慢できなかったみたいな動機らしいんですが、主人公の暴君ぶりを印象づける描写も無いため、イマイチしっくりこない‼️私的には家族のために一生懸命働いてる良き父親に見えたんですが‼️一日300人もの容疑者を扱い、疲労困憊となり、挙句に拳銃がなくなって失職と懲役の危機‼️誰だって気が狂いますよ‼️次女ももうチョットやり方があったはず‼️結局、ラストで父親を殺したことになってるんですから‼️私的には一人で家計を支え、家族のために身を粉にして働いてる父親を尊重すべきだと思う‼️それさえも凌駕するような父親の家族へのヒドい描写があったら話は別ですが‼️
映画で他国の内情を知る。
レバノンの実状を知る映画でした。
娘の反抗心、怖いです。
家族で裕福な良い生活を続けるか、女性の人権活動をして撃たれるか。
父親の職務を避難する方法は難しい。
全34件中、1~20件目を表示