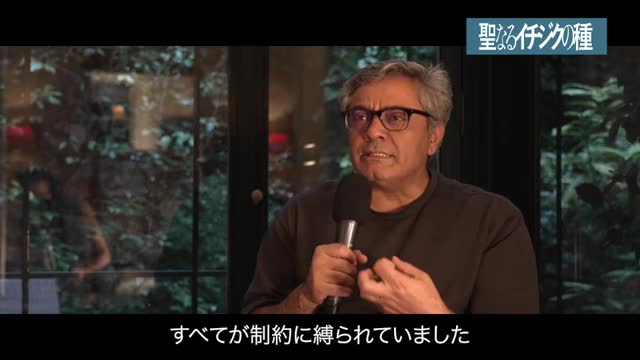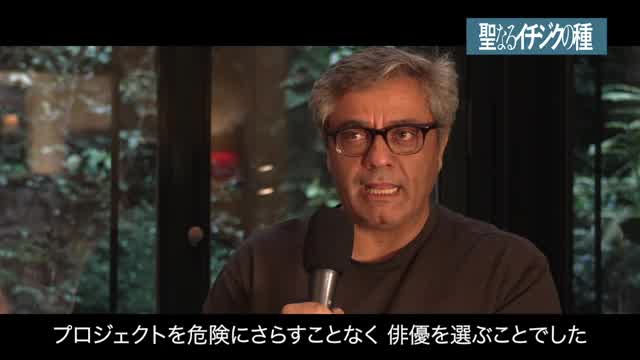「167分は長い」聖なるイチジクの種 正山小種さんの映画レビュー(感想・評価)
167分は長い
原題のdāne-ye anjīr-e ma'ābedのうち、anjīr-e ma'ābedとはインドボダイジュのことで、学名または英語ではFicus religiosaまたはsacred fig と言うそうですが、これを「印度菩提樹の種」と訳さず、あえて英単語を単語レベルで翻訳するに留めて、「聖なるイチジク」と訳したのは素晴らしいと思います。「印度菩提樹の種」というタイトルだと、どうしても仏陀が悟りを開くイメージを持ってしまい、父親が狂気をおびるようになる、この物語とは真逆のイメージを持ってしまいますから。また、anjīr-e ma'ābedを単語レベルで直訳したところで「寺院のイチジクの種」となり、あまりキャッチーではない気がします。「聖なるイチジク」とのタイトルは神秘的で実に秀逸です。
なんでもこの印度菩提樹は、他のイチジク属と同様に絞殺しの木になることがあるそうで、本物語も冒頭にその旨のメッセージが流れ、物語が始まります。あたかも鳥によって宿主の樹上に落とされた種子が発芽し、根を伸ばし、宿主の表面を覆い、宿主が枯死し、木の中心部に円筒形の空間を残すかのように、父親に支給された拳銃、あるいはその弾丸が彼あるいは彼の家庭に根を伸ばし、彼が理想としていた伝統的な家庭を失わせしめ、最後には……という物語ですが、まさに絞め殺しの木の物語だと思いました。最後にはご丁寧に穴まであきましたし。
物語に登場する人物は、中流以上の家庭に属する、裕福ではあるがごく普通の人たちばかりでした。そのような家庭の父が最後には狂気に走ることになり、ボタンを掛け違えると誰もがそのようなことになることを痛感します。日本でも、テレビのニュースで重大事件を扱った際に、「あんなことをする人には思わなかったんだけどねぇ」などと近所の人たちが話していることが思い起こされます。劇中で彼や彼の奥さんがイスラム的価値観を大切にする様子や、彼がイスラム体制側の人間として描かれていることから、だから宗教は危険なのだとのイメージを持ちがちですが、彼があのような狂気に走ったのは、上司からの無理な指示に従わされることで次第に心がすり減っていき、貸与された銃が盗まれたことから出世の道を断たれ、収監される恐れを感じたという非常に世俗的なことから狂気に走っています。まさに私たち日本人にも同じように起こりうることだと思います。
物語の冒頭で取調官(字幕では調査官となっていますが、bāzporsは検察官の指示のもとに取り調べや証拠の収集に従事し、必要であれば起訴状を書いたりする役職ですので、取調官のほうが適切な気がします。実際、終盤で彼が娘を取り調べる際にはbāzporsから派生したbāzporsīの語が使われているのですが、字幕でも「尋問」となっています。「調査」ではありません。また職場についても全てのセリフが字幕では「裁判所」となっていますが、dādgāh-e enqelābの時は革命裁判所でよいとして、dādsarāと話している時は常識的に考えて検察庁としてほしかったです)に昇進したイーマーンが、検察官が死刑の求刑を求めている案件で、ろくに記録の検討もしないまま起訴状にサインなどできないと言っていたのに、最後は娘たちに対する尋問をするのですから、その変化に恐怖を覚えます。
母親のナジュメについても自分たちの今の生活を守るために精一杯という姿が伝わってきます。夫のキャリアに傷がつきそうなときは、娘たちを叱り、たしなめる一方で、娘の友達が抗議デモに巻き込まれて顔に散弾を浴びた際には、その散弾を取り除いてやるという母性にあふれた行動にでますが、散弾を取り除いた後は、やはり今後の自分たちの暮らしを考え、娘の友達を家から追い出します。その際には散弾を受けた顔が見えないよう、顔にスカーフをかけて隠すようにしますが、それとて彼女をいたわってのことではなく、近所の人たちに見とがめられ、夫のキャリアに傷がつくのを避けるためだったりします。もっとも、自分も同様の立場に立たされた場合に、はたして人道主義的な行動に出られるかと考えると、ナジュメと同じような行動に出る恐れがあるので、彼女を責める気持ちにはなれません。
イーマーンにしろナジュメにしろ宗教的な価値観を大切にし、自分たちの生活を平穏無事に送るために努力するという、本当にごく普通の人たちで、私たちと異なる別世界の人間などではないと思います。
娘たちについても、抗議デモに好意的なごく普通の、ありふれた若い世代の人たちとして描かれています。マハサー・アミーニーさんがお亡くなりになった際にBBC等の番組を見ていた時に、若い世代の女性たちが頭からスカーフを外して町中を練り歩いたり、スカーフやホメイニーさんの写真の印刷された教科書のページを燃やしたりしている姿を目にし、若い世代の人たちはすごいなあと感じたことが思い出されます。
この世代間のギャップといったものも映画では見事に表現されていました。インターネットの発達でより簡単に外国からの情報にアクセスできるようになった世代からの「なぜイスラムでは~」という問いに、論理的な回答をできない親世代。個人的にはヘジャーブについては、守りたい人は守る、守りたくない人はなしでかまわないという制度になるのが一番だと思いますが、イラン政府にとっては難しいことなのでしょう。
全部で3時間足らずある本作の約3分の2が、物語の舞台設定説明、つまり当時のイランの雰囲気の再現に充てられています。消えた拳銃に関する物語は、実質最後の1時間ほどのみです。恐らくこれは、イラン人ではない私たち外国人が当時のイランの状況をより身近に、具体的に理解できるようにとの配慮なのでしょうが、少々冗長に感じました。もっとも、拳銃が盗まれたことをイーマーンが上司に報告した後の帰宅途中、彼の車の隣に信号で停車した車のステレオからシェルヴィーンのbarāyeが聞こえてきた時には、「あの時期流行ったよね」などとニヤリとさせられましたが。
ドキュメンタリーあるいはzan zendegī āzādī運動(字幕や新聞記事等ではzan zendegī āzādīを「女 命 自由」と訳していますが、zendegī を「命」と訳すのは何とかならないものでしょうか。zendegī というのは、これに「~する」という意味の動詞kardanをつけ加えると「生きる」や「住む」、「暮らす」という意味になる通り、「生きること」を指しているはずです。例えば、lifestyleという英単語は、lifeという単語を含んでいますが、命の形という意味ではなくて、「生き方」や「生活スタイル」という意味ですよね。できれば「女 生きる 自由」などとしてほしかったです。この運動は女が女として自由に生きることを求める運動であって、命を大切にしましょうという運動ではないはずです)に関するラスーロフ監督の政治的な声明や表明ということであれば、評価できるのですが、サスペンスの映画としては正直、少々物足りない気がします。
映画をきちんと見ていない、あるいは理解できていないだけなのかもしれませんが、下の娘が銃を盗んだ動機や方法が分からないまま映画が終わってしまいましたし、また、最後に母と娘たちがイーマーンから逃げようとする際にも車を使って逃げなかったことや、廃墟の中のおっかけっこも、少しコミカルな感じに思えたのが残念です。
最後に登場人物の名前等についてですが、引く音や小さな字を徹底的に避けようとする翻訳者の方の態度が少し気になりました。確かに字幕翻訳の世界では、使える文字数に制限があり、可能な限り引く音等を使いたくないというのもわかりますが、イーマーンをイマン、ナジュメをナジメ、ヘジャーブをヒジャブとされると、その表記が気になって物語に集中できなくなってしまいます。確かに英語至上主義の翻訳者の方からすると、たかがペルシア語風情が英語様に逆らうんじゃない、ビシビシ短くすればばいいんだという判断なのでしょうが、できればもう少し元の言語を尊重してほしいものです。また、監督の名前もラスーロフでなくラスロフと引く音を省くのは失礼極まりないことだと思います。例えば、私たちが日本人として、「タロウ」という名前を「タロ」とされると正直あまり気分の良いことではないのと同様に、ちょっとしたことですが、他の国の人たちの名前に関して、最低限の礼儀を払ってほしいものです。
とても語学に堪能でいらっしゃいますね。レビューとても参考になりました。本作は色々と暗示的に描かれたような作品だと思いました。次女が拳銃を隠す動機があえて語られないとか最後に遺跡を舞台にしたのもなにかメッセージが込められてるように思いました。遺跡を父親の死に場所にしたのはそれが古き捨て去るべきものの象徴として描いたのかなと思いました。
実際のデモの映像が挟み込まれたりとその作風から普通のサスペンス映画ではないと感じながら鑑賞してました。確かに長すぎですよね(笑)。私の同じ列の女性は遺跡の場面で席を立ってしまいました。そこまで見たんなら最後まで見たらいいのにと思いましたが。
ご丁寧にありがとうございます!私ももしかしてペルシャ語かな?と思ってましたが思慮なくすぐに行動してしまったので、YouTubeで見られるようですよ、と伝えた方にまた急ぎ伝えておきます!
すみません。
私が見たyoutubeの動画は日本語や英語の字幕のないペルシア語だけのものですので、ペルシア語が分からないと内容が理解できないと思います。
شيطان وجود نداردで検索すると出てきますが、いま確認したところ、やはり自動生成のペルシア語字幕のみでした。
舞台となっている国、映画で使われている言語へのリスペクト、私もとても大事だと思います。ペルシャ語は私にとっては未知の言語ですが、ご指摘のこと納得です。