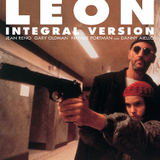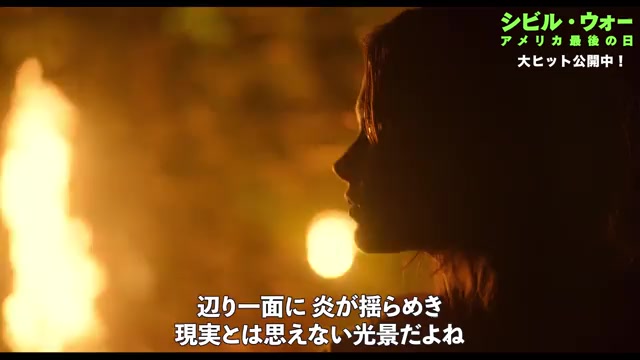シビル・ウォー アメリカ最後の日のレビュー・感想・評価
全232件中、121~140件目を表示
申し訳ないですが、自分はダメな映画でした
(完全ネタバレなので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
結論から言うと、今作は自分にはダメな映画でした。
鑑賞前はアメリカの分断社会の現実の中で、遂に内戦状態に陥り、双方の戦闘が主張と共に繰り広げられる内容を期待していましたが、ほぼ全くそういう内容ではありませんでした。
今作のストーリーは簡単に言うと、著名な女性報道カメラマンのリー・スミス(キルステン・ダンストさん)らと、彼女に憧れている女性報道カメラマンの卵であるジェシー・カレン(ケイリー・スピーニーさん)との4人が、権威主義的な大統領(ニック・オファーマンさん)にインタビューを試みる為に、内戦の中、ニューヨークからワシントンD.C.のホワイトハウスへ向かうロードムービーです。
すると、著名女性カメラマンのリー・スミスのカメラマンとしてのポリシーが映画の初めの方で伝えられます。
リー・スミスは女性カメラマンの卵のジェシー・カレンと共に、道中のガソリンスタンドの裏で武装した男に吊るされて半死になった2人に遭遇します。
しかし、リー・スミスは特に感情を動かすこともなく、武装した男を吊るされた2人の真ん中に立たせて、報道写真を撮影します。
リー・スミスは、暴行されて吊るされた2人を救うことなく、カメラマンの仕事は記録に徹することだとジェシー・カレンにその後の車中で伝え教えます。
私は(映画の1観客としても)、この報道カメラマンとしてのリー・スミスの報道ポリシーは(それがリアルだとしても)受け入れることは出来ません。
なぜなら人命を超えて報道が優先される考え方に、私は反対で同意出来かねるからです。
そんな私のような感想はさて置かれ、女性カメラマンの卵のジェシー・カレンはリー・スミスの報道ポリシーを受け入れて、例えば戦場であればジュネーブ条約違反の国際法違反である、人質を処刑する場面の報道撮影を心を動かすことなく遂行して行きます。
物語は進んで、4人の内の1人のジョエル(ワグネル・モウラさん)の報道仲間の車と遭遇し、走行している互いの車の窓を伝って移動遊びをしたりしている内に、1台だけがはぐれて、いわゆる権威主義的なアメリカを信奉しそれ以外の人間はアメリカ人とは認めず虐殺を続けている集団にジェシー・カレンらが捕らえられます。
リー・スミスやジョエル達は、捕らえられたジェシー・カレンらを助けに行くのですが、結局はジョエルの友人の香港出身のジャーナリストやその同僚が、純粋のアメリカ人でないということで権威主義的なアメリカ信奉の人間に殺害されます。
この場面は、もちろん現在の極右思想の持ち主が差別的に排外的に振舞っている帰結が大量虐殺であることを現わしていて、個人的にもその短絡思想の延長線上の殺戮に対し、激しく嫌悪する場面でした。
ところでその後、4人の内の1人のベテランジャーナリストのサミー(スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンさん)が、機転で車を権威主義的なアメリカ信奉者にぶつけて倒し、銃殺された2人以外の、リー・スミスとジェシー・カレンとジョエルの3人を救い出すことに成功します。
しかし、サミーもその救出の過程で凶弾に倒れ命を落とします。
そしてその後、リー・スミスとジェシー・カレンとジョエルの3人は、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる「西部勢力」の陣地に合流し、その部隊に従軍することで、ついにワシントンD.C.のホワイトハウスの大統領に迫ります。
しかし、大統領に会う直前にリー・スミスはホワイトハウス内で凶弾に倒れ、3人の内、大統領に到達出来たのはジェシー・カレンとジョエルだけでした。
そして大統領は命乞いだけをして、「西部勢力」の兵士に殺害されて映画は終了します。
で、さてこの映画はいったい何を伝えたかったのでしょうか?
そして、この映画が伝えている内容の趣旨に対して、私は全く同意出来ないなと思われました。
おそらくこの映画で言いたかったことは、戦場あるいは無秩序な空間での報道カメラマンは感情を殺して記録することが出来るぐらいしかない、事だったと思われます。
では、その事でその先に一体何を伝えたかったのでしょうか?
感情を殺して記録に徹することで人間性が壊れていくリー・スミスを通して、このような非人道的な戦闘や戦争を起こしてはならない、だったのでしょうか?
その割には、ホワイトハウスに乗り込んで、大統領の周囲の人間や大統領の条件を伝えていた報道官などを簡単に「西部勢力」の兵士は殺害し、命乞いをする大統領も簡単に殺害し、ジョエルも大統領の殺害を喜んでいたと思われます。
この「西部勢力」による大統領や周辺に対する一方的な殺害は、道中の差別的で権威主義的なアメリカ信奉者による香港出身の人間などを一方的に敵とみなしていた殺害と、何か違いはあったのでしょうか?
それぞれの自身の陣営の思考を正当化し、相手に対する殺戮を正当化している時点で、他者を抹消したい欲動の帰結の点では(コインの裏表の)全く同じ思想だと思われます。
感情を殺して記録に徹することで人間性が壊れていくリー・スミスを通して、とてもこの悲惨な戦場や戦闘における殺害を、この映画は否定しているとは思えませんでした。
この映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で描かれていたのは、(権威主義的な思想の信奉者であろうが、それに対峙する「西部勢力」の人間であろうが)敵とみなしたものに対する容赦のない殺害であり、一方の側の殺戮に加担するか、あるいは、それを否定することなく感情を破壊して記録する報道機関の姿でした。
私は、他者への想像力を抹消し他者の存在を消滅させようとする思想には(それが右派的であろうと左派的であろうと)組することは出来ません。
そして、それを記録する事を感情を消すことで可能にし、相手の蛮行に対して異議申し立てをしなくて良いとする報道機関の考えに同意することも出来ません。
報道機関の人間が感情を殺している事を1人になった時に苦悩されても、目の前に存在する他者に対して想像力を辞めたことで起こっている問題の責任から、免れることなど出来ないだろうと、映画を観ていて思われました。
であるので、徹頭徹尾、この映画が提示している考えに合わず、申し訳ないですが僭越ながら個人的にはダメな映画だったと思われました。
意表を突きたい監督のラストは亜流脚本。 途中からネタバレ ★2.9
まず、よくこんな大層なタイトルを付けれたもんだ!
私が内容から付けるなら、せいぜい「新人戦場カメラマンの欲望」だ! (欲望と付くのはラストに起因)
恐らく多くの方とは真逆の評価に。
内戦というぐらいだから、序盤から時事がドンドン進行すると予想したが、本筋以外の描写シーンに時間をとり、物語がタイトルの様にシリアスに進まない・・。
そして描写とは相違なる、アッケラカーンとしたBGM。 シリアスシーンにあえて "明るい曲調" を使うというのは、黒沢明監督が「野良犬」や「生きる」で使った "コントラクンプト" という斬新な手法。 だが、本作はそれを模倣してるだけで、そこだけミュージック・ビデオの様に見えてしまう違和感が。
そして物語はほぼ、カメラマン達のロードムービーに、
小規模戦闘が挟まれる形で進行し、その戦闘描写がややシリアスというだけで、内戦の実情説明はなく、西部勢力がワシントンに侵攻するという稚拙で大まかな物だけ。
作品の全体像が、かなり中途半端でまとまりなく感じて、ぶっちゃけ大いに期待外れ。中盤まで私的に★3.2~3.3ぐらいに感じた。 (最近、鑑賞中にその時点での★点数が、頭をよぎる癖が♪)
それに、戦場最前線で敵建造物に侵入するという、最も生死が分かれる瞬間に、足手まといになるプレス関係者が、ほぼ一緒に行動してるのにも、違和感・・。
ショッキング映像を単純物語に挿入して、さも奥深い作品です、という誤魔化した様な浅はかさが私には伝わる・・。
が、終盤ホワイトハウスへの大規模攻撃シーンで、ようやくハリウッドらしくなり、★がやや上がった時、ラストシーンに唖然・・・。
その、観客を欺きたいだけの描写にあきれた・・。
★が2点台に急降下・・。
唯一、キルスティン・ダンストは、DCヒロインから年月を経て、女優では稀少なしっかり顔になって、重厚な演技を示せる存在になっている。 この様な役が自然に演じる事ができれば後年も活躍するだろう。
↓ ネタバレ含む
ラストシーン
ジェシー役のケイリー・スピーニーが、通路の真ん中にまで出てカメラを構えた時、ああ、やはりこんなエンディングか・・。
それをダンストが、かばって犠牲になる・・。
と瞬間に悟った。
ラストに誰かの死を持って、作品に奥深さを増す私的に、“逃げの脚本”だと。
ダンストが、ほぼ撃たれに行ってるような不自然な動きも、わざとらしいし・・。
が、それだけに終わらず、なんとジェシーはそのダンストを写真に撮り、彼女を無視してまだ撮ろうとする・・。
唖然を通り越し、なんと無謀で亜流な脚本か。
自身の欲望のみで動く姿は、常人として100%あり得ない行動。
憧れを持って近づいた人物が、自分を助けて目前で絶命したのに、人の死で嘔吐していた者が、突如心のない機械の様に無表情で次の行動なんて、まさにフィクション描写。
この監督は、意外性を濃く描写して、観客を驚かせたいだけと感じて、一気に冷めた。
私が敬愛するハリウッド俳優・監督である、イーストウッド、デンゼル・ワシントン、スタローンなどが、もしこの作品の制作に関わっていたら、絶対こんな恥ずかしいラストにはしていない。
彼らは自分の作品に誇りを持っていて、あり得ない様ないい加減な人物像は絶対描かない。
昨今、こういう意外性や曖昧性が強調された作品が多く、
それを評論家が高尚な作品と言わんばかりに絶賛し、アカデミー候補にもなったりする・・。
が、それらの作品はTVで何度、再放送されても、それなりの視聴率を獲る名作・・には当然至っていない。
シビル・ウォー アメリカ最後の日上映中
アメリカの終焉を予感させる
わざと?というか、ドキュメンタリー&ロードムービー風に作っている。コレはアメリカ人に対する警告orレクイエムor懐古なのかもしれない。
話は現在のアメリカの市街地の貧困と騒乱の延長線上の様な混乱と国内紛争から入っていく。
警察や州兵が水を求める市民に向かって暴力を振るいながら秩序を維持しようと努める中にアメリカ🇺🇸国旗を持った女が自爆テロで突っ込んで辺りを吹き飛ばす。アメリカ自体も西部軍と政府軍の内戦真っ只中、もう目も当てられない有り様だ。
一見客観性を保っていそうな報道の主人公の女性(と言っても若い方でなくスパイダーマンの彼女のキルスティンさんの方)は冷静にスクープを追いかけて同僚と車でNYから大統領のいるD.C.を目指す。
もう1人の主人公の女性(若い方)は、freshmanなのは束の間、古き良きアメリカは遥か彼方、人の死と暴力とクソみたいな道中を経験してあっという間に報道写真家稼業に魅入られ、戦争とは違う狂気の世界に嵌りこんで行く。
若い方の主人公のジェシーは、最後自らを庇って死んだリーの死に際まで写真に撮り、屍さえ無表情に踏み越えて大統領の銃殺というクライマックスとエクスタシー向かって突き進む。
取り立ててすごい戦争映画的映像は出てこなかったし、感動的で心温まる人間ドラマも無い、若干軽めで薄め、砂のようなシャリシャリ感のある映画ではあるが、それでもなおタイムリーというか、現実の21世紀が暴力と階級間や国家間での憎しみをモチーフに始まるのを見届けている現代人の心に酷く刺さる…。
現実のアメリカが帝国化するのか、この映画の様に国内市民間での内戦に沈んで行くのか、想像力を掻き立てることこの上ない。
思った感じじゃなかったが良かった
•報道の人のロードムービーとして進んでいったが、戦争の怖さをずっと伝える感じで、ド派手なアクションとかはなく、狙撃兵の静かな淡々としたシーンなど、戦争の本当はこうなんだというのが伝わった。(実際のは知らんけど)
•最後はちょっと派手になって見応えはあった!怖かったけど、、
•カメラマンあんなに近くで撮ったり、兵士に指示を受けてついて行くのかと思った、、
•主人公が女の子を庇うシーン、その前から女の子は危ない行動をしてて、?となって、見終わった後もモヤモヤしてる、、
金の掛かった安い映画
なんと言うか大体想像通りに流れてく
爆発からの無音の演出はプライベート・ライアンもそうだしゲームならCoD MWと最早伝統でにっこり
しかしまぁ内容が余りにもアホらしいと言うかなんと言うか
途中出てくるお前はどの種類のアメリカ人だ?のガンギマリおじさんの様に保守派は排他的で差別的なクズの集まり、革新派は文明的で先進的と表現したかったみたいだが現実の選挙結果を見ればご覧の通りで革新派を自称する連中の思う様にはいかなかったようで何より
と私のしょうもない思想は置いといて途中のスナイパーとスポッターは何だったんだとかあるけどまぁ考えたら負けなのだろう
とはいえ淡々と流れて行く雰囲気は結構好き
最後の大統領を「黒人女性兵士」が射殺する辺りもふふっとなる
かの国も不平不満がぐつぐつ煮詰まってる様子でござい
戦争映画ではなくロードムービー(追記あり)
日常世界に非日常をぶっ込むロードムービー、というフォーマットは好き。ぶっ込まれるのが異形(ホラーやファンタジー)でなくリアル系ならなおさらで、個人的にはツボにはまった。ただ、映画として何を伝えようとしているかはよく分からなかった。
何が対立の種か、なぜ分離主義運動が起こり戦争に至ったかは作品内で一切説明がないので、米国政治社会の具体的な問題へのメッセージではないだろう。戦略も作戦もないので(合衆国大統領以外の指導者も将軍も出てこない)仮想戦記でもない。
最初に思ったのは、挿入される正規軍と民兵(一般人)の戦闘、捕虜の処刑、難民キャンプ、市民の虐殺といったエピソードを通じて、こうした人道的悲劇は今も世界の至るところで起きていると米国人に擬似体験させたいのかということ。だがどれも類型的、きれいに整い過ぎていている気がした。(このくらいライトでないとついていけないとの判断かもしれないが)
次に考えたのはジャーナリズム批評で、カメラマン(フォトグラファー)の「記録し発表しなければならない」という職業的本能についてはドキュメンタリー作品「キャメラを持った男たち 関東大震災を撮る」「続 戦車闘争 [戦争]を伝え続けるということ」のレビューで書いたが、本作にも(フィクションゆえによりピュアに)一歩でも被写体に近づき、シャッターを切ることへの強迫観念が映し出されている。
同時に、現在の戦争報道がembed方式で部隊の同行者として行動し、兵士に守られて最前線で決定的瞬間に立ち会える反面、当局の統制や誘導を受け得ることも描かれている。特に官邸突入後は、本人たちはジャーナリストとしての使命から行動していたとしても、客観的には大統領を殺害するプロセスの一部となっているように見える(最期の証言、死亡の証拠写真)。
そして大統領や警護官らの遺体と共に写り笑う兵士たちの「記念写真」は、勝利の高揚、戦争終結の安堵を割り引いてもある種の違和感を禁じ得ないし、兵士らに頼まれて撮ったのだとしても、新人写真記者がジャーナリストの一線を越えたように、個人的には思える。制作者が射殺直後の「現場写真」ではなくそれをエンドロールに誂えたのは、そこに何らかの問題意識を持っているからだろう。(SNSで誰もが発信者になれる時代のジャーナリスト倫理とか。あの写真が商用配信されたかは説明されていないので、うがった見方かもしれないが)
最後に、はじめの論点に立ち戻れば、相手方の大統領をトロフィーのように扱い、「敵」を軍民問わず殺害する姿からは、同じ国民・人種・民族・共同体の成員であっても、いったん「他者」として認識すればもはや同胞ではなく暴力の行使に躊躇しないという、分断の理由ではなく分断そのものの病理を描いているともいえようか。
なお、IMAXで観たが、戦闘シーンや装備品は全く実物とCGの見分けがつかなかった。驚きの迫力である。ただしクライマックスにしか登場しないので、それを目当てで行くと肩透かしかも。むしろキービジュとは正反対のオフビートな面白味(と後味の悪さ)の作品であった。
追記:最後の写真への違和感の中身
(初出:レントさんのレビューへの10月12日コメントを抜粋、改編)
見習いだったジェシーは道行きで精神的・肉体的にもタフになり、撮影技術も学んだが、「権力との距離」は学ばなかった。ジャーナリズムには力があると知っているので、権力者はそれを利用しようとする。特にエンベッド方式では、軍には最初から自らに有利な写真・記事を出稿させる意図がある。
ジャーナリストはそれを意識して権力との関係を律する必要があるが、最後の「記念写真」を見る限り、ジェシーは(WF支持者だったのでなければ)そのことに無自覚だった。先輩のリーならあの撮影は断っていただろう。これはジェシーの未熟さゆえかもしれないが、私はむしろ、伝統的なジャーナリストの倫理感・行動規範が滅びつつあり、代わって何やら明確ではないが異質な考え方が台頭してきている、そのことを制作者がリーとジェシーに仮託したのかと解釈した。
それはジャーナリズム批判というより、社会の変容への警告かもと思う。
戦場カメラマンの実態ってどうなのか
あまり事前情報を入れずに(マーベルではないことは把握して)観たが、終盤以外は「報道とは」な話が多く、そこにあまり共感できなくて入り込めなかった。
右翼っぽい兵士のところから緊張感はより出たけど、まあ日本人も殺られるよね。。
戦場カメラマンがついて回るのが煩わしくてフレンドリーファイヤされないのかなと思ってしまった。
実際の所どうなんだろうか。
絵はすごく良いところがいっぱいあったけど、世界観もいまと何処で分岐したイメージか掴めず。
なんとなく好かない作品だった。
予告編をみたイメージとは違った
戦争アクション映画と思って観たら
違っていました
戦場カメラマンの成長、PTSD、倫理観
などを描いた作品。
とても重厚な人間ドラマでした
政治的なメッセージがない
なぜ内戦に至った決定的な要因が分からない
現実的ではないテキサス州とカルフォルニア州の同盟
などなど
観る者に多くのことを考えさせることが作品のテーマ
だと思います
我々が今なすべきことは何か?
決して他人事とは思えない
気持ちが重くなる作品でした
音響がすごいのと
BGMがカッコいいのと
サミーがよかったです
(スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソン氏)
赤メガネの男がとても怖かったです
(ジェシー・プレモンス氏)
続編は望みません
これはこれで終わって欲しい
リアリティ? なのか?
現代アメリカの内戦がもし起こったら、という思考実験的な映画。
と思うのだが、現代においてSNSやスマホがほぼ登場しないのは不自然だし、そこでこの映画のリアリティはほぼないな、と思う。その点は作っている側もすごく意識していたと思うが、SNSの要素を入れると破綻するか面白くなくなると判断したんだろうと思う。
戦場におけるジャーナリズム、が日本には馴染みのない概念なのが個人的にこの映画を理解しきれない理由だと思う。ルールを知らないスポーツを観戦している感じに近い。日本で戦場でカメラマンと言うと渡部陽一さんを連想するが、彼が撮った写真をちゃんと見た人間が何人いるだろうか。
戦争の発端は政治的な問題のハズが人種差別や暴力など表層の問題に帰結する。こういう社会問題を描いた映画を観るたびに思うが、「面白い」と言っていいのか困る。描いている問題で苦しんでいる人間が実在しているのは確かだ。ただ、サスペンスとロードムービーとしてはすごく完成度が高い面白い映画と思う。
主人公の同行者のジョエルがハイになっていたり、一方でサミーが努めて理性的であろうとしたのも、女性主人公2人がジャーナリズムに徹してようとしているのはその中庸、戦争環境における人間性の表現なんだろう。戦争から眼を背けている人間が登場し、主人公達も家族は戦争には無関心だと共感しあうシーンは、問題を先送りにしたがる人間の弱さを示していて印象的だった。
物語の最後、大統領が兵士に銃を突き付けられジョエルに言葉を求められた時、出た言葉は泣き言であり命乞いだった。アメリカ=大統領とするなら、この思考実験は悲劇的な結論を出してしまったんだろう。せめて気丈な言葉と共に射殺されていれば‥‥‥。
うん…色々感じる所が…
本当に人によって感じ方や感想が変わる映画だと思いましたね。
まず、米国で大ヒットという事でおめでとうございます。
それと、米国で本当に起きそうな映画なので、唯一国民が銃を持てる国としてこの人間の恐ろしさが、米国民の暴動の抑止になる事を願うばかりですね。
さて、皆さん色々感じ方が違うと思うので、賛否あるかもしれませんが、まず僕の思った感想は若い人の無知からくる野心と、未熟から来る今ここでこういう行動したらどう危険か判断出来ない不意の思い付きの予想出来ない行動は怖いなと思いました。
若いカメラマンが映画だからか米国人だからか、グロシーンの耐性は進むに連れて付いてましたが、ガソスタのシーンも一歩違ったら撃ち殺されてただろうし、アホな仲間のカメラマンの乗り移りの真似して皆に迷惑かけて1人失ってしまったり、最後も待てなくてとっさにカメラを構えてしまって1人失って、映画だしそういうシーンを撮って成長を見せり、伏線回収と尺稼ぎをしたいんだろうけど読めすぎてモヤッとした。あのトヨタのカメラマンもウザかったです。若い子もトヨタの人も要らなかったなと思いました。空気ぶち壊し。
ただそのシーンの所で唯一面白かったのははだかる人によってはガソスタの人みたいに金があると分かっても殺さない人や、記者と分かれば撃たないスナイパー2人みたいに物分りの良い人と、容赦なく殺すあの2人みたいに、人によって結果が変わる所はリアルで怖かった。
あと、左右に別れれば同じ同国民でも笑いながら殺す米国人には、南北戦争したり、差別あったり、銃所持出来るする国に住んでるだけあって怖さを感じました。
でも、概ねの西の兵士達は重荷でも、記者を守りながら戦場に付いて行かせる所は、兵士も個々で色んな思いを持ちながらも仕方なく戦ってる人も居るからこそ、こういうリアルを残して欲しいと思ってるんだなって感じました。
と思ったら大統領との最後のシーンでの若い子と男のカメラマンと兵士達の笑顔でサイコパスになってしまってた所が残念でした。
戦場カメラマンはそうでは無いでしょって。
その少し前にはアホの若い子のせいで1人亡くしてるのに。
思い返せば、非日常と生死の境を短期間で経験してしまい若い子ですら頭おかしくなったのかと悲しくなった…
男のカメラマンみたいに銃声で楽しめないとあんな危険な所に行く気が沸かないのもあるのかもしれないけど、人の死を撮って笑顔はいけないだろと思いました。
画面の向こうのリアルと怖さを知るには良い映画だと思いましたし、画面で死体に慣れててもリアルで起きる画面の向こう側はでは命は1人1つだし五感にもくるし、だからこそ画面に踊らされて一線を越えてはならないと強く思いましたし、中々グロシーンを攻めててある意味良いなと思いました。生きたなんちゃらを思い出した。
ブラックホーク・ダウン以来の見た後の儚さと悲しさを感じて少しの間虚無になりました。
本当に色々考えさせられるし、平和って凄い紙一重だと思えたので大事にしようと思いますし、凄く難しい事ですが内戦ほど愚かな事は無いと思いました。
痺れるほどの皮肉が効いた米国内戦下のロードムービー
「3期目」の大統領が君臨するアメリカ合衆国で起きた内戦下のロードムービー。
テキサスとカリフォルニアという二つの州が同盟を組んで政府軍と戦うという「あり得ない設定」ですが、分断の進んだ現在のアメリカでは必ずしも「あり得ないとは言い切れない」絶妙なリアリティ。
その中でベテランの戦場カメラマンと戦場カメラマンを志す若者、そして2人のジャーナリストが、独裁者である米大統領のインタビューを取るべくワシントンDCを目指します。
内戦で崩壊した「自由と夢の国」を舞台とした暗澹たるロードムービーの果てに、ベテラン戦場カメラマンはそのプロとしての矜持をすり減らした結果、人間性を取り戻し、戦場カメラマン志望の若手は人間性をすり減らし、「プロ」としての矜持を獲得します。
その結末に描かれるのは、「正しい」目的を持ち、独裁者の殺害を正当化するようなプロパガンダとしての一枚の写真を示すことで物語は終結を迎えます。
予告を見る限り、よりアクション要素の強い戦争映画を予想させつつも、アレックス・ガーランドがそこまでシンプルな映画を作るはずもなく、「正義」が正義ではなくなる瞬間の皮肉を見事に描き切った一作に仕上がっています。
タイトル間違えてません?
シビルウォーというよりも、女性カメラマンの成長がテーマのような気が、、、。
シビルウォーにしたほうが、集客は良いのでしょうけども。
あと、選曲のミスマッチ感。
シリアスな場面になぜか軽い曲を選んでしまっていたりと、いったい何の意図があったのか。ラストシーンしかり。あれが副題のアメリカ最後の日なのか、、、。
日常と非日常。政治的な不安定、経済の不況、自然環境の劇的な変化、
などの要因で日常が突然非日常に変わってしまう。
そんなことを少し考えさせられたけども、アメリカの内戦の背景を客の想像に任せずに、
もう少し可能性を深堀して欲しかった。
ストーリーは特にアイデアというものも感じられず、
ただ、最後のほうの戦闘シーンは映像と音響の迫力がありました。
鬼才により描かれる現代アメリカへの警鐘。
IMAXレーザーにて鑑賞。
『エクス・マキナ』『MEN 同じ顔の男たち』の鬼才アレックス・ガーランド監督による体感型ロードアクションムービー。4名のジャーナリストの視点を通して描かれる、分断されたアメリカ社会の闇。クライマックスで戦場と化すワシントンD.C.での戦闘描写は、IMAXやDolby等の映像や音響の優れた没入感抜群の上映環境での体験推奨。
内戦が勃発し、国内が西部勢力と政府軍に分断された近未来のアメリカ。かれこれ14ヶ月もの間取材を受けていない大統領を取材する為、リー、ジェシー、ジョエル、サミーら4名のジャーナリストがニューヨークからワシントンD.C.を目指し、約1,400kmの道のりを車で向かう事に。彼らは次第に、アメリカ社会の闇と内戦の恐怖を目の当たりにする事になる。
前半はロードムービー、後半は臨場感タップリのアクションムービーと、異なる姿を見せる物語が良い。スイッチが切り替わるのは、中盤でジェシー達が差別的な武装兵に尋問されるシーンだろう。
「お前は、どの種類のアメリカ人だ?」
予告編でも使用されていた、この印象的な台詞と共に紡がれるあのシーンの緊迫感は、間違いなく本作の白眉だろう。
この差別的な兵士を演じたジェシー・プレモンスが、主演のリー役キルステン・ダンストの夫である事によるカメオ出演という裏話も興味深かった。優れた作品は、不思議と優れた俳優を引き寄せるのだろう。
内戦の理由が明かされない点も良い。冒頭、リテイクを重ねて権威的な演説をTV放送する大統領を映す事で、その後の西部勢力の「独裁的な大統領を打倒する」という動機はすんなりと理解出来る。しかし、それ以外の要素を意図的に明かさない事で、「彼らの行いは正当なものなのか?本当に正しいのはどちらか?いや、どちらも間違いなのか?」と、我々観客が考察する余地を残している。あくまで本作は「勝つ側」の視点に立って物語を追ったに過ぎず、視点を変えれば西部勢力の勝利は更なる混乱の時代の幕開けかもしれない。ニューヨークのホテルで、「西部勢力は、勝ったら今度は自分達同士で争う」とサミーが予見したように。
音楽の使い方も印象的だった。オープニングを飾るSilver Applesの『Lovefingers』を始め、随所で挿入される楽曲が、ロックやポップといった、本作の暗く絶望的な状況とは対照的(但し、提示される歌詞は反戦や自由といった本作のテーマに通じるもの)なのが、物語のトーンを陰鬱にし過ぎず、フラットな視点で観客に物語を追走させる手助けとなっていたように思う。
個人的なアレックス・ガーランド監督作品への信頼として、「画作りへの拘り」がある。代表作『エクス・マキナ』は勿論、『MEN 同じ顔の男たち』でも顕著だった、「悲惨、もしくは不穏な状況下にも関わらず美しい画面」というアンバランスさが醸し出す妙が、本作でも顕在だったように思う。
特に、Sturgill Simpsonの『Breakers Roar』と共に描かれる、焼き討ちされ燃え盛る森の道を走り抜ける車の周囲を、まるで儚き命の灯火かの如く火花が宙を舞うシーンの圧倒的な美しさには、思わずため息が出た。その中で静かに息を引き取るサミーの悲惨さも相まって、個人的には先述した武装兵のシーンより素晴らしかった。
ところで、本作はジェシーの成長譚としても楽しむ事が出来る。演じたケイリー・スピーニーは、『エイリアン:ロムルス』でも主演として抜群の存在感を放っていたが、本作でも夢見る純真無垢な女性から、戦場の過酷さ、ジャーナリズムの中でジャーナリストが背負う宿命に翻弄され覚醒していく様を見事に演じ切っていた。序盤こそ理不尽な暴力の光景に打ちのめされ涙を流しながらも、次第に戦場で真実にカメラを向ける高揚感に取り憑かれ、最後は尊敬するリーの犠牲すらも糧にして、歴史的瞬間をカメラに収める。特に、ホワイトハウスで自らを庇って銃弾に倒れ、真横で息絶えたリーの方を見ないのが素晴らしい。リーの犠牲を糧に覚醒し、最後にリーの亡骸の方を振り返るジェシーの目には、最早理不尽に打ちのめされ涙を流していた数日前の姿は無く、冷徹に真実のみを追い求めるジャーナリストの姿があった。
ともすれば、それは間違った成長だろう。リーが過酷な戦場をカメラに収めてきたのは、人々に真実を伝える事で最悪の未来を回避する為だった。しかし、祈り虚しく内戦が勃発し、自らのジャーナリズムに対して不信感や敗北感を抱えていた。そんな彼女が命を賭して守ったジェシーは、しかしリーの思いを正しく継承したとは言えないだろう。内戦という最悪の事態が、不必要な犠牲と生まれてはならない怪物を生み出してしまったのだ。
ラストで射殺された大統領を囲んで笑顔でカメラに映る兵士達の写真。ジェシーの古い型のカメラ故にモノクロで収められたその歴史的瞬間は、色という他者への共感性や感心を失った現代社会の悲惨ささえも写し取ったかのよう。
これまでSFやホラーといったファンタジー色の強い作品を得意としてきたアレックス・ガーランド監督は、本作で現実問題に根差した臨場感あるアクションまでも描き切ってみせた。益々プロとしての円熟味と切れ味を増していく監督の次回作が、今から楽しみで仕方ない。
何を訴えたかったのかな
ヒトコワ~人間が一番怖い~。こんな世の中になってしまったけど、結局人が一番怖い…という事ならば、ウォーキング・デッドであんな静まり帰ったアメリカの風景や殺し合いは既に見たな。それとも、女カメラマンの成長を描きたかった?だとしたら、憧れの先輩のあの最後…トラウマでカメラマン続けていけるか?!オー凄いね、頑張ったね、とはならない脚本。説得力は弱い作品。
またもやA24 アメリカの様々な問題をブチ込んできた怪作
報道スチルカメラマンを主人公にした作品だけに、カメラや写真の観点から感想を書いてみたい。
まずジェシーが持つカメラは、なぜNikon FE2だったのか?
FE2は1983年に発売されたフィルムカメラ
映画の中では祖父が持っていたカメラとのことだった
ハイエンドではないので写真を趣味とする人などが一般的に買う機種だったはず
1983年当時で考えても、おおよそ報道のプロを目指すような人間が手にするカメラではない。
話はちょっとズレるが、今フィルムカメラは静かなブームになっていて、現代のデジタルカメラのシャープで全てを写してしまう高分解能に対して、気分を写し込むような、あいまいさや鈍いフォーカスなどの雰囲気がレトロ感も相まって人気がある。
映画に戻ると、このNikonFE2というアイテムは、ジェシーのあどけなさやひ弱さ、薄っぺらいTシャツなどと相まって、彼女がその辺りにいる普通の子で、思いつきでしか行動していない危なっかしい無知な女の子であるということを補強している。
映画の中でジェシーがフィルムを自家現像しているシーンが出てくるが、水道もない場所で現像→停止→定着→水洗の工程を行うことはできない。
フィルムなので多くて36枚しか撮影できないが、フィルムを詰め替えるシーンはひとつもない
ホワイトハウスに侵入するシーンでは、兵士の機関銃の弾切れのシーンはやたら出てきたが、ジェシーの弾切れは一度も無かった
ここまで矛盾点が多い中、FE2にしたかった理由とは何なのか?
監督に聞いてみたい
またジェシーが使っているのはモノクロフィルムだった
これについてはアメリカの過去の内戦「南北戦争」を想起させたかったという気もする
この南北戦争との関連も映画の中にはたくさん詰まっていそうで、その観点から読み解くのも面白そうだ
最後に、大統領が射殺されて兵士たちがその前で笑っているモノクロ写真は、よくハンターが獲物を前にポーズしている写真のようだった。
大統領をハントした兵士たち、その写真をハンターのように激写したジェシー。
Shootという英単語が「銃を撃つ」という意味に加え、「写真を撮る」という意味もあるように、快感さえ覚えながら本能のように連射したジェシーと、頂点(絶頂)をすでに迎えたリーとの世代交代がこの銃撃シーンで行われたのは暗喩的な気がする。
アメリカ内戦
予告では派手さが目立ったがストーリーはジャーナリスト一行が大統領取材の為に陥落間近のワシントンへ向かうロードムービー。平和な日常中に突然、残酷なシーンが現れる。確たる内戦の発端は描かれず、ロメロのゾンビ映画を思わせる異様な不気味さが漂う怖さ。ウクライナ、ガザ、ミャンマー、様々な紛争地域で起きている戦闘、虐殺、理不尽さをアメリカ内戦に置換え分断され内戦下のアメリカを描くのが主題。ジャーナリストとは何か?を描くのかと思いきや、あれだけ最前線にいたらそりゃ死ぬ!?悲観的にならない潔さ。
アメリカには武装組織や民兵がいて政府が人民の自由や権利を抑圧するなら武器を持ち戦うと普段から備えている人間がかなりいるので、内戦になれば狂信的な人間が率先して一般市民を交戦規定などガン無視し喜び虐殺に加担する。まあ、いざとなれば日本にもいるけど。
パンフレットはよくできてる
鑑賞後に友人と内戦のことを描きたいのか、ジェシーのカメラマンとしての成長を描きたいのかよくわからないって議論に。パンフレットを見ていると、表紙の値札が剥がれないし、よくみると縁が緑色だけどTIMEに似てる…となり、ページをめくっていくと最後の方に載っていた白黒の写真がジェシーの撮ったものだけで、リーの撮った写真が1枚も無いことに気づく。つまり、このパンフレットは大統領の死後、映画の中の世界で実際に出版された雑誌で、ジェシーの写真が評価されたということになってるのか?
これが「アメリカの最後」でもいいのか?!
米国で発生した架空の内戦をジャーナリストの視点から描いた問題作。
政治的な主張の違いから深刻な対立が激化する現代のアメリカ。そんな状況に着想を得て本作が作られたことは容易に想像できるが、一方で現実の政治的対立を反映しないよう、慎重な配慮がなされていることにも注目。
そのひとつが設定上のリアリティの欠如。
3期目の任期に突入した合衆国大統領は、FBIを解体した以外にどんな施策を行ったか、作品上まったく示されない。
従って、いかなる理由で19もの州が連邦離脱に至ったのかも、WF(西部勢力)との間で内戦にまで発展したのかも最後まで不明のまま。
そんな中、唯一具体的といっていいのが、WFを構成しているのがテキサスとカリフォルニアの二州だという点。
政治的に保守的な地盤のテキサス州と、リベラルな政治風土のカリフォルニア州が連合して政府に反旗を翻すことなど有り得ないのは、合衆国憲法で大統領の任期が二期までに制限されていることと同じく、アメリカ人にとって常識。
当然、これらの非現実的な設定が恣意的なものであることも明白。
さらなる対立を煽るような政治的題材を引用して、公開後に暴動を誘発することを危惧しているからで、それが杞憂ですまされない可能性があることは、2020年に起きた連邦議会占拠事件が証明している。
NYでの暴動を取材後、メディアに沈黙を続ける大統領から独占インタビューを取るべくワシントンDC入りを計画するベテランジャーナリスト3人。
その中のひとり女性カメラマンのリーに憧れ、フォト・ジャーナリストを志す若いジェシーがさらに加わった一行は自動車で首都を目指す。
作品は一貫してジャーナリストの主観で綴られ、民間人の犠牲を声高に非難したり、兵士との心の交流などの戦争映画にありがちな、お涙頂戴の場面や感動的な演出を排除することで、製作者が観る側にも画面から目を背けず中立な立場で鑑賞するよう求めていることが伝わってくる。
戦争がなぜいけないのか─。
殺人の肯定もだが、戦争が人間を簡単に狂わせるからだと自分は思う。
一行は首都までの道中、幾度も戦闘に遭遇し、戦争の狂気を目の当たりにする。
拷問した捕虜との記念撮影をリーらに求める若い兵士、相手が誰かも分からぬままライフルを乱射する狙撃兵、ホワイトハウスで交渉中の報道官を文字通りの問答無用で射殺するWFの突撃兵。
そして、極めつけは顔見知りのジャーナリストと合流後の一行を待ち受ける所属不明の武装グループ。
一行に「どんな種類のアメリカ人なんだ」と訊問し、異質と判断すれば即座に射殺する彼らの正体は明確には示されないが、おそらくは内戦に便乗して人間狩りを繰り返す差別的な自警団。
これらのエピソードは戦時下での実際の出来事をモチーフに「再現」され、非現実的な設定とは裏腹に、リアルな戦争の狂気と恐怖を観る者に突きつける。
ジェシーを演じたのは、『エイリアン・ロムルス』でヒロインの少女を熱演したケイリー・スピーニー。
撮影時の実年齢が25歳で設定上は23歳だが、メンバー中とりわけ若い彼女の見た目の印象はもっと若く10代にもみえる。
自警団に捕らわれて自らも殺されそうになった挙げ句、合流した報道仲間と一行の知恵袋的存在だったサミーの命を奪われ、激しく動揺したジェシーはその後の行動に変化が生じる。
それまでは若さゆえか、拙さや戸惑いが目立ったが、首都制圧を目指す現地のWFに合流後、飛び交う銃弾をものともせず、率先して被写体にカメラを向ける。
つらい経験を越えて報道カメラマンとしてひと皮剥けた姿にもみえる一方、自暴自棄にも映る彼女の行動をリーたちは心配する。
クライマックスの首都攻防戦のシーンは圧巻の一言。
火力にものを言わせ、殲滅作戦で政府軍を圧倒していくWFは脱出を図る大統領の車列にも、容赦なく砲弾を浴びせる。
そんな中、リーは長年の経験から大統領がホワイトハウスにとどまっていると判断、ジョエルやジェシーとともに邸内へ進入し、WFの突撃兵も追随する。
数度の銃撃戦ののち、突撃隊はついに大統領執務室に肉薄し、世紀の一瞬を逃すまいとジェシーは不用意にも一歩前へ。シークレットサービスの照準に捉えられた彼女の命を救ったのは、みずから盾となったリーだった。
自身の憧れで道中の庇護者だった彼女が代わりに銃弾を浴びて斃れるのを目の当たりにしながらも、ジェシーはスクープを優先して執務室へと向かう。
その姿をジャーナリストとしての成長と捉えるべきか、人間性の喪失と感じるべきなのか─。
作品中の大統領をトランプ前大統領に比定する人も多いと思うが、本作の大統領は出番も極めて少なく、ほぼ無個性で名前すら判らぬまま。
最後でジョエルに促されて命乞いするが、WFの兵士に躊躇なく「処刑」される。
このシーンを観て溜飲を下げる人もいれば、やり過ぎと感じる人も多い筈。
だが、内紛や内戦下で敗者が正式な手続きなしで処刑されるケースはルーマニアのチャウシェスクやリビアのカダフィらの例にあるとおり、珍しいことではない。
製作側は鑑賞者の中にこれらの例を想起する人がいることを期待し、同時に「アメリカの最後も同じでいいのか」と問い掛けているのかもしれない。
映画はジェシーが撮影したと思しき、処刑された大統領を取り囲む誇らしげな突撃兵の写真にエンドロールが重なる映像で終了する。
このラストに強い違和感や嫌悪を感じた人は、やはり「戦争はいけない」と分かっているからだと思う。
作品の最後で一人前の戦場カメラマンとして、スクープをものにしたジェシー。
彼女の将来を待ち受けるのは、ピュリッツァー賞などの名誉や富か。
それとも目標だったリーや、26歳で戦地に散ったゲルダ・タローと同じ末路なのか。
そんなことは、世界中で戦争が続く限り誰にも分からない。
ないようがないよう
アメリカ最後の日とかアメリカ分断とか
御大層な文言の割にそこはバックボーンでしかなくて
戦場ジャーナリストのお話
なのに戦場カメラマンについての話も薄い
冒頭ガススタと途中のイカれた奴くらいしかイベントもないし
最後もアドレナリン出てたって感じなんだろうけどあれでいいの?
全232件中、121~140件目を表示