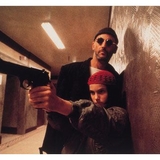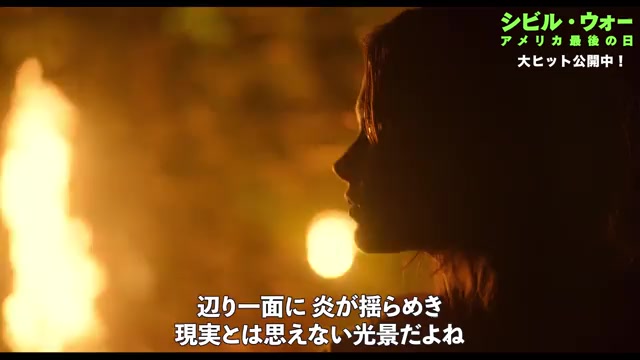シビル・ウォー アメリカ最後の日のレビュー・感想・評価
全623件中、21~40件目を表示
自国で再現
サブタイトルがダサくないか。
だが本編はメチャクチャ面白かった。
シュミレーションというより、おそらくSFジャンル。
かつ米国自身が他国で行ってきたことを、自国内でもやってみたら、という皮肉が凄まじい。
大戦では一度も本土が脅かされることのなかった米国において、自分たちの国がヨソでやてきたことを実感することは難しいだろう。目の当たりにしたことで、作品がヒットしたこともうなずける。
赤勝て、白勝ての話にしないため、視点をプレスにおいたことと、写真という客観の究極であるモチーフの導入、そしてプレスが疑似家族構成であるところに、状況との絶妙な距離感を感じている。冷静、公平に観察しつつも、物語の中には感情移入しやすい自分のアバターが存在するというのは、かなり没入感を高めているはずだ。
国内が内戦になったら、というテーマももちろんあるが、様々他国の内戦にいっちょかみしてきた米国である。同じことが自国でも行われたらというシュミレーションで問題定義も兼ねているとしか思えない本作は、アッパレだ。ただの戦争映画に終わらない。
戦闘シーンのリアルさ、緊迫感が凄まじかった。
オレンジグラサンの兵士に捕まるくだりはもうどこかで見た気しかしなかったし、本当に怖かった。
斬新で奇妙
内戦って、寧ろ酷くなる??
内戦状態になったアメリカを、ジャーナリストの目を通して描く物語。
トランプ政権誕生で顕在化したアメリカの分裂を、シビアに映した秀作です。
物語はロードムービーテイスト。ワシントンを目指すジャーナリスト達が、その道すがら目の当たりにする残虐な光景を活写します。
市民の分断、人間の残虐性、身近な死、そして恐怖・・・ユーゴ内戦を想起させるようなシーンの連続に肌が粟立つ思いです。
ベテランと記者志望の若者を組ませたのも秀逸でした。特に、想像を絶する光景に立ちすくむ若者の姿は、鑑賞している私の代弁者でした。
クライマックスは迫力十分。でも、中盤迄のリアルを失わない程度に抑えられていて好感が持てました。
私的評価は4.5にしました。
「米国の分断」を描いた映画ではありません
内戦が起きたアメリカで大統領にインタビューしに行くジャーナリストが主人公です。これは題名から想像されるような政治系の話ではなく、戦争状態における戦場での狂気や生々しい恐怖が主体となった作品です。「米国の分断」を描いたような映画ではありません。
戦争の現場は殺人が肯定される場所であり、そこでは丸腰であるかどうかなど関係なく殺人が易々と実行されると。手を上げている人間を易々と射殺する、そういう狂気にあふれた非人間的な場所だと言うことを強く訴えていると感じました。この映画の見せる狂気・悪意は戦場であればどこでも通じるのだと思います。そこがとても怖ろしく感じました。今もこのような悪意にさらされている人々のことを思うと胸がいたみます。面白くなかったわけではないですが、あまり気持ちの良い映画ではないです。
報道カメラマンの話だった…
あの『地獄の黙示録』と被るかな?と思った瞬間、少し冷めたかもしれない
監督は、『エクス・マキナ』『MEN 同じ顔の男たち』のアレックス・ガーランド。この二作は、どちらも独特で面白かったから、いやでも期待値は上がるよね。
よくできた作品だけど、ちょっと微妙なとこはあったね。アメリカの内乱というとんでもない状況で、戦場カメラマンとして成長していく女の子の物語とも言えるのだけど、成長と言うには、いくつかの点で無理があって、、、
その女の子をケイリー・スピニーが演じるのだけど、キルスティン・ダンテストと並んで演技していると、ただのお人形さんにしかに見えなかった。『プリシラ』と『エイリアン:ロムルス』の主役の女の子だったんだっていうのも後から気づいたくらい。三作品とも、無表情で少し気の強そうなワンパターンの演技だったからかも。言い過ぎかな。近々、超大作の主役とかで大活躍するかもね。いや、それはないかあ。
でも映画自体は、ホワイトハウスで大統領を追い詰めるクライマックスとか超迫力あったし、登場人物もそれぞれいい味出していたし、『地獄の黙示録』的なインパクトある映像といかにもな音楽による世紀末的演出???もよかった。話題になった赤いサングラスの男だけど、『おまえはどんな種類のアメリカ人なんだ?』はキレッキレッ演技だったよね。急遽代役として起用との経緯らしいけど、実生活ではキルスティン・ダンテストの結婚相手というのには驚いたね。
いまに始まったことじゃない分断。某大統領の存在など、リアルなアメリカの近未来の映画なんだ的な話もあるけど、そこじゃないと思った。イギリス人なガーランド監督って、社会性を意識したっぽい脚本書くけど、結構引き気味なスタンスだよね。どこか全然違う方向を見ているようなファンタジーっぽい違和感がある。うまく説明できていないけど。今作品で強く思った。
アベンジャーズ ⁉️
死に身の戦場カメラマン
A24史上最高の製作費を費やした映画と言われ興行も批評も成功した。
が、私見としてはゾンビを内戦にした映画、という印象。主人公はロイターの記者ら。リアルだがシチュエーションがありそうにないから、ジャーナリズム魂の根拠が希釈された。にもかかわらずひたすら命がけ、ノーヘルで小隊にぴったりはりついてアナログ写真を撮りまくるのが変すぎる。シリアスなジャーナリスト、なのに動機がない。ゾンビなら解る世界だが、内戦と言われるとピンとこなかった。
だがRottenTomatoesは81%と69%で意外にも批評家がサムズアップしていた。どこがいいと言っているのか見ると、幾人かの批評家はこれをホラーとみなしている。ゾンビ映画と同列にみるなら社会派視点からの講評がまぬがれる。
またサウンドデザインがいいと言っている。たしかに選曲とその使い方は地獄の黙示録風で秀逸だった。
さらに説明を省いているのがいいと言っている。内戦に至った経緯や情勢など解らぬまま、戦闘描写を見せられ、状況が解らなすぎるゆえに、その解らなさが戦争の無意味さを際立たせた、と評価された。
そのほかキルスティンダンストの演技やスペクタクルで手加減しない殺戮シーンなどが評価にあがっていた。
が、個人的にはピンとこなかった。新米戦場カメラマン役のCailee SpaenyはラフなTシャツ姿で死に身の戦場にいるっていうよりスーパーボウルかなにかを観戦している人にしか見えず、そこらへんに死骸や乗り捨てた車両が転がっている世界は内戦よりもウォーキングデッドが連想された。ゾンビを内戦にした映画という見方でいいのは解ったが、となれば比べるのはロメロになるから、むしろハードルは上がってしまう、という話である。
唯一凄みを感じたのはジェシープレモンスが出てくるシーン。超国家主義かつ白人至上主義で戦乱に乗じて気に食わない人間をコロしまくっている暴徒を演じていた。プレモンスが演じるとほんとに怖いのはさすがだった。白眉だったと思うがプレモンスは旦那枠でノークレジットだった。
wikiからの引用だが、否定派の批評家が『脚本が有色人種の登場人物を残虐行為の媒介物として利用している点はもっと掘り下げる必要があった』と述べていた。
この意見は、内戦が政治的なものでなく、ヘイトから発展したものである可能性を示唆していると思う。前述したプレモンスのシーンで殺されたのはいずれもアジア人の記者だ。
かつての南北戦争=Civil Warは黒人を奴隷あつかいする派と解放したい派の争いだったが、あたらしいCivil Warはアジア人のヘイト派と擁護派の争いなのかもしれない、という示唆である。そして懸案となるアジア人とは当然中国人のことだ。言うに及ばず、世界中に中国人が蔓延している。未来にはアメリカに限らず中国人を火種とする争いはじゅうぶんに考えられる。
ホラーより怖い「アメリカ合衆国」の最期
2024年公開、アメリカ・イギリス合作映画。
【監督・脚本】:アレックス・ガーランド
主な配役
【リー・スミス】:キルスティン・ダンスト
【ジョエル】:ヴァグネル・モウラ
【ジェシー・カレン】:ケイリー・スピーニー
【サミー】:スティーヴン・ヘンダーソン
1.あまりに生々しい終末のアプローチ
◆他国から奇襲攻撃を受ける
◆隕石が地球に衝突する
◆異星人が侵略を試みる
◆核戦争が始まる
過去には、さまざまな空想(科学)のアプローチで、
アメリカの危機や終末が描かれてきたが、
「内戦」によるアメリカの自壊は、いまを反映していて生々しい。
本当に生々しすぎて、映画を観てまったく笑えない。
2.アメリカ人と日本人の違い
アメリカ人はこんな人たちだろう、と想像している通りの人物たちが次々と登場してくる。
ナチュラルに怖い。
日本人とは決定的に異なることが分かる。
アメリカ人=敵対勢力は、原則として、殺す
デフォルトプログラムが「殺す」なので、
やりとりの緊迫感はハンパない。
3.まとめ
記録映画のようなリアリティ。
本当に怖い映画。
ホラーより怖かった。
素晴らしい作品とは思うが、
怖い映画は苦手なので、☆3.0
アメリカの分断を描く最終形。そしてジェシーのお尻も大きい
アメリカ国民の銃の所持の権利は政府が間違っている時、国民は力を持って政府を打倒せよと合衆国憲法が定めでいるのです
シビル・ウォー アメリカ最後の日
2024年4月米国公開
Amazon prime video
シビル・ウォーとは辞書で引くと内戦のこととあります
というより米国人には南北戦争のことだとまず最初に理解するみたいです
1861年から1865年のアメリカ合衆国と南部連合国との内戦
南部連合国の国旗はXです
ツィッターを買収した大富豪はそれをX と改名しました
南北戦争は内戦と言っても本格的な戦争でした
それも両軍で300万人もの兵力が激突し4年で66万人が戦死したガチの戦争です
同時期の日本の内戦戊辰戦争では戦死者は両軍合わせて1万人ほどしかありませんでしたからケタ違いです
戦場になった合衆国南部の諸州の街々は焼かれ荒廃しました
「風とともに去りぬ」のクライマックスで焼かれたアトランタのように
アメリカ人は南北戦争をトラウマのように大変に恐れています
国論が二分され対立が激化したときまた南北戦争を起こしてはならないと恐れています
本作は合衆国大統領選挙の直前に撮られました
もちろん片方の候補が当選を阻止するための政治的な思惑によるものです
報道や映画界などメディアが先頭に立ってそれを防げ!そうしないと、数年後には本作の世界が現実になるぞという警告です
その戦いの結果はご存知の通り
1月20日何がなんでも大統領にしてはならない人物が大統領に就任しました
ウクライナは早々に見捨てられ
欧州もNATOと共に見放されました
アジアもどうなるか知れたものではありません
だから、新大統領が就任した以上本作の役割は終わりました
それでも本作をそれ以降も見る意義や意味はあるのか?
今日は2025年4月15日です
新大統領は関税戦争に取りかかって大騒動を全世界に繰り広げています
株式市場も債権市場も乱高下して
正に合衆国最後の日を迎えようとしているかのようです
本作の中で大統領が話す内容は
まるで現実のニュースのままです
合衆国憲法で禁じられている三期目の大統領就任まで考えているとのニュースですらつい先日現実に聞いたばかりです
彼は独裁者になろうとしているのです
しかし合衆国の人々は新大統領に従っています
表立って異を唱えたり反抗する議員や政治勢力はないようです
何故かって?
政府から弾圧を受けるから?
いくら酷い大統領であっても大統領は大統領、従うしかないから?
それもあるでしょう
しかし、本当のところは真っ向から対立して国が半分に割れてまた南北戦争になったらと恐れているからだと想います
本作の世界が現実化しないように
黙っているのです
彼らアメリカ人には本作の世界があり得ることをよくわかっているのだと思うのです
いくら酷い政策であろうとも南北戦争の再来よりはマシであると
リアルです
リアル過ぎるほどです
第二の南北戦争に突入したときアメリカがどうなってしまうのか
克明に映像化されています
アメリカ人にはもう本作の世界が見えているのだと思います
今日のニュースの延長線上にこの世界があることを
だから、この世界を現実化させないために、自分は黙っていよう
本作の中でも衣料品店の女性がそれが一番良いことだ思うと言っていました
この世界は間違い無く訪れてしまう
そんな悪寒に震えました
ではどうしたらそれを防げるのか?
ジャーナリスト?
メディア?
こうなった以上
そんなもの何の力も無いというのが本作の結論だったと思います
アメリカ国民の銃の所持の権利は政府が間違っている時、国民は力を持って政府を打倒せよと合衆国憲法が定めでいるのです
身も蓋もないことですがアメリカ国民がこの大統領を望んだ結果なのですからまして他国の日本人の私達になし得ることなど何も有りません
力だけがものをいう世界になってしまったこと私達日本人も本作を観ることでより早く気がつくことだとだけだと思います
暗澹たる思いです
武器を持たずに戦場を走り回る報道カメラマンの仕事の厳しさが分かる。...
混乱期において剥き出しにされる人間の本性
正直いうと、もっと戦闘場面が中心の作品かと思っていたのだが、もちろん戦闘場面は必然的に描かれてはいるもののドンパチよりもむしろ人間の心の動きを描き出す作品となっていた。その意味では、いわゆる「戦争映画」を期待していた人には物足りないかも知れない。
本作が現実社会における社会の分断を表象として、「内戦」というのは実際には極端だとしても、風刺的に描いていることは誰の目にも明らかだろう。ただ、カルフォルニアとテキサスが手を組むという現実ではあり得ない設定にすることで、単純な民主党対共和党といった構図で物語が構成されることを回避している。そして、大統領もどちらの立場なのかもわからず、だからこそ単なる一人の個人としての資質が明らかにされることになる。
さらに、政治的信条とは無関係にある程度公平な立場を取ろうとするジャーナリストや、内戦が起きていることなど知ったことではないと全くの無関心な層、さらに、内戦状態に乗じて好き勝手に人を殺している自衛団的な層なども併せて描かれることで、混乱期において剥き出しにされる人間の本性が炙り出される。
社会の分断はアメリカに限った話ではなく、日本を含めた世界各国で起きていることであり、また、実弾こそ使わないかも知れないが、容赦なく他人を傷つけ心をズタズタにするようなことばの応酬による戦いはネット上で日々繰り返されている。
本作は、初めは惨状を直視できなかったジェシーの成長譚でもあるが、我々一人ひとりが自らの心持ちをどこに置くのかを問われる話でもあるのではないだろうか。
ちなみに、邦題の「アメリカ最後の日」は不要だろう。
大嘘の切り取り方
報道カメラマン
全623件中、21~40件目を表示