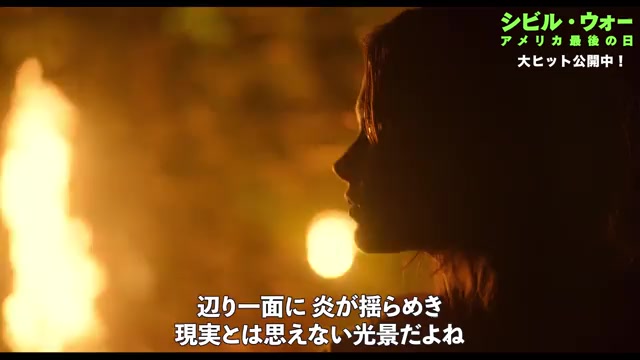シビル・ウォー アメリカ最後の日のレビュー・感想・評価
全623件中、1~20件目を表示
日常の、その先に
ふっと、倒れた兵士ではなく、草花にフォーカスが合わされる。陰惨な殺し合いが繰り広げられていても、草は風に心地よくそよぎ、花は可憐に咲く。戦場カメラマンの彼らは、銃弾を避けるため、よりリアルな画を撮るため、幾度となく身を潜める。そんな低い視線が捉えた、凡庸だが美しい光景が印象的だった。
衝撃的な予告編、大きなスクリーンでの上映で、派手なアクション映画を期待した観客は多かったと思う。(たまたまかもしれないが、私が観た回は中高年男性率が高かった。)同行者も「予想と違った…」とつぶやいていた。それでも、戸惑いながらも惹きつけられる、不思議な力が本作にはある。
舞台は、内戦で壊滅寸前のアメリカ。大統領のインタビューを取るため、主人公たちは戦線をくぐり抜け、ワシントンD.C.に向かう。容赦ない撃ち合い以上に不気味だったのは、「面倒ごとには関わりたくないの」と無関心を決め込む田舎町の人々。「今も世界のどこかで戦争をしています」という言葉を聞き飽きたと感じてしまう自分に重なり、どきりとした。そんな町であっても、銃口はごく当然に向けられる。無関心は、安全とはおそろしく無縁なのだ。
監督の過去作に「わたしを離さないで」の脚本•製作があり、なるほどと思った。東日本の震災後、おずおずと映画館が再開しても、ラインナップは明るく元気が出るものが主流だった。そんな中、ようやくあの作品に出逢えた。ためらいなく脱力し、悲しい、むなしいと感じていいんだと思えた安堵の記憶は、今も鮮やかだ。がむしゃらに進むだけでなく、こぼれ落ちるものを丁寧にすくい取る、そんな作風が、本作にも生きているように感じた。
非日常な戦争や災害の中にいても、笑い、はしゃぐのは当たり前。ただ、そのすぐ先に、何があるかわからない。だからこそ、なのか、それでも、なのか。彼らも私たちも、つかみきれない「今」に、感情を委ねずにはいられない。
予告では触れられていなかったので、主演がキルステン•ダンストだったのには少し驚いた。「スパイダーマン」のMJ、「マリー•アントワネット」のタイトルロールと、スクリーンを華やかに彩ってきた彼女。最後に観たのは、「メランコリア」だったと思う。ちょっと気難しく見える目元が、歳を重ねた熟練の戦場カメラマンという役どころにぴったりだった。ドレスもメイクもいらない!彼女を、これからも様々な映画で観てみたい。今後に期待だ。
こうならないための未来にするには
人によっては戦争映画と思うだろうし、ロードムービーだと思う人もいるだろうし、戦場カメラマンの成長譚と思う人もいるだろう。
それぐらい、見る人がどこに印象を感じたかで変わる映画だった。
「アメリカで19の州が離脱し、テキサスとカルフォルニアの西武勢力vs政府軍の内戦が起こっている」という、本当にそれだけしかわからない状態で物語は進んでいく。
内戦勃発のきっかけや、お互い何を正義として戦っているのかなどは一切わからない。
ただ、それも今のアメリカの状況を思えば致し方ないのかもしれない。
ファンタジーであればある程度理由付けもできるかもしれないけれど、今すでに存在しているアメリカの実際にある州での話となると、影響力の大きな映画は政治批判と受け取られるかもしれないし、プロパガンダと揶揄されるかもしれない。
作り手が見ている人にそう思われずに、今国内がひとつになっていない危機感だけをメッセージとして伝えたいと思ったのなら、こう描くのが一番なんだろう。
ウクライナやシリアのドキュメンタリー映画を見たことがあるので、内戦の描き方がすごくリアルだと感じた。銃社会のアメリカなので、市民が簡単に武装ができ、殺し合いができるという環境はとても恐ろしい。常にヒリヒリとした状況に、心休まる暇がない。
歴史物の戦争映画とは異なり、高層ビルや現代の風景(しかも都会)に、戦車や軍隊が進軍し、銃声が飛び交い、空には軍のヘリや戦闘機が飛び交う光景は恐ろしかった。こんな未来には絶対ならないでほしい。
あと、戦場カメラマンの人たちが、こんなに命懸けで戦場にいて撮影していることにも驚いた。
でも確かに、百聞は一見にしかずというし、聞いたことよりも実際見た光景が真実だと思うので、カメラでその瞬間の真実を記録することは、大切なことなのだと思った。
戦場カメラマンを通して見る、ifの世界線。
ひとつ間違ったら、こんな未来になってしまうかもしれないと、そうならないためにはどうしたら良いかを考えるきっかけになる映画だった。
理想と良識と常識はどこへいった?
内戦の背景などの説明がわずかであることから、さまざまな解釈を見かけた。もちろん受け手である観客自身が決めればいいとも思うのだが、自分の印象では、決して俯瞰などしておらず、非常に熱のある現代批判である。
というのも、カリフォルニアとテキサスという政治信条的には混ざり合わない二州が組んで大統領政府に立ち向かうという一見現実ではありえなさそうな設定も、「大統領が3期目」、つまり合衆国憲法(正確には修正第22条)に違反、もしくは強引な改憲をしたことが明らかであり、国の根幹を揺るがす非常事態であるとわかる。
民心が分断したというレベルでなはない。危機にさらされているのは、民主主義国家を成立させている大前提、つまり憲法であり、建国の理想であり、国をひとつに結びつける根源的な理念が壊れつつあるからこそ起きた内戦だと考えるのが打倒だろう。
ジャーナリストたちが追いかけているものも、ただのアドレナリンや興奮ではない。劇中のリーは、伝える価値があると信じていた仕事に疑いを持ったと述懐するが、リーの無力感は、信じていた前提が通用しない時代になったから生じたものだ。
現実の分断も、もはや政治的対立と呼べるようなものではない。この映画で描かれているような不条理な自体は、すべて現実の半歩先に想像できるものばかりであり、リーのように絶望する前に、常識と良識を取り戻そうと呼びかけている映画なのだと、自分は解釈しました。
武装権を認めている合衆国憲法
アメリカ合衆国の憲法修正第二条は、「武装する権利」を認めている。銃規制の議論などで度々引き合いに出されるこの条文には実際に何が書かれているかというと、「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない」とある。この条文の解釈は歴史的に議論があって、民兵を組織する権利を認めたのであって個人が銃を持つことを許したのではないという解釈と、個人が武装する権利だという解釈があって、今は個人の武装する権利と解釈されているのが一般的だ。
ただ、これは最高裁の解釈であって、解釈はひっくり返ることもある。この映画は、テキサスとカリフォルニアが武力で中央政府に挑んだことで内戦が始まったことを背景にしているが、これは民兵が政府に戦いを挑んだという状態に近く、憲法解釈としては前者に近いかもしれない。
修正二条ができたのは、独立戦争の後。当時、イギリスから独立を勝ち取ったアメリカは、人民の自由を奪う時、国は武力を持ってやるに違いない、人民の自由を守るためには武器を手放すべきではないという論調があった。国が人の自由を奪う時は、民兵が立ち上がってこれに抵抗することを保障するための条文が修正第二条だ。
本作で大統領や政府が何をしたのかわからないが、これに対抗して武器を取ることを憲法が保障しているのがアメリカという国なのだ。
つまり、憲法解釈によっては、この映画のような事態が起きることを保障している国と言える。元々、イギリス相手に武力で独立と自由を勝ち取ってできた国なので、武力行使と自由が密接に結びついている国なのだ。
何がアメリカ人民の自由を脅かすのか、この映画はそれを直接描いていない。現実にその火種はたくさんあるので、見る人によってそれこそ「解釈」が変わるだろう。火種がたくさんあるから、このような内戦の勃発は決して絵空事ではないと思わせる。何せ憲法で保障されてるし。
ちなみに、テキサスとカリフォルニアは、全米の州兵で最も強いトップ2と言われている。この2州が手を組んだら、本当に政権転覆できるかもしれない。
状況と瞬間を濃密に焼き付けた一作
冒頭、スピーチ練習をする大統領の言い回しには、かの元大統領を思わせるものがあるし、この映画の挑発的設定がいくらかリアルに感じられるのも、我々の脳裏に議事堂襲撃事件が鮮烈に刻まれているからだろう。だが、結論から言うと本作は特定の人物や党を連想させることなく、あえて事の経緯は曖昧なまま、分断の果てにある状況そのものを描き出す。と同時に、これは世界各地の紛争を我が身に置き換え体感する映画でもあるのだと感じる。そのカオスを分け入るロードムービーの動線を担うのは銃の代わりにカメラを構えたジャーナリストたち。一つの車に同乗する性別、世代の異なる彼らは時おり疑似家族のように思えたりも。はたまた感情豊かな新米と冷静沈着なベテランの対比は一人の写真家の出発地と現在地を集約させているかのようだ。世にある歴史的瞬間を記録した一枚に写真家らの姿はない。その切り取られた世界の外側や背景を自ずと想像させる秀作である。
「お前はどの種類の日本人だ?」への正解を想像できるか
アレックス・ガーランド監督には「エクス・マキナ」や「アナイアレイション 全滅領域」などSFの印象が強かったので、新作が内戦を題材にしたアクションスリラーと聞いて意外に感じたものだ。だが実際に見ると、この「シビル・ウォー アメリカ最後の日」も米国の政治的社会的現状を客観的にふまえつつ、近い未来にもし内戦が勃発したらどんな戦闘や混乱が起こり得るか、それをジャーナリストが取材しようとしたらどんな行動をとるのかといったことを、出来る限りの科学的な正確さでフィクションとして描くという点で、広義のサイエンスフィクションと呼んでもよいのではと考えを改めた。
それにしても、ガーランド監督(脚本も担当)と製作会社A24の機動力には恐れ入る。2020年米大統領選の不正を訴えた当時現職トランプの過激な支持者らが米国議会議事堂を襲撃したのが2021年1月。それが映画の直接的な出発点ではないにせよ、インスピレーションの1つにはなったはず。ガーランドとA24は2022年1月までに契約を交わし、次の大統領選が行われる2024年の4月に米英での公開にこぎつけた。
映画では、連邦政府から19州が離脱し、テキサス・カリフォルニアの西部勢力が大統領側の政府軍と武力衝突を繰り広げていると説明される。赤い州(共和党支持)のテキサスと青い州(民主党支持)のカリフォルニアを組ませた点が脚本のしたたかさ。大統領選の年に公開されたことも考え合わせると、もし反政府勢力が赤い州か青い州のどちらに偏っていたら、本作が政治的プロパガンダだという非難をまず間違いなく浴びていただろう。そうしたリスクを回避するための戦略的な設定だと考えられる。
民間人の遺体を処理する武装集団のリーダー的存在、赤いサングラスの男を演じたジェシー・プレモンスは短い出演時間ながらも強烈な印象を残す。予告編にも使われている、ワシントンDCに向かうジャーナリストたちに向かって「お前はどの種類のアメリカ人だ?」と問う台詞が、米国の分断の根深さを象徴している。
昨年公開の「福田村事件」で描かれた、香川から関東を訪れていた行商の人々が、朝鮮出身者ではないかと村人たちから疑われる場面が思い出される。近い将来、日本でまた大規模な災害と大混乱が生じ、自警団とそれに追従する人々が似たような暴走を起こす可能性がまったくないとは言えない。そんな状況で、「お前はどの種類の日本人だ?」と問われたら、果たして何と答えるのが正解なのか。そんな想像をすることで、この「シビル・ウォー」がよりリアルに迫ってくるだろう。
ケイリースピーニーの進化!
戦場カメラマンが出来るまで?
迫力ある戦闘シーンとスローモーションで写し出される破壊の炎。
動と静の芸術的な対比。
背景や理由が極力排除されているため内戦の発端はよく判りません。
主人公の戦場カメラマンと記者が所属する報道機関の無事も判りません。
写真を売る先が果たして残っているのか?
内戦の進行に伴って、大統領を仕留めるためにワシントンDCに向かう反乱軍と随行する戦場カメラマン、記者を描いた一種のロードムービーです。
あまりにもシンプルにただ出来事だけが描かれているので、何が伝えたいことだったのか理解出来たたとは言えません。
ただ一つ、印象に残ったのは若い見習い?カメラマン、ジェシーです。
彼女のせいで何が起こったか?
それを彼女は撮っています。
そしてその写真は公表されるのでしょう。
その写真は手柄か?
愚かな行為で他人を犠牲にして手に入れた栄誉ではないのか?
それは彼女の師的存在のベテラン戦場カメラマンが最後の戦いで動揺するのは、彼女自身も他人を犠牲にして名声を手に入れてきた半生が視えてしまったせいではないか?
そして更に、ベテランカメラマンのそのまた師も同様に…
物語の後も世界が続くならば、恐らくジェシーは将来、戦場カメラマンとして名声をはせるのでしょう。
それがこの映画が伝えたかったことか判りませんが、これまで思ったこともない視点を得た気がして印象に残りました。
アメリカの内戦の話だということで、派手な戦闘シーンを期待して見てみ...
めちゃくちゃつまらなかった
ネタバレなし
戦争映画ではないです。多分監督、脚本のオナ映画だと思います。
まず主観が兵士じゃなく記者です。
戦闘シーンが見たければ他の映画の方が断然良いです。
CODのキャンペーンモードの方がはるかに面白い。
意識を切り替えて記者としてみても特段何を見させられてるのか理解できない。
途中つまらな過ぎて寝てしまったが、なんで内戦してるのかもわからない。
それぞれの思想やそれぞれの正義と悪、みたいなのもない。
戦場記者として描きたいのであれば現実のアフガンとかを題材にしてた方がよっぽど理解できる。
わざわざ架空のアメリカを描くかは最後まで理解できない。
・とにかく何が言いたいのかわからない
・挿入歌とそのタイミングがゴミ
・終わりが唐突過ぎてイミフ
・現実のアメリカと照らし合わせてもあり得ない、意味わからないことが多い
・最後以外の銃撃戦がサバゲーレベル
・現実の戦争と比較して人質射殺などが現実離れしすぎの部分がある、とくにラスト
・仲間は死んだけどラストは射殺してみんなで記念撮影ピース✌ハッピーエンド、全然理解できない
・結局何が伝えたいのかわからない
・そもそもなぜ反政府勢力が勝利したのかもわからない。
戦場に身を置いてみるということ
いやぁ、すごい映画だった。久々に米国映画の底力を見せつけられた。近未来映画といってもいわゆるSF的要素は無く、一昔前の第三次世界大戦ものみたいとでも言うべきか、要するに一種の架空戦争映画だが、戦争を娯楽的またはシミュレーション的にとらえたものでもなく、南北戦争(英語ではAmerican Civil War)以降本土が戦場となったことのほぼ無い米国が戦場の狂気を疑似体験してみるといった感じの映画。実際にガザやウクライナでも行われているであろうような、目を背けたくなる戦場の恐怖と狂気がこれでもかと描かれていく。音響も素晴らしく、銃声や爆発音が鳴るたびにビクッとしてしまった。ところどころで流れるロックやヒップホップなどの音楽も印象的で心に残る。
主演の戦場カメラマン役のキルスティン・ダンストはいい女優になったなあ。もうすっかりおばさんで中年体型になりながらも、それすらも魅力に変える演技派ぶりを遺憾なく見せてくれている。初見はたぶんドラマ『ER 緊急救命室』でのゲスト出演だったと思うが、まだ10代の可愛い少女ながら抜群の存在感を見せていた。その後、『スパイダーマン』シリーズでの大ブレイクを経て、実力派若手スターから今ではすっかりベテラン女優になりました。そして彼女に憧れる新人カメラマン役の若手女優ケイリー・スピーニーって子も良かった。今後、要注目かな。ラストがややあっけなくて少々拍子抜けなのがちょっとだけ残念。
シビル・ウォー アメリカ最後の日 Dolby Atmos鑑賞
キルスティン・ダンスト老けたなぁ〜
サブタイトルの失敗例
【追記④】2025.10.13
シビルウォー:内戦、アメリカでは南北戦争の事を言う。この戦争があった為、ペリーが江戸幕府を無理矢理こじ開け開国を迫ったがその後日本に対して干渉しなくなったのである。60万人以上が亡くなったとされる米国が関わった戦争の中で最大の死傷者となった戦。しかしこの作品はそこまで大規模では無い。もし本当に南北戦争のようになったなら、戦術核が使われるだろう…⁈ ……だからこの作品を観る前はそんな事を想像してしまったのだ。特にサブタイトルの"アメリカ最後の日"はそんな事を連想させるのでこの日本語サブタイトルは好きでは無い‼︎……と言うより無い方が断然良かった‼︎
【追記3】2025.4.8
あり得ない3選(米国憲法で禁止されている)の前に内戦となる可能性が段々と大きくなって来た。否、内戦の前に他国との戦争になるかも知れません…。。 トランプは全世界に対して相互関税と言う "ケンカを売った" 売ってしまった。国対国と言うのは"ディール"(取引)では無い。何故なら決して商売では無いので。持ちつ持たれつの関係であると思う。それが隣人との関わり方なのだ!
トランプは全く歴史から学んでおらず戦前のフーバーの保護主義失政の二の舞いとなる。今のままでは貿易戦争から実際の戦争とならない事を切に願う。イヤその前に流石に米国民も気付くか…⁉︎ が、問題だ‼︎
【追記2】2025.2.28
いよいよこの映画が現実味を帯びてきた…トランプとその側近達が国家憲法まで変えて3選に挑むのでは…と噂され始めている。。 この映画とは対象的である"アプレンティス"も観たがあり得る話しである(それは観たからこそ、そう思えてしまう)。そしてある意味、米国とイスラエル以外には恐怖でしかない…なぜなら米国第一主義なので米国だけ良ければ他国はどうなろうと構わないので。あぁ恐ろしい… 本当に恐ろしい…
【レビュー】 2024.9.26
まず現在の米国は以前にも増して分断された国となっている。その構図は白人対非白人、保守対リベラル、格差拡大、犯罪率の高さ等様々な要因により病める大国となっている。そんな中で銃社会である米国はいつ反乱が起こってもおかしく無い世界とも言える。だからこのような内戦が絵空事ではないのだ。
先行IMAX上映が限定館で行われ鑑賞した。本編では内戦になった直接的な説明は無い。視点は飽くまでジャーナリスト目線で物語は進む。戦闘場面は凄いのひと言だが途中、中だるみするシーンが結構な尺あり緊張は持続しない。観ているとツッコミ所満載でもう少しリアリティを追求して欲しかった… 特定の党を名指ししたく無いのだろうが、まずカリフォルニア州とテキサス州は絶対に手を組む事はない(なぜなら青の州と赤の州だから)。こういう作品を観たい訳ではなかったのだよ… またしても期待し過ぎてしまった感が否め無い。しかしこれは製作側の問題では無く観るこちら側の問題である。また鑑賞中に斜め後ろの席のお兄さんが席を揺らす?貧乏ゆすり?で絶えずシートが微妙に揺れていて最悪の環境であった事も影響したかも…
A24の作品なのでやはり怖い映画である事は間違い無いのでその点は保証します。
【追記】 2024.10.14
日本版副題の「アメリカ最後の日」は余計ではないのか⁇ 観る者は全く違う内容を想像してしまうので…
戦争の悲惨さ
バックグラウンド情報はなしで、内戦の終盤戦から物語が始まるというかなりの攻めた導入。
全623件中、1~20件目を表示