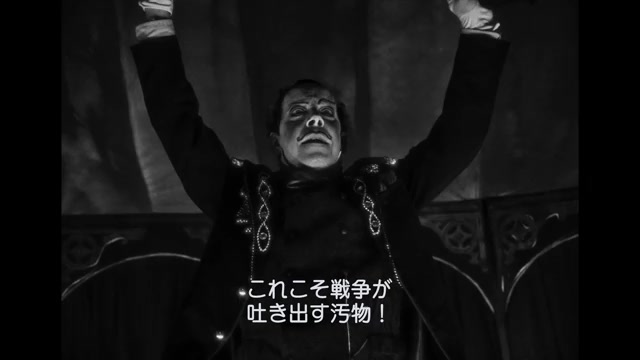ガール・ウィズ・ニードルのレビュー・感想・評価
全109件中、81~100件目を表示
善いことをしましたね!
キャンディーショップの女主人が赤ちゃんを預かって。母親を送り出す時の決まり文句。善い事をしましたね!
ストーリーが進むうちに、この言葉の悍ましさが。ジリジリと刺さってきます。
見ぬもの清し。母親には金持ちの里親という夢を与え。
水面下の汚れ仕事を引き受ける。仕掛人藤枝梅安に比するともいえるか。
しかし極悪人に限って始末する梅安と幼気な赤子を扱うのでは大いにギャップが。
しかし国も時代も変わったとしても。その時々、折々で社会の矛盾を請け負う人らは常にいたのだろう。
そして。どれだけ後味の悪いバッド・エンドが有るのか?ビクビクしながらラストを迎えると!しっかり救いのある結末で。心底ホットします。
心と体のエネルギーが充満してへこたれないタイミングで鑑賞してください。
実在の犯罪であったことが恐ろしい
不穏な雰囲気を漂わせる予告に惹かれて、公開初日に鑑賞してきました。観客は中高年のおひとり様ばかりの10名程度で、まあそうでしょうねという感じの客層です。
ストーリーは、第1次世界大戦後のデンマークで、夫が戦争から戻って来ず、貧しい生活を送っていたカロリーネが、職場の上司と恋仲になるも土壇場で捨てられた上に職場も追われ、すでに上司の子を妊娠して途方に暮れていたところに、養子縁組の斡旋をしている女性・ダウマに声をかけられたことをきっかけに、カロリーネは産んだ子をダウマに預け、自身もダウマの家で世話になることになるが、そこである重大な秘密に気づいてしまうというもの。
本作は、デンマークで実際にあった犯罪を題材にしているようで、なかなか重い話です。それをモノクロで鮮烈に描くことで、人間らしい優しさやゆとりも潤いもない、空虚な心と生活を表しているかのようです。さらに、そこに不穏なBGMを加え、観客の不安を煽ります。
展開は予告からある程度予想できたものでもあり、意外性は感じません。明らかに怪しい振る舞いを見せるダウマがやはり…という展開ではあるものの、むしろ事件発覚後の裁判での彼女の態度のほうに驚かされます。全く悪びれる様子もなく、自分は正しいことをしたと言ってのけます。そして、それが開き直りではなく、心の底からそう思っているように見えます。
一方で、そんなダウマを一斉に糾弾する女性たちの姿にさらに驚かされます。理由はどうあれ、我が子を育てられず、かといって自分の手を汚すこともできず、体よくダウマに赤ん坊を引き渡した母親たちに、ダウマを責める資格はないと思います。その心情を理解できなくはないですが、言いようのない憤りも感じてしまいます。彼女たちになりかわって、ダウマは汚れ仕事を引き受けていただけだと言えなくもないです。
しかし、もうすこし視野を広げれば、苦悩する女性を簡単に切り捨て、こんな状況をつくり出した男たち、それを容認していた社会こそ、責められるべきではないでしょうか。これは、”そういう時代だった”と簡単に片づけていい問題ではないと思います。望まぬ妊娠に苦しむ女性は今でもあとをたたず、現代にも通じるものがあると思います。堕胎にしろ未婚の母にしろ、女性だけが責任と苦労を負わされるような社会について、もっと真剣に考えなければいけないと思います。
キャストは、ビク・カルメン・ソンネ、トリーヌ・ディルホム、ベシーア・セシーリ、ヨアキム・フィェルストロプら。知らない俳優さんばかりですが、厭世的な雰囲気が漂う演技が、作品にマッチしています。
なかなか辛すぎる作品でしたが─
鑑賞動機:あらすじ10割
あらすじもさらっと見ただけで、あまり吟味せずに観たけども。
ポーランドと思い込んでいたけど、デンマークなのね。ヨーロッパで公衆浴場のイメージがなかったので、へー、となる。
序盤、ストーリーの方向性がかなり変わるのでまごつく。結構大きなネタをかすめてかすめて「本題はそこか」と腑に落ちるまでは困惑してた。
なんかこううまく引っかかりが持てず。
【”歪んだ倫理観と母性が惹き起こした事により、蘇った母性。”今作は重く、暗く、哀しく、恐ろしい物語であるが、ラストシーンで示される蘇った母性の尊さと人間の善性に未来を感じさせる作品なのである。】
■第一次世界大戦後のコペンハーゲン。戦いに出た夫は消息不明で裁縫工場のお針子として働くカロリーネ(ビク・カルメン・ソンネ)は、アパートの家賃が支払えずに、それまで住んでいたアパートを追い出され、ボロッチイアパートに引っ越していた。
だが、彼女は裁縫工場の工場長で男爵家のヤアアン(ヨアキム・フィェルストロプ)と恋に落ちるも、ムッチャオッカナイ彼の母親から拒絶され、工場も首になってしまう。
すでにヤアアンの子を妊娠していた彼女は、もぐりの養子縁組斡旋所を経営し、望まれない子どもたちの里親探しを支援する表向きダウマ砂糖菓子店女性ダウマと堕胎しようとした浴場で出会い産み落とした子を彼女に預ける。
そして、カロリーネは預けられた子の一時的な乳母の役割を引き受け、ダウマとの間には絆が生まれていく。だが、彼女はダウマが行っていた旋律の事実を知ってしまうのである。
<Caution!内容に触れています。>
・モノクロームで始まるこの映画の冒頭で、様々な男女の歪んだ笑い顔や泣き顔や叫び顔が次々と登場する。非常に気味が悪い。そして、この映画もダークテイスト溢れる中で進んで行くのである。
・カロリーネの夫が彼女が仕事終わりに戻って来るシーン。彼の顔には金属のマスクが装着されている。彼女は夫を家に連れて行き、食事を摂らせるが、食事中にヤアアンとの関係を告げ、家から追い出すのであるが、ダラシナイ、ヤアアンにより彼女は男爵家の嫁の地位も職も失うのである。
・ヤアアンの子を妊娠していたカロリーネが公衆浴場で裁縫張りで自らお腹の子を堕胎しようとするシーンは思わず”ウワワ、デンマーク版”あのこと”かよ!”と思う程、嫌であるし、痛そうである。だが、そこに現れたダウマは素早く処置し、彼女を保護し、その後彼女が炭坑工場で陣痛に襲われた時も適切に赤子を取り上げて上げるのである。
ー ここまでで、私は完全にカロリーネが犯人になって行くのだと、ミスリードされる。-
■だが、カロリーネがダウマの家に招かれた時に、映し出されたダウマのフルネームの表札で、真実に気づくのである。
だが、ダウマはカトリーネと仲良くなり映画に行ったりするが、彼女は情緒不安定で涙を流している時にエーテルを水に入れて飲んでいる。で言う言葉”これを飲むと、気が休まるんだよ・・。”いやいやいや、エーテルは危険ですから。飲んだら駄目だから。だが映画館でカトリーネにもエーテルを飲ませ、笑いだす二人。ダウマの神経が病んでいる事が分かるシーンである。
・カロリーネがダウマが、預かった赤ちゃんをベビーカーに乗せて、裕福な家に連れて行くのを追いかけるシーン。あのシーンは怖かった・・。ダウマはその前に言っていた。”子が出来ても何度も流産していた・・。”
そして、捕らえられた彼女が法廷で言い放った言葉”アンタたちの代わりにやってあげたんだよ!感謝して欲しいくらいだ!”ダウマの歪んだ倫理観と恐ろしい母性が明らかになったシーンである。傍聴席でその言葉を聞いていたカロリーネの驚愕の表情。
<そして、施設に入れられていたダウマの所にいたカロリーネに懐き、彼女の母乳を飲んでいた女の子を、カロリーネが引き取りに行くシーン。
現れた女の子は、カロリーネの姿を見ると駆け寄って抱き着き、カロリーネも女の子を強く抱き締めるのである。
今作は、重く、暗く、哀しく、恐ろしい物語であるが、ラストシーンでカロリーネの蘇った母性と善性に微かなる未来への希望を感じさせる作品なのである。>
下手なホラーより怖い
望まれない子
WW1終戦後のコペンハーゲンで秘密裏に養子縁組の仲介業をする女と、自身が産んだ赤ん坊が切っ掛けでそこの世話になる女が知った闇の話。
終戦間近、夫が行方不明になり家賃を滞納して家を追い出された女が、自身の働く縫製工場の社長と良い仲になって巻き起こっていくストーリー。
突然帰ってきた夫を追い出し、社長に妊娠を告げて結婚かと思いきや、ママの登場であっさり捨てられ…と展開して行く。
ていうか、公衆浴場で公衆欲情ですか?
この当時の女性が1人で行きていくのは難しいのはわかるけれど、カロリーネはなんだか寄生思想がチラホラ…そして自己中な感じも。
そしてドライにみえてなんだかんだ面倒見の良いダウマは実は…というところから、倫理観と現実とそれぞれの正義の形みたいなものをみせる流れ。
言いたいことはわかるし、一応最後は問題提起みたいな取り上げ方になってはいるけれど、カロリーネの人間性や話しの進め方から、問題提起というよりも単なるショッキングなドラマにみえてしまう。
それにこの展開は想像ができてしまうから、ドラマとしてみせて終わりだとちょっと弱かったかな。
あっ、現在はエーテルなんか飲んじゃダメだからね。
歪んだ坂道に背筋が凍り付きます
映画館で知り合った方からお誘いを受けて試写会に行って参りました。
もはや正気の沙汰じゃありません。
映画自体が凶器です。(褒め言葉)
人によっては刺し殺されるような衝撃を受けてしまうと思います。
描写に関してはドギツイ表現はほとんどないのですが、白黒映像で綴られる「悪意」を感じ取った人にはかなり衝撃的な作品になるのではないでしょうか。
とはいえ、上映後のインタビューで監督も答えていましたが、映像を白黒にし、ドイツ表現主義の作品を参考にしてセットを歪ませ、果てはお伽話からも着想を得るなど、現実と映画の中の虚構にきちんと境界線を設けています。
それを感じ取れた人ならば本作の映像が持つ説得力を存分に味わう事ができたのではないでしょうか。
濃淡のみを追求したシーンなどは目を見張る出来映えでした。
勿論、ロケーションの選び方も秀逸。
中でもダウマーの菓子店に向かう坂道がとんでもない!
左右に歪んでいる石畳みの坂道が観る者に不安を与えてきます。
ダウマーが乳母車を押して下っていくシーンでは恐怖すら覚えます。
乳母車が下るというだけで「戦艦ポチョムキン」も頭を過り、更に背筋が凍りました。
導入直後、主人公を共感できない人物として描いた点も良かったです。
子供に「ネズミが出る」と言って脅し、負傷兵の夫に「出ていけ」と叫ぶ姿から「自分勝手な主人公だ」という考えが頭の中で増殖してしまうのですが、ある事をきっかけに彼女の中で変化が起こり、ラストシーンへと集約されていきます。
救いがない実話を虚構として描き、綺麗に纏めた見事なラストシーンだったと思います。
貧困と尊厳
今の自分なら色々言えるが、同じ立場だったらどうだろうか・・・。
主人公は貧困、無教養、世間知らずの3拍子が揃った23才の未亡人?
晩年のアルパチーノ(まだご存命だけど)を思わす風貌だけど、あちらでは美人なのかな。
闇で養子斡旋をしている女性は主人公女性の面倒まで見るなど、心底困っている人を助け正しいことをしていると考えているが、裁判であの女性を責めた母親たちが多かったことの方がより驚かされる。
主人公同様に面倒見れきれなかったから預けたのではないのか。
ただ本作に登場する女性たち皆を一様に責める事はできず、モヤモヤした感じで映画館を出る、そんな映画でした。
またモノクロってあんなに清潔感がなく見えるものなのかと何となく思いました。
子を生すことが女にとっての罪業となるのか?
夢に出る。
正しいことをした
合わなかった。この美しく撮影された陰鬱な寓話にハマらなかった。期待していた作品とまるで違った。(社会的に搾取される職業としての)お針子たちが消えていって社会における女性の立場の弱さや構造上の問題を突きつける作品かな…なんて思っていたら、早々に替わるし全然違った。ただ、象徴的なファーストシーンから強烈に引きのある画が続き、心に棲み着きそうなこと請け合い。
"裕福で善良な人々"。縫製工場長の金持ち坊っちゃんに旦那、そして口の裂けた赤ちゃんと、男性キャラの肉体的損傷や欠損、障害といった要素(=サーカスという見世物"バケモノ")はどういうことだろうか?なぜ消す必要があったのだろうか?戦時下・戦後と、出兵により男性が減ったであろう時代=女性にもさらなる負担がかかった時代において望まれぬ命。日々生きるのでやっと精一杯で、他の命にまで責任取れないかもしれない。目障りに思って命を奪おうとまでしたり。ただ、それでも…。
↑↑↑↑↑
【鑑賞前期待コメント】
この第一次世界大戦後のデンマークを舞台にしたゴシック・ミステリーは、独特な雰囲気に呑まれるような予告だけでも目が離せず興味をそそられる!白黒映像美の撮影に美術、音楽・音響と期待。そして、タイトル通り、歴史的に女性のイメージが強いお針子という職業の主人公からして、きっと広く観られるべき社会性が本作にはあると確信している。
「あんな悲惨な時代だったから仕方がない」で済ませてしまって良いのだろうか?
最初の頃は、誰が主人公で、どんな話なのかがよく分からない。
やがて、勤め先の御曹司の子供を身籠り、戦争から傷痍軍人として帰還した夫に「出て行け」と言い放つ女性が、主人公であると分かるのだが、余りに自己中心的な振る舞いのせいで、中々感情移入することができない。
案の定、御曹司から捨てられた主人公が、サーカスの見世物になっている夫とよりを戻し、出産した子供を養子の仲介者に託すところで、ようやく、どんな話なのかが分かってくるものの、ここまで、プロローグとしては長過ぎるのて、もう少しテンポ良く描けなかったものかと思ってしまった。
物語のポイントとなる養子の仲介にしても、「闇」でやっていて、しかも、子供を預ける側から手数料を徴収している時点で、その実態が容易に想像できてしまい、それが明らかになっても、さほど驚きを感じなかった。
ここでも、案の定、悪事がバレて、乳児たちを殺めた犯人は逮捕され、裁判にかけられるのだが、その一方で、主人公に何のお咎めもないことには、どこか釈然としないものを感じざるを得ない。
例え、知らなかったとは言え、主人公は、乳児の殺人に明確に関与していた訳だし、麻酔薬のせいで意識が朦朧としていたのだとしても、主犯の女性と共に、1人の乳児を死に至らしめたのも確かなのである。
「子供は宝だから絶対に手放すな」と言っていた主人公の夫が、終盤、子供を手放したことを「それが一番だ」と言ったことにも、今一つ納得することができず、ここは、身勝手な主人公を非難するような一言があっても良かったのではないかと思ってしまった。
悲惨な物語の末に、主人公が、同居していた少女を養子として引き取るラストからは、仄かな希望が感じられて後味は良いのだが、その一方で、「あんな時代だから仕方がなかった」という理屈で、主人公のすべてが許されてしまったかのようにもなっており、「本当に、それでいいの?」という疑問も残った。
映像美に呆然とする2時間
夫は戦場へ行った
モノクロといい、第一次大戦といい、かつての名作を彷彿させられました。カロリーネが帰って来た夫に向かって、「出て行け!ここから出て行け!」と怒鳴り散らしたのは、これから始まろうとする、救われる人生の為(私はそう思いますが)なのが、癒されの想いを持ちました。
全109件中、81~100件目を表示