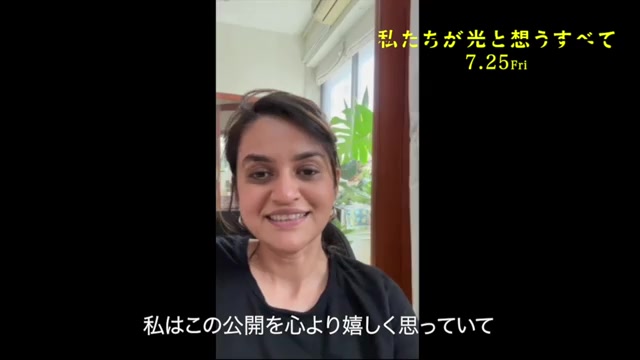私たちが光と想うすべてのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
ムンバイに生きる市井の女性の心模様を繊細に綴る日常系インド映画
オープニングからの数分、湿度を感じる雑踏とそこで生活する人々の数節の言葉で、訪れたことのない街ムンバイのイメージが胸の奥に広がった。
日常系インド映画とでも言おうか。説明的な台詞を極限まで排した脚本とキャストの自然な演技には、パヤル・カパーリヤー監督がこれまで手掛けてきたジャンルであるドキュメンタリー映画に通じる雰囲気が漂う。
現代インドの女性たちの生活文化や恋愛観をほとんど知らなかったので、新鮮に感じる場面が多かった。
考えたら自然なことだが炊飯器を使うんだなあ、とか(ちなみに90年代にインドに炊飯器を普及させたのはパナソニックだそうだ。それまではガスか薪で炊いていた)、好きな相手にお菓子はともかくポエムを贈る男性って、インドの女性にはウケるのかなとか。
彼女たちの置かれている環境も社会的・宗教的背景も私自身とは随分違うのに、彼女たちが抱く感情には不思議なほど垣根を感じなかった。
その理由は、特に主人公のプラバについて顕著だが、彼女の心の揺れについての説明的な描写がほとんどないからだと思う。彼女が働く姿、アヌの態度や炊飯器を抱く姿を見て観客はプラバの心境を想像する。もちろんそういった描写には監督の意図が内在するが、観る側の想像と解釈の余地が大きいということは、そこに観客自身の価値観が映り込みやすくなるということであり、垣根を感じなくなるのは自然なことかもしれない。
一方、奔放なアヌの行動についてはちょっとハラハラさせられた。ヒンドゥー教信者がムスリムと交際することは社会的にNGのようだったが、どれほどのレベルのタブーなのか、アヌの様子だけでは測りかねた。親から交際を反対されており人目を避けてデートしていることはわかったが、割とオープンな場所でキスしたりもしてたし……インドの観客ならこの辺は肌感で理解するところなのだろうか。
タブーレベルに迷いながら観ていたので、終盤ラトナギリの海岸で誰かが救助された場面では、もしかしてアヌとシアーズ(アヌの彼氏)が心中したのだろうか、実は二人ともそこまで思い詰めていたのだろうかと嫌な想像をしてしまった(もっともイスラム教では自殺は禁忌らしいので、これは見当違いの予感だったのだろう)。
この遭難者、当初はプラバと全く面識のない男性なのに周囲が夫と勘違いしている、という様子だったが、いつの間にかプラバは彼と夫婦として対話していた。この辺、観ている間は正直よくわからなかった。あれ? さっき勘違いされてるとか言ってたよね? ドイツから戻ってきてたの?
恥ずかしながら後でパンフレットのコラムを読んで、このシークエンスが「幻想」だったことを確認した次第だ。ここはもうちょっとわかりやすくしてもらってもよかったかなと思う(読解力のない人間の勝手な言い分です)。
とはいえ、それまで社会的な慣習に押し付けられた形だけの結婚に甘んじてきたプラバが、この対話で自らの状況にようやくキッパリNOと言えたことはよかった。
彼女は、職場の医師にフランクに接するアヌを「誘惑している」と非難したこともあったが、後で思えばそれは彼女自身が、自分を抑圧する古い価値観に無抵抗になってしまっていたことの表れだったのではないだろうか。
ラストでプラバはアヌとムスリム彼氏の交際を受け入れ、カラフルなイルミネーションに彩られた海辺の店でスタッフの子が踊る(典型的インド映画とは別系統の作品とわかっていても、インド映画のDNAに触れたような謎の安心感)。自己肯定と受容が重なりほのかにあたたかい気分になるエンディング。
ひとりの女性の小さな心の成長をたどる繊細なドキュメンタリーを見たような気持ちになった。
素晴らしい映画だった。
良作と聞いていたので、期待して鑑賞。
期待以上に素晴らしかった。
インドの昔ながらの習慣に自分の道をふさがれそうになる、アヌとプラハ。
看護婦の同僚として働いているが、それぞれの道を行く。
アヌはイスラム教徒と恋人関係にあるが、異教徒との付き合いということで周囲の目は厳しい。その中でも自分の道を模索し、あの洞窟に行き、新しい自分になっていく。この風景は素晴らしかった。
一方、ドイツに働きに行ったきり音沙汰のない夫(家族の勧めで結婚させられた)のいるプラハの方は、マジーノというDrからとても奥ゆかしい詩や言葉を贈られるが、結局断ってしまう。そして田舎にパルヴァティを送って行ってるときに偶然海でおぼれた夫を救急医療で蘇生させるが、結局夫とも別れる。
そしてラストの自由にあふれた素敵な景色。
この先のインド女性の未来を描いているような、素敵な映画だった。
よかった
演技とは思えない自然さで、場面も本当にその場にいるかのような臨場感で、インドのムンバイにいるようだ。コンディションの調整に失敗して中盤海辺の町に行く手前でウトウトする。自立した女性ばかりの話で、女性がひどい人権侵害を受けてなくてほっとした。ただ、海辺の町で泊まっていけというから泊まると床で寝かされるし、家自体がバラック小屋のようだし、蚊がいそうでつらい。自分が若い時ならそんな環境も楽しめたかもしれないけど、もう年寄りだから嫌だ。布団かベッドで寝たい。お酒を飲んで夜の9時に寝たい。
インド映画の新しい傑作
ケララ州は教育に熱心で都会に行く若者が多いが、主人公と後輩の看護師とイスラムの恋人、同僚医師はケララ州からムンバイに出てきた優秀な人々のようだ。
キスシーン、着替える場面、ドイツ製炊飯器に足を絡めるシーン等性的な描き方はフランス共同製作だから可能になった面もあるが、濱口竜介監督のドライブマイカーに影響を受けているとも言えると思う。
多言語国家、トイレ問題、宗教と婚姻の問題、等インドが抱える課題を盛り込んでストーリーが進む。
舞台となる病院は堕胎手術専門のようで、胎盤、パイプカット、等の精神的に辛いシーンが続き、娯楽はダンス映画鑑賞が描かれる。
主人公はドクターや新人ナースから信頼されている一方、堅苦しく付き合いの悪い、勃起した患者をしっかってEDにしてしまうような人格と笑われている。
同居する後輩ナースの奔放な性格に主人公が徐々に変化して行く。
猫の妊娠をドクターと検査し、その後怒りの感情を唯一発散する場面と謝罪するシーン以降は対等な関係になって行く。
同僚のドクターからノートに書かれた詞とお菓子で告白されるが返事のシーンが無く、ディレクターカット版が公開されたらその後の二人の関係が描かれていると思う。
主人公がドイツへ電話した時に女性のアナウンスが流れ、この電話は現在使われていないようだ。
富裕層はベンツ、貧乏人は日本車と対比される。
あえて他言語で撮る監督もいて、ネイティブな言葉の細部にこだわりすぎて作品のテーマが曖昧になるのを避ける意図があるそうだが、本作はヒンディー語、マラヤーム語、マラーティー語の三言語で描かれているとも言える。
ケララ州の名監督、アラヴィンダンとゴーパクリシュナンの作品は幻想的なストーリーが盛り込まれていることが多いので、主人公が人工呼吸で救った男と夫が重なるシーンは両監督の影響があると思う。
主人公の表情がガンダーラ仏像と敦煌壁画のように見える。本作のテーマと主人公を演じる俳優が持つ雰囲気がピタリとはまり、傑作が生まれている。
ムンバイと東京、幻想、光
すごく良い映画だった。
人が多くて仕事がある都会、ムンバイと今わたしが住んでいる東京という街がリンクして、異国の風景を見ながらも自分と重ね合わせて見ることができた。
「『どんなにどん底の生活でも気張ってやっていく』それがムンバイの気概だ」
「幻想をみていなければおかしくなる」
※セリフはニュアンスで正確では無いと思います
私が好きな青森のねぶた祭りと重なって見えたお祭りのシーンも、村の海と似ている東北の海辺の風景も、私にとっての生きていくための幻想。
遠くにいるパートナーを想うことは光だけれど、迎えに来られて「来てくれ」なんて言われたらそれは光ではなくなってしまう。私には私のキャリアと人生があるし、遠く離れているからこそ想えるのであって、近くにいたらそれは現実になって苛立ちや困難に変わってしまうから。
久しぶりに映画館で登場人物の恋愛感情にも共感することができました。
私たちは光を感じ幻想を抱えながら生きている。私にとっての光や幻想ってなんだろう。
そんなことを考えながら帰る素敵な夜をもらいました。ありがとうございました。
作品情報の写真の意味
作品情報の写真は炊飯器を訝し気に見ているシーンだったのかと映画を観始めて分かり、可笑しかった。ヒロインらのやりとり、夜景とBGMが心地よかった。色々辛いことやめんどくさいことあれど、最後の4人でテーブルを囲むシーンで一息という感じで良かった。閉館予告のシネマカリテで観ることできたのも良かった。
ムンバイで生きる
ムンバイの女性達を描いた作品、に惹かれての鑑賞。( フランス・インド・オランダ・ルクセンブルク合作。 )
女性達の生き辛さを、ムンバイで看護師として働く2人の女性視点から描く。冒頭の混沌としたムンバイの空気感、女性達のやるせない表情が印象に残る。
エンドロールの楽曲が素敵でした。
映画館での鑑賞
外国の今の異文化をこういう映画で知れるのもいい
いつもの映画館で夏休みに
チラシと予告編で興味がわいた
カンヌのグランプリ 是枝監督のお墨付きだし
インド映画だけど踊らないというし
で うーん自分が好きな感じとは微妙なズレ
バスで送別を兼ねていきとことかはよかった
酔っぱらって2人が踊るところも
外国の今の異文化をこういう映画で知れるのもいい
ラス前の海岸からのエピソード いまひとつ飲み込めず
ん まぼろしなのか現実なのか
上映終了後 廊下の雑誌記事の切り抜き ふたたび
監督のインタビューを読んで あぁなるほどと
終了後は球場まで1時間歩いてナイター観戦
負けたけどいい試合で満足
心の中で描く「光」は、いずれ現実を変える火種へと育っていくのだろうか
2025.8.14 字幕 京都シネマ
2024年のフランス&インド&オランダ&ルクセンブルク合作の映画(118分、PG12)
インドのムンバイで働く女性たちを描いた社会派ヒューマンドラマ
監督&脚本はパヤル・カパーリヤー
原題は『All We Imagine as Light』で「私たちが光として想像することのすべて」という意味
物語の舞台は、インドのムンバイ
看護師として働くマラヤリ族のプラバ(カニ・クルスティ)は、見合い婚をしていたが、夫はドイツに出稼ぎに行ったまま音沙汰がなかった
彼女は後輩看護師のアヌ(ディビヤ・プラバ)とルームシェアをしていたが、彼女には良からぬ噂が立っていた
それは、ムスリムの男性と交際しているというもので、ヒンドゥー教一家のアヌとしてはあるまじき行為だった
ある日のこと、プラバの働いている病院の調理師パルヴァティ(チャヤ・カダム)から相談を受けたプラバは、知り合いの伝手を頼って、弁護士のデサイ(Bipin Nadkarni)に会いにいくことになった
パルヴァティはアパートの建て替えのために立ち退きを要求されていたが、弁護士は今住んでいるアパートの居住照明が必要という
それを知る夫はすでに他界していて、弁護士は「書類がないと居住を証明できないので裁判すらできない」と告げた
そこでパルヴァティは、なす術もなく地元の村に帰ることになった
物語は、パルヴァティの引越の手伝いのためにプラバとアヌがラトナギリの農村を訪れる様子が描かれていく
パルヴァティ同様にプラバもアヌも田舎の出身だったが、アヌは「いまさら村では住めない」と思っていた
プラバは帰らぬ夫を待つ身でありながら、勤務先のマノージ医師(アジーズ・ネドゥマンガード)からアプローチを受けていたが、道を逸れることなど微塵にも思っていない
彼女は生活を大きく変えようとは思っていなかったが、パルヴァティの引越やアヌの恋愛を見ていく中で、ある想いを抱くようになっていた
映画の後半にて、パルヴァティの村にて、ある男(Anand Sami)が海から救出されるのだが、なぜか医師の家にいる老女(Shailaja Shrikant)は2人を夫婦だと思い込んでいた
男は海難事故か何かで難破していて記憶を失っていたが、夫婦で思われていることを知るとプラバにそのことを確認してきた
プラバは即座に「違う」と否定するものの、その後彼女は、男を夫に見立てた妄想をしていく
この一連のシーンが妄想と分かりにくいために「実は夫だったのでは?」と思えてしまうのだが、シーンとしては「プラバが窓際に立って語り、最後のセリフは無人の背景で完結する」という演出になっていた
プラバとしては、妄想の中で現実を壊すことが唯一の光となっていて、それが原題の意味へとつながっている
タイトルには、アヌやプラヴァティも含めた「私たち」という言葉が使われているように、彼女たちの年齢と立場によって、それぞれが「光(希望)」と想像するものが違っているとも言える
アヌは未婚で若く、プラバは既婚で中年層、プラヴァティは死別で壮年となっていて、それぞれが向き合う問題も違っている
そんな中でも、アヌは恋愛や結婚を光だと感じ、それは自由意志が尊重されることだと言えるだろう
そして、プラヴァティにとっては、結婚や子育てはすでに過去のものであり、どのように死んでいくかを考える年頃となっていた
元々は夫と過ごした場所で死ぬことを望んでいたが、それは大いなる意志によって阻まれ、自分が生まれ育った場所へと回帰することになった
彼女にとっての光は、書類で形式的に存在する空間ではなく、命を感じられる場所だったと言えるのかもしれない
そんな2人の行動に揺れるプラバは「現状を変える気はないように見えるものの、2人の変化によって意志が変わろうとしていた」と言えるのではないだろうか
彼女が現実に戻って同じように変化をもたらすのかはわからないが、これまでにしたことのない電話をしたように、少しずつ行動へと結びついていくのではないか、と感じた
いずれにせよ、観念的な作品となっていて、冒頭のモノローグが登場人物とは関係なかったり、劇中で婚活サイトで金持ちの男性の本音がアヌの想像で語られたりしていた
これらはムンバイにおける大衆の総意のように紐づけられていて、その中でも3人の女性を中心に描くことで、結婚におけるインド女性の苦悩というものをクローズアップしているように思えた
「Imagine」という言葉を選んでいるように、現実とは切り離される想像というものが光に直結しているのだが、それが現代のインド女性の抑圧のベースになっているように思えた
そう言った意味において、現実的な解決はしていないけど、心の持ちようによっては心理的な解放を得ることができるとも言えるので、それが救いに繋がっているのかな、と感じた
孤独な人を映し出す鏡のような輝き
夕闇の中、インドの都市ムンバイの地下鉄で運ばれていく人たちに、無名の人たちのモノローグが重なる。「都会の暮らしは決して安住できるものではないが、人が集まる場所に私たちは希望を見続けてしまう」(大意)。この冒頭だけで引き込まれた。
高架を走る電車(上に架線が走っていないから地下鉄仕様なのだと思う)の「むき出し感」や、夏なので窓が開いた団地の家々を覗き込む感じが、見知らぬ人の人生を垣間見る映画のテーマを予告している。
看護師である主人公プラバは、良くも悪くもまじめで「堅物」といえる働きぶり。後輩の看護師が胎盤の処置に弱腰なのを叱り、中年女性のパルヴァディが地上げ屋に追い出されそうなので一緒に弁護士に相談して抵抗する。ただ、他人のために動けても自分のためには動けない。連絡が取れない夫との関係にしがみついているが、よりを取り戻したいのか、きっとプラバ自身もよくわからない。
ルームシェア相手の若い看護師のアヌは対照的な性格。宗教の違う恋人と、半ば公然とデートを繰り返している。プラバはそれをとがめるでもなく、新しい恋のチャンスをつかもうとするわけでもない。ただ、見ている側は「プラバの幸せとは何なんだろうか」をじわじわと意識させられる。
後半はパルヴァディが海辺の田舎に帰ることになり、プラバとアヌの2人も見送るため同行する。アヌはちゃっかり恋人と逢引きするのに対し、プラバも海で年上の男性を人命救助するという事件が起こる。
この男性に寄り添うなかで、プラバの脳内でドイツにいる夫が重なってくるのだ。許しを請う夫に、プラバはきっぱり別れを告げる。
重苦しい展開の中でようやく「光」が差すようなシーンだったが、これは果たして希望だったのか、それとも断念か。
思うに、アヌのような人が都会に「光」(たとえ幻想であっても)を見つけようとするのに対し、プラバは本来そういうタイプではない。アヌの言葉で言えば、洞窟の中で「何かが起こるのを待っている」女神のような存在。ちょうど鏡のように、孤独な人の思いを映し出すことで輝く。
プラバが都会の光を浴びるとき、また誰かの横に寄り添うとき。プラバ自身の中に何か大きなことが起こるわけではない。しかし人どうしが照らし合うような、希望と闇が交錯する時間が流れる。それをそのまま映し取ったような映画だった。
付け加えるならば、冒頭の魅力的なモノローグにつながるような、またプラバの未来を暗示するようなラストがあってもよかったと思うのだが。
どんな状況でも光は差す
2024年カンヌ映画祭でグランプリ(審査員特別賞)を受賞した、パヤル・カパーリヤー監督作品のインド映画です。原題はAll we imagine as lightです。是枝裕和監督が「傑作だ」としているのを見て、興味を惹かれました。
インドのムンバイが主な舞台ですが、都心の超高層ビル群と、そのまわりの古い町並み、割と空いているきれいな地下鉄と、満員のきれいとはいない通勤電車。郊外の窓のしまらないアパート。ムンバイの南にある、自然の中で用を足す田舎町のラトナギリ村。ヒンディー語が苦手なマラヤーム語話者。貧富の差。男尊女卑の社会。50ルピー(85円くらい)のとれたての鯖…。と現代インドのリアルがわかる映画になっています。韓国のいまがわかる、ポン・ジュノ監督作品の『パラサイト 半地下の家族』が、カンヌでパルム・ドールを受賞したのは2019年でしたが、こういったその土地固有のものを紹介する映画が受賞する傾向にあるのでしょうか?
個人的にはそれほど心に響かなかったですが、マノージ先生の詩が妙に心に残っています。たしか、光についてのものだった気がします。
インド映画お約束の踊りは、最後ではなく、映画の途中で少しだけですがでてきます。
ラストシーンが、どんな状況でも光が差すことはあるということを象徴している気がして、美しかったです。
タイトルなし(ネタバレ)
エンディングに流れる楽曲の力強い響きが心に沁み響きました。全ての文脈はこの瞬間の為にあったと思える力強い空間に満たされました。もちろん人により感覚は違うと思いますが。
タイトルなし(ネタバレ)
現代のインド・ムンバイ。
看護師のプラバ(カニ・クスルティ)は年若い同僚アヌ(ディヴィヤ・プラバ)と同居している。
プラバは結婚してすぐに夫がドイツに出稼ぎに出たままで、最近一年以上も音信が途絶えている。
一方のアヌは、故郷から見合い結婚を薦める両親に内緒で、ムスリム男性と交際している。
大都会ムンバイの暮らしは苦しい。
そんな中、食堂で働く初老の女性パルヴァディ(チャヤ・カダム)が、高層ビル建設のために立ち退きを余儀なくされ・・・
といったところからはじまる物語。
実際にはじまるのは、ムンバイの実景から。
そこに、ムンバイについて語る様々な人のモノローグが被る。
この冒頭から嫌な予感がした。
このモノローグ、主役ふたりとは関係ない人たち。
とすれば、主役は女性たちではなく、ムンバイという大都会ということになる。
街が主役というのは、かなり難しい。
登場人物を上手く広範囲に動かさないと街が活写できない。
が、映画はやはりプラバとアヌが主役のようで、彼女たちふたりのドラマを描いていくのだが、設定を活かすほどシナリオは深掘りされておらず、ドラマが展開するかと思うと、安易にセンチメンタルな音楽が流れる演出となっている。
なんだか、ムード演出だなぁ、と。
ただし、時折、良い描写もある。
予告編でも用いられている、高層マンションの屋外広告に石を投げつけるシーンなどは、女性たちが越えられない階級に対してのやるせなさ・諦念を感じます。
終盤ふたりは、故郷へ帰るというパルヴァディに付き添って海辺の寒村へ行くのだが、物語は唐突にファンタジー味を帯びて来、悶絶というか絶句というか。
久しぶりに、物足りなく、ガッカリ度の高い作品でした。
Why did this film win the Grand Prix at Cannes in 2024, second to the Palme d'Or ?
This film has three elements: documentary, realistic fiction, and fantasy. However, it lacks realism, and ultimately represents only one aspect of Mumbai as seen from a Western perspective, which I think may have been difficult for Indians to accept.
First of all, Prabha and Anu, who share an apartment, are nurses, but even though the hospital has an inpatient facility, they do not appear to work the night shift. The third main character, Parvathy, works in the hospital kitchen and is close to Prabha, but she does not interact with Anu.
Prabha is a down-to-earth woman who met her husband once through an arranged marriage and he is now working in Germany, but they have not been in contact for over a year. It is likely a paper marriage to obtain a residence visa. He presumably only sends money to her husband's parents. However, deep down, it seems that she still has feelings for him.
Meanwhile, the young and outgoing Anu is in a relationship with a Muslim. She tried to keep it a secret, but everyone knows. Her partner, Shiaz, is, as usual, weak and unreliable.
Parvathy is told there is no proof of ownership and is ordered to vacate her home to make way for the construction of a high-rise building. There seems to be no concept of residential rights. Perhaps there is no residential registration either.
Prabha and Anu accompany Parvathy back to her seaside hometown, but it's unclear how they managed to take holidays while working as a nurse. Shiarz also accompanied Anu. There is insufficient electricity and water, and no toilets, but for some reason their smartphones are able to charge. In a village near Ratnagiri, I thought it was Shiarz, who was going into the sea, but it turns out that the person who drowns and was rescued by Prabha is an unidentified man, pretending to be Prabha's husband. Even though it is a fantasy, the line between fantasy and reality is unclear.
The best part was the bustling Mumbai market that appeared in the documentary part, a market many times louder than the ones in Paris. It reminded me of that brief glimpse of the city from the plane.
The biggest problem with the Japanese version is that it doesn't distinguish between Hindi, the predominant language in Mumbai, Malayalam spoken by Prabha and Anu, and Marathi, spoken by Parvathy; we had no way of knowing the multilingual nature of the film. What a shame!
驚くほどつまらない
驚くほどつまらない。
カンヌで賞を獲るような映画。
大都会ムンバイで働くまじめな看護師プラバの夫はドイツに出稼ぎ(?)に行ったきり、ルームメイトの若い後輩は、ムスリムの男性と道ならぬ恋に落ち、プラバと仲が良い仕事仲間のおばさんは法律に疎くて長年住んだ家を追い出されそう。彼女たちの日常描写が延々、単調に続く。ムンバイの都市生活者の生態は興味深かったが、残念ながら話が単調かつつまらない。唯一面白くなりそうだった、プラバに好意を抱く、自作の詩をプレゼントしたり手作りお菓子を渡しながら「おいしくなかったら気まずいから家で食べて」という乙女チックな医師も特に爪痕を残すことなく消えてゆく。
居住の権利を証明する書類を一つも用意できないおばさんがしかたなく故郷に帰るところでようやく「転」が来たかと思ったが、何かが進展するわけでもない。
プラバが、おぼれた男性を救助し介抱していて、唐突に出てくるプラバの夫は一体何?
私には刺さるところがなく退屈で、気づいたら寝てました。何とか最後まで観たが私には合いませんでした。
インド映画で、おとなしめながら、そーゆーシーンがあろうとは!
何も怖くなくなる
こないだ鑑賞してきました🎬
病院に勤める2人の女性がメインのストーリー。
プラバにはカニ・クスルティ🙂
真面目すぎるきらいはありますが、そこが彼女の取り柄でもありますね。
一方で、夫がドイツに行ってからは疎遠に😥
しかし後半、色々あってからの彼女は明るく、希望を見出したようで何よりです。
アヌにはディビヤ・プラバ🙂
基本自由な彼女ですが、かといって悩みがないわけではなく。
イスラム教徒のシアーズと交際しており、親には内緒にしつつまめに連絡を取っています。
病院ではうわさのたねになっていますが、気にしないのが清々しい😀
奔放ですが繊細さもある、魅力的な女性を表現していました。
インド映画はあまり見ませんが、ゆったりとした日常の中で感じる漠然とした不安。
何処か満たされない思い。
それを抱えつつ、変わらない日々にこそ希望を見出していく、そんなメッセージを感じました🫡
インド発のヒューマンドラマとして、おすすめの1本です👍
インドの日常を描きながらも、前むきに生きる女性の姿が、心に沁みる
まずはインドの街 ムンパイ、街は活気があるが、何か雑然としていて働く人もどこか無気力。行政的にも問題がありそう、そんな中で、生きる全く性格の違う二人の女性の物語。友人の田舎に二人が同行して行くところから、今までの荒いカメラワークが、優しくなり、ラストまでとても心地よい気持ちになります。宗教観、結婚観、労働者、女性の立場など、問題提起はされていますが何一つ解決しませんが、屋台のイルミネーションのような色とりどりのライティングと海を見つめる女性の姿が彼女らの思いを現してくれています。
帰り道にインドの勉強をして思い起こすもの。
最初は不夜城に見える高層ビル群を背に生き抜く女性を描いているかと思いきや、光が差し込んだのは闇の多さ。
光と影をわざとチラつかせて色んなものを見せてきたね。
望もうが望まないが関係なしに増えていく人口。
夫婦でもない男女が常に世間の目を気にする空気感。
親族が絶対な環境に格差以外何物でもない社会にエネルギー事情も宜しくない……。
観ている途中でパラレルワールドにでも迷い込んだもう一つの日本の姿にも思えたよ。
だからこそあのiPhoneで照らす環境や個性の塊の着信音で笑えてくるし皮肉でもあるよね。
対アメリカのスタンスから見ると。
長いものや新しいものに弱い日本人の性質のおかげで今日の日本がある訳だから。
当たり前に広がる星空に弱々しい色付き電球。
どちらもこれからのインドの闇を討ち破る光になりうるのか?
難しいね。うん。
生きているうちにそんな若い世代が世界を揺り動かすムーブメントを起こすのを期待してます。
神にでもなろうとしている人達
商業大都市ムンバイの病院で看護師として働くプラバ、彼女の同僚で年下のルームメート、アヌがこの映画の主人公。
プラバには結婚式以来、長い間会っていないドイツの工場で働いている夫がいる。1年以上電話の連絡さえもしてこない夫を待ちつつ、同じ病院の食堂で働くパルヴァティ、彼女は高層ビル建設のために何十年も住んでる住居の立ち退きを迫られているが、プラバはそんなパルヴァティに何かと世話をする優しい女性だ。
アヌには周囲に隠して交際している男性がいる。彼はムスリムでヒンドゥー教が主要な宗教であるインドでは異教扱い、風当たりが強い様だ。アヌは自由でいられる場所が何処かないものかと思い悩んでいる。
彼女達を抑圧しているものは慣習、規律、宗教観でそれは親、お金持ち、国家でもある。
しかし劇中で彼らの姿は出て来ない。
パルヴァティが言う、「神にでもなろうとしている人間達」。日常、時間、意志を奪い続けている見えない力と見えない姿。
何だか眉間にしわの寄る話続きの様だか微笑ましい場面や笑えるシーンもある。
まさか外国映画で「写真で一言」が観れるとはね。反則でしょ。
高層ビルによる深く長い影、モンスーンによる大雨と暗い空。人口密度の高さによる熱気と圧迫感。そんな暗闇の中、彼女達のまなざしの先には様々に美しく差す光。
僕が生きている間に人口やGDPによる変化ではなく、規制や制約に収まらない本当の変化がインドで起こったら、真っ先にこの映画が思い浮かぶだろう。
女性の強さ
日常を懸命に生きている人々の作品が好きなので、今までは観ることの無かった、インド女性の生活を垣間見た感じて良かったです。
旦那様から送られてきた炊飯器を抱きしめるプラバの姿は切なすぎました。
でも職場の友人女性と共に行った海辺の町で、心の中で夫と決別をした姿は女性の強さを感じ感動しました。
また、一緒に同行したアヌも困難な道を彼氏と進むと決めたようで、また違った強さを感じました。
最後の海辺でみんなが話すシーンは景色も波の音も全てが美しく、彼女たちのまだまだ続くであろう道のりの休憩時間として、心に残りました。
全23件中、1~20件目を表示