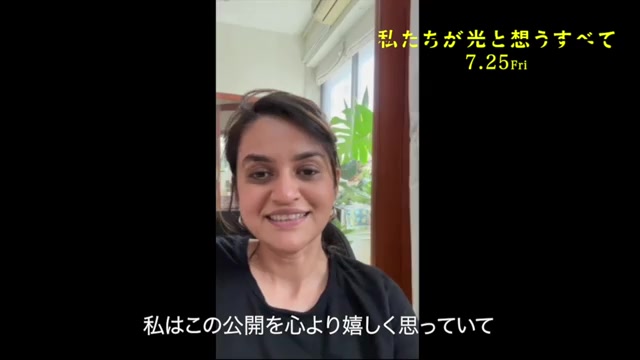私たちが光と想うすべてのレビュー・感想・評価
全95件中、61~80件目を表示
欠けたる月たちの詩
本作はフランスやインドなど4か国による合作映画ですが、舞台は全編インドで、監督も登場人物もすべてインド人ということから、実質的にインド映画と言ってよい作品でした。そして、インド映画として初めてパルムドールを受賞したということもあり、期待を込めて鑑賞しました。
パルムドール受賞作だからという訳ではないでしょうが、いわゆる“インド映画”にありがちなダンスシーンの含有量は全体の1%ほどと非常に控えめ。ド派手なアクションや過剰なバイオレンスもなく、むしろ日常生活に密着した写実的な映像、洒脱な音楽、そして人間の内面にじっくりと迫るストーリーが印象的で、極めて詩的な作品に仕上がっていました。
物語は、擬似姉妹のような関係の3人の女性の人生、結婚、恋愛を描いたものです。登場するのは、年長のパルヴァティ(チャヤ・カダム)、中堅のプラバ(カニ・クスルティ)、そして若手のアヌ(ターニシュカ・クタリ)。3人はいずれも同じ病院に勤務しており、パルヴァティは食堂職員、他の2人は看護師として働いています。
パルヴァティは夫を亡くし、子どもたちも巣立って一人暮らしとなった矢先、長年住み慣れた家から立ち退きを迫られるという境遇。プラバは親の決めた相手と結婚してはいるものの、夫はドイツで働いており、今では音信不通。アヌには恋人がいるものの、彼は異教徒のムスリムであり、両親に紹介することができずに葛藤しています。三者三様の“欠けたる月”のような状態にある彼女たちは、疑似家族、擬似姉妹のように互いに助け合い、寄り添いながら日々を生きています。
物語の背景には、貧富の格差や男尊女卑、親による強制的な結婚、宗教対立、都市と地方の経済的格差といった現代インドの社会問題が巧みに織り込まれていますが、それを声高に訴えるのではなく、あくまで静かに、自然に描いているところが美しく、また奥ゆかしさを感じさせました。
中盤までの舞台であるムンバイの街並みも過不足なく描かれており、まるで自分もその街を散歩しているような気分に。そして洒落たジャズピアノの劇伴も非常に印象的でした。終盤ではパルヴァティの故郷である田舎へと舞台が移り、わずかながらもインド舞踊が披露される場面があり、観客へのささやかなサービス精神に感服しました。
喧噪たるムンバイを離れ、それぞれの人生を見つめ直した3人の女性たちに幸あれ、光あれと思わずにいられない良作でした。
そんな訳で、本作の評価は★4.4とします。
自分がしっくりくる場所を探して
気になる映画を観に行く機会に恵まれ、「私たちが光と想うすべて」を鑑賞。設定を聞く限りではもっとドラマチックな展開があるのかな?と思っていたが、どちらかというと日常に根ざした落ち着きのある映画だった。
いい映画だったなぁと思うが、娯楽度は低め。一応製作国にインドも名を連ねているものの、テイストはヨーロッパ映画である。というか、インドでは無理めなシーンがチラホラあって、観てる最中に「これインド映画じゃないな」と気づく。
そこは大した問題じゃないけど。
主人公のプラバの変化が作品の一本の道筋となっていることは明白だ。
見合いで結婚した夫がいるが、関係を深める間もなくドイツへ出稼ぎ中。長らく不在の夫は音信不通気味で夫婦関係などほとんど存在していない。だが、離婚したわけでもない、宙ぶらりんの状態なのに、根が真面目で規範に忠実なプラバはほとんど表情を変えることもなく、職場と家との往復だけの毎日を淡々と送っている。
そんな彼女とルームメイトのマヌが同じ病院で働くパルヴァティの帰郷に同行したことで、ほんの少し変化するのだ。
規範とされていることに疑問を抱く暇すらない都会の忙しない日常と、その対極として田舎のゆったりとした空気感。
その雰囲気の違いが彼女の心のケリをつけられない部分に変化を促したのだろうと思う。
また、もう一人の主役はムンバイという都市そのものなのだろうとも思う。都市を離れることでプラバが変化する物語ではあるが、監督はムンバイを悪役にしようとは考えていないように思うからだ。
プラバを人生の鎖から解き放ったのはムンバイから離れたことがきっかけではあるが、プラバの同僚であるアヌは「今さら田舎で生きていける?私は無理だな」と口にしているし、ムンバイという都市の持つ圧倒的なパワーが伝わってくるようなシーンも多かった。
大事なのは「自分にとってしっくりくる」生き方や場所、それを選ぶのは自分自身なのだということなんじゃないかと思う。
私自身はバリバリの都会っ子なんだなということも痛感した。前半のムンバイ・後半の海辺の村ともに、映画は色んな音にあふれている。工事の音、雨の音、電車の音、風の音、波の音、虫の音。
これは意図して大きめに入れているそうなのだが、映画前半ではほとんど気にならない、むしろ音として認識していなかったものが、後半ではやけに大きく聞こえたからだ。
普段聞き慣れている音はあまり意識に残らない。私にとっては工事の音や電車の音は無音に近い感覚で、波の音や風の音ははっきりと聞こえてくるものなのだ。
うるさい、とは思わないが「音デカいな」とすぐに気づくほどには顕著な差があったのである。
気になる映画を気軽に観に行けるのも都会っ子ならではの幸せだ。
私が私らしくあるために一番大事なことでもある。
ムンバイの雑踏に入り込んだよう
ムンバイの騒がしさ
臭い、暑さが生々しく感じられた。
海辺の田舎町は鬱蒼と生い茂る木々の香り、潮の香りがするようだった。
プラバは笑わないねんな。悩みを抱えているからか始終陰気な印象。対照的に年下の同僚のアヌはイケイケな感じで明るい。なんで一緒に暮らしてるんやろ?
運命に抗えない女性達がなんか悲しい。
終盤で
全く刺さらなかった
ドイツ製炊飯器と子持ち猫
鑑賞後に感じる深い余韻でとんでもない名作を観たのではないかと感じさせる一品
この映画、鑑賞後感が非常に良くてちょっとびっくりしました。映画を観ている最中にはそれほどでもなかったのですが、エンドロールをぼーっと眺めていると、あー、今日は本当にいい映画を観たなぁという満足感に全身が包まれてゆきます。晩ご飯の後に飲んだ一杯のお茶のようにこの作品の持つ滋味が五臓六腑にしみわたり、まあ人生ままならないこともいろいろあるけど、明日からも生きてゆくかという気分にさせてくれます。
主な登場人物は看護師の同僚で住処をシェアしているプラバ(演: カニ•クスルティ)とアヌ(演: ディビヤ•プラバ)の二人、そして彼女たちの勤める病院でまかないの仕事をしていたけど、住まいの立ち退きを要求されて郷里の海辺の村に帰ることになったパルヴァティ(演: チャヤ•カダム)。この女性3人を中心に物語は進みますが、前半を引っ張るのはムンバイの街です。ムンバイはインド最大の都市で人口2000万弱とのことでケタ違いの大都会。この映画では特にその夜の喧騒をよく捉えています。また、ムンバイを走る電車の捉え方が秀逸です。夜のムンバイを走る、東京で言えば京浜東北線か東海道線のように都会の中心と郊外を結ぶ電車。警笛を鳴らしながらガタンゴトンと走る、外から見たロングショットもいいですが、中の様子を撮したショットもいい。大都会の電車には人がたくさん乗っていてもなんともいえない寂寥感と哀愁があると思うのですが、これはインドでも日本でも同じなんだと感じました。
その電車に乗って、異教徒の恋人の住む街へその恋人に会いに行こうとするアヌ(ヒンズー教徒でしょうね)。彼女は「スパイになった気分」と言い、店でムスリム女性が身につけるブルカ(例の全身を覆うあれですね)を購入し、それに着替えて電車に乗ります。色は黒で外からは目の部分しか見えませんでした(結局、事情があってその日は会えなかったんですけど)。異教徒と恋愛をするというのはこういうことなのだ、それを簡潔に映像で表現していて見事でした。
郷里の海辺の村に帰ることになったパルヴァティ。プラバとアヌもその海辺の村へと旅行します。前半のムンバイの喧騒とは打って変わって後半は海辺の村の幻想的なシーンが続きます。そのコントラストがいいです。特に秀逸なのが終盤に登場する浜辺に建てられた「海の家」の紛い物みたいなふた部屋続きの横長の掘立て小屋みたいなお店。その小屋の前にテーブルや椅子が並べられて飲み物が提供されるような感じのお店なのですが、インド洋からの強風であっという間に飛ばされそうな造りです。でも夜に電飾を施されるとなぜか美しい。郷愁も感じます。メインの3人の女性とアヌの恋人が夜、その店に集うのですが、なぜか目頭が熱くなりました。この先、この人たちの身の上にいろいろなことが起こるでしょう。思い通りに進まないことのほうが多いかもしれません。でもどうか、今日よりはよくなる明日を信じて前進してほしいと心から願いました。
本当にとんでもない名作なのかもしれません。
中だるみがあり、長く感じた
閉じ込められた女神
言語化できない強い余韻──インドと日本の現在をつなぐ映画
言葉にして感想を書いてしまうと、何か大事なものが抜け落ちてしまうような、言語化できない強い余韻を残す映画だった。
いつまでもそれがなんなのか考えてしまいそうだから、とりあえず鑑賞直後の感想を書いてみたい。
インドの映画はこれまで何本も観ているけど、エンターテイメントの極致のような映画ばかり。本作は、そうしたエンタメ性は全くない。
ただ、この映画を観てはじめて、僕らと同じく、現代を生きる困難や葛藤を抱えて一生懸命生きている個人、国籍は違えど同じ悩みを持つ同志として話してみたくなる個人としてのインドの人の姿を教えてもらった感じがした。
映画の冒頭で、正確な言葉は覚えてないが「この町で暮らして10数年以上になる。でもこの街を故郷と呼ぶには躊躇してしまう。いつお前はここからででいけ、と言われるかわからないから」
こんなようなモノローグが街の風景をバックに流れる。
これは、自分が安心して所属していると思える場所などないんだという本作の1つのテーマの提示ではないかと思った。
そしてその後のストーリーで、凄まじい発展の最中の現代のインド社会の様子が丁寧に描かれていく。
僕はインドに行ったことがない。敬愛する藤原新也の「インド放浪」(彼が20代、1970年代に出版された凄本)の近代以前の価値観が色濃く残る時代のイメージでインドを捉えがちな僕の認識もひっくり返してくれた。
今のインドは、日本で言えば、明治の近代化、戦後の民主化と自由主義と経済発展、さらに男女雇用機会均等法とグローバル化の影響が同時に訪れているような状況なんだと思う。
基本的にはポジティブな発展ではあるけれど、そこで起きている共同体の喪失や個人が機能として能力で測られること。自分らしさを自分で見つけてそれにしたがって一人一人が自分で人生を切り開かなければいけない……そうした困難が丁寧に描かれた映画だと感じた。
しかし、そうした時代の中でも、資本の論理で人を機能としてみるような流れに飲み込まれず、本来の人間らしい関わりを大事にしている。そんな人としての強さも強く感じさせられた。
ここらかは余談になるけれど、先日、永田町にある自分の会社の近所のコンビニでそんな体験があった。
飲み物と電子タバコを買ったら、レジの外国人の若い女性(おそらくインド出身)が「マスカットがお好きなんですね」と話しかけてくれたのだ。
? 何を言われたのか一瞬わからなかった。そして手元の商品を見て気付いた。僕の買った電子タバコがマスカットフレーバーで、飲み物がマスカット味のいろはすだったのだ。
なんかすごく嬉しかった。それに何か大事なことを教えてもらったと思った。
店員と客で、コンビニは資本主義な等価交換の場。忙しい店だから効率が大事。そこに個人的な、相手のその人らしさを見て、それを承認するというようなことは、なかなかできることではないと思う。
だいたい僕らは会社員として、有能で成果を出しているか、組織に与えられた役割と責任を果たしているか……そんな画一的評価の中で生きているから、自分が他の人とは違う個性のある人であるという自己重要感が得られなくなっている。それが現代の発展の裏にある大問題であると思う。(庵野秀明のエヴァは、そうした彼の個人的欠落感を、キャラクターたちに反映させて、そこからの救済の可能性を探る作品でもあると思う)。
そうした僕ら日本人の現代の課題にも通じる普遍性を持った素晴らしい映画。満席だったから、すでにその評判は周知されているのだろうけれど。
さらに余談。
こんな感想を映画を観たあと小伝馬町のインド料理店「デシ タンドール バーベキュー」で、ビリヤニ付きのちょっと贅沢なランチを食べながら書き始めていた。
ビリヤニが素晴らしく美味しかった。会計の時にそんな話を店員さんにした。僕はチャーハンみたいなものだと思ってたけど、大間違い。2〜3時間も手間のかかる炊き込みご飯のようなものなのだとか。冷凍のお店も多いけど、味が落ちるから、彼の店ではやらない。人気でもたくさん出せないのだそうだ。
彼の仕事にかける意気込みと倫理観、誇りに触れて感激。握手して店を後にした。
映画の感想からずいぶん離れてしまったけど、直接その素晴らしさを語れない、でも何かが強く心に残る、そんな映画でした。
インド市井の女性たちが織りなす静謐なドラマ
◾️作品情報
監督・脚本はパヤル・カパーリヤー。主要キャストはカニ・クスルティ、ディヴィヤ・プラバ、チャヤ・カダム、リドゥ・ハールーン。2024年・第77回カンヌ国際映画祭でワールドプレミア上映され、グランプリを受賞したフランス・インド・オランダ・ルクセンブルク合作映画。
◾️あらすじ
ムンバイで看護師として働くプラバと年下の同僚アヌはルームメイトだが、それぞれの人生にはままならない現実があった。真面目なプラバは、親が決めた相手と結婚したものの、ドイツに住む夫からは長らく連絡がない。陽気なアヌはイスラム教徒の恋人と秘密の恋愛をしているが、家族に知られることを恐れている。そんな中、同じ病院の食堂で働くパルヴァティが立ち退きを迫られ、故郷の海辺の村へ帰ることを決意する。プラバとアヌは、ひとりで生きていくというパルヴァティを村まで見送る旅に出る。神秘的な森や洞窟のある別世界のような村で、彼女たちはそれぞれの人生を見つめ直す。
◾️感想
インド映画と聞くと、華やかなダンスと歌のイメージが先行しがちですが、『私たちが光と想うすべて』は、そんなインド映画のイメージとは一線を画す、静かで内省的な作品です。ムンバイの喧騒の中で生きる市井の女性たちの日常を、まるでドキュメンタリーを観ているかのように、ありのままに穏やかに描き出しています。
真面目で内向的なプラバと、奔放で現代的なアヌ。対照的な二人の看護師の姿は、現代インド社会に生きる女性たちが抱える息苦しさと、そこから抜け出したいと願う自由への希求を、等身大で誠実に浮かび上がらせています。彼女たちの心情に寄り添い、その微細な揺れ動きを丁寧に捉えるカメラワークは、観る者の心に静かに染み入るようです。
しかし、その抑制された演出ゆえに、物語の展開は時に淡々とし、退屈に感じてしまう面もあります。ドラマチックな起伏は少なく、観客自身が彼女たちの感情に深く潜り込み、共鳴できるかどうかに委ねられる部分が大きいと感じます。それでも、ラストに向けて見せる二人の変化、特にプラバの内面の解放が詩的に描かれる場面は印象的で、静けさの中に確かに灯る希望の光を感じさせます。
大都市ムンバイで、既存の枠に自分をはめることで心の安定や社会的体裁を保ってきた三人の女性たち。彼女たちが、事情は違っても、内に秘めた息苦しさ、生きづらさに共感しあい、海辺の村で自身を解放する姿が眩しく映ります。光は、都会の幻想ではなく、彼女たちの心の中にあったのでしょう。
とにかく、この邦題に惹かれて
見事!ドキュメントタッチでもどこか温かい作品
インド映画はダンス、アクションのイメージが強いが本作品は正統派作品。ドキュメントタッチでインドのカースト制度の現実に直視しつつも恋愛したい、夫と会いたい看護師姉妹の生き方に好感。ラストシーンは◎。看護師妹もカースト制度の厳しい中、素敵なボーイフレンドと出会えて良かったなと感じた。
異文化を知るには映画を観るのが一番だが、本作品はインド社会を知る上で最適な作品。
眠かった・・・
諦観と自己肯定と開放
淡々とし過ぎていて私には合わなかったかも
【今作は喧噪の街、インド・ムンバイに住む女性達の連帯を斬新な演出、アングル、色彩で描き出した作品であり、踊りなし、是枝監督コッソリお勧めアーティスティック作品である。嵌る人には嵌ると思います。】
■ムンバイの病院で働く看護師のプラパは年下の同僚アヌとルームシェアをしている。彼女は出稼ぎでドイツに行ったっきりの夫を待ち、ムスリムの男シアーズを恋人に持つアヌは、親から見合いを勧められるも、カンムシ。
そんな時、病院の食堂で働く老いたパルパティが、高層マンション建設のために住居からの退去を迫られてしまう。
◆感想<Caution!内容にやや触れています。>
・ご存じの通りムンバイはインドの大都市の一つであり、仕事で行くと今作で描かれているように、高層ビルがガンガン建設されている。
一方で多様な人種が住む街であり、貧富の差も大きい。今作のプラパとアヌとの様に、正規の職についていても、ルームシェアをする人が多いとも聞く。又、街の裏通りを歩けば(お勧めはしない。)道の片隅に不可触選民が茶色い格好で寝転がっている。貧富の差が大きいのである。仕事があるために出稼ぎ労働者も多い。
・今作ではそんな街に住むプラパ、年下の同僚アヌ、パルパティの結婚、仕事、格差、伝統という縛りの中、思い通りにならない人生と、そんな中で三人が連帯して暮らす様が、抑制したトーンで描かれる。
■自由恋愛を楽しむアヌが、現代インドで生きる中級階級の女性の代表とすれば、プラパとパルパティは伝統的な生き方をする女性の代表なのかもしれない。
だが、三人は緩やかに連携をしている。支え合っている。アヌの生き方をプラパは否定しないし、パルパティが退去を迫られた時に漏らす”私が、この街から消えても誰も気づかない。”という言葉に対し、プラパは”私は覚えている。”と答え、二人で夜、高層マンションの華やかな看板に石を投げるのである。
・病院を辞めたパルパティの故郷に行った三人。アヌは恋人をチャッカリ連れて来て森の中で、インド映画では珍しく性愛行為をするが、全く猥雑感はない。
一方、ある日浜辺には男が打ち上げられ、プラパは躊躇なく男の唇に口を付け息を吹き込みテキパキと処置をし、蘇生させる。
男は、プラパの中で長い間自分の元に帰って来ない夫に変容し、彼はその事を謝罪するが、彼女は”二度と会いたくない。”ときっぱりと拒絶するのである。
このシーンはプラパが家父長制に縛られていた状態からの解放を示しているのである。
<プラパ、アヌ、パルパティそしてシアーズが夜、ほの暗い赤、青の灯が点る家で過ごす姿を、ロングショットで映すシーンは幻想的で美しい。
あのシーンには、自分達の人生を自分の意志で生きようとするメッセージが込められていると思うのである。
今作は、喧噪の街、インド・ムンバイに住む女性達の連帯を斬新な演出、アングル、色彩で描き出した作品なのである。>
緊張感のないストーリーだから、想像力が必要不可欠だ
全95件中、61~80件目を表示