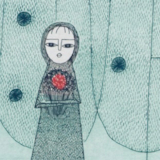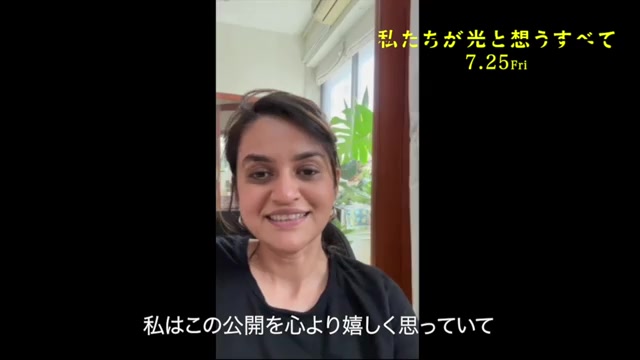私たちが光と想うすべてのレビュー・感想・評価
全120件中、101~120件目を表示
淡々とし過ぎていて私には合わなかったかも
面白いと思えなかったなー。
淡々とし過ぎていて、私には合わなかったかも。
インドのムンバイが舞台。
医療機関で働く看護師の女性2人が主人公。
中盤で耐えられずにウトウトしてしまって、断続的には観たけれど、物語を深く理解できず。
壁に立ち向かう2人に幸あらんことを
インド南西端、ケララ州の公用語、マラヤーラム語の原題の意味は(Chat GPTに訊いてみたところ)All that imagined as Prabha だという。
つまり「プラバとして想われるすべて」。
そしてPrabhaは、lightを意味する名前なんだそうな。
プラバは、主人公の名前である。
「光さんの想いのたけ」ということか。
もちろん英語圏でもあるインドなのだから、
All We Imagined as Lightという英題にも
監督の意思は反映されているだろうけれど。
大都市ムンバイの病院で「シスター(字幕は"姉さん")」と呼ばれる看護師プラバは、
謹厳実直で禁欲的。
同じ職場で働き、なぜかプラバと部屋をシェアするアヌは、
ちょっとだけ無邪気で、思った通り行動したい。
2人の出身は、ケララ州。
この2人と、もう1人、
病院の食堂で働いていて、
富裕階級のためのマンション建設で立ち退きをくらう
パルヴァティという寡婦のおばさんが、話の中心。
* * *
プラバはかつて、
親から突然呼び出され、帰省したら結婚相手が勝手に決められてた。
その夫は、その後すぐドイツへ行ってしまって、
最近は1年以上音沙汰がない。
だからプラバには、恋愛という経験がない。
そういう彼女へ、(おそらく同郷の)医師が(控えめな)告白をする。
アヌはといえば、今まさに、
プラバと同じように、親から見合いの相手を提示されているのだが、
それとは関係なく出会った彼氏(こちらもたぶん同郷)との付き合いに夢中。
だがその彼氏はムスリムで、
ヒンズー教徒であるアヌの両親が、アヌを嫁に寄越すはずがない。
――という状況で、さて彼女たちの未来はどうなるのか。
* * *
(ここからネタバレあります)
* * *
この映画が投げかける主な問題は、
男女・結婚・家族・宗教をめぐる古い価値観と、
最近のインド政権が明確に打ち出しているヒンズー教指向および
それにともなうイスラム教との摩擦の先鋭化だろう。
プラバは、
男女・結婚・家族をめぐる古い価値観に絡め取られ、
遠くドイツにいる名ばかりの夫に縛られている。
プラバよりいくつか年下のアヌは、
その古い価値観に絡め取られまいと抗っているが、
宗教をめぐる大きな壁にぶつかっている。
ただ、壁は宗教だけではない。
ムスリムの彼氏は、
「君の親を説得しに行こうか?」とは言うものの、
「僕の親を説得するよ」とは決して言わない。
つまりそこには、旧態依然たる男女の問題が、
大きな壁として立ちはだかっているんである。
* * *
後半、
立ち退き要求に抵抗できず、あきらめて
故郷のラトナギリ近くの村に帰るパルヴァティを、
プラバとアヌは休暇をとって送ってゆく(引っ越しの手伝い)
よくアヌが来たな、と思ってたら、
ちゃっかり彼氏を呼び寄せ、こっそり会う筋書きを立てていたという寸法。
他方、プラバは、
海で溺れた男性を、看護師として救命する。
病院もないその村で、その晩の看護もつとめるんだが、
そこからが、幻影? 妄想?
記憶を失っている男性が、
いつのまにやらプラバの夫に……
いやまさか、
ドイツから泳いできたはずはなくw
地元のおばあちゃんが2人を夫婦と誤解したことをきっかけに、
プラバの脳内でそういう会話が生まれたんだろうと、
思っておくことにする。
ただいずれにしろここでプラバは、
名ばかりの夫に抑えつけられ続けることを拒否する。
こうして、
前途はむちゃくちゃ多難だけれど、
プラバもアヌも、
それに立ち向かって生きていくことを、決意したんだろう。
たぶん。
2人の前途に幸あらんことを。
* * *
ちなみに、
アヌを演じた役者さんの名前が、
ディビヤ・プラバ――苗字が「光さん」――
なんだね……
【今作は喧噪の街、インド・ムンバイに住む女性達の連帯を斬新な演出、アングル、色彩で描き出した作品であり、踊りなし、是枝監督コッソリお勧めアーティスティック作品である。嵌る人には嵌ると思います。】
■ムンバイの病院で働く看護師のプラパは年下の同僚アヌとルームシェアをしている。彼女は出稼ぎでドイツに行ったっきりの夫を待ち、ムスリムの男シアーズを恋人に持つアヌは、親から見合いを勧められるも、カンムシ。
そんな時、病院の食堂で働く老いたパルパティが、高層マンション建設のために住居からの退去を迫られてしまう。
◆感想<Caution!内容にやや触れています。>
・ご存じの通りムンバイはインドの大都市の一つであり、仕事で行くと今作で描かれているように、高層ビルがガンガン建設されている。
一方で多様な人種が住む街であり、貧富の差も大きい。今作のプラパとアヌとの様に、正規の職についていても、ルームシェアをする人が多いとも聞く。又、街の裏通りを歩けば(お勧めはしない。)道の片隅に不可触選民が茶色い格好で寝転がっている。貧富の差が大きいのである。仕事があるために出稼ぎ労働者も多い。
・今作ではそんな街に住むプラパ、年下の同僚アヌ、パルパティの結婚、仕事、格差、伝統という縛りの中、思い通りにならない人生と、そんな中で三人が連帯して暮らす様が、抑制したトーンで描かれる。
■自由恋愛を楽しむアヌが、現代インドで生きる中級階級の女性の代表とすれば、プラパとパルパティは伝統的な生き方をする女性の代表なのかもしれない。
だが、三人は緩やかに連携をしている。支え合っている。アヌの生き方をプラパは否定しないし、パルパティが退去を迫られた時に漏らす”私が、この街から消えても誰も気づかない。”という言葉に対し、プラパは”私は覚えている。”と答え、二人で夜、高層マンションの華やかな看板に石を投げるのである。
・病院を辞めたパルパティの故郷に行った三人。アヌは恋人をチャッカリ連れて来て森の中で、インド映画では珍しく性愛行為をするが、全く猥雑感はない。
一方、ある日浜辺には男が打ち上げられ、プラパは躊躇なく男の唇に口を付け息を吹き込みテキパキと処置をし、蘇生させる。
男は、プラパの中で長い間自分の元に帰って来ない夫に変容し、彼はその事を謝罪するが、彼女は”二度と会いたくない。”ときっぱりと拒絶するのである。
このシーンはプラパが家父長制に縛られていた状態からの解放を示しているのである。
<プラパ、アヌ、パルパティそしてシアーズが夜、ほの暗い赤、青の灯が点る家で過ごす姿を、ロングショットで映すシーンは幻想的で美しい。
あのシーンには、自分達の人生を自分の意志で生きようとするメッセージが込められていると思うのである。
今作は、喧噪の街、インド・ムンバイに住む女性達の連帯を斬新な演出、アングル、色彩で描き出した作品なのである。>
緊張感のないストーリーだから、想像力が必要不可欠だ
忍耐力と想像力を要求する作品です。こゝろして、鑑賞して下さい。
期待度◎鑑賞後の満足度◎ チラシにある様な優しいだけの映画とは思わないけれど監督の登場人物達への視線はあくまでも優しい。前半の大都市ムンバイと後半の海浜の穏やかな村との絶対的な対比が正に映画的。
※2025.08.01.2回目の鑑賞[ユナイテッド・シネマ橿原]
①各登場人物の台詞が勿論あるし、それを説明する様な記号やシグナルが出てくるし情景描写もあるのだが、その後ろというか同時に流れる空気というか情景がとても映画的…というよりも正に映画。
②国が違っても、人種が違っても、宗教や政治体制が違っても人間は全て「光」を想い描いて求めて生きているものではないだろうか? 原題が“think”ではなくて“imagine”なのも意味があると思う。求める「光」が結局想像の範囲を越えないものでも想い続けずにはいられない、想い続けずには生きていけない、それが人間というものではないか、インド社会を描きながらもそういう普遍的なテーマを持っているからカンヌでインド映画初めてのパルム・ドールを取ったのではないか、と思う。
③如何にも女性監督らしい柔らかな演出と思想。
④ビーチハウスのバイト(?)の男の子が良いアクセントになっていて面白い。
⑤映画はやっぱり何回も観直さないとね。
タイトルとポスタービジュアルに魅かれて‥‥
ボンベイからボリウッド
私たちが光と想うすべて
東京以上の大都会になりつつあるムンバイは、江戸と同じ頃に開発された都市と言うこと
いかな大都会でも、封建的でカースト制や長く英国植民地、更にはムスリムとの宗教紛争が今も残影が貧困の暗闇にあり続けている
医療機関に働く三人の女性は、地方から出てきた
一人は、未亡人となり残された住居の所有権で不利な立場にいる
もう一人は、見合い結婚したが夫は直ぐにドイツに出稼ぎに出国して連絡も無い
三人目は、独身でムスリム男子と恋愛ししたくて仕方がない
その内未亡人が弁護士相談や住人権利奪回の集会に参加しても奏功せず、郷里にUターンする
そこに、他の二人も引越しに付き合い、幻想的な一夜を過ごす
未来はあるのに、その準備ができて来ない。
大都会の喧騒から離れた夜の浜辺で三人の女性が潮騒を聴きながら対話していて、これまでをわだかまりを手放しそれぞれが決心を固めた様だ…
夜光灯の下で、パンクをイヤホンで聴きながら無心に踊っている一人の少年
そうだよね、彼女と関わった男達は無責任で、お調子者だよねー
おしまい
ムンバイは7月でも28℃と案外涼しいらしい。
だからエアコンも要らないのかな…
それにしても、倫理に厳しいインド映画で電気炊飯器と⚫︎⚫︎⚫︎する映像は衝撃だ。
ドイツ製だけに対象となるのだろう。
それても、あの汚い街に人は集まる。
(^∇^)
私たちが光と想うすべて
ままならない人生に葛藤しながらも自由に生きたいと願う女性たちの友情を、光に満ちた淡い映像美と幻想的な世界観で描き、
2024年・第77回カンヌ国際映画祭にてインド映画として初めてグランプリに輝いたドラマ。
ムンバイで働く看護師プラバと年下の同僚アヌはルームメイトだが、真面目なプラバと陽気なアヌの間には心の距離があった。
プラバは親が決めた相手と結婚したものの、ドイツで仕事を見つけた夫からはずっと連絡がない。
一方、アヌにはイスラム教徒の恋人がいるが、親に知られたら大反対されることがわかりきっていた。
そんな中、病院の食堂に勤めるパルヴァディが高層ビル建築のために自宅から立ち退きを迫られ、故郷である海辺の村へ帰ることになる。
ひとりで生きていくという彼女を村まで見送る旅に出たプラバとアヌは、神秘的な森や洞窟のある別世界のような村で、
それぞれの人生を変えようと決意するきっかけとなる、ある出来事に遭遇する。
パルヴァディ役に「花嫁はどこへ?」のチャヤ・カダム。
ドキュメンタリー映画「何も知らない夜」で、山形国際ドキュメンタリー映画祭2023インターナショナル・コンペティション部門の大賞を受賞するなど注目を集めたムンバイ出身の新鋭パヤル・カパーリヤーが、長編劇映画初監督を務めた。
私たちが光と想うすべて
劇場公開日:2025年7月25日 118分
社会のルールと友情の連帯
よく分からなかった…
微かな光を求めて
あくまで「少数意見」として
劇場で一度、見るともなしに見た本作のトレーラー。何となく気になって後で確認してみると、第77回カンヌ国際映画祭グランプリ作品(しかもインド映画初)であり、更に米国映画レビューサイトの評価もかなり高い。と言うことで期待を膨らませ、公開初日にヒューマントラストシネマ有楽町にて鑑賞です。実際に客入りも上々で、改めて本作に対する期待の高さが伺えます。
訳あって夫と離れ単身、ムンバイで看護師として働くプラバ(カニ・クスルティ)は同僚のアヌ(ディヴィヤ・プラバ)と共同生活をしています。なお、劇中においてアヌはプラバを「(字幕上)お姉さん」と呼びますが、これは単に両者間における呼称であって血縁関係はありません。(ちなみに本作この他にも、特に説明はされず判らなければ「観ながら解釈(言語、宗教など)が必要」な点が少なくないため、案外集中力が試されます。)確固たる後ろ盾や保障もなく、一労働者としてしがなく働きながら生活する彼女たち。普段から口数少なくて日々を無難に過ごそうとするプラバと、要領が良くマイペースで時に大胆さも垣間見えるアヌは一見対照的な存在。ところが、女性一人で生きていくには不利な点が余りにも多いインド社会において、物語の大半はこの二人にまつわる「男女関係」に関わる内容で、画から感じるイメージ以上にドラマ性が強く、地味でありながらも葛藤の連続。プラバ&アヌを演じる、カニ・クスルティとディヴィヤ・プラバのイメージ通りで的確な演技も相まって、二人の人生から目が離せなくなります。
ところが、、、如何せん、ストーリーとしてはいまいち面白みに欠け、寝不足もあって眠気に抗うのに必死。そもそも恋愛事に対する高すぎる難易度設定(既婚、宗教など)は、折角の現実感の高い背景よりもまさって、むしろ「インドである意味」が記号的になり、ひいては形骸化されてしまっているように感じます。また、中盤までのリアリティを一気にひっくり返す、本作の要=後半のファンタジーな展開は観ていて驚いたものの、やはり納得度と言う意味では強引すぎてやや無理筋。何なら最早「看護師」であることすら。。
まぁ、ケチを付けるのはこれくらいにします。何せ、カンヌグランプリで是枝さんを筆頭に絶賛評も多いわけですから、あくまで「少数意見」としてお取り扱いください。個人的な好みの問題と言うことで、何卒悪しからずご容赦ください。
静かに、でもはっきりと表明されるプラバの「NO」
こんなに静かな語り口のインド映画は初めて観た。もちろん世界に冠たる映画大国だから歌い踊り闘う以外の作品もあるのは当然なんだろうけど。長編第一作とはいえ、俊英女性監督の脚本、演出ということで、なかなかの切れ味を隠し持った作品だった。
プラバは医者や同僚からも頼られる優秀な看護師である。また時として家賃を踏み倒されながらも後輩のアヌとルームシェアし、病院で賄い婦をしているパルヴァディが家を追い出されそうになれば相談にものってやる頼れるお姉さんでもある。
でも、彼女がモヤモヤしているのは、ドイツにいる夫のこと。元々、夫とは勝手に見合いさせられ、よくお互いを知らないうちに結婚させられたのだが、ドイツの工場で働くうちに最近では電話一つよこさなくなった。
この夫がいきなり電気炊飯器を送りつけてくるエピソードがある。この炊飯器が赤色で〜私は小津安二郎の映画の茶の間や台所に配された挿し色を連想したが〜言ってみれば妻を家庭に縛り付けておきたいという夫からのメッセージにみえる。まあとんでもない野郎なのだが、映画のこの段階ではプラバはこの炊飯器を抱きしめて泣き崩れるのである。
ただ、アヌやパルヴァディとともに苦境をくぐり抜けていくうちにプラバはだんだん強くなる。そしてパルヴァディの故郷の海沿いの村で過ごすうちに、海から上がってきた(何か怪獣みたいだけど)夫、もしくは夫の幻影と対峙することとなる。プラバは、溺れて怪我もした夫の命は助けるが、彼を受け入れることははっきり「NO」という。
映画の前の方で出てくる、恐らくはプラバに惚れた医者もそうなんだけど、彼らが利用しようとしているのはプラバの母性であったり包容力であって、ブラバの人格や職能を評価、尊敬して、対等な関係で愛し合うということではない。そこがブラバには見透せたので「NO」ということになったのだと思う。
近年のインド社会の状況はよく知らないけど、インドでも中国、韓国でも、そして日本でも、アジア的な夫婦の関係というのは似たりよったりだと思う。そこに一石を投じている気持ちの良さはあるよね。
そうそう、最後の海辺のバー(といっても海の家に電飾している程度なんだけど)の映像の美しさは素晴らしいです。ここだけでも観に行く価値はあるよ。
人はそれぞれ思い通りに行かなくたって、時は経過していくもの
主要な登場人物たちはそれぞれが、思い通りにならない人生を送っています(海外に仕事で行って連絡もおぼつかない夫・信仰が異なる男女・【名前】の無い女性など)。
かなり深い問題で、どうすれば解決するのか糸口も掴めませんが、いつも降り続けている(感じがする)ムンバイの雨のように、劇的に何かが変わってはくれません。
それでも時間は誰しも同じように過ぎて行って、それに伴い人の意識も同じところに留まり続けるのではないのかな?そんな印象を与えてくれるような作品だった気がします。
都市から地方へ移動して、海を身近に感じたら、何となくですが心が穏やかになったのかも。
何かが起こる訳ではないので、一点集中して観るよりも、風景なども含めてスクリーン全体をぼんやりと眺めて空気感を味わう、それが良いのかもしれません。
現代を生きている者の一つの普遍的人生観
インドのリアルな日常
青と夜に包まれたシスターフッドな関係
インドのムンバイで看護師をしているプラバと、年下の同僚のアヌ。境遇も性格も対極にあるルームメイトの2人が、故郷の海辺の村へ帰る事にした病院の食堂に勤めるパルヴァディを見送る旅に…
観ていて気になったのは色彩。女性達が着る看護師の服や家の壁、列車やバスの内装、後々登場する男性の服、はてはポスターアートなど、至るところに「青」が用いられている。“清楚”なイメージの青だが、「ブルーになる」との言い回しがあるように“憂鬱”の意もある。それはムンバイという都会で暮らす事にどこか閉塞感を感じている女性達の心情と捉えられる。その青をスライドさせるかのように印象に残るのが「夜」のシーン。ムンバイだったり後半の舞台となるパルヴァティの故郷の田舎町での夜は、どこか青みがかっているも、それを無にするかのように暗闇に浸す。
インドで暮らす女性が直面する現実。それは厳しくもあり孤独でもある。それでもプラバとアヌ、そしてパルヴァディは、年代は違えどいつしかシスターフッドな関係を築き、逞しく生きていくのだ。
現代インド都市生活を描く傑作
ムンバイの大病院。ベテラン看護師のアヌーはヨーロッパへ出稼ぎに出た夫の留守を守って忙しい日々を過ごしている。若い同僚でルームメイトのプラバは独身。二人は少し齢が離れているがなぜか気があう。アヌーはすでに病院では中核で、若い看護師を指導する立場にある。プラバは仕事の手を抜くこともないが私生活の充実にも熱心で、つぎつぎボーイフレンドを取り替えては遊び回っている。アヌーはそうしたプラバの生き方にかすかに苛立ちを感じるが、生真面目な自分の人生には起こらなかった楽しみを軽々と手にするその姿に、羨望を感じてもいる。あるとき二人が休暇を合わせ一緒に海辺へ旅に出ると、二人の前に不思議な出来事が起こり始める。
2024年のカンヌでインド映画として30年ぶりの大賞にかがやいた名篇です。ムンバイを舞台に現代インドの都市生活がていねいに描かれていて、湿度の高いざらりとした手触りの夜を描写する手つきは、たいへんみごと。二人の旅行が始まってからの、日常生活の延長上にひっそり夢のようなことが混じり込むのも、グル・ダッドやサタジット・レイにさかのぼるインド映画の素晴らしい伝統です。どこの部分もよくできているのですが、とりわけ終盤は嫋々たる美しい余韻を残します。
これも日本で早く公開されてほしい作品のひとつですね。
全120件中、101~120件目を表示