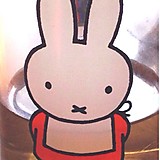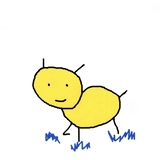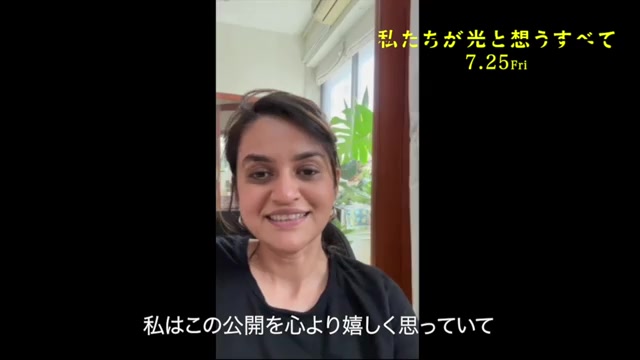私たちが光と想うすべてのレビュー・感想・評価
全120件中、61~80件目を表示
驚くほどつまらない
驚くほどつまらない。
カンヌで賞を獲るような映画。
大都会ムンバイで働くまじめな看護師プラバの夫はドイツに出稼ぎ(?)に行ったきり、ルームメイトの若い後輩は、ムスリムの男性と道ならぬ恋に落ち、プラバと仲が良い仕事仲間のおばさんは法律に疎くて長年住んだ家を追い出されそう。彼女たちの日常描写が延々、単調に続く。ムンバイの都市生活者の生態は興味深かったが、残念ながら話が単調かつつまらない。唯一面白くなりそうだった、プラバに好意を抱く、自作の詩をプレゼントしたり手作りお菓子を渡しながら「おいしくなかったら気まずいから家で食べて」という乙女チックな医師も特に爪痕を残すことなく消えてゆく。
居住の権利を証明する書類を一つも用意できないおばさんがしかたなく故郷に帰るところでようやく「転」が来たかと思ったが、何かが進展するわけでもない。
プラバが、おぼれた男性を救助し介抱していて、唐突に出てくるプラバの夫は一体何?
私には刺さるところがなく退屈で、気づいたら寝てました。何とか最後まで観たが私には合いませんでした。
インド映画で、おとなしめながら、そーゆーシーンがあろうとは!
何も怖くなくなる
こないだ鑑賞してきました🎬
病院に勤める2人の女性がメインのストーリー。
プラバにはカニ・クスルティ🙂
真面目すぎるきらいはありますが、そこが彼女の取り柄でもありますね。
一方で、夫がドイツに行ってからは疎遠に😥
しかし後半、色々あってからの彼女は明るく、希望を見出したようで何よりです。
アヌにはディビヤ・プラバ🙂
基本自由な彼女ですが、かといって悩みがないわけではなく。
イスラム教徒のシアーズと交際しており、親には内緒にしつつまめに連絡を取っています。
病院ではうわさのたねになっていますが、気にしないのが清々しい😀
奔放ですが繊細さもある、魅力的な女性を表現していました。
インド映画はあまり見ませんが、ゆったりとした日常の中で感じる漠然とした不安。
何処か満たされない思い。
それを抱えつつ、変わらない日々にこそ希望を見出していく、そんなメッセージを感じました🫡
インド発のヒューマンドラマとして、おすすめの1本です👍
これがリアル?
インド映画は歌あり踊りありで楽しいイメージがありますが、そうでない作品でも秀作も多く、本作品も歌踊りなしの作品としては出色の出来だったと思います。
あの「花嫁はどこへ」と高い評価を分かち合ったというのも納得でした。
とにかく、インドの生々しいリアルな日常が描かれており、色々と共感したり、なるほどな〜と得心がいくことも多かったです。
都会での生活の楽しさを享受し自らその中に飛び込んでいく若者、夫との関係に煮えきれなさを覚えながら、都会での生活に息苦しさや閉塞感を覚え日々鬱々とする年嵩の女性、この2人の関係性を軸に物語が進んでいきますが、それぞれの考え方や行動に、部分的ではあっても納得できたり、違和感を覚えもし、両者の視点から観ている間は自分の中でも様々な感情が渦巻いていました。無論、日本とは社会状況や、宗教観などが異なるので、所々理解に苦しんだり、疑問に思うところもありましたが、人が思い悩む根本の部分は人種国籍関係なくどこかしら共通してるのではないかな、と思いました。つまり、結局のところは「自分本位」ということ。そこを起点として人と関わったり、認め合ったり、あるいは離れたりして日々光明を見出しながら生きているのだな、とあらためて思いました。人間て複雑ですね。だからこそ色々なドラマがあって面白いのかな?
とまあ、そこは私自身が勝手に感じたことなので、これだから人生は素晴らしい!と謳う人生礼賛映画ではないのですが、凡庸だと思っている人生でも、其処此処に明るさや希望が潜んでいるんじゃないか、と、たまにはこういうことをあれこれ考えさせてくれる作品を観るのも悪くはないですね。それも「脳天気」で楽しい賑やかな映画を数多く作っているインド映画だからこそ(?)、本作品は観る価値があるような気がしました。
頭がクラクラするほど素敵な鑑賞後感
インドの日常を描きながらも、前むきに生きる女性の姿が、心に沁みる
まずはインドの街 ムンパイ、街は活気があるが、何か雑然としていて働く人もどこか無気力。行政的にも問題がありそう、そんな中で、生きる全く性格の違う二人の女性の物語。友人の田舎に二人が同行して行くところから、今までの荒いカメラワークが、優しくなり、ラストまでとても心地よい気持ちになります。宗教観、結婚観、労働者、女性の立場など、問題提起はされていますが何一つ解決しませんが、屋台のイルミネーションのような色とりどりのライティングと海を見つめる女性の姿が彼女らの思いを現してくれています。
フランス映画のようなインド映画
このようなインド映画もあるんだと思ってたら、制作国はフランス=インド=オランダ=ルクセンブルクとなっていた。都会のムンバイと何処かのインドの田舎が舞台で監督もスタッフも出演者もインド人だがテイストが少しフランス映画っぽいてことかと思う。
私は一時マレーシアに住んでたのでイスラム教のマレー人とヒンドゥー教のインド人と中国人が共存はしていても確実に壁があることを身近に感じていたので、イスラム教のパキスタンを敵国としているようなインドにおいては宗教の違い(インドのイスラム教比率は14%で世界3位のイスラム教徒の数があるにも関わらず)を乗り越えて男女が一緒なれるのはとても大変なことなのかと思う。だから、陽気で奔放なアヌは勇気ある恋愛をしてるのである。プラバは見合い結婚したが夫はドイツに出稼ぎに出たままずーっと会えてない。そんな身勝手な仕打ちをされてても夫を想う幻想(溺れた男性を救助し看護するシーン)を見てしまうのが悲しい。
そんな2人の色んな出来事を淡々と描く映画であったが、観た後、何故か爽やかな気分になれた。カンヌの審査員もそんな感じだったのかも、。映画とは不思議なものである。
たぶんこれが世界最先端。それはよくわかる。
パヤル・カパーリヤー監督。西洋的教養と技術を持った人がインドで映画を撮るとこうなるのか、という現代映画詩。
ムンバイに暮らすインドの女性たちのいまを垣間見しつつ、ふわっとそれが幻想と交差する。タイのアピチャッポンとかもそうだけど、未知の国の教養を武器にしたアジア映画ほど強いものはない。何せ見たことのない街や人を見れるのだけで面白いのだから。
ムンバイの湿気溢れる映像、遠くで鳴る車のクラクションの音、背後を流れる列車の光、田舎の海辺、海辺の海の家みたいなところの安っぽい光、とにかく魅力的。都会の問題を引きずって田舎で想像外のものと遭遇する。土着的なものとPOPなものの融合という側面もある。まあ英語のクレジットでもあるが、音楽がとてもかっこよかった。
なんとなくこれの一年後の『ルノアール』はこれに寄せたんだな、という気はした。
絶賛の意味がわからない。致命的に見づらい映画。
物語の内容や登場人物やムンバイや田舎の風景は素晴らしかった。音楽も良かった。それなのに始まって1分もしないうちに見るのが苦痛だと感じた映画は久しぶりだった。とにかく画面が暗い!荒い!電車の中や車の中から見せるムンバイの風景も目で追うのが大変な速さ。おまけに撮影監督はピンボケが大好きらしくやたらピンボケしてくる。せっかくコントラスト強めな美しい色なのに全く活かしきれてないし時に色が薄くなる場面でムードがぶち壊されて集中するのが本当に大変だった。リアリティを追求した結果照明が少ない為夜のシーンは何も見えない。
かなり不潔だと感じるシーンもかなり多めだったが生活感を出す為にやったんだろうなと思う反面インド映画に必要な描写とは何なんだろうと強く考えさせられた。
幾つか考え抜かれたシーンにおーっ!となったのとエンディングはとても好きなタイプの映画だった。残念!
なぜかフェリーニを想起した
話が面白くないですね
邦題に惹かれて、そして、何となく気になったので映画館に足を運びました(カンヌで受賞とか、関係ない)。
でも、退屈だった。つまらないと思った。
もちろん、感じるところはたくさんあった。
アジアの湿気をはらんだ空気や雑然とした街の雰囲気、それに大都市の一隅で暮らす生活者の日常などは、際立ったリアリティーを持って伝わってきました。
ラストシーンも、言葉では言い表せない余韻が胸にひろがった。
けれども、ストーリーが単調で眠たくなった。
むずかしいことはおいといて、やっぱり「話が面白い」って大事なことだと思いませんか?
芸術性においては優れているのでしょうが、娯楽性がほとんどなかった。
プロの批評家でない、僕のような一般の鑑賞者には、やはり「娯楽性」というものが少ないとしんどいところがある。
『あなたの名前を呼べたなら』や『グレート・インディアン・キッチン』なんかのほうが、自分には合っていた。
田舎のインド人、都会のインド人
前作の「何も知らない夜」に比べればはるかに世間一般に向けた平明な物語の手法に寄せているが、それでも不可解な点はいくつか残る。浜辺に打ち上げられた男は本当にプラバの夫だったのか?プラバに「お姉さん」と呼びかけるアヌは途中までてっきり本当の妹かと誤認していた。
前作ほど直截的な反権力のメッセージは強くないけれども、理不尽な結婚や異教徒間の交際などの根深い問題は相変わらず影を落としている。他国との共同制作だから何とか黙認されているのか、社会の矛盾をありのままに描こうとする作者の意図が、政権の統制をかいくぐってかくの如く発表されることは貴重だ。建設予定の高層ビルの看板に投石するぐらいしか憂さを晴らす手段がない現実が悲しい。
希望の光は与えられるものではなく、自分たち自身が思い描いて手に入れるもの
前半の舞台はムンバイ。夢を見て田舎から都会に出てきたはいいが、夢に敗れ、厳しい現実に直面する人も少なくない。それでも幻想を追いかけ続けなければ、自分が自分に負けたように感じてしまう、というのはインドに限らず、何処の国でも同じであろう。
主人公はムンバイで看護師をしているプラバとアヌの二人の女性。プラバは親の決めた相手と結婚したが、結婚後ほどなくしてドイツに出稼ぎに行き、ほとんど音信不通状態。アヌの恋人はイスラム教徒で、異教徒との付き合いを親が認めるわけがない。
地上げ屋に住処からの立ち退きを迫られ、故郷の海辺の村に帰ることにしたパルヴァディについて行ったプラバとアヌは、そこで自らの人生に改めて向き合う……。
人と人を隔てるものには、国籍、人種、宗教、性別、言語、そして経済格差などがあるが、その障壁を乗り越えさせてくれるのが愛。
多民族で多宗教で多言語で、なおかつ家父長制とカースト制による差別意識がまだまだ根強いインド。女性たちが自分らしく生きるための自由を渇望しても、ままならないことが少なくないはず。それでも力強く人生を切り拓いていこうとする女性たち。
希望の光は与えられるものではなく、自分たち自身が思い描いて手に入れるものだというタイトルに込められたメッセージは美しい映像の中で一段と輝きを増しているようだ。
魅力的なタイトル
帰り道にインドの勉強をして思い起こすもの。
最初は不夜城に見える高層ビル群を背に生き抜く女性を描いているかと思いきや、光が差し込んだのは闇の多さ。
光と影をわざとチラつかせて色んなものを見せてきたね。
望もうが望まないが関係なしに増えていく人口。
夫婦でもない男女が常に世間の目を気にする空気感。
親族が絶対な環境に格差以外何物でもない社会にエネルギー事情も宜しくない……。
観ている途中でパラレルワールドにでも迷い込んだもう一つの日本の姿にも思えたよ。
だからこそあのiPhoneで照らす環境や個性の塊の着信音で笑えてくるし皮肉でもあるよね。
対アメリカのスタンスから見ると。
長いものや新しいものに弱い日本人の性質のおかげで今日の日本がある訳だから。
当たり前に広がる星空に弱々しい色付き電球。
どちらもこれからのインドの闇を討ち破る光になりうるのか?
難しいね。うん。
生きているうちにそんな若い世代が世界を揺り動かすムーブメントを起こすのを期待してます。
すごいCPR
ままならない都会暮らし
ムンバイの病院で働く2人の看護師と、同病院の食堂で働く女性の葛藤と再生の話。
夫はドイツでお仕事中のベテラン看護師と、彼女とルームシェアしているイスラム教徒の彼氏と内緒で交際中の後輩看護師から始まって、亡き夫と暮らしていた住居の立ち退きを迫られる食堂のおばちゃんへと展開し、3人の現在の暮らしや悩みをみせて始まって行く。
新人だかインターンとの指導をしつつ、帰ったら後輩の面倒も?
そして後輩ちゃんは金が無いと言いつつ秘密のデートに忙しく使えるツテは使わなきゃの今どき女子?
そしておばちゃんは法律というか現代社会の常識に疎く証明出来ないのに強きに主張。
みんな中々大変だけど、気づけばロードムービーに…と思いきや、海辺の村で恋愛映画!?
インド映画でこういう欧州映画の様なテイストのものをみたのは始めてかも?という意味では、意外だし悪くはないのだけれど、インドの社会情勢とか宗教観とかに明るくないからかそういうものなのか…ぐらいにしか感じられなかったし、自分の苦手な恋愛色がちょっと強くて合わなかった。
全120件中、61~80件目を表示