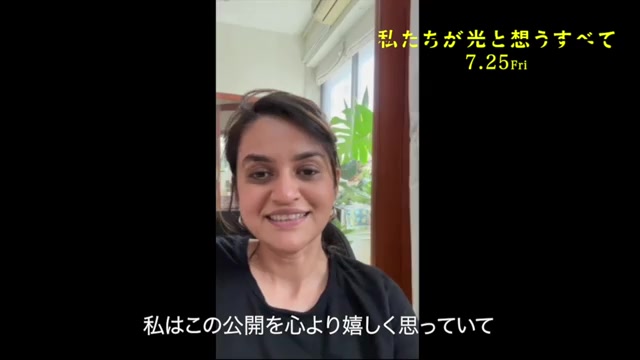私たちが光と想うすべてのレビュー・感想・評価
全121件中、1~20件目を表示
ムンバイに生きる市井の女性の心模様を繊細に綴る日常系インド映画
オープニングからの数分、湿度を感じる雑踏とそこで生活する人々の数節の言葉で、訪れたことのない街ムンバイのイメージが胸の奥に広がった。
日常系インド映画とでも言おうか。説明的な台詞を極限まで排した脚本とキャストの自然な演技には、パヤル・カパーリヤー監督がこれまで手掛けてきたジャンルであるドキュメンタリー映画に通じる雰囲気が漂う。
現代インドの女性たちの生活文化や恋愛観をほとんど知らなかったので、新鮮に感じる場面が多かった。
考えたら自然なことだが炊飯器を使うんだなあ、とか(ちなみに90年代にインドに炊飯器を普及させたのはパナソニックだそうだ。それまではガスか薪で炊いていた)、好きな相手にお菓子はともかくポエムを贈る男性って、インドの女性にはウケるのかなとか。
彼女たちの置かれている環境も社会的・宗教的背景も私自身とは随分違うのに、彼女たちが抱く感情には不思議なほど垣根を感じなかった。
その理由は、特に主人公のプラバについて顕著だが、彼女の心の揺れについての説明的な描写がほとんどないからだと思う。彼女が働く姿、アヌの態度や炊飯器を抱く姿を見て観客はプラバの心境を想像する。もちろんそういった描写には監督の意図が内在するが、観る側の想像と解釈の余地が大きいということは、そこに観客自身の価値観が映り込みやすくなるということであり、垣根を感じなくなるのは自然なことかもしれない。
一方、奔放なアヌの行動についてはちょっとハラハラさせられた。ヒンドゥー教信者がムスリムと交際することは社会的にNGのようだったが、どれほどのレベルのタブーなのか、アヌの様子だけでは測りかねた。親から交際を反対されており人目を避けてデートしていることはわかったが、割とオープンな場所でキスしたりもしてたし……インドの観客ならこの辺は肌感で理解するところなのだろうか。
タブーレベルに迷いながら観ていたので、終盤ラトナギリの海岸で誰かが救助された場面では、もしかしてアヌとシアーズ(アヌの彼氏)が心中したのだろうか、実は二人ともそこまで思い詰めていたのだろうかと嫌な想像をしてしまった(もっともイスラム教では自殺は禁忌らしいので、これは見当違いの予感だったのだろう)。
この遭難者、当初はプラバと全く面識のない男性なのに周囲が夫と勘違いしている、という様子だったが、いつの間にかプラバは彼と夫婦として対話していた。この辺、観ている間は正直よくわからなかった。あれ? さっき勘違いされてるとか言ってたよね? ドイツから戻ってきてたの?
恥ずかしながら後でパンフレットのコラムを読んで、このシークエンスが「幻想」だったことを確認した次第だ。ここはもうちょっとわかりやすくしてもらってもよかったかなと思う(読解力のない人間の勝手な言い分です)。
とはいえ、それまで社会的な慣習に押し付けられた形だけの結婚に甘んじてきたプラバが、この対話で自らの状況にようやくキッパリNOと言えたことはよかった。
彼女は、職場の医師にフランクに接するアヌを「誘惑している」と非難したこともあったが、後で思えばそれは彼女自身が、自分を抑圧する古い価値観に無抵抗になってしまっていたことの表れだったのではないだろうか。
ラストでプラバはアヌとムスリム彼氏の交際を受け入れ、カラフルなイルミネーションに彩られた海辺の店でスタッフの子が踊る(典型的インド映画とは別系統の作品とわかっていても、インド映画のDNAに触れたような謎の安心感)。自己肯定と受容が重なりほのかにあたたかい気分になるエンディング。
ひとりの女性の小さな心の成長をたどる繊細なドキュメンタリーを見たような気持ちになった。
無数の光によって彩られた街の神話
この映画の虜になるのに5分とかからないだろう。映し出されるのは大都市ムンバイ。繊細な光で照らされた街並みと喧騒、音のコラージュ、人々の言葉が相まって、街の鼓動を親密に響かせていく。とりわけ通勤電車の窓から望むビル群の夜景は無数の星が点々と輝く宇宙のようだ。それらは美しくとも少し孤独で悲しげな生命の集合体に見える。本作は当地で暮らす地方出身者の胸の内を探究しつつ、同じ病院で働くルームメイトの看護師らが心を寄せ合い生きる日々を紡ぐ。片やムスリム青年との恋愛に夢中な年下のアヌ。片やお見合い結婚した夫と長らく連絡を取り合っていないプラバ。真逆の性格の二人が悩みながら自分の幸せを精一杯に模索する姿を、本作は安易な価値判断を下すことなく、ただただ柔らかく見守る。時に本能の赴くまま、時に友情と絆、マジックリアリズムを加味しながら進む歩調が心地よく、全てを暖かく包み込む監督の視座にすっかり陶酔させられた。
「花嫁はどこへ?」と並走する、インド発女性映画のトップランナー
2024年のカンヌ・コンペ部門でグランプリを獲った話題作。念のため、カンヌの最優秀賞はパルムドールであり(昨年の受賞作は「ANORA アノーラ」)、グランプリは準優勝に相当する。この年のコンペ出品作を振り返ると「エミリア・ペレス」「憐れみの3章」「メガロポリス」「アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方」「サブスタンス」など力作がひしめいており、これらをおさえての銀メダルと考えれば「私たちが光と想うすべて」への期待も高まるのではないか。
インド第2の大都市ムンバイの病院で働く3人の女性たち。看護師のプラバは既婚者だが、見合いで結婚した夫がドイツで働いていて疎遠になっており、年下の同僚アヌとアパートに同居している。アヌはイスラム教徒の青年と交際しているが、インドではヒンドゥー教徒が大多数であることから親や周囲から猛反対されるのは明らかなので、恋人のことは隠している。病院の食堂に勤める寡婦のパルヴァディは自宅から立ち退きを迫られているが、プラバが親身になり助けようとする。
「女性たちの友情」と単純に紹介されることもあるが、世代も境遇も違う3人の彼女らの繊細な絆や連帯感、穏当なシスターフッドの物語と評すべきではなかろうか。前半は都会を舞台に、プラバとアヌ、プラバとパルヴァディの関係がそれぞれ描かれるが、後半のパルヴァディが故郷の村へ帰る際にほかの2人が手伝いで同行する展開が、海辺のロケーションも相まって開放的で心地よい。
監督兼脚本のパヤル・カパーリヤーも女性で、本作で長編劇映画デビューを飾ったムンバイ出身。今年5月開催の第97回アカデミー賞のインド代表を「花嫁はどこへ?」(日本では2024年10月公開)と競うも選ばれなかったが、両作ともに女性監督がメガホンをとった女性映画である点も共通する。当サイトで「花嫁はどこへ?」の新作評論を担当し、「インド映画の2大潮流として、複数の娯楽ジャンルを混ぜ合わせた商業的な“マサラ映画”と、マサラ映画の特徴である歌とダンスのシークエンスを排した現実主義的な“パラレル映画”」と紹介したが、こちらの「私たちが光と想うすべて」もパラレル映画の流れ。インド固有の階級制や宗教事情を背景にしつつ、女性の自由や自立という普遍的な題材を繊細な感性で扱っている点において、世界で、そして日本でも評価されてしかるべき好ましい佳作だ。
ムンバイドリーミング
精神は誰にも支配されない
インド社会の複雑な構造 結婚制度、宗教的緊張、階級や経済格差 を通して、人間の尊厳や自由を問いかけてくる。
プラバは『運命からは逃れられない』と言う。運命に縛られながらも、それでも希望や解放を夢見る姿は悲痛。
精神的な自由『光』を求める姿そのものが、抑圧的な状況の中の『光』なのだろうか。
ラストが心に刺さる
五感で感じるもの
美しいタイトル。
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
何かを教えてもらおうとでも思ってたのか。始まりはあまりに厳しい。同じような人生は何万もあるだろうと思わせる。いなくなったってこの街は何も気づかない。足掻いたところでかなわないとわかってる。表情が無になっていく。最初は登場人物の表情の変わらなさに、何を考えているのかわからなかったが、あぁ、なるほど、といつの間にかこの世界に引き込まれていた。
自由を求め行動しているようで、踊らされていただけかもしれない。ただ、自分が選んだことを認めてもらいたかったのだと思う。
そこに一人ひとりの人生がある。その尊さが光となり、最後のシーンと映画のタイトルとともにスッと心に入ってきた。
まずはタイトルが素晴らしい。 数ある光を捉えたショットもタイトル負...
素晴らしい映画だった。
良作と聞いていたので、期待して鑑賞。
期待以上に素晴らしかった。
インドの昔ながらの習慣に自分の道をふさがれそうになる、アヌとプラハ。
看護婦の同僚として働いているが、それぞれの道を行く。
アヌはイスラム教徒と恋人関係にあるが、異教徒との付き合いということで周囲の目は厳しい。その中でも自分の道を模索し、あの洞窟に行き、新しい自分になっていく。この風景は素晴らしかった。
一方、ドイツに働きに行ったきり音沙汰のない夫(家族の勧めで結婚させられた)のいるプラハの方は、マジーノというDrからとても奥ゆかしい詩や言葉を贈られるが、結局断ってしまう。そして田舎にパルヴァティを送って行ってるときに偶然海でおぼれた夫を救急医療で蘇生させるが、結局夫とも別れる。
そしてラストの自由にあふれた素敵な景色。
この先のインド女性の未来を描いているような、素敵な映画だった。
よかった
演技とは思えない自然さで、場面も本当にその場にいるかのような臨場感で、インドのムンバイにいるようだ。コンディションの調整に失敗して中盤海辺の町に行く手前でウトウトする。自立した女性ばかりの話で、女性がひどい人権侵害を受けてなくてほっとした。ただ、海辺の町で泊まっていけというから泊まると床で寝かされるし、家自体がバラック小屋のようだし、蚊がいそうでつらい。自分が若い時ならそんな環境も楽しめたかもしれないけど、もう年寄りだから嫌だ。布団かベッドで寝たい。お酒を飲んで夜の9時に寝たい。
インド初の女性監督による作品らしい…
インド映画といえば、お気楽なダンスとアクション映画をイメージするけど、本作品は全くちがった。
インド初の女性監督の作品と聞いてなるほどと思った。
インドも相当な男性優位の社会のようである。
インドの宗教やカーストなどの社会の詳細を知っていればもう少し没入して鑑賞できたのではと思うと、自分の知識のなさが残念である。
市井のインド女性のことなど考えたこともなく、お気楽インド映画を楽しんでいたことに胸が痛む。
インドののGDPが世界第4位だとか5位だとか言われているけれど、国民一人あたりのGDPは最貧国のレベルの究極の格差社会(階級は特権という看板の家族の肌の色は白く、この映画の大半の登場人物の肌は黒い)でなおかつ男性優位社会で、このような映画が作られて、世界的に評価されたことは大きな意味のあることだと思う。
先週、駆け込みで観てきた。 歌も踊りもないインド映画で、ムンバイで...
インド映画の新しい傑作
ケララ州は教育に熱心で都会に行く若者が多いが、主人公と後輩の看護師とイスラムの恋人、同僚医師はケララ州からムンバイに出てきた優秀な人々のようだ。
キスシーン、着替える場面、ドイツ製炊飯器に足を絡めるシーン等性的な描き方はフランス共同製作だから可能になった面もあるが、濱口竜介監督のドライブマイカーに影響を受けているとも言えると思う。
多言語国家、トイレ問題、宗教と婚姻の問題、等インドが抱える課題を盛り込んでストーリーが進む。
舞台となる病院は堕胎手術専門のようで、胎盤、パイプカット、等の精神的に辛いシーンが続き、娯楽はダンス映画鑑賞が描かれる。
主人公はドクターや新人ナースから信頼されている一方、堅苦しく付き合いの悪い、勃起した患者をしっかってEDにしてしまうような人格と笑われている。
同居する後輩ナースの奔放な性格に主人公が徐々に変化して行く。
猫の妊娠をドクターと検査し、その後怒りの感情を唯一発散する場面と謝罪するシーン以降は対等な関係になって行く。
同僚のドクターからノートに書かれた詞とお菓子で告白されるが返事のシーンが無く、ディレクターカット版が公開されたらその後の二人の関係が描かれていると思う。
主人公がドイツへ電話した時に女性のアナウンスが流れ、この電話は現在使われていないようだ。
富裕層はベンツ、貧乏人は日本車と対比される。
あえて他言語で撮る監督もいて、ネイティブな言葉の細部にこだわりすぎて作品のテーマが曖昧になるのを避ける意図があるそうだが、本作はヒンディー語、マラヤーム語、マラーティー語の三言語で描かれているとも言える。
ケララ州の名監督、アラヴィンダンとゴーパクリシュナンの作品は幻想的なストーリーが盛り込まれていることが多いので、主人公が人工呼吸で救った男と夫が重なるシーンは両監督の影響があると思う。
主人公の表情がガンダーラ仏像と敦煌壁画のように見える。本作のテーマと主人公を演じる俳優が持つ雰囲気がピタリとはまり、傑作が生まれている。
ムンバイと東京、幻想、光
すごく良い映画だった。
人が多くて仕事がある都会、ムンバイと今わたしが住んでいる東京という街がリンクして、異国の風景を見ながらも自分と重ね合わせて見ることができた。
「『どんなにどん底の生活でも気張ってやっていく』それがムンバイの気概だ」
「幻想をみていなければおかしくなる」
※セリフはニュアンスで正確では無いと思います
私が好きな青森のねぶた祭りと重なって見えたお祭りのシーンも、村の海と似ている東北の海辺の風景も、私にとっての生きていくための幻想。
遠くにいるパートナーを想うことは光だけれど、迎えに来られて「来てくれ」なんて言われたらそれは光ではなくなってしまう。私には私のキャリアと人生があるし、遠く離れているからこそ想えるのであって、近くにいたらそれは現実になって苛立ちや困難に変わってしまうから。
久しぶりに映画館で登場人物の恋愛感情にも共感することができました。
私たちは光を感じ幻想を抱えながら生きている。私にとっての光や幻想ってなんだろう。
そんなことを考えながら帰る素敵な夜をもらいました。ありがとうございました。
作品情報の写真の意味
作品情報の写真は炊飯器を訝し気に見ているシーンだったのかと映画を観始めて分かり、可笑しかった。ヒロインらのやりとり、夜景とBGMが心地よかった。色々辛いことやめんどくさいことあれど、最後の4人でテーブルを囲むシーンで一息という感じで良かった。閉館予告のシネマカリテで観ることできたのも良かった。
全121件中、1~20件目を表示