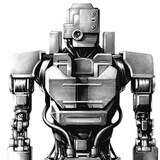サブスタンスのレビュー・感想・評価
全685件中、1~20件目を表示
自覚してエンタメ界に身を投じた者がルッキズム、性差別を批判する声に、喝。
オレの娘はダンサーにあこがれ、韓流アイドルを真似てダンスの練習をしている。オレからすると、韓流アイドルなんて、と思うわけだが、本人は(こちらから見る限りは)本気だ。
エンタメ界が存在する(というより、人が「美」に価値を求める、快楽を求める)以上、見た目(舞台や芸能人)の華やかさにあこがれるのは少なくともオレが生きている限りは変わらない。そしてどんなに見た目がよくっても、若いときはもてはやされても、自身で自分の価値を積み上げることが非常に困難な世界であることは、よくわかる。
オレからすると、応援する気持ちはあるものの、やめとけ、の話だが、オレが言う前に彼女の成長過程でエンタメ界の「価値観」が評価を下す。そして評価されたとしても、そこからはまたさらにその価値観の中で生きてくことになる。とオレが言うまでもなく、数えきれないほどの「イケメン男子」「美少女」の無念の上で成り立っている。逆に勝ち取った、とは外野からの勝手な評価でしかない。当たり前だが、勝者なんて、外野が決めることではない。
なんだが、娘語りから入ってしまったが、美しいもの、強いもの、に惹かれ、憧れるという「本能」、人間の「本質」でエンタメ界に限らず、人間社会が成り立っているという、当たり前の根本に対し、「ですよね」と映画オタクがその引き出しを総動員した、
「サブスタンス」
・
・
・
とてもじゃないが、オレの価値観で「衰えている」とは思えないムーアのエアロからわかるように、プロデューサーのクビ宣言も、理不尽なのは、こちらの意見。力あるものの(理由は末端の人間には分からない」一声で人事は変わる。クエイドの食べ方は、「醜い」とかそういうことではなく、そもそもキレイな食べ方って何?という視点もある。ムーアのフランス料理教本からの料理がぐちゃぐちゃなのも、フランス料理のお上品って何?
ムーアのクローズアップの多投も、皺の醜さの強調ではなく、それすら「美しく」も見える。
クアリーのエアロは圧倒的な鍛錬の上に成り立ってあり、その健康的でもあり、セクシーに感じるのは、当たり前で、監督もそれを「皮肉」を包みつつも、やっぱりすごいよね、ですよね、というほど、エアロシーンがたびたび描かれる。(さすがにお尻から変な映像が出たといってスタッフが巨大な画面でクアリーのお尻に注目するのは笑った)
オレらの生活圏においては、ルッキズムが間違ったとらえ方で、学校や職場ではばかることは断固として忌み嫌う。
しかし、ことエンタメ界ではルッキズム批判はおかしな話。
演じたムーアも言っている。「私は決して被害者ではない」と。
本作は、ただそこに生涯をかけてしまった、自身の価値観をそこのみにしか置けなかった主人公の悲劇と、血しぶきの救済。
なかには、親から連れられてきたのか、自身で臨んで参加したのか、少女も洗礼を受ける。
ましてや、性差別なんかは描かれておらず、「薬」を紹介、利用したあの男も本能に忠実。一方、連絡先を水たまりに落としたメモを渡す、元同級生のあいつが一番ダメな奴。
(そんなメモを取っておいた)そんなダメな奴へのデートへの準備で奮闘する主人公の価値観はすでに狂ってしまっているのだが、笑えない人が多いと思うし、このシーンが「若いころ」のオレに刺さる。
終盤、自身の顔の写真を切り取り、鏡を前にする。ブルース・リーの「死亡遊戯」(’78)を思い出し、笑った。
「死亡遊戯」はリー死去のためで苦肉の策だが、本作においては、CGそして整形を茶化している。同じく、ムーアから見た目が別の、今風にアップデートされたクアリーが誕生するのも整形ブームへの茶化しなんだろうな。
若さと美の追求の行き着く先
若い後輩と一緒に写った写真を見た時
「あー歳をとったな…」と思ったり
20代の頃の自分の写真を見た時
「あの頃は肌艶も良くて、今より痩せてたな…」と思ったり
いつからか歳を重ねるのが嬉しくなくなり、若さと美しさを渇望する時間が長くなる。
きっと誰しも一度は美と若さを手に入れたいと思ったことがあるんじゃないかな。
私も絶賛見た目の老いに日々抗い中だ。
こんな私ですらそうなんだから、それが商品価値にもなってしまうエンタメ界では尚更、美と若さ=自分の価値に感じてしまうのもわからなくはない。
この映画は、そんなルッキズムに囚われる現代人に警告を鳴らすかのような劇薬作品だった。
グロテスクなシーンがとても多く、苦手な人にとっては目を瞑りたくなるシーンも多いけれど、命を弄ぶようなスプラッタホラーではない上に、魅せ方がとても上手なので不思議と見れる。
カメラワーク、音の使い方、色彩、サブスタンスのパッケージから説明書のフォントまで、細部まで監督のセンスが光っていて、世界観の統一が気持ち良い。
後半まではほぼセリフらしいセリフもなく、ひたすら主人公のエリザベスやスーの表情で物語が進むが、セリフがなくても痛いほど感情が伝わってくるのが秀逸。エリザベスの化粧のシーンなんて、気持ちが分かりすぎて後ろから抱きしめたくなった。
最初から最後まで全く飽きさせることなく、次の展開はどうなるんだとノンストップの140分で大満足。始まりのハリウッド ウォーク オブ フェイムからすでに「あ、好き」と思ったけれど、ラストがこれまた最高だった。
私が「サブスタンス」を手に入れたらどうするだろう…。
これからどんどん老いていく自分が、若さと美だけが価値にならないように、自分を愛せる部分をたくさんつくっていきたいなと思った。
お仕着せの価値観と行き過ぎた執着がもたらす地獄
デミ・ムーアのまさに体を張った狂気の演技に圧倒された。
名優はもちろん綺麗に撮られることより表現を優先するものではあるが、顔や背中の瑞々しさを失った肌を強調するカメラワークで撮られつつ若い女優と対比させる演出で演じるのは、女性としてはなかなか勇気のいることだ。
もっとも、そういった勇気を必要とする価値観や社会の風潮こそ本作の批判の対象なのだろう。だから私の「女優なのに体を張っててすごい」という稚拙な感想自体、コラリー・ファルジャ監督から見れば唾棄すべき古臭い価値観に毒されたものなのかもしれない。
とはいえ、マーガレット・クアリーが眩しすぎる。
かりそめの空疎な分身だが、若さを失った故に表舞台から退場させられたエリザベスにとってはあまりに蠱惑的な存在。クアリーが美しいからこそ、エリザベスがサブスタンスのルールを破り狂っていく気持ちもよくわかる。
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」のプッシーキャット、「哀れなるものたち」のフェリシティなど、短い出演時間でも印象深い少女の名残を感じる愛らしい顔立ちと完璧過ぎるスタイルが、あやかしのクスリで生まれたスーにぴったりだ。
デニス・クエイドの演じたハーヴェイ(……ワインスタイン?)とエリザベスの隣人、ハーヴェイが連れてきた白髪頭の株主たちは、若くて美しい女性しか人間扱いしないという有害な男性性の象徴として登場する。
ハーヴェイは吐き気がするほどドアップのカットで登場し、エビ料理を大袈裟なほど汚く食い散らかすなど、生理的嫌悪感を煽るかのようなデフォルメをほどこして描かれる。「女性は若く美しくあってこそ存在意義がある」というくだらない価値観はこういうレベルの奴らが押し付けてくる戯言ですよ、とでも言わんばかりだ。若さ偏重でエリザベスを切るお前自身も脂ぎったおっさんだろと思わず言いたくなるような、クエイドの怪演がいい。
冒頭のウォークオブフェイムを使ったエリザベスの状況説明は、簡潔ながら十分な情報があって上手いなと思わせる。その後も終始テンポがよく、展開から眼が離せない。
彼女の弱さゆえに事態が混沌としてゆく流れは想像通りだが、落とし所が予想出来なかった。まさかあんな状態になってあそこまでブシャーと撒き散らすとは……
ビジュアルのグロさと若さへの執着に負けた代償の恐ろしさに震え上がる一方で、笑える瞬間も結構多かった。
ハーヴェイの誇張された愚かしさもそうだし、騒音のクレームを入れに来た隣人の豹変具合、プロの職人並のDIY能力でバスルームにドアを設置するスー。声をかけてきた昔なじみ(多分本作唯一の善良な人間)に会いにいくのにド派手なおめかしをするエリザベス(この直後のデミの演技がすごい)、完全に老婆形態になったのにスーとやりあう時はめっちゃ素早いエリザベス(笑)。
モンストロと化したエリザベス&スーがショーの舞台に出る場面で「ツァラトゥストラはかく語りき」が流れた時には、2001年宇宙の旅かよ!と笑ってしまった。
この交響詩を作ったシュトラウスがインスピレーションを受けたニーチェの同名の著作に出てくる「超人」の概念は、既存の価値観に囚われず新たな価値を生み出す存在であり、人間が目指すべき姿として定義されている。
女性の体は2000年以上にわたり見る者の目によって形作られ、支配されてきたとファルジャ監督は言う。考えてみれば、そのように女性を縛ってきた古い概念の否定という本作のテーマと、この曲の由来はよく馴染むのではないだろうか。
私は変わっていない私のままだと、「モンストロエリザシュー」は叫ぶ。悲鳴をあげる客席の男女と同じ恐怖に見舞われながら、彼女の叫びに観客の自分までも試されているような気持ちになった。
最後に、崩れたモンストロからこぼれ落ちた異形の姿のエリザベスは、自分が賞賛され愛されていた頃の象徴であるウォークオブフェイムに辿り着き、ほっとした表情で息絶える。融解した彼女の痕跡はあっという間に干からび、翌日には一瞬でバキュームクリーナーに吸い取られ消えてしまう。
最後まで「他人が女性に望む理想の外見」に振り回された彼女の物語を、「こんな生き方はくだらない」と一蹴するような皮肉の効いたラスト。オープニングと同じシンプルな表現で、ピリッとした落とし方が小気味いい。
デミ・ムーアの執念が視覚効果を凌駕している
最先端の再生医療、サブスタンスの力を借りて、若々しく生まれ変わろうとしたベテラン女優のエリザベスが辿る、再生と崩壊のカタストロフ。この映画の肝は、エリザヘスがCGIで若返るのではなく、上位交換によって全く異なる個体であるスーとなって、エリザベスの背中を破って出現するところ。さらに、両者はそれぞれのコンディションを維持するために1週間毎に入れ替わらなければいけない点にある。このアイディアは確かに斬新で、従来の若返りに関する映画とは一味違う。
スーがルールを破ったことで両者の肉体に訪れる衝撃的な出来事は、視覚的には『遊星からの物体X』('82年)だったり、デヴィッド・クローネンバーグだったり、または『キャリー』('76年)だったりする。しかし、エリザベスを演じるデミ・ムーアの肉体が、特殊メイクや人形を用いてほぼ別物に変化した後も、よく見ると、依然としてデミ・ムーアであり続けるところが凄い。そこに、メイク担当の気配りと言うか、エリザベスの苦闘に自身のストーリーを重ねつつ演じたであろうデミの執念を感じるのだ。
個人的には、ハリウッドで整形美容の是非論が取り沙汰された1990年代初頭に製作された『永遠に美しく・・・』('92年)に近いと思うが、映画のテーマをやはり当時としては最先端の特撮技術と笑いによって具現化した『永遠~』とは異なり、女性に向けられる性差別、年齢差別、ルッキズムの問題が過酷な分、本作が発するメッセージはシリアスで強烈だ。さて、『サブスタンス』も『永遠~』と同じくカルトムービーとして生き残り続けるだろうか?
“本質(substance)=内なるモンスター”を解き放ったファルジャ監督
外国映画の原題がシンプルな1ワードのみの場合、往々にしてダブルミーニングとなっている(米元副大統領チェイニーを題材にした「Vice」に「副」と「悪徳」の意味が重ねられていたように)。本作「サブスタンス」(The Substance)において、第一義は新たな自分を生み出す「物質」を指すが、substanceには「本質」の意味もある。フランス人女性監督のコラリー・ファルジャはあるインタビューで、「女性は若く美しくあるべき」という旧来の考え方に基づき隠すよう教え込まれてきた「老いつつある不完全な自分の一部」が自身に内在する“モンスター”であり、解き放たれたモンスターが女性の肉体を破壊し戯れることで、女性たちを抑圧し束縛してきたものを吹き飛ばしたかった、といった趣旨を語っていた。破壊されるべき醜い怪物とは、他者に美しさを求める身勝手な欲望=人間の本質そのものだ、とも読み取れる。
ファルジャ監督は2017年に「REVENGE リベンジ」で長編デビューした後のインタビューで、自作にオマージュや引用が少ないのは観客の没入を妨げるからだ、とも語っていた。だがこの第2作「サブスタンス」では考えを改めたのか、わかりやすい引用や参照に満ちている。特殊な手段で永遠の若さを手に入れようとする筋は、オスカー・ワイルド原作「ドリアン・グレイの肖像」(映画化・ドラマ化ともに複数回)やロバート・ゼメキス監督作「永遠に美しく…」。ボディホラーの要素はジョン・カーペンター監督作「遊星からの物体X」、デヴィッド・クローネンバーグ監督作「ザ・フライ」、ブライアン・ユズナ監督作「ソサエティー」など。スタンリー・キューブリック監督作からは、「2001年宇宙の旅」の光の回廊に似た視覚効果と交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」のBGM、「シャイニング」のシンメトリー構図やインテリアの配色。大量の血しぶきは「シャイニング」に加え、ブライアン・デ・パルマ監督作「キャリー」も想起させる(ちなみにこの2作はスティーヴン・キング原作という共通点も)。
20世紀の巨匠たちが手がけた傑作群への言及を散りばめつつ、表層的なマッシュアップで終わらせず、自身の実体験に根差したオリジナルなストーリーに消化/昇華させた点がファルジャ監督の偉業であり、「サブスタンス」が私たちの心を揺さぶる理由でもある。自身のキャリアに重なるような落ち目の元大スター役を引き受けたデミ・ムーアと、完璧な肉体を表現するため人工の乳房を装着したマーガレット・クアリー、2人の熱演に依る部分ももちろん大きい。過激な表現とブラックユーモアをまといながらも、女性の真の解放とは何かを問いかける力作であり、ルッキズム的傾向を無自覚に持つ多くの観客は冷や水(と血しぶき)を浴びせられたように感じるはずだ。
ある種の中毒性を持った最高の劇薬
これはもう破壊力満点。かなり重いパンチを腹に決められた気分だ。ファルジャ監督の『リベンジ』もぶっ飛んだバイオレンス・アクションだったが、今回はさらに壁をぶち破り未曾有のゾーンに突入した超怪作と言っていい。「substance」は「薬物」や「実体」などの意味を持つが、なるほど、本作は若さを求めて薬品に手を伸ばす欲望の暴走劇でありながら、真っ二つに引き裂かれていく壮絶なアイデンティティのドラマでもあるわけだ。ある意味、悪魔の契約。大人のファンタジー。大量の血糊と特殊メイクを伴う作品ゆえ、この手のジャンルが苦手な人はくれぐれも注意願いたいが、しかしある程度の描写なら許容可能な人ならば、過激さが振り切れ、もはや歓喜にまで昇華する瞬間を何度も感じるはず。特に幾つかの名作映画すら思い起こさせる終盤は「やりやがったな!」と笑いが止まらなかった。全身全霊、体当たりで演じたムーア&クアリーを心から称えたい。
前半4:後半2の採点
エログロ。後半はホラースプラッター。
あらすじを見て、面白そうだと視聴したが大誤算。
現代のルッキズムとアンチエイジングを風刺した映画なのか?
ラストシーンを冒頭シーンに帰着させて、巧くまとめているのかもしれないが、皮肉が効いているのかも分からないくらいグロい。不快レベルの気持ち悪さ。
2人で1つとか言いながら、本体と分身で全く別人格。分身が活躍する記憶は、本体に宿らない。入れ替わって分身に栄養を与える度に、本体は大ダメージ。分身がルールを逸脱すると、本体は異常な速さで老けていく。分身をコントロール出来ないのに、本体が身を削って続けるメリットがあるとは思えなかった。
サブスタンスに誘った若い医者の本体が、カフェの老人だと判明するが、医者が若返ったところで??あと注射痕デカすぎ。
マーガレット・クアリーの美しい肢体は必見だが、何か食べながら見るのはやめた方が良い。
Pump it up.Σ(゚ロ゚ノ)ノ
デミー・ムーアとマーガレット・クアリーが熱演。映画「ゴースト」あれから30年以上経っても相変わらず美しい大物女優と、その若さを分けてくれ(笑)と思う程、これまた可愛いマーガレット・クアリー様31歳。二人とも本当に若い。凄い!((( ;゚Д゚)))
年齢相応とか思わす、例えばエリザベスの冷蔵庫にあったチキンとかキッシュ、ビタミン剤だけの朝食とか運動とか努力は続けるべきなんだと思いました。(笑)
笑ゥせぇるすまん×バイオハザード的な何か
いやぁまいりました。面白かったです。
予告編が面白そうで、前から観てみたいと思っていたのをようやく鑑賞しました。本作140分超えですが、とにかく無駄がない。一切飽きることもなく、間延びもせず、強烈に走り切ったような印象です。
ポイントはいくつかあると思いますが、まずストーリーですね。いわゆる「喪黒福造」はいないのですが、プロットはよく似ています。心の隙間を抱えた主人公が、必ず守らなければならないルールのもと不思議な力を手にする。ルールの中では幸せでいられるのに、どうしてもそれを守ることができない。結果破滅が訪れる。まさしく、ですね。本作に登場する謎の物質「サブスタンス」。誰が何のためにあんなものを生み出したのか。壮大な実験なのか、はたまた大富豪の道楽的な何かか。結局何も明かされないのですが、出所や由来が不明なことの不気味さも相まって、面白いストーリーでした。
精神のみならず、肉体までバイオハザードの如くモンスター化していくデミ・ムーアの怪演が大変印象に残りました。特にフレッドとデートに行く前のシーンは、セリフが一切ないのに心情をカメラワークと表情だけで完璧に表現していて監督のテクニックというか執念みたいなものを感じました。ストーリー的にもあそこが分岐点で、本体からの乖離が始まります。スー役のマーガレット・クアリーもまさしく陽キャで健康的な美の象徴として素晴らしかったです。陽キャなままで終わらず、「ひとつ」である彼女にもしっかり破滅が訪れるわけですが、歯のシーンはゾクゾクっとしました。
書いていて思いましたが、ラストシーン。しっかりバッドエンドなんですけど、主人公の晴々とした様子が印象に残りました。彼女なりに、最後の最後輝けたんでしょうか。どんな状況にあっても、自分がどう感じるかによって救いは得られるという深み的なものを感じつつ、複雑な余韻が残りました。
最後に、二人ともそんな脱がなくてもいいのにってくらい脱いでまして、程よいエロが加えられている点も飽きさせない工夫でニクイですね。マーガレット・クアリーは本作以外でも複数作品で思い切り脱いでいるので、興味のある方はぜひお調べになってください。
着想は良いのだけれど
アリストテレスx遊星からの物体X・・傑作に性別は無関係だが女性監督による快挙。
傑作に性別は無関係、とはいえホラーという特殊なジャンルにおいて、女性監督が成し遂げた、ホラー映画史上の画期とも言える作品。オファーを受け入れたデミ・ムーアの勇気と怪演、ゴールデングローブ賞受賞にも拍手を贈りたい。
繰り返し描写される卵黄の分割と鏡に写し出される姿。肉体と美醜、生と老い、排卵と化粧、造物主と被造物、主人と下僕、搾取と被搾取、そして主観と客観、不変と変化、形相(けいそう)と質料・・重ね合わされる対比の数々。
【問】美とはなんだろう? 美への執着とはなんだろう? 美はどのように作り出されるのだろう? 美への執着もまたどのように作り出されるのだろう?
・・・
【恐怖の源泉〜内側からの変身と外側からの改造】 変身も改造も「自分が自分ではなくなること」なので、どちらも恐怖を喚起します。本作のベスもスーも、美しくありたいという内面の動機から自発的な《変身》を華麗に遂げてゆき、当初は2人の間には互いに必要とし合う「共生」の関係がありますが、自身を優先するところから内面が狂気を帯び、関係が「支配-被支配」(搾取-被搾取)へと変容し、そこから2人の意に反する強制的な《改造》に見舞われます・・ジョン・カーペンター監督の「Things」(遊星からの物体X)の悪夢。
【作品が隠喩するもの】既にレビューや考察において、1) ハリウッドへの風刺、2) ルッキズム(外見至上主義)やエイジズム(年齢差別)への批判、ひいては3) 男性優位の社会構造への批判、などが指摘されているところですが、
おそらくそれら全てが重ねられているとともに、作品名の「サブスタンス」の意味から推測できるのは、4) 普遍的な価値、「本質」に相当するものを、個人も社会も十分見極められているのだろうか? という問い掛けにあると思っています。
【形相と質料】サブスタンスの原義はアリストテレス哲学の「形相」(けいそう)です。普遍的なある種の構造が形相、それが実体となって現れたものが「質料」。類推で想像するしかないですが、分子生物学で言えば形相が「遺伝子型」、質料が「表現型」。量子力学で言えば形相が「可能態」、質料が「現実態」。形相は不変ですが、質料は変化します。作中での美しさは脆くも醜く変化するもの・・質料です。
・・・
【問1】それでは美の基準とは何か? それは不変か? 基準に適う(かな)う美は不変であり、形相と言えるのか?
【答1】比喩になりますがケインズは、株式市場での人気を「美人投票」に例えています。美人投票での美しさは相対的です。いずれも群衆心理によるもの。もし群衆心理に固定的なバイアスがかかっている場合、社会構造的な要因が何かありそうだと仮設できます。(←男性優位社会構造云々を含めて)
【答1】(別解)客観的な美の基準になりそうなものは限られています。群論での「対称性」くらい。一般相対論での共変性や場の量子論での局所ゲージ不変性なども。自然界に存在する秘められたデザイン(フラクタル構造や決定論的無秩序)、そのごく一部としての「黄金比」なども。(←プラトン的な美や一般に美と言われるものに比べて、淡白な内容)
【問2】男性優位社会の構造と言われるものをどうみるか?
【答2】動物としての人類の進化史の観点から捉えると、人類がチンパンジーと分かれてから約700万年、男女をひっくるめて「奴隷」が作られたのがせいぜい1万年前。仮に女性だけがまだ奴隷と強く言い換えてみたとして、その歴史は極めて浅く、生物学的理由によるものでは全くなく、文化的理由によるものだ、と言い切ってよいでしょう。(楽観的に言えば、十分に修正・書き換えが可能です。)
特異な脳の発達から250万年、以来ヒトは他の動物に比べて未熟児の段階で生まれ落ちるので、約2年を十分ケアするに足る夫婦の絆が必要であり、親密な関係にある夫婦(共生関係)というものが(個々にバラツキがあるのは当然として)、ヒトが獲得した有効な「生存戦略」の1つです。(←「愛」の起源)
【まとめ】本作品に立ち戻ると、最初、ベスとスーは生存戦略として「共生」していましたが、途中、関係は大きく変質して「主従」の関係が生じ、生存自体が破綻します。
ご利用は計画的に。怖かった
デミ・ムーアがスゴかった
特撮?特殊メイク?もリアル
老いを受け入れること
若さを保つこと
若さという価値観
ルッキズム
男目線の女性の露出
スッキリはしないことが多すぎるけど
まあおもしろかった
デミ・ムーアは見る価値あり
好みがあるとは思うけど暇つぶしにはオススメ映画
2回は観ないかな
エロと血がぶっ飛ぶ怪作?
なんの予備知識もなく鑑賞。後半は途中で観るの やめようかなと思うほどグロい。注射や血が苦手な人は要注意。
前半、自分の分身が背中から脱皮のように飛び出るシーンは、ツッコミどころはあるが、アイデアとしては面白いと思った。ただ、遺伝子複製によるクローン的な演出なのに見た目が(若返ってるのは良いとして)全くの別人になってるのはロジックが崩壊してないか。また、掃除のオバチャンを解雇して自分で掃除することで身バレを防いでるのは理解できたが、分身がオーディションを受ける時、身分証明はどうしてるんだ、今時SNSとか確認するだろ、など細かいところが引っかかるがとりあえず無視して見続けるも、それぞれ入れ替わってる時に意識も記憶も別々なことが判明し、それって「二人は一つ」ではなくもはや完全に別の個体じゃん、と払拭できない疑問が湧く。本体側の記憶、経験として蓄積されないのに分身二重生活を続けたいと思う本体の気持ちが分からない。
後半、本体と分身に様々な心体的変化が畳み掛けてくるところはもうワケが分からず、この作品は論理ぶっ飛び系のクリエイティブ系?に振った作品と割り切ることで所々クスクス笑いながら鑑賞。血が苦手な自分にとって全体的には不快感が勝るが、ぶっ飛び方がいろんな意味で「面白い」とも感じたし身体美もあったため星2.5。
こんな感じか!
序盤、若干グロめだけど、映像としてはスタイリッシュとも言えるスピード感もあり。
着地点は…?と期待しながら鑑賞を進めましたが、終盤あんな感じとは!
「遊星からの物体X」大好きなので、笑ゥせぇるすまん的な因果応報ストーリーと相まって、大満足な作品でした。
グロいシーンの印象が強い
話題になっていたので配信で観た
トップ女優だったが
年老いて女優としてやっていけなくなったエリザベスが
事故を起こして行った病院から「サブスタンス」という違法薬物の存在を紹介される
「サブスタンス」で自分の分身スーが出てくるが
必ず守らないといけないルールがあり
7日ごとに肉体を入れ替わらないといけないとか
活性化液を脊髄から取り出して注射しないといけない。
7日ごとに肉体を入れ替えると
分身に精神が蝕まれて、元の肉体に戻ることを拒否しはじめる。
7日ルールをエリザベスは破ってしまったために
そのペナルティが自分の肉体が負うことになり
元の肉体の老化が進んでいく
最後はエリザベスがサブスタンスを辞めるために
薬品をスーに注射しようとするが
なぜかスーの肉体も人格を持っており
スーにエリザベスが殺されてしまう
最後はスーが「サブスタンス」でもう一度
分身しようとするが、大失敗をして化け物になってしまう
そのまま、番組にでようとするが
血しぶき全開で身体が崩壊をしていく。
演出がかなりうまいと思ったが
グロいシーンが多いのでうまく味わえない
プロデューサーの男がエビを食っているシーンなど
下品な誇張をしているところも印象的
この映画はいろいろ
ハリウッド構造とか女性問題とかを突き付けているように思うが
グロいシーンとか演出とかのほうが印象が強い。
「サブスタンス」の対価などはどうなっているのかというところはよくわからなかった
途中で「サブスタンス」を紹介した医師の「本体」らしき人がでてきた
結末が予想外だった
全685件中、1~20件目を表示