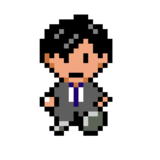バード ここから羽ばたくのレビュー・感想・評価
全60件中、1~20件目を表示
アーノルド作品には珍しい魅力的な父親キャラ
貧困家庭、片親とネグレクト、思春期の少女の人生への抵抗、人間の暮らしと隣接して描かれる自然と動物たちなど、アンドレア・アーノルド監督らしさを詰め合わせた集大成のような作品だが、はっきりと違いを感じるのはついに人間と動物の垣根を越えてきたかのようなバードという主要キャラクターの存在と(それもアーノルドの作品世界では非常に微妙な垣根ではあったが)、バグという父親の愛されキャラだろう(カエルに向かって合唱するシーン最高)。
これまでは基本的に父親は不在かクズ、父親的存在はみんなクズというのがアーノルド作品の定番だったと思うのだが、バリー・キオーガン演じる粗野な父親バグには、圧倒的なユーモアとダメ親父なりの愛情とそれに伴う行動力がある。アーノルドは作品を自伝的と取られることを好まず、また自分の生育環境について(シングルマザーで動物がたくさんいた家庭であったこと以外)多くを語っていないが、これまでの父親ないし男性キャラの描き方から推して知るべしという感じではあった。ところが本作で過去作になかった魅力的な男性キャラたちが生まれたのはどういう変化があったのか。そんなこともつい考えてしまうアーノルドワールドの最新形。
羽ばたきの疾走感に満ちた秀作
『レッドロード』『フィッシュタンク』などで英国におけるインディペンデント映画の可能性を押し広げてきたアーノルド監督。これまでの作品に比べると、『バード』のヒロインの年齢はやや低めで、その目線で見つめるホームタウンは多少荒れていて、家庭環境もはちゃめちゃではあるものの、決して絶望しているといった感じではない。むしろこの映画には過去のアーノルド作品よりもずっと心地よい光と風が差し込み、少女の人生や逞しさを優しく包み込んでいるかのよう。そこで出会う一人の無垢なる男。その存在を助けようと奔走する姿は、自分で考え、自分で行動し、ここではないどこかへ羽ばたこうとする彼女の、未来へ向けた助走のようにすら感じられてならない。彼女の息を飲むほど堂々とした演技と、バードが醸し出す浮遊感。そして何よりタトゥーだらけの父親役バリー・コーガンがもたらす、奔放で身勝手ながら憎めない人間味と無軌道なパワーに圧倒される。
カエル苦手……
初めは世の中の何もかもに対して不満タラタラのベイリーちゃんに共感もできず、ふぅ、こんなんで最後まで観ていられるのかしら?と些か不安だったけれど彼女の成長の度合いが感じられる良作だった✨
結構しんどい描写も多かったけど、バリー・コーガン演じるお父さんが最高💜
監督の動物愛が凄すぎる☺
初っ端から苦手なカエル(しかも大きなトノサマガエルみたいなやつ)出てきて死亡フラグ立ったかと思ったけど意外とカエル描写少なめで安心したー。
パパ・バグは名前の由来なのか虫好きでめっちゃ虫タトゥー入ってる。
ベイリーちゃんは鳥好きで引き寄せるメンズも不思議バード。自分自身も……とかなり理解の仕方が難しい場面もあるけど素敵な映画でしたゎ🌀
バードが導くベイリーの希望
主人公ベイリーの視点を通して、自身の成長と家族の本質的な愛情に気づくストーリーだ。
ベイリーのおかれた環境は、おせじにも幸せとは呼べない。
父親は4日後に結婚式をあげるようで、新妻となかなかうまい関係性が築けないベイリー。
それが原因で父親ともうまくいかない。
そんな状況下で出会うバードは、少し変わったミステリアスな存在感を纏っている。
ともに過ごしバードの父親を探すことで、母を守る、父親の愛情に気づくといった、
家族愛をテーマにしつつ、ベイリーが少しずつ大人になる姿を描いている。
兄は兄で彼女がいるが、最後の最後で別れざるを得ない状況になる。
そこに寄り添う父親と妹ベイリー。
ベイリーが初潮をむかえた際に父親の新妻を頼り優しくしてもらう。
そこでわだかまりがなくなり、父親との結婚を心から祝福できる心持ちになるベイリー。
常にバードがベイリーに寄り添う。ベイリーからの「大丈夫」という言葉が
ベイリーに希望の光になったに違いない。
バードは本物の鳥の姿になったりするが、これはベイリーの想像だと思う。
クソみたいな大人もたくさん出てくる(毒を持つ)が、子どもたちはピュア。
子どもたちがどう成長するかはやはり親や子どもを
とりまく大人次第なのだろうと思う。
やはり俳優としては、ベイリーの父親を演じたバリー・コーガンの存在感が圧倒的。
バードを演じたフランツ・ロゴフスキも只者ではない。
これからも要注目の俳優だ。
ベイリーを力一杯ハグしてやれ
どんな環境でも愛さえあれば乗り切れる
イギリスかアイルランドの田舎に住むシングルファーザーとぎくしゃくする12歳の黒人少女の話。
こないだ観たアイルランドのラップ映画も家庭の荒れっぷりが酷かったが、こちらはそれを上回るクズ家庭。ここまでとっ散らかって、もしかしてまとめる気がないのかと不安になるレベル。
大傑作「アメリカン・アニマルズ 」で好きになったオレのバリー・コーガンがタトゥーまみれのクソみたいなおとっつあん役でがんばるも、中盤、娘が鳥の妖精みたいなおじさんと出会って、まあ思春期の女の子の巣立ちを描いてるんだろうなとは思ったけど、ジェネレーションギャップを描く装置に、コールドプレイ、ブラーなど2000年代に流行ったUKロックという、ボクの苦手分野が出てきてついていけず。
これは、はずれ確定かなと、ボーッと眺めてたら、観た人しかわからない衝撃シーンが😛
もう、狂ってる!と思いましたが、そこからの畳み方がとても素晴らしく。ラストシーン、観た人ならわかるイメージのインサートで泣いてしまいました。
呉美保監督の「ふつうの子ども」は、危ういけどほっこりする映画でしたが、本作の子どもたちは、14歳の妊娠に悩むなど、ちょっと家庭環境ごとふつうの子どもになれない感じでしたが、バリーコーガンのクズだけどいいおとっつあんと娘の交流から、どんな環境でも愛さえあれば乗り切れることを力強く感じさせるのでした。
あー、2000年代のUKロックがドンピシャの方は絶対おもしろいと思うのでオススメします!知らんけど。
鳥人間は何かしら?
チラシに「世界が大喝采」と書いてあったが、私には今ひとつでした。
主人公のベイリーは男の子だと思ってましたが、女の子でした😅。でベイリーには、兄(←彼女を妊娠させてしまう)と妹や弟たちがいるのだが、兄は異母兄妹?妹や弟たちは異父の関係みたい?←そのあたりが、クリアになっていないというかハッキリしていないので、この人間関係が理解できないまま鑑賞していたので、しっくりこなかった。
ベイリーが兄の代わりに兄の彼女の家に行き、手紙を渡そうとするシーンがあるのだが、そこに登場したカラスは名演技でした。冒頭にもカモメが登場しますが、そのカモメも名演技。
DV男は、結局は謎の男バードにどこかに連れて行かれたのかしら?
ベイリーの父バグは、刺青が凄かったですね。(←あんなに刺青してたら、病気になったら困るだろう...MRI検査とか受けることになったら一苦労だなぁ...と呟いていました。)
ベイリーは父バグの再婚の結婚式に出るのを最初は嫌がっていたのだが、ラストでは結婚式に出席して何かが吹っ切れたように感じだった。「さぁ前を向いて羽ばたこう」と感じかなぁ...
やるせない日常だけど
導き?
そこに愛があったとしても
なんとかなる。
レイトショーで観ましたが序盤は音楽が鳴りっぱなしでアッパーな流れにずっと惹き込まれていました。マンチェスターが舞台なのか。貧困とか家庭環境を扱った映画でしたが序盤のドリーミングな映像、音楽がとにかく良かったと思います。最後に流れた曲がやられました。リアルすぎるだろ、拒絶するほどに。
“If I were a bird… 中学英語で習った仮定法の例文をふと思い出す 最悪の環境下でも明るくけなげに生きる少女をめぐるおとぎ話??
鑑賞動機はバリー•コーガンが出演しているからです。『ダンケルク』や『イニシェリン島の精霊』で見せた彼の怪演ぶりからすると、彼が出ているだけで名作ではないかという錯覚を起こしそうです。彼は本作では主人公の少女の父親を演じます。
私個人はあまり好きではない言葉ですが、現代日本には「親ガチャ」なる言葉があります。子からみた親の当たりはずれということでしたら、この物語の主人公ベイリー(ニキヤ•アダムス)は親ガチャ大ハズレと言ってもよいと思います。父親と2歳ほど上の兄と同居しているようなのですが、兄は異母兄のようですし、バリー•コーガン演じる父親のバグはあまり働いてる様子もないのに新たな女性と結婚しようとしています。別に住んでいるベイリーの実母側に目を移せば、バグと別れた後もそれなりに男出入りがあったようで子どもが何人かいます。すなわち、ベイリーにとっての異父妹や異父弟ですね。まあ、ひょっとしたら、みんな父親が違うのではないかといった雰囲気も漂っているのですが、問題は現在の夫でこれがどうしようもないDV男で、ベイリーの幼い異父妹弟たちはとても可哀そうな境遇にいます。
そんななかベイリーは自らバードと名乗る不思議な青年と出会います。このバードを演じるフランツ•ロゴフスキもバリー•コーガンに負けず劣らずの怪優の雰囲気をたたえておりまして、図らずも、欧州二大怪優競演の趣きもあります(ただし、ふたりの絡みはありません)。で、このバードは生き別れた親を探しているとのことで、ベイリーも捜索に協力したりもします。
一方、ベイリーの異母兄はガールフレンドを妊娠させたみたいで彼女とスコットランドへの逃避行を企てているようです。このお兄さん、まだ14歳で妊娠させちゃったみたいなのですが、父親のバグは俺も14歳でお前の父親になったよみたいのこと言ってて、この男、30そこそこで孫を持つのか、と呆れるやら、びっくりするやら。でも、バグはまあクズと言えばクズなんでしょうけど、息子や娘に対する愛はホンモノで、根は善良でいい奴だとは思います。
この作品には、時折り、鳥の群れが空を飛んでるシーンが挿入されます。また、カラスが伝書鳩ならぬ伝書ガラスになって手紙を運ぶシーンもあります(まあでもカラスが運んだ距離は伝書鳩が運ぶ距離をフルマラソンとすると100m競走の範囲でしたけど)。そして、バードが演じるファンタジー•シーン……
ベイリーはとてもいい子です。幼い妹や弟の面倒は見ますし、兄にも協力的です。見ず知らずだったバードにも協力します。周囲の人たちともおおむねうまくやっていけそうです。でも、親ガチャだけでなく、階級社会の英国で階級ガチャや地域ガチャにも大ハズレしている感じで、日本流で言えば小6か中1あたりの年齢なんでしょうけど、学校に行ってるシーンがまるで出てきません。
タイトルに挙げた中学英語の仮定法の例文ですが、”If I were a bird, (もし、私が鳥なら)の条件節に対して I would fly to you.” (あなたのところに飛んで行くのに)という流れで、ちょっとロマンチックで切ない感じだったように記憶しています。そして、文法事項として、仮定法過去は現在において実現が不可能なことの裏返しであると習った憶えがあります。ベイリーは今、非常に厳しい環境下にいて実現が不可能なことの連続のようですが、どうか自分の周囲にある愛を大切にして、夢だけは持ち続けてほしいと思いました。
アンドレア•アーノルド監督は私にとってこの映画が初見だったのですが、英国の最貧層のリアリティを描きながら、そこにファンタジーを入れ込んでくるサジ加減が絶妙で感服いたしました。別の作品も観てみたいと思います。
ここから羽ばたく
稀有な映画
私が嫌いな要素が揃っていた
最初は、なぜこんな映画を観なければいけないのかと思った
主人公の少女12歳のベイリーに扮するニキヤ・アダムズは大柄で、14歳どころか17歳位にもみえる。既にある程度、固まっているようで、ロンドンの下町言葉とも違うぶっきらぼうな英語を話す。アフリカからの移民系を思わせる風貌、シングル・ファーザー(バリー・コーガン)、異母兄と一緒に、郊外の労働者向けの集合住宅で暮らすが、彼女は彼らとも、今は別に暮らす母や異父姉妹の誰とも似ていない。毎日違う服を着て、バックやリュックを持って外出し、それが映画に出るための条件であったかのように、一瞬だけ楽しそうにする。学校に通っている様子も、もちろん働きに出ているわけでもない。食事や洗濯のお世話を誰がしているのかも不明。お金はないようだが。
ただ、バードと呼ばれる、明らかにヨーロッパ系の男(フランツ・ロゴフスキ)が出てきて、彼は「天使」だなと思った時、全体が寓話であると悟った。
ストーリーを述べるほどではないが、まだ20歳台の父親の再婚までの数日間と、バードが生き別れした父親と再会するところが描かれる。
少なくともブレグジットの頃まで、アフリカ系等の難民の最終的な行き先が英国であることは、いろいろな映画で見てきた。英国には、彼らを受け入れるだけの度量と制度や施設があるのだろう。たとえ最初は、どうにもならないにしても、潜在的な力を持つベイリーのような娘が、バードのような天使と出会った時、蘇って途轍もない力を得てゆく。オリンピックの時見るように、今や英国は、明らかな多民族国家である。
ベルギーや、パリ郊外を扱う映画で出てくる、難民系だけれど、どこか優美さを持つところが、この映画でも垣間見られると、もっとよかったが、それは無い物ねだりということか。
全60件中、1~20件目を表示