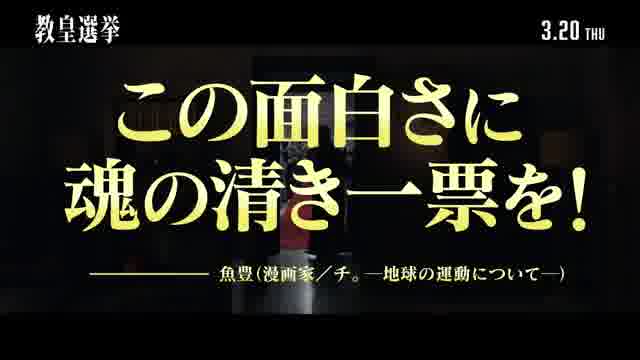「驚異的な現実とのシンクロ! 法廷サスペンス×『薔薇の名前』の手法でコンクラーベを描く。」教皇選挙 じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)
驚異的な現実とのシンクロ! 法廷サスペンス×『薔薇の名前』の手法でコンクラーベを描く。
やっぱり時節柄、これだけはさすがに観ておかないとね!!
いやあ、まさかマジで公開の真っ最中に、現実のコンクラーベとかち合うなんて!!
こんなこと、ホントにあるんだなあ。
てか、マーケティング部門、もしかして狙ってた??
この辺りで逝きそうだって、逆算して公開してたんならエラい。
本当は連休あたりのガチで「ドンピシャ」だった時期に観たかったんだけど、帰省したり、明けてすぐ仕事の詰めがあったりで、なかなか足を運べず今に至る。
(ちなみに部下は5月の連休に新婚旅行でイタリアに行ったけど、マジでサン・ピエトロ広場やシスティナ礼拝堂が封鎖されていて入れなかったらしいwww これぞ旅の忘れがたき思い出ですな。余談ですが、僕は25年前のやはり5月の連休に新婚旅行でヴァチカンを訪れ、システィナ礼拝堂の内部はツアーでしっかり実見している。代わりにミラノでメーデーにぶつかり、寺まで休んでしまって『最後の晩餐』が観られなかったw しょうがないので嫁を置いてひとりでエッチな映画館に行ったのは内緒。)
実は、『サブスタンス』を観る前日には既にレイトショーで観ていたのだが、あまりに『サブスタンス』が面白かったので、ついそちらの感想を先に書いちゃいました。
とはいえ、『教皇選挙』も、とても面白かった。
今年のアカデミー賞候補は、ほんと粒ぞろいだったんだね。
最近のアカデミー賞でオスカーを獲得する裏要件の一つとして、「人種問題」もしくは「ジェンダー問題」を扱っていることが必須条件であるような気がしているわけだが、あからさまにユダヤとアメリカの関係を問う『ブルータリズム』や、ロシアとアメリカの関係、および女性の性労働の問題を扱う『アノーラ』、バリバリのフェミニズム映画でもある『サブスタンス』と比べて、『教皇選挙』はそういった要素は若干薄いかな、と内心思ったりもしていた。
おじいちゃんしか出てこないし。
でも、いざ観てみたらびっくり。
中盤戦では、思った以上に「人種」と平等性の問題、あるいは聖職者の性搾取の問題を真正面から扱っているし、終盤戦では……以下、自粛。ああ、なるほど、そういうこともあって、きちんとこの映画もアカデミー賞候補に「ど真ん中から」あがってきたのね、とおおいに感心した次第。
あと、『サブスタンス』はフランス映画だけど、ハリウッドが舞台。
『教皇選挙』は英米合作の映画だけど、イタリアのヴァチカンが舞台。
そういや『ブルータリスト』はアメリカが舞台だけど、ハンガリーでロケしたらしい。
最近は、だんだん映画のプロダクションにおける国の境目が薄くなってきていて、結果としてアカデミー賞も、いろいろな国の映画が本賞を競い合うことが多くなってきている。
結局は、脚色賞しか獲れなかったようだけど、十分にアカデミー賞にふさわしい映画だったのではないでしょうか。
― ― ― ―
『教皇選挙』は、扱っているテーマこそ珍しい感じもするが、基本的には由緒正しい「法廷もの」のフォーマットを援用して作られている。
完全に隔離されたメンバーが、
投票によって合意を得られるまで
ひたすら投票し続ける。
これは、まさに「陪審員」制度の延長上に置かれうる「ルール」だ。
要するに『教皇選挙』は、投票の目的が「有罪/無罪の認定」か「次期教皇が誰か」と違うだけで、本質的には、シドニー・ルメットの『十二人の怒れる男』やクリント・イーストウッドの『陪審員12番』と同種のプロットを持つ映画なのだ。
監督本人は、アラン・J・パクラの70年代のポリティカル・スリラーが霊感源と述べている。その言葉が正しいなら、おそらくは『大統領の陰謀』(76)を意識して言っているはずで、たしかに「選挙の候補者の裏の顔を暴いて引きずり落とす」という意味では、両作品は似た構造を持っている。なお、アラン・J・パクラは、その後、法廷劇スリラーの佳作、『推定無罪』(91)を撮っている点にも留意したい。
なんにせよ、リーガル・サスペンスとしての枠組みを持つ以上、『教皇選挙』はリーガルもの特有の「弱み」をも併せ持つことになる。
ここで言う「弱み」とは、法廷劇で頻発する「後出し」の問題だ。
「密室」下で「すでに得ている情報を元に判断を下すこと」が、もともとの裁判もののキモであるはずなのに、実際には後から後から「新情報」が出てきて、「法廷(投票所)」に持ち込まれてくる。つまり、最初の評決の段階では「判断のための情報がもとより出そろっておらず」、後から提示される情報でどんどん評決の根拠も揺らいでいく、ということになる。これ(新証拠・新証人の登場)は、実際の裁判ではほとんどないシチュエーションであり、娯楽としての法廷ものならではの「ズル」と呼ぶべき仕掛けである。
本作でも、最初の投票で多数派が形成されなかったあと、教皇戦を左右する「マイナス情報」は、後からどんどん都合よく投入されてくる。
結局、物語構造としては、「過去の過ち」や「教皇に相応しくない行動」が露見して、バレた者から順番に落ちていくだけのお話になってしまっている点は否めない。
だんだん観ているうちに「単にろくなやつがいない」消去法の教皇戦にしか思えなくなってくるのは、さてどうなんでしょうか(笑)。
あと、主人公のローレンス枢機卿が、教皇選挙自体を仕切りながらも、自身にも被投票権があって、しかもどんどん当選確率が上がっていくのは、そんな制度でホントに大丈夫なのかと思わざるを得ない。
そもそも、これって延々とただ同じ投票行為を繰り返すだけの原始的なシステムで、足切りも決戦投票もない不思議な制度。これでよく今まで750年近く、無事に教皇を決められてきたもんだと素直に感心する。そんだけ枢機卿たちはみんなで、なんとなく空気を読み合ってきたってことか。自分が「少数派」だと判明したら、より多数派の教皇候補で信条的に乗り換え可能な勢力に、さっさと気を利かせて移っていくようにできている、ということなんだろうな。
なんにせよ、「固い」と思われた評決が、意外な事実の露見によってどんどんと覆っていく面白さは、まさに法廷サスペンスの読み味であり、その辺のクリシェをうまく「援用」していると思う。
― ― ― ―
「法廷サスペンス」要素と並んで、『教皇選挙』のミステリ性を支えているのは、「教会の探偵」としてのローレンス首席枢機卿の存在である。
彼は、いわば「苦悩する名探偵」として本作に君臨する。
役どころとしては、教会内の隠された内情を調査するという意味で、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』に出てくるウィリアム修道士や、エリス・ピーターズの創造した修道士カドフェルのような立ち位置にある。
必ずしも推理を働かせて真相に迫るというわけではないが、新たに得た情報を分析し、必要な尋問を推し進め、何より「選挙の展開を調整して落としどころを付ける」役割を担っていて、これはまさに推理小説における「名探偵」の機能に他ならない。
『教皇選挙』の場合、少なくとも最初の二人の有力者は、疑惑を突きつけられただけで比較的簡単に白状&降参するので、ちょっと拍子抜けする部分もあるが、かといって三人目の有力者のように最後まで抵抗しても、疑惑を認めようが認めまいが「投票者の支持を喪って票が入らなくなる」ともうおしまいである。
「名探偵」としてのローレンス枢機卿の決断が、自らの内なる正義に問うというよりも、「亡くなった教皇が生前どう判断していたか」に常に依拠しているのはちょっと新鮮な感覚があるが、彼は「使命」に従って仕切っている立場である以上、そこはわからないでもない。
― ― ― ―
以上のように、本書はまずもって「法廷もの」と「名探偵もの」の要素を掛け合わせた「ミステリー」としての足場をしっかり保持している。
だがそれと同時に、「内幕もの」(バックヤードもの)として抜群に面白い点もまた強調されるべきだろう。
カトリックにおいて、「儀式」の秘儀性は重要だ。それこそがカトリックをプロテスタントと分ける最大のアイデンティティであるとすらいえる。
教皇選挙もまた、厚い秘密のヴェールに隠されたとびきりに「謎めいた」儀式であり、その中身を垣間見られるというだけでドキドキさせられるものがある。
儀式の手順や所作、ガチで使用されるラテン語、本物のミケランジェロ『最後の審判』の前での宣言、有名な「煙」を用いた外部への連絡。いやあ、面白い。
ふだんは普通の恰好をしている老人たちが、真っ赤なおべべを着て「権威」を身にまとい、発するラテン語の台詞まで決められた究極の「ロールプレイ」に挑んでいく姿は、どこか地域の祭事に臨むおじいちゃんたちにも似て、ほほえましい。
しょせん現代の俗世しか知らない老人たちが、必死で750年の歴史を背負って「それらしくやろう」とやっきになってあたふたしているのを、外から観察する面白さというか。
それにこいつら、カトリック界の頂点に君臨する者たちの最高位の選挙といいながら、過去の過ちがどうしたとか、相手を陥れるためにどうしたとか、やっていることがやけに世俗じみているうえに、あまりにしょぼくて、みみっちい。
だいたい、パンフには「メディアさえ立ち入りを禁じられ、外部からの介入や圧力を徹底的に遮断する選挙」と書いてあるけど、選挙期間中に外からもたらされた情報に右往左往してるし、思いっきりテロの影響受けてるし、正式の投票の場では結局何も決まらず、夜の秘密の追及劇や急遽開かれた野良会議でほぼ全てが左右されてるんだもん。ぶっちゃけ最後とか、明らかに「なりゆき」と「ノリ」だけで、超大事なこと(教皇)が決まっちゃってる気がするんだけど……大丈夫か?(笑)
― ― ― ―
以下、寸感。
●鳥瞰カメラで枢機卿たちの日傘が動いていくショットは、『シェルブールの雨傘』みたい。このあと『サブスタンス』でもシェルブール・オマージュと思しきオープニングに出くわし、あの映画の不思議な影響力を感じる。
●英米合作の映画でありながら、ヴィスコンティやベルトルッチを観ているような「イタリア」的な映像感覚が顕著で、イタリア映画好きの僕としては胸が躍った。枢機卿たちを象徴するカーマインレッドのインパクトと美観も、忘れがたい。チネチッタ・マジックか。
●レイフ・ファインズ以外、誰も知らない俳優ばっかりだなあと思っていたら、トランブレ枢機卿ってジョン・リスゴーだったのか!! 『レイジング・ケイン』以来の邂逅(笑)。あと、野中広務みたいな顔の修道女が意外に重大な役回りで出てるなと思ったら、なんとびっくりイザベラ・ロッセリーニだった!!
●イタリアが舞台なのに、この映画も『ハウス・オブ・グッチ』みたいにみんな英語でしゃべるんだな、と思っていたら、ローレンスは英国人、ベリーニは米国人、トランブレはカナダ人だから英語で話してるのね! あとから出てくる連中は自分の国の言葉をしゃべるし、選挙中は公用語のラテン語を話す。なるほど、これは考えられてるなあ。
●ほかのアカデミー賞候補作同様、映画の背後には「トランプ対リベラル」「キリスト教世界対異教」といった要素がほの見え、製作者のスタンスがうかがわれる。このあたり、パンフのコラムがとても示唆的だった。
●個人的には、つい自分の名前を投票用紙に書いちゃったとたんに、天罰覿面のごとくテロの被害に遭って、心身ともにダメージを負って悄然としているレイフ・ファインズにいちばん萌えた(笑)。
●ラストのひねりについては、ネタ自体たしかに面白いは面白いけど、結局は「何者としてどう生きてきたか」が重要なのであって、「そのこと」については本人すら知らなかったくらいなのだから、あんまり気にする必要はない、むしろ問題視すること自体がナンセンスなのでは、くらいにしか思わなかった(笑)。
そりゃ、家父長制の権化みたいなカトリックの根底を揺るがす事態ではあるんだろうけどね。
●ロバート・ハリスの原作はなぜか未訳(まあ地味な話だしね)。読んでみたいのでどこかの出版社でぜひお願いします。
娯楽大作でしたねぇ。
そして「どうすれば作品をヒットさせられるか」―、その要素を徹底的に練った“ハリウッド的商業主義”の結晶でもありました。
実際の教皇選挙や「アノーラ」との賞レースも有って、まったくタイムリーな封切りでした。
ではでは😆🖐️