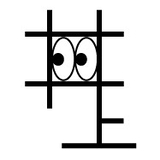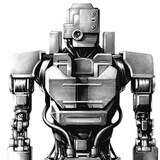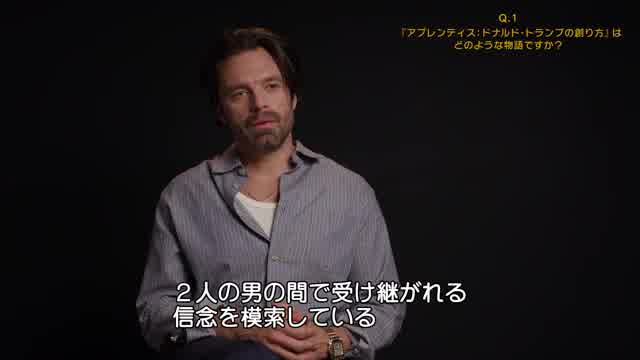アプレンティス ドナルド・トランプの創り方のレビュー・感想・評価
全49件中、41~49件目を表示
ロイコーンの強烈なキャラクター
トランプの若いころの映画らしい
時代的には70~80年代のアメリカという感じ
本作では個人的にもトランプよりも
トランプの師匠であったロイコーンのほうがキャラが強烈だと思った
彼は「赤狩り」でローゼンバーグ夫婦を電気椅子に送るために
違法な手段まで使った悪徳カリスマ弁護士らしい
勝利のために以下の三つのルールをトランプに教える
1攻撃 攻撃 攻撃
2非を絶対認めるな
3どんな苦境でも勝利を主張し続けろ
このルールはネット社会になった現在では
さらに世間で有効になったように思う
バズった政治家とか普通に使いそう
ロイコーンの言葉はいろいろ強烈で
それによってトランプが大物になっていくという感じだが
トランプは成功するために行動をしている感じになっているが
信念みたいなものはあまりないので空虚な感じがする
ロイも危ない道をわたってまでトランプを助けようとした理由がよくわからない
トランプがビッグマウスで「税金を免除してもらう」というところは
ロイは助けなくてもよかったよなと思った
ロイは筋トレでストイックだったりするが
トランプはカネと医療によって
コンプレックスを解消しようとする部分が
二人の対比をしていると感じた
ロイはゲイであり、晩年エイズになって亡くなってしまうが、
そのことをインタビューで最後まで認めなかったのは
3つのルールを最後まで守ったことになるのか?
彼は「赤狩り」の急先鋒だったり
当時は共産主義に対して相当な危機感があったので
反左翼、反共産主義がアメリカのためになるという
信念がかなり強いように思えた
トランプはイヴァナに相当ぞっこんだったのに
まったく興味を持てなくなってしまう
トランプの裁判の発端は
黒人を入居させなかったことから始まっているが
差別主義者としては描かれていなかったので
妻へのハラスメントなどは衝撃だった
ロイがエイズになったときに
距離をとっていたときがあったのは
エイズが怖かったからなのかなと思った。
そのあと、普通に接していたし
最後にトランプは3つのルールを
語るがそれを「自分でつくった」ようにふるまうが
トランプは過去を詮索されるの露骨に嫌がるのは
ロイとの関係を隠そうとしているように感じる
【”ドナルド・トランプという怪物を生み出したモノ”ひ弱な若きトランプが周囲の人のエキスを吸ってドンドン怪物になって行く様と、演じたセバスチャン・スタンが、ドンドントランプに見えてきた事に驚いた作品。】
ー 私は、ドナルド・トランプという男が大嫌いである。だが、今作は何故にあのような怪物が出来上がったのかを、明瞭に描いていて大変に興味深く鑑賞したモノである。-
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・20代に厳しい父の跡継ぎとして不動産業を任されたトランプが、ローゼンバーグ夫妻をソ連のスパイとして死刑に持って行った悪徳弁護士ロイ・コーン(ジェレミー・ストロング:一切、笑顔を見せない怪演は素晴らしかった。)に多大なる薫陶、影響を受けて行く様は、実に見応えがあった。
特に、ロイからの三つの教えである。
1.攻撃、攻撃、攻撃
2.自分の非を絶対に認めない
そして、”一番重要なのだが・・、”というフレーズの後に告げられる
3.自分の勝利を主張し続ける
これ、今のトランプそのモノじゃない!
トランプが、元々は”中身のない空っぽな男”であり、彼が怪物になって行った大きなきっかけが悪徳弁護士ロイ・コーンに、気に入られたという事が明瞭に分かるのである。
・更には、最初に一目ぼれしたチェコスロバキア出身のモデル、イヴァナ(マリア・バカローヴァ)への猛アタックシーンの数々。部屋中が一杯になる程の薔薇を贈り、スキー場まで追いかける姿。彼女が結婚していたにもかかわらず。マア、ドッチモドッチ夫婦である。そして、豊胸手術までさせておいて飽きると浮気をする。人間として駄目駄目である。
・兄が困窮してやって来ても、部屋には入れずにハイアット・ホテルに部屋を取る姿。で、兄は急死。
序でに、老いたロイ・コーンから何度も電話がかかって来ても出ずに、ロイからの教えをインタビュアーに自らの考え方の様に、滔々と述べる姿。
漸く、エイズに罹患している可能性があるロイを海が見える別荘に招き、彼の59歳の誕生日を祝うシーンでの、ロイが、初めて見せる涙。あれは、嬉し涙ではなく悔し涙であろう。そして彼が亡くなると、トランプは、さっさと部屋中を消毒させるのである。
・彼の肉体改造シーン。アンフェタミンを常用していたために腹が出て来て、髪も薄くなった時に、脂肪吸引、頭皮切除するシーンも凄かったなあ。
今でも、色々とアヤシイ薬を飲んでいるのかな?
<今作は、ひ弱な若きトランプが周囲の人達のエキスを吸ってドンドン怪物になって行く様を見事に描き出し、且つトランプを演じたセバスチャン・スタンが、ドンドントランプに見えてきた事に驚いた作品である。
今後の世界、大丈夫かな。それにしても、この映画を良く上映したモノだなあ。>
目を背けたくなるシーンあり。
面白おかしくドラマを作っているだろうが、強調されるから、ちょっと、目を背けたくなるシーンも何ヵ所かある。ご本人サイドも、この映画をフェイクと訴えているらしいが、妻のイヴァンカに後ろから襲いかかるシーンはグロテスクだ。亡くなったイヴァンカの自伝にあるということだが、ドアップで劇場で、それも若くもなくロマンスでもなく、他人のご夫婦の情事を見させられるのはちょっと、ストーリーとは関係なくきつすぎる!フェミニズムの観点からトランプはひどいやつだという印象操作だろうが。敢えてこういうのを入れる所が、反トランプのプロデューサーが作っただけある映画だ。
師匠のロイが、結婚して離婚するときは夫から妻へのプレゼントを返還せよと、イヴァンカに婚前契約の文言をいれたが、晩年に、トランプからウソモノのTIFFANYのジルコニアを贈られ涙するシーンがあった。人間は身体が丈夫なときはいいが、不健康になったら自分がトランプに教えた事が堪えるものだなぁ。(苦笑)
これからのトランプと、我々日本人も共に同じ時を過ごすのだとおもうと、全く関係ない場所に住んではいるが、自分と同じ時代にいきているってすごいことだなぁ。ちょっと怖い。
プロパガンダか、問題提起か? これがトランプの実像なのか?
日本橋の映画館は公開3日目でほぼ満席。最前列での鑑賞となった。アメリカ新大統領、そしてこの映画への関心の高さを感じる。
鑑賞前の懸念は、多くの報道やメディアで知識人たちが強調するトランプの「悪魔性」を一方的に強調するものではないかということだった。多くの問題を抱える毀誉褒貶の激しい人物であるのは周知のことだが、2回の民意の支持を受けた人物である。そこには、多様な価値観の渦巻くアメリカの複雑な人々の意思が反映されている。
単純に断罪する視点で描くのは、彼に託された民意を矮小化するものになりかねない。そんな映画だとイヤだなと思ったのだ。
イラン出身のアリ・アッバシ監督のこれまでの作品は未見だが、調べてみると、単純な善悪の二元論でわかりやすく描く監督ではなく、「人間の複雑性」や「真実と言われるものの曖昧さ」を描いてきたという評価のようだ。期待を高めつつ、座席に座った。
冒頭で、弾劾され辞任したリチャード・ニクソン元大統領の記者会見を引用し、明快にテーマが提示される。
「もし、大統領が悪魔なのであれば、国民はそれを知る権利がある」
そして若き日のトランプの物語が始まる。
序盤では、権力とお金にしか興味がない若き日の彼の姿が描かれる。デート相手の女性が彼の軽薄さに嫌悪感を抱き、トイレに向かう姿が象徴的だ。
記録映画と見紛うほどトランプ本人にそっくりな主演俳優の演技がリアルで、エピソードも戯画化されつつリアリティ抜群だ。
物語は、資産家2世としての初々しい野心を持った若者のトランプが、悪魔的な能力を持つ弁護士ロイ・コーンに気に入られるところから進む。コーンはトランプに勝利の方程式である「3つの原則」を叩き込む。
1. 攻撃は最大の防御である
2. 決して謝罪するな
3. 現実を作り出せ
トランプはこの行動原則を武器に、欲しいものを次々と手に入れる。障害となる人物を社会的にも経済的にも「抹殺」することにためらいはない。
映画で描かれるトランプの実像は、徹底的に醜悪だ。恩師も、父母も、兄妹も、妻や子供すらも愛せない人物として描かれる。そして、自らの醜さを覆い隠すために整形手術を受ける場面では、その醜悪さがさらに強調される。
彼にとって「愛」や「絆」は重要ではなく、「3つの原則」のみが彼の人格を形作っているという印象が残る。
また、映画では政治家になる前の彼のルーツが描かれるが、何らかの社会課題認識や志に基づく政治的野心の原点は描かれない。本当に何もない空虚な人物ならば描きようがないのかもしれないが、これまで「人間の複雑性」をテーマにしてきたという監督の作風とは異なるのではないか。紋切り型に善悪の二元論で描く、ピカレスクエンタテイメント作品と私には見えた。
ラスト近く、伝記作家と思われる人物とのインタビューシーンで、トランプには語るべきルーツも思想もなく、彼の中にあるのは『3つの原則』だけの空虚な人物であることが重ねて描かれ、映画の締めくくりとなっている。
最後まで飽きさせない、強烈に面白い映画であった。
しかし、アメリカの複雑な民意を反映して選ばれた人物としてのトランプには一切触れられない。もちろん、政治家になる前の彼のルーツを描く映画だから、触れようもないのかもしれない。現代アメリカの複雑な現実に触れることなくストーリーが終わる点は物足りなさを感じるが、それこそが監督の狙いでもあったのだろう。
冒頭で投げかけられた問い――「もし大統領が悪魔ならば、国民はそれを知る権利がある」――は、映画全体を通じて、その悪魔性が補強される。
一方で、この映画には監督自身が「自らにも繰り返し問いかけた」作家的な深い問いではなく、観客を啓蒙しようとする意図が感じられた。まるで、「愚かな大衆の1人であるあなたにも、これでわかったでしょう?」と言われているような気さえした。
この映画を見たトランプ支持者はどう感じるのだろう? 本作は対話を生まず、分断を加速するのではないか?
とても面白く、よくできたプロパガンダ映画だ。これが観賞後の率直な感想である。私は何かを見落としているのだろうか?
明日就任するのは本当にこの人?
大体の悪徳弁護士ものは、倫理的にどうなの?とか、違法すれすれ!というものだが、ロイ・コーン(ジェレミー・ストロング)は完全に違法。
それでも、挙げられないのは、声を上げれば自らも破滅してしまうという人間の弱みをがっちり掴んでいる「勝者」だからなのか。ウツボのような澱んで微動だにしない瞳が恐ろしい。
そんなコーンに助けを求めたトランプ(セバスチャン・スタン)は、ウツボに飲み込まれて消化されてしまうのかと思ったら、大き過ぎてウツボがゾウの形に変形していく。
水をちびちび飲みジジババ相手に集金していた冴えないトランプが徐々に自信をつけていくところは応援したくなるような部分もあったが、増長し過ぎた彼は人間として醜悪極まりない。ラスト近くの手術はあえてグロテスクな描写が、フランケンシュタインのような怪物を作っているようにも見えた。
彼が超大国の主となるこれからの4年間、日本も相当強く出ないと滅茶苦茶にされてしまう。それにしても、次期大統領になろうという人を題材に日和らず忖度せず、よくこういう映画を作れるな、とアメリカの表現者たちのバイタリティは本当に尊敬に値する。
それにしても、コーンはどうしてあんなに力をなくしてしまったのかが分からず。年と病気が原因としても、愛人1人良い施設に入れられないなんて、お金は使い果たしちゃったの??
終わりがあっさりしすぎて、もっと見たかったので少し物足りなかったけれど、全体として怖さとストーリーがしっかりしており、見応えあり。ジェレミー・ストロングとセバスチャン・スタンの演技も素晴らしかった。
実業家としてのトランプの、何を描きたかったのかがよく分からない
トランプに似ているというイメージのなかったセバスチャン・スタンだが、特徴的な口元をうまく再現していて、そのうちトランプ本人に見えてくるのだから、やはり熱演と言って良いのだろう。
内容的には、トランプと、彼に影響を及ぼした弁護士との関係が描かれているのだが、確かに、弁護士は、成功するための三原則なるものを教示しているものの、それで、トランプが、純粋な若者から「怪物」に変身したのだとはとても思えない。
攻撃的で、自分の非を認めす、勝つことに執着する実業家なんて、それこそ五万といるだろうし、生き馬の目を抜く実業界では、そういうキャラクターこそ求められるに違いないと、逆に納得してしまった。
トランプがのし上がっていく手口にしても、相手の弱みにつけ込んで脅迫し、人種差別の訴訟を取り下げさせたり、ホテル建設に伴う税金を免除させたのは、あくまでも弁護士の方で、トランプ本人があくどいことをした訳ではない。
あるいは、積極的な不動産事業の展開で資金繰りが苦しくなったり、結婚生活に行き詰まったり、脂肪の吸引や薄毛対策の手術を受けたりはするものの、それで、トランプの人格に大きな問題があるとも思えない。
むしろ、エイズに罹患した弁護士を、一度は切り捨てようとしたものの、最後は、死期の迫った彼を自宅に招いて、感謝の気持ちを伝えるところなどは、トランプが「善い人」に思えてしまった。
結局、実業家としてのトランプの出自は分かったものの、そんな彼の何を描きたかったのかは、最後までよく分からなかった。
トランプが、国民的な人気を獲得する契機となったリアリティ番組への出演のエピソードは描かれないし、自らが政治家になるよりも、金を渡して政治家を動かした方が良いと考えていたトランプが、どうして大統領になろうと思ったのかも分からずじまいで、観終わった後には、大きな物足りなさが残った。
歴史を知っているとより楽しめる
来る1/20に米国史上2人目、クリーブランド*大統領以来132年ぶりとなる復活大統領となるドナルド・トランプ。
*日本製鐵とUSスチールの買収に介入しているクリーブランド・クリフスの前者は地名だが、由来はクリーブランド大統領の親戚筋の先祖で独立戦争時の准将(後に将軍)に因む。
最初は今のトランプとは雰囲気も違うし、配役のミスマッチ?と思いますが、時間の経過と共に現実のトランプに近づいていく事に驚かされます。
インタビューで特殊メイクなどに極力頼らず、過去のトランプ氏のインタビュー映像などを研究して演技でカバーしたというから役者の凄さを感じます。
また師であるロイを抑えて、変貌…は見どころの一つ。
また個人的には父の会社に就職してトランプ・オーガナイゼーションの副社長という一方で仕事は家賃の取り立て(集金)で住民たちから嫌がらせを受けたりするシーン。まさにアプレンティス(見習い)時代といった所。
日本ではヒラリー・クリントンとの2016年の大統領選挙以降の事は報じられますが、NYの不動産王や資産家、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(BTTF,1985)の悪役ビフ・タフネンのモデルになった人物というイメージでしょうか。
米国では本作と同名のバラエティー番組『The Apprentice』(2004-2017)は米国版『マネーの虎』。BTTFでもFAXで登場する"You're Fired"(お前はクビだ)をトランプ氏に言わせる等のパロディを知っていると本作はより楽しめると思います。
特にBTTF Part2は必見でしょう。外観から内装、あの階段まで本当によく参考にしています。
本作の邦題は上記のイメージが十分にない日本向けに副題付きで描かれています。
米国やNYの時代背景、バックグラウンドの知識がないと感慨もなく、勝つために手段を選ばないエグい話に思えるかもしれません。
しかし本作のタイトルを元々の『アプレンティス』にこだわりたかった担当者の気持ちはわからないではありませんが、同番組が定着していない日本ではタイトル詐欺ではありませんが『ロイ・コーン ドナルド・トランプを創った男』としていたら評価はもっと高かったのではと個人的には思います。
作中にはドラッグ、乱交パーティやゲイのセックス、トランプの不倫や情事などが度々出てきます。
またトランプの兄のアルコール依存、トランプ自身のゲロを吐くシーン、脅迫、脂肪吸引や頭皮の薄さを頭を開いて皮膚を繋ぎ目立たなくする手術による血や肉、骨などのかなり露骨な表現があり、人によっては気分を害するかもしれません。
また最終盤、トランプ氏お気に入りのフロリダのマール・ア・ラーゴでティファニーのダイヤ入りカフスをプレゼントに贈る場面。ここは色々な解釈が出来、トランプとカードのトランプをかけた創作である可能性が高いと思います。
愛=ハート
プレゼント=ダイヤ
セックス=スペード
出逢った場所=クラブ
ドナルド・トランプ=キング(ジョーカー)
単純に考えればドナルド・トランプはケチな奴という意味でロイ・コーンへの贈り物が偽物(ジルコニア)で、イヴァナへプロポーズする場面との対比で離婚したらプレゼントは返却するロイ・コーンの提示した婚前契約書への復讐。イヴァナはプロポーズで贈られたティファニーのプレゼントは偽物で、そして既にトランプの愛を失っていたイヴァナが「私もあなたもトランプに騙された」と、病気で衰えたロイが本物のダイヤ(トランプ)を見抜けなくなったことを皮肉る場面。
またロイ・コーンに贈られたティファニーのダイヤは本物で、「私には偽物を贈ったのに…彼が本当に愛していたのは私ではなくあなただった」(トランプ氏とロイ・コーンは実は相思相愛だった)という皮肉や嫉妬かもしれません。
後者であればトランプ氏が大統領選挙集会でYMCAを流して踊る意味と繋がります。
本作を鑑賞後に個人的に思ったのはドナルド・トランプが大統領になったのは必然的ということ。本人は「全くのデタラメ」と公開を握り潰そうとしましたが、それが殊更リアリティを感じさせるプロレスであると思わせます。
米国という世界大戦以後の覇権国家で、民主主義(共和主義)の極地とも呼ばれる国の勝者には、裁判や訴訟さえ握り潰せる…まるで大統領選挙の勝者総取り(Winner takes all)を政治やビジネスでもやっているような、米国の底堅さというか"強欲を正当化"する強さの根源を垣間見た気がします(それが日本や先進国で同じく社会的に評価されるかは別問題ですが)
映画作品の様な人生
めちゃくちゃ面白かった。トランプ本人が制作に関わってるわけではないからどこまで本質的なものを表現してるかは分からないが、映画作品の様な人物が出来上がる過程がかなり見応えある。
まぁある程度トランプを追ってるとこの作品をみて特段驚く事はなく納得する展開が続くのが心地よい。トランプのエゴ、突き詰めた利己主義、目標を成し遂げる執念は良くも悪くも興味をそそらされる。
まぁこの作品のトランプはまだ序章に過ぎず続きも作品化して欲しいものだ。ロイコーンもまたある種魅力的でロイをもっと知りたくさせてくれる作品。
全49件中、41~49件目を表示