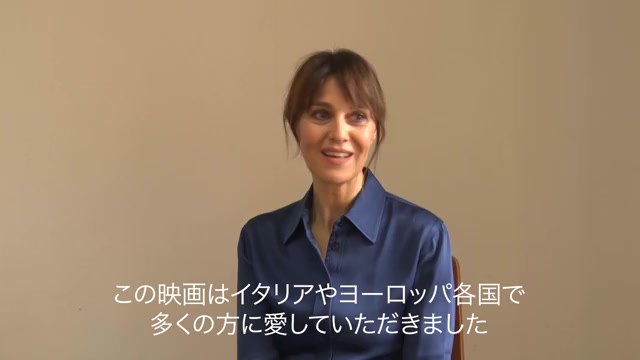ドマーニ! 愛のことづてのレビュー・感想・評価
全14件を表示
歴史を語り継ぐ意義と、あらたにはまり込んだ泥沼を思う
この映画が描いていることはただの昔話ではないし、えらく昔に感じる人もいるかもしれないが、現実にはそうではないんですよというメッセージは時代考証を気にすることなくジャンルレスで流れる音楽によく現れていると思う。また、かつての女性たちが勝ち取った権利の大切さと、彼女たちの歴史を語り継いでいくべきという思いもよくわかる。明るいタッチの「ジャンヌ・ディエルマン」とも言えるいい映画だった。
だが、選挙によって担保される民主主義の価値や社会の進歩みたいなことが絵に描いたモチだったのではないかとどんよりすることが多い昨今では、選挙という権利を行使するには社会的な責任や知識もセットで考えねばならないのではないか、選挙権の大切さを描くだけではもはや足りないのではないか、と頭を抱えてしまって、正直、彼女たちがつかんだ喜びが、今また別の袋小路にはまり込んでいることに暗澹としてしまった。
「パーソナル・イズ・ポリティカル」 個人の課題が社会を変える力になる
映画「ドマーニ! 愛のことづて」を観て、すぐに連想したのは「パーソナル・イズ・ポリティカル」(The Personal is Political)というフレーズだ。
このフレーズは、今春放送されたテレビドラマTBS日曜劇場「御上先生」で何度も登場する、個人の問題を単なる私的な事柄として片付けるのではなく、社会全体の仕組みとして捉え直す視点を喚起する言葉だ。
この「パーソナル・イズ・ポリティカル」というフレーズは、1960年代から1970年代にかけてのフェミニズム運動で広まったスローガンで、個人的な経験が社会や政治の構造と深く結びついていることを示すものだ。
この概念は、家事分担の不平等やセクシャル・ハラスメントなど、従来「私的」とされてきた家庭内の役割や個人の選択が、実際には広範な社会的不平等を反映する政治的な問題であるということを主張している。
「パーソナル・イズ・ポリティカル」という言葉が広く知られるようになったきっかけは、1969年にキャロル・ハニッシュが書いたエッセイ「The Personal is Political」から。
ただし、ハニッシュ自身はこの言葉はフェミニストたちの集団的な議論から生まれたものだと述べている。
「パーソナル・イズ・ポリティカル」という考え方は、現代社会における重要な課題ととらえられているジェンダー平等や環境問題、多様性の尊重などを考える上でもとても有益な考え方だと言えるだろう。
そして、「パーソナル・イズ・ポリティカル」というフレーズが一躍脚光を浴びる契機となったテレビドラマ「御上先生」では、教育現場の不条理に立ち向かう官僚教師の戦う姿が描かれている。
主人公の御上孝が、文科省の官僚から派遣された私立高校の教師となり、腐敗した教育制度の改革に挑み、子どもたちの未来を守るために奮闘するという物語だ。
一方の映画「ドマーニ! 愛のことづて」は、戦後ローマを舞台に、家父長制の抑圧に苦しむ主婦デリアが、家族の未来のために小さな勇気を振り絞る姿を描いている。
彼女の行動は、当時、男性が優先される社会の中で、女性の権利を求める社会的なムーブメントの一端を象徴している。
両作品に共通するのは、個人の課題が社会全体の課題とリンクしている点だ。
主人公たちによる身近な問題を解決するための行動がめざす高い次元での課題解決が、社会全体の変革につながる可能性を秘めているというところが共通している。
この考え方は、歴史上の偉人たちの思想にも通じる。
マハトマ・ガンディー
「あなたがこの世界で見たい変化そのものになりなさい」
この言葉は個人の行動が社会を変える力になるという信念を表していると言えるだろう。
ヘレン・ケラー
「一人でできることは少ないが、共に行えば多くのことができる」
この言葉は連帯の重要性を強調していて、私たちが直面する課題を「個人的な問題」として片付けるのではなく、それを社会全体の課題として捉える視点が求められている。
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア
「どんなに小さな行動でも、それをするべき正しい時に行うことは決して無意味ではない」
この言葉は私たちが日常的に行う小さな行動も、社会全体の変革に繋がる可能性を秘めていることを示唆している。
ジョン・F・ケネディ
「最も強いコミュニティは、一人一人がその一員として力を発揮するときに築かれる」
この言葉は個々の努力と協力が強い社会を作り上げる鍵であることを説いている。
マリー・キュリー
「人生から恐れを取り除いて見れば、理解することしか残らない」
この言葉は課題や問題に直面した際、恐れるのではなく、それを深く理解することで解決の道が開けるという力強いメッセージが備わっている。
「御上先生」の主人公御上孝が生徒たちとともに、教育制度の改革に挑もうとする姿や「ドマーニ! 愛のことづて」の主人公デリアが、強権的な夫の引き留めを掻い潜って選挙の投票をしにいく姿は、世界中の女性のより良い未来のために立ち上がる強いメッセージを私たちに与え、立ち上がる勇気を与えてくれる。
個人の勇気ある行動が社会を変える力に繋がっていくという両作品が発する共通のメッセージは、私たち一人ひとりが小さな一歩を踏み出すことで、より良い社会を築くことができるのだという、重要な示唆を与えてくれていると言える。
テレビドラマや映画という娯楽の枠から飛び出した、社会的メッセージ性を帯びた作品に簡単に出会える環境は、決して当たり前のものではない。
そういった作品に出会い、何らかの刺激を受けた一人ひとりが小さな行動を示すことで、閉塞感漂う現代社会の問題や課題を解決する糸口になるということを、私たちは忘れてはいけないだろう。
ライフ・イズ・ビューティフルの国からのナイスストーリー!
パオラ・コルテッレージという主演女優の監督作品。どことなくロベルト・ベニーニの『ライフ・イズ・ビューティフル』を思い出しながら観ていた。イタリア、白黒、戦後の話と主演&監督ということで。
不意に観たくなったのは日本ではそんなに入っていないけど中国で大ヒットしてると聞いて。
で、まったく中身を知らずに愛のことづては何のことかと思ったらそれか!という感動のオチ。そしてドマーニとは「明日」のことなのね。それを知ると企画とエンディングの鮮やかさが際立つな。
冒頭から妻を引っ叩く旧時代(日本でも同じ昭和のそれ)の悪しき風習のオンパレードででそれをコミカルに処理しながら、新世代に生きるべき娘の結婚、娘のために、という思いと娘からお母さん、このままでいいの!というつけあげをくらいながら、その世代の間に生きる「お母さん」の元に届く謎の手紙。途中までただのメロドラマへという風にもみえるところ、最後に落ち合う船着場にでも着いたかと思ったらまさかの初の婦人参政権の選挙に向かうお母さんだった。教育もまともに受けてこなかったお母さんのへそくりの行方とこの投票に集まるイタリア女性たちの描写。そして落としてしまった謎の手紙をみて「あのアマ!」と追いかける夫と、それを持って追いかける娘。娘とのカットバックが素晴らしい。とてもいい映画だった。
途中義理の父の死におけるギャグ&サスペンスが面白かった。特に意味もなく入ってくる近所の婆さんとか。
女性の逞しさをスクリーンから感じるカッコよさ!!
監督・主演のパオラ・コルテッレージの才能及び魅力をふんだんに感じる作品である。
冒頭、いきなり起き抜けに夫からビンタを張られる妻デリア。
なんじゃこのDV夫!と誰もが思うこと間違いない。
1946年のイタリアはこういう男尊女卑甚だしい社会であり時代だったのだろう。
いろんな映画を観ているとLGBTQに対する差別も酷かったので、さもありなんとは思うが
それにしても酷すぎる夫。
そんな夫がいて、かわいい娘には良い相手との結婚をさせたい、二人の息子は夫の影響を受けており
実に口がきたない。
そんな家庭環境だが、アメリカ軍の軍人との出会いがあったり、昔好きだった男からアプローチされたり、
その男から駆け落ちに誘われたりと、デリア自身はとても魅力的。
そこにデリアあての手紙が届くのだが、当時は女性に手紙が届くのは珍しかったのだろう。
てっきり男から誘いの手紙だと思ったが、実は女性の参政権を得るための選挙の投票用紙だったことが
ラストでわかる。
このあたりのミスリードが実にうまい。
死んだ義父をさておいても選挙にいきたかったデリア(その後の展開が結構笑える)。
投票用紙を家に落として、それを見た夫が「クズ女」と吐き捨てるように言い、追いかける。
その用紙を拾い、母のもとに届ける娘。
そして一暼くれてやる的な目で夫を見るデリア。
そしてそして、笑顔で涙を流しつつ誇らしげに母を見る娘。
娘に歌うように笑顔を届ける母デリア。
めちゃめちゃうまい。素晴らしいつくりあがりだ。
ミュージカルっぽい演出も入れていて、それが実にシニカルだったりする。
それであるがゆえ、DVシーンもミュージカル仕立てにして、皮肉を効かせながら見せる
この手腕はとても初メガホン作品とは思えない。
久しぶりに良いイタリア映画を観た気がする。
パオラ・コルテッレージ監督の次回作も観てみたい!
ぜひ、多くの女性に観てもらい、勇気をもらってほしいと思う。
【”愛のことづてってムッチャ皮肉が効いてるなあ!”今作は第二次世界大戦終了直後の女性の人権ほぼ無きイタリアを舞台にした、前半苛苛、最後半スカッと爽快なる女性の権利とは何かを描いた映画である。】
■第二次世界大戦終了直後のイタリア。デリア(パオラ・マッコーリ)はDV夫イヴァーノ(で、本人チョッとしか自覚無し。当たり前と思っているナス野郎。)と似たモノ親子のセクハラ義父の看病をしながら、朝から晩まで掛け持ちで仕事をしながら、稼いでいる。
そんな時、娘のマルチェッラが、ナチスへの密告で一財産作った成り上がり一家の息子と恋仲になる。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・前半は、DV夫イヴァーノのデリアに対するDVに苛苛しながら、観賞。朝、”おはよう”と言った彼女にイキナリ、平手打ちだもんな。腹立つわ!
・けれども、デリアはそれに対抗せずに、只管働くのである。当時のイタリアは、女性の人権が軽んじられているシーンが描かれる。新米の傘職人の青年の方がデリアより給料が良いってどういうこと?
・そんな母の姿を見ている娘のマルチェッラは、”お母さんみたいな、人生は送らない!”と言って成り上がり一家の息子との恋愛を育むのだが、彼女が婚約を了承したあとの息子の態度急変を母は見逃さなかったのである。
そして、知り合いになった進駐軍の黒人兵の助けを借りて成り上がり一家が営むトラットリアを、ナントTNT爆弾で爆破するのである。イタリア女性を怒らせると怖いのである。爽快だったけどね!
・そして、デリアは少ない稼ぎの中からコツコツと、娘のウエディングドレスのために貯めていたのだが、成り上がり一家の息子の本性を見抜き、嫌味な一家そのものを追いやった後に、そのお金をどう使ったかが、チョイ沁みるのだなあ。あれは、自分みたいに学が無い女性では戦後は生きていけないという母の、親心だよね。高校に行かせない父親とは、大違いである。
<そして、デリアに届いた”ことづて”は、てっきりお互いに小さい頃から思い合っていたニーノからの駆け落ちの誘いだと思っていたら、女性の参政権を決める選挙の投票用紙だったというオチは、実にシニカルであるが、事実なんだから仕方がない。
そんな、母の姿を見た娘のマルチェッラが、母を見上げる眼からは、嬉し涙が流れているんだよねえ。
今作は第二次世界大戦終了直後の女性の人権ほぼ無きイタリアを舞台にした、前半苛苛、最後半スカッと爽快なる女性の権利とは何かを描いた映画なのである。
<2025年6月1日 刈谷日劇にて観賞>
義務じゃなく権利です
フランスが実は伝統的にごりごりの男権社会だったのをつい最近知ったが(映画で!)イタリアもそうだったか、これでは昭和の日本よりひどくないか? イヴァーノは周囲のおんなたちからは非難されるろくでなしだが、社会全体としては許容されていた模様、そういう社会。。
ひどい目にあわされるデリアを延々見てストレスたまりまくったところで、オチはそれかい。。
みじめすぎる女性を救うのは、根本的に社会を変える必要がある、政治に参加するのだ、という意識に目覚めての行動を起こした、自分の意志で。
納得はするけど、もうちょっとカタルシスほしかったです。
追ってきたイヴァーノから逃げようとしたところ、決然と振り返ってにらみつけたデリアは、娘の婚約者の店を爆破させるくらいの決断力と行動力があるのでこれからは黙ってハラされてないだろうし、娘とタッグで家庭内変革していきそうだし、と自分を納得させました。
デリアが日曜日が過ぎても「まだ明日もある」と言っていたり、わざわざ夫に出かけてくると告げるとか、駆け落ちするにしては??なところなど確かに伏線はあったけど、わざとミスリードさせるように作られており、そのせいで若干不自然なところがあるようでした。
そうかしら
全く勘違いしていました。
「ドマーニ」とはイタリア語で「明日」という意味だそうです。
監督は私の大好きな「これが私の人生設計」の主役を務めた人でした。
追記
気になって2回目の鑑賞。
最後がわかったうえで見てみると、種はいたるところに蒔いてはあるが、逆に観客がミスリードをするように少し無理をしている面も感じた。
私は自分に選挙権があることも、女性に選挙権があることも当たり前のこととしか考えてなかったが、改めてその大切さを学んだ気がする。
追記の追記
3回目の鑑賞。やはり、ミスリードをするために、本筋が犠牲になっている気がする。
でも、1回目よりは2回目、2回目よりは3回目の方が印象がよくなる映画でした。
理性と感情両方に訴求する秀作
今週はコナンの新作が公開されたということもあって、コナン以外は全般的に品薄な感のある映画界。そこで気になっていながらもまだ観に行けていなかった3月14日公開の本作を遅ればせながら観に行きました。
チラシの写真が白黒なので、てっきり昔の作品のリバイバル上映だと思っていたのですが、実際は全く違って新作でした💦でも舞台は第2次世界大戦直後のイタリアはローマ。主人公のデリア(パオラ・コルテッレージ、監督兼主演)の夫イヴァーノ(バレリオ・マスタンドレア)は、壮絶なDV野郎。何かにつけて妻を殴る蹴るなどの暴行を働くのは勿論、暴言の数々は目に余るもの。加えてイヴァーノの父である舅も、今は体調を崩して寝たきりになっているものの、イヴァーノに輪を掛けたDV野郎。ベッドに寝ながら嫁を罵り続ける恐ろしさたるや、怖気が走りました。さらに夫婦の2人の小学生くらいの息子たちも、祖父や父に倣って既に乱暴な言葉遣いをするDV予備軍。つまりは親子3代に渡る折り目正しいDV一家な訳です。娘のマルチェッラこそ母に暴力を振るわないものの、DV夫に唯々諾々と従う母のようになりたくないと母のことを軽蔑している始末。
こんな地獄絵図を描いた本作ですが、嫌悪感満載で観てられないと思う一方、イタリアの懐メロ風の音楽が流れてミュージカル調に夫婦がDVをしながら踊ってみたり(このアイディアと振り付けは抜群!)、会話のそこここにクスっと笑いを誘うフレーズが入っていたりと、コメディとDVを見事に融合させた監督の演出に心を左右に揺さぶられる心地良さもあり、一筋縄ではいかない作品でした。
そしてここぞという時に失敗するデリアの姿を描くという”伏線”を張り巡らしておいて、ラストで一気に回収するという構成も見事であり痛快。そして謎の”手紙”が、実はイタリア史上初めて女性参政権が認められた選挙の投票券だったとは、全く予想だにしておらず、この展開にも唸るばかり。特に、毎度のドジを踏んで投票券を落として投票所に向かったデリアの後を追ったDV夫との追っかけっこに興味を集中させておいて、最後に娘が投票券を持って来て母に手渡すシーンは秀逸でした。これは戦後80年経過しても、いまだ世界的にミソジニーが幅を利かせる世界への、映画表現を使った理性的抗議であると同時に、感情表現によって親子の情愛の美しさを描く普遍的な物語でもあり、非常に美しいシーンでした。
そんな訳で、本作の評価は★4.6とします。
タイトルなし(ネタバレ)
第二次大戦後のイタリア・ローマ。
主婦のデリア(パオラ・コルテッレージ)は、傘の修理、カバンなどの繕い物、洗濯女などと複数の仕事を掛け持ちして家計を支えている。
が、男尊女卑の世の中。
夫イヴァーノ(ヴァレリア・マスタアンドレア)は、何か気に食わないことがあるとデリアを殴って気を紛らわせている。
そんな様子を常日ごろから見ている長女マルチェッラ(ロマーナ・マジョーラ・ヴェルガーノ)は母のようにはなりたくないと思っている。
そんなある日、デリアは幼馴染の自動車修理工から駆け落ちしないかと誘われ、マルチェッラは交際している成金息子からプロポーズを受ける・・・
という物語を、モノクロで描いています。
とにかく男尊女卑が凄まじい世の中で、まともに撮ると気が滅入りそうになる内容。
なので、息抜き的ユーモアを交えてみせる。
特に、夫の暴力シーンはミュージカル仕立て。
まぁ、ユーモラスといえばユーモラスだが、やりすぎと言えなくもない。
半ば過ぎにデリアのもとに届く「謎めいた封書」がミソだが、「愛のことづて」かというと、そうでないあたりが興味深い。
ということで、副題「愛のことづて」はちょっとミスリード的。
ただし、映画もちょっとミスリード的なストーリーテリング、演出なんだけれど。
なお、モノクロ映像で戦後の雰囲気を醸し出そうとしているが、室内描写はまだしも、屋外描写が戦後にみえず現代的なのは、少々マイナス。
監督が若い人たちに伝えたかったこと
舞台は、終戦後、米軍が進駐し木戸番をしている1946年のローマ。
労働者階級で、アパートの半地下の部屋に住んでいるデリアは、夫と寝たきりの義父の圧迫に苦しみ、口よりも手が早く出てきて、しかも口を開けば、罵る言葉が出てくる貧しい環境で、幾つもの仕事を掛け持ちしながら、3人の子供を精一杯育てている。モノクロ・スダンダード画面で、まるでネオレアリズモを思わせるが、実はそうではない。音楽は時代を超越していて、アキ・カウリマスキみたいだし、深刻な場面になると、ダンスが入って、アメリカのミュージカルのような味付けになり、飽きさせない。
ネタバレとしなければいけないことが残念。
二つ大事な要素あり。
イタリアは、もともとカトリックが極めて強い上に、戦争前からファシストが支配していたため、男性中心社会が長く残った。特に日本と違うのは、財布も男性が握っていたこと。お隣のフランスでも、長い間、女性は夫の了承なしに、銀行口座を開くこともできなかった。ただ、この映画の主人公、デリアは、娘のために、ちゃっかりタンス預金している。彼らにとって、最も大事なことは、日曜日、できるだけ正装して、礼拝に出ること。
このような社会を打破する最も有効な方法は、女性が参政権を持つことだけど、この映画でも、それがポイントになる。女性が漸く参政権を持ったこの年、デリアは、困難を乗り越え、投票所に駆けつける。
一番、印象的だったこと。美しく育った娘のマルチェッラは、成り上がりの息子ジュリオからプロポーズされるが、表面だけをみて、母親を非難している。デリアは、マルチェッラが目の前の幸せをつかむことよりも、自分とは違って、チヤホヤしてくる男に騙されず、男を見抜く力を蓄えてくれることを、何よりも望んでいた。
肩のこらない、しかし見終わって、爽やかなものが残る、良い映画だった。
与えられたカードで変わるのは、自分自身のアイデンティティなんだと思った
2025.3.24 字幕 イオンシネマ京都桂川
2023年のイタリア映画(118分、G)
戦後イタリアの女性投票運動を描いたヒューマンドラマ
監督はパオラ・コルッテレージ
脚本はパオラ・コルッテレージ&フリオ・アンドレオッティ&ジュリア・カレンダ
原題は『C'è ancora domani』、英題は『There’s Still Tomorrow』で「明日はまだとある」という意味
邦題の副題は劇中で引用される「Anna Garofalo(イタリアのジャーナリスト、アンナ・ガラファロー)」の言葉「Stringiamo Le Schede come biglietti d'amore」の邦訳「投票用紙は、私たちの愛の言づて」からきていると思われる
物語の舞台は、1946年のイタリア・ローマ
戦後まもないこの街には在留米軍が駐留し、人々は普通の暮らしに戻っていた
サントゥッチ家の母デリア(パオラ・コルテッレージ)は、献身的に夫イヴァーノ(ヴァレリオ・マスタンドレア)を支えていたが、彼は戦争体験がトラウマとなっていて、短気で粗暴な性格も相まって、何かあるごとにデリアに暴力を振るっていた
デリアの娘マルチェッラ(ロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノ)は、そんな母を心配しながらも、父に服従する姿に嫌気を差していた
家にはセルジオ(Mattia Baldo)とフランチーノ(Gianmarco Dilippini)という幼い二人の息子がいたが、二人は父の真似をして悪態をついていた
さらに、イヴァーノの父オットリーノ(ジョルジュ・コランジェリ)は不随で動けず、デリアと近隣の世話人アルヴァーロ(Raffaele Vannoli)が交代で面倒を見ていた
また、デリアには30年前に相思相愛関係だったニーノ(ヴィニーチオ・マルキオーニ)がいたが、デリアはイヴァーノの求婚を受けて結婚していて、ニーノは毎朝彼女を見かけるたびに後悔していると告げていた
映画は、マルチェッラとジュリオ(フランチェスコ・チェントラーメ)との結婚が決まり、両家がデリアたちの家に来るところから動き出す
マルチェッラは家族のことを恥じていて、それが原因で破談になるのではと恐れていた
ジュリオの父マリオ(Federico Tocchi)は戦時に飲食店を経営して成功した人物で、妻のオリエッタ(Alessia Barela)はマルチェッラの家柄を気にしていた
だが、マリオは当人同士の意思を尊重し、結婚後に息子がちゃんと躾けるだろうと考えていた
ジュリオも結婚したら彼女が専業主婦になることを望んでいて、しかも自分以外の男に綺麗な姿を見せないようにと、人前での化粧も禁じ始めていた
デリアはジュリオが結婚相手として相応しいのかを心配していたが、マルチェッラは聞く耳を持っていなかった
物語は、イタリアの女性参政権前日を舞台にしていて、デリアが姉のアーダ(Barbara Cheisa)から「ある手紙」を受け取る様子が描かれている
それは6月2日、3日に行われる選挙の投票権で、デリアは当初はそれに参加する気はなかった
だが、ニーノが去り、義父も他界して状況が変わってくると、デリアは「娘のために」と投票に行く事を考え始める
友人のマリーザ(エマヌエラ・ファネリ)とも口裏を合わせるように仕向け、ようやくイヴァーノからの解放を考え始めるのである
ラストでは、投票に行く行かないでハプニングが起きて、そこである人物がデリアの落とし物に気づくという流れがある
それを手渡すシーンはとても感動的で、投票行動そのものが女性に勇気を与える様子が描かれていく
これによって時代の変化が生まれ、ほとんどの女性が参加した投票によって、時代は大きく移ろいゆくことが示されて映画は終幕となっていた
いずれにせよ、1946年6月にイタリアで何が起きたかを知っているとグッとくる内容になっていて、ラストのアンナ・ガラファローの引用も小気味の良いアクセントになっている
彼女はイタリアのジャーナリストで、女性参政権の運動家だった人物で、最後の言葉は彼女の言葉の引用となっている
「投票用紙(カード)をラブレターだと思っている」という趣旨の言葉で、映画では「愛の言づて」という風に翻訳されていた
それがマッチするのかは何とも言えないのだが、原題の一部を切り取って「ドマーニ」だけを抽出するのもナンセンスだと思うので、そこは「私たちの明日は手のひらの中に」みたいなニュアンスの方が映画の内容がわかりやすく伝わったと思う
邦題の印象だと戦後イタリアのメロドラマみたいに思われてしまうので、その趣旨がないとは言わないが、明日を勝ち取ることになった女性の勇気を示すには足りない部分があったのではないかと感じた
副題は完全にミスリード。洒落を狙っているなら捻りすぎ
劇映画としては、とても面白かったのだけれど、クライマックスが。。。
このクライマックスに、物語的な重要な意味があるのはとても良く分かるのだけれど、物語の展開的には、かなりシラケてしまったかな。
投票啓発映画ですか。
原題はイタリア語で「C'e ancora domani」。直訳すれば「まだ明日がある」。
直訳を、そのまま邦題として使えると思う。
意味ありげにイタリア語の「ドマーニ」をそのまま使うのは良くない。
副題の「愛のことづて」は更に良くない。完全にミスリードしているし、洒落を狙っているなら捻りすぎだと思いました。
オープニングクレジットと音楽が素敵!!
昔のモノクロ映画を観ているようで、音楽の使い方が今時で、好みでした。
ストーリーは完全にミスリードされちゃいました。娘が書類を持ってきたところとか、涙溢れてしまいました。母親の愛の逃避行を見守るのか、と思いつつ、あー、選挙かー!そうだ、そうゆう映画だったと思い出した次第。女性の家庭や社会での地位など、シビアな社会背景を、描きつつ、基本はコメディで、うまく演出された映画だと思いました。館内でも結構くすくす笑い声が起こってました。
斬新で愛おしい映画。
モノクロで虐げられた女性の権利をテーマとした映画。
確かにその通りではあるが、まったく予想の斜め上をいく凄い映画だった。
夫のDV場面がミュージカル風だったり、恋心で見つめ合う2人の歯がチョコレートまみれで、しかも待たされて怒るおっさん客を入れ込みながらのグルグルカメラワーク!
突然、普通に起き上がる寝たきりの義父をはじめ、バカ夫、バカ息子2人、娘のバカ婚約者等々のキャラクター祭り!
その中で輝く娘の可憐な美しさは、主人公の母からテーマを受け継ぐにふさわしい。
ラスト、拭う口紅からのエンドロール曲に合わせたハミングの口の動きのチャーミングさ。
なかなか考えつかないセンスのある演出で彩られた上質の人間ドラマであり、上質のコメディである。
少しでも多くの人に観てもらいたい傑作。
全14件を表示