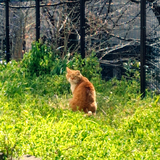愛はステロイドのレビュー・感想・評価
全104件中、1~20件目を表示
筋肉美映画
筋肉美を強調する女性が主人公の作品は珍しい。舞台は80年代。80年代といえば、アーノルド・シュワルツェネッガーやシルベスター・スタローンなど、筋肉系男性スターの時代だ。男性的な価値観が支配する町を舞台に、そこから抜け出し夢を追いかけようとする2人の女性の戦いが描かれる。
元ボディビル選手のケイティ・オブライアンのほれぼれするような肉体が本当にいい。もう一人の主人公・クリステン・スチュワートのボーイッシュさもすごくいい。いずれもあのような町では生きにくそうである。
クリステン・スチュワートは、この映画でずっと何かを掃除しているなと思った。初登場シーンはいように汚いトイレを掃除しているし、ジャッキーの殺害現場の掃除もするし。映画を通して何度も掃除している。これはどういう風に解釈したらいいか、ずっと考えている。
最後の展開はやたらぶっ飛んでいて、清々しい気分になれる。
「サブスタンス」との共時性。女性監督たちのジャンル映画への進出、大歓迎!
本作のローズ・グラス監督は1990年英国生まれ。デミ・ムーアが主演した「サブスタンス」のコラリー・ファルジャ監督は1976年フランス生まれ。年齢は一回りちょっと違うが、2人の女性監督がタイミングを同じくして、米国資本も入った合作で女性の身体をモディファイ(改変)するボディホラー風味の強烈なスリラーを撮ったことが興味深い。シンクロニシティか、一大潮流の始まりなのか。
偶然でなく時代の流れだととらえるなら、ポリティカルコレクトネスやコンプライアンスが重視される昨今、男性のフィルムメーカーが女性への暴力や女性の身体を損壊したり醜く変形させたりする表現を、差別だ蔑視だなどと批判されるのをおそれて自由に描きにくくなっている状況が背景にあるのではないか。一方、女性のフィルムメーカーが女性の身体をどう扱おうが勝手、フィクションの中なら暴力だろうがあり得ない変形、変身だろうが文句あるか!的な奔放さが、作り手と出資する側に共有されているのでは。そんなことを、「愛はステロイド」を観ながら考えていた。
後半のステージの場面が、緊張と高揚と狂気が交錯する映画のハイライトの1つになっているのも、「愛はステロイド」と「サブスタンス」の共通点。ここではデヴィッド・クローネンバーグ監督のテイストに近いものを感じたが、ラストの超展開では突き抜けた独創性に爆笑。よいものを見せてもらった。
クリステン・スチュワートの作品選びのセンスは相変わらず冴えている。共演のケイティ・オブライアン、これからのさらなる活躍に期待。従来は男性監督の寡占状態だったバイオレンスやボディホラーなどのサブジャンルに、女性監督たちが進出してきたことを大いに歓迎したい。
笑っちゃうほど豪快で楽しくて危険
またもA24から誕生したジリジリと焼けつくような異色のサスペンスだ。田舎町、スポーツジム、ボディビル。これらの要素が二人の女性を運命的に巡り合わせ、やがて巻き起こる犯罪がらみの展開を経由し、想像を超えた結末へ突き落とす。世界の果てのような町を舞台に、これほど常軌を逸した描写を次々と矢継ぎ早に生み出せる手腕はなかなかのもの。あらゆる登場人物はもはや”力の匙加減”が思い切り馬鹿になってしまっている。だからこそつい感情が先行し、近くにいる大切な人や関係をつい台無しにしてしまうのだろう。その意味でも即効薬にして副作用もある「ステロイド」は、全てを包含する象徴的な存在。刻々と立場を変えるスチュワート&オブライエンがかつて見たことのない輝きを放てば、名優エド・ハリスも外見から内面まで全てに凄みあふれるたまらない怪演ぶりを発揮。人間のおっかない闇を垣間見せつつ、笑っちゃうほど豪快で危なくて楽しい一作だ。
ホントの愛は怖いよ…
面白かった。
ハイリハイリフレハイリホー♪
邦題が意外にピッタリとハマる
ベルリンの「壁」のニュースが出ていたのでこの映画を描いていた時代がわかった。ニューメキシコ州はヒスパニック系の人口比率がアメリカの州の中で1番多いとのこと。メキシコからの移民も多いのだろうからトランプが作った「壁」も今はあるのだろう。だがこの映画はそんな政治的なことや民族的なことはほぼ関係ない。荒廃したとある場所で起きる恋人や家族の愛憎劇を衝撃的なショットの連続で見せつけるやや不気味な物語だ。なので作り手側も何かに共感して欲しいことなどはないだろうから見る側もとにかく観て楽しむべき映画と言える。
ルーとジャッキーの出会いと恋に落ちていく様、ジャッキーのボディビルへ注ぐ情熱。異常者である父親の行動、JJに鉄槌をくらわせた後のドロドロの展開〜映画としてたっぷり楽しめました。邦題の「愛はステロイド」なんてセンスのかけらもないと思ったが、最後にジャッキーがルーへの愛の証明の如く巨大化するの見たら、何だ邦題はピッタリだと納得。大笑いしそうになったけどね、。まぁ〜傑作でした!
女たちの愛は強し
レズビアンとボディビルダーのロマンスというユニークな設定が面白い。
ルーは裏社会に生きる父の呪縛に捕らわれながら荒んだ人生を送っているレズビアン。ジャッキーはボディビルダーのコンテストの優勝を夢見る流れ者。孤独な者同士、惹かれ合っていくが、そんな二人の前に父権主義、つまりルーの父親が立ちはだかる。昨今の潮流で言えば女性の地位向上、フェミニズム映画の片鱗が見て取れる。それはルーの義兄のDVからも窺い知れる。
監督、脚本は前作「セイント・モード/狂信」で長編監督デビューを果たしたローズ・グラス。
「セイント~」にもレズビアンのラブシーンがあったが、その流れを汲めば本作のルーとジャッキーのロマンスは興味深く読み解ける。グラス監督は女性作家なので、シスターフッド的な繋がりに強い関心を持っているのかもしれない。
前作からすでに映像に関しては卓越したセンスを見せていたが、今回も画面の構築力は手練れている。
例えば、映画の冒頭。どす黒い岩肌を舐めるようなカメラワークで捉えた映像に引き込まれた。そこがどこかなのかは一切説明がないのだが、衝撃的な事実と共に後半になって判明する。なるほどと思った。
真っ赤に染め上げられた毒々しいイメージショットが時折インサートされるが、これも終盤になってその意味が分かる。やや凝り過ぎという気がしなくもないが、不穏なトーン作りに一役買っていると思った。
ステロイドの注射で膨張するジャッキーの筋肉を捉えたクローズアップも強烈なインパクトを残す。まるで”ハルク”を思わせる肉体の変容にボディ・ホラーのような怖さを覚えた。
終盤ではファンタジックな演出も挿入される。前作のラストもそうだったが、観る人によって様々な解釈が出来るような終わり方となっている。個人的にはルーの妄想と解釈した。
一方、物語も基本的には面白く追いかけることが出来た。ブラックユーモアとサスペンスタッチを変幻自在に織り交ぜながら上手く作られている。
ただ、終盤にかけてやや強引な展開が目についたのは残念である。FBIの捜査が杜撰だったり、ルーの父親の行動も何だか締まりがない。
また、ジャッキーのバックストーリーは後半で少し語られるのみで、ほとんど不明である。ルーにとってのミステリアスな存在として造形したかったのかもしれないが、ドラマ的には少し物足りなさを覚えた。
キャスト陣では、ジャッキーを演じたケイティ・オブライアンの肉体美を活かした怪演がインパクト大である。今回が初見だと思ったが、実は「ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング」にもクレジットされていたことを後で知った。潜水艦でトム・クルーズを助けた女性隊員と言えば、思い出す人も多いかもしれない。
ルーを演じたクリステン・スチュアートはバイセクシャルをカミングアウトしているので、こういう役は正にうってつけという感じがした。本人的にもかなりノリノリで演じていたのではないだろうか。
そして、ルーの父親を演じたエド・ハリスの、ちょっと笑ってしまうくらいのやり過ぎ演技もいい味を出していた。
期待した俺がバカだった
自由の獲得とその代償ーー平成元年アメリカを舞台にした稀有な恋愛スリラー
変わったタイトルなので、スルーしていたのだが、先日、別の映画で予告編が上映され、これはいいかも!と思って、観にきてみた。公開からしばらく経っていることもあり、平日1日1回の上映はガラガラだったけれど、観て大正解! 面白いし、考察ポイントがたくさんある映画だった。
しかもオープニングで気づいたけれど、先日観た「テレビの中に入りたい」に続けてA24の制作で期待が高まったし、高まった期待に見事に答えてくれた。「テレビ〜」に続き、本作も作家性が高く、色々な要素が詰め込まれている。そして、現代社会の批評的な文脈も豊富に取り込まれている、なかなかに手強い1作であるとも思う。観終わって、まだモヤモヤしているところもあるので、感想を書きながら自分なりに読み解いてみたい。
ベルリンの壁に関するニュースが挿入されていたので、舞台は、おそらく1989年。日本では平成元年で、僕が就職した年だ。ということは、本作の主人公の女性二人、トレーニングジムで働くルー(クリステン・スチュワート)と、ボディビルダーのジャッキー(ケイティ・オブライエン)は僕と同世代だから、より共感が深まった。
実際、本作が描く社会状況や様々な文化は覚えがある。現在のアメリカの状況の原点が、この時代に見ることができるし、当然、日本人の僕らにもそれは関わってくることだ。40年前の過去を舞台にすることで、現代を鮮やかに描くことに成功した映画だと言っていいと思う。
本作の設定で重要なのは、ジャッキーがアメリカ中部オクラホマ出身で、西海岸を目指しているという点だ。アメリカ内陸部は家父長的・宗教的規範が強い「内陸の保守」。その世界に息苦しさを感じて、目指すのは西海岸カリフォルニア。世界で最も、開放的で自由、多様な生き方と自己表現が許容される「沿岸のリベラル」エリアだ。
ジャッキーは、おそらく教育も不十分でお金もない。性的にもノンバイナリーで保守的な田舎では認められ難い。そして異形の肉体で、さらに保守的内陸部では生きにくい。だから自らの個性「筋肉」を武器に自由を手にするために西海岸へ向かう。
自らの意志と個性で、自分の力で、自分の人生を切り開く。これは当たり前のようだけれど、80年代から急速に広がった感覚でもある。
1989年は『7つの習慣』がアメリカで刊行された年だ。自己啓発を代表する1冊の冒頭の第一の習慣は「主体的である」。人はデフォルトでは、周囲の人や環境に動かされるように生きている。そうではなく、どう感じ、考え、行動するかは自分で決めることができるし、そうするべきだという教えだ。
これが案外困難だ。僕自身は2000年頃本書に出会い、その後、後輩たちの求めに応じて読書会や社内研修もした。分かっている、実践できているつもりでいたけれど、今年、退職を決めた日に、通勤電車の中で「あっ」というような気づきの瞬間があった。この第一の習慣が初めて理解できた感覚があって、思わず電車の中で泣いてしまった。
この(少なくとも僕にとっては)とても困難な「主体性の獲得」を主張する本が、この時代にアメリカで広まった背景には80年代のレーガン政権がもたらした新自由主義的価値観がある。小さな政府と規制緩和によって実現した自由に成功を求められる環境のもとでは、成功できないのは自己責任となる。
個人の成否はセルフヘルプ(自助)の結果。自らの意思と努力で自己改善に励み自由と自己実現を手にすることが普遍的価値として提示され、それが受け入れられる時代となった。
ルーが働くトレーニングジムの壁の様々な標語が映画中でも何度もインサートされるが、それらもそうした価値観を表している。
「肉体は、心が信じることを成し遂げる」
「負け犬だけがあきらめる」
「体が痛むのは、心の弱さが去っていく表れだ」・・・などなど。
トレーニングはある種の宗教的行為でもあり、ジムは宗教的な殿堂として、その信仰の確認と実践の場でもあるという表現が迫力満点だ。
筋肉が増えることは人間の根源的欲求にも繋がっている。ニーチェのいう「力への意志」やアドラーの言う「権力への意志・劣等感の克服」としても理解できる。そして、次第に筋肉獲得自体が自己目的化していくのは、ダイエットとも同じ構図だ。筋肉は自制心の証明でもあり、自己実現なのだ。
そして目的となった筋肉獲得のための最も効果的な手段が、本作のタイトルにもあるステロイド(アナボリック・ステロイド)。映画では、ステロイドを使わず肉体を作り上げたジャッキーに、ルーの副業的な商品でもあるステロイドを気楽に打ち、そこから物語が急展開していく。ステロイドの作用の表現として、筋肉がぎしりぎしりと音を立てて、肥大していく描写が何度も挿入される。
ステロイドの副作用として(医学的には必ずしも証明しきれていないようだが)精神面の不安定化や、攻撃性の上昇ということが言われていて、映画でもそうした流れになっていく。
僕はかつてプロレスファンだった。だから、主人公たちや僕と同世代の新日本プロレス出身のレスラー、クリス・ベノワを思い出してしまう。日本ではジュニアヘビーの小さなレスラーだったが、アメリカに戻って急速にマッチョとなりヘビー級チャンピオンにもなった。そのベノワが家族を殺し、自殺するという衝撃的事件。当時、ステロイドによる錯乱のように伝えられたのだけれど、それを思い出させるような変化が、この映画でもジャッキーに起こっていく。
女性にとっての筋肉の意味はさらに複雑だ。80年代にはミスオリンピアが創設されたが、当初のチャンピオンは、ジャッキーほどマッチョな感じではない。その後、筋肉をつけることは女性開放なのか、男性的価値観への服従なのかというような議論もあったようだ。この作品はその歴史的文脈を押さえて、筋肉(力)による自己決定の自由の獲得のダークサイドも描いている。
当時の、そして現在のアメリカでも、自由を享受できるのは、一部のエリートに限られている。エリートは自らの努力でその地位を手に入れたと言うが、様々な研究で言われる通り、所属する社会階層など先天的に決定されている要素は相当ある。
何も持たないものが自由を獲得するには、大きなリスクを取るか、裏技的な手段に頼らなければならないという現実があるという認識が、この映画を撮らせたのではないだろうか。
そうした先天的恵まれた条件を持たない人が、厳しい世界で生きるには、「心の痛み」が伴い、それがオピオイド中毒という現象となった。この映画はそこまでを射程に入れて物語っているのではと感じさせた。
まとめると本作は、1989年の情景(保守とリベラルの分断、自己責任文化の萌芽、そして現在に続くジム文化の隆盛)をを再現しつつ、自由の獲得と女性開放や、薬物による精神と肉体の自己改造の問題などを、恋愛スリラーという形に見事にまとめ上げた稀有な1作と言えると思う。
ボディビル大会では「でかい!」という掛け声が最高の承認の一つであるそうだけれど、本作は様々な現実をそのデカさを求める精神性という単純明快なイメージに集約して見せている。
なんか小難しい感想になってしまったけれど、さまざまな考察要素を埋め込むのがA24作品の真骨頂だ。的外れな考察だっていいのだ。そうして何度も咀嚼し直して楽しむのが正解なんだと思う。何度も思い出して考えたくなる、豊かで、複雑で、寓意に満ちた見事な作品だ。
愛はステロイド
申し訳ない、合わなかった😣
女性の筋肉美に焦点を当てているのが面白い 洋題にはステロイドって言...
女性の筋肉美に焦点を当てているのが面白い
洋題にはステロイドって言葉は入ってないのに思い切った邦題だけど、ストーリーの不穏さをうまく表してるかな
主役の二人と久しぶりに見たエド・ハリスがいい味を出し、どっちに転ぶかわからない展開で最後まで楽しめた
シスターフッド映画の傑作!「純愛は最強のステロイド!」 突き抜けたクライマックス!エド・ハリス怪演!
レズビアン映画の怪作?快作!
Youtubeで予告編を観て気になっていた。ムキムキ美女がゴジラ化して大暴れするのか?!と思ってしまったけど、本編は真面目なレズビアン世界をサスペンスたっぷり、そしてぶっ飛んでいながら田舎町というスケールが心地良いんです。
主演のクリステン・スチュワートはじめ、キャスト、スタッフはレズビアンを公言している多様性の一作とも捉える事が出来るが、セックスシーンも多いけど全く嫌らしくないのは監督が女性だからでしょうか。
出てくる男は全員が悪。だから主演の2人にボコボコにされてしまうけど、痛快さはそこには無い。やればやるほど破滅への道へ進んでしまうというヤバさ。これがマイノリティの現実なんだろう。
クリステン・スチュワートは過去一と言って良いほど良い演技をしていて、田舎町でくすぶっているヤサグレ感に彼女の本性をみた気分。
そして怪演エド・ハリス!
タイトルロールで名前を見たとき、良いお爺ちゃん役でちょっと出るくらいと思っていたら、この映画の要となるラスボスで大迫力。まさかヘラクレスオオカブトを丸ごと食べるなんて、このシーンだけでも一生忘れない映画になりました。
濃厚な女性レズビアンワールドに酔いしれる怪作です。
ノワール苦手かも
主人公ルーの日常が、あまりに救いが無くてゲンナリ
親父が悪いやつなのは分かるけど、抵抗する気力すら失ってる絶望感にゲンナリ
お姉さんは確かに可哀想なんだが
ルーがそれを助ける事に執着してるのは、そこにしか自分の存在意義を見出せない事による依存な気がするし
そこに現れたジャッキーは魅力的だけど
速攻「卵焼きは黄身ぬきにしてね」「はい…わかりやした」
って感じで主人公は結局誰に対しても虐げられ体質で
根本変わらないと結局どこで誰といても救いが無いよ…と
冒頭の詰まった便器のような不快さに
自分まで引きずり込まれてしまうような感覚になってく作品
でもそこまでリアルに主人公の境遇を表現してるだけで
すごいレベルの映画なのは間違いない!
ただ私が映画であんま嫌なきもちになりたくないから
少し減点してしまっただけ…
確かに不快な割に好きなシーンも多い
・エドハリスは強烈すぎて出てくるたび笑う
・デイブフランコの髪型の不快さも笑う
・デイブフランコの死体を発見する時のクリステンスチュアートの演技が上手すぎる
驚きすぎて二度見するのがリアルで面白すぎる
・ラストのビックリサプライズ
・役者は全員演技最高、特にケイティオブライエン!
愛はステロイド、なかなか粋な邦題
1989年、ボディビルの大会に出るためヒッチハイクでラスベガスに向かっていたジャッキーは、仕事を紹介してもらうため途中の街で男と寝て、射撃場のウェイトレスの仕事を紹介してもらった。その後トレーニングジムへ行き、従業員のルーと出会った。ルーはレズで、ジャッキーに惚れ、2人は恋に落ちた。実は、ルーの父親は射撃場とトレーニングジムの両方のオーナーだったが、街の裏社会を仕切り凶悪な犯罪を繰り返していた。そして、ルーの姉は夫からDVを受けていて、ルーは家族にさまざまな問題を抱えていた。そんなルーの苦悩を解決しようとしたジャッキーは、仕事を紹介してくれた男がルーの姉のDV夫だとわかり、ルーのために彼を懲らしめようとし、度を越して彼を殺してしまった。姉の家にやってきたルーにDV男の死体を発見され・・・さてどうなる、という話。
ボディビルダーのジャッキーは肉体美が素晴らしいし、ルーも可愛いかったし、レズシーンはエロくて良かった。
警察も巻き込んでの裏社会を仕切る親父、自分の身を守るためなら娘でも殺そうとするものなのか?相当な悪だなぁと驚いた。
悪の親父を演じたエド・ハリスの怪演は素晴らしい。
確かに、裏社会の悪人たち、レズシーン、殺した男の崩れた顔面など、ノアール、ラブストーリー、スリラー、とてんこ盛りだけど、行き当たりばったりのジャッキーは何か抜けてる。ステロイドの影響?そこがユーモアなのかも。
ハードなレズビアンの激愛
全104件中、1~20件目を表示