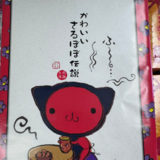国宝のレビュー・感想・評価
全2378件中、181~200件目を表示
「本物の歌舞伎に触れる、魂揺さぶる物語」
【正反対の運命を背負った二人の青年】
物語の軸となるのは、吉沢亮さん演じる喜久雄と、横浜流星さん演じる俊介。
喜久雄は長崎に暮らしていた15歳のとき、目の前でヤクザの義父を殺され、そのまま大阪の歌舞伎一家に預けられ、意志とは無関係に厳しい修行を受けることに。一方、俊介は生まれながらにして歌舞伎一家に育ち、歌舞伎をやるのが当たり前という環境に身を置く青年。
まったく異なる出自の二人が、血縁と才能という逃れられない運命に翻弄され、互いに刺激しあいながら、役者として成長していく姿が描かれます。
【それぞれの魅力と演技の違い】
喜久雄はもともと女方の素質があり、飲み込みが早い。一方で俊介は、生まれながらに歌舞伎役者という「恵まれた立場」に甘んじつつも、自分の進む道に苦しみながらも懸命に努力するボンボン的存在。
横浜流星さんは、映画『正体』でも見せた「可哀想な子」を演じる才能が今回も存分に発揮されており、「ほんまもんの役者になりたいんや」というセリフには心を打たれました。
俊介の父・半二郎(渡辺謙)が、自身の跡継ぎを血の繋がらない喜久雄に託すという、歌舞伎界のタブー中のタブーを描いた展開も衝撃的。その選択に葛藤しながらも、最期に息子・俊介の名を呼ぶシーンには深い愛が感じられました。
【圧巻の歌舞伎シーン!亮と流星の努力の結晶!】
とにかく、歌舞伎のシーンが素晴らしい!
吉沢亮さん、横浜流星さんは、他の仕事も抱える中、1年間かけて歌舞伎の踊りと演技を習得したそうです。もともとの素質では亮さんが一歩リードしていたそうですが、流星さんは持ち前のガッツと努力でそれを追いかけ、見事に演じ切っています。
劇中に登場する演目では「二人道成寺」では手ぬぐい、笠、鈴太鼓などを使った妖艶な舞、「曽根崎心中」の緊迫した感情表現など、どれも素人が見ても圧倒される完成度でした。
【撮影現場で体感した「本気の現場」】
今回、私は京都・南座や上七軒の歌舞練場(芸子、舞妓の訓練場)、大阪の昔ながらのキャバレーなどでエキストラとして撮影に参加しました。普段は入ることのない場所に足を踏み入れ、歌舞伎の世界を映画で表現しようという壮大な挑戦に触れられたのは、一生の思い出です。
現場では、俳優陣(亮さん、流星さん、渡辺謙さん、寺島しのぶさん、高畑充希さんなど)をはじめ、李監督、カメラ、照明、方言指導など多くのスタッフが一丸となって映画づくりに挑んでいました。
朝5時から夜9時まで、衣装・髪型・小物のチェック、食事の用意、300人近いエキストラの管理…。ものづくりの裏側に、これだけの人と労力があることを知って感動しました。
印象深いのは、俊介が観客として喜久雄の「曽根崎心中」を見つめるシーン。俊介の心の揺れが物語の分岐点になる重要な場面で、監督の演出も非常に熱が入っていました。
【推しのために全国から!エキストラたちの熱量】
エキストラの多くは亮さん、流星さんのファン。北海道から九州まで、交通費も宿泊費もすべて自費で駆けつけていました。
観客役だったため、舞台で演じるお二人を堂々と見られるという特典付き。花道の近くでは「生の素足と爪が見えた!」とファンが歓喜する場面もww。
そして、映画『国宝』の評価は――
評価は、文句なしの5.0。SSSトリプルSのランクです。世界に誇れる映画だと現場でも確信しました。
エンタメ性、芸術性、ストーリーの分かりやすさ、衣装、音楽、映像…。どれを取っても素晴らしく、全体の完成度が非常に高い作品です。
一つの作品が出来上がるまでに、どれだけの人の情熱と時間が注がれているのか。
それを肌で感じたこの映画、ぜひ多くの人に見てほしいと心から思います。
そして、映画ならではの映像による歌舞伎体験を、ぜひ劇場で味わってほしいと思います。
※あとがき
記念品とともに心に残る時間。
ボランティアエキストラなのでもちろん報酬はありませんが、映画のタイトル『国宝』と監督の名前が刻まれた記念品をいただきました。
ちなみに、記念品はステレンスボトル、扇子、傘の超吸水ポーチ、保冷バッグなどなど。
まさに自分にとっての『国宝』。
以上
久しぶりに映画観に行けた
吉沢亮と横浜流星の見分けが難しくて何度か間違えて観ていた・・・白塗りするとますます見分けが付かない。あと何故か横浜流星の方が主演だと思い込んで観ていたので、途中であれって・・・
べらぼうんl流星と違う!役者ってすごいな。
永瀬正敏気が付かなかった!
渡辺謙が女方って、なぜ?!と思ったけど白塗りして舞台に立つとそんなに違和感はない。でも渡辺謙は白塗りしてても渡辺謙だと分かるなぁ。
田中泥さんが良かった。
吉田修一は悪人や怒りの人だから・・・吉沢亮が渡辺謙に毒を持ったのかと思って観ていて、横浜流星にも毒を?!と思ったけど違うようだった。悪魔と取り引きしてたからてっきりもっとドロドロした話なのかと・・・
うーん、もっとドロドロしてても良かったのでは?
歌舞伎の上手い下手は正直分からないけど、音響や演出の工夫がされていて、舞台シーンは迫力があった。
スクリーンで観られて良かった。
いやすごいけど
すごいけど、まじで昭和元禄落語心中と話にすぎません?!途中であれなんでこんなに似てるんだと考えて、どっちらかパクリ?とあることないこと考えてしまった😓でもやっぱ歌舞伎は難しいなあ、感情理解も、セリフを理解するのも、一回観に行きましたが、イヤホンの説明がないと何もわからない感じだった。こんなこと言うのはなんなんだが、本当に人をこんなに辛くさせられるものってそんなに大事かと思ってしまった。
死の間際に実の息子の名を呼ぶのはある意味普通
死の間際に実の息子の名を呼ぶのはある意味普通だ。芸より血だと思っているんだとしかあの場では思えなかったし、実際本音としては実の息子に襲名させたかっただろう。家継続の為にはもう待てない。自分は我慢して目の前で頑張っている喜久雄に継がせよう。その我慢が限界を超えた瞬間が襲名披露の壇上だったのは不幸だったけど。それでも死ぬときは預かった息子ではなく、0歳から育ててきた息子の方の名を呼ぶのは役者としてではなく、父としての自分の心から、飾りなしに出た言葉だった。と思う。
喜久雄が俊介と違うのは、父を二回看取っていること。実の父と歌舞伎の父。それだけでも業が違う。俊介が帰ってきて隅に追いやられた時間は人生の休み時間であり、俊介がいない間に握っていたバトンを一時返していただけ。そして俊介が死んだあとは孫にバトンを渡す役目を遂げたはず。立派につないだのだ。
最後、国宝=国の宝にはなれた。見たかった景色を見つけた。けれども本当に喜久雄は国宝になりたかったのだろうか。それよりも、どこかのたった一人の一番の宝物になったほうが、人間としては幸せだったのかもしれない。死ぬときに混濁する意識の中で、「喜久雄」と必死で自分の名を呼んでくれる。そんな人はこの世界にいるのだろうか。芸に魂を売った結果、そんな人はいないかもしれない。わかっていてその寂しさをも抱きしめながら生きる喜久雄と、国を背負う全ての芸の人に心より感謝と敬意を表したい。
国宝
何で高評価?
当初、本作は観ないと決めていたのですが、私の周りで観てきた方々が皆さん絶賛するので、重い腰をあげて観てきました。
結論から言うと何でこんなに高評価なのかさっぱり分かりませんでした。
まず、踊りの場面については、私自身が歌舞伎を観た経験がないため、上手いのかどうか判断がつかず、頑張っているようには見えましたが、感動するまでには至りませんでした。ただ、映像的には早変わりの場面など、観客に分かりやすいような工夫がみられ、その点は評価できると思います。
また、ストーリーについては、後継ぎを一度決めてしまったら戻せないと、半二郎の妻がさんざん騒いでいた割には状況次第でころころ変わるし、主人公の恋人にしても、いつの間にかあっさり俊介の恋人になっていて、どっちでもいいの?って言う感じで、同情なのか愛情なのか、心の内が伝わって来ませんでした。
極めつけはラストのカメラマンが、偶然にも実の娘だなんて都合良すぎでしょう。
(追記)
歌舞伎は女性の役を男性が演じ、宝塚は男性の役を女性が演じるわけですが、何でわざわざ異性の役を演じるのか、私にはその良さが理解できず、違和感しか感じません。
想像を上回る、物凄いモノ 観た‼️
私、5回観ました。最初に観終わった時、感動で動けなかった。こんな凄い作品を、こんなに安い値段で観せていただいても良いのか‼️と思った。全編引き込まれるストーリー構成と、魅惑的なカメラアングルと映像の美しさ、劇中に流れる音響効果、何よりも吉沢亮と横浜流星の舞踊の完成度と演技力には、本当に恐れ入りました。どんだけ練習したんじゃろか、凄すぎる‼️演技を超えて、完全に憑依してました、もー絶句モノの感動巨編です。舞踏の場面は美し過ぎて、何回も何回も観たくて映画館に通いました。セリフの一言一句を覚えたかもです(笑)ラスト、エンドロールの向井さんの啜り泣くような歌声に魂を掴まれて、動けなくなりました。3時間、観客が全く微動だにしない、物音ひとつ、咳ひとつ聞こえない、エンドロール終了後も、皆んなが感動で、動けない、立ち上がらない観客が一体となってる連帯感すら感じました。こんな体験、なかなか出来ないよ。映画館で観なきゃ損だよ。
まだまだ、毎日でも観たいほど凄い‼️李監督凄い‼️
どこ見てんの?ーだから、どこ見てんのよ!
国内ではかなり評判がいいらしい。
そんな話を、帰国前から聞いていた。歌舞伎ファンの自分としても、期待はそれなりに大きかった。
けれど、森七菜演じる彰子のあの一言——
「どこ見てんの?」
このセリフが、なんとも皮肉に、この映画のすべてを言い表していた気がする。
俳優たちはそれぞれ“よく見て”演じていた。
でも映画そのものは、いったいどこを見ていたのだろう。
目がうつろになっていく二代目の姿が、その迷走ぶりを象徴しているようにも見えた。
森七菜は、以前の繊細な印象から一転、少し挑発的な役をそつなくこなしていた。
ついこの間まで「賢治の妹」だったのに、成長したものだ。
そして滝内公美(綾乃)や見上愛(藤駒)のキャスティングには、どこか奇妙なつながりを感じた。
「光る君へ」では、明子であり、彰子でもあった。登場人物たちが別の世界で呼応しているようで、つい目が泳ぐ。
定子=高畑充希=春江……この連鎖も面白い。
結局、「どこ見てんの?」と、観客の自分にも跳ね返ってくるのだ。
問題は、タイトルの「国宝」だ。
まさか本当に喜久雄が“国宝”になってしまうとは思わなかった。
タイトル通りすぎる展開に、ちょっと拍子抜け。
中盤のぐだぐだした流れも、俊坊や喜久雄のライバルが“人生の迷走”を繰り返すくだりも、正直、何を描きたかったのか掴みづらい。
脚本は結局、何を軸にしたかったのか。
人物なのか、芸なのか、それとも「国宝」という制度そのものの寓話なのか。
焦点がずっとぼやけたままだった。
とはいえ、俳優陣の演技は見ごたえがある。
吉沢亮の演技は確かに光っていたし、横浜流星も悪くない。
むしろ渡辺謙や田中泯といったベテランの存在感が、やや浮いて見えるほどだった。
でも、もし世間が“名演”だけを見て満足しているのだとしたら、やっぱり言いたくなる——「どこ見てんの?」
この映画、演技の力で持っているけれど、映画という総合芸術としてはバランスを欠いている。
演技が良ければ良いほど、作品自体の空洞が目立ってしまうという皮肉。
チームで作る映画を、個の技量だけで完結させてしまった感じがする。
結局のところ、吉沢亮——いや、アイリスオーヤマのCMだけが、自分の視線の行方をちゃんとわかっていたのかもしれない。
ラストの余韻まで、どこか広告っぽいきらめきが残るのはそのせいだろう。
アイリスオーヤマだけが、きっと喜んでいる。
……そして気づけば、自分も問われている。
「で、あなたはどこを見てたの?」と。
芸を極めるためには全てを捨てる潔さ
国宝になるためにこの世に生を受けたような吉沢亮くんの演技は圧巻でした。
そして、横浜流星くんの存在もなくてはならない存在で、お互いに切磋琢磨して芸を磨き上げる、特訓のような厳しいお稽古の毎日、歌舞伎という特殊な世界に身を置いた二人、家柄血筋全てを持っている横浜流星くんと違い、やくざの子である吉沢亮くん、何よりもほしいのが血筋、しかしどうしても手に入らない葛藤、お稽古にお稽古を重ねる以外には手だてがない、芸を極めるためには全てを捨てる潔さ、
何かを得るためには何かを捨てなくてはならないのだと思う。
とにかく舞台も音楽も美しいので、映画館で観るべき作品です。
リピーターも多いようで、私も2回目でしたが、2回目も感動しました。
3時間があっという間にすぎていき、最後まで飽きることなく鑑賞出来ました。3回目も観たいと思います。
賞という賞を総なめするのではないかという予感がします。
また、
昭和の古きよき時代の3名の女性陣にも拍手を送りたいと思います。
高畑充希さん、見上愛さん、森七菜さん、各々に素敵な女性を演じられていました。
吉沢亮さんは、国宝になられるくらいの男性ですから、女性たちも関わり方が難しかったでしょうし、ご苦労をされたのではないかと思います。
しかし、お三方共に吉沢亮さんの凄さは見抜かれておられましたよね。
人間模様も細やかに描かれていて、見ごたえ十分な素晴らしい作品です。
製作してくださり有り難うと言いたいです!
感謝です。
原作の良さを活かしきれていないのでは…
映画化が決まる前に大変面白く一気読みしていました。
映画の前評判が、かなり高く「映画館で見るべき映画」との口コミも多かったので期待して見に行きましたが、残念ながら映画の方は期待外れでした。
原作の魅力は、細かい人間ドラマや時代背景によって、メインの歌舞伎の世界で生きる喜久雄と俊介エピソードに深みを与えているところにあるかと思うのですが、3時間の映画ですので、かなり端折られています。
原作を未読の人は話が分かるのかな?と、鑑賞中に心配になるレベルでした。他の方もレビューされていますが、かなりぶつ切りで、すぐに時間軸も飛ぶので、感情移入はかなり困難です。
歌舞伎のシーンは確かに美しく、俳優さん達の歌舞伎シーンを成立させるための苦労や努力は、とてつもなかったかと思いますが、それが映画としての面白さには直結していないと感じてしまいました。歌舞伎シーンを見るためなら、歌舞伎そのものを見た方が良いのではないでしょうか。
映画制作のリソースを歌舞伎シーンではなく、ドラマ部分に費やしてほしかったです。そして、2部作にすべきだったと思います。
確かに面白かったんだけど…
美術のセットも凄く画面全体にエネルギーを感じる凄い作品ではありました。
歌舞伎てこういう世界なんだな。と教養を得た気分にもなれます。ただ、一旦集中力が途切れてしまうと続きを見るのはしんどくなるかな。映画で見るからこそ迫力で楽しめたと思います。歌舞伎ファンに限らず、歯を食いしばって舞台に挑むっていう所はスポ根が好きな人も楽しめそうですね。
本物の歌舞伎を見てみたい
前評判で期待し過ぎたかな
邦画における空前のヒット作と言われ、メディアでも大きく取り上げられて、監督や主演俳優たちのインタビューなども多く流れていたので、初期の混雑がおさまったタイミングで観に行ってきました。
前評判で期待し過ぎたせいか、期待ほどではなかったなというのが正直な感想。主演2人の歌舞伎シーンなどは確かに素晴らしいと感じました。ただ、歌舞伎にそれ程、関心も造詣もない人間からすると、歌舞伎シーンが多すぎて、最後の方は少し飽きてきてしまいました。
そして最も残念だったのは、ストーリー展開。閉鎖的な伝統芸能の世界に生きる人たちの心模様を描いた人間ドラマなのだから、もう少し深い人物描写があると良かったです。ストーリー展開が少し雑に感じる場面も何箇所かありました。(主人公の恋人の唐突な翻意、師匠が舞台上で倒れた際に口にする言葉…など)
海外の人や歌舞伎に全くアクセスする機会のなかった人が、日本の伝統芸能の世界を垣間見るには良いのかも知れません。しかし3時間がとても長く感じられました。
正直なところ、最近観た3時間もの(「宝島」や「韓国ミュージカル ON SCREEN」)ではそんなことはなくて、アッという間の3時間でしたが…
国宝
『鷺娘』の演目は確かに心震える演目です。
李相日監督の作品は
心震える作品が多いのではないかと
個人的には感じ
大変体力を要しおじけることもありますが
やっぱり観てしまいます。
この映画のコアのひとつとなる!?
『鷺娘』という演目は
もうひとつ違う軸を提供してくれているのではないかと
個人的に感じます。
それは
20年以上前に京都の南座で
坂東玉三郎さんの『鷺娘』をみたからかもしれません。
正直、人間業ではない
芸!?に我が目を疑いました。
そうしますと
この映画の重要な役どころのひとつは
あらためて
田中泯さんとなるのかもしれません。
あれ以来
川辺に白鷺を見ると気になってしまいますが
宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』をみて
その後は青鷺も気になってしまいます。
川辺で佇む青鷺はもはや
初老の老人です。
白鷺は娘で
青鷺は老人。
もはや完全に
映画『国宝』の感想を離れていますが
田中泯さんの映画の内外の在り方をみて
また、ひとつこの映画の別の出入口があるのかしら!?と
脱線しました。
よい映画を
ありがとうございます。
生き様を醜く美しく描き切った
1人の男の人生を描き切るタイプの映画
時系列はそれゆえに長めで、1つ1つのイベントは意外に淡白に、何年後、何年後、と進んでいく
思いつくあたりでは、
市民ケーン、スカーフェイス、アイリッシュマン、ラストエンペラー、ウルフオブウォールストリート、ソーシャルネットワーク
などと同じ構造
好きな構造
(ただどうしても長く・暗くなってしまうものだから、映画好きは好きでも今の日本でこんなにヒットするとは正直びっくり)
ただ今回は芸術的な美しさや迫力が、映像や音楽からひしひしと伝わってくるところがある
その分かりやすさと凄みがヒットした理由なのかも
大抵こういう構造の話は、男が何らかの高みを目指して(大抵は地位や名誉、富など目指して)、あらゆるものを犠牲にしながら人生を過ごし、最終的に孤独や虚無感で終わるパターンが多い
それゆえにその当初の目的よりも、何らかの別の大切さ(rosebudのような、愛のような)があったのではと示唆する
ただ今回は目指しているものが、芸術の美しさ。
歌舞伎という芸能の素晴らしさ、高揚、その先の景色。
それを決して映画内で否定しない。
あらゆる犠牲のもとでもその価値を疑わせない。
視聴者をもその虜にさせる。
主人公の感じる執着に、視聴者も願ってしまう。
ブラックスワンをはじめとするダーレンアロノフスキー作品を一生という時系列で描き切ったとも取れるし
芸術への価値観としてはセッションをはじめとするデイミアンチャゼル作品にも似ている。
一つ一つのシーンとして印象的なのは、登場人物たちの死に様
ヤクザの父も壮絶に、しかしその肉体の迫力のもとに死んでいく
渡辺謙も生への執着を見せながら、強烈なインパクトを残して死んでいく
横浜流星も人生のピークで華々しく散るように死ぬ
万菊も静かに、みすぼらしく、しかしそれ故に印象的に死んでいく
吉沢亮だって、万菊とリンクさせるように描かれているのだから、きっとこのまま孤独に死ぬことになるのだろうと示唆される
良い作品
これが日本でヒットしたというのも何だか嬉しい
全2378件中、181~200件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。