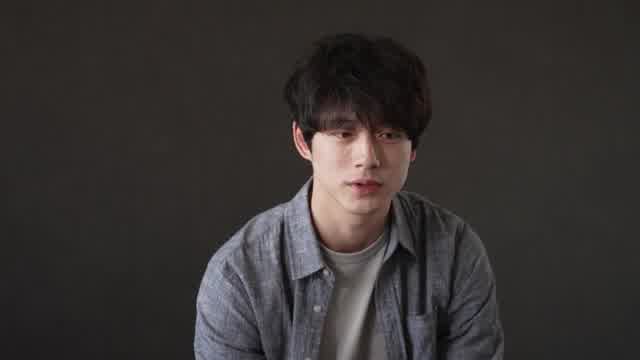「盤上の沈黙が呼び戻す“生のリズム”人間の「業」と「赦し」」盤上の向日葵 こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)
盤上の沈黙が呼び戻す“生のリズム”人間の「業」と「赦し」
柚月裕子の原作を熊澤尚人監督が映画化した本作は、単なる将棋ミステリーではない。むしろこれは「人間の尊厳をどう保つか」という社会派ヒューマンドラマであり、その質感は明らかに松本清張的だ。構成の重層性、陰影の深い照明、そして「才能」「出自」「罪」の三層構造を通じて描かれる人生の皮膜。これを“清張以後の『砂の器』”と呼ぶのは、決して大げさではない。
主人公・上条桂介は、天才と称されながらも、生い立ちの闇に蝕まれた棋士。対する東明重慶は、裏社会の賭け将棋で生きてきた勝負師。彼らは単なる対立軸ではない。光と影、盤上と盤外、正道と邪道――そのすべてが互いを映す鏡であり、どちらか一方が消えると、もう一方も存在できない。映画はこの二人を通して、「勝負とは生きることそのものだ」という命題を突きつけてくる。
特筆すべきは、終盤に上条が飛び降りを試みる瞬間、東明は何も語らず、ただ盤上に駒を並べ始める。カチ、カチ、カチ──その音だけが風の中に響く。東明は何も発しない。だがその駒音こそ、上条の心に刻まれた唯一の“言語”だ。
この演出が卓越しているのは、音が記憶と命を繋ぎ直すという点。駒音は、上条にとって“父の声”であり、“生のリズム”でもある。理屈も説得もいらない。人は、誰かに「生きろ」と命じられるのではなく、「生きてほしい」という行為によって救われる。この瞬間、映画は“盤上の向日葵”というタイトルを超えて、「沈黙の中にある愛情」という普遍的な主題に到達する。
熊澤監督は、構図と音のリズムで感情を語る。画面の多くは灰色と木の色で構成され、温度のある色彩はわずかに差し込む向日葵の黄色だけ。盤上の木肌の光沢は、まるで人間の皮膚のようであり、駒音が打たれるたびに“生命の鼓動”のように響く。『砂の器』における和賀英良のピアノが“贖罪の旋律”であったように、ここでは駒音が祈りの旋律となる。
東明が上条に放つ「お前ならプロになれる」という台詞もまた、勝負師の矛盾を凝縮した言葉だ。プロを「遊び」と切り捨てていた彼が、最後にそれを肯定する。そこには、敗北でも誇りでもなく、“赦し”がある。自分のようには生きるな。お前は盤上で光を掴め。その静かな願いが、言葉よりも深く観客に響く。
近年、邦画の中でこれほど「沈黙」を力に変えた作品は稀であると思う。SNSのノイズが支配する時代にあって、駒の音だけで人の生死を語る映画。清張の筆が現代に蘇ったとすれば、それはこの沈黙の中にこそある。
『盤上の向日葵』は、勝敗を超えた「人間の最終局面」を描く。勝つとは、生きること。
そして生きるとは、誰かの駒音を心で聞くこと。観終わったあと、静寂が胸に残る。それは敗者の音ではなく、まだ終わっていない“人生の一手”の余韻ではないだろうか。
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。