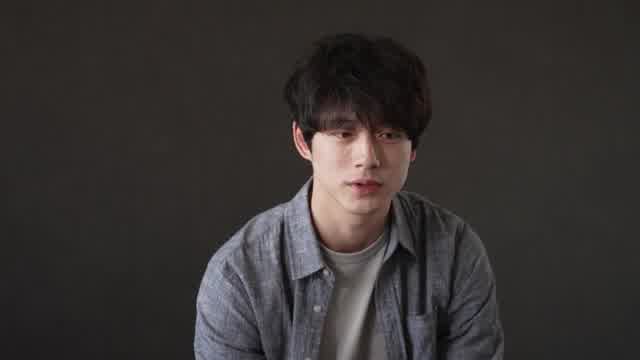「▲(先手)2六歩、△(後手)3四歩、と言われてすぐに譜面が頭に浮かぶ人が羨ましい」盤上の向日葵 グレシャムの法則さんの映画レビュー(感想・評価)
▲(先手)2六歩、△(後手)3四歩、と言われてすぐに譜面が頭に浮かぶ人が羨ましい
原作を読んでからの鑑賞。
尺の問題もあるので当然、改編や割愛はあるが、監督が「この原作をどのように解釈し、どの部分を映像として表現したかったのか」を想像するのもまた楽しみのひとつです。
【向日葵について】
原作では、偶然立ち寄った大型書店(たぶん新宿の紀伊国屋書店)で出逢ったゴッホの画集の中の『ひまわり』のなかに亡き母を見出します。
「ゴッホが描いた向日葵は、亡き母そのものだった。
背景の白に近い浅緑は母の淡さで、カンヴァスの中央に咲く花は、母の美しさと重なった。そしてなによりも似ていたのは、薄暗さだった。」(中公文庫下巻P11)
ゴッホが描いた向日葵は仄暗く、絵を明るくするはずの要素が逆に陰影を濃くし、その逆転の変異が、いつも顔に笑みを浮かべていたのに、ひどく寂しげに感じた母の姿にそっくりだと感じていたのです。
桂介は対局中に重要な一手を打つ直前、偏頭痛に襲われ、盤面に向日葵が咲くことがある。
9×9=81マスすべてに咲き誇った後に一か所だけ向日葵の残像が消えないマス目が残る。
それが決め手となり、桂介が勝利を積み重ねていくのですが、壬生に挑む竜昇戦の最終第7局においては、いくら待っても向日葵が咲かないのです。そして、勝負の行方は…
映画においては、ゴッホの絵画については触れられず、原作には出てこない「ひまわり農園と土屋太鳳さん」を登場させ、向日葵のイメージを映像として表現。おそらくその明るさが、東明重慶という影しか纏っていない男に「生き切ろ!」と言われることとの対比で向日葵の持つ前向きなイメージと結びつけたのだと思います。
東明重慶という影の濃い男が向日葵の明るさとそこから生まれる陰影を際立たせ、桂介という人間の内面を浮かび上がらせる効果を生み出しています。
【唐沢夫妻について】
桂介の今日があるのは、唐沢夫妻のおかげといっても過言ではなく、映画を見ながら、原作での唐沢夫妻の桂介に対する思いとサポートを追想するだけで泣けてしまうのです。
唐沢は、幼い桂介との対局でも決して手を抜くことはなく、実力が上だからといって、手を抜くのは対戦相手へのリスペクトを欠く行為であることを対戦を通じて教えていきます。
唐沢から受け取った名匠・初代菊水月作の将棋駒は、最後まで将棋の世界で生き抜いた東明に捧げられたが、それは桂介にとっての父親が唐沢から東明に引き継がれたことの象徴だったようにも思えるのです。
【ラスト】
原作小説と映画、どちらも桂介がこれからどうなっていくのかを示唆することで終わりますが、たぶん正反対の方を向いています。どちらが好みかは見る人、読む人次第ですが、個人的には映画のほうがいいかな、と思っています。
グレシャムの法則さん、ご無沙汰してます。
原作にある盤上に浮かび上がる向日葵は、NHKのドラマ版では忠実に再現してました。
原作通りである必要はないのですが、映画オリジナルの部分にちょっと空回りしてるところがあったかな、と思いました。
でも、映画ですから、映像で魅せたという点は素晴らしかったですね。
こんにちは。
私も原作は読んでいて、だからこそアレだと「盤上の向日葵」が意味する事を表現できていなかったと思ってしまいました。
向日葵もただの思い出の一部にしか感じられず残念でした。
ただ、ラストは映画の方が良かったですよね。
桂介が可哀想過ぎてかなしいです泣
将棋は挟み将棋と山崩ししか出来ません(°▽°)b