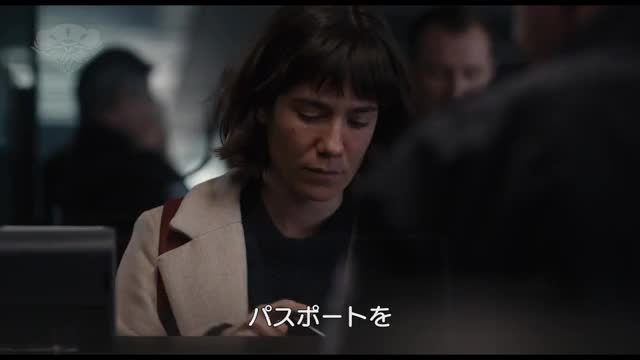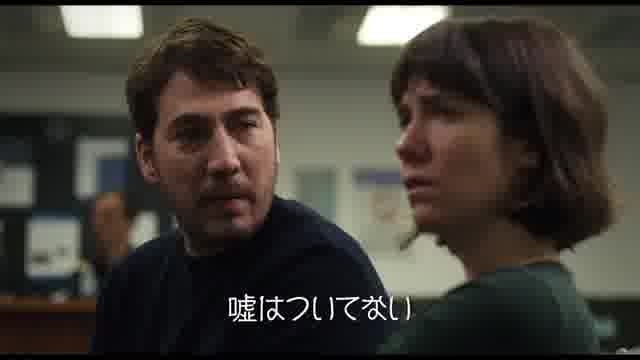「被害者視点での緊張感。描かれない国家の論理」入国審査 ノンタさんの映画レビュー(感想・評価)
被害者視点での緊張感。描かれない国家の論理
公開1週間の週末に鑑賞。映画.comでの評価はあまり高くないので、空いてるかなと思ったら、有楽町の映画館はほぼ満席。賛否両論の映画なのかなと予想して見始めた。
観終わって、自分の中でも賛否両者が残る、どう捉えたらいいのか、モヤモヤする映画でもあった。
本作の監督はベネズエラ出身で、現在はスペイン在住。自身がスペイン入国審査で体験した出来事を発想の起点に、本作を作り上げたという。
主人公の38歳のベネズエラ人男性に、監督自身が投影されているのだろう。政情不安定な祖国を離れ、現在はスペイン在住だが国籍は取得できていない。
パートナーは34歳のスペイン人女性で、彼とは契約を交わした事実婚。この二人が移住先に選んだアメリカの空港で入国審査を受ける場面が、映画のほぼ全てである。
観終わった直後は、正直モヤモヤした。非人道的な扱いを受ける恐怖と理不尽さを訴える作品だと感じたものの、自分の経験や想像の範囲を大きく超える新たな発見がないと感じた。なんとなく監督が未熟に感じて、感想は書かなくてもいいかと思ったほどだ。だが一晩経って、なぜ引っかかったのか、少し整理できた気がする。書いてみたい。
入国審査は、多くの人にとって他国の権力と直接対峙する数少ない場だ。何も悪いことはしていなくても緊張する。自国とは異なる倫理やルールに晒され、何が“悪いこと”なのかが曖昧になるからだ。
入国審査の独特の緊張感は、自分も何度か味わった。何も悪いことをしていないのに、呼吸が浅くなる。あの感覚を思い出しながら観ていた。
過去の海外旅行では、多くの場合は職業的無関心。温かくサポートしてもらったこともある。逆に、理不尽で、あるいは差別的に感じる扱いを受けたこともあった。それを強く思い出した。
作中の二人は、国境を超える緊張に温度差がある。ベネズエラ人の彼は入国審査を前に恐怖を感じ始める。
スペイン人の彼女は無頓着だ。「私は世界のどこでも人道的に扱われて当然」という確信があるからだ。だが、その当然は裏切られる。
やがて彼女は、彼が過去に婚約していた相手の存在を知らされる。そして入国審査官たちは、それを手掛かりに「国籍取得やビザ目的で彼女を利用しているのではないか」と追及する。
彼の「君には僕のことはわからない。君には帰る場所があるけれど、僕にはない」というような、終盤のセリフ率直な彼の本音だ。祖国は帰る場所ではなくなり、スペインからさらにアメリカへと活路を探すのが彼の生き方。
しかしその言葉は彼女に、「利用されていたのでは」という疑念を決定的にする。二人は釈放されるが、残るのは「もう無理…」という感覚。「アメリカへようこそ」という皮肉な幕引きに宙吊りにされた気持ちになった。
改めて考えると、本作はきわめて現代的な物語だ。どの出自の人も等しく人間的に扱われるべきというリベラルな価値観は、いま揺らいでいる。
米国ではトランプ政権下で国境の壁や入国制限が強化され、ドイツではメルケル政権下の難民大量受け入れが社会を二分し、その後の選挙では極右政党の台頭を招いた。日本でも移民や国境管理の議論は敏感な争点になりつつある。
そうした現実から見れば、主人公カップルは無邪気にも映る。特に彼女は、国境の存在が薄いEU圏で育ち、「どこに行っても自分は自分らしく生きられる」という確信を持っている。しかし国家には国民を守る義務がある。そこには選別がある。その論理が最も露骨に表れる場所の一つが入国審査だ。
本作のもう一つの特徴は、描写の非対称性だ。
主人公の内面や背景は描かれるが、入国審査官たちは徹底して「人間性のない、役割の仮面」を被った存在として描かれる。彼らが何を背負い、どんな論理や倫理で動いているのかは全く描かれない。この非対称性が、観終わった後のモヤモヤの正体だったのかもしれない。
結果として本作は、理不尽さと被害者視点の緊張感を極限まで高める一方で、制度や権力の複雑さを省き、単線的な感情を残す作品になっている。
そこに掘り下げの浅さや未熟さを感じるか、意図的な作劇かと受け止めるかで評価は分かれると思った。