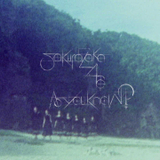ぼくのお日さまのレビュー・感想・評価
全271件中、41~60件目を表示
美しさと、残酷と、
ドビュッシーの「月の光」に纏われて、
美しいフィギュア・スケーターが舞う。
ヒソヒソ声の多い静かな映画中で、そのシーンは
三上さくらの決意を告げるように激しい。
“微塵も許さない“
私のスケーティングに荒川先生の
“訳ありな人生“の介入を、
私のスケーティングは、
“アイスダンスなんかではない“
半分お遊びの、吃音リハビリのような、
タケシのスケート
に、“組み込まれたくない“
繊細な映像表現の情景詩のような映画です。
時にソフトフォーカスして焦点が広がりぼやける。
美しい少女スケーター。
吃音の少年は、何をやっても下手っぴ。
唯一、荒川先生の教えてくれたアイスダンスの基礎。
「滑れるようになったタケシ」
さくらとの幸せな時間、
荒川先生の掬い上げてくれる優しさ、
さくらは心構えも既にプロで、
彼女はある意味で完成しているし、
心に“遊び“がない、
だから潔癖で汚れや妥協を許さない、
タケシは流されただけ?
でもタケシの自信になったと思う。
小さな小屋の芝犬、
雪中の真っ赤なポスト、
高い橋を走る電車、
置いてかれる荒川先生の恋人、
車に積まれた思い出品の段ボール、
(なんで捨てないんだよ!!)
この町を出て、また次の町へ流れていくフェリーボート、
捨てたもの、捨てられたもの、
残したもの、
タケシの心に荒川先生が灯した明かりが、
タケシのこれからをを支えることを、
私は心の中で、
願っている。
ぼくのおひぃさま
小学生の恋愛を描いた作品は珍しく、あっても子供向けか演技が拙いものだが、本作はどちらでもなかった。
越山敬達くんもだが、中西希亜良ちゃんの魅力が凄い。
清原果耶の凛々しさに芦田愛菜の愛らしさをちょい足ししたような感じで、横顔の綺麗さは特筆もの。
スケートも、越山くんは徐々に上達する様子が、中西ちゃんは神々しいまでの美しさが印象的。
なかなか3人が絡まないので心配になったものの、荒川がタクヤを教えるあたりで俄然良くなる。
2人が次第に活き活きしてくる様がとても自然。
技が成功した時の喜び、特に教えた側のそれが真っ直ぐ伝わってきてこちらまで笑顔になる。
アイスダンスをやる流れは、本当にさくらのためになるか、タクヤの応援が先に立っていないか少しモヤる。
そして、2人の練習を不満気に見つめていたさくらが心を許す段階がなかったのは残念。
しかしその後の3人の交流はそれを忘れるほど眩しく、特に湖のパートは多幸感に溢れていて目が潰れた。
光の差し込むリンクで演技を合わせるシーンは美しすぎて目玉が溶けた。
というか、小学生で女の子とあんな距離なんて、たとえ好きなコじゃなくてもドキドキ堪らんだろ。
まぁタクヤからそういう疚しさは感じないので、純粋にスケートも好きなのだと思う。
ただ、後半の展開は正直好みじゃなかった。
恋人と察するには弱く、逆に理解したならタクヤに邪な感情があるなんて勘違いしないと思うが、そこはいい。
それでも、さくらと荒川が決裂したままで、アイスダンスの本番にも挑めない幕切れはスッキリしない。
荒川は一応前進と捉えてもいいし、タクヤとさくらはまた何かが始まりそうなラストではある。
決してバッドエンドではないが、ストレートに幸せな3人が見たかったです…
タクヤの友達も、もっと絡ませてほしかったなぁ。
ただ一緒に居たいだけなのに、、、
イヤータクヤくんとサクラちゃん可愛すぎて、あんなに一生懸命練習したのに、、、タクヤくんにはアイスダンスを続けて欲しかったなー。サクラちゃんは出て来た時からスケートが上手いのは充分分かっていましたが、タクヤくんは本当に上手くなっているようで、アイスダンス出させてあげたかったなー。タクヤくんの爽やかな淡い気持ちを思うと切ないなー。タクヤ役の越山敬達くんサクラ役の中西希亜良さん2人の演技が凄すぎます。タクヤくんは本当にきつ音に見えてしまいます。最後に流れる主題歌も反則ですよー。最後にあの感じでエンドロールにいかれて、自然に涙が出てきます。ハンバートハンバートさんのぼくのお日さまものすごく素敵な曲でした。最後久しぶりに会ったサクラちゃんにタクヤくんは思っている事言えたかな?観終わった後の余韻の残り方がすごいなー。これだけ感想が出て来るくらい映画館で観て良かったです。今年観た映画で1番良かったです。
テアトル新宿でまだ観る事が出来たので2度目の鑑賞致しました。映画の中の風景が素晴らしく、特に自然光や光入れ方がMVみたいです。ゆっくりした時間の流れがあり、空気感すら感じます。何回観ても、良かった。やはり今年1番心に沁みる映画でした。3人でカップラーメンを食べながら足をカタカタやる所や先生の居ない所でサクラちゃんと合わせて友達が拍手するシーン等素晴らしいシーンの連続です。本当にありがとうございました。
淡く輝く「ぼくのお日さま」
言葉で多くは語られないものの、目線の揺れ動きや画面のトーン、映像の前後関係などによって登場人物の心情がしっかりと伝わってくる作品。
タクヤが初めてサクラに目を奪われるシーンや、荒川が初めてタクヤを見つけるシーンは、彼らの「お日さま」がここにあるのだと如実に表されている。そしてそれは、サクラがじっと荒川を見つめる時も同様の意味を持っている。
加えて、サクラにとっての「お日さま」である荒川が、しかし彼女の理想通りの存在ではないと気づき、失望を顕にした時、作品のトーンがぐんと下がる展開も面白い。
そして彼らの美しいバランスは崩壊し、スケートを通じた繋がりも失われる。
だが、だからこそ何度失敗し転んでも立ち上がるタクヤというキャラクターが重要になるのである。
太陽と月
スケートリングで滑るサクラに合わせて流れた音楽がドビュッシーの月の光。「僕のおひさま」は「月の光」、たけるにとってそういうことなのかな、と。序盤から心掴まれた。
おそらく少し時代も前の北海道の小さな街(函館?)の染まってないその街感の演出の仕方、
そこで生きる人たちの生活の表現が凄いな〜と。
物語的にも、活音を抱えるたけるの頑張りや、そこに光を見てる池松君、それを見て?のサクラのそれぞれの心情が刺さってくるものがあった。
たしかのサクラから観たらなんでアイスダンス?なんでこいつ?先生どうした?ってなるよなそりゃと思うけど
エンドロールで流れるハンバードハンバードからも伝わるたけるのやるせなさや、当時の小さい街では理解されない恋愛感情をもつ池松君の苦悩とか、見ていて苦しいものが込み上げてくる反面、
地域の美しさ、羽を広げたように滑るタケルや、大自然の氷の湖で3人で滑って踊る姿がとても眩しくて印象的だった。
じーんと心に響く良い映画。
ムーミン谷に春が来た
この物語は冬の物語であるが
人生の春のようでした
すべてが愛おしい時間のように感じ
そしてとても残酷でした
早く雪が溶けないかなと思っていた少年が春が来ることを名残惜しくなる頃
スナフキンは旅立ちます
また帰ってくるよねというムーミンに
わからないと言う
そこはムーミン谷に冬が来たらねと
本来なら逆だけどそう言ってよスナフキン
と涙ながらに思いながらもその対話は素晴らしかった
二人で滑るシーンはとてもとても幻想的すぎてこの世のものとは思えないぐらい美しいシーンだったからこそ、その後のあのシーンは
滑りきったあと何を思ったのか
さらに青年はなんと言ったのか考えさせるなと噛み締めているとハンバートハンバートが歌い出すんですよ
そんなの涙しかない
素晴らしかった
かわいいと美しいの融合
優しくて温かくてちょっと痛い
お日さまのような光に溢れた映画
スタンダードサイズの画面に映し出される一コマ一コマが、導入場面から一枚の絵として成立しているようだった。気を衒わず、ズドンと主題を真ん中に配置する中央構図が多いのだが、その分、描かれる人や物に、観ているこちらもグッと気持ちが寄る。
最初、その後いじめやトラブルが描かれることを予感し、「主人公タクヤの吃音という要素はいらないのでは?」と思っていたのだが、友人たちがそこを全く問題にしない展開が心地よかったし、マイノリティとはいえど吃音の人は一定数いる訳で、単に身構えてしまうこちら側の問題だった。それに、マイノリティということで言えば、サクラがコーチである荒川の性的指向に嫌悪感を表明することによって、サクラの恋愛感情や思春期ならではの心の動きと、同性カップルにまだ不寛容だった描かれている時代性が、対比的にごく自然に立ち上がっていたと思う。
それに、鑑賞後公式ページを見てみたら、なんとこの映画、ラストの主題歌がきっかけで作られたことがわかり、なるほどと思った次第。
(ちょっと脱線するが、エンドロールの主題歌の歌詞を見ながら、歌だと吃音が出ないというのは、「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」でも出てきたエピソードだったなということを思い出した)
フィギュアスケートの場面で流れるドビュッシーの「月の光」。「ぼくのお日さま」というタイトルなのに、月の光なんだ…と漠然と思いながら観ていたが、月はお日さまによって光輝くのだから、これ以上の曲はないのかとこれも途中で思い直した。
帰路で、妻に「タクヤにとって、サクラがお日さまってことだったのかな?」と話しかけると、妻は「私は、荒川コーチやフィギュアスケートそのものがお日さまだったんじゃないかな?」と言っていて、確かにと思うと共に、荒川自身もタクヤとサクラ2人の関係をお日さまのように、まぶしく暖かく感じていたんだろうなと思いが広がった。
とにかく、全編、お日さまのような光に溢れた映画。
この奥山監督はまだ28歳とのこと。ベイビーワルキューレの阪元監督も28歳。ナミビアの砂漠の山中監督は27歳。日本映画の若手の活躍がこれからも楽しみ。
何とも言えない余韻あり
劇場では見逃すかと思いましたが、タイミング合い、ラッキーでした。映像がとてもよく、ペアの二人はほとんどセリフないのに自然でわかりやすい。カセット時代ならではの風潮や意識も前提なのですね。ほろ苦いながら、希望も感じる結末かと思いました。男の子はどこまで事情を知っているのだろうかと思いました。若い俳優のお二人はとても楽しみ。池松さんは素晴らしいですが、若葉さんも出ていると知らずに観て、程よい存在感がさすがですね。
すごいリアルな映画
さくらの気持ちも理解は出来るけど、荒川が一番傷つく言葉言われてて凄い悲しくなった。あの時代設定なら当然とも言えるかもしれないけど、でも凄く現実味があって感情移入もしやすい凄く良い映画だと思う。
最後の解釈お任せって感じも好き。
雪と光の美しさ
美しい師弟関係の裏にある危うさ
優雅にスケートを滑る女の子(さくら)に憧れる、不器用な男の子(タクヤ)。タクヤにスケートを教えることに生きがいを感じるコーチ。そしてさくらはそのコーチにひそかに憧れる。3者が出会い、スケートに打ち込んだある冬のストーリー。
凍った湖で3人が練習するシーンが前半のクライマックスだ。3人の距離が縮まり、美しいシーンになればなるほど、何か不吉な予感が漂う。さくらが目撃したコーチのある行動に幻滅し、ついに3人は離れ離れになってしまう。
さくらがコーチに突きつける言葉(「お気に入りの男の子を踊らせていただけなのか。気持ち悪い」という主旨)には、コーチの恋人への嫉妬、タクヤとペアを組むことへの疑念など、色々な感情が入り混じっている。そこにはさくらのコーチへの(無自覚な)独占欲もうかがえる。そもそもコーチがタクヤとさくらにペアを組ませたことは、お気に入りの2人と一緒にいるためのエゴのようにも見える。
つまり師弟関係というものは美しければ美しいほど、そこには互いへの独占欲がある。これぞと思った子に熱を入れるからこそ互いの成長もあるのだが、危ういバランスのうえに成り立つ、いずれ終わりを迎える関係なのかもしれない。
可愛そうなのは、唯一独占欲や嫉妬と無縁なタクヤである。そのタクヤが最後にさくらに再会し、成長した姿で互いに向き合う(何か、背の高さも対等になっていた気がした)。師は去っていく運命にあるが、残された子どもは成長するという結末のように見えた。
弱い人がつながりあう一瞬の美しさとはかなさを描く作品だと思うが、さくらの背景や成長がもう少し示唆されていればもっと満足感が高かったかもしれない。
すべりこみで観れた
淡い恋、美しい背景、そして美しい少女
宣伝を一度も目にしていなかったため観賞予定に無かったのだが、ネットの映画記事で絶賛されているのを読んで急に興味を持った。調べて行くと、ヒロインが可愛い(笑)。常に魅力的ヒロインを求め続けている俺なので、それはとても重要なことで、俄然観たくなった。
元々上映館が少ないのに既に公開から間が経っているため、少ない候補から上映館を選んで急遽観賞。
【物語】
舞台は北海道。タクヤ(越山敬達)は夏は野球チーム、冬はアイスホッケーチームに所属するも、チームのお荷物的存在。タクヤ自身も上手くなりたいという気持ちは薄かった。また、吃音(きつおん)を抱えていたため、学校でもバカにされることが多かった。それでも、親友の存在もあり、落ち込むことなくのほほんと日々過ごしていたタクヤは、ある日ホッケーの練習後にフィギュアスケートの練習をしている少女・さくら(中西希亜良)の姿に釘付けになる。
それ以来さくらをじっと眺めたり、ホッケー靴のままフィギュアのスピンをまねては何度も転んでいるタクヤを毎日見ていた荒川(池松壮亮)は、見かねてタクヤに声を掛ける。荒川はリンクの整備をする傍らさくらのコーチをしている元有名フィギュアスケート選手だった。荒川はタクヤにフィギュア用のスケート靴を貸して練習に付き合う。荒川の指導でメキメキ上達するタクヤを見て、荒川はさくらとタクヤにアイスダンスのペアを組むことを提案する。
【感想】
観て良かったと思う。
何よりヒロイン中西希亜良は期待通り可愛かった。この作品で重要な少女の初々しさも十分に醸し出されていた。 本作が映画初出演らしいが、今後の活躍を期待したい。
主役のタクヤを演じる越山敬達も良かった。こちらも可愛らしい少年なのだが、タクヤという特別才能があるわけでもなく、特別頑張り屋でもなく、思わず美少女に見とれてしまう少年の極々“普通”感が良かった。
池松壮亮も当然良い。こういう熱くなく、やや冷めた感じだけど優しい青年は池松の最も得意とするところ。キャスティングが絶妙。
舞台が俺の第2の故郷北海道ということもプラス点。観るまで知らなかったのだけど、雪景色の白さ(道路まで終始白い)が、本州ではなく北海道に違いないと思って観ていたが、そのとおりだった。 この背景の白さもこの作品には重要な要素だったような気がする。
唯一俺が気に入らないのは、本作でも安易に同性愛が使われていること。レビューで俺は度々愚痴っているのだが、LBGTが色々取り上げられている現代なので、同性愛をテーマに取り上げた作品を制作することには文句は言わないが、テーマ的に入れる必要のない作品で安易に取り込むのが気に入らない。本作は無垢な少年と少女の心の動き、そして淡い恋を描くのが主軸だと思う。荒川に普通に女性の恋人がいることをさくらが知る、で十分だったはず。ここにLBGTを持ち込まれると、俺はそっちに頭が行ってしまう。LBGTを否定するつもりはないが、やはりマイノリティーであることは間違いないので、「同性カップルの存在なんて全然普通」とは俺には思えず、作品のテーマとして必要以上に意識・印象がそっちに引っ張られてしまうから。
それが自然に受け容れられる人には、なおさら良い作品と思えるのではないか。
冬靄
吃音をもつ少年タクヤは、ホッケーの練習の帰りにさくらという少女のスケート姿に心を奪われる。
さくらのコーチの荒川はタクヤにスケートを教え、2人で男女のアイスダンスに挑戦しないかと提案する。
雪が降りはじめてから雪がとけるまでの小さな恋たちの物語。
傑作。
冬の日差しのように温かくて氷のように冷たく痛い。
ひと冬のあまりにも美しく残酷な青春。
映画を観終わってから予告やポスターを見ると自然に涙が溢れてきてしまう。
ああなんて無垢で罪深いんだ。
もうね、「月の光」が流れる時点で私の映画なんだけど、こういう痛みを伴う少年少女の成長譚って大っっ好きなんですよ。
映像、音楽、役者、ロケーション、全てが完璧。
この映画について多分永遠に喋ってられるけど、これ以上言うこともない気がする。
公開からだいぶ経っての鑑賞になってしまったのが残念。
もう一回行きたいがちょっと難しいか……
あと、冬か春に公開して欲しかった気もする。
おかげで冷房が寒い寒い。
劇場がスケートリンクだったよw
流行りの映画より満足度は高いかも
キラキラしてる
全271件中、41~60件目を表示