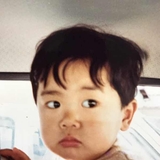35年目のラブレターのレビュー・感想・評価
全313件中、261~280件目を表示
上白石萌音ちゃんに萌え💕
古都奈良を舞台にある家族の半世紀を描いた物語でした。
なぜそれまで気づかなかったの?そんなことあり得る?という若干の不合理性に疑問は残るものの、実話を元にしたということなので事実は小説よりも奇なりということなのでしょう。
若き日の二人と晩年の二人。キャストのギャップを気にしなればそれぞれに魅力あふれるカップルで心が暖かくなりました。
特に、「夜明けのすべて」魅了された上白石萌音さんの愛らしさときたら!
舞台設定と物語が絶妙にマッチして、一見行きつ戻りつのように感じられるストーリーが、ラストに至ると、「普通の人」の人生の個々のエピソードは第三者から見るとこんな感じなのかもしれないと思い至りました。本人にとっては大変な山あり谷ありなのでしょう。
今の季節にマッチした美しい奈良の風景、全編を彩る柔らかな関西弁も作品の魅力を引き立てます。
好きになれるから
好きなところ3つ
何歳になっても、目的のある努力は実るものなのだと思った
2025.3.8 イオンシネマ京都桂川
2025年の日本映画(119分、G)
原作は小泉孝保のノンフィクション『35年目のラブレター』
読み書きのできない夫が妻のためにラブレターを書く過程を描いた恋愛映画
監督&脚本は小泉連平
物語は、1999年を起点にして、27年前の新婚時代と幼少期を過去編として描いていく
幼少期の生活とトラウマから読み書きができないまま大人になった保(重岡大毅、老齢期:笑福亭鶴瓶、幼少期:渋谷そらじ)は、色んな職場を転々としながら、寿司屋の逸美(笹野高史)に世話になることになった
勤勉な保は仕事を真面目にこなし、新人を教えるまでに成長する
そんな折、逸美の知り合いから見合い話が来て、保は渋々参加することになった
そこに現れたのは皎子(上白石萌音、熟年機:原田知世)で、彼女は保が驚くほどの美人で、自分とは不釣り合いだと思っていた
読み書きができないことを言えないまま、二人は結婚することになり、それから半年が過ぎた頃、保はこれ以上隠せない状況に追い込まれてしまう
この半年間は楽しかったと言う保だったが、皎子は「わたしがあんたの手になったる」と言い、それから二人の夫婦生活が始まった
物語は、この過去パートを丁寧に描き、
現代パートで夜間学校に通う様子が描かれていく
夜間学校にいられる時間は20年で、半分が過ぎた頃でも満足に字が書けなかった
一度はやめようと思うものの、谷山先生(安田顕)は進歩していると言い、自分のこれまでの学習を振り返って勇気づけられることになった
その後、ラブレターを書くために邁進する日が続くものの、皎子が病魔に襲われてしまう
脳の血管に異常が見つかると言うもので、手術をして一度は回復するものの、その時が来てしまうのである
物語は、手紙が読めない保で始まり、それが読めるようになるまでとなっていて、そこには夫婦それぞれの想いが隠されていたことになる
面と向かって言えないことも手紙でなら言える
そんな素敵な要素が詰まっていて、タイプライターの味わいのある文字が、さらに涙腺を緩めてしまうのである
映画は、現代パートと過去パートを違う俳優が演じることになっていて、これをどのように受け止められるかのように思う
似ている似ていないを重視するのか、気質が似ていると脳内変換できるのかで見方は変わってくると思うが、個人的にはこの夫婦の歴史としては合っていたのではないか、と感じた
いずれにせよ、実話ベースの物語で、特異な過去があったとしても、当時はそこまで稀有なことではなかった
時代が変わり、今では読み書きできない人はほとんどいないけれど、義務教育を全うできない人がいるのも事実だと思う
人は何歳になっても新しいことができるので、それを再確認する上でも、勇気づけられる
人生には色々あって、その時にしかできないこともあれば、かなり年月を要してからでもできることはある
なので、今足踏みが必要な人は足踏みをして、前に進むためのタイミングを見つけたら良いのではないか、と感じた
笑って泣いて。素敵な夫婦の純愛物語
この作品のモデルになったご夫婦のことはテレビで見たことがありました。本当に素敵なご夫婦だと思ったものでした。
その実話を元にしたこの映画もとても素敵な温かい作品になっていました。
全編に溢れる夫婦の愛情と思いやり。そして家族の愛が余す所なく描かれていました。
鶴瓶さんの好演はもちろんのことですが、原田知世さんの何と美しく素敵なことでしょう、旦那さまを想う奥さまをものの見事に演じられていました。
若き日の2人を演じた重岡大毅くんと上白石萌音ちゃんは共にチャーミングでした。生徒思いの心優しい学校の先生の安田顕さんも強く印象に残る素晴らしい先生役になりました。
63点は愛情の証し。保さんにとって皎子さんの良い所は3つでは収まりきらず溢れ出ていましたね。
お互いのラブレターは生涯忘れられない宝物です。皎子さんの元にもきっと届いていると思います。
いい映画を見ました
心が温かくなる映画です。
久々に作品を見て涙が溢れました。
夫婦の始まりと晩年部分が描かれていますが、夫婦のお互いを思いやる姿に心が温かくなります。
また、夜間学校の仲間との関わりも、ご近所との関わりも、全て温かくて素敵です。
クスッと笑える場面もあり、笑って泣いてとても良い作品でした。この作品に出会えて良かったです。
夜間中学の存在意義に触れている良い映画。
今年76本目(合計1,618本目/今月(2025年3月度)10本目)。
実はこの映画、エンディングロールには出てきませんが、文科省とタイアップの扱いです(文科省のサイト参照)。
先の大戦の終結のあと、いわゆる混乱期や貧困等で学校に行くことができなかった方は高齢者の方を中心におられ、それを扱った映画です。ほか、夜間中学の存在意義についても触れていて(この点後述)、きわめてよかったかな、というところです。
個人的には、ただ単に当時の混乱期と教育の機会が現在ほど充実しておらず、実際に読み書きができなかった「だけ」だろう、というのが観方です。精神疾患・軽度知的障害等に触れられている方もいらっしゃいますが、
・ 寿司屋で働いていたという実際の実話から、漢字が読めなくても魚の知識から漢字を推測することは、ある程度の知識がないとできない
・ 1/2 + 1/3 を(他の生徒に)教えるときに「1000円札と5000円札の違い」をたとえとして出すのは、すし屋の経験(おそらく、会計もされていたのだと思います)から得られたものであり、その例示を出すにはある程度の知識が必要
…等が理由で、現在(2024~2025)のように、不登校等でも教材がそろっているのとは違い、和歌山の農村育ちであればありえる話であり、個人的にはその見方(読み書きができない「だけ」)です。
映画内では夜間中学として色々な方が登場します。また、夜間中学に関しては法改正もされ、入れる方が拡充されています。つまり、形式的に小中を卒業しても、大半がいじめ等でいわゆる「保健室登校」に過ぎなかったり、離婚再婚等を繰り返して学校を何度も変えたなど(親の虐待が絡むケースが大半)、あるいは、いわゆるフリースクール登校で「まったくわからないわけではないが、部分的にわからないところがある」等、形式的に卒業したに過ぎない当事者もいたところ、法改正、解釈によって本人からの聞き取り等で現在では認められるようになっています。
現在では夜間中学といえば、
・ 戦中、戦後の混乱期の中、通えなかった当事者(高齢者が大半。映画もここ)
・ いわゆる外国人生徒(映画内にも出ます)のうち、特に日本語の学習につまづきやすい方(愛知、静岡等の在日南米出身の方が多い。これにともなって愛知・静岡は学校数が多め)
・ 重度身体障がい者(1979年まで「就学免除」という名の就学拒否がまかり通っていた)
・ いわゆる「いじめ」等で登校できない、できなかった当事者(映画内にも出ます)
…等であり、最高裁判例が述べる「子供の学習権」(子どもが、自分から学習したいと申し出る権利のこと。いわゆる「新しい人権」)に沿ってもいるこの制度は、今後は姿かたちを変えていくのだと思いますが(戦後の混乱期の当事者の方は高齢者が多い為)、存在しなければならないものです。
採点に関しては以下まで考慮しています。
---------------------------------------
(減点0.1/妻の協力についてある程度深い描写があってよかったか)
間接的には述べられていますが、当時の女性の「憧れの仕事」としてタイプライターがあり、映画内で登場する女性も、そうであるからこそ「文字の読み書きの大切さ」は他の職業(映画内ではほかに「エレベーターガール」等が出ますが、他にしいてあげれば「看護婦」(当時の言い方)さん?)に比べて人一番わかっていたはずであり、このことについて「なぜ彼女が協力的だったのか」という点について明確な誘導が欲しかったです(9割以上の方はわかると思いますが)。
(減点0.1/主人公が小学生でいじめにあった理由の描写がやや不足)
この話は実話で、映画内でも「小さいときから働いて100円を稼いで学校に行って…」というお話ですが、当時の100円は現在(2024~2025)では2~3万円といわれます。これだけの大金なのですから、「現在の価値でいえばいくらくらいか」という点についてはある程度誘導が欲しかったです。
---------------------------------------
(減点なし/参考/現在の夜間中学の在り方)
映画内でも「漢文の読み方」を学習するシーンが出ます。夜間中学というのは上述した通り、現在でも一定数、戦中戦後の混乱期で学校に行けなかった方と、重度身障やいじめ等で通えなかった層が別々にあります。前者の層(この映画で述べる層)は、「最低限の読み書きができれば」という趣旨で通うことが多いですが、一方で高校、大学等への進学をやがて考える後者の層はもちろん高校入試の前提としての「日常生活では使うことはないが、入試などで必要」になるこれら(漢文の読み方しかり、数学の「どうでもいい」公式しかり)を学習するようになっています。映画内でどうでもよさそうな「漢文の学習」や「ローマ字」といったことが出てくるのもその理由です。
※ 実際には夜間中学は法律上の「中学校」なので、同じカリキュラムにして履修しないと正式に卒業はできません(だから、映画内でも出てくるように「体育」の科目もある)。ただ、前者(高齢者層)では「最低限の読み書きがわかればすぐに退学する」(卒業認定は得られない)こともあります(映画内で描かれる通り)。
せめて最後に奥さんを旅行に連れて行って欲しかった
あの歳になるまで勉強するチャンスはあっただろうにずっと奥さんに頼りきりで奥さんが可哀想だと思う。
奥さんが一生懸命頑張ってアルバイトみたいな仕事して小銭稼いで文句も言わず行きたい旅行も行けず脳の病気で旦那より早く亡くなって旦那の方はやっと字が書けるようになりましたとかもっと早く奥さんを楽にさせて欲しかった。
最後奥さんが可哀想で涙が出ました。
この映画の主役は奥さんの方だと思う。
素敵なご夫婦
文字の読み書き出来ない夫を支える、献身的な妻のお話だと、あらすじを見ただけだと思ってしまうのですが、それだけでは無くて、お互いが思い合っているからこそ、歳を重ねても笑顔溢れるご夫婦でおられたんだなって、感じました。
過去パートでは、保さんの辛さや悔しさ、申し訳無さを受け止めて寄り添ってくれる皎子さん。
現代パートでは、それを乗り越え過ごす中、出来ない事に立ち向かう保さんの背中を押し見守る皎子さん。
そうやって、支えてくれる皎子さんの幸せには、保さんは絶対必要だったんだなって、最後まで観て思いました。
過去と現代で、保さんと皎子さんは別の演者さんでしたが、過去のお二人を経て現代のお二人があるんだなと思える程、違和感がなくて、演技と言うよりこのご夫婦の日常を観ているような感覚だったので、微笑ましくなったり、クスッと笑ってしまったりしましたし、悲しさや辛さのあるシーンでは、一緒に泣いてしまいました。
この映画は、特別何かに強く訴えかけるようなお話では無いのですが、共感したり感情移入出来るので、観た後に、私もこうなりたいな、やってみたいなって自然と思えました。
また、観終わった後パンフレットも読んだのですが、シーンの補足的な事も載っていて、本当に実話なんだって更に感じました。
人を思い遣るって、どんな事なのかを自然と感じられましたし、諦めずにやってみる事の大切さも知れる、そんな映画だなって思いました。
⭐︎4.3 / 5.0
優しい、一生懸命、かわいい‼️
不幸な生い立ちのため十分な教育を受けることが出来ず、読み書きができない65歳の主人公。定年を機に夜間中学へ通い、長年支えてくれた妻へ感謝のラブレターを書こうとするが・・・‼️感動的な物語です‼️物語だけは‼️天邪鬼な私の感想としては、表面的な取り繕いが目立つ映画、外ヅラがいい映画ですね‼️まず主人公が読み書きできない恥ずかしさや悲しさがあまり伝わってこない‼️妻からのラブレターを読めず、万年筆のプレゼントも使うことが出来ないみたいなエピソードはあるのですが、なぜ主人公は35年間も読み書きを習得しようとしなかったのか⁉️あまりにも忙しすぎて時間がなかった⁉️妻が一生懸命教えてるのに居眠りする主人公‼️あまり真剣味が感じられないし、仕事が忙しいなら忙しいで、その辺の深掘りな描写が欲しかった‼️そして夜間中学の描写もヒドい‼️担任の教師のキャラも薄っぺらく、教師と主人公の交流描写もホントに浅い‼️その夜間中学の同級生たちの描写も甘っちょろく、注目されるのがストレスになる男子や、小学校低学年から中学卒業まで不登校な女子など、問題ありそうな興味深いキャラはいるのですが、次の瞬間、主人公が彼らの問題をすべて解決してるみたいになってて、あ然としてしまう‼️そしてラストの主人公の卒業式で、たくさんの同級生たちが祝福してくれるのですが、主人公と同級生たちの人間ドラマが無いに等しいため、無理矢理感があってかなりシラケてしまう‼️そしてタコ焼きや公園のベンチ、万年筆といったこれみよがしの小道具も扱いにもう一工夫欲しかったですね‼️妻が病に倒れてしまったり、妻からの35年目のラブレターなど、いいアイデアだと思うのですがエモーショナル感がイマイチ盛り上がらない‼️すべての要素を活かしきれてない印象がある‼️これは監督の演出力不足ですね、間違いなく‼️主人公に扮する鶴瓶さんも読み書きが出来ない設定が妙に納得できてしまうのがミスキャストで、演技自体も悪フザケしてるみたいに感じられ、悲しみが観てる者に伝わってこない‼️もうちょっとキャラ設定やストーリーに奥行きが欲しかったです‼️ただ妻を演じる原田知世さんと上白石萌音ちゃんの、聖母マリアのような存在感は素晴らしかったと思います‼️
温かい空気感がとても素晴らしい映画でした。
重岡さんのファンの者です。
公開初日に早速観ました。とても心温まる、素敵な映画だったと思います。
過去パートの重岡さんと上白石さん、現在パートの鶴瓶さんと原田さんはそっくりというわけではないのに、空気感が同じで過去と現在を行き来しても違和感がありませんでした。
特に上白石さんと原田さんは一瞬見間違える瞬間もあって…驚きでした。
自分に重ね合わせたときに10年後、20年後にこんな夫婦にはなれないだろうなぁと思ってしまったりもして、号泣!とまではいきませんでしたが、終始ホカホカとした温かい気持ちになることができました。
歳を重ねてから観るとまた違う印象を受けるかもしれませんね。
主人公と同世代のシニアの方にも、若い方にも観ていただきたい映画です。
優しさと温かさに涙
字が書けないことで様々な葛藤があったと思います。書けないと告白するシーンではバレたくない気持ちや嘘をつき続けた事への罪悪感...色んな感情が映像からどんどん伝わり涙が止まらなくなりました。
鶴瓶さんと重岡くん演じる保さんと原田さん萌音ちゃん演じる皎子さんの夫婦愛はとてもほっこり温かくて、ずっと2人でいてほしいと思ったし、こんな風に支え合って生きていけたら素敵だろうなと思いました。
だからこそ最後のラブレターはとても感動しました。映像も儚く美しかったです。
なんだってやり直す事はできる、諦めないことの大切さ、そして人々の優しに触れまた明日から頑張ろうと思える映画です。
全313件中、261~280件目を表示