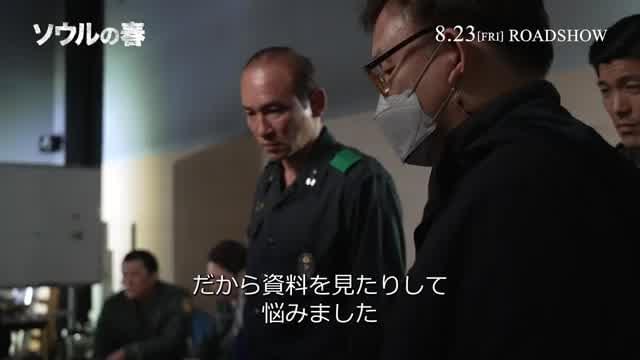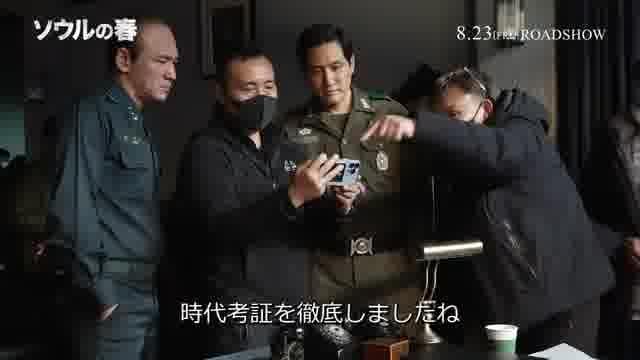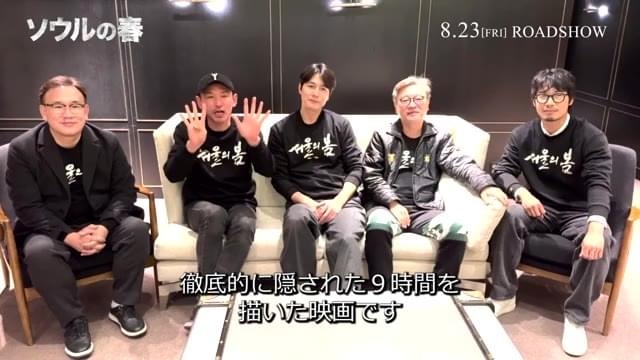ソウルの春のレビュー・感想・評価
全153件中、61~80件目を表示
2時間半があっという間に過ぎた
K国以外の海外字幕版・日本語字幕版は、( )表記でも良いので、実名を記して欲しかった。
K国現代史は、架空小説の様に面白いので、鑑賞しましたが、
K国の混迷は‘’過去の出来事‘’として、終焉したわけでもなく、
今でこそ"こちら側"ではありますが、政治はいまだ混沌としており
日本語字幕では「友」と訳されはしていたが、タイトルエンド曲で「アリラン(朝鮮統一歌の題名)」を連発連呼していた事でも、K国の混沌さが、よく理解できると思います。
K国現代史は、複雑であり、1番面白くもある時期なので、K国現代史を知らない人には、予習してから、本作を観る冪だと思います。
日本的に判り易く解説すると、映画の主人公は、信長を直接手にかけてはいないが、まさに明智光秀であり、ライバルが秀吉となる。
崔 圭夏10代大統領は、家康的な毛利元就の立場に近いのかもしれない。
そして、ハナ会とは、暗殺された信長的な朴正煕 9代大統領親派である。
すると「光州事件」は、「刀狩り」に相当する。
この映画を観る前に、近年 映画化され続けているK国 現代史を理解する為に「KCIA 南山の部長たち」「ある革命の真実」「タクシー運転手 約束は海を越えて」「偽りの隣人 ある諜報員の告白」と言った映画を観て、予習しておく事が良いかもしれない。
歴史の暗部を見つめようとする意志が伝わってくる
私は同時代を生きてきましたが、軍事独裁政権が続いていた韓国の内実は、新聞や雑誌「世界」などによって断片的にしかわかりませんでした。韓国の政治状況は日本にも影響があり、1973年には金大中拉致など日本の主権侵害が起きましたが、うやむやに処理されましたた。
1979年10月朴正煕がKCIA部長によって暗殺されたことは、日本人にとってもショッキングでした。韓国が民主化するかと思いきや、1980年5月光州事件と軍事政権は続いた。
70代以上の方の歴史認識の欠落を埋めるのに役立つと思います。どこまでがフィクションかは不明ですが。
全斗煥役のファン・ジョンミンはいい人過ぎて、権力欲まみれのサイコパスという雰囲気に欠けます。
当事者である全斗煥が2021年に亡くなったことも、この映画が製作された要因かもしれません。展開に勢いがあり、最後まで飽きさせません。歴史の暗部を見つめようとする意志が伝わってくる良い映画だと思います、
すごいモノを観た!
重厚かつよくできた歴史エンタメ作品
一連の流れは教科書的には知っていました。
それを一本の映画としてどのように映像化するのか、それこそが一番の関心を持って観劇しました。
ただひたすら見事であり、悪役としての全斗煥や盧泰愚の行動に怒りを覚えつつも、民主的な手続きを踏まえた上での抵抗しかできない張泰玩らの頑張りには涙します。
このような骨太のエンタメ作品がきちんと成立してヒットする韓国映画業界は素晴らしいとしか言いようがありません。
様々な問題的をしてヒットした「ラストマイル」を蔑む意図はないですが、映画に求める表現のベクトルの違いには大きな差を感じざるを得ません。
「春」が潰える物語
恥辱の季節
ヤバ。まじでヤバ。
映画としてどうこう以前に、まずベースとなった史実がヤバすぎる。
韓国の歴史に疎い人間としては「KCIA」の大統領暗殺事件の後、そこから光州事件に至るだいたいの流れを知ることができて、なるほどなーと納得した。文字通り血まみれで勝ち取った民主化だもんなぁ。。
もちろん英雄譚として盛られてる部分はあるんだろうけど、いかに韓国が恥辱の時代を経て今の自由な空気を謳歌できるようになったのか、そのために少なからぬ血が流されたことも含めて、超ハードかつ誇り高い歴史の一端を垣間見ることができた。
観終わって劇場を出る人たちはみな、重いため息と沈黙に包まれていた。
そりゃそうだ、こんな題材をちゃんとスターを使って娯楽大作に仕立てちゃうんだから、韓国映画ヤバすぎるでしょ。。
内容は韓国における2.26事件であり、序盤は押井守の「パトレイバー2 」を連想した。そこにナウシカとしてのチョン・ウソンが舞い降りる…のだがしかし。
登場人物が多いしだいたい軍服なので敵味方の見分けがつかなくなるとか細かい問題はあるけど、後半に行くに従って解消するし、とにかくそれどころじゃない。
みんな大好きファン・ジョンミン、今回ふと松田優作みがあるなあと気づいた。顔が似てるというより、親しみやすいそのへんのニーチャンて感じなのに、なに考えてるかわかんなくて怖いとか、狂犬ぽい役が似合うとか、全体的に体型がヒョロっとしてるとか…長生きしてね!
帰り道、思わずその辺を歩いてる人に全員観て!と言いたくなった。ていうか観て!
上手いことやったのが全斗煥、下手打ったのが226?
タバコの本数と電話のなる音に負けず劣らず、情報量が多くて登場人物も...
権力暴走への危機感
クーデター発生から反乱軍と対反乱軍の対応攻防など、テンポよくスピーディーかつ緊迫感のある描写で面白かったです。
正直、スピーディー過ぎて名前とか所属とか位置関係とかきちんと把握しきれていませんが、実話モノらしい説明字幕などでおおむね状況は分かったように思います。
主要人物は対比的なキャラクターとなっており、上層部の事なかれ主義のクズぶりも際立ち、人物描写は分かりやすく見やすかったです。
クズぶりは戯画的過ぎるようにも感じましたが、もしかしたら実際にこんな感じだったかも知れませんが。
とは言え、一応この作品を観る前にクーデター事件の概要はネットで調べて把握していたので、全く知らない状態だとクーデター計画の流れとか理解しにくかったかもと。
チョン役のファン・ジョンミン、イ役のチョン・ウソン、それぞれのキャラクターがよく伝わる演技も良かったです。
チョンのアクの強い野心家ぶりも、イの真っ当な軍人としての信念を貫く様子も、それぞれに印象深いです。
最後の対比は、もうなんとも……
軍事力を持った権力が暴走することや、暴走を容認してしまうような体制への危機感がひしひしと伝わります。
これを繰り返してはいけないと。
日本も自衛とは言え軍事力を持った組織がありますし、費用を膨らませたり不祥事が発覚したりしている昨今、完全に大丈夫だとは言えないのではと思ってしまいますが。
韓国軍事政権の暗闇と正義の潔さ
全153件中、61~80件目を表示