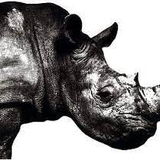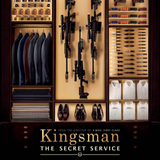侍タイムスリッパーのレビュー・感想・評価
全1290件中、21~40件目を表示
やっぱり映画は予算じゃないよねぇー
この作品は本当に観た方がいい!!
監督、スタッフ、協力者、俳優さんと、本作品に関わる全員の本気度が映像から伝播してしまう作品でした。
劇中にはいろいろ『んん?』が頭にが出てきちゃう場面もあるんだけれど、それがぜんぜん気にならないくらいに劇中に引き込まれます。
待てよ、、もしかすると端から期待せずに観たからか?と思い、2回観ました。ですが、2度目も劇中にいるような感覚に、フッと我に返る場面がいくつもありました。 特に終盤、寺での決闘シーンでは、あたかもその場にいるような錯覚にさえなりました。 俳優さんの緊迫感、終わりを迎える寂しさのような、堪らない感情がスクリーンからあふれ出て来ていました。
映画ファン必見の作品です。
日ごろの煩わしい事を忘れたい方は是非ご覧ください。
話題性に負けない面白さ。
トリッキーな感想です
少々、トリッキーな感想になりそうだ。
メタフィクション。フィクションの中で繰り広げられるフィクションとでも言おうか。
それを一発で表現した言葉が『侍タイムスリッパー』。実に見事なタイトルだ。
時代劇の撮影村で斬られ役として生きる本物の侍。
軽妙な日常と、丁々発止の命のやり取りを同居させるこの映画ならではの演出に心を打ちぬかれた。
何より、主演の芝居が非常にいい。あまり詳しくないのでこの俳優さんのことは全く知らないのだが、それも良かった。まるで、本当に侍がトリップしてきたような印象を受けるからだ。
この先はネタバレを含みますのでもし読む人はご注意ください。
正直言って、前評判が高すぎて、見ている間はちょっとがっかり感があった。「これじゃ、駆け出しの斬られ役が斜陽の時代劇映画で成功していく物語じゃないか」というような感想だ。主人公が「本物の侍」である必然性があるだろうか?
ところが中盤で意外な展開を迎える。
同じ斬られ役から身を起し、国民的人気俳優に上り詰めていった男からのアプローチを受けた時のことだ。なんとこの男もタイムスリッパーだったのだ。この映画が秀逸なのは、それぞれの到達点に時間差があったこと。そこを上手に生かし、主人公がやがて行き着くであろう成功した姿を一瞬で表した。さらに、侍として持つ覚悟と一人の人間としての苦悩を告白し、それ故に主人公に接触してきたことを明かす。
このふたりのやり取りが非常に素晴らしい。
ふたりは、同じゴールを目指して走るランナーだ。
リードする侍は40キロ地点で、主人公は20キロ地点にいる。40キロ地点から見れば、きつい坂道だったり、向かい風も乗り越えて同じ困難に向かう後進のランナーにアドバイスを送れる。だが、ふたりともゴールは見えていない。
この構図が実に見事だ。というより、それを分かりやすく、それでいて確実に伝えきる。そのことが見事だ。
そしてクライマックス。
この緊張感は、今までの時代劇で感じたことのないものだった。
本物の侍たちが、劇映画の立ち回りの中で命のやり取りをする。この倒錯した設定に、ただ息を殺して見つめるのみ。そして見終わった後の少しの清涼感と、まだ続きがあるのかと思わせるような裏切り。
この侍たちの行く末を、もう少し見ていたいと思った。
本当は、不満点もいっぱい書きたい。でも、やめておこう。ひとつだけ、分かりやすいところで印象に残るシーンについて考察したい。
侍が、ちょんまげをやめて実生活に合うように髪を切るところ。
時代劇の役者たちはヅラをかぶり、あたかも本物のちょんまげであるかのようにしている。ところが主人公のちょんまげは本物だ。それをやめて、短く整える。それによって、少しだけ不便から解放される。現代人に馴染もうとするのだ。
このシーンがよく表していると思うのだが、簡単に言うと、リアリティが無い。そう感じた。いっそのこと、この役に合わせて本当にちょんまげを結い、劇中で本当に切るぐらいのことは出来たんじゃないか。そのような違和感を、けっこうな頻度であちこちに感じた。それが不満点だった。
そんなことはすっ飛ばして、単純に楽しめばいい。見てよかったと思う。
2025.10.13
幕末の侍が現代にタイムスリップ!?
日本アカデミー賞で作品賞を受賞したのがきっかけでどんな映画なのか金曜ロードショーで初めて観ました。
幕末の侍がある夜の雷で目が覚めたら現代の日本にタイムスリップする所から始まります。そっから右も左も分からず彷徨ってしまい寺で居候という形になり、他の人からは時代劇の役者だと勘違いしますが、ある撮影で主人公の侍が斬られ役が凄っと感じ斬られ役で生きてきます。
中でもラストの殺陣シーンで真剣を使ってやるのが凄かったです。
※前述の通り日本アカデミー賞で有力候補(キングダム、正体)のどっちかと思ったらまさかのこの作品で僕は驚きました!
やっぱり低予算で製作した映画は凄いなと改めて感じました。
レビューが書けないほど、何度も見たくなる作品
公開当初は知らなかったが、東映撮影で撮影した時代劇とのことで公開から3か月経って見に行った。見た当初、今レビューを書こうとするが、なかなか筆が進まない作品だ。
ストーリーは単純明快でタイムスリップした侍が斬られ役になる話。山口馬木也氏演じる会津藩士・高坂新左衛門が侍で侍役を演じているのだ。所作、身なり、セリフがあって役を演じているのが時代劇の侍役だが、高坂の生きてる侍が現代で斬られ役になるのだ。
当初から高坂の侍の心情、小ネタ、最後の2人の侍同士の殺陣は素晴らしいが、今改めて見ると切ないのだ。
おそらく、時代劇が衰退と言われ、良くも悪くも変化していき、無くなってしまうものと重なってしまう。
時代劇について考えるにもいい作品だ。
転生侍と棒読み和尚
結局、タイムスリップものって最近流行りの異世界転生と同じ構造ですよね。
別の時代に飛ばされて、そこで何かしら活躍する。
本作も所謂それなんですが、侍が現代で斬られ役になるという一点突破が潔くてわかりやすい。だからこそ、演技のリアリティが際立ちます。
本物の侍さながらに、所作も空気も違う演技は見どころで、“演技”ではなく“覚悟”が滲んでいるような、妙な説得力が生まれていました。
そして、聞いてはいたものの改めて観るとやはりエンドロールが壮観。
監督が、脚本・撮影・照明・編集・機材運搬・キャスト管理など、計11以上の安田淳一。助監督役の彼女も、実際に助監督として名を連ねており、少数精鋭ぶりが清々しい。(和尚の役がキャスト不足の弊害だったのかはさておき。)
奇抜さはなくとも、時代劇への愛と斬られ役への敬意が詰まった良作でした。
評価 ★★★★☆(エンドロールで+1)
侍は俺達しかいない
みんな大好き、不器用ですから
前評判どおり、予算が限られた作品としてはよくできている。特にクライマックスの対決シーンはドキドキして息を呑む感じは映画で久々に感じさせてくれた気がする。
日本人の持つ、いや外国人もか、『侍』への夢と希望を具現化してくれた感じ。昭和生まれの時代小説を読んじゃうしらけ世代くらいにヒットしたのか。不器用だけど男気ある高倉健さんみたいなキャラは嫌いな人はいないんじゃ。だからこそ、ズルいね。無名の、そして上手な役者さんだからスッと入り込めた。
現代へタイムスリップしてからの順応性の高さや、人によってたどり着く時期が違うのとか、ツッコミだしたらいろいろあるが、現代にもサムライ魂は生き続けてると信じたい、その信仰に琴線が触れました。
これぞ映画、これぞエンタメ
まず、なにより主役を演じた山口さんのなり切りっぷりがすごい。表情から言葉遣い、所作まで現代に生きる侍が本当にいるかのようです。がんばって演技してます感がなくてとても自然なのがすばらしい。パンフに監督が「メソッド法を完璧に体得」と書いているのも納得。
主人公の愚直で生真面目な性格もいい。国のために自らの役目を全うしようとする姿勢とか、タイムスリップものにつきものの現代の社会に驚いたり感動したりするときのどこまでも素直な態度は、「テルマエ・ロマエ」の主人公に通じるものがありますね。
この作品、時代劇の部分は劇中劇であって構造としてはあくまでも現代劇だとは思いますが、主人公の意識はしっかり元の江戸時代にあって過去を忘れていないので、内面的には時代劇といっていいかもしれません。
時代劇部分が劇中劇である以上、斬り合いは芝居であって本当の闘いではない。そのことが緊張感を最後まで持たせるには不都合なんじゃないかと思って見ていたら、終盤の展開はそう来たかという感じでしたね。最後まで手に汗握って見ることができました。
公開当初は東京でしか上映していなくて、それにもかかわらずネットの評価が高いのが気になっていましたが、いざ地元にきて見たら本当に面白かった。その後の快進撃も必然の快作だと思います。
侍、まさかの“斬られ役”デビュー!
幕末の侍が、まさかの現代の時代劇撮影所にタイムスリップ!
しかも“斬る側”じゃなくて“斬られ役”で生きていこうと決めるって、発想がもう面白すぎる。歴史の重みとコメディがいい感じに混ざっていて、笑えるのにちょっと胸が熱くなる瞬間もある。
主人公・高坂新左衛門を演じる山口馬木也さんがとにかく魅力的。渋くてかっこいいのに、現代社会に四苦八苦する姿が妙に可愛くて、見ていてニヤニヤが止まらない。アクションは本格的だし、所作や立ち回りの美しさも見応えあり。
「侍が現代で“斬られ役”になる」なんていう冗談みたいな設定なのに、気づけば引き込まれてる。時代劇好きも、タイムスリップもの好きも、軽い気持ちで見始めて絶対ハマるタイプの作品。
評判通り
2024年公開、配給・未来映画社、ギャガ。
【監督・脚本】:安田淳一
主な配役
【会津藩士 高坂新左衛門】:山口馬木也
【長州藩士 風見恭一郎】:冨家ノリマサ
【助監督 山本優子】:沙倉ゆうの
1.面白かった
『蒲田行進曲』と小学生の時に読んだ小説(タイトル不明、一寸法師が現代にタイムスリップしてくる話)を足したような話。
(↑追記 おそらくだが、福田紀一『こんにちは一寸法師』であることが判明)
ラストの落とし方もよかった!
高坂新左衛門を演じた山口馬木也が、
まるで実話再現しているくらいのハマり方。
2.良い人だけの映画
良い人しか出てこない作品。
私は大好きだ。
映画の世界くらい、そんな夢が見れてもよい。
3.まとめ
良作。
何度も繰り返し観ることになるだろう。
☆4.5
正直総評としては期待を上げすぎたのでそこまででは無かったけどタイム...
人の温かさに触れる作品
全1290件中、21~40件目を表示