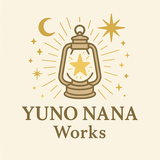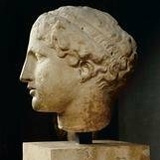ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全66件中、1~20件目を表示
コーダとして生まれた主人公の苦悩とそこにある普遍的な愛の物語
本作品は、作家・エッセイストの五十嵐大による自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」を実写化した映画です。吉沢亮さんが主演を務め、中学から青年までの主人公を繊細かつ力強く演じています。吉沢さんの子役の見上げる仕草が、吉沢亮さんそのものだったので、演出が細かくて素晴らしいなぁと思いました。
この映画で描かれているのは、コーダ(耳のきこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子ども)というマイノリティな生い立ちの主人公五十嵐が、苦悩しながらも成長していく姿です。その環境は少し特殊なものであったかもしれませんが、その本筋に流れるものは、とても普遍的で誰にでも共感できる家族の愛の物語です。
私の号泣ポイントは
息子五十嵐が、「今までごめん」と母に言った時に、「え?なにが?」みたいにとぼけたシーン
おい、世の中の息子ども
母の愛❤️舐めんなよ!!
障害があろうがなかろうが、あなたを産むって決めた時から、こっちは腹括ってんのよ。あなたの思春期のかわいらしい反抗なんて、ほんのジャブにもならんのよ。
また、
電車で母と息子が仲良く手話ではしゃいでいる場面からの
母が息子に「手話で話してくれてありがとう」みたいなシーン。
そうそう!!そういう何気なく普通に成長した息子とはしゃげる瞬間って、母の夢よね。たまらんね。
子どもが「申し訳ない」と思っているほど、親はなんとも思ってないとか、子どもが幸せだと感じたパフェのことを母は覚えてなかったりするのとか、「あるあるだなぁ〜」って、深く共感しました。
こちらのレビューは、絶賛母目線で書かせていただいておりますが、もっと遡れば、生まれた家が何故か自分には窮屈で19歳で家をでた自分の姿にも重なり子ども目線でも涙でちゃう本作品、もうほんとにやばいです…😭
子を持つ親御様方、思春期のお子さんたちも、おばあちゃんおじいちゃんも、どうぞ厚めのハンカチをご用意してご鑑賞下さい。
それぞれ違った悩みがある、それはどの家族も同じ
ろう者の両親を持つコーダの主人公、大の人生の描写は赤ん坊の頃から始まる。
原作者の五十嵐大氏は1983年、宮城県生まれ。両親から愛される素直な子供だった大が、年頃になり「普通でない」両親を嫌悪するに至る過程が丁寧に描かれる。
市場の鮮魚屋で初めて母の「通訳」をして店の人に褒められて以来、誰が強制したわけでもないが自然と、両親と健聴者の通訳が彼の役目になっていったのだろう。相手から褒められ、両親の助けにもなることで幼い大は単純に嬉しかったかもしれないが、その役目が固定化され当然のものとなったまま思春期を迎えると、だんだん両親が疎ましくなった。
一見「普通でない」家庭の、世間的にはマイナーな苦悩の物語のように見える。確かに、大が家庭の内外で苦悩する理由は、コーダ独特のものだ。
だが、彼が母親に対して抱く嫌悪感は、誤解を恐れず言えば、どこか私自身の思春期の感情にもかすかに重なる部分があった。コーダ独特の悩みの中に、誰もが通過する反抗期に共通する感情も透けて見える。だから、全く違う境遇なのにどこか不思議な共感を覚えた。
彼の両親が一貫しておだやかな愛情を我が子に注いでいることは、節々のさりげない描写から伝わってくる。大が自分のフラストレーションを母親にぶつけることができたのも、本人は意識せずとも、母親の愛情への信頼が根底にあったからだろうという気がした。
彼らの物語を見て、ろう者を両親に持つ人は「普通の人」より特殊で大変だな、とか、ましてやかわいそうだなどという気持ちにはならなかった。
海沿いの道で、父親の陽介が母の明子に伝えた言葉の通りなのだ。
「まあでも、どんな家も、それぞれ悩みがあると思うよ。多分ね」
それぞれの家庭で、家族の悩みは千差万別。そういう意味では、「普通の」家庭の定義などないし、裏返せば五十嵐家もそのバリエーションの中のひとつの形に過ぎない(彼らの苦労を軽視する意味合いでは決してない)。家族の在り方そのものよりも、彼らと接する周囲の人々がそのような理解で受け止めないことが、大の苦悩を大きくする原因だった。
一方、大は上京して両親以外のろう者と出会い、同じ手話でも地方によって表現の違いがあることや、進んで通訳をすることが時にろう者の自立した行動の妨げになるという視点を知った。この考え方は、両親を故郷に置いて来たという大の罪悪感を和らげたに違いない。
コーダという立場を疎ましく思って逃げるように家を出た大だったが、上京したことで結果的にろう者の世界の広さを知り、両親との関わりを素直に見つめ直すことができた。
静かで切なく、そして最後に清々しい気持ちになれるひとりの青年の成長譚だ。
ラストに長い回想シーンを持ってきてほぼそのまま終わる(電車の中でPCを打つタイトルカットはあったけど)というのはちょっと意外だった。一般的に、終盤の回想というのはクライマックスを盛り上げるための足掛かり的な使われ方をすることが多いので、あのあと進行中の時間軸に戻ってひと山あるのだろうと、漠然と思っていた。
駅のホームで、人前で手話を使ったことに母から礼を言われて初めて、大は自分の言動が母をどれだけ追い詰めていたか気づき、罪悪感と後悔に苛まれ、自分を恥じて泣く。彼の気持ちが変化する節目の場面だ。
上京後、祖母に取り次いでもらった電話で大声で母に話しかけた場面や、父の入院で帰省した時に「俺、帰ってこようか?」と言う場面は、時系列的にはこのシーンの後の出来事になるが、20歳の大の涙を知らずに見るのと知って見るのとでは彼の気持ちの解釈が全く変わってくる気がする。
原作では時系列通り中盤に描かれているこのエピソードをラストに持ってきたのは、単にもっともエモーショナルな場面だからか、あるいは他の意図があるのだろうか。個人的には、時系列で感情を順番に積み重ねてもよかったかな、と思った。
あと、手持ちカメラの揺れが多用され過ぎてノイズに感じる時がちょっとあった。この手法、言うほどリアリティに貢献するかなあ、と思うことがある。
吉沢亮が大の中学生時代から演じていたのは驚いたが、あの年頃の難しい感じを絶妙に演じていて嫌な違和感はなかったし、成長していく様子も自然でよかった。
ろう者の役は全て実際のろう者が演じたとのこと。「コーダ あいのうた」に影響を受けてそうしたと呉美保監督が語っているが、当事者性からくる説得力はもちろん、みなさんの個性が物語によく合っていて魅力的だった。大の両親の雰囲気もよいし、河合祐三子の演じるパチンコ屋で出会ったお姉さんが自由で、大の世界を広げるキーパーソンとしても効いていてかなり好感を持った。
こういう作品が好き
吉沢亮を前面に出す内容になるのかと思いきや、序盤はしっかり大の幼少期を描くいたことに驚き。
コーダの人の軌跡を示そうとする姿勢にはとても好感を持てた。
大も「こんな家に生まれてこなきゃ良かった」的なひどいことを言っているが、決して「嫌なやつ」と思わせない吉沢のバランス感覚も見事。
最終的には親子の仲が縮まったが、「もう少し歩み寄れたら良かったのに…」と思うが、やはりコーダとして生きてきた大にとっては、時間を置き、別環境で生活しないと、気持ちの整理はできなかったのかなと思う。
障がいの有無にかかわらず、親子関係の難しさも感じた。
また、ラストが東京移住前夜だったところもなんか良かった。
全てのCODAに共通する話ではない
東北の漁村に育った大。両親は聞こえないで手話を使うろう者。子供の頃から当たり前に手話に親しみ、通訳をする生活。小学校の同級生からは奇異な目で見られる。思春期に入ってからは自身の
失敗を親のせいにするとか反抗期に入る。
バカ私立高校を出ては、自分が何をしたいのか分からず、職を転々とする。ようやく、編集の仕事に就いて生計を立てる。
手話サークルでろう者に出会い、ろう者のコミュティを知る。自身がCODAと呼ばれる人たちだと知るのもろう者から言われて初めて。
出版社が倒産して文筆業として身を立てる決意をする。父親がクモ膜下出血で倒れる。帰省して初めて、周囲の反対を押し切って自分を産み、育ててくれた母親の姿を思い起こすという話。
通常、ろうあ者は地元のろうあ協会に入っている。ろう者のコミュティはあるし、CODAも親を通じて交流がある。この主人公の様に都会に出て初めて自身の立場を知るということは無い。
ろう者やCODAを知らない鑑賞者の為に、実際には無い設定をして、少しずつ理解ができる様に作られた物語だと思う。
主演の吉沢亮は良く手話を勉強している。母親役の忍足亜希子も良いが、個性溢れる脇役陣の演技が素晴らしい。
亡くなった母に会いたくなる映画
耳が聞こえない両親の中で、健常者として生まれ育った若者の葛藤と生きた証
元々「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」という自叙伝をドラマにしたもの
言葉が交わせず、中々意思疎通が出来づらい親子の話ですがラストが素晴らしかったです。
親の愛に気づき、ホームで泣いている主人公こと大ちゃん
その間無音であり、あれがし聴覚障害の聴こえる世界なのかと
手話を使っている方をたまに見ますが、素晴らしい会話だと思っています。
手振りや表情も豊かで、言葉を交わすよりも暖かい何かを感じてしまうのは私だけでしょうか?
昨年の1月に母を亡くし、私も母親になり子供への愛情や心配がわかるようになり無性に会いたくなり声が聞きたくなりました。
見た後に心がポカポカするそんな作品でした。
コーダ
両親の耳が聞こえない子供はコーダって呼ばれてるんだ。
それってあの映画?観たよ。あの映画良かったよね。
この映画はコーダの日常を淡々と映していて、
それは辛いよね、やるせないよね、家族っていいよねという映画でオチもなければフィナーレもない。
そんな映画だった。
障害を持つ人の映画見るたびに思うんだけど、健常者の我々はどう接していいのかわからないんだよね。
でも人それぞれ思いは違うじゃない?
ある人は助けて欲しい。ある人は見守るだけにして欲しい。
だからどうして欲しいのかいつも悩んでしまう。
良く分からなかった!!
特に石巻の人たちの口調がキツく、心がガサガサになります。主人公が東京に出てきても大きく成長したとな思えず、浮ついた印象でした。何か途中で終わっている様に感じました。
いつかいなくなる、ただひとりのあなた
だいだい いつもそうなんですが、ふたりの同居している家族に今夜(ホームシアターで)何を観ようか相談というか聞いてみたんです。
Yは「考えさせられる映画がいいな」と言い、Aが「泣ける映画がみたい」とのことなので、ふたりのニーズに答えられそうな映画をNetflixでみつけました。
東北弁はネイティブなので聞き取れるのですが、字幕付きで鑑賞しました。
結果的に良い選択でした。
原作も有料パンフレットも未読です。
キャメラウォークの ブレというか グラつくのが氣になりました。
淡々と時系列で主人公(大ちゃん:吉沢亮)の成長過程を観るといったスタンスで、ホームビデオっぽく演出してリアル感があります。
木製の箱に入ったチャンネルを回すタイプのブラウン管テレビから始まって、リモコン型のブラウン管テレビになり、ファミコンとスーパーマリオブラザーズのカセットを買ってもらって、後の大ちゃんの部屋にはゲームボーイが置いてあって、おそらくお小遣いで購入したであろう漫画本を読んで過ごします。
それからラジカセがあって、いかにも団塊ジュニア世代の子ども時代の描写に「ああ、こうだったなぁ」と懐かしく思ったりするシーンが多くありました。
舞台は宮城県の海が比較的近い場所。2011年3月を予感させます。
劇中で、アメリカ、フランス、カナダの共同製作の『Coda コーダ あいのうた』(2022年日本公開)のことを言及したということは、今作はリメイクではなさそうですし、邦画らしい視点で東日本大震災を描く映画なのかと思いました。
母親の回想シーンは、きっとそういうことだろうし、『あまちゃん』(主演:能年玲奈、現のん)のようにトンネルを抜けると悲惨な光景が!のようなことになるかと思っていた矢先、「letters」(下川恭平)のアコースティックギターと声のハーモニーが美しいエンデェングになり、原作者が今作の主人公だったと最後に知りました。
震災前の家族、特に母とのことが描かれていて、メンタルの強い祖父母がいたから母がいて、父と出会って恋をして、赤ちゃんを産んで、それが自分(大ちゃん)で...と、命の歴史と自分と世界の関係を20代くらいの頃に理解したのだと思います。
一緒に観たYは泣いていました。
Aは泣かず無言で何かを考えていました。
人は自分に足りないものを求めてしまうものなのかもしれません。
タイトルについて考えてみます。
“ぼくが生きている”というのは当たり前のことですから、わざわざ言う必要がないのですが、敢えて言うというところに意味を感じます。
“ふたつの世界”は、交流としての「聞こえない人たちと聞こえている人たち」、単純に場所としての「田舎と都会」、「外の世界を知らずに電車の中しか見えなかった頃と外が見えてからの世界」、「生と死」、異なる二つのことを言っていることは確かだと思います。
何事も表裏一体であるという観点からみて、タイトルの対義語を考えてみるのも楽しいです。
ああだこうだと考えることができますし、考えているうちに泣けてくる作品です。
赤裸々に描く家族の姿
ひとつの家族、その20数年に渡る物語を赤裸々にそして情緒豊かに描き登場人物像たちの生きてく時間・世界をとても切なく美しく感じられた。
地に足をつけて生きる人々を描く監督の才が出ていて、内面を浮き彫りにした姿が親近感を呼び、その家族にのめり込んだ様に心を揺さぶられた。
東京🗼でも生きる
いわゆるcodaとして生まれた、大、の成長譚。
中盤以降に明かされる両親の馴れ初め、
そして駆け落ち、東京🗼パフェ、
家庭にもよるかと思うが、
codaの立場は知らない者からしたら大変そうと思いがち
大の家では聴覚障害者の両親と母明子の両親と暮らす。
一人っ子でジジババからも大事に育てられた。
ただ、10歳前後から同級生の目を気にするようになり、
怒涛の思春期に突入。
何にでも神経質に尖って見て感じて言うお年頃。
お母さん、お母さんと言ってたのに、
母をバカにする。
相談したかったら、お前から相談しろ❗️
三者面談なのに、担任事前に用意できないのか❓
懇談内容を簡潔にまとめ文書にして見せること。
母親の来た意味無いやろ。
お父さん、ナイス👍
大がしたい事本人がわからない。
役者? パチンコ屋でバイト、 編集者?
最初のお上品なとこは駄目みたいだったが、
むさくるしそうなところには引っかかった。
パチンコ屋のバイトの時、
たまたま手話を使い客と会話。
その人の繋がりで手話サークルに参加。
バーちゃんの携帯からかかって来た電話、
無視せずかけ直すあたり、
心配しているんだね。
手話サークルに行くなんて自分の生活の一部として
思っているからかな。
手話会話もしたいし、
また手話会話することでより上達したい想いもあるのかな。
そして、
そこからまた派生する人脈を自ら進んで構築していく。
東京🗼に行け。
というお父さんの言葉にしたがって良かった。
実家にいる時は、母と噛み合わずイライラしていたけど、
一人の人間として生活する中、
出会った人たちと付き合ううちに
これまでの自分の人生で常に身近な手話を臆面なく
使い会話して楽しむ生活の一部となっている。
両親共に聴覚障害者だから?
皆と同じく元気に生きているんだよ。
美人のお母さんの一言が心に沁みる❤️
私たちが生きていくふたつの世界は、きっと素敵だ
耳の聞こえない両親の元に生まれた子供。“コーダ”。
アカデミー作品賞を受賞したあのハートフル感動作が有名だが、本作はその日本版と言うべきか。
日本リメイクではない。原作者の自伝的エッセイの映画化。題材は同じだが、アプローチも違う。
『コーダ あいのうた』は聾唖の両親の元に生まれた娘の人生の岐路と家族の絆。
本作は子供の誕生から成長、家族との関係や葛藤、主に息子と母親の心の機微、双方を通してより繊細に“ふたつの世界”を描いていく。
共に耳が聞こえない陽介と明子。二人の間に、待望の子供が誕生。
大と名付けられ、無事耳も聞こえる。喜びや幸せに包まれるが、ここからが大変。
明子の両親も一緒に暮らしているが、耳が聞こえない二人に子育ては苦労の連続。
赤ん坊が泣いていても気付かない。ちょっと内職に専念し側で何かを倒しても気付かない。大事には至らなかったが、もしも…だったら?
愛情は人一倍。それを一身に受け、大は成長。まだ幼い頃から手話を身に付け、それで両親と会話したり、時には周囲との通訳になったり。
それが当たり前で、仲も睦まじかった。
小学校に上がった頃から。家に遊びに来た友達から耳が聞こえない母親や上手く喋れない事を“ヘン”と言われる。手話も物珍しい。
次第に周囲の“普通”の家族とのギャップを感じ始め、授業参観なども知らせず。
高校生ともなると手話で会話する事すら煩わしくなった。母親にも素っ気ない態度。
20歳になるとそんな両親や退屈な地元から逃げるように、東京へ。
本を読む事や物を書く事が割りと好きだった事から、出版社へ面接。一流どころは何処も落ちる。
下世話記事などを扱う小さな会社へ面接。複雑な家庭環境話が気に入られ、いきなり採用。
いい加減な感じの編集長から金言。実力より高い仕事が来たらチャンス。逃げるな。…と思ったら、タモリの受け売りかよ。
仕事は忙殺ながら、徐々にその世界の色に染まっていく。
時に耳を塞ぎたくなる事も。これが“聞こえる世界”としたら…
まだパチンコ店でバイトしてた時、たまたま耳の聞こえない客と知り合う。
それがきっかけで聾唖者の集いに参加。交流を持つ。
聾唖の両親や手話が嫌で東京に出てきたのに、数奇な縁。
交流を通して改めて…いや、初めて知らされる事も。
地元では通訳を介さなければ生活もコミュニケーションも難しかった。しかしここでは、聾唖者であっても自由に自分の人生を生き、社会の中で暮らしている。不便な事もあるだろうが、それを苦や恥とはしていない。
会食時、気を遣って注文役をしたが、私たち自身で出来る事を奪わないで、と。
勝手に聾唖者を不器用、何も出来ないと思い込んでいた。
そのポジティブな姿に教えられる。寧ろ自分の方こそネガティブだった。
こちらが“聞こえない世界”。不思議と心地よさや居心地の良さを感じる。
“聞こえる世界”と“聞こえない世界”。
確かに双方に、偏見や生きづらさはある。
が、違いは無いのだ。
幸せ、喜び、悩み、葛藤…。各々持ちながら、周りと触れ合いながら、一人一人が自分の人生を生きている。
ふたつの世界を生きる事は、多くの他の人には無い、特別な事かもしれない。
いい事も嫌な事も含めて。
そして感じるのだ。
改めて知らされる。無償の温もりを。
父が倒れ、8年ぶりに帰郷する。
命に別状はナシ。祖母によると、母は今まで上げた事のない声を上げて狼狽したという。
母は今は落ち着いて、あの頃と変わらず迎えてくれる。
一時ぎくしゃくしたけど、母と自然なやり取りを。
変わった?…と聞かれる。
変わったんじゃない。気付いたんだ。
帰れる場所がある事。迎え入れてくれる人がいる事を。
聾唖のキャストを起用したり、聾唖や手話に通じたスタッフを配したり、リアルに拘ったという“聞こえない世界”。
劇伴を廃し、周囲の雑踏や自然音に溢れた“聞こえる世界”。
丁寧に紡ぎ上げていく。
もっとドラマチックな作りにも出来たかもしれない。大が聾唖グループの人と恋に落ちたりとか。
気になる余白の部分もある。知り合った聾唖女性から私の話を書いてと言われ、大は書いたのか。
『コーダ あいのうた』のようにもっと泣ける大衆向けにも出来た。
しかし、そういった安易な作りにはせず。静かでドラマチックな大きな展開は無いが、引き込まれる。尺は100分ちょっと。もっと長くこの作品に浸っていたかった。氾濫する無駄に長い作品なんかより、こういう作品こそ120分やそれ以上あっていい。
長編映画は9年ぶりになるという呉美保監督だが、その確かな演出は変わらず。シリアスな作品も多いが、最も温かく、優しい。
『コーダ あいのうた』がアカデミーで好かれたのなら、本作だってそのレベルにある。勿論、日本のではなくアメリカの。一切無視した日本バカデミーに価値は無い。
吉沢亮の好演。幼少期や少年期を演じ、見事な手話も披露した子役たちも。
出番は多くないが圧倒的存在感のでんでん。タモリの金言受け売りのユースケ・サンタマリアなども印象的。
やはり聾唖のキャストの好演光る。
パチンコ店で知り合った中年女性、聾唖グループで知り合った若い女性。その温かい輪。
『コーダ あいのうた』のトロイ・コッツァーほどではないが、人柄溢れ出す父親役の今井彰人。東京に行きたいと言った時、全面的に応援。三浦友和よりカッコいい。
大金星は、忍足亜希子。彼女から滲み出るは、聾唖者の悲喜こもごもより、母親の優しさや温もり。
誰もが愛情溢れる母親の姿に魅せられ、自身の母親と重ね、思い出すだろう。
私の母が亡くなってもう10年経つ。ちと世間知らずで不器用な母だったが、一緒に映画を観に行ったり、外食したり、思い出すのは良き思い出ばかり。
演じた母親像や姿に、在りし日の母を思い出させてくれた忍足亜希子の名演。
キネ旬助演女優賞受賞。妥当で当然の受賞。時々異論もあるキネ旬だが、こういう所をきちんと評価するのは信頼に値する。一切無視した日本バカデミーには本当に呆れ果てる。今後も存続していく必要性、あるのか…?
大は東京へ戻る。
駅のホームで思い出すは、東京に出る直前の事。
母に伝えたら、驚かれたが、一緒に必要なものを買いに。
喫茶で軽食。父親から聞いた駆け落ちエピソードに赤面し、その時食べたパフェ。
電車の中でも自然と手話での会話続く。
何故あの時は、あんなに自然体でいられたのだろう。
それに気付くまで、ちょっと遠回りした。
昔からそこに居てくれた。
あの温和な笑顔、優しさ、美しさ…。
変わらず、ずっと。
それに涙する。
それらを胸に、ぼくはまた生きていく。
私たちも生きていく。
聞こえる世界と聞こえない世界。
ふたつの世界で。
それはきっと、素敵だ。
CODAのストーリー
ろう者の話では無くて、CODA(障害の親の元で生まれ育った子ども)の話。
映画の雰囲気はとても良い。
邦画らしい良い映画だと思う。
ただ、物語はお涙頂戴でも無い、主人公に特別大きな葛藤が表現されてる訳でもない。
観てて、「まあ、そんな事もあるよね」ぐらいな展開。
CODAとか関係なく、普通の人と変わり無い心情だと思う。(もしかしたら、これがメッセージなのかもしれない)
正直な、感想としてドラマを求める人には物足りない映画かな。
コーダの人生を丁寧にリアルに描く
「そこのみにて光輝く」の呉美保監督作品。
とても丁寧で、リアルに描かれている。
コーダ(両親がろうで子供は健常者)の息子と母(ろう)の関係を生まれてから、20代後半までを描く。
とても面白かったので、色々と調べたりインタビュー動画を見た。
監督は、リアルさの追求を大前提で撮ったとか。だから幼少期から子役や小学生の子役たちは主演の吉沢亮によく似ていることを前提で選んだとか。全く違和感がない。そんなところも気を遣ったとのこと。
今回は、両親役は本当のろうの役者を使っていて、他に登場するろうの人は皆さん本当のろうの人を使っている。
手話の脚本もあり、手話の演出の人も常時立ち会って撮影した。
主人公の現在までの半生をその時代時代で点描していくのがとても滑らかで見入ってしまう。
でラスト。それまで、劇的効果を排していたけど(音楽なし)、ここで映画的な演出をする。静かながら、ドンとくる演出。
じんわりと泣けてくる。
音楽が全くない(エンドクレジットにはテーマ音楽が流れるがそれまではない)のは、ろうの人が見ても健常者と同じように楽しめるようにという考えからとか。
ドキュメンタリー的では全くなく、しっかり劇映画だけど現実を切り取ったようなリアルな世界がしっかり息づいている。
役者もみんないい。祖母役の烏丸せつこがリアル。いい役者になりました。
あと、母親役の忍足亜希子。彼女が声を出すのですが、それだけで泣けてくる。ろうの人は言葉にならないような声を出して手話をするのがリアルらしいのです。
呉美保は、凄い監督だ。
これはもっとたくさんの人にみてほしい作品。
⚠️私自身、配慮が足りず偏見のある書き方をしている場合があります。申し訳ございません。
冒頭のシーン。音が聞こえない。この始まりがまず素晴らしいと思いました。
私は普段ポップコーンを食べながら映画を観ますが、あの静けさはほぼ初。でもまんまとこのシーンで映画の世界に引き込まれた気がします。
冒頭でぐっと引き込まれてから、吉沢亮くんの芝居に最後までやられました。
親は悪くないけど、結局は産んでしまったから子供が不幸になってしまう。私の想像以上の苦しさを感じる作品でした。でも、それでも親は悪くないんです。
そこがわかるまでずっと親を恨み続けてしまうというか、親のせいにしてしまう大にも共感できてしまいました。
どの世界でも人のせいにしていたら成長は一生できないんです。それを知るまで成功なんてしないんです。失敗だらけなんです。でも失敗も成功もあるから成長するんです。
私の今までの人生を少し重ねてしまう部分もありました。
そして。最後も刺さってまたもや涙。
ぜひ皆さんに観ていただきたいし、2024年のTOP5に入る作品でした!
自分ごととして共感できる成長物語
コーダとして生まれた主人公の
成長譚。
コーダであるが故の
悩みや困難もあるのだが
誰しもその人なりの
悩みや困難があり
誰にでも相通ずる成長の物語。
息子がどんなに反抗しようと
どんな生き方をしようと
存在自体を愛し信じ続ける
両親がすごい。
仏のような両親に
育てられたのだから
じゅうぶん幸せなのに、
そこに思いを馳せられず
思い通りにいかない人生を
両親や家族のせいにするしかない。
これも
誰にでもありがちなことだから
自分のこととして共感できる。
そして
自分らしい生き方を見つけ
いろいろな人と出会い
成長していく中で
両親や家族の思いにたどり着く。
両親や家族を受容することは
自分を受容すること。
子役が全員吉沢亮さんとそっくりで
小さい頃から見てきた気がする大ちゃんが
両親や自分を受け入れられてよかったと
親戚のおばちゃんのように
うれしくなった。
かつて
グラビアアイドルだった
烏丸せつこさんの
かつてを1ミリも感じさせない
俳優としての覚悟や大成を感じさせられる
演技に脱帽。
聞こえる世界と聞こえない世界
きこえる世界ときこえない世界を行き来する大。
その大を演じる吉沢亮さんが良かった。
コーダの一面しか見ていなかった大。
周囲と違うから、学がないからと胸をはれず
親のせいにしていた。
上京して違う社会と接して少しずつ大人に
なり、自分が経験してきた一面が他者と重なり
繋がり違う扉を開けてくれた感じ。
自分と同じ境遇の日本人が二万数千人、この世の中に存在すると知った時の表情は印象的。
電車から降りて母親が『電車内で話してくれてありがとう』涙腺がゆるむ。
その背中姿は無音だが、母親に対しての想いが
溢れ出てた。“ありがとう”と“ごめん”が
涙………。私も号泣。
体全体での表現。良かった。
素晴らしい記事がきっと書けると思います。
ありがとうございました。
あなたの人生が、うまくいく事を願っています
耳の聞こえない両親の元に生まれた五十嵐大を吉沢亮さんが好演。パチンコ屋の店員として働く姿はイケメンホスト ✨
父・陽介を今井彰人さんが、母・明子を忍足亜希子さんが演じる。息子を思う母親の眼差し、夫婦で交わされる言葉が温かい。
祖父をでんでんさんが、祖母を烏丸せつこさんが演じる。お二人の妙にリアリティを感じさせるコミカルで自然体な演技が見事 ✨
ホームで母親の背を見送りながら思わず嗚咽する大の姿に、色々な感情が湧き起こり涙が止まらなくなった。
愛に溢れた素敵な作品。
-大は大丈夫だから
映画館での鑑賞
本筋とあまり関係ない感想になってしまった
吉沢亮の、あの反抗期の息子、まさにアレ。
だるそうなところなんか、まったくそのもの。
私はいわゆる健常者ですが、息子たちの反抗期は重箱の隅をつつくように親の至らないところ、不足をみつけて、そこを全力で突っ込んで理不尽だろうとなんだろうと親を責め、拒否してふてくされ、口を利かなくなる。母は、蛇蝎のごとくというか憎しみの対象みたい。次男が特に酷かった。
スーツを作りに行くところ、自分たちのことかと思いました。
反抗期の次男が大学に合格して、入学式用にスーツを買ってやる、と私の仕事が休みの日に二人で出かけて、店の人に聞きながらあれがいいとか、これがいいとか、次男、他人様の手前があるのかいつになく機嫌が良く普通に口をきくので、私はうれしくて天にも昇る気持ち。それから近くのファミレスでランチして、何でも食べていいと言ったらほんとに遠慮なく、ランチのパスタコースにポテトフライとコーンスープ追加、デザートにパフェ食べて、私の残したパスタまでペロッと食べてしまいました。かーちゃんのお小遣いでお会計したけど、100万回散財してもいいと思いました。
その間、別人みたいにあれこれとよく喋ること。学校のこと、友達のこと、これからどうしたいのかとか、ファミレスをでて家に帰るまでそれが続きました。(長々と自分語りで恐縮です。)
なので、この母の気持ちが我がことのようにわかります。
息子の気持ちはよくわかりませんが、あまり深く知らなくて良いのかも。
出ているところで推測するくらい。親といえども他人に心の奥底まで知られたくないでしょう。
エンディングの曲の歌詞、親の心はあんなものです。
親がそう言うと、子どもにしたら押し付けがましいのでしょうけど。
大は、アメリカ映画のCODAみたいに特に何かに才能があるわけでもない、普通の子どもだが、それ故、特殊な環境の普通のコドモのことを知ることができるよう。
周囲から特別視されるのも嫌だろうし、複雑な感情を抱きがちで反抗期となったらそれが爆発、母のよいところすらウザくなってしまうのだろう。
両親は、障害者が故に教育を受けられなかったようだし、小さくておかあさん大好きな頃までは良いが、それ以降はなんで自分だけ、と思う気持ちは当然だと思う。
迷える大を、温かく見守る両親と祖父母、彼は家族には恵まれている。
就活にことごとく失敗しても腐らない、どこでもやっていけそうな自己肯定感の高さは、愛されて育っているが故でしょう。
両親は、障害が故に息子に負担をかけていることに「罪悪感」を持っていないか、顕にしない。でも、感謝はする。そして、障害者ができることを先回りしてしてしまうことは良くないのだとわかった。
周囲の者はどうするのが良いのか良くないのかわからないので、当事者からどんどん発信してほしい。この映画は、貴重な発信源の一つだと思う。
CODAの話だが、男の子と母親の話だと思いました。
駅で去っていく母はきっと、昔より確実に年を取っているんでしょう。
背中が何かを語ってましたか。
良い映画でした。
見ようかどうしようか散々迷ったけど、観てよかったです。
全66件中、1~20件目を表示