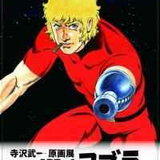ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全200件中、161~180件目を表示
親がたっぷりと愛を注いでいたからこそ。
コーダである彼とそれ以外の彼
産まれた瞬間からどんだけ愛されてきたかを切り取っている。
耳が聞こえない両親を持つという事の苦労は計り知れない。
思春期の反抗も理解できる。但し、思春期の反抗の仕方はコーダじゃなくても、あんな感じ。そこが良い。
きれいごとばかりじゃない、親が反対するのも分かる。
彼が自立していく過程を少しずつ切り取っている映画。
彼はコーダだけど、私と同じで聞こえるから、聞こえない両親の事を理解するのは難しい。だからこその行き違いが生まれて、それが少しずつ埋まっていく。
手話を通じて新しい出会いが生まれていくのも、良かった。
私にも息子がいる。早く自立してほしいと思っている。いつか自立する時、あのお母さんのようになれたらいいな。そして、一緒に買い物行けたらいいな。
吉沢亮は白いTシャツにブルーのシャツがよく似合う。
日常が日常でない
前半は良かったが...
知らなかった世界。多くに人に知ってもらいたい世界
ろうの両親から生まれた子供と言うのはなるほど成長を重ねるにつれ様々な感情の揺らぎの中で孤独感や苦悩と葛藤しながら日々を生きるというのが良く分かります。
反対もそうなのでしょうね。聞こえる両親から生まれた聞こえない子と言うのも同じなのだろうと思います。
誰が悪いと言う訳でも無いけど、でも辛いし悲しい。苛立ちを覚えつい辛く当たってしまうのも仕方のないことなのかも知れません。
この作品の中でも母親にきつい言葉を投げるシーンがありますが、あれは悲しいですね。
きっと言った子供も辛いだろうし言われた母親は本当に悲しいだろうな。
明るく前向きに考えていても子供のその言葉でくじけそう。僕にはコーダの子供の苦悩より母親の気持ちの方が悲しく突き刺さりました。
でも嘆くばかりでは無い希望もきっとある。
だからこそ電車の中で人目もはばからず手話で会話する子供の姿に母が喜びの気持ちを伝えるシーンには救われました。何気ない母子の会話でもこの世界ではとても大切な事なんだと知らされます。
この作品の中でお父さんの存在も大きかったなと感じます。息子との会話でも自身を包み隠さず話し、そして妻であるお母さんの悲しみや苦しみも受け止め、自身の苦悩もあるだろうと思える中で頼もしいお父さんだと思います。この両親を演じた忍足亜希子さんと今井彰人さんは実際にろう者だそうで、経験から来る日常を演じて素敵な両親役でした。吉沢亮くんも難しい役だったと思いますが自然体で演じていたようでやはり実力者ですね。
まだまだ知らないことが多いこの世界ですが、ろう者だって強く生きていこうとしているし、聞こえる側も同情するだけではなく、共に助け合う社会になればいいなと考えます。
あまり身近な問題として捉えることもありませんでしたが、誰もが普通にいれるのが一番ですよね。
いい映画を見ました
忍足さんの演技で、主人公の気持ちに重なっていく
母の生い立ちに比べれば
反社祖父母に育てられた五十嵐大の母明子の生い立ちはどんなに凄まじいものであっただろうか?
孫息子大の奇異な生活と思春期の葛藤よりも博打うち祖父、念仏祖母、ろう娘の壮絶な家庭に関心が持てるモチーフを想像してしまった。
静かな両親達は、ろう学校の同級生で恋仲となり東京に駆け落ちをして、各種の反対を振り切り母の実家で生活を始めた。
子供を授かりここでも出産に対する軋轢があったが何とか五十嵐大を出産をした。
そんな息子大も大きくなり、今までの家庭環境でない生活を求め両親も行った東京で一人生活を始めた。
人は自活して初めて社会、家庭、両親祖父母、知人、生活がはっきり見えてくる。
そんな生活の一つとしてコーダとしての世界を知り始める。
悲しいことに大の思いは9.5対0.5の母のこと。親父は何処に行ったのか?
母役の忍足亜希子さん、素晴らしかった。自然で何処までも優しくて、可愛かった。
(o^^o)
ぼくが生きてる、ふたつの世界
作家・エッセイストの五十嵐大による自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」を映画化。
「キングダム」シリーズの吉沢亮が主演を務め、きこえない母ときこえる息子が織りなす物語を繊細なタッチで描く。
宮城県の小さな港町。
耳のきこえない両親のもとで愛情を受けて育った五十嵐大にとって、幼い頃は母の“通訳”をすることもふつうの日常だった。
しかし成長するとともに、周囲から特別視されることに戸惑いやいら立ちを感じるようになり、母の明るさすら疎ましくなっていく。
複雑な心情を持て余したまま20歳になった大は逃げるように上京し、誰も自分の生い立ちを知らない大都会でアルバイト生活を始めるが……。
母役の忍足亜希子や父役の今井彰人をはじめ、ろう者の登場人物にはすべてろう者の俳優を起用。
「正欲」の港岳彦が脚本を手がけた。
ぼくが生きてる、ふたつの世界
劇場公開日:2024年9月20日 105分
大事件発生😭
イケメンのはずの吉沢亮のヤサグレ感が半端なく素晴らしい😊
全編が芝居とは思えない本当に日常にあり得そうな事ばかりなのもいい☺️
それぞれの葛藤も変に大袈裟でなく、本当に自然な感じなのがいい😄
そして、まさかの編集長の大事件😅
でも、私めの大事件は編集長ではなく、ポップコーンとソフトクリームと生ビールを、一口も口にすることなく、派手にぶちまけてしまった事です🤣
人生初でぬかりました(^^ゞ
映画館のスタッフさんが改めて用意してくれると言ってくれましたが、完全に自分の落ち度なので、さすがに申し訳なくてそこは断りました😅
スタッフさんには、本当に余計な手間ひまかけて申し訳ない気持ちでいっぱいでした(_ _;)
イスに座った時にパンツが変にお股に食い込んじゃって、それがメチャクチャ居心地が悪くて、エイヤーで食い込んだパンツを引っ張ったら、エイヤーでぶちまけたと言う、誰にも共感してもらえない出来事でしたが、そんなモヤモヤもこの作品が吹き飛ばしてくれました😂
聴覚障がい者夫婦の子として生まれ、普通の世界と音の無い世界をつなぐ...
ふたつの世界に違いなんてない!
予告だけで泣けてきて、公開を楽しみにしていた本作。公開2日目の朝イチでさっそく鑑賞してきました。そして泣いてきました。
ストーリーは、耳の聞こえない両親のもとに産まれた五十嵐大が、愛情いっぱいに育てられ、自然と覚えた手話で日常の中で母を支えてきたが、成長とともに周囲の視線が気になり始め、ついつい母に苛立ちをぶつけるようになり、高校卒業後に両親と距離を置くために始めた東京での独り暮らしの中で、さまざまな人との交流を通してその心境がしだいに変化していくというもの。
全編通して特に大きな出来事や事件があるわけでもなく、前半は大の誕生から大人へと成長していく日々が淡々と描かれます。ありふれた日常ではありますが、我が子の泣き声や危険を察知できない、火にかけた鍋の吹きこぼれに気づかない、背後から迫る車のクラクションも聞こえない、健常者とのコミュニケーションが取りづらい等、聾者にとっては気苦労の連続であることが描かれます。少し考えればわかることなのですが、自分の生活を振り返ると、普段はまったく聾者の存在を意識していないことに気づかされます。
そんな中、赤ちゃんから子役を経て吉沢亮さんへ繋ぐリレーで、大の心情の変化を丁寧に描いているところがとてもいいです。家族からの愛情をいっぱい注がれて屈託なく成長していきながらも、しだいに聾者である母を恥ずかしく思い始め、さらには疎ましく感じて反発し、距離を置く大。一見すると、彼の心情の変化は普通のことのようにも思えますが、彼にそう感じさせてしまったものは何でしょうか。周囲からの同情、余計な心配、心ない言動、無自覚な悪意など、両親が健常者なら受けることのなかったさまざまな差別だったのではないでしょうか。と同時に、父とのやりとりからはごく自然な親子関係も感じ、一連の大の反発は、思春期特有の普通のものであったようにも感じます。
上京した大は、聾者の交流会に参加します。(時系列がいじられているのでこの行動が腑に落ちなかったのですが、ラストシーンで理解できます。)ここで聾者の思いに触れ、自身の言動を振り返ったことでしょう。中でも、そこで出会った彩月たちとの飲み会で、大がみんなの分まで代わって注文した時、彩月から発せられた「取り上げないでほしい」という言葉が印象的です。よかれと思ってした大の行為は、これまでに聾者の息子として大が受けてきた周囲の反応と同じではなかったのでしょうか。
父の入院を機に実家に帰った大は、母・明子が祖父母の反対を押し切って大を出産したことを聞かされます。相当な苦労を乗り越えて自分を育て上げた、母の深い愛情を噛みしめたことでしょう。それとともに、障害者だから何かを制限され、我慢を強いられる必要などないことを強く感じたのではないでしょうか。聞こえる世界と聞こえない世界の違いは音の有無だけで、それぞれの世界に生きる人々の思いに何の違いもないのですから。それを知った大は、その思いをこれから自分の言葉にして広く伝えていくのではないでしょうか。祖父の言った“人に威張れるもの”、編集長の言う“しがみつけるもの”、それを手にしたのではないかと思います。
主演は吉沢亮さんで、多感な10代からの大の変容を見事に演じています。脇を固めるのは、忍足亜希子さん、今井彰人さん、烏丸せつこさん、でんでんさん、ユースケ・サンタマリアさんら。中でも、忍足さんの純度100%の愛情演技が心を揺さぶります。他に本当の聾者の方々が多数起用され、作品の説得力が増しています。
自己肯定感の高い両親の生き方が自然体でGood
聴覚障害者の両親を持った健常者の子供(コーダ)の人間ドラマ&成長物語。敢えて山場は作らず、親子の日常をドキュメンタリータッチで淡々と綴っていく。2022年アメリカ・アカデミー賞作品賞受賞作コーダあいのうたと同様に、本作に登場する聴覚障害者はすべて実際に聴覚障害のある俳優が演じている。
本作の舞台は宮城県の小さな港町。主人公は五十嵐大(吉沢亮)。彼は聴覚障害者の両親の元で生まれ、小さい頃は母親の耳となり母親と周囲の健常者たちの通訳を熟していた。しかし、思春期に入り、周囲の目、両親が聴覚障害者であることに苛立ちを感じはじめ、明るく優しい母親と衝突するようになる。そして、彼は上京して彼の家庭事情を知らない東京でアルバイト暮らしを始める・・・。
主人公役は中学2年生までは子役が引き継いで演じるのだが、子役の面差しが徐々に吉沢亮に似てくる。主人公の成長に不自然さを持たせず、中学3年生から激変する主人公を際立たせている。作り手の丁寧な演出である。
主人公が思春期になって荒れても両親は自然体である。どんな家族にも色々あるからという父親、荒れる主人公に責められて父親に凹むと穏やかに吐露する母親、が象徴的である。両親は、聴覚障害を負い目ではなく個性だと考えている。だからこそ、両親は結婚し子供を産み育てることができたのである。両親は、確固とした自己肯定感を持っている。
主人公が東京で知合った聴覚障害者たちも同様である。彼らは、出来ることは自分でやろうとする。レストランなどの公の場でも聴覚障害者であることを隠そうとはしない。主人公が何でも助けてくれるのを良しとしない。
ラスト。もっと切れ味の良い、後味の良い幕切れにはできただろう。敢えて、そうしなかったのは、まだ、主人公が発展途上だからである。健常者と聴覚障害者の世界で生きていること、生きていくことを強く自覚して終わる。ストーリーよりも主人公の今に寄り添った素直な幕切れだったと解釈できる。
コーダの辿る道
コーダでは映画向け?尺不足?で聾の子供の悩みがあまり深く描かれて無かったような気がしたけど、こちらでは乳児の頃からなので聾の育児の大変さ、子供が学校(特に小学校 子供は残酷だ)で浮いた感じになる様子等とてもリアルだと思った。ら、やっぱり実話だった そして子役が雰囲気似ていて吉沢亮の制服姿も死んだ目も違和感無かった 手話も覚えたのかな?
手話にも方言が有るのですね
母の産むという決断、不器用ながらも愛情深くしかし押し付けがましくなく、とても良かったです 新宿の○○フルーツパーラー親子で行って欲しかったけど...
祖母は烏丸せつこ!びっくりです
『コーダ あいのうた』は少なくとも超えている。ただ事前予習は凶と出るので 前提知識無しでおすすめ 個人的に。
コレ 事前予告編動画が秀逸すぎて 本来なら その葛藤に心❤️揺すぶられるトコ 予習効果あり
ホームページ自体は良いですし。
有料パンフ🈶も 読みやすくて 言いたいことがよくわかる秀逸パンフ。 3拍子揃った文字どおり
俺 今日 『あの人が消えた』以降時間が空いたので
有料🈶パンフは全て事前に完読【アホです🙇❗️】
おまけに有料パンフにはシナリオついてて読みやすくて事前に完読【やっぱりアホですね🙇】
つまり 親子の葛藤に本来は胸打たれる ところ イマイチ
みなさんはこの轍を踏まないで❗️
俺のしかばねを越えていって❗️
きこえる【聴こえる 聞こえる】子供 と きこえない両親 なぜか母親のみ圧の対象 反抗期
忍足亜希子さん 今井彰人さんら ろう者の方が好演❗️
ただ 実際の集客力は吉沢亮によるトコが大きいと推測される
面白さは でんでん 烏丸せつこ【昭和50年代は イイ女の代名詞的な】 ユースケ・サンタマリアによるところ大
吉沢亮 すごいよな 渋沢栄一はともかく
佐野万次郎マイキー🏍️東京リベンジャーズ と 本作の反抗期こなすとは❗️ 役者としての力量か
忍足さんはそうイヤ 『黄泉がえり』で 田中邦衛の妻だったか❓
制作者 俳優 何らかの ろう者の方との接点ある模様 有料🈶パンフの受け売り
手話には方言的なものあるんだね 手話演出 等の専門スタッフさん素晴らしい👍
劇・無い🎵かも でも 感じ入る作品 エンディング曲は要注目
普遍的な 母子の愛情 葛藤 家族だからこその 剥き出しの残酷な本音の吐露 反抗期
今はLINEがあるから薄れてしまったが 昔は【原作の方は1983生まれ 俺は高度成長期生まれの違いはあるが】
進学や就職で親元離れた時の 駅での別れ 母親からの食料品➕手紙✉️ で 母親の存在のありがたさ 感じたものだ。
単純な おせっかいな同情では無く 理解し合う大切さ 感じる作品
俺は 多様性映画は 説教臭くて嫌いなのですが 本作のような リアル多様性葛藤 は大歓迎
誰でも 老いたおふくろの後ろ姿 泣けるよねぇ 俺も 今はとっくのとうに亡き おふくろお母さん思い出した。😭
『コーダ あいのうた』はアメリカ人的な 非現実あっけらかんで違和感あったけど
本作は 葛藤 剥き出し 日本人的な湿っぽさ のあっけらかんで 共感できた。アップデート。家族の形はいろいろあれど本質的な愛は同じ❗️ 本来なら星4・5 だけど 予習しすぎて失敗😔しました。
予想外の 前3列除いて 超満員🈵 観客の良質さは完璧 予告編でのおしゃべりどころか みんなシーンとして
途中トイレ行くもの無し おススメです。予習なしで・・・
お前かわいそうなの?
嗚咽
昔から親子物に弱く、「北の国から 初恋」ではラストの泥のついたピン札で1時間泣き通し、昨年公開された「AfterSunアフターサン」では劇場でなかったら嗚咽していた
呉美保監督の約10年ぶりの新作は母子物
予告の段階でヤバい案件だと思っていたら、案の定、ラスト間際で涙腺崩壊、家で観てたら嗚咽していた
吉沢亮が石巻から上京後フラフラしながら、中途半端に二十代を過ごしている姿が当時の自分と被り…
田舎の母親から届いた手紙を無造作にしまうシーンや、電話に無愛想に応対するシーンなど、刺さりまくりですよ…
それで、最後のあのホームの吉沢亮の無音シーン
わかっちゃいるけど、思い出ポロポロ
男にとって、世界でただ一人の味方が母親ですからね…
色々当時の記憶を呼び起こされましたよ
母親役の忍足さん、好演でした
祖母役の烏丸せつこ、クレジット観るまで気づかず(ユースケ・サンタマリアも)
響きました…オワリ
苺のパフェ~!
息子と母親って特殊なんだよねぇ
全200件中、161~180件目を表示