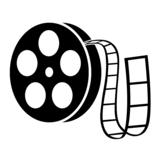ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全200件中、101~120件目を表示
耳は聞こえなくとも、母の愛と父の眼差しは同じ
とてもよかった
普通に育った男の子の人生を追った記録映画のようにも見えるが、両親は2人とも耳が聞こえずそこだけが"普通"とは違う
成長するにつれ、他との違いに悩む息子の大くんだが、思春期になれば悩みは違えどどの男の子(女の子も父親に同じ様な感情が沸くのだろうか?)もイライラしてお母さんが疎ましくなるものだ
だが、成長がある地点を越えると、疎ましく思っていた母の愛が心に染みて来る
それこそ走馬灯のように母の表情を思い返したときの大くんの感情は、大人となった今の自分にもシンクロし、そこから劇場を出るまで涙が止まらなかった
鑑賞した映画館が宮城県で、公開から間もない時期だったこともあり周りには撮影地がご近所のお客さんもちらほらと居たようでした
田舎のあるあるもありながら、全国共通な誰もが知っている心の動きを描いた良作でした
聞こえない世界を知ること
「コーダ」の世界は数年前のアカデミー賞受賞作で知っていたが、「そこのみにて光り輝く」でキネ旬一位を獲った呉美保監督がどのように描くのかと観たら、期待を裏切らない心温まる作品に仕上がっていた。
「コーダ」と言われる方は日本でも2万数千人もいるという。そんなに沢山いらっしゃるのに私は会ったことはない(コーダであることはよほど親しくならないと言わないとは思うが)。
「きこえる世界」でしか生きたことがない多くの人は一生「きこえない世界」を知らないままなのだろうと思う。
映画の中で出てきた聴者とろう者が共に手話を学ぶ会などの存在を知ることもない。
しかし、我々はこの映画を通じて、大が生まれた時の喜び知り、幼い頃から手話を覚え母に寄り添う姿を見て、小学生の頃からは違和感を持ってしまい中高生からは苛立つ大と、それを知りながら愛情の深さが変わらない母と、母との駆け落ちエピソードを大らかに伝える父を知った。「きこえない世界」の一端にふれることができた。
8年の時が流れ帰郷し母に会い、電車の中で思い切り手話で話しができたことを喜んでくれる母の後ろ姿を見て涙する大、、。エンドロールに母の手紙をそのまま英語で歌うラストソングが胸を打ちます。
とても、清々しい気持ちになれる映画です。
号泣
久々の呉美保監督、いつもながらカメラがいい
まさか五十嵐大って実在の人(エッセイ原作)とは!
エッセイのタイトルをそのまま使わなかったのがイイ!
スーファミのマリオが小学生なら同世代かと思ったら一回り下やった
宮城県石巻(塩釜市ロケ)
父親の存在感ってあれぐらいの感じよねぇっていう共感
お母さん(忍足亜希子)可愛い
日本アカデミー賞主演女優(助演女優)賞間違いなし
まだ2024年作品全部みてないけど。
烏丸せつこの娘っていう感じする(顔の系統合わせイイ)
編プロのキャスティングも絶妙
吉沢亮の子役達が全員吉沢亮になりそうでナイスキャスティング
『コーダ』と違う切り口で良かった
主人公の自伝
母からのたくさんの愛情に気付いたとき…
ろう者の青年の成長物語
五十嵐大の自伝「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」を映画化した作品。
宮城県の小さな港町で、耳のきこえない両親のもとでコーダとして育った五十嵐大にとって、母の通訳をすることは普通の事だった。しかし周囲から特別視されることにだんだんといら立ちを感じるようになり、20歳になった大は、罪悪感を持ちながらも親を捨てるように上京し、誰も自分の両親の事を知らない都会に来て、パチンコ屋でアルバイト生活を始め、その後編集者となり・・・という話。
赤ちゃんの時から、4人くらいの子役を経て中学生くらいの時から吉沢亮が大を演じているが、赤ちゃんの2人は演技してたか不明だけど、小学生の低学年くらいと、高学年くらいを演じた2人はなかなか上手かった。
もちろん、吉沢亮も良かったし、母親役の忍足亜希子や父親役の今井彰人など、ろう者の登場人物にはすべてろう者の俳優を起用したとのことで、真実味のある作品になってると思った。
コーダあいのうた、みたいな感動は無かったけど、ろう者に対する接し方について、彼ら彼女らの出来ることまで取って、やりすぎてはいけない、など勉強になった。
活き活きとそして温かみを感じ、沁みる作品
子どもの思いも、親の思いも
障がいのある両親を持つ子どもが大人になっていく過程が描かれているが、誰しもが通り抜けてきたであろう、子ども時代の親との衝突と、大人になってから知る親への悔悟の思いが熱く伝わる
映画を観た私が子どものときの親(特に一緒にいる時間の多かった母親)との衝突、思いきり傷つけたであろう自分が吐いた暴言を、この歳になってすっかり弱っている親を思うと、悔いても悔いきれない思いになる
「どうして私だけがこんな目にあうのか」、親ガチャじゃないけど、親や家族の病気や障がいと向き合っているヤングケアラーたちも、まさにそういった思いと闘っているのであろう
主人公が東京に出て、思うような人生を切り拓けなくても、見守っている母親
せめて声を聞きたい、話がしたい、寄り添いたい、という思いは自分が親になって共感できる気持ちである 呉監督前作の「きみはいい子」も、子どもの目線、母親の目線(先生の目線も)を暖かく描いていたが、人、特に親子の間のあたたかみは、時間距離が離れても損なわれる物ではないことを信じたくなる (9月28日 なんばパークスシネマにて鑑賞)
その世界を知ることで、見え方も違ってくる
聴こえない両親の世界と、自分を含めた周囲の人間の世界。少々身勝手な祖父母は手話を覚えてくれず、聴こえる大が、小さい頃は当たり前の事として両親の為に通訳をしていた。思春期になると、周囲の目が気になり、意思疎通の難しさにも直面して、自分だけが重荷を背負っていると感じ
てしまう。大は優しくて明るい母のポジティブさにも反発して、家を出て上京したいと願う…
聴こえない世界のことは知っているつもりだった。でも自分は母親の気持ちが分かっていなかった。
自分だけが特殊な環境にいると思っていた大が、世界が広がることで、気付きが増えていく話です。
吉沢亮さんの表情の一つ一つが良いです。特に泣き顔が。
他のキャスティングも素晴らしいです。子役が吉沢さんの子供の時の写真にそっくりでした。
それ、タモリな
こんなにも深い親の愛情。でも、リアルタイムでは気づかない
ラストシーンは、この映画を見事に象徴していて、泣ける。場面設定、カット割り、音の効果もうまいし、吉沢亮、忍足亜希子の演技も最高。
映画全体として吉沢亮の手話はネイティブのようで、違和感がなく、感心した。
ふたつの世界とは、「聞こえる世界」と「聞こえない世界」なのだが、「東京」と「石巻」というふたつの世界で成長していく主人公を描いたようにも思える。「思春期、親に反発した世界」と「愛情を感じている世界」のふたつ、と解釈することもできそう。
母親の無私の愛情がとても大きく、強い。主人公に愛情をそそぐ場面がたくさん出てくる。心から主人公のことを思って最善をつくしていた。
だからこそ、予告編にも出てくる「おまえのかあちゃん、しゃべり方、変じゃねえ?」という場面や「こんな家に生まれて来たくなかった!」という場面は、心が締めつけられて、悲しい。
そして後日、愛情をそそがれた場面を思い出して、その時の母親の気持ちを理解した時の、強い感謝の念と後悔の念に共感する。
父親の方も、主人公のことを信頼して「大は大丈夫」と応えたり、石巻に戻って来ないで東京へ行けと勧めたり、愛情が深い。映画「リトル・ダンサー」では、父親が息子の将来のためを思って自己犠牲の行動をとるのだが、その場面を思い出した。
主人公が挫折したり、つらいことが多く描かれる。主人公も観ている人も嬉しくなるような場面は少なく、映画の展開として盛り上がりに欠けるかもしれない。でも、実際には、この主人公は映画の原作になるくらいの本を書いて、成功しているライターである。ライターになる努力と成功をもう少しポジティブに描いても良かったかもしれない。
成長記録であってエンタメではない
よく集めましたね吉沢亮似の子役
まるで、出世魚のブリとかスズキのよう。産まれてから中3役の吉沢につなぐまで4人。
そして、吉沢本人は中3から30代を。最後の方は武田真治風のメイクでした。
宮城県塩竈が実家。
親子三代が暮らす漁港の町。
おじいちゃん(蛇の目のヤス)役はでんでん。
おばあちゃん役が烏丸せつこ。
お食い初めの支度風景。
でんでんがアワビ煮を口元に持っていくと火がついたように泣き出す赤ちゃん。
「なげーなげー、男は声とポコチンのデカさできまんだどー」
CODAの男の子(五十嵐大)はひとりっ子。
聾者の両親が子供を育てるのはとても大変。おじいちゃん、おばあちゃんが元気なうちはサポートできますが・・・
題名はこちらも、Both Sides Now(ジョニミッチェル)的 。
コーダ あいのうたでは描かれない細かい部分も多くて、より家族の物語でした。
補完しあえる映画。
漁港の市場での買い物シーン。オマール海老ではなくてワタリガニ。
バークレー音楽大学をめざしたりしないので、その分話に起伏はあまりありませんが、より身近に感じることができてよかったです。
高校を卒業してから実家と東京を往復しながらパチンコ店のアルバイトから雑誌ライターになった五十嵐大さんの半生の手記を元にした映画でした。原作を読みたくなりました。幻冬社刊。
母親役の忍足亜希子さんと父親(船体整備士)役の今井彰人さん、手話サークルの聾者の役者さんたちもよかった。とくに、忍足亜希子さんは生んだ時から30年以上の母親役を健気にあかるく演じていらっしゃっていて、とても綺麗でステキだった。
車内で手話を交わすシーンとか、息子に悪態つかれて悲しそうにするシーンとか。
聾者の夫婦って辛辣な言葉で喧嘩したりしない気がするし、自分たちだけで手話で冷静に話せて、普通の夫婦より仲がいい気がする。コーダあいのうたのマリー・マトリンも明るかったし、羨ましかった。
夕方に観たらやたら腹が減った。
家族で食事する場面やパフェやカレーのせいもあると思うけど、食欲が出る映画はいい映画なんじゃない?
全くの余談だが、京成線車内で吉沢亮と目があったとウチのオババ姫が妙にコーフンして話しておったのを思い出した。たぶん他人のそら似だよと言うと、京成線沿線に住んでいるし、京成のイメージキャラクターもやっていたから間違いない❗と自信満々に畳み込んできた。なんでそんなに意地張るのかね。
【追記】
でんでんお目当てで鑑賞した。やっぱりさすが😎
母親に甘えて反抗した若い日々。 今のうちに感謝の想いを伝えよう。後悔しないように。
全てをかけて育ててくれた毎日への感謝を伝えられなかったこと。
それどころかうるさがって歯向かっていたことへの後悔。
きっと誰にもあることを、思い出させてくれる。
間に合ううちに、ひとりでも多くの子供たちに、
母への感謝を伝えるきっかけになれば、
この映画はとてつもなく価値がある!
聴覚障がい者の両親を持つ青年の生活のリアルを描く。
両親役の俳優がともに実際の聴覚障がい者であるため、とても自然に観れる。
しかし、そこに描かれるのは特別なことばかりでなく、普通の母と子の想いと変わらない。
何もわからないまでも、子供がやりたいことができるように思ってくれている。
ちゃんと食べているか、常に気にしてくれる。
とてもシンプルな母親の愛と、その感謝を伝えられていない後悔が詰まっていて、泣けた。
日本版コーダ?音が少ないのが絶妙に良い
全200件中、101~120件目を表示