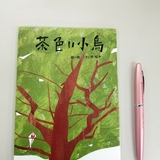ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全200件中、41~60件目を表示
Diversity Inclusion、Unconscious Bias
吉沢亮君が世間を賑わす前の暮れに都内最後の上映となる映画館で鑑賞。
呉美保監督の9年ぶりの作品。淡々と場面が流れていく。
吉沢亮は東京リベンジャーズ、キングダム、最近観たのは大河ドラマの青天を衝けだが、それらの作品では悪くはないのだけれど、等身大以上の役を演じてる感があり、ちょっと白々しい印象を受けていた。それが、今回はすっと入ってきた。ああ、吉沢亮はこれが素なんじゃないか。そう思わせるぐらいの自然さだった。
印象的だったのは、健常者の吉沢亮がろうの人に親切心から手助けをした時に言われた、「ありがとう、でも私達から取り上げないで」と言う言葉。ハッとした。できる事が限られている人達は、できる事を大切にしたいのだ。余計に気遣ってほしくないのだ。普通に接してほしいのだ。多くの人達はできる事が多い側の人間だ。だから、たくさんあるものから優先度をつけて捨てていく。我々の世界は引き算だ。でも彼らの世界は足し算なのだ。できる事が限られている人達からできる事を取り上げてしまったら、引いてしまったら、ゼロに近づき、その人は自分の存在価値を希薄に感じてしまうのかも知れない。親切という名の傲慢。本当の優しさとはいつも難しい。
そして電車の中で吉沢亮がお母さんと手話で普通に話した後、電車を降りた時のお母さんの、「ありがとう、人前なのに話してくれて。普通に接してくれて」という言葉にも固唾を飲んだ。人は無意識に人の目を気にする。無自覚に偏りを持って人を見る。Diversity InclusionとUnconscious Bias。もっと色々な人達に触れ、想像しないと身に付かない。基本的に世の中は不平等だらけだが、平等であろうと心掛ける事はできる。どうか明日の自分は普通に平等な自分でありますように。
「ベビ大ちゃん・プチ大ちゃん・ミニ大ちゃん・チビ大ちゃん・ラスボス大ちゃん」【12月24日追記】
【12月24日レビュー追記】
私の2024年ベスト1映画です。
.
「2024年ベスト3」
まだ何者にもなれない今の自分を受け入れ、周囲との暖かい関係に支えられ、少し上を見て前を向き生きていく、というラストの映画3本を選びました。
.
「ベストレビュー」
12月初めに、私にとってのこの映画のベストレビューと出会いました。そのレビューに私の想いの全てがあると思い、素直に「読者でいたい」とコメントしてしまいました。
人の縁とは不思議なもので、そのレビュアーさんに自分でレビューを書くことをススメられたことがきっかけで、こうしてポンコツレビューにも追記しています。
大好きな作品だけに思い入れが強くレビューが書き終わらず、映画の中と外にあるものを書き散らかした下書きのまま、未完成のレビューを追記しておくことにしました。
.
「非公式アンバサダー」
初日に映画館で観た後、毎日会う人に2種類のフライヤーを渡して、勝手にボランティアアンバサダー活動をしていました。
オススメした相手全員が、その当日から週末に映画館に行ってくれたこと、そして全員が良かったと感想を教えてくれたこと、そんな小さな奇跡が起きた映画でした。
(男の人たちは映画で泣いたと言うのが恥ずかしい様子で、その話を聞き出すのが楽しかったです、ごめんなさい)
.
「ロングラン」
9月13日の宮城県先行公開、9月20日の全国公開から、細く長くロングランが続いています。『侍タイムスリッパー』も9月13日の全国拡大公開からロングラン中なので、どちらもファイナルランまで頑張ってほしいです。
11月17日の「ロングラン上映御礼舞台挨拶」に呉美保監督と吉沢亮さんが登壇して、公式Xで募集した質問に答えるというステキな企画がありました。
海外5カ国の映画祭で上映された報告を読むと、日本と同じように、コーダとしてだけではなく普遍的な親子や家族の物語として受け止められている印象でした。
.
「バリアフリー字幕」
『ぼくが生きてる〜』で、初めてバリアフリー字幕を体験しました。映画館で2回観ましたが、初日に字幕で鑑賞したことは「ふたつの世界」の理解を深めてくれました。
邦画の字幕版のニーズは多様な理由で増えているので、座席で簡単に表示の選択ができるようになればいいなと思っています。
.
「パンフレット」
劇場パンフレットを久しぶりに購入しました。初日に全国的に売り切れてしまったことをSNSで知り、再々入荷でやっと手に入れました。
「宮城県の漁港で東日本大震災は?」「ラストの演出の意図は?」「エンディングの手紙の歌詞はどうして英語なの?」、完成台本も掲載された素朴なパンフレットは、私の疑問に答えを教えてくれました。
.
「監督復帰作」
呉美保監督は、次男が産まれた頃に映画の企画の話があり、小さな男の子2人の育児をしながら9年振りに監督復帰したそうです。この映画からやさしい母親の愛情が伝わってくるのは、復帰当時の監督の目線もあるのだろうと思います。
子役4人が本当に吉沢亮さんに成長していくように見える連携リレーは、五十嵐大さんのノンフィクションを映像化するのに欠かせない演出でした。
母親役の忍足亜希子さんが54歳、父親役の今井彰人さんが33歳、21歳差でも赤ちゃんを抱いている夫婦に見えること、30歳の吉沢亮さんと父親が3歳しか違わないのに親子に見えること、これも監督のマジックでした。
.
「主演男優賞」
吉沢亮さんは、今年デビュー15年で、この映画で初めて主演男優賞を受賞。2018年に俳優として初めての映画賞の新人賞も、同じTAMA映画賞で最優秀の受賞でした。
11月30日の映画祭授賞式のスピーチで「緊張しています。ご縁を感じています。受賞したのがこの作品で良かったです」
監督とのトークで「30歳になる男が中学生を演じました。監督が絶妙なダサさにこだわった昭和の髪型のかつらは不安でした。手話は顔の表情によって意味が変わってくることを知りました」
監督から「役にも周りにも媚びないストイックな職人のよう」、脚本家から「役作りの努力や演技の苦労をおくびにも出さない」と、公式Xでもコメントがありました。
「俳優30歳の壁」をこの作品で乗り越えてくれたこと、吉沢亮さんとこの映画の一ファンとして、とてもうれしいです。
(12月23日、吉沢亮さん主演の吉田修一原作『国宝』の公開が、2025年6月6日に決定しました。予告映像に息を呑みました)
.
「ティザー広告」
今年7月に少し退屈なハリウッド映画を観た日、この映画の予告編を観ました。ちょうどその日、この映画のフライヤーのティザーと本広告の入替えでした。
ティザーは、予告編でも印象的なブルーのシャツの吉沢亮さんのアップ、パンフレット表紙や原作文庫Wカバーにも使われたビジュアル(フォトギャラリー画像21)。
本広告は、五十嵐大(吉沢亮)とお母さん(忍足亜希子)が駅に並んでいる、映画.comのポスター画像です。
製作費も宣伝費も少ないこの映画で、このティザー広告のメインビジュアルと予告編は、「映画の嘘のない宣伝」と「この映画を観に行きたい」と感じた観客の予感の、本質を捉えていたのではないかと思います。
.
「エンディングソング」
映画のエンディングに流れる「letters」のMVが、映画の大ヒット記念で、今年の10月10日から1年期間限定でYouTubeで公開されています。
呉美保監督の公式Xの表現が面白かったので、このレビューのタイトルにお借りしました。
「映画の編集中に、ベビ大ちゃん(3ヶ月)、プチ大ちゃん(6ヶ月)、ミニ大ちゃん(4才)、チビ大ちゃん(9才)、ラスボス大ちゃん(15才〜28才)、5人の大ちゃんがあまりにも似てるから、短めに繋いで主題歌をのせてみたら、なんかええやん!とMVが完成したのです」
.
P.S.
まだレビューを書き始める前の、12月7日の自分のコメントを引用しておきます。
「ラストの駅のシーンを『ニュー・シネマ・パラダイス』に例えられていて、あー先を越されちゃった(泣)…を思い出しました(笑)
鑑賞後に完成台本が載っているパンフレットと原作を読み、公式SNSもフォローしました。
監督があの駅のシーンをラストと決めたところから、この映画作りが始まったことを知り、私の思いをレビューにしたかったのですが…」
.
P.S.2
5/14「第34回⽇本映画プロフェッショナル⼤賞」監督賞受賞・2024年ベスト10第4位
4/24「第34回日本映画批評家大賞」作品賞・主演男優賞・助演女優賞・編集賞最多4冠受賞
2/5「第98回キネマ旬報ベスト・テン」助演女優賞受賞・日本映画ベスト・テン第6位・読者選出日本映画ベスト・テン第10位
1/8「第38回高崎映画祭」最優秀助演俳優賞受賞
2025/1/3「第67回ブルーリボン賞」1部門ノミネート
12/19「第79回毎日映画コンクール」3賞ノミネート
12/1「第46回ヨコハマ映画祭」2024年日本映画ベストテン7位
11/13「第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」1部門ノミネート
11/12「第49回報知映画賞」2部門ノミネート
2024/10/3「第16回TAMA映画賞」特別賞(監督・スタッフ・キャスト一同)・最優秀主演男優賞2部門受賞
✎____________
今年は邦画の当たり年で豊作だった、という声をよく聞きます。
初日に鑑賞して、映画館でリピートした作品が何作もありました。
私の2024年ベスト3候補は、この映画です。
今まで映画.comはほぼ見る専門でしたが、★★★★★の作品には評価とレビューの投稿を最近始めました。
他の方のレビューを読むと自分の語彙力と文才の無さで、好きな映画ほど言葉が見つからなくなります。
✎____________
2024年9月20日・10月17日映画館で鑑賞
10月28日★★★★★評価
12月2日レビュー投稿
12月24日レビュー追記
2025年5月14日レビューP.S.2映画賞追記
自然体
悩んで育った自身の経験を文章にする事で、
自分を客観視する、
その姿勢が自然体だ。
そんな気がした。
美談でもない、
恨みでもない、
僻みでもない、
現実を現実として受け入れ、
そして寄り添うことが、身についている。
それはきっと聾者の両親を持つ五十嵐大の、
差別を受け、両親への不満に悩み、苦しみ
(どうして自分の親だけ、耳が聞こえないんだ!!)
そんな苦悩や怒りを乗り越えた先にある境地、
受け入れること、手伝うこと、
そして時にそれは自分を支えてもくれる。
だから主人公は、聾者の世界に居場所を見つけ、
時に寄り添い、
時に安らぎを見つけ、
障がい者を大きな包容力で受け止める。
「ぼくの生きてる、ふたつの世界」
聾者の世界にも、自分がいる、
健常者の大は、
余計なお世話・・・と、言われることもある。
しかし時には、聾者との橋渡しの役割も果たす。
聾者に出来ること、そして出来ないこと、
そこを補えばいい、
受け入れればいい、
それを主人公は自然に身につけている。
自然に受け入れている。
それは私たちにとっても必要なこと、
人間の一人として、
「お手伝いすることは、ありませんか?」
自然に言える事、
そして支える手を差し出す事、
主人公が苦悩し受け入れた姿がこそが、
「自然体」なのではないでしょうか?
それが「ふたつの世界」をひとつにして、
より豊かにする。
大ちゃんが成長する過程を演じた4人の子役たち、
3ヶ月位の赤ちゃん、
ハイハイ、伝い歩きをする1歳位、
小学生の大ちゃん、
中学生の大ちゃん、
みんな吉沢亮似のイケ面だったね。
5人で演じた事、
そこに真実味が色濃く出ていた。
私の知らない世界
聴覚に障害がある方を描いた内容であることのみの事前確認で鑑賞。
ストーリー的には、両親に聴覚障害があり、その間に生まれた1人息子の誕生から自立までを描いたもの。
自分の人生では関わったことのない内容であったため、こういう大変さがあるんだなと、1つ1つの出来事を見ていた。
全体として雰囲気は重めで、辛いことやうまくいかないことが続いていくような内容。
物語を楽しむというよりは、ドキュメンタリーを視聴するといったような感覚。
主に子供想いの母と思春期の息子に焦点があてて描かれている。常に息子のことを1番に考える母と、まわりからの冷たい視線を感じて不満が積もる息子。息子が社会人になったあたりを境に、徐々に母の愛を実感し、また両親から教えてもらった手話を活かして社会とのつながりを持つようになる。
ハラハラドキドキや考察をするのが楽しいタイプの映画ではないが、聴覚障害の世界とそこに住む家族の愛情をみることができた。
障がいは可哀想ではない
障害者家族における親子関係の脆さと修復のドラマを通じて伝えたかったこと
1 耳の聞こえない両親を持つ子が穏やかな心境に達するまでの軌跡を通じて、社会生活や人間関係のあり方を描く。
2 田舎で耳の聞こえない両親及び健常者だけど伝法な祖父母と暮らす主人公。彼はある日友だちから母の喋り方が普通ではないことを指摘された。彼は恥ずかしいという感情から母
や手話を避け、意思疎通も控えるようになる。そして、一方的な被害者意識を持つてしまい、あてもなく家を出て上京する。そして・・・。
3 主人公は、東京で色んな経験をし、何年も経って故郷に帰省したある日。駅であることを思い出す。それは、上京前日に母と出掛け人前でも自然と手話で会話し笑い会ったこと。そこで彼はようやく気付く。普通に接することがなにより大事だと。
4 本作では、一つの障害者家族の実話を通して、障害者を特別視することのない意識と気付きのみならず、健常者と同じように当たり前に生活できる社会の姿が大事であることが示された。そのための課題として、障害の状態に応じ聾唖教育など適時適切な教育の付与や職務経験や集まりの場など社会から孤立しない取り組みが必要であることも示された。劇中において、主人公の母親が親の無理解から適切な教育を受けられず、置かれてきた境遇は余りにも悲しく、東京で知り合った手話サークルのメンバーは生き生きしていた姿から明らかであった。
5 監督は、重めのテーマを含んだ個別ドラマを説教臭くなることなく、巧みな編集でサラリとまとめあげた。主人公の吉沢は好演。
観に行って良かった!
両親とも耳が聞こえないという青年。 自宅では手話、外では口と耳で会...
両親とも耳が聞こえないという青年。
自宅では手話、外では口と耳で会話。
周囲から特別扱いされることもあり、違和感も抱きつつ、大人になってゆく様子。
母は一途に息子思い、決して𠮟らず応援してばかり。
大人になって、ある時ふっと親の有難さに気づく息子、
静かに丁寧に描かれていました。
時代や地域の特徴も、一目でわかる隙の無さ、
(ゲーム機やブラウン管、語尾けさいん、仕送りに油麩や海藻)
感心しました。
---
忍足亜希子さん(母親役)、だいぶん前に演劇の舞台で観させていただいたことがありました。
"嵐になるまで待って" 2002年、サンシャイン劇場、だったかな…。
その際も、舞台上での手話には圧倒されましたが
変わらないお姿、しみじみ感じます。
耳聞こえない者同士の子供なんてとんでもねえって、じいちゃんとばあちゃんは大反対したの。そんでも明子は産んだの。あんたを。
最後の最後、僕は、母の後ろ姿を見つめながらの大とまさに同じ感情で心がいっぱいになった。障碍を持った両親のもとで生まれ、育てられた大が、どこかひねくれてしまうのも分かる。親ガチャにハズレてしまったようなものだもの。だけど、いつか親の、特に母の深い深い愛情に気づくときがある。見返りを求めない無償の愛に。そしてその時は突然なのだ。幼い頃からいままでのいくつもの母の姿が脳裏に鮮やかによみがえり、それまでの自分の感情や行いがどれほど親を傷つけていたか、そしてそれでも親が自分を愛してくれていたか、ほんと、すべて一瞬で理解し、悟る。だから大は、ああなってしまう。そりゃああなるさ。吉沢亮が、そのほとばしる感情を見事に体現してくれたおかげで、こっちも感情がシンクロできた。
それにもまして、母親役の忍足亜希子の演技が素晴らしかった。聾者であることに甘えず世の中に寄りかかろうとせず、自分のできる生き方を胸張って、恥じることなく、そして朗らかに過ごす人生に、大きな拍手を送りたい。
それから、「仕事っていうのは、実力より高めがくるから。でもね、それはチャンスだから逃げちゃダメ」ってタモリの名言を、俺っていいこと言うだろ?的に得意げに話すユースケ・サンタマリアが憎めない。そのくせあとで、、、いやそれはまあいいか。
コーダの人生
母は強し
■あらすじ
東北の港町、耳の聞こえない両親のもと育てられた五十嵐大。
幼いころから、母親の通訳をし、手話も我流で少しずつ覚える。
しかし、成長するとともに、周りから特別視されることに違和感、戸惑い、
苛立ちを感じる。そして反抗期を迎え、母親の明るさすら、
うっとおしいと感じるようになる。
二十歳のときに逃げるように上京、一人暮らしを始めるが・・・
■レビュー
母親の強さ、愛情の深さに、感動。
思春期の反抗的な息子の態度であれ、すべてを受け止める。
そして息子を信じ、寄り添う。
20万円もする補聴器を買ったのも「大ちゃんの声が聴ける」って。。。
いや、聞こえてないじゃん!と笑いたくなった。
父親も息子の上京に背中を押すところに感動。
母親とのなれそめ、駆け落ちエピソードを話す姿は、
男同士ならではか。
ばくち打ちの祖父、そして毎日お経を唱える祖母にとっては、
孫の大が唯一の話し相手だったのかもしれない。。。
ラストの母親との電車のシーン、そして電車を降りたホームで母親から
「手話で話してくれてありがとう」という言葉に大が泣き崩れたシーンは
ぐっときた。
主人公の大を演じた吉沢亮さんも素晴らしかったが、
母親役の忍足亜希子さんの素敵な笑顔、前向きな姿勢に感動。
現実
私の両親は健常者だ。
だから、この主人公や原作者の気持ちを本当に理解することはできない。
私には想像だにできない多様な困難や苦悩があったことだろう。
でも、だからと言って、それをだらだらと垂れ流されてシンパシーを感じるほど、
私は善良ではない。
現実を離れてフィクションの世界を堪能したいのに、
ダメ息子を想起させられるシーンを延々と見せつけられる。
ウンザリだよ。
健常者だって多かれ少なかれ苦悩し乗り越えようともがいている。
そんなものは見せていただかなくても十分認識している。
障害者の子供だから許されると甘い気持ちなら止めてもらいたい。
一方で、障害の有無に関わらず、親の気持ちは痛いほど分かる。
そんなちっぽけなことでも嬉しいんだよね、と目頭が熱くなった。
とにかく前半で暗澹たる気持ちになってしまった。
ラスト近くでほんの少し盛り返したが、遅きに失した。
咽び泣くところでした。
まず驚いたのは、
子役の子が吉沢亮さんの子ども時代か
と思わせる顔のシンクロ率のおかげで
五十嵐大と言うキャラクターの人生を
隣でちゃんと観てたような気になれました。
そのおかげでラスト前の
コーダとして生まれた事で逆に
耳が聞こえる両親から生まれた子より
たくさんはは親と喋ってたんだなと思わせる所で
危うく映画館で咽び泣くところでした。
ろうの両親の子供として生まれた映画に
「コーダ あいのうた」や「エール!」があって
耳が聞こえない両親の対比で歌手になる夢と言う設定を
用いたと思うのだけど、
耳が聞こえると聞こえない人生だけでもう対比は充分に
成り立っているから、
大ちゃんはこんな両親の子に生まれたくなかったと言うけど、人生においては両親やろうの方と接してる時の方が穏やかで生き生きしてるように思えました。
中学時代から30代までを演じた吉沢亮さんは素晴らしいし、出て来ただけで華があるな!と思ったけど、
あの子役の子が吉沢さんの子ども時代を演じた事が
この作品の解像度をスゴくあげてくれたように思いました。
多くの人に觀てほしい映画
親子の関係が真に迫っていた
冒頭の3分くらいで、
これは覚悟して見ないと駄目だと思い、身を乗り出して鑑賞しました。
モノローグとか、テロップとか安直に説明を始めていく最近の日本映画だらけの中で、どんどん話を進めて観客を引き込んで行く演出に感服です。
吉沢くんも良かったですけど、わたしは両親の2人、特にお母さん役の忍足さんの演技に感動しました。補聴器買って喜んだり、吉沢くんと時には衝突したり、それでも笑顔で前向きで楽しそうなお母さん、なんと言えばいいのかわかりませんが「強い」でいいのか、とても良かったです。
最後、三浦友和さんの辺りから、パスタ、ローカル線、駅、サイレント、このあたりの10分くらい、泣かすような演出ではないのですが落涙しておりました。わたしの場合、母はわたしが22の時に死んでしまったので、吉沢くんと忍足さんのような、2人で外食した記憶がありません。楽しそうな食事シーン、メニューの選び方から羨ましくなりました。
作品では、もちろん、障害がある方々の生き方や健常者との関わり方なども大きなテーマになっています。でも、わたしとしては「家族みんなの愛」の方に感動しました。
今年のベストワンでいいんじゃないですか?。呉監督の作品は全部観てますけど、「そこのみにて」より好きです。
でも、吉沢くん、8年も帰らないのは、気持ちはわかるけどそりゃないよ。
でんでん、久々に怖かった。迫力満点、もんもんはリアルすぎる。
5人で飲むシーン、出来ることを助けてはいけないは、リアル社会では難しいと再認識。
いいストーリーだけどもったいない!
ようやく観る事ができた作品。
コーダがテーマだが、色々考えさせられた。よくできた作品。
ただ、脚本やテーマはもう少しコーダにスポットライトをあてても良かった。
大の成長記かと思うところもあった。
せっかく吉沢亮を起用しただけにもったいなさも感じる。
いい作品、テーマだけにもったいない。
全200件中、41~60件目を表示