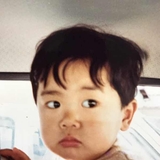ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全200件中、1~20件目を表示
コーダあいのうたのリアル版
最後の駅のホームのシーンに、心を全部もっていかれた。あのラストシーンの吉沢亮を見れただけでも、この作品の価値はある。あのシーンにこの作品のメッセージが全て込められていたように思えた。
コーダといえば、米国のアカデミー作品賞を受賞した『コーダあいのうた』が思い浮かぶ人が多いと思うが、あのリアル版という感じ。この作品は主人公である五十嵐大さんのエッセイが元になっている作品なので、フィクションの『コーダあいのうた』と比べて、よりコーダの葛藤や苦しみが描かれている。それと同時に、聾唖者の方々は私たちが思う以上に自由で、自立をしていて、特別視しなければならない存在では無いことも描かれていた。
それにしても、吉沢亮が良すぎた。
あんなに綺麗な顔をしているのに、吉沢亮はダサかったり、気弱だったり、不器用な役を演じるとすごく光るように思う。今回の役は服装も髪型もダサすぎて、それが逆にめちゃくちゃ良かった。PICUのドラマの時も思ったけれど、どこにでもいる普通の人に溶け込むのが上手い役者さんだなと改めて思った。
「私たちのできることを奪わないで」
ろう者の当事者を多数起用した上で、手話演出の専門家とコーダ監修をつけた上で、ろう者のリアリティにこだわって制作されている本作。そのリアリティがあるからこそ、ろう者と聴者の狭間を生きるコーダのリアルが深く映像に刻まれている。耳が聞こえない時にどういう生活になるのか、その生活の実態がさりげなくちりばめられているのが良い。キッチンで鍋が吹いていることに気づかなかったり、赤ん坊の泣き声が聞こえなかったり。それらが大事件に発展することはないのだが、細かい苦労の積み重ねを日々、強いられることがよくわかる。その中で、ろう者の両親に育てられた聴者の主人公が、他者とは違う家庭で育ったことに葛藤する。アメリカ映画『コーダ あいのうた』では家族を離れるところまでが描かれるが、本作はその後も描かれる。上京してから初めてコーダという概念を知り、家族を見つめなおし、自身の進むべき道を考えるようになる。
二つの世界の狭間で生きるコーダの苦しみは何なのか、『コーダ あいのうた』と比較してもより深く迫っていたのではないか。なまじろう者の世界を知っているが故に、助けようと思って「私たちのできることを奪わないで」と諭されるシーンなど、重要なシチュエーションだと思う。
徹底したリアルな映像世界は、さすが呉美保監督。今年を代表する邦画だと思う。
普遍的な家族の愛の物語
耳のきこえない両親のもとで育った息子の話、という本作の設定を最初に知ったとき、2021年米製作の傑作リメイク「コーダ あいのうた」(オリジナルは2014年の仏映画「エール!」)の主人公を男性に変更してアレンジした日本版リメイクかと早とちりしたが、正しくは作家・五十嵐大による自伝的エッセイを原作にしたオリジナル映画。とはいえ、「コーダ」(CODAはChildren of Deaf Adults=“耳の聴こえない大人に育てられた子”の意味)が主人公の家族役に実際に聴覚障害のある俳優たちを起用し高評価された流れを受けて、この「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の企画が実現したのは呉美保監督も明かしている通り。また、「コーダ」の主人公が夢の実現のため家族と離れて一人立ちするところで終わっていたので、主人公・大(吉沢亮)が単身上京してからの物語が後半で大きなウェイトを占める「ぼくが生きてる、ふたつの世界」は、本質的な部分で「コーダ」と連続性があるようにも感じられる。
両親に反発するように家を出た大は、紆余曲折を経て編集プロダクションに就職し、やがてライターとして文章を書くように。事件・事故などの出来事の断片的な情報を集めて一本の記事にする行為は、出来事の推移と当事者らの関連性を俯瞰し、客観的にとらえ直すということ。東京でのさまざまな出会いと経験に加え、物事を客観的にとらえる力を培った大が、家族との関係を見つめ直すことができたのも自然な流れだっただろう。
思春期の大に反抗的な態度や非難の言葉をぶつけられても、悲しみをぐっとこらえて天真爛漫な笑みを絶やさず息子に愛情を注ぎ続ける母・明子に、観客の多くは理想の母親像を見るはず。演じた忍足亜希子は文句なしに素晴らしく(本年公開作が対象の映画賞で助演女優賞の受賞にも期待がかかる)、ろう者の親と健常者の子の話に限定させず普遍的な家族の愛の物語に昇華させた脚本・港岳彦の貢献も大きい。安易に“泣ける映画”という言葉を使いたくないが、この「ふたつの世界」には本当に泣かされた。
あるがままと達観が情緒を振り払う日本版『コーダ』の魅力
フランス映画をハリウッドがリメイクしてアカデミー賞に輝いた『コーダ あいのうた』('21年)があったように、日本にも2万人以上いると言われるろうの両親のもとに生まれた子供にフォーカスした本作。そして、『コーダ~』がそうだったように、ここに登場する親たちの自然体と、音のない世界とある世界の狭間で揺れる子供の葛藤が観る側にも伝わって、何があろうと決して深刻ぶらず、あるがままを受け入れて生きる強さに心が震えてしまう。情緒に傾き過ぎない演出と演技にも助けられた。
ろう者の登場人物はすべてろう者に演じさせたことも成功の要因だろう。特に、『コーダ~』でもそうだったが破天荒でいて物事を達観視し、息子を心から信じている父親のキャラクターが魅力的だ。でも、与えられた境遇に疑問を持ち、やがて受け入れていく息子を演じる吉沢亮の計算し尽くされた変容の演技に感心する。
人は誰でも過去を振り返って気づかなかったことに感謝して、そこからまた前を向き、新たな一歩を歩み出す。取りこぼしが多い人にも希望を与えてくれる映画だ。
人は誰しもいくつかの世界を行き来して生きているのではないか
きこえない母と、きこえる息子が織りなす親子の物語であり、“きこえる世界”と“きこえない世界”を行き来する、ひとりのコーダ(きこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子供)の心の葛藤と成長を描いて、普遍的な家族の愛の物語へ昇華させています。
人は誰しもいくつかの世界を行き来して生きているのではないでしょうか。本作は“きこえる世界”と“きこえない世界”を描いていますが、無意識の差別を引き起こす、国や民族、出自や身分、言語や肌の色が違う世界、さらには他の社会的マイノリティの世界と置き換えて見ることもできます。
そして、自身の親しい人を思い出し、その人への後悔や懐かしい記憶が重なると、自分の物語として心に響いてくる作品です。
展開が早過ぎて残念
もっと関心を持たねば
バイト先で近くにあった映画館でちょうどいい時間帯にやってて、主演が吉沢亮君ということで、観に行った。
耳の聞こえない両親から産まれた、耳の聞こえる子を「コーダ」というそうで、日本には2万人以上いると言っていた。
宮城県塩釜市で、コーダとして産まれてきた五十嵐大君は、幼少期は両親と手話で話をするのが当然として育ったが、小学生のころから違和感を感じるようになり、高校生くらいで機嫌の悪い時に「俺は両親とも耳が聞こえない家になんか産まれたくなかった」と言ってしまい、20歳になって東京で一人暮らしを始める。しかし精一杯大君に愛情を注いできた両親の愛に気づいていく。コーダとして産まれてきた人たち特有の気持ちや、耳の聞こえない人たちにはまだまだ暮らしにくいところも多々あり、自分にもできることがあると感じた。
自分(59歳)は健常な両親から産まれてきたが、やっぱり20歳過ぎで荒れて両親にひどいことを言った経験があり、両親は既に死んでしまったが今は謝りたい気持ちでいっぱいで、この映画をみてその感情が沸き起こった。
吉沢亮君が、小さな映画にも社会的意義があれば出ていて、感心した。
吉沢亮が出ていなかったら、観なかっただろう。
とりあえず原作本をアマゾンで注文した。
デフリンピックも見てみようかな
映画のゴールがわからなかった
意味も分からず泣いてしまった。
映画のゴールはどこだったんだろう。全体的に大きな盛り上がりというのは感じなかった。
でも伝えたいものがすごく大きかった作品だと思った。
こういった両親に障害がある家庭は実際にたくさんあると思う。
苦労してきたのも分かる。つらい。
隠したくなる気持ちもわかる。お年頃だととくに。つらい。
すごくリアルに描かれていたと思う。
手話って穏やかにゆっくりしゃべるイメージだった。(ニュースのはじっこでやってる手話くらいしか、あまり自分とはかかわりがなかった。)
すごく感情的な、激しい表情を交えた手話があるんだと思った。
手話にも早口とかもあるんだと知った。
手話に方言もあるんだと知った。
一番印象に残ったシーンは耳の聞こえない人の手助けをしたつもりが、「私たちの仕事を奪わないで」だった。良かれと思って手伝っても、生きる権利を奪ってしまっているようになってしまう。その人が、やりたい、できる、を奪ってはいけない。
助けを求めてきたら、その時は手伝ったらいいのだ。知らなかったし勉強になった。
カレーおいしくないんか~い。そのへんもリアルだったなあ。
お父さんがいい人で良かった。子供が親に悪態をつくことっていっぱいあると思う。
お母さんが泣いたとして、傷ついたとして、そこでお父さんが感情的に怒鳴り散らすタイプだったらこの子はもう出て行って戻らなかったと思う。
ちゃんと落ち着いて息子と話ができる人で良かった。
お父さん、お母さんも聞こえないことでつらい経験をたくさん乗り越えてきたと思う。だからこそ、生まれたやさしさなんだと思う。
おそらく自分はこの映画の半分も理解はしていないと思う。
でもなんだかもう1回見たいと思う映画。
よくわからないけど涙が止まらなくなる映画。
ひとりで生きていく強さ
手話にも方言がある
聴覚障害者は、日本では約34万人いるとされています。劇中でも語られていましたが、2万人余のCODAがいるとのこと。大の母親はろう学校に行かず、普通の学校に行っていたとのことだけど、現在でも大勢いるみたいです。知らなかった・・・
『コーダ あいのうた』、『エール!』のようなドラマチックな内容ではなく、セミドキュメンタリーのような大の成長物語を描いた内容には好感が持てます。好きという手話だけ覚えました。聴覚障害者の家族が普通だと思っていた大の心境が揺れ動いて、家を飛び出したくなる気持ちも伝わってくるし、東京に出てからの就職の苦労。それと同時に手話サークルに参加することで家族のことを忘れない気持ちも良かった。
私事ですが、タクシーのお客様にもろうあ者がいます。行先をスマホで提示してくれたり、紙に書いてくれたりと様々ですが、道を間違えようものなら肩を叩いてくれたりします。喋らなくてもいいので楽でもあります。最も怖いのが車の音に気づかないことでしょうね。
映画を観ていて、手話を使えることで得することもあるんだな~などと不謹慎にも感じてしまいました。大音量で音楽が流れているお店や電車の中。ちょっと微笑ましい光景でした。今ではスマホという便利なツールがあるので、親子関係を疎かにすることもないでしょうけど、劇中では手紙もいい感じで使われてました。あと、カレーには味噌を入れないように・・・
⭐︎4.2 / 5.0
ある家族のお話
涙が溢れた
久しぶりに泣けた・・・(膝の上に座ってた猫が驚いてたw)
一年前に観そびれてたこの映画、WOWOWで録って観たんですが…
すごくいい映画ですね。
作家 五十嵐大本人の話で、両親がろうあ者の元に生まれて、愛情いっぱいに育てられるんだけど、田舎の閉塞感もあって思春期に親に反発するようになり、卒業後東京へ。
都会で苦労するうちに人の愛に気づく。
ろうあサークルに入っての関わりもいいですね。
自分は何者なのか?って、結局他者と関わらないとわからないもんです。
両親、特に母親がいつも明るく、優しく、可愛い…
どんなに息子に疎まれても、包み込む…
義両親と同居で大変だろうに。
この映画はとにかく、主人公の自分探しの物語であると同時に、親子関係の原点みたいなものに気づかされる。
私自身も、これを観ると、嫌でも親の顔が浮かんできて、おじいちゃんおばあちゃんの顔が浮かんできて… あぁ、面倒くさいこともあるけど、こんなだったなぁ…と、少し胸が苦しくなるのです。
そしてとにかく、この映画のテーマがギュッと凝縮されてるシーンが、ラスト近くの駅のホーム。
ここで涙腺崩壊でした。
こんないい映画だったのか。ちゃんと映画館で観ればよかった。 でも、きっと今の私にタイミング測ってやってきたのかな。
吉沢亮唸るほど上手いし、男前の華を封印して、すごく等身大の悩める青年を演じてます。上司のユースケサンタマリアも大らかでなんかいいし。ろうあの両親も友達も、実際に障がい者の方が演じているのも見どころかも。やっぱり大変リアルです。
母の愛情に溢れてる
パフェ
難しいテーマではあるが、バランスが取れており、 映画としてクオリテ...
優しい名作
私は昔、数年間手話を習っていたことがある。教えてくれた人は先天性難聴のかたで、とても丁寧にいろんな言葉を教えてくれた。そのおかげで、日常会話程度は話せるので仕事などで手話対応する場面があるとととても喜んでもらえる。
前に、日本のドラマである俳優さんたちが手話を使って会話するというシーンがあったが、あまりにも手話がひどくてちゃうちゃう!!ちゃんと勉強しろや!!と怒りを感じたことがあった。手話を題材とした映画やドラマに関してはシビアに見てしまいがちなので、この映画上映中は観に行かなかった。
結果、この映画は残念シーンは皆無。吉沢亮さんの作品は恥ずかしながら一度も観たことがなかった(というか邦画をほとんど見ないもので…)が、とても自然でめっちゃ勉強したんやろうなと尊敬した。吉沢さんがたくさんの人に支持される理由がわかった。
肝心の内容やけど、日本版コーダという感じ。都内だと多様性という言葉はだいぶ浸透しているが、地方の方だとこういった差別は確かにあるやろうなと。反抗期あるあるのあなたの子どもに生まれなければよかったという言葉は健聴の親にとってもショックな一言だが、自分のせいで負担をかけていると認識しているお母さんにとっては特に残酷なひと言やなと胸が苦しくなる。いいから東京に行け!とそっと背中を押してくれる父もいい人やし、東京に行ってから両親のあたたかさに気がつく大ちゃんもまたいい子。
吉沢亮をはじめとする俳優の魅力と、ストーリーともに光ってました。優しい名作やと思います。
⭐︎余談⭐︎
手話習う人が個人的には増えてくれるといいなと思うが、手話には派閥みたいなものが存在し、先天性難聴か中途難聴かでもだいぶ表現や認識が違う。また、言語というのは時代により移り変わるものなので、高齢者と若者では手話表現が異なるケースもある。
教えてくれる先生が代わり、使う手話表現が古かったり、手話歌は差別的だ!など価値観の主張が強く違和感を感じて途中で学ぶのをやめてしまった💦(最初に教えてくれた先生は手話歌大好きだった。)
映画の中でも出てきたライトな手話サークルがもう少し増えれば、学ぶ人も増えるんちゃうかな?
75点
映画評価:75点
コーダという単語を初めて知りました。
この主人公の成長と葛藤がしっかりと伝わる
素晴らしい作品でした。
でも正直言うと、この主人公の気持ちなんて
どうでもいいです。
別にコーダの人じゃなくたって、
誰だって、何かしらの悩みがあって、
試練があって、むしろ当たり前です。
何の障害もなく、周りから特段迷惑をかけられてもいない、何不自由なく生きて見える私ですら
常に様々な世界を行き来しています。
そこに同情する余地はありません。
ですが、この作品の本当の魅力はそこではなく
母親の無償の愛にありました。
小さかった頃の思い出をひとつひとつ
当時の自分を見つめる母父の顔と、爺婆の顔を
思い出しながら涙が流れてきました。
たくさんの人からの、
たくさんの思いやりによって
今の自分がある事を、
改めて感じる事ができました。
それに気がつけた1人の青年の涙が
この作品を全て物語ってくれました。
今までと、これからの出会いに感謝します。
【2025.6.14観賞】
全200件中、1~20件目を表示