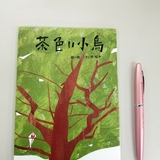「手話にも方言がある」ぼくが生きてる、ふたつの世界 kossyさんの映画レビュー(感想・評価)
手話にも方言がある
聴覚障害者は、日本では約34万人いるとされています。劇中でも語られていましたが、2万人余のCODAがいるとのこと。大の母親はろう学校に行かず、普通の学校に行っていたとのことだけど、現在でも大勢いるみたいです。知らなかった・・・
『コーダ あいのうた』、『エール!』のようなドラマチックな内容ではなく、セミドキュメンタリーのような大の成長物語を描いた内容には好感が持てます。好きという手話だけ覚えました。聴覚障害者の家族が普通だと思っていた大の心境が揺れ動いて、家を飛び出したくなる気持ちも伝わってくるし、東京に出てからの就職の苦労。それと同時に手話サークルに参加することで家族のことを忘れない気持ちも良かった。
私事ですが、タクシーのお客様にもろうあ者がいます。行先をスマホで提示してくれたり、紙に書いてくれたりと様々ですが、道を間違えようものなら肩を叩いてくれたりします。喋らなくてもいいので楽でもあります。最も怖いのが車の音に気づかないことでしょうね。
映画を観ていて、手話を使えることで得することもあるんだな~などと不謹慎にも感じてしまいました。大音量で音楽が流れているお店や電車の中。ちょっと微笑ましい光景でした。今ではスマホという便利なツールがあるので、親子関係を疎かにすることもないでしょうけど、劇中では手紙もいい感じで使われてました。あと、カレーには味噌を入れないように・・・
kossyさま
共感ありがとうございます🙂
『僕が生きてる〜』のエンディングソング「letters」を歌っている下川恭平さんは、映画にもレストランのウェイター役で出演しています。
呉美保監督は、エンディングソングを敢えて英語にした理由を説明しています。
母親が息子の五十嵐大に宛てた劇中の「手紙」を、聾者も聴者も字幕の文章で読んでほしかったからだそうです。
ちなみに下川恭平さんは、『国宝』の冒頭の長崎の宴会で、黒川想矢くんの喜久雄と一緒に歌舞伎を舞っていた、幼馴染の徳次の役でも出演しています🫡
最近見たこの監督の子どもの映画でも、とびぬけた才能があるわけでもない普通の子どもだが、自己肯定感が高い子が出てきました。この映画の大も、失敗しても腐らないどこでもやっていけそうな自己肯定感の高さがありました。二人とも愛されて育っているが故だな、と思いました。
共感ありがとうございます。
ろう者への向き合い方が自然で、これはそれが当たり前に育ってきた健常者の息子を主人公にした最大の効果だったと思います。
この監督の子どもの映画を最近観ましたが、そっちの方が作り込んでる感じを受けました。