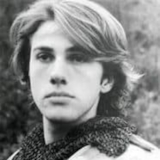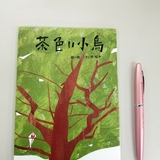「私たちが生きていくふたつの世界は、きっと素敵だ」ぼくが生きてる、ふたつの世界 近大さんの映画レビュー(感想・評価)
私たちが生きていくふたつの世界は、きっと素敵だ
耳の聞こえない両親の元に生まれた子供。“コーダ”。
アカデミー作品賞を受賞したあのハートフル感動作が有名だが、本作はその日本版と言うべきか。
日本リメイクではない。原作者の自伝的エッセイの映画化。題材は同じだが、アプローチも違う。
『コーダ あいのうた』は聾唖の両親の元に生まれた娘の人生の岐路と家族の絆。
本作は子供の誕生から成長、家族との関係や葛藤、主に息子と母親の心の機微、双方を通してより繊細に“ふたつの世界”を描いていく。
共に耳が聞こえない陽介と明子。二人の間に、待望の子供が誕生。
大と名付けられ、無事耳も聞こえる。喜びや幸せに包まれるが、ここからが大変。
明子の両親も一緒に暮らしているが、耳が聞こえない二人に子育ては苦労の連続。
赤ん坊が泣いていても気付かない。ちょっと内職に専念し側で何かを倒しても気付かない。大事には至らなかったが、もしも…だったら?
愛情は人一倍。それを一身に受け、大は成長。まだ幼い頃から手話を身に付け、それで両親と会話したり、時には周囲との通訳になったり。
それが当たり前で、仲も睦まじかった。
小学校に上がった頃から。家に遊びに来た友達から耳が聞こえない母親や上手く喋れない事を“ヘン”と言われる。手話も物珍しい。
次第に周囲の“普通”の家族とのギャップを感じ始め、授業参観なども知らせず。
高校生ともなると手話で会話する事すら煩わしくなった。母親にも素っ気ない態度。
20歳になるとそんな両親や退屈な地元から逃げるように、東京へ。
本を読む事や物を書く事が割りと好きだった事から、出版社へ面接。一流どころは何処も落ちる。
下世話記事などを扱う小さな会社へ面接。複雑な家庭環境話が気に入られ、いきなり採用。
いい加減な感じの編集長から金言。実力より高い仕事が来たらチャンス。逃げるな。…と思ったら、タモリの受け売りかよ。
仕事は忙殺ながら、徐々にその世界の色に染まっていく。
時に耳を塞ぎたくなる事も。これが“聞こえる世界”としたら…
まだパチンコ店でバイトしてた時、たまたま耳の聞こえない客と知り合う。
それがきっかけで聾唖者の集いに参加。交流を持つ。
聾唖の両親や手話が嫌で東京に出てきたのに、数奇な縁。
交流を通して改めて…いや、初めて知らされる事も。
地元では通訳を介さなければ生活もコミュニケーションも難しかった。しかしここでは、聾唖者であっても自由に自分の人生を生き、社会の中で暮らしている。不便な事もあるだろうが、それを苦や恥とはしていない。
会食時、気を遣って注文役をしたが、私たち自身で出来る事を奪わないで、と。
勝手に聾唖者を不器用、何も出来ないと思い込んでいた。
そのポジティブな姿に教えられる。寧ろ自分の方こそネガティブだった。
こちらが“聞こえない世界”。不思議と心地よさや居心地の良さを感じる。
“聞こえる世界”と“聞こえない世界”。
確かに双方に、偏見や生きづらさはある。
が、違いは無いのだ。
幸せ、喜び、悩み、葛藤…。各々持ちながら、周りと触れ合いながら、一人一人が自分の人生を生きている。
ふたつの世界を生きる事は、多くの他の人には無い、特別な事かもしれない。
いい事も嫌な事も含めて。
そして感じるのだ。
改めて知らされる。無償の温もりを。
父が倒れ、8年ぶりに帰郷する。
命に別状はナシ。祖母によると、母は今まで上げた事のない声を上げて狼狽したという。
母は今は落ち着いて、あの頃と変わらず迎えてくれる。
一時ぎくしゃくしたけど、母と自然なやり取りを。
変わった?…と聞かれる。
変わったんじゃない。気付いたんだ。
帰れる場所がある事。迎え入れてくれる人がいる事を。
聾唖のキャストを起用したり、聾唖や手話に通じたスタッフを配したり、リアルに拘ったという“聞こえない世界”。
劇伴を廃し、周囲の雑踏や自然音に溢れた“聞こえる世界”。
丁寧に紡ぎ上げていく。
もっとドラマチックな作りにも出来たかもしれない。大が聾唖グループの人と恋に落ちたりとか。
気になる余白の部分もある。知り合った聾唖女性から私の話を書いてと言われ、大は書いたのか。
『コーダ あいのうた』のようにもっと泣ける大衆向けにも出来た。
しかし、そういった安易な作りにはせず。静かでドラマチックな大きな展開は無いが、引き込まれる。尺は100分ちょっと。もっと長くこの作品に浸っていたかった。氾濫する無駄に長い作品なんかより、こういう作品こそ120分やそれ以上あっていい。
長編映画は9年ぶりになるという呉美保監督だが、その確かな演出は変わらず。シリアスな作品も多いが、最も温かく、優しい。
『コーダ あいのうた』がアカデミーで好かれたのなら、本作だってそのレベルにある。勿論、日本のではなくアメリカの。一切無視した日本バカデミーに価値は無い。
吉沢亮の好演。幼少期や少年期を演じ、見事な手話も披露した子役たちも。
出番は多くないが圧倒的存在感のでんでん。タモリの金言受け売りのユースケ・サンタマリアなども印象的。
やはり聾唖のキャストの好演光る。
パチンコ店で知り合った中年女性、聾唖グループで知り合った若い女性。その温かい輪。
『コーダ あいのうた』のトロイ・コッツァーほどではないが、人柄溢れ出す父親役の今井彰人。東京に行きたいと言った時、全面的に応援。三浦友和よりカッコいい。
大金星は、忍足亜希子。彼女から滲み出るは、聾唖者の悲喜こもごもより、母親の優しさや温もり。
誰もが愛情溢れる母親の姿に魅せられ、自身の母親と重ね、思い出すだろう。
私の母が亡くなってもう10年経つ。ちと世間知らずで不器用な母だったが、一緒に映画を観に行ったり、外食したり、思い出すのは良き思い出ばかり。
演じた母親像や姿に、在りし日の母を思い出させてくれた忍足亜希子の名演。
キネ旬助演女優賞受賞。妥当で当然の受賞。時々異論もあるキネ旬だが、こういう所をきちんと評価するのは信頼に値する。一切無視した日本バカデミーには本当に呆れ果てる。今後も存続していく必要性、あるのか…?
大は東京へ戻る。
駅のホームで思い出すは、東京に出る直前の事。
母に伝えたら、驚かれたが、一緒に必要なものを買いに。
喫茶で軽食。父親から聞いた駆け落ちエピソードに赤面し、その時食べたパフェ。
電車の中でも自然と手話での会話続く。
何故あの時は、あんなに自然体でいられたのだろう。
それに気付くまで、ちょっと遠回りした。
昔からそこに居てくれた。
あの温和な笑顔、優しさ、美しさ…。
変わらず、ずっと。
それに涙する。
それらを胸に、ぼくはまた生きていく。
私たちも生きていく。
聞こえる世界と聞こえない世界。
ふたつの世界で。
それはきっと、素敵だ。
近大さん
コメントへの返信を頂き有難うございます。
親の思い、子の思い、祖父母の思い、聾である故の様々な事、家族ならではの温かな眼差し、多くの思春期の若者達にも是非観て頂きたい作品ですよね。
鑑賞後、原作者の五十嵐大さんが書かれた「 しくじり家族 」を図書館で借りて読んだのですが、本作同様、生き生きと率直に綴られた文体が好印象を残す作品でした。
そうだ、そうでした❗️
今作もだし、
2024マイベスト「ぼくのお日さま」、
2024一番泣いた「アイミタガイ」も、
日本アカンでミーはスルーでしたね❗️
今更ながら腹立ってきました🤣
近大さま、初めまして。
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』『ファーストキス』『侍タイムスリッパー』『夜明けのすべて』に共感ありがとうございます。フォローバックもありがとうございました。
五十嵐大ちゃん(吉沢亮さん)のバイト先が、『侍タイ』主演の山口馬木也さんのマネージャーのお兄さんのお店で、マネさんもエキストラ出演されていました。「侍タイファミリー」からも、『ぼくが生きてる〜』を是非観てとオススメが拡がっています。
キマ旬表彰式に出席しましたが、忍足亜希子さんは和装もステキで、スピーチの吉沢亮さんへのメッセージに感動しました。呉美保監督が花束贈呈、吉沢亮さんは登壇できない事情があり、本人も残念だったと思います。客席後方にいた共演俳優さん達が、手話の拍手で手をひらひらさせると、会場全体もひらひらの拍手になりました。
キネ旬は選考過程の透明度が高く、表彰式は完全生中継でスピーチに時間制限が無く、アーカイブを期間限定でなく配信するところなど、日本アカデミー賞に見習ってほしいです。
※初コメントで長文失礼しました。
近大さん
本作、邦画の素晴らしさに改めて気付かされるほどに、温かな余韻の残る作品でした。
青年が抱えたモヤモヤとした心情を丁寧に演じた吉沢亮さん、他キャストの皆さんも個性豊かにそれぞれ魅力的で、色々と大変な事もあるけど、人生って案外捨てたもんじゃない、そんな原作者の思いに溢れた素敵な作品でしたね。