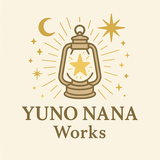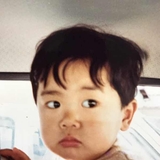ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全269件中、1~20件目を表示
コーダあいのうたのリアル版
最後の駅のホームのシーンに、心を全部もっていかれた。あのラストシーンの吉沢亮を見れただけでも、この作品の価値はある。あのシーンにこの作品のメッセージが全て込められていたように思えた。
コーダといえば、米国のアカデミー作品賞を受賞した『コーダあいのうた』が思い浮かぶ人が多いと思うが、あのリアル版という感じ。この作品は主人公である五十嵐大さんのエッセイが元になっている作品なので、フィクションの『コーダあいのうた』と比べて、よりコーダの葛藤や苦しみが描かれている。それと同時に、聾唖者の方々は私たちが思う以上に自由で、自立をしていて、特別視しなければならない存在では無いことも描かれていた。
それにしても、吉沢亮が良すぎた。
あんなに綺麗な顔をしているのに、吉沢亮はダサかったり、気弱だったり、不器用な役を演じるとすごく光るように思う。今回の役は服装も髪型もダサすぎて、それが逆にめちゃくちゃ良かった。PICUのドラマの時も思ったけれど、どこにでもいる普通の人に溶け込むのが上手い役者さんだなと改めて思った。
コーダとして生まれた主人公の苦悩とそこにある普遍的な愛の物語
本作品は、作家・エッセイストの五十嵐大による自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」を実写化した映画です。吉沢亮さんが主演を務め、中学から青年までの主人公を繊細かつ力強く演じています。吉沢さんの子役の見上げる仕草が、吉沢亮さんそのものだったので、演出が細かくて素晴らしいなぁと思いました。
この映画で描かれているのは、コーダ(耳のきこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子ども)というマイノリティな生い立ちの主人公五十嵐が、苦悩しながらも成長していく姿です。その環境は少し特殊なものであったかもしれませんが、その本筋に流れるものは、とても普遍的で誰にでも共感できる家族の愛の物語です。
私の号泣ポイントは
息子五十嵐が、「今までごめん」と母に言った時に、「え?なにが?」みたいにとぼけたシーン
おい、世の中の息子ども
母の愛❤️舐めんなよ!!
障害があろうがなかろうが、あなたを産むって決めた時から、こっちは腹括ってんのよ。あなたの思春期のかわいらしい反抗なんて、ほんのジャブにもならんのよ。
また、
電車で母と息子が仲良く手話ではしゃいでいる場面からの
母が息子に「手話で話してくれてありがとう」みたいなシーン。
そうそう!!そういう何気なく普通に成長した息子とはしゃげる瞬間って、母の夢よね。たまらんね。
子どもが「申し訳ない」と思っているほど、親はなんとも思ってないとか、子どもが幸せだと感じたパフェのことを母は覚えてなかったりするのとか、「あるあるだなぁ〜」って、深く共感しました。
こちらのレビューは、絶賛母目線で書かせていただいておりますが、もっと遡れば、生まれた家が何故か自分には窮屈で19歳で家をでた自分の姿にも重なり子ども目線でも涙でちゃう本作品、もうほんとにやばいです…😭
子を持つ親御様方、思春期のお子さんたちも、おばあちゃんおじいちゃんも、どうぞ厚めのハンカチをご用意してご鑑賞下さい。
それぞれ違った悩みがある、それはどの家族も同じ
ろう者の両親を持つコーダの主人公、大の人生の描写は赤ん坊の頃から始まる。
原作者の五十嵐大氏は1983年、宮城県生まれ。両親から愛される素直な子供だった大が、年頃になり「普通でない」両親を嫌悪するに至る過程が丁寧に描かれる。
市場の鮮魚屋で初めて母の「通訳」をして店の人に褒められて以来、誰が強制したわけでもないが自然と、両親と健聴者の通訳が彼の役目になっていったのだろう。相手から褒められ、両親の助けにもなることで幼い大は単純に嬉しかったかもしれないが、その役目が固定化され当然のものとなったまま思春期を迎えると、だんだん両親が疎ましくなった。
一見「普通でない」家庭の、世間的にはマイナーな苦悩の物語のように見える。確かに、大が家庭の内外で苦悩する理由は、コーダ独特のものだ。
だが、彼が母親に対して抱く嫌悪感は、誤解を恐れず言えば、どこか私自身の思春期の感情にもかすかに重なる部分があった。コーダ独特の悩みの中に、誰もが通過する反抗期に共通する感情も透けて見える。だから、全く違う境遇なのにどこか不思議な共感を覚えた。
彼の両親が一貫しておだやかな愛情を我が子に注いでいることは、節々のさりげない描写から伝わってくる。大が自分のフラストレーションを母親にぶつけることができたのも、本人は意識せずとも、母親の愛情への信頼が根底にあったからだろうという気がした。
彼らの物語を見て、ろう者を両親に持つ人は「普通の人」より特殊で大変だな、とか、ましてやかわいそうだなどという気持ちにはならなかった。
海沿いの道で、父親の陽介が母の明子に伝えた言葉の通りなのだ。
「まあでも、どんな家も、それぞれ悩みがあると思うよ。多分ね」
それぞれの家庭で、家族の悩みは千差万別。そういう意味では、「普通の」家庭の定義などないし、裏返せば五十嵐家もそのバリエーションの中のひとつの形に過ぎない(彼らの苦労を軽視する意味合いでは決してない)。家族の在り方そのものよりも、彼らと接する周囲の人々がそのような理解で受け止めないことが、大の苦悩を大きくする原因だった。
一方、大は上京して両親以外のろう者と出会い、同じ手話でも地方によって表現の違いがあることや、進んで通訳をすることが時にろう者の自立した行動の妨げになるという視点を知った。この考え方は、両親を故郷に置いて来たという大の罪悪感を和らげたに違いない。
コーダという立場を疎ましく思って逃げるように家を出た大だったが、上京したことで結果的にろう者の世界の広さを知り、両親との関わりを素直に見つめ直すことができた。
静かで切なく、そして最後に清々しい気持ちになれるひとりの青年の成長譚だ。
ラストに長い回想シーンを持ってきてほぼそのまま終わる(電車の中でPCを打つタイトルカットはあったけど)というのはちょっと意外だった。一般的に、終盤の回想というのはクライマックスを盛り上げるための足掛かり的な使われ方をすることが多いので、あのあと進行中の時間軸に戻ってひと山あるのだろうと、漠然と思っていた。
駅のホームで、人前で手話を使ったことに母から礼を言われて初めて、大は自分の言動が母をどれだけ追い詰めていたか気づき、罪悪感と後悔に苛まれ、自分を恥じて泣く。彼の気持ちが変化する節目の場面だ。
上京後、祖母に取り次いでもらった電話で大声で母に話しかけた場面や、父の入院で帰省した時に「俺、帰ってこようか?」と言う場面は、時系列的にはこのシーンの後の出来事になるが、20歳の大の涙を知らずに見るのと知って見るのとでは彼の気持ちの解釈が全く変わってくる気がする。
原作では時系列通り中盤に描かれているこのエピソードをラストに持ってきたのは、単にもっともエモーショナルな場面だからか、あるいは他の意図があるのだろうか。個人的には、時系列で感情を順番に積み重ねてもよかったかな、と思った。
あと、手持ちカメラの揺れが多用され過ぎてノイズに感じる時がちょっとあった。この手法、言うほどリアリティに貢献するかなあ、と思うことがある。
吉沢亮が大の中学生時代から演じていたのは驚いたが、あの年頃の難しい感じを絶妙に演じていて嫌な違和感はなかったし、成長していく様子も自然でよかった。
ろう者の役は全て実際のろう者が演じたとのこと。「コーダ あいのうた」に影響を受けてそうしたと呉美保監督が語っているが、当事者性からくる説得力はもちろん、みなさんの個性が物語によく合っていて魅力的だった。大の両親の雰囲気もよいし、河合祐三子の演じるパチンコ屋で出会ったお姉さんが自由で、大の世界を広げるキーパーソンとしても効いていてかなり好感を持った。
「私たちのできることを奪わないで」
ろう者の当事者を多数起用した上で、手話演出の専門家とコーダ監修をつけた上で、ろう者のリアリティにこだわって制作されている本作。そのリアリティがあるからこそ、ろう者と聴者の狭間を生きるコーダのリアルが深く映像に刻まれている。耳が聞こえない時にどういう生活になるのか、その生活の実態がさりげなくちりばめられているのが良い。キッチンで鍋が吹いていることに気づかなかったり、赤ん坊の泣き声が聞こえなかったり。それらが大事件に発展することはないのだが、細かい苦労の積み重ねを日々、強いられることがよくわかる。その中で、ろう者の両親に育てられた聴者の主人公が、他者とは違う家庭で育ったことに葛藤する。アメリカ映画『コーダ あいのうた』では家族を離れるところまでが描かれるが、本作はその後も描かれる。上京してから初めてコーダという概念を知り、家族を見つめなおし、自身の進むべき道を考えるようになる。
二つの世界の狭間で生きるコーダの苦しみは何なのか、『コーダ あいのうた』と比較してもより深く迫っていたのではないか。なまじろう者の世界を知っているが故に、助けようと思って「私たちのできることを奪わないで」と諭されるシーンなど、重要なシチュエーションだと思う。
徹底したリアルな映像世界は、さすが呉美保監督。今年を代表する邦画だと思う。
普遍的な家族の愛の物語
耳のきこえない両親のもとで育った息子の話、という本作の設定を最初に知ったとき、2021年米製作の傑作リメイク「コーダ あいのうた」(オリジナルは2014年の仏映画「エール!」)の主人公を男性に変更してアレンジした日本版リメイクかと早とちりしたが、正しくは作家・五十嵐大による自伝的エッセイを原作にしたオリジナル映画。とはいえ、「コーダ」(CODAはChildren of Deaf Adults=“耳の聴こえない大人に育てられた子”の意味)が主人公の家族役に実際に聴覚障害のある俳優たちを起用し高評価された流れを受けて、この「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の企画が実現したのは呉美保監督も明かしている通り。また、「コーダ」の主人公が夢の実現のため家族と離れて一人立ちするところで終わっていたので、主人公・大(吉沢亮)が単身上京してからの物語が後半で大きなウェイトを占める「ぼくが生きてる、ふたつの世界」は、本質的な部分で「コーダ」と連続性があるようにも感じられる。
両親に反発するように家を出た大は、紆余曲折を経て編集プロダクションに就職し、やがてライターとして文章を書くように。事件・事故などの出来事の断片的な情報を集めて一本の記事にする行為は、出来事の推移と当事者らの関連性を俯瞰し、客観的にとらえ直すということ。東京でのさまざまな出会いと経験に加え、物事を客観的にとらえる力を培った大が、家族との関係を見つめ直すことができたのも自然な流れだっただろう。
思春期の大に反抗的な態度や非難の言葉をぶつけられても、悲しみをぐっとこらえて天真爛漫な笑みを絶やさず息子に愛情を注ぎ続ける母・明子に、観客の多くは理想の母親像を見るはず。演じた忍足亜希子は文句なしに素晴らしく(本年公開作が対象の映画賞で助演女優賞の受賞にも期待がかかる)、ろう者の親と健常者の子の話に限定させず普遍的な家族の愛の物語に昇華させた脚本・港岳彦の貢献も大きい。安易に“泣ける映画”という言葉を使いたくないが、この「ふたつの世界」には本当に泣かされた。
あるがままと達観が情緒を振り払う日本版『コーダ』の魅力
フランス映画をハリウッドがリメイクしてアカデミー賞に輝いた『コーダ あいのうた』('21年)があったように、日本にも2万人以上いると言われるろうの両親のもとに生まれた子供にフォーカスした本作。そして、『コーダ~』がそうだったように、ここに登場する親たちの自然体と、音のない世界とある世界の狭間で揺れる子供の葛藤が観る側にも伝わって、何があろうと決して深刻ぶらず、あるがままを受け入れて生きる強さに心が震えてしまう。情緒に傾き過ぎない演出と演技にも助けられた。
ろう者の登場人物はすべてろう者に演じさせたことも成功の要因だろう。特に、『コーダ~』でもそうだったが破天荒でいて物事を達観視し、息子を心から信じている父親のキャラクターが魅力的だ。でも、与えられた境遇に疑問を持ち、やがて受け入れていく息子を演じる吉沢亮の計算し尽くされた変容の演技に感心する。
人は誰でも過去を振り返って気づかなかったことに感謝して、そこからまた前を向き、新たな一歩を歩み出す。取りこぼしが多い人にも希望を与えてくれる映画だ。
人は誰しもいくつかの世界を行き来して生きているのではないか
きこえない母と、きこえる息子が織りなす親子の物語であり、“きこえる世界”と“きこえない世界”を行き来する、ひとりのコーダ(きこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子供)の心の葛藤と成長を描いて、普遍的な家族の愛の物語へ昇華させています。
人は誰しもいくつかの世界を行き来して生きているのではないでしょうか。本作は“きこえる世界”と“きこえない世界”を描いていますが、無意識の差別を引き起こす、国や民族、出自や身分、言語や肌の色が違う世界、さらには他の社会的マイノリティの世界と置き換えて見ることもできます。
そして、自身の親しい人を思い出し、その人への後悔や懐かしい記憶が重なると、自分の物語として心に響いてくる作品です。
コーダについて知ることが出来ました。
お互い思いあうからこそぶつかり合う親子の絆とコーダであることを受け入れるまでの葛藤と成長が描かれています。最後のシーンは本当に涙が止まりませんでした。
劇中で時折訪れる完全な無音の演出や吉沢亮さんの繊細な演技も素晴らしかったです。
親が愛をもって育ててくれたことに気づく話
まさに自分の知らない世界
を垣間見ることができて貴重な経験となりました。物音がきこえない世界、コーダとして生きてることに嫌悪感が増した思春期の気持ち、きこえないことを馬鹿にしている世間の冷たい目線など、昭和の時代も相まって酷い仕打ちのシーンは目を覆いたくなりました。大の家族ではない人で、良き理解者がいてくれたら少しは違ったかもと想像しました。この映画を通じて、きこえない母ときこえる息子であってもより強く結びついていると思ったし、自分もきこえない人をもっと理解したい気持ちが強くなりました。それには手話を習う必要がある。子供のうちから手話の基礎を習う制度があってもいいのかも。誰もが障害者を支えられるような国にならないといけないと思いました
こういう作品が好き
吉沢亮を前面に出す内容になるのかと思いきや、序盤はしっかり大の幼少期を描くいたことに驚き。
コーダの人の軌跡を示そうとする姿勢にはとても好感を持てた。
大も「こんな家に生まれてこなきゃ良かった」的なひどいことを言っているが、決して「嫌なやつ」と思わせない吉沢のバランス感覚も見事。
最終的には親子の仲が縮まったが、「もう少し歩み寄れたら良かったのに…」と思うが、やはりコーダとして生きてきた大にとっては、時間を置き、別環境で生活しないと、気持ちの整理はできなかったのかなと思う。
障がいの有無にかかわらず、親子関係の難しさも感じた。
また、ラストが東京移住前夜だったところもなんか良かった。
展開が早過ぎて残念
もっと関心を持たねば
バイト先で近くにあった映画館でちょうどいい時間帯にやってて、主演が吉沢亮君ということで、観に行った。
耳の聞こえない両親から産まれた、耳の聞こえる子を「コーダ」というそうで、日本には2万人以上いると言っていた。
宮城県塩釜市で、コーダとして産まれてきた五十嵐大君は、幼少期は両親と手話で話をするのが当然として育ったが、小学生のころから違和感を感じるようになり、高校生くらいで機嫌の悪い時に「俺は両親とも耳が聞こえない家になんか産まれたくなかった」と言ってしまい、20歳になって東京で一人暮らしを始める。しかし精一杯大君に愛情を注いできた両親の愛に気づいていく。コーダとして産まれてきた人たち特有の気持ちや、耳の聞こえない人たちにはまだまだ暮らしにくいところも多々あり、自分にもできることがあると感じた。
自分(59歳)は健常な両親から産まれてきたが、やっぱり20歳過ぎで荒れて両親にひどいことを言った経験があり、両親は既に死んでしまったが今は謝りたい気持ちでいっぱいで、この映画をみてその感情が沸き起こった。
吉沢亮君が、小さな映画にも社会的意義があれば出ていて、感心した。
吉沢亮が出ていなかったら、観なかっただろう。
とりあえず原作本をアマゾンで注文した。
デフリンピックも見てみようかな
映画のゴールがわからなかった
意味も分からず泣いてしまった。
映画のゴールはどこだったんだろう。全体的に大きな盛り上がりというのは感じなかった。
でも伝えたいものがすごく大きかった作品だと思った。
こういった両親に障害がある家庭は実際にたくさんあると思う。
苦労してきたのも分かる。つらい。
隠したくなる気持ちもわかる。お年頃だととくに。つらい。
すごくリアルに描かれていたと思う。
手話って穏やかにゆっくりしゃべるイメージだった。(ニュースのはじっこでやってる手話くらいしか、あまり自分とはかかわりがなかった。)
すごく感情的な、激しい表情を交えた手話があるんだと思った。
手話にも早口とかもあるんだと知った。
手話に方言もあるんだと知った。
一番印象に残ったシーンは耳の聞こえない人の手助けをしたつもりが、「私たちの仕事を奪わないで」だった。良かれと思って手伝っても、生きる権利を奪ってしまっているようになってしまう。その人が、やりたい、できる、を奪ってはいけない。
助けを求めてきたら、その時は手伝ったらいいのだ。知らなかったし勉強になった。
カレーおいしくないんか~い。そのへんもリアルだったなあ。
お父さんがいい人で良かった。子供が親に悪態をつくことっていっぱいあると思う。
お母さんが泣いたとして、傷ついたとして、そこでお父さんが感情的に怒鳴り散らすタイプだったらこの子はもう出て行って戻らなかったと思う。
ちゃんと落ち着いて息子と話ができる人で良かった。
お父さん、お母さんも聞こえないことでつらい経験をたくさん乗り越えてきたと思う。だからこそ、生まれたやさしさなんだと思う。
おそらく自分はこの映画の半分も理解はしていないと思う。
でもなんだかもう1回見たいと思う映画。
よくわからないけど涙が止まらなくなる映画。
ひとりで生きていく強さ
手話にも方言がある
聴覚障害者は、日本では約34万人いるとされています。劇中でも語られていましたが、2万人余のCODAがいるとのこと。大の母親はろう学校に行かず、普通の学校に行っていたとのことだけど、現在でも大勢いるみたいです。知らなかった・・・
『コーダ あいのうた』、『エール!』のようなドラマチックな内容ではなく、セミドキュメンタリーのような大の成長物語を描いた内容には好感が持てます。好きという手話だけ覚えました。聴覚障害者の家族が普通だと思っていた大の心境が揺れ動いて、家を飛び出したくなる気持ちも伝わってくるし、東京に出てからの就職の苦労。それと同時に手話サークルに参加することで家族のことを忘れない気持ちも良かった。
私事ですが、タクシーのお客様にもろうあ者がいます。行先をスマホで提示してくれたり、紙に書いてくれたりと様々ですが、道を間違えようものなら肩を叩いてくれたりします。喋らなくてもいいので楽でもあります。最も怖いのが車の音に気づかないことでしょうね。
映画を観ていて、手話を使えることで得することもあるんだな~などと不謹慎にも感じてしまいました。大音量で音楽が流れているお店や電車の中。ちょっと微笑ましい光景でした。今ではスマホという便利なツールがあるので、親子関係を疎かにすることもないでしょうけど、劇中では手紙もいい感じで使われてました。あと、カレーには味噌を入れないように・・・
⭐︎4.2 / 5.0
全269件中、1~20件目を表示