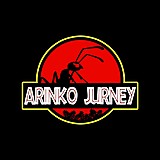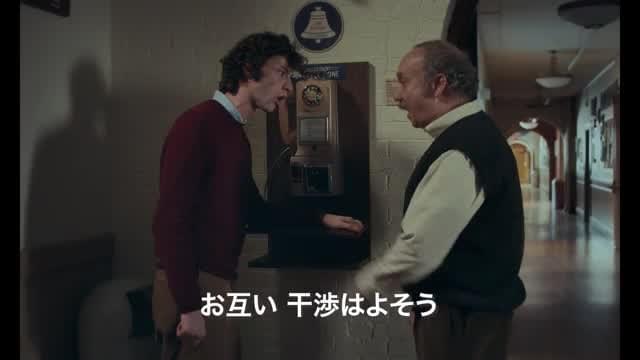ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価
全253件中、61~80件目を表示
ペイン監督の渋い一作。ベトナム戦争の終盤期に時期を置いているけど、...
ペイン監督の渋い一作。ベトナム戦争の終盤期に時期を置いているけど、9.11以後のアメリカは常時予備役部隊を戦地派遣展開している状態。徴兵制は停止しているものの大学進学の学費稼ぎで入隊したりしており映画が描いた状況と似ている。みんな嫌な属性を抱えているけどそれには理由があってという事が丹念に解かれていく。そして不発弾とでもいうべき出来事が物語を決定付ける。終わってみると監督の人を信じる姿勢が残る作品になっていた。
劇中に出てくる「士官学校」、おそらくMILITARY ACADEMYから訳されてると思うのですが、アメリカにはいわゆる軍設置の士官学校(陸軍ならウェストポイント)の他に大学・短大としてヴァージニア工科大学などいくつか軍事学科を設置していて士官資格も取れるようになっているところがある。そことはさらに別に高校で士官学校を模したカリキュラムを取るところがあって(ウェストポイントなど目指す予備校的なところと普通高校だけど士官学校方式をとっているだけのところに分かれたはず)こういうところもMILITARY ACADEMYを名乗っている。トランプもそういうところを卒業していたりするんですが、劇中言及がある学校も士官学校方式の全寮制高校じゃないかなと思った次第。コロンボとかこの種の学校が出てくるケースがありますが翻訳はみんな区別してないのは少々不満ですね。日本の陸軍幼年学校とは話が違うのが大半でしょうから。
人間臭さ。あたたかみ。
この作品、よくある話かなと思いつつ観てみたが、なかなか面白い映画。心温まる内容。寒さが厳しくなり何となく人恋しくなる12月頃にはとてもよかった。
このようなパターンの話では、ふつう生徒のほうが未熟で欠点だらけだと思うが、ここでは師の側の人間的デコボコや未完成さがクローズアップされていて、ちょっと面白い。おとなのクセ、欠陥、不完全さが素直にされけだされる。
ポールは、最後に、彼の立場でできる最も誇るべきことをした。大仕事を成したという自信がポールをも変えていく。アンガスは、受けた愛情をまた他の誰かに伝えていくだろうな。
アンガスとポールの間には垣根を取り払った人間性のぶつかり合いがあった。先生だから、家族だから、他人だから、という仕切りは不可欠な社会の秩序なのだが、本当に人を変え得るのは本音の付き合いの方なのだろう。柔軟性のある風通しの良い社会なのだろう。
作品では、ストーリーが思いがけない方向に展開していく楽しさも。わずか数日でもたいへん充実した時間になることが人生にはたまにはある。ノリのよい音楽と一緒に、そんな≪ご馳走的の数日≫を映画で観られ、楽しかった。
孤独との向き合いかた
淡々と物語は進んでいき、サラッと終わる感じでしたが、しばらくの間思...
淡々と物語は進んでいき、サラッと終わる感じでしたが、しばらくの間思い出す度に感動していました。
これが良い脚本ということなのかな。
長い人生の中では、一冬のクリスマス休暇は短い期間なのかもしれませんが、あの3人には背負ってきた荷物が少し軽くなり、心の糧となる大事な期間だったのかもしれません。
とても共感できて、疲れたときには見返したい作品になりました。
これがアカデミー賞作品賞でも良かったと思う。
一応、これもクリスマスムービーになるんでしょうか。
本当に味わい深い映画でした。これを本年度のベストムービーに挙げる人が多いのも頷けます。
「いまを生きる」や「グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち」が好きな人はこちらもおすすめです。
最初は、キービジュアルに反して意外と登場人物が多く、あれ?と思ったのですが、途中からの急展開で納得。
もうちょっと早めにあの展開でも良かった気はしないでもないですが。138分もあるので。
ラストのとある「握手」のシーンが特に良いですね。あえてハグじゃなくて握手なのが良い。
キャストは、一番の驚きは文字通りのニューカマーであるドミニク・セッサ。
ロケ場所にいた人物がスカウトされてそのまま映画デビューという、どこぞの鈴鹿央士を思わせるシンデレラボーイで、
それがしかもあのアレクサンダー・ペイン監督作、更にベテランのポール・ジアマッティ相手役という大役にも関わらず、驚嘆するほどの堂々たる熱演でした。
また、大きな喪失を抱える母親を好演してダバイン・ジョイ・ランドルフはオスカー受賞も納得の存在感でした。
見事な肝っ玉母さんぶりで、ポール・ジアマッティと肩を並べるような立ち位置でしたが、
実際はジアマッティよりも二回りも年下というのに驚愕。
そのジアマッティも、キャリア屈指の演技だったと思うのですが、アカデミー賞受賞ならずは残念。
もちろんアカデミー賞が全てとは言いませんし、「オッペンハイマー」が悪いとも決して思いませんが、やはり本作の方を個人的には推したいです。
(余談 DVD特典だとちょっとした別エンディングが追加されています)
ボーっとしてたら見落としてしまう繊細な映画。
最近の映画としては非常に地味な映画です。
だけどそれが素晴らしい。
本作は大変繊細な映画です、ボーっとしてたら見逃してしまう小さなことが作中の人物の心を変化を表しています。
例えば、前半と後半で2回レストランで料理を注文するシーンがあるのですが、前半では「未成年にアルコールはダメ」と主人公の先生は断るのですが、後半では未成年にアルコール提供を断った店に対して「なんて頭の固い店なんだ」と怒ります。
こういう小さなセリフ一つ一つに主人公たちの心がどんどん変化していくのが分かります。
非情に繊細な映画です。
最後に主人公の先生が言う「こっちだこっちの目を見てくれ」というセリフも非常に繊細な意味を持っています。
おススメ。
性格も古典
目的が功名心にまみれている──と思うことがある。
何をするにも、自分の内心に承認欲を感知してしまう。
ほめられたい、好かれたい、栄誉をさずかりたい、バイトくんから尊敬されたい、さりげなく自慢したい、多数のいいねやフォロワーがほしい──そういうことを、日常の端々で、連続的に思っている自分に気づくことがある。
しかし、それを言うなら世の全体がそうである。
大谷翔平のような天才ではないわたしたちは誰もが浮かばれるチャンスをねらっている承認欲のごまめである。SNSは謂わばその歯ぎしりである。わたしたちは毎日スマホを眺めてそういう人々の歯ぎしりを聞いている。と思っていたら、聞こえていたのはじぶんの歯ぎしり、だったりする。
そんな世界のなかで、しばしば無欲な人間に会うことがある。じっさいにハナム先生のような人に会ったことがある──ような気がする。その記憶は、きっと自分が今より廉直に生きていたから、でもあるだろう。
わたしたちはやがて、青少年の健全な育成の理想を掲げるハナム先生に対して、いみじくも校長が言ったように「それはその通りだ、校長になるまではな」というポジションの傘下で生きるようになる。
学校の経営をあずかっている校長が「大口寄付者の息子にCマイナスをつけるな」とハナム先生を諫めるのは当然だからだ。
すなわちひとたびポジションを得てしまえば今まで通りの理想を掲げていくわけにはいかない──という大人の事情に与するわけである。
が、それは言い訳でもある、と映画「The Holdovers」は言っている。
ハナム先生はしがない古典教師であり、生徒にきらわれ女にモテず、やぶにらみなうえ魚臭症だが、職分をまっとうして生徒の訓育につとめた。名利とは無縁だが高潔な人物だ。アンガス青年の心に、永遠に生き続け、かれの人生をよりよい徳へとみちびくだろう。
つまり生徒に嫌われようとも、浮世の欲得から縁遠くあろうとも、信念に正直に生きるならそれで十分ではないのか──とこの映画は言っていて、それが欲得に生きているわたしには新鮮でかゆいのだった。
簡単に例えるなら、いまを生きる(Dead Poets Society、1989)の地味バージョン。加えてビジュアル偏重時代への警笛でもあった。この映画は間接的にせよ、人を外見で判断しようとするな──と言っていたと思う。
もうひとりの主役はノスタルジーだろう。
映画はさいしょからフィルムノイズがのり、レコード針をおとしたようなジリパチ音が混ざる。
『スタッフはフォーカスフィーチャーズとミラマックスのためにレトロ調のタイトルカードとロゴのバリエーションを制作し、映画のオープニングを飾ることで、この映画の1970年代の様式美をさらに際立たせた。』(wikipedia、The Holdoversより)
アレクサンダーペイン監督は実際に1970年代に作られたかのような雰囲気を醸し出すためにEigil Bryldを撮影監督に抜擢し、Eigil Bryldは監督の意向を汲んでフィルム乳剤とカラーグレーディングによって70年代の映像の見た目をつくりだした──という。
おかげでわたしは製作年度を二度見した。まるでさらば冬のかもめ(The Last Detail、1973)を見ている気分だった。
最新技術でつくられたレトロ調がThe Holdoversの雰囲気に大きく貢献し、よってもうひとりの主役はノスタルジーだった──と思うのだ。
また、どうやったのかわからないがハナム先生のやぶにらみ(斜視の特殊効果)が自然だった。オスカーでは作品賞と主演男優賞と助演女優賞と脚本と編集の5部門がノミネートされ、ランドルフが助演女優賞をとった。たしかにランドルフが演じたメアリーは哀しさがあらわれた名演だった。ジアマッティはどこでも巧いので賞レースでは与えすぎないような均衡がとられる。
本作でも他の役者は後配役だったがジアマッティのハナム先生は最初からきまっていた。ジアマッティありきの映画だった。
いい映画だったが老成したアンガス青年がなにかの拍子にハナム先生の写真を見つける──みたいな回顧シーンが、最後にあればよかった気がする。孫に「だあれ」と尋ねられるような。アンガスは懐かしく遠い目をしながら恩師だと答える。そんなラストシーンがあれば時代をまたぐことができた。
──が、ペイン監督は、わざわざ70年代に作られたような雰囲気を重視したのだから、ラストで現代に飛んでしまっては整合が損なわれる。この考察はわたしに蛇足という言葉の成り立ちを思い起こさせた。
imdb7.9、RottenTomatoes97%と92%。
映画の中身と同様にアレクサンダーペインは功名心(承認欲)を感じさせないストイックな監督だと思う。どの作品にも「いぶし銀」の感じがあるがそれは本作にもあった。
シンパシー
は感じるものの、そこまでは入り込めなかった。
友達はいらない(いない)
パーティや宴会は苦手で大嫌い
1人で十分楽しいし気楽
一方、どこかで何かを期待してしまう
そんな主人公にはとてもシンパシーを感じる、
学校にもなじめず家族に依存してしまう生徒の気持ちもよくわかる。
だから、周囲の無意識なのかもしれない身勝手さや差別には腹が立つし、
ラストは爽快で心に染み入るものがあった。
そういう意味では悪くなかった。
だが、冗長でテンポが良くない。
特に序盤は悪ガキどものどうでもいい生態がだらだら続いた。
助演女優賞を穫ったから重要な役回りなのだろうが、
調理係の女性の立ち位置もいまいちすっきりしなかった。
黒人女性故の苦渋ってこと?
むしろマジョリティとしての校長秘書?をもっとクローズアップして欲しかった。
長い割りに生徒のGFについてなどは中途半端でモヤモヤ感も残った。
ベトナム戦争の戦火がまだ収まらない1970年。エリート校と思われ...
ベトナム戦争の戦火がまだ収まらない1970年。エリート校と思われる全寮制男子高校で、クリスマスに帰郷できなくなったたったひねくれ学生、その面倒を見る事になった偏屈教師、寮の料理長を務める女性の3人が過ごす冬の日々を描く物語です。
寒い冬の鯛焼きの様に小さいが確かな暖かみを有する秀作でした。軽みを失うことなく丁寧に綴られるお話には滋味あふれる言葉が散りばめられています。そして、物語の中にさほど強く描かれる訳ではありませんが、映像・音楽などから漂う1970年の時代性こそが本作の持ち味です。これを現代を舞台にしたら成立し得ないのでしょう。我々が生きている現代はそんなにもギスギスしていて、こんな小さな物語すら生息出来ない時代なのだろうと思うと寂しいな。
哀愁漂うヒューマンドラマ
全寮制男子校を舞台に教師と生徒と料理長の関係性を描いたヒューマンドラマ。辛い事情を背負った3人の秘密が徐々に明らかになるにつれ、深まっていく人間関係を上手く表現していて、哀愁漂う街並みやレトロな雰囲気も絶妙で酔いしれました。
2024-143
バートン男子
大人と子供の成長
夏の暑い日に冬の話
あれれ
これが★5じゃないなら何が★5なの
【クリスマス休暇中に、色々有って学校に居残る事になってしまった心に痛みを抱える問題教師、問題生徒、女料理長が世代や立場を越えて相互理解し、絆で結ばれていく姿を描いたヒューマンハートフルコメディ作品。】
ー 「The Holdovers」・・・居残り組。-
■1970年。マサチューセッツ州にある全寮制のモートン名門私立男子学校が舞台。キビシクて、学校運営に忖度せずに駄目な生徒はドンドン落第させる古代史の教師ハナム(ポール・ジアマッティ)は多額の寄付金を学校にしていた議員の息子を落第させたペナルティとして、元教え子の校長から2週間のクリスマス休暇中、寮に残る生徒の監督役を命じられる。
最初は4人居た居残り生徒も途中で自宅に帰り、残ったのは再婚した母に旅行の予定を、新婚旅行に替えられてしまった素行が良くないアンガス・タリー(ドミニク・セッサ)と、息子をベトナム戦争で失ったばかりの料理長メアリー(ダバイン・ジョイ・ランドルフ)の3人だった。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・序盤は、ハナムと生徒達のおバカな遣り取りをクスクス笑いながら観賞。名門と言っている割には、居残りになった男子生徒達がおバカすぎる。空調が勿体ないので、皆保健室のベッドで寝ている。
・だが、徐々にハナムが実は生徒想いの良き教師であり、メアリーの息子を始め若者達がベトナム戦争で命を落とすことに無念さを感じている事が分かるストーリー展開に徐々に引き込まれて行く。
・ハナムは言う事を聞かない直ぐに”ちょっとトイレ・・。”と言って脱走するアンガスに手を焼くが、彼の哀しみを徐々に理解し、クリスマスの夜に彼が”ボストンに行きたい!”と言いだした事に、渋々承諾する。”社会見学”として。メアリーも途中で合流することにして。
■二人は、ボーリング場、古本市などを”見学”するが、映画を観ている時にアンガスが”ちょっとトイレ・・。”と言って脱走する。ハナムは、そんな彼を追い掛けるがアンガスから”お願い。どうしても行きたいところがあるんだ。”といつもと違う真剣な表情で訴えられ、タクシーである場所に行く。そこは、アンガスの実の父親で精神を病んだ男が入院している病院だった。
二人は、強く抱きしめ合うが矢張り父は”食事に薬が入れられている。”と言って挙動不審なまま。
がっくりするアンガスとハナムが夜歩いていると、ハナムに声を掛けて来る女性連れの男。ハナムも懐かしそうに挨拶するが、その男はハナムのハーバード大での卒業論文を盗んだお陰で今や教授になっている男だった。
アンガスが問い詰めると、ナント、ハナムはその男を仕返しで車で轢いたためにハーバード大を退学をさせられていたのである。絶句するアンガス。
ー この辺りのストーリー展開が、絶妙に巧い。再後半のハナムの取った行動原理が良く分かるからである。ー
■学校に戻ると、アンガスの母と義理の父親が憤慨して待っていた。アンガスの父が彼と会ったことで施設で暴れ、別の施設に移った事に対し。そして、校長はアンガスを退学にし軍人学校に入れようとする。
だが、ここでハナムは毅然と、”ボストンには、私が誘った。”と言い放つのである。それは、アンガスが軍人学校に入る事で戦場に行くことを阻止するためである。例え、自分がモートン名門私立男子学校の教師の座を失ってでも。
更にハナムはアンガスの母と義理の父親に言い放つのである。”何で、子供の将来を閉ざすようなことを言うんだ!”
ー このシーンは、非常に胸に響いたなあ。自分の息子の事を何も考えていない愚かしき母との対比。且つ、ハナムが元教え子の校長に言い放った言葉。(笑えたが、ちょっと書けません・・。)-
<そんな、ハナムの気概ある行動に、メアリーは優しく微笑み、アンガスは”何を言ってくれたか分からないけれど・・。有難う。”とそれまでの反抗的な態度は一切なく、ハナムと固く握手をして別れるのである。
今作は、ハナムを演じたポール・ジアマッティのハナムの長所、短所をユニークさを漂わせつつ、時に見せる毅然とした姿や、愛する息子をベトナム戦争で亡くしながらも明るく振る舞い、アンガスの気持ちを汲み取って行く様を演じたダバイン・ジョイ・ランドルフの姿が沁みるヒューマンハートフルコメディ作品なのである。>
<2024年8月13日 刈谷日劇にて鑑賞>
■2024年8月14日
評点を4.0から4.5に変更します。悪しからず。
全253件中、61~80件目を表示