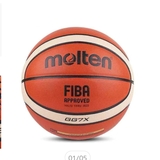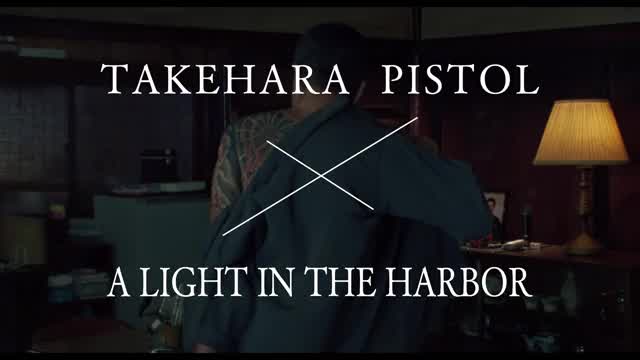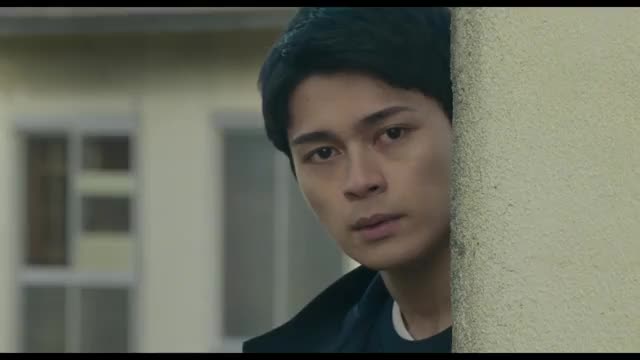港のひかりのレビュー・感想・評価
全187件中、61~80件目を表示
映像にしろヤクザにしろ昔が良かったと思った。
撮り方が違うと、こうも違うものなんだと知ることができた。観ていて疲れないし、好みは分かれるのだろうけど、映像のザラザラした質感が好き。舘ひろしさんの表情、声ととても合っている。私的には高倉健さんを思い起こさせるシーンもあり、ゾワッとするようなワクワクするような感覚になった。
そしてなにより輪島の朝市や、震災で変わってしまった風景を残せて、悲しくもよかったと思う。
話の内容的には予想外というわけではないが、ちゃんと人の心の部分を感じさせてくれた。現代の話なのだが、映像も相まって昔は良かったと思ってしまった。こういう映画は無くなって欲しくない。
懐かしい良さがあった!
流石の一言、映画ヤクザと家族のファンとして待望の一作
映画ヤクザと家族を見てくらって以来、藤井監督の映画はだいたい見ています。館本人の「もう一度藤井監督とやりたかった」のコメントもあり、港のひかりに関しては同映画の系譜として勝手に意識しながら鑑賞しました。
前作での柴崎組組長としての威厳を三浦のそれで再確認する見方があり楽しめた。
クライマックスは圧巻。
ヤクザ館ひろしを存分に楽しめる構成となっていて、そのほか椎名桔平、ピエール瀧、笹野高史らも最高。
藤井フィルムとして、映像、音楽も完璧だったのでは。
テーマは人のため。エンドロールの最後でなぜ舞台が富山だったのかの意味も含めて回収されていて素晴らしかった。
渾身の一作でした。
元ヤクザと盲目の少年の物語。最期のシーンで泣けた
久しぶりの舘ひろし主演映画🎥
尾上菊五郎で寺島しのぶの長男、尾上眞秀が盲目の少年幸太を演じ、大人になった幸太を千葉真一の息子、眞栄田郷敦が演じました。
また、端役ですがピエール瀧が覚醒剤販売をしている暴力団のヤクザ役として登場します。
ピエール瀧は妻夫木聡主演の宝島にも出てましたが、確かに「ヤクザ役」は嵌まり役(笑)
盲目の少年役は難しい役ですが、私は子役時代を演じた尾上眞秀君の演技も良かったと思いましたが、大人になった眞栄田郷敦の演技の方が感銘を受けました。
あと、ヤクザの親分役の椎名桔平はきっと本物なんだろうと思ってしまいました。
ストーリーは単純。
ラリったヤクザの運転する車に衝突され両親を失い、自分も視力を失った幸太少年が元ヤクザの三浦(舘ひろし)と知り合い、彼が手にした犯罪収益で手術を受け視力を回復する。
成長して刑事になった幸太に危害を加えようとするヤクザに命を狙われるが、三浦は幸太を守るために単身暴力団のいる倉庫に乗り込みヤクザたちと対峙するが、そこにヤクザから呼び出された幸太が乗り込み殺し合いが始まる。
三浦は幸太にヤクザの親分を射殺した自分に手錠をするよう懇願しながら絶命するが、このシーンには私の近くで映画を観ていたおじさんがすすり泣いていた。
夜明けを求めて
カタギになった元ヤクザと盲目の子供の織りなすドラマという事で、昭和もとい東映の任侠映画だな〜と思いながら観ましたが、良くも悪くもイメージ通りの作品でした。
ベタな話なので外すことなく観れましたが、もっと展開があっても良かったんじゃとは思ってしまいました。
意外と子供パートが長いなと思ったのですが、ドラマ的には全然ダレる事なく、偶然の出会いからの信頼関係だったり、おじさんと幸太の友情に近いものが築かれる様子は観ていて見応えがありました。
一緒にご飯を食べに行くシーンはハートフルでしたし、目の手術のシーンなんかはおじさんの義理堅さがこれでもかってくらい映像に出ていて胸熱でした。
大人になって刑事になった幸太との再会パートなんかもギュッとは詰め込まれていましたが、感動的な仕上がりになっていましたし、会うことを悩みながらも一歩踏み出して会うおじさんの決意は相当なものだっただろうなと思いました。
ベタではあったんですが終盤に差し掛かるまでは全然面白く観れていたのに、風呂敷を畳まないといけない段階に入った瞬間にハチャメチャになってしまって思わずずっこけてしまいました。
絶対にヤクザとの抗争はあるだろうなーと思ったら倉庫でのみみっちい争いで、仁義はありつつも弱目のドラマが続きますし、単身で突撃してくる幸太もちょっとおバカですし、やられる〜とか思っていたら、ヤクザ側が何故か仲違いして撃って撃たれてで勝手に散っていったのでなんじゃこりゃとなりました。
その後も病院に連れていきゃいいのに港に連れていって思い出を語るシーンになっており、絶対に病院行った方が生きれる確率は高いぞ…とすまし顔で観てしまいました。
その後の展開も綺麗に済まされているけれどあの素っ頓狂な展開があった後なのでモヤモヤしたままエンドロールに行っちゃうのでもうすってんころりんです。
舘ひろしさんがカッコ良すぎましたね。
スーツもカッコいいですし、漁師としての姿もかっこいいですし、普段は優しいおじ様なのに、スイッチが入るとドスのきいた声で圧倒され、ボコボコにされてしまう訳ですからもう小便ちびりもんです。
あぶ刑事でのファンキーさとはまた違う色気があって最高のおじ様でした。
眞栄田郷敦さんのスマートなカッコ良さも素敵でしたし、椎名桔平さんのザ・悪の親玉な感じやピエール瀧さんの心優しき舎弟な感じ、斎藤工さんの起用場所もそこ!?ってところの意外性があって面白かったです。
役者陣の熱演は素晴らしかったですし、能登の風景も素晴らしかったんですが、藤井監督の作品としてはストレートすぎてパンチ弱めかなと思いました。
ヤクザとは切っても切れない関係性は唯一無二だと思うので、またガッツリ任侠映画撮ってほしいなと思いました。
鑑賞日 11/17
鑑賞時間 18:15〜20:15
木村大作さん、フィルム撮影健全なり
藤井道人監督、木村大作撮影ということで鑑賞しました。今年86歳の木村大作さん、流石に本領発揮でした。ラスト近くの港での舘ひろしさんと眞栄田郷敦さんのカラミでの雪が激しく降るシーンでは、昔の「八甲田山」「駅 STATION」「海峡」「鉄道員」(←すべて高倉健さん)の雪のシーンを思いだしました。木村大作さんは、雪のシーンの撮影は日本一だと思います。今回は35ミリフィルムでの撮影とのこと…衰えていませんね😃。
三浦役の館ひろしさん、格好良かったです。(少年時の幸太に「昔 刑事だった」と嘘の話しをするシーンでは、「あぶない刑事だった」と言うと思いましたが...)
荒川役の笹野高史さん、人あたりの良い役似合ってました。(←東京タクシーて公開時期がダブリますが…)
組長役の椎名桔平さんは、似合っていたと思いますが、私は斎藤工には違和感でした。宇崎竜童さん、ピエール瀧さんや市川正親さんもハマっていたと思います。
幸太の少年時を演じた寺島しのぶさんのお子さん(尾上眞秀)も今後が楽しみです。眞繋がりで成長した幸太役の眞栄田郷敦さんの眼差しも印象的でした。(でも手錠ではなくて救急車でしょ…)
岡田准一さんは、どこのシーンだったのかしら?
定番の展開だが、楽しめた。
偏見や過去に囚われず眼の前の人に誠実に向き合えるか
元ヤクザと少年の直球のヒューマンドラマで、
今の時代に物語の設定がどうかしらと思っていたが全くの杞憂で
フィルムの映像の粗い質感や少し褪せた感じの発色が
ストーリーにも説得力を与えて、違和感がない。
背景や顔の皺からもひしと触感や豊かな情感が滲み出てきて、
それだけを見ていても飽きない。
それは映画館での鑑賞によって増幅されていると感じた。
演者さんについて、舘さんは貫禄の存在感で
ちょっと頑固で不器用だが一途で誠実な感じが渡哲也さんのようにもみえた。
真秀さんは拙さがいい感じで、郷敦さんへのシフトも自然。
過去や偏見にとらわれず、
目の前にいる人の今を見つめて正面から相対することができるか
という物語の通底にある問いかけに対して、
勇気を持って体現している登場人物たちにすごく感動した。
キャストが素晴らしい
何と言ってもキャストが皆、素晴しい!
舘ひろしさんの表情が、時折渡哲也さんに見えてしまう。魂を引き継いでいるのか?
そして何よりも子役が素晴らしい‼️実際に目が見えない方を選んだかと思った。光が見えた瞬間の目の動き!素晴らしい!
ただ、物語が…余りにもありきたりな、どこかで見たような…それも何だかご都合主義で不自然な展開…悪い意味での昭和的作品の部分が強すぎる。あくまでも個人的感想だが。
前半だけで良かった…
#港のひかり
藤井道人さんの凄さを知れましたね。
舘さんシブい
キャストがわかりやすく役にハマってる。
舘さん、竜童さんがシブい。幸太役、尾上くんの演技が光った、薄幸で寂しい日々の中、おじさんの存在、それこそが幸太にとって港のひかりだったのだと思った。幸太の親がヤク中の車の事故にあったことが気の毒に思い、あのひどい環境にあったから何か助けたい、と思ったのだと感じた。危険なことしても、幸太の目に光を、そう思ったのだと思う。舘さんのやさしい嘘、言葉にできない想い、表情 シブい
笹野さんが何かと優しく見守ってくれたところもよかった。齋藤工さんは始めはわからなかったけどああいう役は新鮮でした。眞栄田郷敦くんに最後、逮捕されますがすごくせつなかった。
スーツが似合う舘さん
あぶない刑事以来のスクリーンでの舘さん。
漁師姿よりスーツが似合う。
親父の法事の時にスーツで出て来た瞬間。
あーかっこいいなあと思いました。
途中で舘さんか眞栄田くんのどっちか死んじゃうなあと思って、ドキドキしました。
まあでも、舘さんだけだなあと確信する場面があって、
しょうがないとは思いました。
一ノ瀬さん絶対ヤクザ側だと思っていたら、刑事かよ。
斎藤工さん、椎名桔平さんは最近こんな役やってなかったので、懐かしさも覚えました。
少し突っ込み所はありますが、人間愛を感じいい作品でした。
黒島結菜さんが
藤井監督ゆえになかなかにシリアスな作品
光が共有される物語
本作は一見すると「喪失を抱えた主人公が港町で再生する」という類型的なプロットを踏襲している。しかし、そこに木村大作の撮影哲学が加わることが本作の真価を生み出している
そのレンズは光をただ捉えるのではなく、人間の存在理由そのものに焦点を合わせようとするかのよう。港へ反射する薄明の金色、老漁師の皺に宿る陰影、遠ざかる船が吐き出す白煙…。それらはすべて「生きるとは、誰かの光源になることではないか」というテーマを、言葉ではなく映像から語り始める。
おそらく多くの評論が「誰かのために生きる」というメッセージ性を称えるだろう。しかし本作で最も鋭いのは、人物同士の「距離」が語る感情の構造であると感じる。
登場人物は終始、微妙に距離を詰めきれないまま画面に配置される。港の長椅子、船大工の作業場、潮風を受ける遊歩道。どれも身体が半歩ずれている。
この「半歩の空白」は、関係性の希薄さそのものの表現。
だがクライマックスにかけて、人物の距離が縮まるのではなく、「光によってつながる」ように撮られる。逆光に浮かぶシルエット同士が、まるで同じ光源の中に溶けていく。
つまり本作は、「距離が埋まる物語」ではなく、「光が共有される物語」なのだと思う。
本作が独特なのは、「誰かのために生きる」が倫理的メッセージとして提示されるのではなく、生物的・構造的な連鎖反応として描かれている点だ。
この循環構造は、海の潮流のように循環し、港に絶え間なく漂着物を運ぶ潮の動きに重ねられる。
カメラはその循環を、波のリズムとカット割りの周期性で体感させる。
行為が行為を呼び、人の光が次の人の光源になる――
本作のメッセージは善行の推奨ではなく、「生とは連鎖する」という自然現象の描写なのだ。
この捉え方は実はに映画的である。
本作が観客に突きつけるのは、「あなたの光は、誰に届いているのか」という問い。
「誰かのために生きること」が連鎖する様を、道徳ではなく「光の物理」で描いた作品。
そのため、涙や感動の前に観客は光に包まれるような体験をする。
類型的ストーリーでありながら、木村大作だからこそ可能だった極めて映画的な作品と言える。
映画館で 満を持して 見てきました
ニット帽を
全187件中、61~80件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。