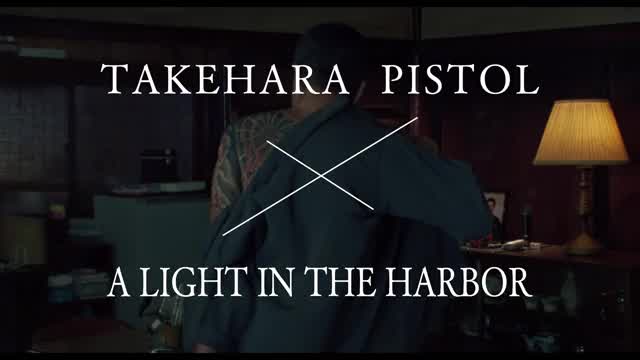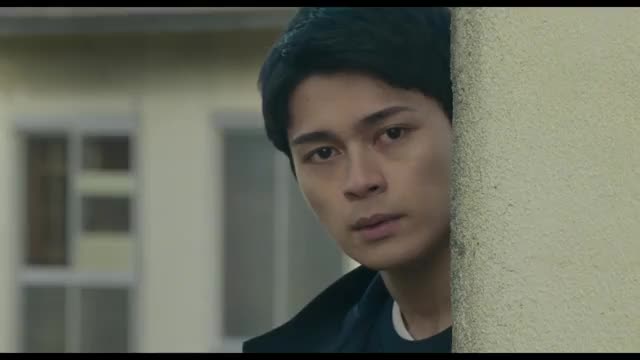「昭和の残響と現代日本映画の“分裂したリアリティ”について」港のひかり こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)
昭和の残響と現代日本映画の“分裂したリアリティ”について
藤井道人監督の『港のひかり』は、観客の心を掴む叙情的な前半と、仁義なき戦いに急旋回する後半という、ある種日本映画の“縮図”のような構造を抱えた作品だ。フィルム撮影を選び、北陸の港町を舞台に、舘ひろしという昭和映画の象徴を据えた時点で、映画はある種の「宿命」を背負ってスタートする。冒頭から中盤にかけての本作は、その宿命と見事に調和している。海の光、漁師の生活、盲目の少年・幸太との静かな絆、贖罪と再生——いずれも藤井作品の美学そのものだ。35mmの粒子が、失われた時間や人間の影を優しく包む。ここまでは完璧に近い。
ところが、大塚(ピエール瀧)が殺害されるあたりから、映画は突如として気圧配置が変わるように“別の映画”へと移行する。倉庫へ車で突入、突如の銃撃戦——この流れはどう見ても昭和・平成アクションの残滓であり、舘ひろしのフィルモグラフィーが持つ文化的記号を強制的に呼び起こしてしまう。これは監督の意図というより、舘という俳優が40年間積み上げてきた「身体の記憶」が画面を支配する現象だ。映画の文法が、叙情から暴力へ、静から動へと断裂し、その矛先が作品の芯を揺らしてしまう。
また、三浦(舘ひろし)がお金を調達するために安易に犯罪へ戻っていく展開も、やや物語構造として説得力を欠く。紡いできた再生の物語を自ら踏みつぶしてしまい、キャラクターの内的葛藤が端折られた印象は拭えない。幸太の義母(めぐみ)が、比較的まっとうな人物として描かれながら、12年間の間に疲れ果てた姿へ変貌している背景も十分に掘り下げられない。彼女が“時間に置き去りにされた人物”であることは伝わるが、その過程も物語の核心たりえたのではないかと感じてしまう。
幸太の車突入も同様で、情動の爆発としては理解できるが、絵面の問題としてどうしても平成アクションの文脈を呼び込んでしまう。観客は叙情映画として観ていたのに、突然“あぶない刑事”の劇場版のような絵面が目の前に現れるのだから、文脈の断裂は避けられない。これは藤井作品の「衝動ラスト」の悪い癖が出たと言える。作品世界が一度乱れ、その乱れを物語内部の必然性で回収しきれないまま“破れ目”として残ってしまう。
しかし、それでも本作が最終的に観客の記憶に残るのは、ラストのエンドロールにおける縦書きキャストの横流しだ。海を背景に縦書きテロップを左から右に流すというクラシックな手法は、日活や松竹の文芸映画の余韻を喚起し、散らかった文法を静かに統合していく。昭和の映画が持っていた「終わりの静けさ」を取り戻し、観客に「この映画は日本映画の系譜にある」という確信を与えてくれる。結果として、乱暴に見える後半のアクションも、昭和映画の記憶と接続することで、どこか許せてしまう不思議さがある。
『港のひかり』は、現代日本映画の抱えるアンビバレンス——叙情と暴力、詩情と脚本の粗、俳優の文化記号と作家の意図——が複雑に絡み合った作品だ。完璧ではない。むしろ綻びだらけだ。しかしそれでも、この港町に流れる光と風景が観客の心に残るのは、本作が“失われつつある日本映画の美学”を確かに掬い取ったからである。そういう意味で、この映画はやはり観る価値がある。
共感ありがとうございます。
3回読みました。
とても好きな作品なのに、
〉綻びが多い・・・
本当にそう思います。
好きだけど、ここ、どうなの?
ってなります。
藤井監督って若いのに不思議な人ですね。
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。