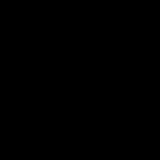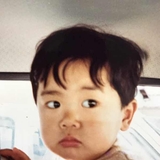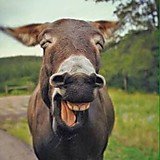あんのことのレビュー・感想・評価
全395件中、161~180件目を表示
「ナミビアの砂漠」も同じ時期に見て、映画は河合優実に背負わせすぎ〜...
「ナミビアの砂漠」も同じ時期に見て、映画は河合優実に背負わせすぎ〜と思った。
はやとくんのお尻丸出しなのがめちゃくちゃ微妙だった。将来的な影響をきちんと説明して本人に合意をとるみたいなことはしてないだろうに。
ちょっと話がずれるけど、東野圭吾の小説が原作のドラマ「さまよう刃」でも同じように河合優実は悲惨な運命を辿っているんだけど、そっちでは悲惨なシーンを執拗に映像化しており明らかに必要以上に感じた。そこまでしつこくそのシーンを描写するのはもはやそのシーンがある種ポルノ的に消費されるのを意図的に狙ってるのでは?とも思えた。
…ので、この映画ではあまりそういったシーンが描かれていなかったので、その点については誠意のような、暴力を直接見せることに表現を頼ろうとしない努力のようなものを感じました。
観るのも辛い・・・
いやまいった。覚悟はしていたがここまでとは・・・
こんなに観てるのが辛いと思ったのは
今や伝説の胸糞映画「ダンサー・イン・ザ・ダーク」以来。
何よりこれが実話ベースの話だというので余計に
実際にこんな母親がいるなんて・・・
とにかく鬼畜過ぎて最早人間ではない!
母親が出てくる度にムカついて、
マジで殺されるべきだ!と思った程。
大人になっても何故母親の暴力に屈していたのだろうか?
やろうと思えば抵抗するどころか
身体的にも勝っているのでぶっ飛ばせるのに!
多分、幼少期の頃から虐待されていたので、
恐怖を植え付けられ抵抗出来ないのだろう。
そして最後まで救いがないまま・・・
このやり場のない怒りは何処へぶつければいいのか!?
世の中にはこのような環境の子が
まだいっぱい居るという現実を突きつけられた。
河合優実、今や飛ぶ鳥を落とす勢いの人気女優。
物凄く良い女優さんですね。
容姿も雰囲気も声も演技も魅力的です。
売れている理由が分かります。
個人評価:3.8 河合優実でなければ、社会の歪に堕ちた少女を、ここ...
河合優実をはじめて見たのは、 「愛なのに」(2022年)だと思っていたが、 「百花」(2022年)と「ある男」(2022年)にも出ていたようだ。
動画配信で映画「あんのこと」を見た。
2024年製作/113分/PG12/日本
配給:キノフィルムズ
劇場公開日:2024年6月7日
河合優実
佐藤二朗
稲垣吾郎
河井青葉
広岡由里子
早見あかり
入江悠監督といえば、
「22年目の告白 私が殺人犯です」(2017年)を見たことがある。
河合優実をはじめて見たのは、
「愛なのに」(2022年)だと思っていたが、
「百花」(2022年)と「ある男」(2022年)にも出ていたようだ。
その後は「不適切にもほどがある!」などでも活躍している。
杏(河合優実)は、母子家庭で育った。
祖母がいる。
母(河井青葉)からの虐待を受け、
小学校4年で不登校となり、
12歳で母から売春を強いられ、
薬物依存症となった。
杏は薬物使用で逮捕され、
刑事の多々羅(佐藤二朗)と知り合った。
多々羅の主催する更生施設に通い、
施設を取材する記者の桐野(稲垣吾郎)の紹介で仕事にも就き、
夜間中学で勉強にも励む充実した生活だった。
このまま、何事もなく杏は更正に励むと思われた。
2020年、新型コロナウィルスの流行で、
非正規雇用である杏は仕事を失い、
夜間中学も休校となった。
居場所を失った杏は途方に暮れてしまう。
そして終劇18分前に悲劇的なことが起こる。
「マジかよこれ!」
思わず声が出た。
この映画は河合優実の代表作となったと思う。
満足度は5点満点で5点☆☆☆☆☆です。
河合優実と河井青葉のこと
ナミビアから、河合優実繋がりで鑑賞。アマプラもこのタイミングで配信開始とは分かってますね笑
しかしそれにしたって、酷い話すぎる。事実は小説よりも、とはよく言ったもの。世の中というものの理不尽に改めてズンと来る気持ちになるお話でした。実際に起こったであろう事象に関して語るのも良いかと思うものの、ここではあえてそこを外して、映画ですから映画として見た時どうかと言うお話を。
重い話ながらもストーリーテリングは明確で、良くも悪くもプロットは分かりやすい。実話ベースの映画に対して失礼かも知れないですが、「わかりやすすぎる」とも感じました。露悪ショーのような作りに見える側面もある。映画論として手放しで「良い」とも言えない感覚は残ってしまいましたね。
その中でしかし、役者は本当にすごい。ステレオタイプに陥ることなく、異様な実在感であんを演じ抜いた河合優実の凄み。ナミビアともう顔そのものも違って見える。最初の売春?薬物の取引?両方?のシーンで、金を払いたくないのか財布を開けられるのを防ごうと組みついてくる男に「ねぇちょっと…」と言って嫌がるシーン。あのニュアンス、相手型に拒絶と取らせることが出来ないような、絶妙に意志の弱い拒絶なんですよね。ああ、この子は「言えない子」なんだ。それを言い方で伝えるニュアンス力。
終盤の母親に対する「てめー子供返せよ」→「誰に向かっててめーって言ってんだ」、包丁→「お前母親刺せんのか」のくだりも人間の弱さの絶妙なラインを演じあげていて、本当に痛かったシーン。懸命に意志を振り絞ってささやかな抵抗をするんですけど、結局は生き汚い母親に蹂躙されてしまう心。
そんな河合優実と今回並んで私が「ヤバさ」感じたのは、母親役の河井青葉。
いわゆるバイプレイヤーの認識の方が強いかもしれません。たくさん見たわけではないですが、いろんな映画に登場している役者さんだと思います。印象深かったのは、安田顕主演「いとしのアイリーン」で主人公が暮らす村のパチンコ屋で一緒に働く、押されたら誰とでも寝てしまう、陰のある美人の役。濱口竜介監督作品にもよく出ている印象があります。
この役が本当にもう、ムカついてムカついてたまらない笑
言ってしまえば再現ドラマのような、なかなかリアリティが出しづらい役どころだと思うんですが、とにかく迫力に全振りしてて、見ていて巨大な悪のエネルギーを感じました。
まず、声がデカい。ドスの効いた声で年端もいかない娘を生物として圧迫する。ババァ餓死させんのか?シャブ打つ金があったら家に入れろよ!売ってこい!最低最悪のクズ台詞をこれほどまでに野太い声で言い放つ女性がいるだろうか…そして暴力もすごい。組み付く、はたく、蹴る、これらの動きに毒親特有のイヤ〜な「念」のようなものが乗っかってる。見るだけで嫌な気分になる所作。
怒鳴りつける。囲い込む。追いかけてくる。人間として大切なものの凡そを捨ててしまった母親。良識、世間体も一切気にすることなく、金づるとしての娘に一直線に向かっていく、まるでゾンビのような禍々しさ。一方ではその母親も、自分の母の介護だけは(おそらくだいぶ適当ながらも)投げ出すことなくやってるんですよね。このあたりの背景は気になりました。
そして、あんを決定的に道ならぬ道に戻してしまった一件。「おばあちゃんがコロナになったかも…」その一言に子供を連れて母親の家に帰ってみたら、そこにいたのは健康体の祖母。あんが物事を把握した瞬間、母親は彼女の弱みである子供を奪い取り人質に…最低最悪!クズofクズ!プロレスだったら最後にこのクズがやっつけられる展開を持ってくれば、東京ドーム満員間違いなし笑
…なのですが、これはあくまで事実に基づいた物語。少し気になったのは、母親の視点、早見あかり演じるあんの隣人の視点、多々良の視点、おそらく意図的にでしょうが深く切り込んではいません。人にはそれぞれ事情があるから悪人なんていないのよ、という見方を必ずしも推奨するわけではありませんが、「どうしてこんなことになったのか」は少し掘り下げて描いて欲しかったかなぁ、と言う気持ちはあります。絶対悪はエンターテイメントの中のお話。リアリティを生み出すのは、それぞれの人間としての営みの描き方、だと思ってます。
話としては、まずそこに不幸があります、と言うところからスタートしており構造的な理解に欠けている作りになっているのが一つ、私がもう一つ乗り切れなさを感じた理由でしょうか。まぁそれやると多分四時間ものですし笑、焦点を絞ったと言うことかも知れません。事実としても、知りたいですけどね。少し、不幸の側面を純粋培養しすぎているかなと言う感じは受けたかなと思います。
あえて映画論としてのレビューをしましたが、改めて事実としては本当に痛ましい話ですし、こんなことが起こる世の中であってはいけないと思います。何らかの関係者というわけではありませんし、映画に触れたと言うだけの人間ではありますが、末端ながら、ハナさんのご冥福を心からお祈りいたします。
父親の不在
杏はあまりにも幼く、弱く、優しかった。
典型的な親ガチャ。
そう言ってしまうとあまりにも不幸で、
その不運の積み重ねに言葉もありません。
親(春海=河井青葉)が杏(河合優実)のことを、
ママ、ママと呼ぶ異様な光景・・・
そして狂ったように激しいDV・・・
それを見て、正直、吐きそうだった。
(母親には嫌悪しかなかった)
11日前に河合優実の「ナミビアの砂漠」を観たばかりだった。
そのあまりの落差(別人)の演じ分けに心から驚いた。
「ナミビア・・・」では2人の男を思いのままに動かす一面のある
杏より世慣れた大人びた女性でした。
対して杏は、万引きがバレて小学4年から学校へいけなくなった少女。
漢字もろくに読めず書けない。
杏の寄る辺のない孤独・・・それを俯きがちで自信ない姿で表現した、
河合優実はカナとは全く別人だった。
心なしか背の高さまで、、小さく見える。
コロナ(パンデミック)から5年半経過ぎたの・・・ですね。
始まりは2019年(平成31年)春でしたね。
もう忘れそうな薄情者の私ですが、本当に怖かったです。
コロナに罹患した人は多く、家族で罹らないのは私だけ。
でも近所や親戚、知人にも、死んだ人は誰も知らない。
あの閉塞感、息の詰まる緊張感は異様でした。
(コロナ後遺症はさまざま聞きます、ワクチンの害とか・・)
はじめに志村けんさんが亡くなった。
親族は葬式もできずに、
骨になってやっと会えた。
見舞いにも行けない。面会も出来ない。
親の死に目にも会えない。
本当に怖いと思いました。
世界中、日本中がパニック状態でしたね。
シングルマザー、田舎から都会へ進学した学生、不定期労働者・・・
弱いものに皺寄せが行き、
若者に特に女性に自殺者が激増したと聞きました。
その一人が杏さんだったのですね。
その日暮らしの社会の底辺で地を這うように生きてきて、
やっと多々羅(佐藤二郎)やジャーナリストの桐野(稲垣吾郎)に、
定職を見つけて貰い、多々羅のヨガ教室や勉強も習い、
立ち直りつつあったのに、
コロナ禍がその希望も奪った。
弱肉強食。
弱者は死ぬしかないのだろうか?
あまりにも不公平な社会だ。
私達が知るべき現実
ありきたりの悲劇を並べただけの薄い作品ではない。お涙頂戴でもない。日本の暗部にしっかりとスポットライトを当てた硬派な秀作だと思う。殆ど報道されないが、こうした悲劇や貧困は私たちの周りに確かに存在する。その深刻さを思うと、軽々しく「鬱映画」「胸糞作品」などと言うべきではない。
主要な脇役に有名俳優を起用したのも、けっして口当たりの良さだけではない。人の良さそうな人物が実はそうでもないという設定は、私達も知らないうちに加害者になっているという現実に他ならない。
また、コロナ禍がいかに過酷だったかを振り返る作品でもある。「リモートワークが根付いただけ」の人も多いだろうが、当時、派遣や非正規の労働者達がどれだけ犠牲になったか。それを伝える作品でもある。
令和の山口百恵
無理のない描写、リアルすぎるほどの演技
河合優実が上手い、入江さんの演出上手い
リアル過ぎてつらい作品でした
教育も受けれずここまで過酷な生育と薬物と体を売る仕事に身を置く少女
それでも望みを抱いて介護の仕事を始めるが…ろくでもないコロナ
どこにぶつけていいか分からない程の悲しみや怒りしか残らない作品でした
まずは毒母を張り倒したい!!
ブルーインパルス*⋆✈︎飛行時は天気のいい日、仕事中で高層ビルから見ていました
杏ちゃんも見てたのかな…
凄い俳優さんでてきましたね、河合優実のこれからが楽しみです✨
山口百恵を彷彿とさせますね
シャブ漬けのマリア
毒親にタカられ12歳でウリをやらされたあげく、ヤクザの客にシャブヅケにさせられた“杏”には、実在のモデルがちゃーんといるらしい。入江監督曰く、既に亡くなっているため反論すらできない故人を弔うためにも、丹念なリサーチを行い、ウソがないよう事実に則したリアルな演出を心掛けたという。
ゴミ屋敷のようなアパートで「杏ちゃんお帰り」としか言わないばあちゃん、そして自らもウリをしていて杏のことをなぜか「ママ」と呼ぶ毒親(河井青葉)と暮らしている主人公の杏(河合優実)。ラブホテルでプレーの直前、シャブの過剰摂取で客が意識不明になったことから警察の取り調べを受けるはめになった杏は、そこで一風変わった刑事多々羅(佐藤二朗)と知り合う。
この多々羅、杏がしゃぶ抜きのために必要なプロセスを、ドが過ぎるほど熱心に教え込もうとするのである。ヨガ教室、カウンセリング・ミーティング、特例アパート、夜間学校から仕事のお世話まで、一刑事の範疇をゆうに越えた援助によって杏を更正の道へひたすら導こうとするのである。それを傍らから見守っていた雑誌記者桐野竜樹(稲垣吾郎)は、そんな多々羅の行動を時折醒めた眼で見つめるだった.......
最低最悪の生活から逃げ出すことに成功し、杏の生活が順回転しだした途端、神はまたしてもコロナ禍という試練をこの杏にあたえたもうのである。同じアパートに住むシングルマザーから突如として押し付けられた幼児の面倒を慣れない手つきで見る杏の姿が“聖母”に見えた、と誰かが書いていらっしゃったが、ウリをしていた元娼婦、そして毒親から呼ばれていた“ママ”という称号からして、入江監督はこの“杏”を“マグダラのマリア”として演出しようとしたのではあるまいか。
そのマリアならぬ杏を救った多々羅はおそらくキリストで、そのキリストを裏切った竜樹はユダをモチーフにしていたのではないだろうか。多々羅が警察に逮捕されるまでは、一応聖書の記述にそった展開になっていたのだが、オープニングとリンクしたラストはあまりにも救いが無さすぎる。おそらく事実はそうだったのかもしれないが、マグダラのマリアこと杏に(ウソでもいいから)もちっと救いを与えてもよかったのではないか。あのブニュエルだったらどんな終わり方にしただろう、見終わった瞬間そんな考えがふと浮かんだ作品だった。
⭐︎4.0 / 5.0
きっつー
重い
実話をもとに製作された作品
親という絶対的存在
そのしがらみはお互いが持っているものというよりも自分で持つか持たないかを決めることができると思う。
杏の弱点 祖母のこと
それを熟知する毒母は、祖母を理由に杏を自宅に戻そうとする。
目的はお金
「早く金作って来いよ」
「さっさと体売って来い」
どんな親でも子によっては唯一無二の存在。
最初に見た存在に付いて行くアヒルと同じ本能
親との決別を選択できても、それが大きな足かせのようになってしまう。
それをすることは大きな罪悪感を伴う。
後天的後付けの理由はあるが、心に大きな針が刺さったようになる。
それはかなり難関であるのは間違いない。
実話…
しかし、何故そこまでしてこの世界は杏のすべてを奪うのだろうか?
確かに毒母にそそのかされて自宅に戻ってしまったことが失敗だった。
それをさせた再会という皮肉
それはもう罠でしかない。
売春
児童相談所に子供をもっていかせた毒母
包丁を持ってもできなかったこと
杏は実家を飛び出した後、そしてまた売春してシャブを買ったのだろう。
日記に書こうとした×印に、過呼吸になる。
コンロで日記を焼く。
日記に書いていたハヤトのアレルギーの記録を取り出したのは、ハヤトとの生活にあった希望に違いないが、それはもう無意味なことになっていたことに改めて気づいたのだろう。
シャブが思考を朦朧とさせている。
外に見える青空
そこに登場したジェット機
コロナ渦と1年遅れの東京五輪に花を添えたブルーインパルス
2021年7月23日
すべての絶望を抱えて杏は飛び降りた。
これが、現実に起きたこと。
多々羅という刑事
彼の闇を暴こうとするライター
結局あの記事がサルベージを潰し、杏を自殺へと誘ってしまったと嘆くシーンがあるが、毒母との偶然の再会があることから、杏の逃げ道はなかったのではないかと想像する。
このライターと刑事の設定の半分以上はフィクションだろう。
早見あかりさんの役もまたフィクションだと思う。
しかし、杏という人物がそうした人生を送ったのは事実だ。
助けてくれる人々はたくさんいる。
どうにもならないことはないと思いたい。
アノニマス集会
駆け込み寺のような施設
杏にも優しい職場
東京には確かに何でもある。
でも東京にしかないものも多い。
狭い東京の地
偶然の再会は狭い中で毎日起きている。
もし杏が地方で新しい生活ができていればそんなことにはならなかったように思う。
環境の所為にはしたくはないが、どうしてもそこが盲点だったと考えてしまう。
この作品で自殺した杏
彼女が結局その方向に向かわざるを得なかった原因こそ、「親」というしがらみを自分自身で断つことができなかったからかもしれない。
多々羅という人物がしたことは結局杏との連絡を絶つことにつながった。
あの記者の役割である仕事の所為で、アノニマス集会が潰れた。
コロナが仕事を奪った。
しかし結局のところ、杏自身を貶める原因の毒母の言葉に従ったことがすべての元凶だった。
最後は自分で判断するしかない。
自分で決断し選択しなければならない。
いったい誰に責任があったのか?
この作品はそれを視聴者に考えさせている。
結局それは、自分自身にあった。
この作品はそれを伝えているように思った。
救い無き映画第二弾
全395件中、161~180件目を表示