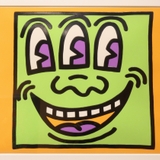TATAMIのレビュー・感想・評価
全102件中、21~40件目を表示
案外知られていないイランの暗部
私たちはロシア、北朝鮮、中国の暗部は良く知っているが、イランにもこうした秘密警察がいて、国民を縛る体制であることをあまり意識していない。いわば自分と家族の人生を賭けて国禁を犯しても皮肉な結果に終わるストーリーは、ズシリと心に響く。それにしても国際スポーツ団体もこういうややこしい、いや、危険な事態もあり得るなかで、それに備えるとは大変だなと痛感した。よくできた人間ドラマ。
なんのための闘いだったのか…
柔道の世界選手権、勝ち抜き戦の最中に政治的な配慮で発せられた祖国からの指示に翻弄される選手、監督、家族の姿を描いています。
事態を察してできる限りのサポートを試みる世界柔道協会のスタッフたちを交えて、容赦ない試合の進行を緊張感に満ちたモノクロの映像が追います。
尖ったカメラワークが緊迫感を更に煽ります。
そして…
観客という第三者の目線で観たこの闘いはいったいなんだったのか、徒労感しか感じられません。
けれど当事者にとっては絶え間なく迫られる決断の一つ一つに力の限り立ち向って手に入れた勝利なのかもしれません。
観終わった後で想いました。
これが女子選手権でなく、選手も監督も男性であったなら、また違う展開、違う感情があったのだろうかと。
イスラム教国での女性の立場を斬新な視点で描き出した傑作です。
息をもつかせぬ2時間でした。
柔道家として単に見ただけだったが、圧巻の映画だった
世界大会において勝ち進む中、政府から負けるよう指示されたイランの柔道家を描いた映画、TATAMI。政治や宗教とスポーツが絡むことのない日本人にはとても新鮮で迫力ある映画だった。柔道に興味がない人にも見て欲しい映画。
特に彼女が試合中に頭のヒジャブを外すシーンは、目の前の試合に全力で臨む覚悟が感じられ最高だった。
余談にはなるが、一回目の計量失格のシーンは何のためのシーンだったのだろうか笑
肉を切らせて骨を断つ
かつてない緊張感
すごく緊張感あふれていて、観ている最中は手に汗握って、冷や汗と鳥肌に襲われました。
怖いし腹が立つし可哀想だし。
スポーツ選手として勝敗に賭けるギリギリ感が、政治的恐怖に塗り替えられていき、家族が人質にされ棄権を強要され、最後には自分自身の命さえ危ぶまれる展開。
大使館の職員や外交官たちに捕まらないように逃げるところなどは、『アルゴ』を思い出したりもして。
本作は、実際に起きた事件を基にしているらしいです。
女子柔道選手レイラ・ホセイニとして描かれてしましたが、イラン出身の男子柔道選手で2020 東京五輪の銀メダリストであるサイード・モラエイの身に起きたことを、そのまま映画へ落とし込んだそうで。
理念上かつ建前では、政治とスポーツは別と言うのが原則ではあるものの、独裁的宗教指導者が支配する国では絵空事に過ぎず、選手は国の駒であって人権などないものとして扱われ、一種の代理戦争的な意味合いすら持つという現実をまざまざと描き出していました。
自分的には「すごい」とひたすら賞賛。
映画好きなら観ておいたほうがいい、とお勧めします。
スポーツと政治 アスリート目線の緊迫感
政治色には染まりません‼️
イラン代表として女子世界柔道選手権で順調に勝ち進むヒロインが、政府から敵対国であるイスラエルとの対戦を避けるため棄権を命じられる・・・‼️自分自身と人質に取られた家族に危険が及ぶが、ヒロインは自らの自由と尊厳のために試合に出場し続け、決勝戦で敗れて政府に連行される‼️それでも国籍を捨て難民グループとして国際試合に出場するヒロイン‼️己の信念に従い、スポーツマンシップを発揮するヒロイン‼️なんか「炎のランナー」を思い出させる秀作‼️まるでヒロインの心情を反映したような、薄暗いモノクロ映像も印象的ですね‼️
闘い続けることの意義
実話なんですね。余りにも理不尽な話なので、世の中の不条理を象徴する、寓話だと思ってました。スポーツに政治を持ち込むな、の建前すら持ち合わせない現実のほうが、作り話みたい。
チラシ見て驚きました。この映画に参加したイラン出身者が、全員亡命。この出来事だけで一本、ドキュメンタリー映画いけますね。
みんな、闘い続けているんですね。
そんな、やりきれない世界だからこそ、このチラシに記載されたメッセージが、刺さります。
全てのアスリートが、自由でありますように。
ついでに全ての映画人も、自由でありますように…。
きっと、この映画創った方は、生まれ故郷を大切にしたいんですよね。だからこそ、欺瞞と抑圧に満ちた現状と、闘い続けるんですね。
多くのものを手にするには、多くのものを手放すことになる。故郷で映画製作を禁じられ、海外で活動される方は、けっこういるそうです。
クニを憂うが故に、クニを棄てる
されど、残された家族への想いは…
政治家の悪口、いくら言っても逮捕されない私からすると、想像すらできない場所で、闘い続けるヒトがいるんですね。
私は、何を手放し
何を手に入れようとしているのだろう?。
え?、そもそも闘っていないって?。
これは、一本取られましたね~。
皆様のTATAMIは、何を求める闘技場ですか?。
人々の結束も分断も産む国境
女子柔道の世界選手権において、国家承認していないイスラエル選手との対戦を避けるべく、イラン政府が自国の選手に対して棄権する様に圧力を掛けるという実話に基づく物語です(本作のモデルとなったのは男子柔道選手でしたが)。
この大会の為に厳しい練習を積み、絶好調だったイラン人選手は順調に勝ち進むのですが、イランの柔道協会から棄権しなければ家族の身の安全は保障できないとの連絡が入り、棄権を訴える父母の映像も添えられます。更にその脅迫は監督にも及ぶのです。激しい動揺を抱えながらTATAMIの上で繰り広げられる対戦の映像はスピーディーで迫力もたっぷり。絶対に危険などしたくない、でも家族の安全は・・イスラエル選手が勝ち進むとは限らないからその結果を待ってもよいではないか・・様々な要因が絡み合います。スポーツ映画と政治映画が混じり合い、時限爆弾を抱えた様な緊迫感を盛り上げるのです。
こうなると、本作のモデルとなったイラン人柔道家のサイード・モラエイがこの選手権をどう戦い、その後どうなったかを知りたくて調べてみました。2019年の東京での世界選手権81キロ級で彼は準決勝に進出しながら、急に心ここにあらずという戦いぶりで敗れてしまいました。その試合では、監督もコーチも会場から退席していました。つまり、国からもチームからも見捨てられていたのです。この時、イスラエル人選手は決勝進出を決めており、モラエイ選手が準決勝で勝っていればイラン対イスラエルの対戦が実現する筈でした。大会後、彼はイランのスポーツ大臣から棄権を強要された事を明かし国を捨て、現在はアゼルバイジャンの国籍を取得しているそうです。また、2020年の東京オリンピックでは銀メダルを獲得しています。
国境というのは、その内側で暮らす人々の強い結束を生み出す一方で、愚劣な分断線にも成り得るのです。
畳
礼節を重んじる柔道家であり、美しい妻であり、愛情深い母でもある。一人の女性の芯の強さと人生を賭けた決断をたった1日の出来事を通して描き出す。めちゃくちゃ良かったです。
柔道世界大会で予想外に勝ち上がってゆくイランの選手が、敵国であるイスラエルの選手との対戦を避ける為に棄権するよう政府から圧力をかけられる。首を縦に振れば国に帰って家族と暮らせる。拒否すれば全てを失う。万一に備えて万全の包囲網を敷いていた政府側の本気度。この用意周到さ。まるであらゆるスポーツで幾人もの選手に行ってきた所業だとでも言うかのように。
この展開なら最後の1カットはカラーになるのかなって思っていたけど、モノクロで通したところに、そんな簡単なことじゃないんやぞと諭された気がした。残念ながらスポーツも政治に利用される。一番被害を被るのはもちろん選手だ。
イランは自由が無く女性が生き難い国と プロパガンダ映画とも見れる
一応、女性柔道選手が、いろんな妨害に合いながらも、頑張る姿。
柔道の国際試合ひとつとっても、まったく なんのしがらみもなく 出来ることは 無く、
過去には オリンピックも 政治利用されてきた。
しかし この映画で 感じたのは イランを下げる プロパガンダ映画にも 感じる。
毎年 反ナチス映画が 繰り返され、ユダヤ人の洗脳が いきわたっているが。。。
気迫が凄い。
TATAMI
スポーツマンシップ
柔の道に政治は介入してはいけない
映画は白黒映像。全編のほとんどが畳(TATAMI)の柔道競技場でのリアルな試合と控え室での緊迫なやり取り。テーマは政治のスポーツ介入。それも執拗なまでの暴力的な介入である。
映画は2019年、武道館での世界選手権で実際に起きた理不尽な事件にインスパイアされ、更には2022年、イランで起こったマフサ・アミニ事件(ヒジャブを適切に被らなかったことを理由に拘束され死亡した事件)にも触発されたとのことである。同時期に公開されてる「聖なるイチジクの種」に引き続きイランという強権的な国家の実像を見せつけられた。又同じように映画は秘密裏に制作されスタッフは亡命してるとのことである。
イランはイスラエルを国家と認めていないので、そのような国と戦わないということなのか、戦って負けたりしたらシャレにならないからなのか、よくわからないが、スポーツマンシップというものを最高指導者が理解しないなら国際的な舞台に参加する資格はない。
イランもパレスチナもイスラエルも戦争や紛争に巻き込まれ被害に合い抑圧に苦しんでるのは国民である。解決の方法は極めて難しいのはわかっているが、いつの日かどの国も民主的な普通の国になってもらいたい。
主演のマリエンヌ・マンディは中東にルーツがあるアメリカ人。Netflix「ナイトエージェント」でもアメリカに亡命するイラン人を演じていたがこの映画では本物の柔道家の如く迫真の演技であった。共同監督を兼任したザーラ・アミールも苦悩の柔道チームの監督を演じ素晴らしかった。2人合わせて主演女優賞を贈りたい。
全102件中、21~40件目を表示