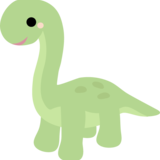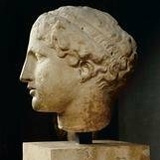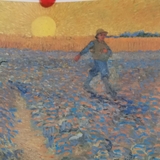TATAMIのレビュー・感想・評価
全102件中、1~20件目を表示
柔道シーンの迫力
国際政治に翻弄されるスポーツ選手の物語である。そのため、見どころは大きく2つ。政治的な駆け引きと翻弄される主人公といかに国の圧力から脱するのかのストーリーと、本格的な柔道バトルだ。
カメラは、手持ちで主人公をどこまでもついて行くタイプの撮り方。そのため、観客は主人公と同じ状況に放り込まれて、突然国の諜報部みたいな連中が圧力をかけてくるところに遭遇させられる。孤立無援の状況の中で、試合もこなさないといけない、しかも、国では家族にも危機が迫っている。目の前の相手とそれ以外のものとも主人公は戦う必要があるという緊迫した状況が続く。
そして、柔道シーンがすごく本格的なのがいい。カメラも近接ショットが多くて、迫力満点。組み合う選手たちの必死の形相がこの格闘技の激しさをよく伝えている。
苦難を乗り越え、戦い続ける主人公がカッコいい。スポーツはとかく政治に翻弄されてしまうものだが、純粋な戦いだけを臨むアスリートの情熱が政治を乗り越えていく姿には感動を覚える。
小粒だが痺れる。モノクロームが技と運命の決断を際立たせる
小粒ではあるが痺れる映画だ。モノクロームで織りなされた映像が、柔道の国際大会ほぼ一か所に限定された舞台の息苦しさと緊張感に拍車をかける。まさかこの場所、このタイトルから、イラン代表の女性選手をめぐる政治サスペンスが勃発するなんて誰が想像しただろうか。助けてくれる者なんて側にはいない。それどころか工作員のような連中まで控室まで易々と入ってくる。そんな状況に主人公がたった一人で抱え込む葛藤。その感情を全て投げ打つかのような畳上での気迫。「一本!」の声が響く時の沸き立つ高揚。余計な色を削ぎ落としているがゆえに、彼女が下す決断の数々が際立つ。その集積の上に彼女の命運とアイデンティティが築かれていくのがわかる。そして繰り返される歴史の鎖を象徴するかのような専属コーチの葛藤も本作のもう一つの魂。同役を演じ共同監督を兼任したザーラ・アミールの実人生が、本作に言い知れぬ力強さとリアリティをもたらしている。
スポーツ・格闘技としての面白さと、国家からの抑圧に抗う人々を描く社会派サスペンスの意義を両立させた傑作
日本発祥の柔道を題材にワールドクラスの傑作映画をイスラエルとイラン(系)が中心の製作・出演陣が作ってくれたことに、率直な感謝と軽い嫉妬(なんで邦画でできなかったんだろうという)が入り混じった思いを抱いた。
映画の重点は柔道そのものよりも、国の抑圧的な干渉に抗う代表選手と板挟みになる監督に置かれる。とはいえ、トーナメント形式で進行する国際大会の一日をほぼリアルタイムで追う大筋の中で、数試合のシーンは臨場感と迫力に満ちている。撮影上のテクニックと工夫が駆使され、激しく組み合う2人をカメラが近い位置からぐるりと回って収めたり、抑え込まれてうつぶせの主人公の苦し気な表情を畳側から(!)とらえたりする。
主人公のイラン代表選手レイラ・ホセイニを演じたアリエンヌ・マンディは、チリ人とイラン人の親を持つ米国人女優。ドラマシリーズ「Lの世界」の主要キャストとして知られる。本格的にボクシングに取り組む姿が短編ドキュメンタリー「Arienne Mandi | Why I Fight」(2022)になるなど、格闘技の選手役に最適なキャスティングだったようだ。
企画の始まりはイスラエルのガイ・ナッティブ監督からだったが、「聖地には蜘蛛が巣を張る」の女優ザーラ・アミールにまずガンバリ監督役をオファーし、キャスティングと脚本への彼女の協力を経て、共同監督としてのコラボに至ったという。「聖地には~」で書いたレビューから長めの引用になるが、「ザーラ・アミール・エブラヒミはイラン出身の女優で、2000年代に同国のテレビドラマなどで人気を博するも、06年に元交際相手と彼女の性行為を撮影したものだとされる動画が流出してスキャンダルに。エブラヒミに非がない上に動画の真偽も定かでないにも関わらず当局から収監されるリスクが生じ、08年にイランを脱出してパリに移住(後にフランスの市民権を得ている)」。体制と男性優位社会から抑圧され亡命したザーラ・アミールの経験が、本作にも確かに反映されている。
スタンダードサイズ(1.33:1)のモノクロ映像は余計な情報を排除し、試合中の選手らの動き、人物らの表情に観客が集中するのに大いに役立つ。さらに、国の関係者らから棄権するよう命じられ追い詰められるレイラとガンバリの閉塞感も効果的に表現している。
人権、とくに女性の人権を尊重せず抑圧するイランの体制を批判する映画の日本公開が、2週間前の「聖なるイチジクの種」、そして本作「TATAMI」と相次ぐ。国の強大な力に、表現というソフトパワーで立ち向かうイラン(系)の人々の映画に、「柔よく剛を制す」の精神を見る思いがする。
国家権力という反則技に対し、彼女たちは畳上で聖なる闘い
奇しくも続けてイラン政府の国家権力と圧力を批判した作品を。
『聖なるイチジクの種』は実際の不審死事件から成る殺伐とした国内の情勢や家族の崩壊を恐ろしく描いたのに対し、こちらは実話ベースでスポーツ映画として。
どちらも訴えは痛烈だが、見易さ分かり易さではこちらの方に一本!
ジョージアで開かれている女子柔道の世界選手権。
イラン代表のレイラは監督のマルヤムと二人三脚で順調に勝ち進み、金メダルも見えてきた。決勝で闘うであろう相手は、旧知のイスラエル代表。
決勝前に、イラン政府から連絡が。イスラエルとの試合を避けるべく、棄権しろと…。
無論マルヤムは拒否する。金メダルを取れば個人や国民や国の為になる。
が、当局は有無を言わせない。従え。さもないと、自分や家族がどんな目に遭うか分かってるんだろうな?
個人の意見など聞く耳持たない強要にゾッとする…。
やむなく従わざるを得ないマルヤム。事情は伏せてレイラに棄権してと伝えるが…。
勿論レイラは納得出来ない。理由を聞いてもマルヤムは答えを濁す。
無視して次の試合へ。不満が怒りの力になったのか、勝ち上がり、また次の試合へ進む。
試合を見て当局からマルヤムに怒りの連絡。説得しても聞かないと言うマルヤムを無能呼ばわり。
当局は強行に。会場に“犬”を派遣。2人の家族にも圧力。
家族から非難轟々。愚か者、恥を知れ。
国際大会に出場したら称えられる筈が、下らぬ理由で責められるなんて…。見ていて痛ましい。
レイラも事情を察する。それでも金メダルを目指し、試合に出場。
が、動揺や影響は隠せない。これまでの奮闘から一転、大事な準決勝で苦戦を強いられ…。
行政や一個人だけではなく、スポーツの場にまで介入してくるとは…。
レイラは準決勝で負けてしまう。本来なら金メダルを目指せたのに…。それを閉ざしたのは誰(何)だ?
試合終わってからマルヤムに当局が迫る。マルヤムは逃げる。
試合後の大事と治癒で入院中のレイラ。彼女にも当局が迫るのは必須。
マルヤムはレイラの元を訪れ、ある提案。国を脱出する。
究極の選択。国に留まり服従し厳しい処遇を待つか、国を捨てもう家族には会えぬが個人の自由や尊厳を取るか…?
2人が選んだのは…。
残したメッセージが沈痛。
その後レイラは難民チームとして再び国際大会の場に。その時の対戦国がイランという皮肉…。
アリエンヌ・マンディとザーラ・アミールの熱演。白黒映像による試合シーンは迫真。
ザーラ・アミールは監督も兼任。ガイ・ナッティブと共同監督。映画史上初めてイラン人監督とイスラエル人監督の共同作。
個人や文化では国と国は繋がれるというのに…。
作品に参加したイラン人は皆亡命。『聖なるイチジクの種』同様、作品はイランでは上映禁止。
日本発祥の柔道。
畳の上で行われる試合は神聖にして正々堂々。
そこに国同士の事情や権力を持ち込むな!
スポーツマンシップ…いやそれ以前に、ヒューマンシップに反する。
イラン政府はバカなのか?
judoと政治
アメリカイギリスイスラエルジョージア合作映画で、イスラエル人のGuy Nattivと聖地には蜘蛛が巣を張る(2022)で主役を演じたイラン人女優のザーラアミルエブラヒミが共同監督をつとめており、イスラエル人とイラン人がはじめて共同監督した映画とのことでした。
イランの女子柔道選手がイランではイスラエルとの公式対戦が禁止されていることから、試合を棄権しろと命じられそれに反抗したことで監督と共にイランを追われる(フランスへ亡命する)という話でした。
白黒で始まる雰囲気はとてもいいです。たとえが適切か自信はありませんがベルイマンみたいです。
しかし柔道の試合はリアリティを欠き実況は野球のようです。選手は合間にスマホで家族と連絡をとったりしています。監督と選手が対立するシナリオも妙な感じでした。
メッセージは直截的で要はイランはひどいですと主張する映画になっていて、むろんかれらの陥った状況は理不尽ですが、それがどうした感はありました。それがどうしたとはイスラム世界のルールが往々にしてそれ以前の問題をもっているからです。すなわちイスラム世界に女として生まれたならば、すでに多くの枷を背負っているのであり、それらは柔道以前の問題です。例えばまずそのヒジャブをどうにかすべきであり、すべてがそれ以前の問題に見えた結果、かれらの悲しい境遇もそれがどうしたという醒めた見え方になってしまったのでした。
ただし製作者らは映画が社会的なメッセージをもっていることを自覚しており、おしつけがましさを軽減するために白黒にしてタイトルもTATAMIにして、客観性や詩的情趣を醸成しようとしています。カメラもよかったです。が、映画には「頑張っている選手に棄権しろなんて、なんてひどいんだイラン政府」という印象以上のものはなかったと思います。
共同監督兼“監督”役のザーラアミルエブラヒミは上手でしたがセリフが悪く素人みたいなアドバイスしか飛ばしません。選手役Arienne Mandiは役の設定もありますが良くなかったと思います。
とはいえメッセージには切実なものがあり批評家評も世評も高評価でした。
imdb7.4、rottentomatoes94%と96%。
個人的にはけっこう浅い映画だと思いましたが、重い主題とタイトルのTATAMIと白黒が効いた、という印象でした。
もちろん映画が内包している志に文句はありません。じっさいにイランからフランスに亡命したザーラアミルエブラヒミの実体験も投映されていると思います。
イランでは2022年9月にヒジャブを適切に着用していないという理由で当時22歳の女性が逮捕されその後死亡した事件を受けヒジャブ着用をめぐるデモが全国的に拡がりました。映画にもあるレイラがヒジャブを外して試合に挑むシーンはそうした抗議運動の延長にもあったと思います。
ただ前述したとおりイスラム世界をかんがみたときに思うのは、おおもとの経典が女性を不平等に扱っているのなら、なにもかもそれ以前の問題だということです。
「製作に参加したイラン出身者は全員亡命し、映画はイランでは上映不可...
「製作に参加したイラン出身者は全員亡命し、映画はイランでは上映不可となっている」か。強烈。
今日のキネカ大森は、「イランの中で声を上げる女性たち」、重たい企画だよね。でも2本とも面白かった。やるな、イラン。でも撮った監督はみな(亡命して)イランからはいなくなっちゃうんだよな、というジレンマが悲しい。
俺はキリスト教であれイスラム教であれ「原理主義」という宗教のスタイルは好きではない (原理主義:聖典の説くことは文字通り真実だと信じ、そのように生活する態度)。キリストもムハンマドといった教祖たちも「おいおい。俺の時代だから必要あってこうしたのであって、盲目的に信じず自分の時代にあった解釈をしてくれよ」と言うんじゃないかと思うんだよね。
もちろん心が弱った時に拠り所となる宗教の計り知れない価値はわかってるつもり。その面では「その都度自分で考えろ」は冷た過ぎて、揺らがない確固としたものであるべきというのもその通り。心が弱ってない人たちの日常の行動様式まで、過去と同じにしようと考えることが好かないだけです。なので、俺はイランの今の体制にも冷たい対応になる。
と余計なこと書いちゃったけど、本作はある世界大会のたった一日(実際には2日かな?)で、限りない緊張感と圧倒的な無力感を与えてくる。
国の代表として闘うのに、国(ここでは国民ではなく集権主義国家の政治体制、かな?イランなら指導者か)
おまけ1
コーチ、監督だったんですね。すごいな。
TATAMI
前半は見えてしまう展開で、これ星★の作品かな?と思いました。
もう脅かして、残り90分どーすんの??と。
それに抗うスポ根的な作品かと思いました。
で、例によって「思ったのと、違う」でした。
スゴく政治色の強い、ヒューマンドラマ(ニセモノの)。
国や宗教に虐げられながらも、自由を求める人達。
親を人質に取られても、なお、
てな、観るべき映画なんです(ニセモノの)。
作品として、フィクションとしては面白い映画です。
ここからは、ニセモノに言及します。
イス〇エルの監督が、アメリカ映画でイ〇ンを批判したら、もう娯楽ではありません。
事実に基づこうが、必ず作り手は都合良く解釈します。
イ〇ンばかりじゃありませんよね?
かの大統領の出現で、アメ〇カも、もはや自由の国じゃなくなった。
不倫して尚、政党の代表に居座るこの国の政治家。
キックバックが当たり前の政党。
でも、列挙した国々よりも、この国はまだまだマシなのかな?と、思う帰り道でした。
簡潔を旨としてるのに、思わず長くなりました。
見て下さる方々、スミマセンでした。
スポーツ × ポリティカルサスペンス
政府から、敵対国であるイスラエル選手との対戦を避けるため、棄権を命じられるイランの柔道選手だが、好調で優勝も狙えそうだし棄権を拒んで試合を勝ち進んでいくと、家族に危機が迫る…
俄かに信じがたい展開なのだが、2019年の世界選手権で実際にあった事件を元に製作された柔道映画(男子選手から女子選手に変更)であり、イランでは上映禁止かつ映画に関わったイラン人の関係者も国外亡命したとのこと。
国による圧力は、今回の件だけではなく、ヒジャブ着用強制など日常生活にも及んでいることが、迫力ある試合シーンの合間に描かれるのだが、ハラハラドキドキそして涙と、想像していた以上にヨカッタ作品でした。モノクロかつ地味な作品で見逃しがちだけど、必見!
不屈の魂に感動
イランはイスラエルとは政治的に対立しており、今回のような国際的なスポーツ大会では極力両国の代表選手を戦わせないようにしているそうである。これは”イスラエル・ボイコット”と言われており、wikiにも詳しく書かれている。鑑賞後に読んでみたが、こうした例は過去に何度もあったということで驚いてしまった。
本作はそんな事例の一つ、2019年に東京で行われた世界柔道選手権をモチーフにして作られた作品ということである。
物語は基本的にレイラが金メダル獲得を目指すスポーツドラマの体で進む。しかし、本作はそこに様々な要素が入ってきて物語を豊穣なものにしている。
その一つは、イラン政府からの棄権要請に抗うポリティカル・サスペンス的要素。もう一つは、レイラと夫と息子の絆を描くホームドラマ的要素である。この二つがレイラの戦いに掛け合わさることで、意外性に満ちたドラマが展開されていく。
また、最終的にイラン政府に対する痛烈な批判を浴びせており、社会派的な気骨ある作品に仕上がっている点も注目に値する。
映像はモノクロームで統一されており、シリアスな物語同様どこか厳粛な佇まいを見せている。
また、ドキュメンタルなカメラワークは、キャスト陣の生々しい表情を拾い上げ、スリリングな緊張感を上手く醸造していると思った。
中でも、特筆すべきは試合会場の照明効果で、観客席がほぼ真っ暗で何も見えないという状況が続くことである。予算の関係でエキストラを用意できなかったことによる苦肉の策だったのかもしれないが、かなりシュールな光景で、これがちょっと寓話的なテイストを持ち込んでいるのは面白い。
試合シーンもふんだんに登場してくる。手持ちカメラで泥臭く活写しながら、ドライヴ感溢れる映像が貫かれている。引きの映像が少ないのは、若干物足りなく感じたものの、変に小手先のテクニックに走らなかったことは良いと思った。
今作で一つ難を言えば、終盤にかけてクローズアップされるマルヤムの葛藤であろうか。それまではずっとレイラの葛藤を中心に物語が進むので、どうしてもここが弱く感じられてしまった。二人が取っ組み合いのけんかをするシーンが出てくる。ここをターニングポイントにしたかったのかもしれない。しかし、それも付け焼刃という感じがしてしまった。ここが更に熱度高く決まれば、その後のマルヤムの葛藤もすんなりと響いて来ただろう。
キャストでは、レイラを演じたアリエンヌ・マンディの熱演が素晴らしかった。権力に決して屈しない姿にはおのずと感情移入もさせられる。特に、夫からの励ましの電話を受けるシーンにホロリとさせられた。
脅迫する原理主義独裁の害悪
最初ザーラ・アミールは、マルヤム・ガンバリ役での出演だけを
ガイ・ナッティブから打診されたんだが、
そのキャラクターがシンプル過ぎるので、これでは演じられないと言ったところ、
共同監督の提案があったので引き受けたんだそうな。
亡命して15年経つとはいうものの、どんな危険が及ぶか分からない中、
勇をふるって世界に問いかけた作品。
なお、レイラ・ホセイニ選手を演じたアリエンヌ・マンディは、
ロサンゼルス生まれのアメリカ人女優。
柔道は未経験にもかかわらず練習を重ね、
映画の中でスタントなしでたたかった相手は
すべてオリンピック級の選手だという。
* * *
事実に基づいた映画ではあるけど、実際に
「イスラエルと対戦する可能性があるから
棄権しろと言われた」と告白したのは、
世界柔道選手権2019年東京大会での
サイード・モラエイ選手(男子)。
それまでもイランの選手は、柔道に限らず、
不審な棄権が多いと言われていた中、
彼が初めて暴露したんである。
棄権させてまでイスラエルと対戦させないのは、
イスラエルを国家として認めていないから
というだけの理由。
しかも、国に残る家族を脅迫。
下手すりゃ拷問。
(つい最近も、イスラエルの選手と握手して一緒に写真を撮ったイランの選手が、イランから「永久追放」になった)
原理主義独裁の害毒、ここに極まれり。
この映画では女子に置き換えて、
イランにおける女性の立場、という要素も加えている。
「事実に基づく」は要ファクト・チェック(追記有)
◇ 映画に対する共感とその印象
映画『TATAMI』は、国家からの抑圧に苦しむ選手の姿を描き、観客に強い感情的な共感を呼び起こす。試合の視界の狭さやモノトーンの映像は、選手の精神状態や国家の閉鎖性を象徴しているとも読み取れる。
◇映画の背景とモデルとなった実際の出来事
映画の舞台は2019年の柔道世界選手権だが、劇中の設定(女子60kg級)は実在せず、実際には男子81kg級のイラン選手サイード・モラエイがモデルとされる。映画は事実を大きく改変しており、観客の印象に影響を与える作りとなっている。
◇ 映画の脚色と現実との乖離
劇中ではイスラエル選手との対戦が実現しないが、実際にはイスラエルのサギ・ムキが優勝しており、対戦の可能性は現実的だった。さらに、イランはすでに世界選手権で金メダルを獲得しており、「初の金メダル候補」とする描写も事実と異なる。
◇イランの対イスラエル政策の背景
イランがイスラエル選手との対戦を拒否する背景には、イスラエルを国家として承認しないという一貫した外交方針がある。これはイスラエルの建国経緯やパレスチナ問題、欧米主導の国際秩序への不信感などと深く結びついている。
◇ 国際政治とイランの対外姿勢
イランの頑なな姿勢は、欧米の干渉や制裁への反発、イスラム革命の歴史、英米の石油利権確保に対する記憶が影響している。こうした背景を無視したままイランを一方的に非難するのは表層的な理解に過ぎない。
◇主人公がパレスチナ人だったら
イスラエルの徴兵制やガザへの攻撃を踏まえると、イスラエル選手の「無邪気な対話」も再考が必要であり、友情美談には疑問が残る。
◇必要なのは体制批判ではなく対話
柔道に対する外国人選手の尊敬の念に学び、体制批判ではなく対話を通じた相互理解が求められると筆者は主張する
◇ 演出の限界と柔道描写の不自然さ(評価対象外)
俳優の柔道の動きは緩慢で、ウォーミングアップもリアリティに欠ける。試合シーンの完成度は低く、柔道に詳しい観客には演出の甘さが伝わってしまう。
全文はブログ「地政学への知性」で
◇追記
多くのレビューが映画の内容を無批判に飲み込んでいるように感じます。この代表がパレスチナの選手でも同じように受け入れるのだろうか?イランがイスラエルを国家承認していないことを承知しているのだろうか?善良なな多くのイラン人がイスラエルを支援する欧米諸国の経済制裁で市民生活が圧迫されていることも踏まえているのだろうか?国の圧力を擁護するつもりはないが、批判ばかりされて態度をあらためるって人間関係でもう難しいこと。国家だったらなおさらだと思います。
あんなに早い段階で棄権させなくても良いのでは?
ジョージアの首都トビリシで世界柔道選手権が開催された。イラン女子60kg級代表のレイラ・ホセイニは金メダルを目指して順調に初戦を突破。元柔道選手で現在は女子代表チーム監督のマルヤム・ガンバリの指導の元、レイラは次の試合も一本勝ちし三回戦に進んだ。しかし、イランの柔道協会の会長からガンバリに、レイラ・ホセイニ選手を棄権させろ、との電話がかかって来た。
イランにとってイスラエルは敵対国で、このままレイラが勝ち進めば、決勝でイスラエルの選手と戦う可能性が出たため、レイラを棄権させろ、と政府からの命令だった。ガンバリはレイラを説得しようとしたが、世界王者を目指すレイラは聞き入れない。説得を試みるガンバリ、試合に出ようとするレイラ、そしてレイラの家族の所に警察が、会場にはイランの工作員が・・・大会が進行する中、レイラとガンバリは決断を迫られ・・・さてどうなる、という実話を基にした話。
男女、場所の違いは有るものの、2019年8月に日本武道館で行われた世界選手権でサイード・モラエイ選手に対し、イラン政府が圧力をかけた事実をベースにした作品とのこと。モラエイ選手はドイツに亡命し、その後モンゴル国籍を取得し、東京オリンピックで銀メダルを獲得したとのこと。しかし、いまだに家族にメダルを見せる事は叶わず、の状況らしい。
イランの大統領や最高指導者の指示を無視したとあからさまに言ってたから、イラン国内じゃあ上映出来ないだろうなぁと思った。制作に参加したイラン出身者は全員亡命したそうだが、自由の無い国は恐ろしい。
イラン映画ってこんなのが多いけど、特に女性に対する弾圧はこれから少しは改善されるのだろうか。
イランにとってイスラエルが敵対国なのはわかるが、闘いを避ける理由がイマイチよくわからなかった。負けたら大変というならわかるが。仮に接触するだけでもダメだと言うのなら、対戦が決まった時(決勝戦に勝ち上がった時)に棄権を指示すれば良いのでは?2回勝った頃から棄権しろと命令されてたが、早すぎじゃないか?
レイラ・ホセイニ役のアリエンヌ・マンディは柔道経験者じゃないらしいが、カメラワークのうまさも有って、試合は迫力あった。代表監督マルヤム・ガンバリ役のザーラ・アミールも保身に走ってたのに途中からレイラの金メダル取得をサポートしてたし、演技は上手かった。
しょうもないプライド
イスラム社会の変遷を映画通じて学ぶ!
私が私であるための
写されてはいるが、描かれていないものがある。それは、この女が、何故戦い抜くかの理由だ。
夫と子供、両親を危険に晒し、信頼を寄せていた監督にも見放され糾弾される。そんな境遇に突如として陥ってなお、闘おうたするのは何故か、その根底にあるだろうことが語られていない。
語られず、闘い挑み続ける姿のみが写されることによって、この「何故か」の問が、より私達に迫ってくる。
国を追われ、最愛のものたちを危険に晒し、試合に臨むことを監督は「意地っ張り」と称した。そうだと思う。そして、その意地はあまり役に立ちそうもないエゴに思える。
たかだかスポーツ。決まったルールの中で、安全な小さなスペースで、ちょこまか投げ飛ばす、ただそれだけのことじゃないか。
だが、自らが、自らを保つためには、その「たかが」の中で闘わねばならなかったのだろう。自分との鬩ぎ合いは、たかが、というものすごく小さな領域で展開され、その小さな領域は国家や宗教を凌駕することもある。
最後の試合で、髪を覆うマスクを脱ぎ捨てて、髪をあらわにして結うシーンがある。
これが、私だ。国家でもなく、妻でもなく、宗教上のオンナでもない、という表れ。ケン・ローチの私はダニエルブレイクと重なるシーンだった。
自分ならどうしただろう…
序盤から恐ろしい展開。意外な終盤。モヤモヤが残る結末
これは、凄まじい映画。傑作だと思います。
事前知識を全くなしで観たけれど、題名のイメージと違って、サスペンスが縦軸、柔道は横軸の物語。
何故かフランス映画のテイストが香る気がするけれど、アメリカ・ジョージア合作。
イラン政府は、敵視するでしょうね。
序盤から恐ろしい展開。意外な終盤。モヤモヤが残る結末。恐れを知らぬ強いメッセージ。
これだけ手に汗握る映画も久しぶりだった。
本当に面白い。
幸せな一夜になりました。
全102件中、1~20件目を表示