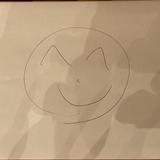小学校 それは小さな社会のレビュー・感想・評価
全106件中、21~40件目を表示
誇るべきことでも卑下することでもない
「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている」は秀逸なコピーだ。
日本は経済規模の割には公教育にお金を出さない国で、公財政教育支出対GDP比はOECD加盟国の中で下から2番目だ。生徒が教室の掃除をしたり、給食の配膳をしたりするのはひとえに金をかけないからであって、生活指導も学校の機能だからというのは国の言い訳に過ぎない。たびたび批判にさらされる、枠にはめたがる画一的な教育も、そこに思想があるというよりも、枠にはめて一律に扱う方が教員の数を少なく抑えられ金がかからないからである。多様性を受け入れるにはコストがかかるのだ。精神論に偏りがちなのもそうだ。要するに「みんなビンボが悪いんや」ということなのだが、結果として、集団性や協調性が身につくと海外から評価されてるというのはなんともこそばゆい。卑下することはないが、決して誇るべきことでもないような気がする。
ただ、教育システムが画一的でも、限られた予算の中で教員たちは悩みながらも連携してよい教育を提供しようと奮闘しているのが画面から伝わってくる。結果、子供の個性はちゃんと様々に伸びる。同じ教育を受けてきただろう教員たちがそれぞれに個性豊かなのが何よりの証拠だ。シンバルの彼女が力不足だったのは入学後から1年間近く見ていた教師は最初からわかっていただろう。それでも、本人の希望に沿ってあえて役を与え、責任感を自覚させ、最後には自信をつけ、やり遂げさせるというのは教育の力としか言いようがない。
フィンランドって幸福の国、サウナ文化の他に教育大国でもあるんですね(笑)
映像資料としてすごく貴重
良くも悪くも集団生活を描く貴重な映像。作りもの感が惜しい
勉強以外の行事や学級の活動が盛りだくさんで、それらが子どもの成長の機会として意図されている日本の小学校。この映画は、集団活動の良さや、若干の弊害に焦点を当てた貴重な映像だ。
ただ特に前半は作りもののように見える場面も多く、ありのままの学校生活を見ている感じがしない。
なぜなのかと考えると、一つに「音」の聞こえ方がある。先生が子どもを指導する声が、遠くに移動した場面でも同じ音量ではっきり聞こえる。これはピンマイクをつけて撮影されているということなのだろうか。
実際の学校ではもっと声が反響してしまったり、子どものざわつきにかき消されてしまったりして、それが学校独特の活気や気だるさにつながっていると思う。この映画の場合、先生の指導内容が明確で、子どものほうも理解しやすく行動する場面が多く切り取られている。つまり「見やすいように撮る」ことが優先され、演技みたいな映像になってしまっているのではないか。
それでも放送委員をしている縄跳びが苦手な男の子のエピソード、卒業式の練習で行動がそろわず叱られる子どもの様子などは現実感があり、映画の見どころになっていた。
クライマックスでは2年生になった子たちが1年生のために楽器を披露する。そこでシンバルに立候補した女の子が練習で間違えて音楽の先生に叱られてしまう。厳しさと暖かさのある良い場面ではあるのだが、集団の同調圧力をありありと感じ取れた。
先生が女の子に自分の考えを言う前に、他の子たちに「練習しているから」楽譜がなくても間違えないと言わせている。でも本当は楽譜を必要とするタイミングは個人で違うかもしれないし、練習しても間違えてしまうかもしれない。
このような指導では、自分に合った練習法を選ぶというより、結局集団からはみ出さないことが大事だと学んでしまうのではないか。ほかに提出物に関する指導でも「反省しているかどうか」、つまり教師に与える心証を基準に評価する価値観が見て取れる。
集団のなかで自分の役割を学ぶ教育や、結果よりも成長を重視する指導はよいと思う。しかしその目的が「輪を乱さない人材」に集約されしまっているのではないか。先生たち自身、自分たちの指導のよしあしを職員室での反省会に委ねていて、確たる基準を持っていないように見える。こうした課題をどう見るのか、多くの人と共有してみたくなった。
見事だけど残念な場面も。
今年のアカデミー賞短期ドキュンタリー部にもノミネートされた作品の完全版。
短編も観たが、本編は初めて。
本編は物凄くよく描けていて見事。小学校の1年はこうだったのかと改めて再認識した。
コロナ禍の小学校がよく分かり今の小学校を知ることができて観て良かった。
ただ、せっかくなら家庭の様子は密着しないで小学校生活に絞ってほしかった。
また、せっかくコロナ禍の小学校を撮影するならコロナ禍の小学生または先生の密着に
絞っても良かったのでは。どうしてもオオタウイン監督の夢見る小学校シリーズや僕たちの
哲学教室を観てしまうと物足りなさも感じてしまう。いい作品だけにもったいない。
ただ、山崎エマ監督のチャレンジは讃えたい。次回作に期待する。
しかし、体育担当遠藤先生の卵の殻を使った殻を破るパフォーマンスは凄かったな。
ユニークな先生も発見できて改めて観て良かった。
明るい日本
揃えた靴は外向きがいいな
私が一年生だった時
きっと落ち着きのないはしゃぎまくっていた子供だったはず
初日かどうかは覚えてないけど何度も先生に叱られてもふざけていたのでしょうね
堪忍袋の尾が切れた先生が私の両隣の生徒に指示をして私の両方の腕を押さえさせて往復ピンタを喰らいました
記憶では四十代くらいの女性の先生で名前は山田先生
その頃の記憶は他になくその後三年生くらいからしか覚えていません
六歳の子供にはとても恐ろしい恐怖の低学年時代だったのでしょうね
そりゃね、「親父にだってぶたれたことないのに」なんてことはないのです
ちゃんとぶたれて育ってます、ただ反省などは一切した記憶はないけどね
先生さぞや腹が立ったのでしょうね、周りの生徒に対する見せしめにターゲットにされたのかは分かりません
私の頃は上の者の恐怖で決まり事を守らせるやり方が当たり前で親もその世代だから自分の子供がぶたれたら自分の子供が悪いからと先生に「ありがとございます」とか言ったりしてね
「これからもお願いします」とか言うからたまらなかったな〜、悪いのは俺なんだけどもね
あの時から人目を気にするようになったんだと思うな
そんな頃を思い出しつつ見てました
今も変わらないな、子供達は
そのぶん教師が大変だなんだろうな
それにしても子供達はもっと考え方が思ってた幼いのかと
あんなに悔しがったり頑張ったりするのだ
教育はずっとずっと古くからの歴史があるのにいまだにその答えを手探りで探していることにも驚いた
確かにまだまだ人類は未熟なのだし未完全なのだろう
そしてそれはきっと完成することもないし答えも見つからないままなのだと思う
常に曖昧で不器用に人は歳をとる動物なんじゃないだろうか
悟りを開く頃にはすでにかなりの歳を重ねているはず
面白いと思いながら生きていくのもありですね
もう、幼かった頃の恐怖の記憶から抜け出したいけどきっと無理だろうな〜
共に生きていくしかないか
凄いドキュメンタリーですね
元小学校教員です。ここにある映像は自分が何十年見てきた光景と非常に近く、そのリアリティは驚きしかないです。また、2021年度の撮影という事でコロナ禍の影響が強く残り、いろいろな教育活動に影を落としていたことも実際に体験した者として大変よくわかります。
映画館でお客さんがお金を払って観る映画ということで、単なる断片的な記録映像ではないのがいいです。ストーリーがある主演級人物として踏み込んで撮影された方が5人います。1年生の女の子と男の子、6年生の男の子、1年生の担任のベテラン女性教員、6年生の担任の坊主頭が印象的な若手の男性教員です。それぞれの人物が他の人物と密接に関わりながら、展開していく物語だけでも見応えがあります。涙を流すシーンがいくつかありますが、演技として泣くのではないガチの涙なので観る方としてもウルっと来ました。
追加です。2学期になって1年生は秋の公園てのどんぐりや落ち葉拾い、6年生は5年生のとき行けなかった日光での宿泊学習。多分他の学年でもコロナが落ち着いて行事が少しずつ復活しているだろうし、本当に良かったですね。なんだかんだ言っても学校行事は子どもを育てると思う。教員の犠牲的な奉仕に支えられているのは言うまでもないが。運動会も全校揃って開催できてよかったですね。羨ましいです。ただ、給食が「個食 黙食」で1年生も例外なしなのはちょっと辛いですね。
「小学生の時を思い出す」
英語版タイトル『日本人の作られ方(THE MAKING OF A JAPANESE)』の方がしっくりきます
ドキュメンタリー映画としての技術的な面はちゃんとしていると感じました。
一方で、描かれていた内容は、教員が子供をコントロールするために強い口調で威圧する姿で、観ているこっちまで緊張し、何度も心臓がギュッとつぶされました。とても辛い映画でした。
ここに出てくる教員は、自分のやっている「子供のために、よかれと思って」やっているその方法を、私のような元小学生に否定されたくはないでしょう。ですが、威嚇することで相手を操るというのは、犬のしつけと変わらない。この映画に登場した教員の皆様には、このままのやり方で本当にいいのか、振り返って考えてくれていることを望みます。
朝一番に学校に来て、自分のクラスの机をぴったり揃えているあの先生が、一番ケアが必要に感じました。これ以上、強い口調で威圧して思う通りの行動をさせるこの方法を連鎖させて欲しくない。
減り続ける教員、増え続ける不登校、増え続ける若者の自死も同時に考えたい。
子供同士で靴箱の靴のおき方をチェックさせ報告させるという悪趣味な方法で、日本人の礼儀正しさが作られているなんて恥以外の何物でもない。
児童個人に貸与されているはずのタブレット端末を、教員が無言で取り上げる行為は窃盗とどう違うのだろうか?
コメントのお返事:
コメントありがとうございます。嬉しいです。
PISAとかOECD の調査とか?の学力的な面は日本は上位ですが、一方で幸福度や社会を変える力があると思える点は低いですね。この辺りも含めて考えたいですね。
考え直してみましたが、子ども同士で靴の揃え方をチェックさせるのは、自分にはやっぱり悪趣味で恥に思います。そういう部分が映像化され、改めて日本の教育の一部分と向き合うきっかけをいただいたのはいい事だと思います。
とくに感動するところはなかったです
とくに面白い映画でもなかった。ドキュメンタリー作品としても、それほど優れているとは思いませんでした。
海外で評価されているようですが、それは日本の学校に対するもの珍しさもあるのではないでしょうか。
ただ、こういう作品を撮るのはかなり大変だっただろうなと推察します。
個人情報やら肖像権やら、いろいろと面倒くさいことをいうこの時代に、よくこういう映画が作れたなと。
一人ひとり保護者の承諾を得なきゃいけないだろうし、撮影にこぎつけるまでにかなり手間がかかったんじゃないかな。
それから、本作では、大都市の小学校の様子をとらえていますが、地方の田舎の学校とでは、同じ小学校でもその有り様はかなりちがうのではないか、などと考えたりもしました(東京と大阪でも、だいぶんちがうのではないか)。
それにしても、昔は、——ぼくが学校にかよっている頃は、——小中高大をとおして見ても、卒業式に泣いたりする男の先生はひとりもいなかったように思います。時代なのかなぁ。
あっ、それから、あの音楽指導の先生はちょっと怖かったです。
成長するということ
小学校の日常を描いた映画
成長する姿
1年生、入学して幼い姿
6年生、最高学年としてはまだまだ幼い姿
1年がたつとこんなにも違うのか
なぜこんなにも成長するのか
子供だから?吸収力がある?
実践をしているからではないのか
子供の頃は学校にいけば好きな事も嫌いなこともある
とにかく毎日が新しい事の連続
新しい学校、新しいクラス、新しい委員会、部活、授業、全て強制的に出来ないことをやらされる
苦手なこともやる
嫌いなこともやる
その上での成功体験、失敗体験
成功させようとする過程
成功したときの自信
失敗したときの悔しさ、情けなさ
ダメな自分と思うことすら成長なのではないか
成長とは心がするもの
肉体は寝て食ってれば勝手にそだつ
心を成長させるためには成功と失敗が必要
子供はそれを日々、毎日行う
だから成長するのではないか
大人だって成長することは出来ると思った
大人になると、自分の好きなこと、やりたいこと、出来ることを仕事として、苦手を選んで失敗することをを逃れようと生きている
無難な日々が続き、同じような毎日になる
そうすると毎日が習慣になる
実践をしなくなる
実践と習慣は違うもの
習慣は心を成長させない
当たり前に出来ることが習慣
目をつぶっても出来ることが習慣
子供の頃は強制的に実践させられ成長させられていた
大人になると強制的ではなく、自分の意思で成長を求めないと成長は出来ない
大人と子供の成長の違いとはこのようなことではないか。
先生も一緒に怒られてあげる
昔と変わっていなかった学校
諸刃の剣 協調性と同調圧力
日本の小学校で行われてるTOKKATSU(特別活動)が海外で注目を集めているという。本作にも出演なされた国学院大学教授の杉田洋教授が現在エジプトで特別活動導入の指導をなされている。
本作の舞台となる塚戸小学校でもこの特別活動を通して成長する子供たち生徒と教師の姿が描かれている。
特別活動とは何のことかと思いきや何のことはない。我々がやはり小学生の時に普通にしていた教室の掃除当番やら、給食当番やら、保険係などなど、クラスの中でそれぞれ役割を決めて自分が任されたことをすることだ。その活動を通してコミュニティ内での自分の役割を認識して自分が役に立てたことに自信を持てるようになり、コミュニティにも役立つというまさに個人と集団に対して相乗効果を生み出す仕組みだ。
集団生活の中でルールを学び協調性を身につけ、そしてその集団の中で自主性を育んでいく。集団とのかかわりを通して自分は何者なのか自己確立を目指す。
この点は欧米などとは違い、向こうは先ずは自主性を芽生えさせる、自己確立を促してからルールを学ばせ協調性を身に着けさせる。主体性、協調性共に重要だがどちらに重点を置くかで子供の成長の仕方も変わってくる。
日本人は協調性を重んじるばかりに集団内での空気を読みすぎて自己主張が苦手だと言われる。逆に欧米で育つと帰国子女なんかが自己主張が強すぎて日本の学校のクラスで浮いてしまうなんてことがよくある。
確かに協調性ばかりを重んじればそれは同調圧力にもなりうる。杉田教授は講演で日本の教育は協調性を学ばせる点で海外からの評価が高いと言われるが、ルールを重んじるあまりルールからはみ出す子供が排除されてしまう危険性もあると指摘する。いわゆるいじめなどにもつながりやすいということだ。だからこそこの教育は諸刃の剣なんだということを肝に銘じてほしいと話された。
確かに海外から評価されている日本の特別活動。しかし常に時代の移り変わりを通してどう子供たちと向き合っていくべきか常に模索し続けなければならないのだという。教育者としてけして現状に甘んじていてはいけないのだという杉田氏の言葉だった。
現場の教師たちにも同じ姿勢が見られた。若い教師が何人か出てくるが、彼らはまだまだ経験が浅く日々自問自答しながら子供たち生徒と向き合っている。自分は厳しすぎやしないか、今のは怒るべきだっただろうか。常に試行錯誤を続け、けして現状に満足せず生徒を通して学んでいこうとする姿勢が見受けられる。
学校は学びの場だ。子供たち生徒だけではなく、大人たち教師にとっても。先生は読んで字のごとく先に生まれたに過ぎない。先生も生徒を通して教師たるものを学んでいく。
集団内での自分の役割を与えて集団に貢献できることを学ばせ自分が役に立てる存在だと自覚させることで子供に自尊心が生まれる。縄跳びが苦手な生徒も、楽器の練習に自信が持てなかった生徒も教師がサポートするなりして目標達成につなげて自信をつけさせる。
そうして自分は社会で役に立つ存在だと自覚させる。自分は社会の中で尊い存在なのだと。そして実際社会にも役立つ人間へと育っていく。
社会で生きていくにはとても大切なことを幼いころから学ばせるTOKKATSUが世界的に注目を浴びるはずである。
いつも行くミニシアターには珍しく子連れの観客が目立った。みな小学生くらいだ。感心したのは鑑賞中誰一人私語もせず行儀よく鑑賞していたことだ。さすがである。
自本の初等教育の今と過去
フィンランドをはじめ、海外で注目を浴びる日本の初等教育の実態がある程度分かる映画かもしれない。しかし、実際には、この映画を見ることで、戦後の日本の教育の現実とを比べることをお勧めする。日本の過去の小学校教育での生活面や行事での指導された状況は、映画で見られる現在とはかなり違ったととらえる人たちも多いことだろう。無言清掃・無言食事、厳格な整列訓練等々、しつけと言いながら、今では想像できないほどの厳しい決まりが多くあった。当然体罰もかなりあった。まるで軍事教練のようだという評価を下す人日本人もいたようだ。昔の欧米の教育だって全く理想的でなかったのと同じように、日本の初等教育だって理想的であったとは言いがたいことが多くあったのだ。今回の映像で見られる教育・しつけは、日本の教育の良い面を残しつつ、欧米教育の民主的で人権を重視する良い面を学んできたことの成果とも言える。今後は、欧米先進国の初等教育が、個人主義の建て前で横暴・我が儘までも認めて無茶をするようになってきたことを押さえられなくなってきた教育を考え直すいいきっかけに、この映画がなるといい。とはいえ、今や、日本の中等・高等教育のあり方が日本では問われている。欧米に遅れに遅れていることで・・・。
全106件中、21~40件目を表示