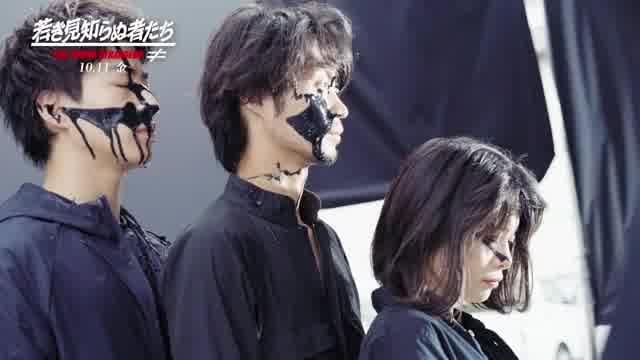若き見知らぬ者たちのレビュー・感想・評価
全127件中、121~127件目を表示
心に鬼を飼うことができなくても、自分を俯瞰できる視点だけは持ち続けたいと思った
2024.10.11 イオンシネマ京都桂川
2024年の日本&フランス&韓国&香港合作の映画(119分、 PG12)
閉塞感に苛まれる若者の半生を描いた不条理系ヒューマンドラマ
監督&脚本は内山拓也
英題は『The Younger Stranger』で「若き見知らぬ人」という意味
物語の舞台は、神奈川県のどこか
難病を患う母・麻美(霧島れいか)の世話をしながら、父・亮介(豊原功輔)の残したバーを切り盛りしている長男の彩人(磯村勇斗、10歳時:林新竜、中学生時代:竹野世椰)は、工場を掛け持ちしながら生計を立てていた
弟の壮平(福山翔大、8歳時:岡崎琉旺、小学生高学年期:大野遥斗)は総合格闘技で活躍していて、ようやくタイトルマッチに手が届くところまで来ていた
彩人には恋人の日向(岸井ゆきの)がいて、彼女は家族同然の存在で、家の手伝いなどをしてくれていた
映画は、ある夜に職質を受けている若者(髙橋雄祐)を助けようとする彩人が警察と因縁を持ってしまうところから動き出す
あらぬ疑いをかけられて連行され、後半のエピソードでは被害者であるにも関わらず加害者として扱われてしまう
その時の警察(滝藤賢一)の対応によって彩人は死んでしまうのだが、映画は「どうしてこうなってしまったのか」を問いかけているようにも思える
警察の報告に嘘を感じた親友の大和(染谷将太)が警察官(東龍之介)に詰め寄るシーンもあるが、この場面での警察の暴論も強烈なものがあった
映画は、彩人の顛末を描き出すものの、その解決にあたるようなことは描かない
その後も自分の道を行くだけの壮平を描くものの、母親をどうするのかなどの問題は置き去りにされたままになっている
おそらくは金を貯めて施設に送ることになると思うが、家族という呪いをどのように断ち切るかというのが命題のようにも思える
彩人があのような結末を迎えた直接的な原因は色々とあるが、自分以外のことに力を注ぎすぎているように思えるので、特に路上の無関係の若者などは無視すべき案件のように思える
また、舞台が神奈川というのもある種の思想が出ている部分があって、結局のところ自分を助けるのは自分しかいない、ということを言いたいのかな、とも感じた
いずれにせよ、彩人の死後に店に行って、そこに血痕があるのに何も感じない大和と壮平を見ていると、何かしらネジが吹き飛んでいる人物ばかりなのかなと思った
警察の報告に違和感を感じるのに現場で感じない理由などはわからず、行政に相談もしないし、全てを抱えて人生を棒に振っている彩人を見ていると、来るべき時が来てしまったようにも見えてくる
反面教師的な側面があるとは言わないが、渦中に入れば見えなくなってしまうものもあると思うので、そういった意味も込めて、常に自分を俯瞰できる視点だけは持っておいた方が良いのかな、と思った
言葉の重み
3.2ぐらい
これでもかって悲惨な出口の無い毎日。
で?おかしくないか?
お母さんの病状から入院とか福祉サービスとか受けられるでしょうよ。家族がいたって介護しきれないのだし。お母さんの所業によるお店や近所の対応も変、いやもうお金とか賠償とかそうゆう問題じゃなくて、福祉に相談しなよ。
挙句にあの警官の所業。先ずは怪我してんだから救急車呼ぶでしょ。なんで犯人はお咎めないの?おかしい、おかしい、防犯カメラ、通行人だっているんだから目撃者多数よ。おかしいって。特にお店の血溜まり、おいおいスルーなのか?
何を言いたいかは分からなくはないが、常識ある設定にして下さい。雰囲気だけで作られた感があるが、嫌いではないので、3.2。
壁一枚隔てたすぐ傍で起こっている
「お願いだから気づいて!!」
「お願いだから見過ごさないで!!」
気づくと、カラオケバーの床を祈りながら見ていました。
観客は真実を知っているからそう思うだけで、実際には私自身もいろんなことを見過ごして生きているに違いない。
そう気づかせてくれる映画でした。
窓の向こうから、楽しそうに遊ぶ声が聞こえるシーンが素晴らしい。
映像に映っていない、フレームの外側を感じさせる演出が大好きなので、てっきり後からつけた音声だと思っていましたが
実際にあの家の前が公園なのだそうです。
家の壁を一枚隔てたすぐ隣りで起こっている現実。
街並みのロングショットでも、同じように並んでいる一軒一軒に、表からでは見えないSOSが隠れていると感じました。
ある出来事を境に多角的な群像劇に広がります。
権力と暴力についても考えさせられました。
先入観の恐ろしさ。
無意識にこれまでの成功体験が先入観となって判断してしまう。
でも、だからと言って、それを責めることができるのか?
警察の廊下のシーンには鳥肌が立ちました。
銃が暴力の象徴であると同時に死をもたらすものとしても描かれます。
現実が重くのしかかって、何も感じないようにしないと生きていけない極限の状況では、自分の心を殺すしかない。
でも、心の自殺は社会からの抹殺でもあり、やはりその引き金を引くのは他者の手なのだ。
岸井ゆきのさんの演技が素晴らしい。
横顔から匂い立つエロス。
私も妊娠中は寝ても寝ても眠かったなぁ。
スプーンを頬張る仕草や笑顔に、彼の面影を見ていたのかもしれない。
そして、畑のシーンは芹澤興人さんですよね?
ほとんど顔が出てないのに、人柄が伝わる。
家族愛が強い人ほど犠牲に
今日もあんな風に声を押し殺して泣いている人達がどこかにいるのかもしれない。
日頃悲しいニュースを聞くたびに、家族愛が強い人ほど犠牲になる事が多いなと感じてたけど。
背負ってるものを減らす方法がもっと簡単にわかりやすく表示されるといいのに。
みんな声を押し殺して泣くから、どうしようかと思った。
色々行政が助けられる事も多いのではと思ったけど、自分たちで何とかしないといけないと思ってる所に、きっと他にもこういう方々がいるよという監督のメッセージが込められてるのかなあとぼんやり思ったり。
あ、あと私今回の作品で磯村勇斗君の良さにちょっとハマったわ。
良いわね、彼。
小汚い格好させてもカッコよかったわ。
めちゃくちゃ優しい役ってのもポイントが高かったのかな。
『波紋』も『渇水』も『正欲』も観てたんだけど、なんか今回のが一番グッときました。
『月』観てみるわ。
助けてが言えなくて頑張ってしまう人達が、少しでも減ると良いなと思いました。
『あんのこと』も思い出したけど、本当に若い時は一瞬なので、幸せな時代を送って欲しい。
子どもが子どもで居られない姿をみるのは本当に毎度しんどい。年齢的に成人になっても出口のない家族の問題に自分を捧げ続けてしまうのは、多分家族という他人が入りにくい場所というのもあるんだろうな。
難しい密室だと思う。
色々考えた映画だった。
ひたすら堪え忍ぶ、見知らぬ者たち
生きるということに命をかける
被写体の感覚を、
舐め回すように捉えるカメラワークが光っている。
匂いたつようなリアリズムがスクリーン全体に浸透し、
その気持ち悪さすらも、
目を逸らすことなく、
ずっと見続けていたいという衝動に駆られる。
空間設計が巧みだ。
カメラの奥行きを活かし、
地面の感触までもが伝わってくるような設計だ。
芝居場にいる人物たちはもちろん、
背景を行き交う人々や車の動きすら、
リアリズムをさらに強化するものに仕立て上げている。
この手間ひまを惜しまない贅沢な空間設計の丁寧さは、
予算がいかに潤沢であっても真似する事は難易度が高い。
重要なのは、この意識と具現化するチームの技術こそが、
リアリズムの本質を舞台に、各役者に宿らせている事だ
ボロボロの靴や、演技の隅々まで生き生きと表現されており、
その正確で真摯な設計は、
過酷で苛烈な現実と観客との緩衝材ともなり得る、
と同時に、
母親や亡き父親、主人公の兄弟をはじめとする登場人物たちが、
この設計によって包み込まれる愛情そのものの空間にもなっている。
しかし、このような愛情のツケは、セリフでもあるように、
いつしか溜まっていくばかりだ。
現実の厳しさと対峙する瞬間が、何度となく訪れる。
それでもなお、信じるしかないと、そう思わざるを得ない。
震えるような良いカットがあまりにも多く、
その一つ一つが生きることへの凄まじい覚悟を突きつけてくる。
ブルーハーツの、
生きるという事に
命をかけてみたい、
が8角形のオクタゴンに響いていた。
全127件中、121~127件目を表示