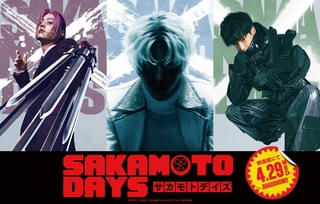コラム:どうなってるの?中国映画市場 - 第73回
2025年4月25日更新

北米と肩を並べるほどの産業規模となった中国映画市場。注目作が公開されるたび、驚天動地の興行収入をたたき出していますが、皆さんはその実態をしっかりと把握しているでしょうか? 中国最大のSNS「微博(ウェイボー)」のフォロワー数280万人を有する映画ジャーナリスト・徐昊辰(じょ・こうしん)さんに、同市場の“リアル”、そしてアジア映画関連の話題を語ってもらいます!
長い沈黙を経て、なぜ再び映画を撮ろうと思ったのか――弔辞の代筆業を描く「来し方 行く末」監督の告白

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd
毎年、日本では数多くの中国映画が上映されています。ですが、メジャー作品を除けば、その大半がカンヌやベルリンなど欧米の映画祭を経て紹介されたものです。中国国内の映画祭で評価された作品が、直接日本に届くという機会はまだ限られています。
上海国際映画祭をはじめ、中国では毎年多くの優れた映画が生まれています。そうした作品を日本にも紹介しようと、2015年には上海国際映画祭と東京国際映画祭が提携し、互いに推薦作品を交換上映するという取り組みが始まりました。
この提携は、コロナ禍で数年間中断されていましたが、23年に再開。上海からは、メインコンペティションで監督賞と男優賞をダブル受賞したリュウ・ジャイン監督作「来し方 行く末」と、アジア新人賞部門で監督賞を受賞した「メイ」が推薦されました。
この2作品は東京国際映画祭「ワールド・フォーカス」部門で上映され、大きな注目を集めました。中でも「来し方 行く末」は、静けさのなかに深い感情を湛えた作品として、多くの観客の心をとらえていました。
そして「来し方 行く末」は、今年の4月25日から日本公開を迎えました。
監督のリュウ・ジャインは、05年の長編デビュー作「牛皮」にて、第55回ベルリン国際映画祭のカリガリ映画賞と国際批評家連盟賞を受賞。その独特なインディーズ・スタイルによって、当時の中国映画界に大きな衝撃を与えました。
今回の「来し方 行く末」は、カンヌ国際映画祭の監督週間、ロッテルダム国際映画祭Bright Future部門で上映された「牛皮II」以来、実に14年ぶりの長編映画です。なぜ長い沈黙を経て、また映画を撮ろうと思ったのでしょうか。
その思いを聞きたくて、北京にいる監督とオンラインでじっくりと語り合いました。
【「来し方 行く末」あらすじ】

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd
大学院まで進学したものの脚本家デビューがかなわなかったウェン・シャンは、不思議な同居人シャオインと暮らしながら、葬儀場での弔辞の代筆業で生計を立てている。丁寧な取材に基づいた弔辞は好評だが、本人は中年に差しかかる年齢で、このままで良いのか自問自答していた。同居していた父親との交流が少なかった男性や、ともに起業した友人の突然死に戸惑う会社員など、さまざまな境遇の依頼人との交流を通して、ウェンの中で止まっていた時間がゆっくりと進みはじめる。

――まずお聞きしたいのは「来し方 行く末」が生まれるまでの背景についてです。前作から14年、ファンの間では「リュウ・ジャインはもう映画を撮らないのでは?」という声もありました。
正直に言えば、私自身もそう思っていた時期がありました。毎年、映画祭や友人たちから「次はいつ?」「どうして撮らないの?」と聞かれて、そのたびに胸が痛くなっていました。まだ“作る”に向き合う準備ができていなかったんです。
――制作から離れていた期間、どのように過ごされていたのでしょうか?
映画とは別の仕事もしていましたが、やはり“作る”ではなかったので、物足りなさはずっとありました。2018年に「このままじゃいけない」と強く思った瞬間があって。「自分の人生がどこか中途半端なまま終わってしまうのでは」という恐怖感に襲われたんです。それで、他の仕事をすべて断って、新作の開発に集中しようと決めました。
――その「恐怖感」とは具体的にどんなものでしたか?
もしこのまま映画を撮らなければ、私は自分の人生に納得できないまま歳を重ねてしまうのではないかという、形のない焦りです。日常はそれなりに穏やかで、仕事も生活も成り立っている。でも本当にやりたかったことを置き去りにしたままだと、どこかで自分を裏切っているような気がして……その気持ちが、一番怖かったです。

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd
――では、脚本執筆に着手されたのは?
2019年の秋ですね。そこから半年かけて書き上げました。ちょうどコロナ禍が始まって、家にこもる時間が増えたこともあって、静かに自分と向き合いながら書くには最適な環境でした。取材も資料も必要ありませんでした。すべては、自分の記憶と考えの中にありましたから。
――主人公のウェン・シャンは「弔辞を書く人」という、非常に珍しい職業に就いています。これはどこから着想を得たのでしょうか?
北京にある八宝山という火葬場が舞台のモデルです。私は子どもの頃からそこに何度も足を運んでいて、どこか懐かしささえ感じる場所なんです。「もし自分がそこで働くなら、どんなことができるだろう?」と考えたときに浮かんだのが、“弔辞を書く仕事”でした。
――つまり、現実に存在する職業ではないですか?
中国にはそういった職業はないと思います。でも、もし私がやるとしたらどうなるか……と想像することで、ウェン・シャンという人物が立ち上がってきたんです。

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd
――弔辞を書くという行為は、ある意味で“他者の物語を代わりに語る”ことでもありますね。
はい。誰かの人生を語ることは、自分自身の人生とも向き合うこと。ウェン・シャンの仕事を考えるうちに、自然とそうしたテーマが浮かび上がってきました。
――映画を観ると、ウェン・シャンというキャラクターを通して、監督ご自身の思索や葛藤が深く投影されているように感じました。
まさにそうです。ウェン・シャンは、私の内面の投影だと思っています。物語に描かれている出来事はフィクションですが、そこに込めた感情や迷いは、まぎれもなく私自身のものです。制作とは、ある意味でそうした個人的な感情を言語化し、物語の形にする作業でもあります。

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd
――話は変わりますが、今回は初めて、いわゆる商業映画のスケールで作品を作られましたよね。
はい。前作はたった3人で撮影したインディペンデント作品でしたが、今回はプロの俳優、スタッフと共に、完全に“映画産業”の中で制作しました。最初は正直、怖かったです。でも、新鮮でもありましたし、毎日が発見の連続で、本当に充実した時間でした。
――主演のフー・ゴーさん、そしてウー・レイさんとの仕事はいかがでしたか?
とても幸運だったと思っています。フー・ゴーさんは、ウェン・シャンという人物の心の機微を深く理解してくださって、台詞に頼らずとも伝わるような繊細な演技をしてくださいました。ウー・レイさんの役は、とても解釈が難しいキャラクターでしたが、彼は想像以上に見事に演じ切ってくれました。
――特にウー・レイさんが演じたシャオインは、現実と幻想のあいだを漂うような不思議な存在でした。
そうですね。彼はウェン・シャンにとって「確かに存在する誰か」でありながら、観客にとっては「どこかあやふやな存在」でなければならない。その曖昧さをどう表現するか、何度も話し合いながら作っていきました。

(C)Beijing Benchmark Pictures Co.,Ltd
――作品には、どこか日本映画との共鳴も感じました。監督ご自身、日本映画をよく見ていますか?
はい、もちろんです。子どもの頃から山田洋次監督の作品や、黒澤明監督の映画をテレビで観て育ちました。日本映画の中には、「語らずとも伝える」感情のやり取りがありますよね。そういう“間”の美しさに、私自身、ずっと惹かれてきました。
――それは、本作にもよく表れているように思います。感情が決して表面的ではないというか。
ありがとうございます。私にとって感情は、声高に語るものではなく、沈黙の中にあるものなんです。だからこそ、ウェン・シャンの感情表現も、極力抑制して描きました。観る人が自分の感情と照らし合わせながら読み取ってくれたら嬉しいです。
――最後に、日本の観客に向けてメッセージをいただけますか?
この映画は、“語ること”と“語らないこと”のあいだにある繊細な気持ちのやり取りを描こうとしました。日本の観客の皆さんには、きっと通じ合える部分があると信じています。どうか、静かに耳を澄ませるように、この作品を観ていただけたら嬉しいです。